http://www.asyura2.com/15/warb16/msg/264.html
| Tweet |
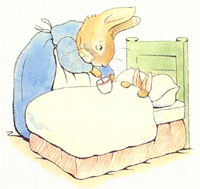
露国防省:シリアの空爆へのデマは対露情報戦争の一環[スプートニク日本語]
© AP Photo/ Vladimir Isachenkov
2015年10月28日 20:08(アップデート 2015年10月28日 22:10)
ロシア国防省のアナトリイ・アントノフ次官は、一連のNATO諸国、及びサウジアラビアの駐在武官らと会談し、彼らに対し、ロシア航空宇宙軍がシリアの所謂「穏健な在野勢力」や平和的に暮らす一般市民、そして民間施設を空爆しているとの派手な主張を裏付ける証拠を提示するか、あるいは、しかるべき反論をするよう求めた。
ロシアは以前から、シリアにおけるロシア軍の行動を貶めようと展開されているマスコミ・キャンペーンについて、危惧の念を表明している。そうした状況は、ロシア指導部が、公式レベルでしかるべき措置を取らねばならないところまで来ているようだ。
ロシア国防省に招かれたのは、いくつかのNATO諸国、そしてサウジアラビアの駐在武官達だった。実際上、彼らが呼び出されたのは、しかるべき説明を求めるためで、自分達の主張をしっかり裏付ける証拠を示すか、あるいは「ロシアが民間施設や、その他の『正しくない』標的を空爆している」との情報を公式に否定するよう求めるためだった。
以下2つばかり、ロシアでは根拠がないとみなされる西側マスコミ報道の一部を、皆さんに御紹介したい―
「米国防総省は、穏健派の蜂起軍が抑えている地区でも空爆がなされたと述べた。」(CNN)
「蜂起軍参加者は、ロシアの空爆により、一般住民36人が死亡したと伝えている。」(Qasioun News)
西側メディアの立場は、よく分かるが、公式筋からも同様の発言が聞こえている。ロシア国防省は、西側諸国の高官、例えば、米国のケリー国務長官やカーター国防長官、NATOのストルテンベルグ事務総長が、自分達の公式発言の中で、そうしたマスコミ報道を引用している事実に、大いなる憤りを感じている。
ロシア国防省のアントノフ次官は、西側のパートナーと呼ばれる人たちに、次のように述べた―
「もし我々のパートナーのもとに、何か追加的な情報がある場合、我々にそれを渡してくれるよう、以前から我々は求めている。ロシア軍機による空爆の結果、病院やイスラム礼拝所、学校が破壊されたとか、一般市民が犠牲になったとかいう、具体的な一つ一つの情報の確認においては、詳しい調査が行われるだろう。それについては、西側のマスコミや軍事外交団は、報告を受けることになる。
もし証拠が示されず、それに関して公式的な反論が無ければ、我々は、自分達に投げつけられる非難の数々を、ロシアに対する情報戦争の一部であるとみなす。」
証拠とニュースソースの信頼性の確認は、もちろん大きな問題だ。しかしもっと大きな問題は、そもそもマスコミ機関が、そうした情報をチェックしたがらないという点にある。
シリアにおける戦闘行動についての情報源として、疑わしい例としてまず挙げられるのは、シリア人権擁護モニタリングセンターだ。この組織の活動は、ロンドンに居住する一人の人物により行われている。RT(ロシア・トゥデイ)の特派員が、カザフスタンで開かれたシリアの在野勢力の国際会議で、彼と接触したが、彼が最後にシリアを訪れたのは、何と2000年で、つまり今から15年も前だった事が分かった。
シリア現地で情報を集める活動家の誰とも個人的な知り合いではないとの事だった。それでも、このセンターの流す情報を、極めてたくさんのマスコミが、それも大手のよく知られたマスメディアが引用している。シリアで内戦が始まってからこれまでの4年間、そうした状況が続いているのだ。
http://jp.sputniknews.com/russia/20151028/1089351.html
投稿コメント全ログ コメント即時配信 スレ建て依頼 削除コメント確認方法
 スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。