08. 2015年4月07日 01:01:20
: jXbiWWJBCA
「河合薫の新・リーダー術 上司と部下の力学」
独機墜落で露呈した“人命無視”の負のスパイラル「とりあえず絆創膏」で問題解決を先送りする、人間の愚かな性 2015年4月7日(火) 河合 薫 「もう(トイレに)行って大丈夫です」
「操縦を任せる」
「私にできるといいのですが」 この8分後、乗客乗員150名を乗せた独ジャーマンウイングスの旅客機は急激に高度を下げ、フランス南東部アルプス山中に墜落。機体は大破した。 「副操縦士が故意に降下ボタンを押した可能性が高い」――。 このフランス当局の衝撃的な発表を聞いたとき、私の頭に真っ先に浮かんだのが、コックピットクルーが持ち歩く、黒い“カバン”だった。 「コックピットの計器の数値は絶対に暗記してはいけない。常にマニュアルを見ながら数字を確認して、運行中も、計器の場所と数字の確認を、声に出しながらやらないとダメ。覚えた途端にミスは起こる。絶対に覚えないことが、ミスを防ぐ最大の方法なんだ。これ、持ってごらん」 フライトエンジニア(FE)の方はこう言って、見るからに重たそうな黒いパイロットケースを差し出した。 ※米ボーイング747-400が導入されるまで、コックピットには機長、副操縦士、FEの3人が乗務していた。 カバンの重さは、“人の命の重さ” 「重たいだろ? これがね、僕たちが人命を預かっているという、仕事の重さ、なんだ」 腕が伸びちゃうんじゃないかってぐらい重くて、軽く10キロはありそうなカバンは、「“僕たち”の仕事の重さ」だ、と。「“人間ならでは”のミスを防ぐために、“僕たち”の仕事の重さを忘れないために、たくさんのマニュアルの入った大きな重たいカバンを持って歩く」んだ、と。新人客室乗務員(CA)だった私に、FEさんは教えてくれたのである。 それは分厚いサービスマニュアルをどうにかして小さくして、軽くすることばかりを考えていた私を、ハッとさせた言葉であり、「訓練、訓練、訓練」の嵐で「30過ぎまで食えない」と言われていたP訓(パイロット訓練生)の謎が解けた瞬間でもあった。 その“僕たち”の1人が、自分の意思で、僕たちの大切な人を、道連れにしたのである。 うつ病
網膜剥離
リストラへの恐れ
彼女にふられたことでの落ち込み……
“故意に墜落させた謎”を巡って、アンドレアス・ルビッツ副操縦士に関する情報が漏れ伝えられている。 だが、彼はこれまで一瞬でも、“カバンの重たさ”を感じたことがあったのだろうか?――。 「操縦室では必ず2人体制を!」
「航空会社は乗員の健康チェックを!」 と、各国は再発防止に躍起になっているけど、何を今さら慌てている? そもそも何百人もの命を預かる機体の操縦室が、「たった1人になれてしまうこと」も、「乗員の健康チェックを徹底できない仕組み」が許されていたことも、それら自体が異常なのだ。 ひょっとして、国も航空会社も、“カバンの重さ”を忘れていた? そんな風に考えたくないけど、各国の反応をみていると疑いたくなる。 だって米国では「常時2人規制」を義務づけていたし、日本では1982年の羽田空港沖の墜落事故後、乗員の身体検査を担う第三者機関「航空医学研究センター」(現在は一般財団法人)を設置。国土交通省によると羽田沖事故以降、乗員の精神疾患が原因の事故は起きていないという(3月28日付朝日新聞デジタル「副操縦士の自宅から『勤務不可』の診断書 独旅客機墜落」)。 同じ空で、同じように重たい仕事なのに、なんで同じような対策をこれまで取ってこなかったのだろう。 つまり、いずれの安全対策も単に傷口に絆創膏を貼ってるだけ。 もちろん、“僕たち”の任務を忘れた(あるいは知らない)“危うそうな人”を危険な行動に走らせないための防止策にはなる。でも、そもそもそういう危ない人を作り出す、“銃弾”を放ってるのは、いったい誰なんだ? 「11時間、交代なし」、パイロットの“過酷な現実” 「CAだってギリギリしか乗っていないのに、トイレごときで即コックピットに来てくれるとは思えない」 「それよりも日本の航空会社は、11時間フライトまで交代要員のいない2人だけの乗務ができることの方が問題」 「ヨーロッパの航空会社も、9時間フライトは休憩なしの2人乗務で、これはかなりしんどい」 これらはいずれも、現役乗務員たちの声だ。 航空機のトラブルや事故が起こると、「パイロットが足りない、パイロットが足りなくなる、どうにかしなきゃ」と、パイロットの“量”の問題ばかりが取り沙汰される一方で、“質”の議論は置き去りのまま。 僕たちを取り巻く“過酷な状況”を見直す兆しはなく、自分たちが放った“銃弾”の存在さえ認める動きがない。 乗員の健康状態チェックを厳格化するだけじゃなく、医療の守秘義務ルールを見直すだけじゃなく、健康状態を把握しながら飛ばせた企業の責任を問うだけじゃなく(4月1日付日本経済新聞「ルフトハンザ、副操縦士の病気を把握 独機墜落」)、「なんでジャーマンウイングスが副操縦士がうつ病だったことを把握しながら、乗務させるようなムチャなことをしなければならなかったのか?」を、徹底的に考える必要があるはずだ。 安全文化(Safety Culture)――。福島の原子力発電所事故以来、耳にすることが増えたこの言葉は、1986年に発生したチェルノブイリ事故の原因の調査と検討の結果をきっかけに生まれた。IAEA(国際原子力機関)は、「安全文化」を次のように定義している。 「原子力の安全問題には、その重要性にふさわしい注意が最優先で払われなければならない。安全文化とは、そうした組織や個人の特性と姿勢の総体である」 これはまんま次のようになる。 「飛行機の安全問題には、その重要性にふさわしい注意が最優先で払われなければならない。安全文化とは、そうした組織や個人の特性と姿勢の総体である」 「安全である」ことが安全文化ではない。安全文化とは、「ヒューマンエラーや事故は起こる」と前提にした文化であり、組織と個人によって熟成させる、“僕たち”の任務だ。 というわけで、前置きが長くなった。今回は、「安全文化」についてあれこれ考えてみます。 今から6年前。奇跡を起こしたと世界中から賞賛された、1人のパイロットがいた。 チェズレイ・サレンバーガー氏。「ハドソン川の英雄」と称えられたUSエアウェイズ1549便機長と聞けば、思い出す方も多いに違いない。 1549便は、米ニューヨーク・ラガーディア空港離陸直後、両エンジンの同時バードストライクというレアケースによって両エンジンがフレームアウト(停止)し、飛行高度の維持ができなくなった。 当初、空港管制は、進行方向の延長上にあるテターボロ空港への着陸をアドバイスしたが、高度と速度が低すぎるため機長はキャンセル。ハドソン川緊急着水を、自らの判断で宣言したのである。 ハドソン川になんとか着水させた後、機長は2回にわたって機内を見回り、乗客全員を機外に脱出させた。乗客たちは機長の指示に従い、川に浮かんだ飛行機の翼の上で救助を待った。その結果、誰1人として氷点下の川の水に濡れることなく助かった。 乗員・乗客155人全員無事。機長のとっさの判断力と行動力が人命を守り、機長は世界中から讃えられた。この一連の出来事は、「ハドソン川の奇跡」(Miracle on the Hudson) と呼ばれるようになったのである。 パイロットより、マックでバイトした方が稼げる ところが、である。なんとこのサレンバーガー機長が、 「過重労働を強いられるパイロットの年収が200万円では安全を確保できない」 と米議会で告発していたことは、あまり知られていない。私自身、それを知ったのは、マイケル・ムーア監督の「キャピタリズム〜マネーは踊る〜」(2009年公開)を見たときだった。 この映画では、「米国ではパイロットよりマックでのバイトの方が稼げる」という見出しの後、年収200万円程度で働く、パイロットの悲惨な労働環境を紹介。 「年収は、タコス屋(実際に例として挙げられたのは米国タコスチェーンのタコベル)よりも安い」 「賃金が安すぎて、学生ローンの返済ができない」 「生活保護の食料配給券を使っていた時期がある」 「“好きな仕事”をしているという弱点に会社は付け込んでる」 といった、耳を疑いたくなるような現役パイロットたちのコメントとともに、「過重労働を強いられるパイロットの年収が、200万円では安全を確保できない」と厳しいパイロットたちの現状を訴えるサレンバーガー機長が、画面に映し出されていたのである。 ちょっとばかり補足しておくと、米国の地域航空会社のパイロットの年収がファストフード店の従業員と同程度になるのは、航空業界の構造の問題が大きいとムーア監督は指摘している。 大手航空会社は節約のため国内便の多くを、提携している地域航空会社にアウトソース。その上で、大手航空会社が運行計画や運賃を設定するため、提携先の地域航空会社には賃上げの余地がない。そのしわ寄せがパイロットに及んでいるとした。 では、話をサレンバーガー機長に戻そう。 機長はハドソン川の奇跡について聞かれると、「いつも常に準備していたことをチームで行った」と語り、いつも持ち歩く航空路線図には、中華料理店で引き当てた「おみくじ」を貼っていた。 「遅れても災難よりまし 〜A delay better than disaster〜」――。おみくじに書かれたこの言葉を肝に銘じるために、貼っていたそうだ。 「時刻通りに運行しろ!」「予定通り飛行機を飛ばせ!」 そんな社内外から浴びせられる要求に屈しないため。 「我々にはパーキングブレーキという武器がある。安全な飛行ができると機長が確信できなければ飛行機を出発させない」ため。 “僕たち”の仕事を見失わないために、プロとして責任ある行動と、プロにだけ許される権限と義務に恥じない訓練と備えを忘れないために……、おみくじを大切な路線図に貼っていたのである。 重たいカバンと路線図に貼られたおみくじ。どちらも、「あなたの任務は人命を守るってことですよ!」ってことを忘れないための、とてもとても大切なシグナル。まさしく、「ヒューマンエラーや事故は起こる」という前提に立った、自らへの警告なのだ。 ちなみに、米原子力規制委員会(Nuclear Regulatory Commission、略称:NRC)では、「ハドソン川の奇跡」を安全文化の啓発に頻繁に利用している。 「就職対策に力を入れすぎた」 だが、安全文化を共に熟成しなければならない企業サイドは、残念なことにコスト削減に躍起になった。 パイロットの月間乗務時間を延長し、渡航先の宿泊数を削減し、ミニマムクルー(最少乗員数)の基準も変え、インターバル(休憩)をなくし、夏休みを廃止した。 生産性を高めるためにジャンボジェットの3分の1程度の座席数で、燃費効率のいい航空機を大量に購入し、便数を増やした。 その結果、パイロットが足りなくなった。その穴を埋めるために、日本では賃金の安い外国人パイロットを採用し、コストのかかる自社育成をやめ、大学などにパイロット養成を任せたのだ。 ところが、である。皮肉にも、ここでも残念な事態が起きる。 なんと桜美林大学の「航空パイロット養成コース」が、訓練管理のずさんさを国交省から指摘され、国の養成施設としての指定を3月末に返上させられたのだ(4月2日付朝日新聞デジタル「桜美林大、パイロット養成指定を返上 管理ずさんと指摘」)。 「就職対策に力を入れすぎ、組織運営や安全管理がおろそかだった。反省している」 日本航空元機長で養成コース長の宮崎邦夫教授は、こう話しているそうだが、これっていったい何? 事故が起きる度に、「安全! 安全!」って大合唱するけど、いったいどんな安全をうたっているのだろう。おまけに、件の“絆創膏”作戦だ。 自分たちが、“銃弾”を放っているなどみじんも考えず、「ホラ、僕たちはちゃんと対策取ったよ。あとは君たちでよろしくね!」と、“僕たち”の任務はどこ吹く風。 国も企業も、“僕たち”の仕事を忘れてる。完全なる負のスパイラル。 そう。つまり、空の熾烈な競争でコストカットされたのは、パイロットの賃金だけじゃない。“僕たち”の任務、すなわち、カバンの重さもカットされてしまったのだ。 「メード・イン・ジャパン」の土壌が崩壊 操縦歴42年のベテランだった、“ハドソン川の英雄”は、事故後のインタビューで次のように答えている。 「いろいろな意味で、あの瞬間に至るまでのこれまでの人生が、あの特別な瞬間を切り抜けるための準備期間だった。私はヒーローではない。訓練してきたことをやっただけ。自慢も感動もない」 その機長の「今のままでは安全を確保できない」というコメントには、言葉以上の重さがある。 42年前に組織の一員になり、厳しい訓練を課され、育てられた時代にあった、「アナタは我が社にとって、大事な人」というメッセージが、今はない。組織と個人の努力で安全文化を熟成させる視点を持たないと、取り返しのつかないことになるぞ、と。機長はそう警告したのだ。 メード・イン・ジャパン——。日本がかつて作り上げたこのブランドは、海外からも評価された。ここ数年、批判の絶えない「終身雇用制度」に代表される長期雇用がメード・イン・ジャパンを確立させたという見解は、国内より国外からの方がはるかに多い。 「アナタは我が社にとって、大事な人」という企業からのメッセージが、忠誠心や帰属意識を育み、“僕たち”の任務を誇りに努力する、プロフェッショナルな人材を育てたのは言うまでもない。 が、その土壌が崩壊した今。もっともっと積極的に安全倫理を意識し、個人だけに委ねるのではなく、国も企業も一緒に安全文化を熟成させなければならない。その自覚が欠けている。実に恐ろしいことだ。これからますますパイロットの量を確保するための施策が進められるに違いない。 そして、自戒を込めて言わせていただくと、乗客である私たちも、お財布の重さをもっともっと感じなければ……。サービスも、安全も、タダじゃない。うん、タダじゃない。安全って、ホント何なんだろう……。 このコラムについて
河合薫の新・リーダー術 上司と部下の力学 上司と部下が、職場でいい人間関係を築けるかどうか。それは、日常のコミュニケーションにかかっている。このコラムでは、上司の立場、部下の立場をふまえて、真のリーダーとは何かについて考えてみたい。
http://business.nikkeibp.co.jp/article/manage/20150403/279577 |
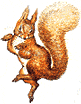
 スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。 スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。