01. 2015�N2��20�� 20:34:55
: xEBOc6ttRg
�R�����F�������́u�Ƃ�����v��������̕����ڕW���R�{�땶��
2015�N 02�� 20�� 17:52 JST
�R�{�땶 �v���r�f���e�B�A�E�X�g���e�W�[�@�}�[�P�b�g�X�g���e�W�X�g�m�����@�Q�O���n - ��N�P�P�����̐Ζ��A�o���@�\�i�n�o�d�b�j����ł̌��Y������ɂ���Ĕ��Ԃ����������������B���Z�s��ł͋ߔN�A�e���͂̑傫���v���[���[���������ė��v�悤�Ƃ���L�`�̃J���e���s�ׂ����X�ƍ���������ł��Ă������ŁA�n�o�d�b�̌����������s�\�Ƃ��������������̓J���e���̋t�P���_�Ԍ�����ٗ�ȏo�����������B ���̕W�I�Ƃ������̂̓V�F�[���v���ƕč��̃G�l���M�[�e����`�A���V�A�鍑��`�A���邢�͐Ζ�������n���������̈�Ƃ���ߌ��h�g�D�u�C�X�������v�ȂǏ������X�����A�ő�́u�Ƃ�����v�����̂͐��E�̑����̒��₪�������Ă���u�C���t���ڕW���x�v��������Ȃ��B ��N�㔼�ȍ~�̌������i�̋}���E����������ɁA�I�[�X�g�����A��j���[�W�[�����h�ȂǑ����̍��ŃG�l���M�[���i���܂ޑ����C���t���A���邢�͂���ɋ߂������C���t����������̃C���t���ڕW�����W�̉��������荞�B���[�����ł́A�P���̏���ҕ����w���i�g�h�b�o�j���A���B����i�d�b�a�j�̒����I�ȕ�������̒�`�ł���u�Q��������邪�A����ɋ߂��v�������͂邩�ɉ����}�C�i�X�O�D�U���i�O�N��j�ƂȂ����B �p���ł��A�P���̏���ҕ����w���i�b�o�h�j���P�X�W�X�N�̌��s���v�J�n�ȗ��̍Œᐅ���ł���v���X�O�D�R���i���j�ɂ܂ŗ������B�C���O�����h��s�i�a�n�d�j�̃J�[�j�[���ق́A���s�̃C���t���ڕW���x������ɖڕW�̉��������荞��ō������ɏ��Ȃ𑗂�H�ڂɂȂ������j�㏉�߂Ă̑��قƂȂ����悤���B ������A��N�P�Q���̍����b�o�h������ł̒��ړI�ȉe���Ɛ��N�H�i���������x�[�X�őO�N��v���X�O�D�T���ł��邩��A�����̎�v������̃C���t���ڕW�����W�ł���u�Q������㉺�P���v�Ɋӂ݂�A�����W���������荞���ނɓ���Ƃ����悤�B �����������A�G�l���M�[���i���܂ޑ����C���t���A���邢�͂���ɋ߂��C���t������ڕW�Ƃ��Ă��钆��͎��X�ƃn�g�h�����A���Z�ɘa�ɒǂ����܂ꂽ�B��v������̒��ł́A�d�b�a�̃}�C�i�X�����E�ʓI�ɘa������M���ɁA�J�i�_����ƃI�[�X�g�����A������s�i�q�a�`�j���������ɓ��ݐ�A�j���[�W�[�����h������s�i�q�a�m�y�j���^�J�h�X�^���X�𒆗����������B �Ȃ��A�J�i�_�ł͎����C���t���͂܂��ڕW���������荞��ł��Ȃ����A�Y�����ł��邽�ߌ����������������ʂ��̉����C���ɂȂ��������ƂƁA�C���t�����������I�ɖڕW���������荞�ތ��ʂ�����������ŗ��������s���Ă���A�s��ɂ̓T�v���C�Y�������������ɏ������ꂽ�搧�I�ȁipreemptive�j�Ή��ƕ]�����ׂ����낤�B �������A���������������Ƃ������₪�����Z����E���ߎ�i�ł͒��ډ����ł��Ȃ��v���ɂ��C���t���ቺ�ɑ��āA���Z����ɂ��Ή�����Ƃ����̂͐�����������Ȃ̂��낤���B ���������ɖ|�M����ɂ����ĉp�̋��Z���� ���Ƃ��ƁA����̓G�l���M�[���i���܂ޑ����C���t�����^�[�Q�b�g�Ƃ��Ă��邽�߂ɐ�������肾�B�������̉e���ő傫�����������G�l���M�[�֘A�����͂ǂ����悤���Ȃ��̂ŁA���Z�ɘa�ɂ���Ă��̑��̕i�ڂ������グ�A�S�̂Ƃ��ẴC���t���������グ��}���Ă��邱�ƂɂȂ�B �ł͂Ȃ������C���t�����^�[�Q�b�g�Ƃ��钆�₪�����̂��ƌ����A����ҕ����Ƃ������v�͍����̊Ԃɔ�r�I����݂�����A�K�������o�ρE�o�ϐ���̐��Ƃł͂Ȃ������Ƃ���єނ炪��\���鍑���Ƃ̃R�~���j�P�[�V�������e�Ղł��邱�Ƃ��傫���Ƃ݂���B �m���ɁA���₪�H���ƃG�l���M�[���i�������A������R�A�C���t������ڕW�Ƃ���ꍇ�A����珜�O�i�ڂ͈�ʏ����̐����ɂƂ��Ĕ��ɏd�v�ȕi�ڂȂ̂Ŗ��ӔC���A�Ƃ����c�_�ɂȂ��肩�˂Ȃ��B �����ڕW�̃^�[�Q�b�g�Ƃ��ׂ��C���t���w�W�ɂ��Ă͗l�X�ȍl����������A�e���Ŏ�����قȂ�B�����A�M�҂͑����C���t������{�I�ȃC���t���ڕW�Ƃ��A�������ŁE����łȂǂ̐Ő��ύX�⍡���ǖʂ̂悤�Ȍ������i�̋}�ςƂ��������₪�R���g���[���ł��Ȃ��i�ڂ��邢�͕ϓ������O������I�C���t�������Q�Ƃ�����ŁA�Q���̃C���t���ڕW��B������悤���Z���������g�g�݂����z�I�ł͂Ȃ����ƍl���Ă���B ��╡�G�ɕ������邩������Ȃ����A�����ǖʂɓ��Ă͂߂�A�����C���t���͒ቺ���Ă��邪���₪�R���g���[���ł��Ȃ��������i�̉e������������I�C���t���w�W���ቺ���Ă���킯�ł͂Ȃ��̂ō���͋��Z�ɘa�̕K�v���Ȃ��A�Ƃ������������\�ɂȂ�B �ߋ��ɂ͑����̒���Ŏ����I�ɂ��������Ή�������Ă����ʂ����邪�A����̌������ւ̑Ή����݂�ɁA�u�C�~�y�i�����������悤�j�Ƃ������A�����C���t���ڕW�Ƃ������x�����邪�䂦�ɃR���g���[���ł��Ȃ����̂��R���g���[�����悤�Ƃ��Ă���A���邢�͒ʉ݈���ʂ��Či�C���h�����������C���t���̍��~��ɂ��ł��Ȃ��������Z�ɘa���A�������𗘗p���Ď��s���Ă��鍑������悤�ɂ݂���B �܂��A���������Ȃ���ΓK�����������������̕i�ڂ̃C���t�������A�������������Z�ɘa�ʼnߓx�ɉ����グ���Ă��܂��ʂ�����͂����B�I�[�X�g�����A��J�i�_�ł́A���łɉߔM�C���̏Z��s�ꂪ�s�K�v�ȉ��x�����邱�ƂɂȂ�Ƃ݂���B ���̓_�A�č���p���͒��₪�R���g���[���s�\�Ȍ������̉e���ɍ��E����ɂ������x�^�c���s���Ă���B�܂��č��́A�����C���t���ł͂Ȃ��R�A�C���t���A���Ȃ킿�R�A�l����x�o�i�o�b�d�j���i�w�����d�����邱�ƂŁA�����C���t�����C���t���ڕW�Ƃ��Ă��鑼�̒���Ɣ�ׂāA�G�l���M�[���i�̐U�ꂩ�炭��C���t�����ϓ��Ɉ���J�����ɍς݁A����I�Ȍo�ϐ�����C���t�����͂ɏœ_�Ăċ��Z���������ł���B ���̌��ʁA�č��ł͍�N�P�Q���̑����C���t�����O�N��v���X�O�D�W���A�����̑����o�b�d���i�w�����O�N��v���X�O�D�V���Ƃ�������ċ��Z���ǂ̃C���t���ڕW�ł���v���X�Q����傫��������Đ��ڂ��Ă���ɂ�������炸�A�����̐����͋��Z����̗\�z�̊ϓ_����͎s��őS�����ڂ��ꂸ�A�R�A�o�b�d���i�w�����O�N��v���X�P�D�R���łȂ��Ȃ��Q���ɋ߂Â��Ȃ��_�ɋc�_���W�����Ă���B ����ɂ��Ă���A�i�C�S�ʂ̉�J���s��̉��P�p�����Ē����I�ɂQ���֎��ʁi���イ���j����Ƃ����V�i���I���ێ�����Ă���A�č��ł͌��������炭��f�B�X�C���t���ɑΉ������ʓI�ɘa�ĊJ�Ƃ������Y�I�ȋc�_���������Ă���B�ނ���A�������̏����I�ȏ����ьi�C�S�ʂɑ��鉟���グ���ʂ������I�ȗ��グ�̕K�v�������߂邱�ƂɂȂ�A���N���̗��グ�J�n�V�i���I���ێ�����Ă���B �Ȃ��A���߂P���̘A�M���J�s��ψ���i�e�n�l�b�j�̋c���v�|�ł͑��}�ȗ��グ�J�n�ɐT�d�_�������ꂽ���A����͕K�������C���t���ቺ�ɂ����̂ł͂Ȃ��A��S�l�������������Y�i�f�c�o�j�������̓݉��ȂǁA���̌o�ϊ����̓݉����X�N�ɔz���������̂Ƃ݂���B �p���ł͂a�n�d�������C���t�����Q������㉺�P���|�C���g���Ɉێ�����C���t���ڕW������̗p���钆�ŁA�O�q�̒ʂ蒼�߂̑����C���t�������O�N��v���X�O�D�R���֒ቺ�����B�������ꂪ���[�����ŋN���Ă�����ʓI�ɘa�g��̋c�_�ɂȂ����Ă����悤�ȏɂ���B �����Ƃ��A�a�n�d�͌������̃C���t�������������ʂ͈ꎞ�I�ŁA�ނ��낱�̈ꎞ�I���ʂ��ꏄ����ΔN���ɂ����ăC���t�������}�������郊�X�N���w�E������ŁA�č��Ɠ��l�ɏ����I�Ȍi�C�h�����ʂ��l�������N�Ɍ��������グ�J�n�V�i���I���ێ����Ă���B�{���A�a�n�d�̓C���t���ڕW�����W��������ō������ɑ��ď��Ȃ𑗂�A�w�i�ƑΉ���������˂Ȃ�Ȃ����A�����ł����l�̐��������A�����̌����������C���t���ቺ�������㖳�����A�`���I�ȃC���t���ڕW�ɔ���ꂸ�ɋ��Z������^�c���Ă���B ����͊�{�I�Ɍ������ɖ|�M����钆��̕��ނɓ��邪�A�ŋ߂͌����̃C���p�N�g�ւ̑Ή��Ɋւ��ău�����݂��Ă���B����̓C���t���ڕW�̑ΏۂƂȂ�C���t�����Ƃ��āA����łƐ��N�H�i�������b�o�h���̗p���Ă��邽�߁A�������i�̉e����傫���A���̃C���t���������q�̒ʂ�P�Q���ɂ͑O�N��v���X�O�D�T���܂Œቺ�B�Q�O�P�R�N�S���ɗʓI�E���I���Z�ɘa���J�n�����ۂ̖������Q�N�Ԃ��Ȃ킿�Q�O�P�T�N�x���̂Q���ڕW�B������ǂ�ǂ������Ă���B ��N�P�O�����ɓ���͒lj��ʓI�ɘa���s�������A���̍ۂ̐����Ƃ��āA����Ō�̌i�C�������z��ȏ�ł��������Ƃɉ����āA���������炭��C���t�����ቺ��f�t���}�C���h�������X�N�Ƃ������W�b�N�����p�����B�����Ƃ��A�ŋ߂ł͌������ɂ��C���t������������lj��ɘa�̗��R�Ɏg���̂ł͂Ȃ��A�C���t���ڕW���Q�O�P�T�N�x���ɒB���ł��Ȃ�������Ɏg���Ă���߂�����B�C���t���ڕW����́u�_��ȉ^�p�v�̈ꌾ�ɐs���邪�A���W�b�N����т��Ă��炸�A�������E�C���t�����ቺ�ɑ������̋��Z���������������ɓǂ݂ɂ����Ȃ��Ă���B ������lj��ɘa�̌����胊�X�N�� ������ɂ���A�����������C���t�����}�ቺ�ɂ��A�����̍��ŃC���t���ڕW�����W�̉�����˔j���Ă��܂����ԂƂȂ��Ă���B�܂��ɂn�o�d�b�ɂ���ăC���t���ڕW���x�̊拭����������Ă�������A�s�v�c�Ǝs��Q���҂̊ԂŃC���t���ڕW����ւ̕s�M�������܂��Ă���Ƃ����b�͕����Ȃ��B �������A����͎s��Q���҂̒���ɑ���M�F���������炾�Ƃ݂�͓̂I�O�ꂩ������Ȃ��B���ꂪ���������Ԉ���Ă��邩�Ɋւ��Ȃ��A����͋��Z����̃��[���Ƃ��̉��߂�����E�ύX���錠���������Ă���A�s��Q���҂͕s�{�ӂł�����ɏ]�킴��Ȃ����߂��B �����������ł̈בփX�g���e�W�[�Ƃ��ẮA�܂��������ł��Ђ�܂��߂������̋��Z�������߂Ɍ������Ă���ăh���Ɖp�|���h�͑��ΓI�ɋ����Ȃ邾�낤�B�����A��N���Έȍ~�̌����}�����āA���N���܂ł͑O�N��C���t����������ɒቺ����\���������A����ɃC���t���ڕW�����A���Z�����Ή����s���X�������鍑�̒ʉ݁A���Ȃ킿���[���A�I�[�X�g�����A�h����j���[�W�[�����h�h���́i�lj��j���Z�ɘa���҂����܂�₷���������͂������葱���邾�낤�B �t�Ɍ����A��҂͌����}�����ǖʂɂȂ�n�g�h�p�����}�Ɏ�艺���A�^�J�h�����郊�X�N������_�����ɓ���Ă����K�v������B ����͏�q�̒ʂ胍�W�b�N���K��������т��Ă��Ȃ��悤�Ɍ����邱�Ƃ���A�����I���̗͂L�����܂߂����������炭��C���t���ቺ�ւ̋��Z�����������A����тQ�O�P�T�N�x���𒆐S�Ƃ���C���t���ڕW�B���Ƃ����g�g�݂̔��C�����X�N���l�����헪�𗧂Ă˂Ȃ�Ȃ��Ƃ���ɓ��������B �M�҂͊�{�V�i���I�Ƃ��ẮA��͂茴�����Ƃ������₪����s�\�ȗv���ɂ��C���t�����ቺ�ł����Ă��A�Q���̃C���t���ڕW���x�̓������̂��f�t���}�C���h���@�i�ӂ����傭�j�ɂȂ���Ƃ�����`�����̉��ł���܂ő�K�͊ɘa������Ă����ȏ�A�Q�O�P�T�N�x���̂Q���ڕW�B�������ۏォ�Ȃ����Ƃ��Ă��B�����悤�Ƃ����w�͂���������ׂ��Ƃ݂Ă���B������S���A�x���Ƃ��V���ɒlj��ɘa���s���A�~�������p���ăC���t���������グ�悤�Ƃ��邾�낤�B���̂��߁A�N���ɂ����Ă̕ė��グ�J�n�����h�����Ƒ��܂��āA�P�Q�T�~�����։~�����i�ނƂ݂Ă���B �������A�S�����ɓ���n���I���T���Ă��邱�Ƃ���A��������قlj������ĉ��x������K�v���o�Ă��Ȃ�����A�lj��ɘa�̉~�����I���Ń}�C�i�X�ɓ������X�N���l������A�lj��ɘa�͐摗�肳��郊�X�N������B���{����̈Öق̗����ĂQ�O�P�T�N�x���̂Q���B������������߁A�lj��ɘa���s��Ȃ����X�N���]���ɔ���܂��Ă���_�ɂ͒��ӂ��K�v���B ���R�{�땶���́A�O�ד����Ɋւ��钲���E���́E��M���s���v���r�f���e�B�A�E�X�g���e�W�[�̑�\��������}�[�P�b�g�X�g���e�W�X�g�B���{��s�ŒZ�ϒ����쐬�A�O�ו��t����i����j��O�s�꒲���E���j�^�����O�ɏ]��������A�h�C�c�E�t�����N�t���g���݂��o�ăZ���T�C�h�ɓ]�o�B�����V�e�B�O���[�v�،��Œʉ݃G�R�m�~�X�g�A���C�����E�o���N�E�I�u�E�X�R�b�g�����h��s�����x�X����уo�[�N���C�Y��s�����x�X�œ��{�ɂ�����בփX�g���e�W�[�`�[���̃w�b�h���C��A�Q�O�P�R�N�W���Ƀv���r�f���e�B�A�E�X�g���e�W�[��ݗ��B���ۊ����w���ƁB
http://jp.reuters.com/article/jp_forumcolumn/idJPKBN0LO03720150220 �@ �@
�A���O���F�N�O���̕Đ����ɉ��M�����A�u�Y�������X�N�v���グ�ɉe��
2015�N 02�� 20�� 19:19 JST
�m�����@�Q�O���@���C�^�[�n - �G�R�m�~�X�g�̊ԂŁA�č��̍��N�O���̐������������C�����铮�����o�n�߂Ă���B�������̂Ȃ��ŁA�Y�����ł���č����̐ݔ���������ᐬ���ɂȂ���u�Y�������X�N�v�ɉ����A�l������v�����قNj����Ȃ�Ȃ��Ƃ��������O������B���グ�J�n�����̒x��₻�̌�̃y�[�X�ɁA�s�����������܂��Ă���B ���D���ȕČo�ς̎��p�A�ݔ������̋}�����w�E���� �P�W���Ɍ��\���ꂽ�c���v�|�ɂ��ƁA�P���̘A�M���J�s��ψ���i�e�n�l�b�j�ł́A�ᒲ�ɐ��ڂ��Ă���C���t�������߂���c�_���s��ꂽ���A������������オ��ɂ����Ȃ��Ă���Čo�ςւ̔�����s���͂e�n�l�b���ł��ʂ����Ă��Ȃ����悤���B�e�n�l�b����̗��グ������y�[�X�ɂ��Ẵ��b�Z�[�W�ɑ���s��̎~�ߕ����A���C�E��C�l�X�������B���N�O���̕Čo�ς̌����ɁA�������X�N���w�E���鐺�������Ă���B ���̈���u�Y�������X�N�v�Ƃ��Ă̐ݔ������������B�G�l���M�[�Y�Ƃ𒆐S�ɁA�ݔ������ւ̉��������͂��͂�����Ƃ��Ă����B�����Ȕ��\�̕Đ����Ƃ̐V�K�͂P�Q���܂łT�J���A�������A�h�r�l�����ƐV�K�w�����P���ɑ啝�Ɍ��������B�č���Ƃ̌i�������A��N�H�ȍ~�A�}�ቺ���Ă���B�ƌv����Ƃ͑ΏƓI�ɁA��ƕ���̈������ڗ����Ă���B �Q���̓��{���{�̌���o�ϕł��A�č��o�ςւ̕]��������C���������A����̌������i�����̉e���ɗ��ӂ��K�v�Ƃ̎w�E����������B �č��̎Y���ʂ͓��ʂP�O�O�O���o�����ƁA���V�A�Ƃقڕ��ѐ��E��R�ʂ̋K�͂��B �쑺�����������E���Z�h�s�C�m�x�[�V�������������̈��N�玁�̒��ׂł́A�������N�}���ɐL�тĂ����V�F�[���֘A�����ȂnjŒ莑�{�����͂��̂P�A�Q�N���Ƃ��Ă��Q�O���߂��������ŁA�����ƑS�̂̓����ɕC�G����K�͂ƂȂ��Ă���B�ٗp�ɂ��Ă��A�ٗp�Ґ��S�̂ɐ�߂�z�Ƃ̃E�G�[�g�͂킸���Ƃ͂��A�������N�A��_�ƕ���̌ٗp�ґ������̂R���̂P���x���A�z�Ƃ𒆐S�Ƃ���U�B�̊�^�Ő�߂��Ă���Ƃ����B ���̃G�l���M�[�Y�Ƃ̐ݔ������̌����͕Čo�ϑS�̂̉��������͂ƂȂ�Ǝw�E����̂��A�r�l�a�b�����،��V�j�A�G�R�m�~�X�g�̊ێR�`�����B�P�T�N��P�E�l�����̕Čo�ς́A�P�������܂Ō�������Ƃ݂Ă���B�u�V�F�[���Y�ƂɈˑ��x�̍����n��ł͎��{�����v�̏k�������x�o�̌����Ȃǂ������ɐ����邽�߁A�č��o�ϑS�̂ɂƂ��Ă������ł��Ȃ����e���ƂȂ邾�낤�v�Ƃ݂Ă���B ���̂��߁A�P�T�N�O���͂P�D�W�������ƁA���ݐ������������y�[�X�ƂȂ�Ɨ\�����Ă���B ���l������݉����ʂ������い �Q�ڂ��A�l������҂���Ă���قǐL�тȂ��\�����B �i�o�����K���،��͍��N�O���̕č����������ʂ��������C�����Q�D�V�T���Ƃ������A�ݔ������ɉ����Čl��������̎�v�����B���،��̃V�j�A�G�R�m�~�X�g�E�����������́u������ٗp���������ɁA�P�Q���̏���͐L�єY�B�s��̊��҃C���t�������ア�v�Ƃ݂Ă���B ���������ƌv�̏�����㉟������Ɗ��҂���Ă��邾���ɁA����̎コ���ꎞ�I�Ȍ��ۂȂ̂��A���邢�͉����i�C�̎コ�ɋN��������̂Ȃ̂��A�����͕s�����Ƃ����B ���R���Z���T�X�́u�T�d�ȗ��グ�y�[�X�v���@�@ �]���ɔ�ׂĕč��o�ςɑ��錩��������C�ɌX���Ă���Ȃ��ŁA�ĘA�M����������i�e�q�a�j�ɂ�闘�グ�Ƃ��̌�̃y�[�X�ւ̌������ω�������B ��㎁�́A���グ�J�n�����͓������ʂ��ʂ�N���Ɏ��{���A�e�q�a�Ƃ��Ă͗l�q�����邾�낤�Ɨ\�����Ă��邪�A�u���͂��̌�̗��グ�y�[�X�ɂ���v�Ǝw�E�B�u��������������̏㏸�y�[�X����w�݂�A�Ăe�q�a�����ŗ��グ�͕s�v�Ǝ咣���鐨�͂ɂƂ��čD�ޗ��ƂȂ�v�Ƃ݂Ă���B �ێR�����A�������i�̉����ɔ����ݔ����������̉e�����l���ɓ���A�]���̖��グ����P�x�݂����Ă̗��グ�y�[�X�Ɍ�������ƁA���ʂ����C�������Ƃ����B �����A�}�[�P�b�g�Ƃe�q�a�E�H�b�`���[�A�����Ăe�n�l�b�����o�[�Ƃ̊Ԃł��A�Čo�ςւ̌������A���グ�J�n���������̌�̋�̓I�ȃy�[�X���A�F���͂܂����L����Ă��Ȃ��悤���B�������́u�B��R���Z���T�X�ƂȂ��Ă���̂́A���グ�y�[�X�͐T�d�ɂƂ������������v�Ǝw�E�A�����ݔ������̕s���������������ŗ��グ���߂��郊�X�N�͌ジ������Ƃ݂Ă���B (�����@�ҏW�F�Γc�m�u)
http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPKBN0LO0QP20150220 �@ �@ �R�����F���Z�ɘa�u���^�_�v�̗��Ƃ��������㏮�Ȏ�
2015�N 02�� 20�� 18:10 JST
���㏮�� �A���C�A���X�E�o�[���X�^�C���i�`�a�j�@�}�[�P�b�g�E�X�g���e�W�X�g �m�����@�Q�O���n - �P���܂ŊC�O�s��ł͕����̕s�m���v���i�M���V�����A�E�N���C�i��A�������i�̑啝�����j��w�i�ɁA���B�ȊO�̊����s��̏�l�͏d���A����ŕč��Ȃǂ̈��S���Y���ɒ[�ɔ���꒷�������̒ቺ���������B�����A�Q���ɓ����āA�������i�̉����~�܂�Ȃǂ��āA�č��s��ł͊����A���������Ƃ��ɍ�N���̐����܂Ŗ߂����B �����̕s�m�������߂���v�f�œ��X�̃}�[�P�b�g�͓����Ă��邪�A����Ō����Ȑ����������č������ł͂Ȃ��A���Z�ɘa�ɂ��h�����ʂʼn��B�o�ς��������A��i���o�ς͑����ĉ��Ă���B�ĘA�M����������i�e�q�a�j�����ݑz�肵�Ă���Ƃ���ɁA�N���ɗ��グ���n�߂���o�Ϗɂ��邱�Ƃ��F������A����܂����i�e�q�a�̐���f�����j���i�������ӎ����ꂽ���Ƃ��A�Q����������̊����A�����㏸�������炵�Ă���ƕM�҂݂͂Ă���B �h���~����́A�Q�O�P�S�N�P�O�����̓���ɂ��lj��ɘa���āA�P�J���]��łP�O�~�ȏ�㏸���A�P�Q�O�~��܂ʼn~�����i�B�t�@���_�����^���Y�̕����̓h�����~���ŕς��Ȃ��Ă��A�N�ԕϓ����ɑ�������啝�ȉ~�����Z���ԂŐi���Ƃ�����A�h���~�̏㏸�͂������Ɉꕞ�����B�Q�O�P�S�N�P�Q���ȍ~�́A�ĉ��̊�������s��قǂɂ͐�ɋ��������X�N�v���ɉe�����ꂸ�A�P�h�����P�P�U�\�P�Q�P�~�̃����W�Ő��ڂ��Ă���B ��N�P�Q���P�X���f�ڂ̖{�R�����u���V�A��@�Ń��X�N�I�t�̉~�������͖{�����v�ihere�j�Łu���V�A���̃��X�N�I�t�ɂ��~���v�Ȃǂ̌�t���̉���ɂ��Ĕᔻ�I�ɘ_�������A�Ƃ肠�����~���͒Z���I�ȃA���ɂƂǂ܂��Ă���B ����ɘa�Ƃ�����C�x���g���I���A�������������܂��Ă��邩��Ȃ̂��낤���B�ꕔ���f�B�A�ɂ�����Ɋւ���L�����ޗ��ƂȂ�A�h���~���ꂪ�s����ɓ�����ʂ��������B ��̓I�ɂ́A�u�����_�ň�i�̒lj��ɘa���s�����Ƃ͓��{�o�ςɂƂ��Ăނ���t���ʂɂȂ�Ƃ̌��������{��s���ŕ��サ�Ă���v�ƁA�ă��f�B�A���i����j�W�҂ւ̎�ނŖ��炩�ɂȂ����Ƃ��ĂQ�����ɕA���̃w�b�h���C�������Ńh���~���ꂪ�ꎞ�~���ɋ}���ɐU�ꂽ�̂��B���Ă̋��Z���h���~�̕������ɑ傫�ȉe����^����̂�����A���ɓ���̐���X�^���X�̕ω����Ӗ�����Ȃ�A��ɏq�ׂ��u�ꎞ�I�ȃA���v�ł͍ς܂Ȃ��B �����A���ۂɂ́A���������L���œo�ꂷ��u�W�ҁv���A���⎷�s����X�^�b�t�Ȃǂ̐������Ăɂ������l���Ȃ̂��s���ł���B�ǂݎ�ɂ͒N��������Ȃ��킯�����A�M�҂́A���c���F���ٗ��������̋��Z����ɔᔻ�I�ȃX�^���X������Ȃ��l�����A�u�W�ҁv�Ƃ��ēo�ꂵ���Ɛ��@���Ă���B ���u�C���t���Ōi�C�����v�̌���� �Q�O�P�R�N�S���ȍ~�̋��Z�ɘa����̌��ʂɂ���āA���{�o�ς̉��n�܂�A�J���s��̎��������P����Ɠ����ɁA�E�f�t���̃v���Z�X���n�܂����B����͂��̌���A�v���X�Q���̃C���t�������ɃR�~�b�g���Ċɘa�������p�����A�ˑR����Ȃ�ɘa�����̗]�n������A�ƍ��c���ق͓x�X�q�ׂĂ����B���ۂɂQ���P�W���̍��c���ق̋L�҉�̔����܂���ƁA����܂ł̃X�^���X�ƑS���ς��Ȃ��Ƃ݂���B ��s���ăA�O���b�V�u�ȋ��Z�ɘa���s�����e�q�a���������K���i�D�ŁA����܂Ő����I�Ȑ�����Ă������B������s�i�d�b�a�j���Q�O�P�T�N����f�t���j�~�̂��߂̗ʓI�ɘa�ɓ��ݏo�����B�o�ψ��艻���������邽�߂ɁA���������グ���āA�f�t���j�~�ɒ��ނ̂͐��E�e���ɂ����钪���ɂȂ��Ă���B����ɁA�ʓI�ɘa�����łȂ��A���B�̊e������s�́A�e�q�a����₪���ݏo���Ȃ������A�}�C�i�X�������������Ɏ����Ă���B ���{�ł́A�Q�O�P�Q�N���̈��{�����a���Ɠ���̑̐����V�ɂ���āA��ɏq�ׂ��Ƃ���A���͂Ȑ����Ή����������Či�C���n�܂����B���Z�ɘa�������炷�i�C�h�����ʂɂ��ٗp�g�傪�x���ƂȂ�A�Q�O�P�S�N�S���̏���łƂ������}�ȋُk��������̃V���b�N���A���Ƃ����z����ꂻ���ɂȂ��Ă���B���Z����̓]���ł悤�₭���{�o�ς�J���s��̐��퉻���n�܂����킯�ŁA���Z����̌��ʂ̑傫���ɂ��đ����̍������C�Â��Ă��邾�낤�B ����A�Q�O�P�S�N�P�O�\�P�Q���̍��������Y�i�f�c�o�j���v�����\���ꂽ���A�R�l�����Ԃ�ɓ��{�o�ς̓v���X�����ɓ]�����B�č��𒆐S�Ƃ������E�o�ϕ����Ɖ~�����ʂŗA�o�������n�߁A���ŃV���b�N���痧���������B���Z�ɘa�ɂ���Ċ�ƋƐђ�グ�ƌٗp�g�傪�������A����̗������݂Ƃ����V���b�N��a�炰�����߂��B ���ꂪ���������A���Z�ɘa��ւ̉��^�_�����������炾�낤���A�Q�O�P�S�N�x�ɋN�������Ō�̃}�C�i�X�����ւ̌i�C�������A�u�C���t���㏸�v�ɂ���Ă����炳�ꂽ�Ƃ����V���v���ȗ������A�ŋ߈ꕔ�Ō��R�ƌ���Ă���B ���ۂɂ́A�ƌv�̍w���͂�D�����̂́A����łɔ����ƌv���傩����I����ւ̋����I�ȏ����ړ]�ƍl������B���ڒ������ɂ₩�ɏ㏸���n�߂����A����ȏ�̃C���p�N�g�ő�^���ł����{����ĉƌv�̎����w���͂��ڌ��肵���̂��B �u�ڕW�ɓ͂��Ȃ��Ⴂ�C���t�����ɂ����ɑΉ����邩�v�Ƃ������ɁA��i�e���̒��₪�ʊ��ɑΉ����Ă������A����ɉ����āA�������̉e���ŁA�����̐V���e���̋��Z���ǂ��Q�O�P�S�N�����瓯�����ɒ��ʂ��ċ��Z����̃X�^���X��傫���ύX���Ă���B���̂悤�Ȓ��ŁA�u���Z�ɘa�ɂ��C���t���㏸�Ōi�C�����������v�Ƃ����̂́A�f�t���}�C���h���蒅�������{�ł���������Ȃ��s�v�c�ȋc�_�ɂ����������Ȃ��B ���Ȃ݂ɁA���{�ɂ����āA���݂̊��S���Ɨ��ł���R�D�T�����x�ł́A���S�ٗp�ɂ͈ˑR�����̂ŁA���ڒ����̏㏸�͊ɂ₩�ɂ����N���Ȃ��B���Ј��Ȃǂ̑ҋ������߂�J���s��̎��v�͈ˑR�Ƃ��đ傫���A��������Ă��Ȃ��̂ł���B���ۂɁA�E�f�t���Ɏ��s�����Q�O�O�O�N�㔼���A���̒��x�̎��Ɨ��ቺ�͊ώ@���ꂽ�B��������f�t�����҂����t���Ă��܂������{�ɂ����āA���Z�ɘa�𒆓r���[�Ɏ~�߂郊�X�N���傫���Ƃ������Ƃ��B �Ƃ���ŁA�{�e�Ŏw�E�����悤�ȋ��Z�ɘa���^�_���ŋߖڗ��悤�ɂȂ�����̂��������́A�R�����ŔC�����I����{����������R�c�ψ��̌�C�l�����A���@�哱�ŁA���݂̎��s�����x���邩�����Ɍ��܂������ƂƊW���Ă��邩������Ȃ��B ���˂Ă���w�E���Ă���Ƃ���A����R�c�ψ��̑I��Ɋւ��鐭�{�̔��f�́A�A�x�m�~�N�X��O�i�������Ŕ��ɏd�v�ł���B�����āA�{�����̌�C�ɂ͓��╛���ق̊�c�K�v�j���Ƃ̋�������������A�W���I�Ȍo�ϗ��_�ɐ��ʂ�������c��w�����̌��c�����I�肳�ꂽ�B�A�x�m�~�N�X�����������邽�߂ɋ��Z�ɘa��O�ꂵ�Čo�ψ��艻���������邱�Ƃ��ˑR�d�v�ł��邱�Ƃ��A���@�͏\���������Ă���Ɣ��f�ł���B �����l����M�҂ɂƂ��ẮA���̐������f�́A�Q�O�P�T�N�ȍ~�̓��{�o�ρA���Z�s����l�����ŁA�|�W�e�B�u�ȍޗ��ł���B�����A���������l���ɔ������Ă��A���Z����ɉ��^�I�Ȑ^�t�̌����������X�̐��ʉ��̓������A�u�W�ҁv�̎v���Ȃǂ̂������ŕ\���̂��낤���B �܂��A�u�����ڕW�B���̐摗��𐭕{���e�F�����v�u����͐����ɔz�����ċ��Z�ɘa�ɑ����ɓ����Ȃ��v�Ȃǂ̋c�_���ŋߕM�҂͎��ɂ��Ă��邪�A��������{������O�ꂽ�����ĂɎv����B�����̌����̍��{�ɂ��A���Z�ɘa����ւ̉��^�I�Ȍ������O��ɂ���ƕM�҂͍l���Ă���B ����ɂ��Ă��A���Z�ɘa�ւ̉��^�I�Ȍ������ˑR�Ƃ��č���������́A�A�x�m�~�N�X���������ꂽ��������قƂ�Ǖς���Ă��Ȃ��悤�Ɋ�����B�M�҂̂悤�ȓ����Ƃ̖ڐ�����݂�ƁA���ɋ����[���B �u���Z�ɘa�͋U��ɉ߂��Ȃ��v�Ȃǂ̎v���Ɏ����A�ߋ��Q�N�̊����A�~���C���̑�������߂����Ă��܂��������A���Ȃ葶�݂��Ă���Ƃ���A���i�������j�̏I���͂��Ȃ��Ȃ̂�������Ȃ��B �����㏮�Ȏ��́A�đ��^�p��ЃA���C�A���X�E�o�[���X�^�C���i�`�a�j�̃}�[�P�b�g�E�X�g���e�W�X�g�B�P�X�X�S�N��ꐶ���ی����ЁA�a�m�o�p���o�A�S�[���h�}���E�T�b�N�X�A�}�l�b�N�X�،��Ȃǂ��o�āA�Q�O�P�S�N�T����茻�E�B
http://jp.reuters.com/article/jp_forumcolumn/idJPKBN0LO0AI20150220
�@
���敨�����L�A����I�y���ʎ����D���|�����������͏㏸
�@�@�i�u���[���o�[�O�j�F���s��ł͐敨���ꂪ���L�����B���{��s�����{��������������I�y�̌��ʂ��Ĕ������D���ƂȂ����B���ʁA���T��40�N���D���T���Ē����������͏㏸�����B
20���̒������敨�s��Œ��S�����̂R�����́A�O����T�K����147�~31�K�ŊJ�n�����B�ߌ�ɓ����Đ������グ�A�ꎞ��147�~47�K�ƁA��������x�[�X�łX���ȗ��̍��l��t�����B���̌�͂��L�єY��ŁA���ǂ͂V�K����147�~33�K�ň������B
�O��Z�F�A�Z�b�g�}�l�W�����g�̐[�㏁���^�p�O���[�v�w�b�h�́A���傤�͓���̔�������I�y���������Ƃ��A�u���낢��s��������Ă������ꏄ�����v�Ǝw�E�B���敨�̏㏸�ɂȂ������Ɛ������Ă���B�@�@
���₪���\������������������I�y�̌��ʂł́A�c�����ԂP�N���R�N�ȉ��A�R�N���T�N�ȉ��A10�N��25�N�ȉ��̉��D�{���͑O��ቺ�����B����A25�N���͏㏸�����B���D�����͂S�{�Ƃ��A��ƂȂ�O���̓��{�،��Ƌ���̔����Q�l���v�l�Ƃ̈������r�����}�C�i�X�ƂȂ����B���ϗ����i���͉����̂P�N���R�N�ȉ��������A�R�{���}�C�i�X�ƁA�S�̓I�ɂ͎s��������Ⴍ���D���ꂽ�B ���������͂P�T�ԂԂ�ᐅ���� ���{���ݏ،��ɂ��ƁA�����s��Œ������� �̎w�W�ƂȂ�V��10�N������337������́A�O���ߌ�R�����_�̎Q�ƒl���0.5�x�[�V�X�|�C���g(bp)�Ⴂ0.385���ŊJ�n�B�ߌ�ɓ���Ɛ�����艺���A�ꎞ��0.375����10���ȗ��̒ᐅ����t�����B���̌��0.39���Ő��ځB�T�N����121������͌ߌ�ɓ�����0.105���ƂX���ȗ��̐����܂ʼn�������A0.115���ɖ߂��Ă���B
20�N����151������͈ꎞ�Qbp�Ⴂ1.175����10���ȗ��̐����܂Œቺ������A1.215���ɏ㏸�B30�N����45������͌ߌ�ɓ����ď㏸�ɓ]���A�Rbp����1.445���܂Ő������グ���B40�N���̂V�������4.5bp����1.555���܂ŏ㏸�����B
�O��Z�F�A�Z�b�g�̐[�㎁�́A24����40�N���D�ɂ��āA�u�������̖߂肪���������̂ŁA�����x�����Ă��������������v�Ǝw�E�B�܂��A���T�͕ĘA�M�������x������i�e�q�a�j�̃C�G�����c�����c��،����s���\��ŁA�u���グ���҂��ǂ��������ɂȂ��Ă������v�����ڂ��Ƃ��A�u�����߂������}���������Ƃ�����A������������\���͂���v�Ƃ݂�B
����A�����������`���{�،��̑����G����X�g���e�W�X�g�́A�R���ɂ͍��̑�ʏ��҂��T���Ă���ق��A�N������Ȃǂɂ�錎���̔N���������������܂��Ǝw�E���A�u�������Z�N�^�[�ɂ��Ă͔������D���ɂȂ肻�����v�Ƃ݂Ă���B
�L���Ɋւ���L�҂ւ̖₢���킹��F���� �O�Y�a�� kmiura1@bloomberg.net;���� �R���p�T h.y@bloomberg.net
�L���ɂ��ẴG�f�B�^�[�ւ̖₢���킹��F Garfield Reynolds greynolds1@bloomberg.net �R���p�T, ��l�G��
�X�V����: 2015/02/20 15:34 JST
http://www.bloomberg.co.jp/news/123-NK0BC26TTDSC01.html
�@
���c�ɘa�̖ڕW�����͓��R��g�g�ύX�ɂ͑㏞-������IMF���ꖱ���� (1
�@�@�i�u���[���o�[�O�j�F���ےʉ݊���i�h�l�e�j�̕��ꖱ�����߂��������r���́A���{��s�̍��c���F���ق��Q���̕����ڕW�̒B��������扄������̂́u���R�v���ƌ����B�������ȂLjَ������Z�ɘa�����������ɔ���傫���ω����Ă��邽�߂��B����܂ł̋��Z����̘g�g�ݎ��̂�ς���ꍇ�ɂ͑㏞�͍������Ƃ̌������������B ���݂͍��ۋ��Z���Z���^�[�������̉������i73�j��19���̃C���^�r���[�ŁA�Q���̕����ڕW�́u������x�̃C���t�����҂��ێ�����̂ɕK�v�v�����A�B�������ɂ��Ă͓��₪�f����Q�N���x���u�K�`�K�`�̖ڕW�ƍl����K�v�͂Ȃ��v�Əq�ׂ��B�啝�Ȍ������َ͈����ɘa�������u�Q�N�O�ɂ͑z��ł��Ȃ������v�Ǝw�E�B���ω��ɉ����āu�B���������ς���Ă���͓̂��R�̂��Ƃł͂Ȃ����v�ƌ�����B
����͂P���Ɍ��\�����u�o�ρE������̓W�]�v�i�W�]���|�[�g�j�̒��ԕ]���ŁA�G�l���M�[���ɂ��C���t�����̉����������ʂ�2015�N�x��0.7�|0.8�|�C���g�Ɛ��v�B����ҕ������ʂ���14�N10�������_��1.7������P���ɉ����C�������B�����A�h�o�C �������i���P�o������55�h�����o���_�ɁA16�N�x�܂ł̌��ʂ����Ԃ̏I�Ղɂ�����70�h�����x�Ɋɂ₩�ɏ㏸���Ă����Ƒz��B16�N�x��2.1������2.2���Ɉ����グ���B
�j���[���[�N�����敨����͂P��29���ɂP�o������43.58�h����14�N�U���̍��l�����U�������B���̌��50�h���O��Ǝl�����x�[�X�ł�09�N�R�����ȗ��̒ᐅ���Ő��ڂ��Ă���B���{��12���S������ҕ����w���i���N�H�i�������R�A�b�o�h �j�́A�S���Ɏ��{���ꂽ����ł̉e����������0.5�����x�ŕ����ڕW�̂S���̂P�B19���t�̎Y�o�V���́A���₪�����ڕW�̒B��������扄����������Ō������n�߂�ƕ��B �������l�����Ɋ���� �h�l�e������04�N����10�N�Q���܂Ŗ��߂��������́A���₾���łȂ����B������s�i�d�b�a�j�Ȃǂ��ʓI�ɘa������̗p���A�e���̍������́u���Čo���������Ƃ̂Ȃ��悤�Ȑ����ɂ���A���Ԃ̎��v�͌����Ă���v�Ǝw�E�B�u���D�̓s�x�A�l���������Ȃ范�����Ȃ邪�A����Ɋ���邱�Ƃ��K�v��������Ȃ��B�{���e�B���e�B�͂��ꂩ��������Ȃ郊�X�N�͂��邾�낤�v�ƕ���p�Ɍ��y�����B
����͂Q���̕����ڕW���Q�N���x�ŒB�����邽�߁A�}�l�^���[�x�[�X ��ςݑ����u�ʓI�E���I���Z�ɘa�v��13�N�S���ɓ����B14�N10�����̒lj��ɘa�ł́A����������������]���̌��U���|�W���~����W���|12���~�ɑ��z�����B�N���Z����ƁA���{��15�N�x�ɓ��D��ʂ��ċ@�֓����Ƃ֔̔����鍑�̎s�����s�z152.6���~�̍ő�X�����ɂ��y�Ԋz�ƂȂ�v�Z���B
�������́A����ł����₪�u���Z�ɘa�̊�{�I�Șg�g�݂�ς���̂́A�����ƃR�X�g�����̂����������v�Ǝw�E�B�ʉ݈������̌��O�����シ�钆�Łu�~���̂��߂ɁA�Ƃ��������ł͍l���Ȃ��̂ł͂Ȃ����v�Ƃ̌������������B �u�����h���v�̍s�� �~�̑h������͓��₪�َ����ɘa������13�N��21����1979�N�ȗ��̉��������L�^�B2014�N12���W���ɂ͂P�h����121�~85�K��07�N�V���ȗ��̈��l��t�����B�u���[���o�[�O���W�v�����ב֗\�z�f�[�^�ɂ��ƁA���N���̗\�z�����l��125�~���B
�����ł͒�����E�N���C�i���߂���n���w�I���X�N��M���V���̍���@�A�����̒lj��ɘa�ϑ��̌�ނƂ������~���v���ɉ����A�e�����₪���Z�ɘa���������B
�ĘA�M�������x������i�e�q�a�j�͍�N10�����ɗʓI�ɘa����I�����A12���̘A�M���J�s��ψ���i�e�n�l�b�j�ł́A���グ�J�n�܂Łu�h�������Ȃ��v�Ƃ̐��������\�����B��������w�i�ɃC���t�����̐L�т͓݉����Ă��锼�ʁA�ٗp��͉��P���Ă���B�C�G�����c���͑������グ�ɐT�d�����A�u���[���o�[�O���ċ����敨�̓����Ȃǂ���ɎZ�o���������\�z�̊m���ł́A�č������N�X���܂łɏ��Ȃ��Ƃ�0.5���ւ̗��グ������Ƃ̊ϑ�����T���ƂȂ��Ă���B
��v�U�ʉ݂ɑ��鋭��������h���w�� �͂P��26����95.527��03�N�X���ȗ��̐����ɏ㏸�B�P���̂e�n�l�b�c���^�̓h�����i�s���A�o�ɑ���u�����I�ȗ}���v���ɂȂ�v�Ǝw�E�������A�č��̈ב�������ǂ��郋�[�č��������͂���܂ł̂Ƃ���A�h���������������Ă��Ȃ��B
�������́A�~�E�h������͌��݁A�u��r�I�����������ɂ���v���A�ė��グ�́u�^�C�~���O���߂����ă{���e�B���e�B�����܂�̂͌��O�ޗ����v�Ǝw�E�B�e�q�a���s��Ƃ̑Θb�헪���u�I�m�ɉ^�c���A�s�ꂪ������x�̏������Ԃ����ĂāA���グ�y�[�X��������x�z�肪�ł���悤�ȃK�C�_���X���o�����Ƃ���Ɋ��҂��Ă���v�Əq�ׂ��B �č��̈ב���ɂ��ẮA�u�������ǎ҂̔��������̎��X�ł��낢��ƕω�����v�Ǝw�E�B�u����܂ł̓��[�����Ɠ��{�����ڂ��Ȃ��������v�̂ŁA���[������~���Ɂu�����Ĉًc�������Ȃ��Ƃ����̂��č��̃X�^���X�������Ɯu�x�i�����j����v�ƌ�����B
�����A�č��ł̌i�C�s�������⑽���Њ�Ƃ̎��v�ڌ���A������Ƃ̗A�o����Ȃǃh�����̉e�������O���鐺���ċc��ɓ͂����ꍇ�ɂ́u�ē��ǎҔ����̃g�[�����ς���Ă���\���͏\���O���ɒu���Ă����ׂ��ł͂Ȃ����v�Ǝw�E�B�s��Ƃ́u�R�~���j�P�[�V�����헪�Ƃ��ẮA�ς���ꍇ�ł��ꋓ�ɕς���̂ł͂Ȃ��A���X�Ƀj���A���X��ς��Ă����̂��낤�v�Ƙb�����B
�������͕ė��グ �̗]�g��1994�N12���ɔ����������L�V�R�ʉ݊�@�ɑ呠�ȁi���E�����ȁj�̍��ۋ��Z�ǒ��Ƃ��đΏ��B�~���h����95�N�S���ɁA�����̐��ō��l�P�h����79�~75�K��t������A�������ɏA�C�����B�匴�p�����ۋ��Z�ǒ���Ɖ~�������Ɏ��g�݁A��v�V�J���i�f�V�j�������������̗����� �A��������Ȃǂœ��N�X���ɂ�100�~�̑��ɉ����߂����B04�N����10�N�ɂ����Ă͓��{�l�Ƃ��ē�l�ڂƂȂ�h�l�e���ꖱ�����߁A���E���Z��@�Ȃǂ�Ή������B �������́A���{���{�́u��v�����҂��~���i�s�ɂ͗ǂ��ʂƈ����ʂ�����Ƃ̃g�[�����B���Ԃ��ƁA�����炢�̐����łǂ����Ă�����Ƃ�����ۂł͂Ȃ��v�ƌ�����B���c���ق��u�~���Ɋւ��锭���ł́A����Ȃ�ɐF��ȋt�E�i������j��t���Ă���悤�Ȉ�ۂ��v�Ǝw�E�B�s��ւ̉e�����l����Ɓu��т��ē����g�[���Řb�����Ƃ��ɂ߂ďd�v���B���ق������ɂ��قǔF�����Ă���̂ł͂Ȃ����v�Əq�ׂ��B�@
�֘A�j���[�X�Ə��F�s�V���������A���Œ��~���̊m��50���ȉ��|�s��͐��肵�߂��~�X�^�[�~�E�匴��:�~���͢���{���裂ɂ��炸��~����������蓾�Ȃ��y�N���W�b�g�s��z��R���̂������ޣ���|�|���C�����g���v�����x�� �L���Ɋւ���L�҂ւ̖₢���킹��F���� ���Ύ� snozawa1@bloomberg.net;���� Chikako Mogi cmogi@bloomberg.net
�L���ɂ��ẴG�f�B�^�[�ւ̖₢���킹��F Garfield Reynolds greynolds1@bloomberg.net ��l�G��, �� ��
�X�V����: 2015/02/20 14:13 JST
http://www.bloomberg.co.jp/news/123-NK1QOL6JTSEI01.html
|
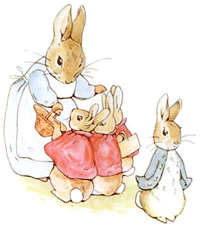
 �X�p�����[���̒����猩���o�����߂Ƀ��[���̃^�C�g���ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B
�X�p�����[���̒����猩���o�����߂Ƀ��[���̃^�C�g���ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B