03. 2015年1月20日 10:12:26
: nJF6kGWndY
時間スケールを、どう考えるかだが、今後、供給が絞られ、新興国を中心に需要が増えれば上がるのが当然だhttp://jp.reuters.com/article/topNews/idJPKBN0KS0DO20150119
視点:原油安は短命、年後半に90ドル目指す=伊藤敏憲氏
2015年 01月 19日 18:07 JST
伊藤敏憲 伊藤リサーチ・アンド・アドバイザリー代表取締役 [東京 19日] - 原油価格は当面、下値を模索する局面にあるが、早ければ2月か3月に底を打ち、年後半には70ドルから90ドル台前半の水準に戻る可能性もあると、エネルギー関連の調査研究などを手掛ける伊藤リサーチ・アンド・アドバイザリーの伊藤敏憲氏は予想する。最大の根拠は、需給動向の大きな変化が見込めることだ。 同氏の見解は以下の通り。 <サプライズではない原油安> 2014年8月に始まった原油安の進行を「サプライズ」と捉えた人は多いようだが、むしろよくそこまで持ちこたえたものだというのが私の率直な見方である。 そもそも原油需給は2013年第1四半期から明らかに弛(ゆる)んでいた。需要の伸びが想定以下にとどまる一方で、供給の伸びは高く、世界的に需給は緩和された状態にあった。つまり、ファンダメンタルズの面からは原油安局面は2年前に始まっていても不思議ではなかった。 では、なぜ昨年夏場まで原油高トレンドが継続したのか。一つには、地政学リスクだ。「アラブの春」以降、中東・アフリカの産油諸国で政情が相次ぎ不安定化した。原油市場の特性として、地政学リスクが顕在化すると、当初は最大リスクを織り込む傾向がある。これが、相場に上昇バイアスをかけた可能性が高い。 次に、過剰流動性の問題だ。原油・石油製品に限らず、幅広い国際商品が世界的な金融緩和マネーによって押し上げられる状況が続いていた。特に米国の量的緩和(QE)で供給されたマネーの多くが新興国・資源国や投機に向かったことは周知の事実だ。 ところが、こうした構図に、大きな変化が見られ始めたのだ。 まず、地政学リスクについては、昨年半ば以降は新しい大きな政情の変化が起きなかった。「イスラム国」の台頭に伴う中東情勢にせよ、ロシア・ウクライナ情勢にせよ、依然として不安定な状況にあるとはいえ、現時点までに原油・天然ガスの世界需給に大きな影響を及ぼしていない。 また、過剰流動性についても、米国が10月にQEを終了し、今年中の利上げ開始を視野に、金融緩和の出口に向かい始めた。原油はドル建てなので、米国の金融政策ががらりと変わると、当然、その価格形成に大きな影響が及ぶ。ドルと原油価格は、かつて逆相関で推移していたこともある。 そして、需給についても、さらに弛む方向で進んだ。供給が着実に拡大する中で、昨年半ば頃から、中国・欧州・日本の原油需要が当初見込まれていたほどの伸びを示さなくなった。この結果、需給の緩和どころか、まさに崩壊の様相を呈してきた。 このようにさまざまな要因の変化が絡み合って生じたことで、原油安が夏場以降加速したと私は考えている。 ちなみに、11月末に原油相場がさらに大きく崩れるきっかけを与えたのは、11月27日に開催された石油輸出国機構(OPEC)総会で加盟各国が協調減産に合意できなかったためと考えられているが、仮に減産で合意していたとしても、原油価格は上昇しなかったか、上昇したとしても一時的なものにとどまったのではないか。実際、過去にOPECが減産に動いた場合でも、ほとんどのケースで、下落トレンドに歯止めをかけることはできなかった。 なぜかと言えば、OPECの位置づけを考えてほしい。OPECは「スイングプロデュサー」、すなわち需給の調整役である。その調整役が協調減産を余儀なくされる局面は、それだけ需給が緩和していたということだからである。 また、OPEC加盟国の多くは、原油・石油製品・天然ガス以外に主要な輸出産品を持っていない。それらが国家の収益の大半を占めているのが実情だ。価格が低迷する局面で実入りの減少を抑える方法は、生産を拡大することである。実際、協調減産が加盟国の抜け駆けによって、形骸化することは珍しくない。 <50ドル割れは長期化しない> では、原油価格は今後も下がり続けるのだろうか。実は私は、現在のような50ドル割れの状態はそれほど長く続かないと見ている。もちろん、今は下値模索中であり、年前半に一時的に40ドルを割る局面もあるかもしれない。 ただ、後述するコスト面を考えると、この状況が続けば、早晩、供給調整が進み、価格に上昇圧力がかかる。恐らく早ければ2月、3月には底を打ち、その後は60―90ドルを目指して、上昇していくと見ている。年後半には70ドルから90ドル台前半までの水準に戻る可能性もある。 最大の根拠は、需給動向が大きく変化する可能性があることだ。まず生産調整は、すぐにではなくとも、次第に進むようになるだろう。 石油掘削設備の損益分岐点は、大別して2つある。一つは開発から生産までにかかる総コスト、もう一つはオペレーション(操業)コストだ。現在の価格だと、操業コストはカバーできても、原油価格が高騰した2000年代半ば以降に開発された多くのプロジェクトが総コストを回収できるような状況ではなくなっている。結果的に新規の探鉱・開発・掘削には急ブレーキがかかる可能性が高い。 原油価格が高止まりしていた間、供給力を増した北米のシェールオイルに関しては、過去の原油価格と掘削設備(リグ)の稼働基数との相関性を調べると、60ドルから80ドル程度に総コストで見た損益分岐点が存在しているケースが多いと考えられる。原油価格が継続的に80ドルを下回ったのは11月だ。その頃から新規投資にブレーキがかかり始めたと考えられる。 北米のシェールオイルの操業コストは40―50ドルでも回収できると推定される。また、掘削の権利を確保している事業者は、とにかく掘り出してしまう可能性が高いので、すぐに生産量が落ちるわけではない。 しかし、新規の掘削が止まることによって、過去の経緯からすると、3―4カ月後からリグの稼働基数がぐんと減少し始める。2月か3月頃から稼働基数は大きく減少する局面に入るのではないか。もともとシェールオイルの特徴は、在来型の油田に比べると、規模が小さくて、生産量の減衰のスピードも速い。 一方、需要に目を移せば、中国の回復もあると考えている。同国の貿易統計を見ると、2014年の夏から秋にかけて原油・石炭など様々なコモディティ商品の輸入が対前年比で減少していた。同国の経済情勢に照らすと、極端な調整が起きていたと考えるのが妥当だろう。中国の輸入量が増加に転じる局面は早晩来ると見ている。 また、世界経済のけん引役である米国経済は比較的好調であり、エネルギー消費は堅調に推移している。シェールオイル・ガス増産などに伴う国産原油・天然ガスの供給拡大によって、海外からのエネルギー輸入量は減少していたが、先述したように原油安を受けて新規開発にブレーキがかかる状態が続けば、同輸入量が再び拡大する局面が来るはずだ。2008年のリーマンショック後の原油安はニューヨーク原油先物相場(WTI)が先導したが、今回もWTIが原油価格の反発をリードする可能性がある。 <過去の経験則が示す上値余地> 原油価格は果たしてどこまで戻すのだろうか。この点については、過去の経験則が役に立つ。直近の安値とその後の高値との乖離(かいり)は、過去の上昇局面ではいずれも3倍から4倍の範囲に収まっている。 例えば、WTIについて、2008年9月のリーマンショック前の価格変動を見ると、2007年1月につけた安値が49ドル台、そして2008年7月につけた高値が147ドル台と、ぴったり3倍だ。その後、リーマンショックを経て、32ドル台まで下がって、2011年4月末から5月頭にそのおよそ3.5倍の水準(114ドル)まで戻している。それ以降、今回の急落局面に至るまでは、おおむね90ドル台から110ドル台の間で推移してきた。 つまり、足元の下落局面でどこまで下がるかによって次の高値めどが見えてくると言える。30ドル台まで調整されるならば、次の高値は、理論上は100ドルから140ドルとなる。ただし、たとえそうなっても、需給構造が変わっているので100ドル超に至るまでには2年、3年はかかるだろう。 テクニカル分析でも、上値の重さは裏付けられる。先ほど言及しなかったが、原油価格が急落した、もう一つの理由はテクニカル要因だ。2009年後半から形成されていた下値抵抗線(90ドル台前半)を下回る水準まで原油価格が下がったのが8月下旬。それ以降、一気に崩れた。テクニカル的には、とても強い下値抵抗線は、それを下回った瞬間に上値抵抗線に変わる。そうしたチャート上の節目を考えると、100ドル台まで切り上がる状況は当面予想しづらい。 では逆に当面の下値めどが見当たらなくなった現在、底なし沼のように落ちていく可能性はあるのか。一部には、1990年代後半に10ドルを割ったことを指して、30ドルどころか、もっと下をうかがうという見方も出てきている。しかし、その可能性はかなり低いだろう。原油市場を取り巻く環境が当時とは全く異なるからだ。 何よりコスト構造が変わっている。2000年代後半以降に生産量が増えた、例えば南米・アフリカ・中央アジア・オーストラリアなどのプロジェクトは採算ラインが相当高く、そこまで下がる前に生産調整が進み、価格に上方圧力をかけるだろう。エンジニアリングコストや石油開発の専門家の人件費は当時の比ではない高さだ。50ドル割れの状況に長く耐えられるような構造にはなっていない。 また、長期トレンドで見ると、少なくとも1999年以降、上げ下げを繰り返しながら、ほとんどのコモディティ商品が徐々に下値を切り上げている。こうしたチャート分析が示唆する情報を軽視するのは禁物だ。 <過大評価されるシェール革命> 最後に米国のシェールオイル・ガスについて補足しておきたい。一部に、シェール革命がエネルギーコストの劇的な低下をもたらすとの論調があるが、私はそうした見方やシェール革命という表現自体に違和感を覚える。 シェールオイル・ガスは確かに米国国内のエネルギー市場には大きなインパクトを与えた。また、北米からの原油や天然ガスの輸出拡大が世界のエネルギー市場に今後徐々に影響を及ぼす可能性はある。しかし近い将来、革命と呼べるほどのものになるとは思えない。 というのも、ガス状のままで取引される天然ガスについては、パイプラインが行き渡っている地域の需給のみによって、価格が決まる特性があるからだ。天然ガスは基本的にローカル商品であり、簡単に貯蔵したり、貯蔵量を調整したり、輸送したりできる原油・石油製品・液化石油(LP)ガスのような国際商品とは違う。 むろん、シェールガスについても、今後、液化プラントの整備が進めば、液化天然ガス(LNG)として、長期契約のみならずスポット市場でも海外に振り向けられるケースは増えてくるだろう。しかし、LNGプロジェクトは相対的に総コストが高く、今の原油価格水準で開発が急速に進むことは期待薄だ。 そもそも2009年以降のシェール開発は、天然ガスの価格が急落したため、オイルが中心となっており、ガスはもっぱらオイルに付随して生産される随伴ガスである。実際、米国のガスリグの稼働基数は増えるどころか、ピーク時の5分の1程度にまで減少している。 米国産ガスの供給増が世界のガス価格を引き下げるという見方も、どうなのだろうか。価格はより大きなマーケットに引っ張られるものだ。米国の輸出量と世界の取引量を比較すれば、圧倒的に後者が大きい。米国の価格が世界の価格にさや寄せされると考えるべきだろう。つまり、世界の価格は多少下がるが、米国の価格はもっと上がるというのが実際に起こることではないのか。 ただ、シェールについては、一つ革命だったと言えることがある。それは、ピークオイル(石油資源の枯渇)説をかき消してくれたことだろう。開発コストの大きさから、シェールオイル・ガスが大量に賦存(ふぞん)していると推察されている中国内陸部などのプロジェクトは現時点では開発のめどが立っていないが、シェールオイル・ガス、オイルサンドなどの非在来型の化石燃料は北米だけでなく、世界各地に存在することが確認されている。 振り返れば、かつてピークオイル説を一つの根拠として、原油200ドル説が吹聴されたこともあった。インフレや需給構造の変化などによって将来200ドル超に上昇しないとは言い切れないものの、少なくとも石油資源制約を理由とする価格高騰説は鳴りを潜めた。それが、シェール資源開発の果たした最大の貢献ではないだろうか。 *伊藤敏憲氏は、エネルギー関連の調査研究・コンサルティングなどを手掛ける伊藤リサーチ・アンド・アドバイザリーの代表取締役兼アナリスト。大和証券、大和総研、HSBC証券、UBS証券などを経て、2012年1月より現職。2013年9月にEY総合研究所の客員研究員に就任。内閣府、経済産業省、日本証券アナリスト協会などの審議会・研究会の委員を歴任。 |
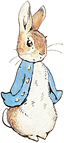
 スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。 スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。