01. 2014年10月14日 07:32:57
: jXbiWWJBCA
世界の警察官がいない世界に
日本はどう立ち向かうべきか?
2014年10月14日(Tue) 山下 輝男
昨年秋以来、気にかっている事項がある。米国が世界の警察官としての役割を降りると言明したが、本当にそうなのかどうなのかが、この1年の小生の関心事項であった。本稿脱稿時点(9月11日)に至るまでの米国が関与したいくつかの事例を検証し、本当に警察官役を降りたのかどうか、降りたとすれば日本はどうすべきなのかについて私見を述べたい。 ウクライナ問題が何とか収束の方向が見え、イラク問題もどうやら有志連合により対イスラム国作戦を展開する方向になりつつある現時点での小生の私見である。 バラク・オバマ政権は少なくともあと2年強は継続する。一部には、既にレームダック状態に陥っているとの指摘もあり、任期の残り2年間で、状況によっては、国際社会の構造が劇的に転換するかもしれない。次期政権は違う政策を打ち出す可能性もあるが、それを期待するのみではあまりにも芸がない。 米国は、本当に世界の警察官を降りたのか? オバマ米大統領、イスラム国打倒に向け国際的連携を呼びかけ
NATO(北大西洋条約機構)の首脳会議で会見するバラク・オバマ米大統領〔AFPBB News〕 1 第2次オバマ政権の大転換 オバマ大統領は、シリア問題に関する2013年9月10日のテレビ演説で、「米国は世界の警察官ではないとの考えに同意する」と述べ、世界の警察官の役割を降りるとの意思を明確にした。 もっとも、歴代の政権が担ってきた「世界の警察官」としての米国の役割についても「約70年にわたって世界の安全保障を支えてきた」と歴史的貢献の大きさは強調したのだが・・・。 この演説をどう評価すべきなのか? 国際社会の問題解決から逃避し、第2次世界大戦前まで原則としてきた孤立主義(Isolationism、モンロー主義)に回帰しようというのか。あるいは、引き続き国際社会の諸問題に関与はするものの、軍事力の行使は抑制的に行うといのうか。 いずれのメッセージと受け取るかは、解釈の分かれるところであるが、大統領や米国の真意は奈辺にあるのだろうか? 米国は、自信を喪失すると、初代大統領ワシントン以来の伝統である孤立主義に回帰する傾向があるようだ。 5月28日の外交演説では、「米国は常に世界の指導的な立場でいなければならない」と表明し、孤立主義を否定し、国際協調路線の継続を明確にしたと受け止められた。しかしながら、この演説にもかかわらず、ウクライナ、中東そしてアジアへの関与を見ると、かっての世界の警察官に戻る力も意思もないのではないかと思わざるを得ない。 昨年9月の演説以降の米国の実際の行動を、次項で検証してみたい。 2 オバマ演説後の米国の威信の低下、軟弱・弱腰外交 シリア大統領、化学兵器の国連決議順守を表明
シリアのバッシャール・アサド大統領〔AFPBB News〕 (1)シリア化学兵器危機 シリア内戦、特に化学兵器により一般市民が犠牲になった事案に対する米国の対応を見てみる。2013年8月、ダマスカス郊外で、化学兵器によって1400人あまりの市民が犠牲になった。 オバマ大統領は8月下旬、アサド政権による蛮行と結論づけ、「シリアが越えてはならない一線を越えた」として軍事介入を示唆した。米上院外交委員会は、シリアへの軍事攻撃を、地上軍投入禁止、軍事行動期間最大90日限定との条件つきで承認した。 しかし、シリアへの攻撃について、英国は同調せず、米の世論調査においても60%が反対とされ、共和党の議員の多数が反対し議会の否決も予期される状況であり、オバマ大統領自身も本心は軍事介入に消極的だったとされる。 米国にとっては幸い(?)なことに、9月上旬、ロシアが、シリアの化学兵器を国際管理下に置き、化学兵器禁止条約に参加することを提案、この提案に対してアサド政権が同意すると、米国も同意し、シリアの化学兵器を国際管理下で廃棄させるとの安保理決議も全会一致で採択された。 米国は、ロシアの提案に乗ってシリアの化学兵器を国際管理下に置くことに同意、オバマ政権は窮地を救われ、ロシアに借りを作った。 (2) ウクライナ危機 ア クリミア併合(2014年初〜3月下旬) 2014年初のウクライナにおける政変で親ロシアのビクトル・ヤヌコビッチ政権が崩壊し親欧米派の暫定政権が発足したことにクリミアは反発し、親ロシア派が実権を握り、クリミアのロシアへの編入を問う住民投票を3月16日に行うことを決定、ウクライナからの独立も宣言した。 住民投票の結果、9割以上の賛成票が投じられた。これに従って3月17日に独立と、ロシアに編入を求める決議を採択した。ロシアは独立を承認するとともに、翌3月18日にロシアへの編入を承認した。 この間、ロシアは国境沿いに部隊を集結させる等軍事的圧力をかけた。これに対して、ウクライナは3月11日に欧米に対ロシア軍事行動を要請したが、それは承認されることはなかった。 この一連のロシアの行動に対して、米国等は、3月18日、編入を非難、20日にロシアのウラジーミル・プーチン大統領の側近を制裁対象に加えるなど、新たな対露制裁を発表し、G8からロシアを除外した。 しかしながら、軍事行動については、3月19日、オバマ米大統領は、米国がウクライナで軍事行動に関わることはないと発言、「もっと良い道がある。ウクライナの人々でさえ、米国がロシアに軍事的に関与することは不適切で、ウクライナにとっても良いことではないと認めるのではないか」と述べたとされる。 クリミヤ併合は、EUのロシアへの経済依存度が高いということと、米国などが軍事行動を起こすことはないと見透かし、欧米の足下を見てのロシアの決断だった。 イ それ以後の情勢と米国の対応 クリミア併合以後、ロシアに支援された親露派武装集団とウクライナ政府との武力衝突が激化した。米欧諸国は、対露経済制裁を逐次に強化したものの、さしたる効果はなく、武装集団の勢力範囲が拡大されるに及び、ウクライナ政府と親露派武装集団が停戦合意(9月5日)するというウクライナ政府が追い込まれる事態にまでなった。 しかも、東部2州に特別な地位を認めるまで譲歩しての停戦合意であり、ロシアの思う壺ではないか。ウクライナ大統領も東部に対する自治権拡大を認める方向である。 もちろん、北大西洋条約機構(NATO)も手を拱いているわけではない。経済制裁(発動は未定、発動の場合ロシアも対抗措置の可能性と言明)および即応部隊の創設などの集団安保を強化するとともに、ウクライナで軍事演習を行うという決断を行った。米国も200人を派遣するという。 ロシアに対する強力な牽制にはなるだろうが、現状での固定化が進み、結局はロシアの思惑の通りになるのではなかろうか? いずれにせよ、プーチン大統領の戦略的な勝利と言わざるを得ない。 (3)イラク情勢への関与 イラク戦争後の2006年5月に発足したマリキ政権は、イスラム教シーア派主体である。国民和解を標榜しての発足ではあったが、統治能力に欠けるとして欧米から非難され、退陣を求められていた。 2014年初め以降勢力を拡大してきたイスラム教スンニ派の過激派組織「イスラム国」(ISIS)に脅威を感じた米国は、2014年6月下旬、イラクの空爆要請は断り、代わりに軍事顧問団(300人規模)をイラクに派遣した。 米国防総省は8月8日、イラク北部でイスラム過激派「イスラム国」への限定的な空爆に踏み切り、以降継続的に限定的な空爆を実施し、9月8日で1か月となった。 米国人ジャーナリストを相次いで殺害しているイスラム国に対して、米議会が攻撃強化を求め、9月上旬以降、安保理やNATOなどと国際的な包囲網を構成すべく協議を始めた。 オバマ大統領は、9月10日夜の演説で、イスラム国を打倒するため、米国が確固とした容赦ない軍事作戦を展開し、米軍の空軍力で各国の地上部隊を支援する。この戦いは反テロ戦略に沿ったものであり、米国が対イスラム国の幅広い有志連合を率いると述べた。 しかしながら、米国の戦闘部隊が外国領土で戦うことはないとも述べ、改めて地上部隊の派遣を否定した。 なお、対イスラム国作戦においてシリアに対しても空爆を拡大する方針を表明した。一時期、シリアに対する攻撃を検討した国に対するある意味ではアサド政権支援とも受け止められ、国際情勢は複雑だと思わざるを得ない。 (4)パレスチナ問題 ガザ地区のトンネル破壊に係るイスラエルとハマスの戦闘に関しても、薄氷を踏むような停戦がやっと成立した。この間における米国のリーダーシップの凋落は明らかである。米国はもはや強力な仲介者では足り得ないし、あえて中立的に振舞おうとしているかに見え、イスラエルや親米諸国の米国に対する信頼が揺らいでいる。 (5)リップサービスは十分だが・・・ ●2014年4月24日、赤坂の迎賓館で行われた日米首脳会談で、オバマ大統領は尖閣諸島が日米安全保障条約の適用対象であることを明言した。 ●2014年8月9日、ミャンマーの首都ネピドーで米中外相会談を行われた。ジョン・ケリー国務長官は、中国とフィリピンなどとの摩擦を念頭に中国を批判したが、王中国外相は反論したという。 東南アジア諸国連合(ASEAN)は、米国の本気度をどう認識しているのか? 南シナ海では中国の挑発が続き、米国が戦後築いてきた国際秩序が揺らいでいるが、有効な手を打ち出せないでいる。 3 米国の行動考察 (1)自ら前面に出ず、国際連帯を重視する傾向顕著 ウクライナもイラクも、国際的な連帯・連携を重視し、共同行動を採ることが重要であると認識して、そのために必要な根回しや協議を行っている。このやり方は、一見合理的に見えるが、そのような態勢を採るには相応の時間を要する。その間に、ロシアは既成事実を積み重ね、イスラム国の脅威は拡大している。 世界の警察官であるならば、初期対応が極めて重要であるはずだし、抑止力を発揮して、事態を悪化させない、拡大させないことが重要であるはずだが、そのような意識はない。 (2)主導権なき米国の対応 前項のような対応を取るがゆえに、米国の諸情勢への対応を見ていると、すべてが後手後手となっており、なすことが消極的となる。これは、情勢に対する明確な理念が確立していないからであろう。 ロシアに対して先手を取って行動しておれば、さすがのロシアも沈黙せざるを得なかったはずだ。特に大国同士の抗争においては先手を取った方が断然有利である。 イラクについても、イスラム国に対する明確な理念がないので、状況対応に追い込まれ、イスラム国の勢力拡大を許している。やっと危機感を抱き始めて、9月5日、イスラム国を倒すための10か国連合を組むことを決め、10日夜の国民向け演説で説明を行った。 オバマ大統領は、自らの警察官としての役割は極小化し、関係各国との国際協調路線を推進していると思われる。 しかしながら、ウクライナの状況を見ても、そのような路線は、決定に時間を要し、各国の利害が絡み、非効率的であり、実効性にも疑問が残る。警察官なき世界というのはそういうものであることを思い知ったはずではないのか? (3)軍事力を行使せずに、戦略的・政治的目的を達成できるのであれば、孫子に言われるまでもなく、それは上善である。しかし、軍事力はそれが使われる可能性があると考えるがゆえに、抑止効果がある。 外交的な制裁〜経済的・財政的制裁〜空爆や空母の展開による威嚇などの軽度の軍事力行使〜地上部隊による攻撃までのあらゆるオプションとそれらによって達成できるであろう戦略目的を冷静に分析・考量しなければならないはずだ。 10日夜の演説では、最終的にイスラム国を壊滅させると威勢のいい言辞がみられたが、その戦略目的を達するための作戦は果たして妥当なものか? 戦略目的と手段が釣り合っていないのではないか? (4)米国が行っている世界の警察官としての行動は、経済制裁などを除けば、地上部隊による軍事作戦は伴わず、空爆のみである。空爆を行う場合でも目標を極めて限定し、人道的支援あるいは大量破壊兵器による女性や子供を含む一般市民殺害への制裁を行う場合に限ると極めて抑制的である。 良く言えば、国際社会や国内世論の動向を睨みつつ慎重の上にも慎重に軍事行動を行う極めて慎重な対応である。しかしながら、慎重さは優柔不断の裏返しでもある。オバマ氏の人間性が顕れているようだ。 (5)限定的空爆のみでは達成できる成果も極めて限定的であり、それをもって世界の警察官の役割を果たしていると言えるのか? 仕方なしにお茶を濁しているとしか思えないし、単なる自己満足ではないか。現時点までは、空爆はそれなりの効果はあるものの、限界がある。それはベトナム戦争を見れば明らかだ。 空爆のみで、例えばイスラム国を一掃・撃破できるのか、疑問である。対イスラム国作戦が、向こう3年程度は予期されるとしたら、その間空爆と情報提供だけで済むのだろうか?新たな作戦は必要ないか? イラクやシリア等の関係国の軍事力の増強が思惑通りに進むのか、不確定要素だらけだ。米国が、兵家が最も戒めるところとする戦力の逐次加入に陥らぬか気にかかる。 (6)米地上部隊の投入は、運用の柔軟性ある航空攻撃や空爆と異なり、引くに引けない状況に陥り、ズルズルと泥沼に嵌まり込んでしまう可能性があるので、基本的には、軍事オプションとしては採用しないとの基本的方針であろう。 利口だとは思えないのだが、なぜか、そのことを早々と言明して、自らの手足を縛ってしまう。 (7)軍事オプションを採用するかどうかについては国内世論や議会の動向をことさらに気にする。また、相手が強国であり、強烈な反撃が予期される場合には、軍事行動は控えがちだ。 国民に対する情報開示と取り得るオプションとそれのメリット・デメリットを示して啓蒙すべきであると思うのだが・・・。 そのような努力がなされているのか懐疑的だ。民主主義国家は、危機感が鈍いのは常ではあるが、状況を正確に国民に伝える責務も国には在るはずだ。 (8)大統領が、日米首脳会談で、日米安保の適用範囲に尖閣が包含されることを明言したが、これほど明確に述べるのは極めて異例であると言える。 4 米国が極めて抑制的な軍事オプションを取らざるを得ない背景 警察官が警察官としての役割を果たすためには、その意思があることとその能力があることの2つの条件が不可欠である。この条件を基本に、いくつかの要因を指摘したい。 (1)巨額の財政負担 2013年3月には、財政赤字削減を巡って、共和、民主両党の協議も決裂し、歳出の強制削減が発動された。その結果、国防費が削減された。 また、債務上限引き上げ問題でも、与野党対立が激化し、デフォルトに陥る危機的状況であった。一部の政府機関が閉鎖され、同年10月のAPEC(アジア太平洋経済協力)首脳会議にも大統領は欠席せざるを得なかったのは記憶に新しい。 2009年以降、1兆ドルを超える財政赤字が続き、貿易赤字も拡大し、双子の赤字と言われてきたが、最新のデータでは財政赤字も貿易収支も改善しつつある。しかしながら、国防費の増額は財政赤字の拡大に直結するので、大規模な軍事作戦遂行には抑制的にならざるを得ないと考えられる。 (2)国民の厭戦気分の蔓延と内向き志向 イラクとアフガニスタンでの12年間の戦闘で数千人の兵士の命と巨額の国費を費消したと言われる。そして、その結果がどうであったかというと、世界から感謝されないばかりか批判・非難を受けた。 2013年9月上旬に米国内各地で開かれたシリア攻撃反対のデモには、多くの退役軍人も参加したと言う。 国民の厭戦気分は世論調査にも表れ、なぜ米国が諸外国の問題に介入するのかに国民が疑念を表明している。最新の世論調査でも半数以上が、「米国は自国の問題に専念すべきであるとの論に賛同しているとされる。この傾向はエリート層も同じである。 米国民は、不幸なことだが、イラク戦争で、そしてエドワード・スノーデン証言で、政府の説明を信じなくなっている。政府がいくら警察官としての役割の必要性を説明しても国民に受け入れてもらえない。それが政権の政策不支持となって世論調査に跳ね返っている。 イスラム国によるジャーナリスト殺害を受けて、空爆に対する国民の支持が増加したが、それでもなおかつ地上部隊を派遣してまでもという段階にまでは至っていない。米国の内向き志向はかなり強固であると認識すべきだろう。 (3)軍事介入の結果に失望 米国は戦後、多くの紛争に軍事介入し、多くの人命を失い、巨額の国費を消費した。しかしながら、米国が得たものは果たして何だったのか。称賛と感謝ではなく、批判と非難の嵐であり、国内世論の分裂であってみれば、彼らが軍事介入に懐疑的になるのもうなずける。米国民の内向き志向の背景にはそのような思いが潜んでいる。 (4)国際社会の賛同などの有無 国際社会においても、米国は孤立することを恐れている。もちろん、唯我独尊では困るが、一寸した批判にも、行動を躊躇う傾向が強すぎる。イラク戦争で、サダム・フセインが持っているとされた大量破壊兵器が結果的に存在しなかったことで、国際社会から厳しい批判に晒されたのがトラウマになっているのかもしれない。 (5)米国の孤立主義を可能とするシェールガス革命 化石燃料はもはや米国にとって、国家安全保障上のキー・ファクターでなくなりつつあるのではなかろうか。米国が、中東問題に対して、冷淡になりつつあるとしたら世界にとっては不幸だ。 (6)小規模な紛争といえども、二正面の作戦遂行を回避したいとの思惑が働いている。 圧倒的な戦力を有していた時ならば、いざ知らず、相対的に低下している現状においては、手を広げたくないとの意識が強いのだろう。 4 警察官なき世界はどうなるのか? (1)予想される事態 警察官不在の社会はどうなるのであろうか? 弱肉強食、泥棒やギャングの横行する暗黒の社会が思い浮かぶが、法と秩序を守るべき警察官がいない国際社会も同様であろう。 冷戦後の超大国米国とその他の諸国と言う一強多弱の国際社会から、概ね同等レベルの軍事力を持つ諸国が牽制と覇権を繰り返す多極化時代に突入しつつある。もちろん、米国が相変わらず圧倒的な力を持つことには変わりはないが、それを行使する意思が希薄であるから他の諸国と同等であると考えて戦略を構築すべきだろう。 米国の緊密な同盟国であるイスラエルは「いかなる脅威からも自己防衛できるよう力を強化しなければならない」(ネタニヤフ首相)とし、もう米国を頼りにしない姿勢を打ち出している。同様の認識は、多くの国家に共通するものだろう。 地域覇権を狙う国家にとっては、目の上のたん瘤がいないのでやりたい放題だろう。一方、弱小国家は、合従連衡して、覇権国に対抗しようとするだろう。国連という集団安全保障が機能しない体制では、この動きは止めることができない。 (2)日本への影響 米国が世界の警察官を降りて孤立主義・内向きになれば、日本にも甚大な影響が及んでくる。日本の防衛は米国の核抑止力を含む抑止力に大きく依存しているが、その抑止力が効かなくなれば、単独自主防衛を目指すしかない。 中国との抑止力均衡が崩れる可能性があり、日本は、中国にのみ込まれてしまうかもしれない、また北朝鮮に対する抑止効果もなくなり、核やミサイルの脅威に自力で対処しなければならなくなる。 核に対するには核しか有効な対抗策がない状況においては、日本としては、自らの核武装も視野に入れなければならなくなるかもしれない。 国民意識的に、財政的に、核武装のような負担に耐えられるのであろうか。あるいは、戦わずして敵の軍門に白旗を掲げるのを最善とする敗北主義が日本を覆うかもしれない。 5 日本はどう対応すべきか? (1)日本自身の防衛努力 危機管理の基本は「最悪の事態に備える」ことであり、そういう意味において、米国がいざという場合に頼りにならないとすれば、自らの平和と安全は自ら守るとの決意の下、相応の努力を行うことである。米国に期待し得る部分・程度を冷静に分析して足らざるは自ら構築しなければならない。 ●新大綱・中期防の確行なし得れば前倒しの実施
●安全保障法制の整備に関する閣議決定(7月1日)に関する法的整備 (2)国際協調と積極平和主義 米国の力が相対的に低下しているとすれば、共通の価値観と利害を有する諸国家と協調して対処することが必要である。ASEANや豪、印との連携は極めて重要である。第二次安倍政権が掲げる積極平和主義を推進することだ。 対イスラム国戦略では日本も応分の貢献を求められるだろう。少なくとも軍事以外の分野では貢献可能なものが多々あろう。日本がさらなる一歩を踏み出すかどうか、覚悟を決めて議論する必要があろう。 ●地球儀俯瞰外交の下推進しつつある諸施策の実施 (3)日米関係などについて 米国の内向き志向が一時的なものかどうかは不明であるが、我が国も他の諸国も、米国にばかり警察官としての重責を押しつけるばかりで、感謝の念を表したことがあったのか、時には批判と非難を口にしたのではないか。 また、自ら応分の負担を負おうとしたか、顧みて反省すべきだ。もちろん、米国が警察官としての役割を果たすことには米国なりの冷徹な国益の追求があったとしても、その恩恵に浴したことは間違いないのだから、感謝すべきだろう。それを前提として新たな日米関係を模索すべきだろう。 ●米国は日本助けるべしとの世論が形成されるために両国の関係をさらに強固にするための戦略的アプローチを構築し、推進すべし ●日米防衛協力のための指針(ガイドライン)の改定に向けた協議の実施と速やかな策定
●安全保障法制の整備に関する閣議決定事項の内日米関係に関わる事項の早急なる実行 (4)米国民の意識をどうして変えるか? 国際社会はいまだに米国の力を必要としているということをいかにして米国民に理解してもらうか、それは米国政府の為すべきことではあるが、関係諸国としても何らかの方策が取れるのではないか。それをあらゆるレベルで、模索・実行すべきだろう。 6 終わりに 一党独裁国家などと違って、民主国家は国民の意識を必要以上に気にかける傾向がある。あまりにも迎合的に過ぎると結果として国策を誤る可能性もある。米国には、冷静に情勢を分析して必要な責務を果たしていただきたいものである。 一方、我が国としては、危機管理の要諦が最悪に備えることであることに思いを致し、米国が世界の警察官としての役割を少なくとも減じつつあることを冷静に受け止め、なすべき対策を打ってほしい。
http://jbpress.ismedia.jp/articles/print/41899 |
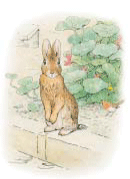
 スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。 スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。