http://www.asyura2.com/14/senkyo173/msg/480.html
| Tweet |
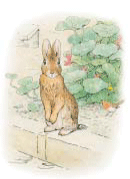
空手形どころではない菅官房長官の普天間運用停止口約束の不誠実
http://www.amakiblog.com/archives/2014/10/26/#002968
2014年10月26日 天木直人のブログ
きょう10月26日に投開票される福島県知事選は脱原発派にとって失望的な結果に終わることになる。
これは立候補者の顔ぶれが決まった時点において自明であった。
ならば10月30日に公示される沖縄県知事選だけは辺野古移転反対派に勝ってもらいたい。
その為には安倍・菅政権の不誠実さを白日の下に晒さなければいけない。
その不誠実さの極みが、菅官房長官が9月に沖縄を訪れ、普天間基地の運用停止を5年以内に行うと仲井真候補(現知事)口約束したあの発言だ。
こんな選挙対策の空手形を許してはならない。
この菅官房長官の不誠実さこそ、沖縄知事選の一大争点にすべきだ。
そう私は当時書いたものだ。
そして、菅官房長官の不誠実さは、10月17日の朝日新聞のスクープ記事でさらに裏付けられた。
すなわち米国防総省当局者が朝日新聞の取材に対し、そんな要請は日本政府から受けていない、合意から5年後(2019年2月)の運用停止など米政府は同意していない、と明言したというのだ。
朝日は更に10月22日の社説で書いていた。
米政府との調整がつく見通しもないままの(沖縄に対する)約束なら、とんだ空手形だと。
菅官房長官はその後も記者会見で「米国に様々なレベルで繰り返し伝えている」と説明しているが、米政府内で一顧だにされていないではないかと。
ここまで私の考えと同じ事を書いた朝日の記事は珍しい。
安倍政権下で絶大な権力をふるう菅官房長官を朝日がここまで批判するのは珍しい。
それほど沖縄に対する菅官房長官の不誠実が目に余るということだ。
そう思っていたら、きょう10月26日の東京新聞が書いた。
運用停止どころか、米軍が基地の運用を停止した後も、米軍は普天間基地を使い続けるというのだ。
そもそも辺野古基地が使用できるようになるのは着工から9年後になるという。
住民の反対で着工がいつになるかわからないのに、たとえ今すぐ着工しても、使用開始は2023年だ。
5年後の運用停止などあり得ない。
そこまでは私も指摘した。
ところが、オスプレイの訓練移転を沖縄の外に持っていく事で運用停止と見なす可能性があるというのだ。
辺野古に移転した後も、緊急着陸の理由で普天間基地の使用が続くというのだ。
これ以上の不誠実はない。
辺野古建設を強行しようとする安倍。菅政権の口癖は、普天間の危険を放置することは許されないということだ。
しかし、それさえも真っ赤なウソだということだ。
辺野古移転後も普天間の危険性はほとんど変わらないということだ。
ここまで安倍・菅政権に馬鹿にされている沖縄県民は、何としてでも今度の選挙で安倍・菅政権と、それに支持されている仲井真候補を拒否しなければウソだ。
近年まれに見る政治決戦がもうすぐやってくる。
最大の関心を持って私はその行方を見届けたい(了)
▲上へ ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK173掲示板 次へ 前へ
 スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。