http://www.asyura2.com/14/senkyo169/msg/204.html
| Tweet |
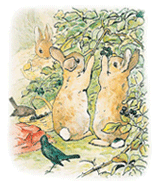
「機関車先生」に見る本当の強さと本当の優しさ
http://kikko.cocolog-nifty.com/kikko/2014/07/post-54a3.html
2014.07.28 きっこのブログ
マレーシア航空機の撃墜事件で最も多くの犠牲者を出したオランダで、「オランダ軍をウクライナに派遣して、ウクライナ軍との共同作戦で親ロシア派を殲滅しろ!」という世論が高まっているという。もちろんこれは、あくまでも一部の過激な層の声であって、日本のネットウヨクがネット上で韓国や中国を攻撃してるようなレベルだと思う。だから、真面目に取り合うこともないんけど、あたしは、とっても悲しい気持ちになった。
他にも、イスラエルによるガザのパレスチナ人の虐殺、ISISによるイラクでの虐殺、ボコ・ハラムによるナイジェリアでの虐殺、アサド政権によるシリアでの自国民の虐殺、ケニア、エジプト、チュニジア‥‥って、挙げて行ったらキリがないほど、世界のあちこちで、何の罪もない人たちが殺され続けてる。あえて言わせてもらえば、大人の男たちが始めた戦争で、何の罪もない子どもたちや女性たちが殺され続けてる。
だから、あたしは「何か書かなきゃ!」って思ってるんだけど、ロシアの問題にしても、イスラエルとパレスチナの問題にしても、他の国々の問題にしても、多くの専門家が書き尽くしてきたことを、シロートのあたしが繰り返しても意味はない。そして、これらの問題に絡めて、戦争へと突き進む安倍政権を批判することを書いても、それはそれで、あまり意味はない。やっぱり、あたしは、あたしらしい書き方で、自分の伝えたいことを表現して行こうと思った今日この頃、皆さん、いかがお過ごしですか?
‥‥そんなワケで、前回のブログの「きっこさんのつぶやき」の中に、こんなツイートがあったことを覚えてる人もいると思う。
瀬戸内海の島を舞台にした小説と言うと、壺井栄の「二十四の瞳」、横溝正史の「獄門島」、角田光代の「八日目の蝉」などから、最近ブームの村上水軍モノに至るまで何十作もあるけど、あたしが一番好きなのは伊集院静の「機関車先生」だ。アニメもドラマもイマイチだったけど原作は本当に素晴らしい。
2014.07.23 11:55
で、今日は、この『機関車先生』(講談社文庫)を紹介しようと思うんだけど、あたしが伊集院静さんの作品を読むようになったのは、阿佐田哲也さん(色川武大さん)の麻雀小説『牌の魔術師』の後書きを読んだことがキッカケだ。伊集院静さんが、まだ作家になる前、阿佐田哲也さんと一緒に全国の競輪場を旅打ちしたり、麻雀を打ったりしてた時代のことが短く書かれてるんだけど、この後書きの素晴らしさにシビレちゃったあたしは、伊集院静さんの作品をいろいろと読むようになった。そして、この『機関車先生』にも出会った。
‥‥そんなワケで、敗戦から十数年後の昭和30年代、山口県の瀬戸内海の小島、葉名島(はなじま)が舞台のこの小説は、島に1つだけの小学校に、1人の体の大きな男の先生が赴任してくるところから始まる。全校生徒が5人だけの小学校は、それまで佐古周一郎という校長先生が1人で教えていたんだけど、春から新入生が2人入学して7人になる。そこで、先生の数を増やすことにしたワケだ。
赴任してきた先生の名前は吉岡誠吾、子どものころの病気が原因で、言葉を話すことができない。口を「きかん」先生、D51のように体の大きな先生、それで、子どもたちから「機関車先生」というアダ名をつけられる。そして、校長先生との二人三脚の授業で、子どもたちと仲良くなって行く‥‥って、この調子で書いてくとキリがないし完全なネタバレになっちゃうので、アレもコレもソレもドレもみんな割愛して、あたしの伝えたい場所へ、クルリンパとワープしちゃう。
海に面した崖の中腹に、人工的な横長の窪地があった。そこを指差して、校長先生が機関車先生に話し出す。あそこは戦時中に海軍が弾薬庫を造ろうとした跡だと。そして、そのすぐ下にある尖った四角い岩が「八子部(ヤコブ)の裏切り岩」と呼ばれていたことを。
この島の女が、本土の遊郭で働いていた時、1人のドイツ人に見染められて、子どもを産んだ。でも、そのドイツ人は国に帰ってしまったので、その女は子どもを連れて、この島に帰ってきた。その子の名前が、ヤコブ。ヤコブは髪が赤かったので、他の子どもたちから虐められた。石を投げられた。でも、とてもやさしい心を持った子どもで、よくお母さんの手伝いをしていた。
敗戦が色濃くなってきた昭和20年、岩国の海軍基地から、突然、兵隊たちがやってきて、あの場所に弾薬庫を造り始めた。島の男たちも工事に駆り出された。でも、上空には頻繁に米軍の偵察機が飛びまわっていて、弾薬庫の建設は敵に筒抜けだった。あんなところに弾薬庫を作ったら、この島も必ず爆撃されてしまう。島の人たちは不安になった。中には島から出て行く者もあらわれた。
そんなある日の夜、弾薬庫を建設している場所のすぐ下の岩の上で、大きな火が燃えているを兵隊の1人が発見した。誰かが焚火をしているらしい。兵隊は焦った。これでは米軍の偵察機に「ここに弾薬庫がありますよ」と教えているようなものだからだ。でも、その岩までは、波が荒くて近づくことができない。
朝になって見てみると、岩の上には誰もいなかった。でも、夜になると、また誰かが焚火を始めた。そして、3日目の夜、また焚火が始まったので、兵隊たちは焚火に向かって機関銃を撃ちまくった。朝になると、岩の上で血まみれになったヤコブが死んでいた。ヤコブのお母さんは岩国基地に連行され、島の人たちも取り調べを受け、結局、ヤコブが敵のスパイだったということで事件は終わった。そして、その岩は「八子部の裏切り岩」と呼ばれることになった。
スパイのヤコブによって、この場所は米軍にバレてしまったという見方がなされたため、海軍は、この場所に弾薬庫を造ることを諦めた。結局、ヤコブのお陰で、葉名島は米軍の爆撃を受けずに済んだのだ。
実は、校長先生は知っていた。夜遅くに、小舟を漕いで岩へと向かうヤコブの姿を目撃していたのだ。それで、何のために焚火などするのか?軍に知れたら殺されてしまうぞ!とヤコブに言ったのだ。でも、ヤコブは、「これは自分のすべきことだ」と言って焚火を続け、そして、殺されてしまった。ヤコブは、この島に弾薬庫など造らせない!この島が爆撃を受けるようなことだけは止めたい!その一心で、自分の命と引き換えに島の人たちを戦災から守ったのだ。
‥‥そんなワケで、これが「八子部の裏切り岩」の概要なんだけど、それから十数年後、校長先生は、機関車先生と一緒に、子どもたちと海を見ている。そして校長先生は、子どもたちにも、この「八子部の裏切り岩」の話をした‥‥ってワケで、ここからは、本文を引用させてもらう。
<引用ここから>
「どうして戦争をしたんじゃ」
修平が言った。
「どうしてだと思う?修平」
(校長の)周一郎が修平に聞いた。
修平が首を横にふった。
「人間は昔から戦争を何回もしてきたんじゃ。その度に大勢の人が死んだ。葉名島からも何人もの人が戦争に連れて行かれて帰って来なんだ。そんな馬鹿なことを二度とくり返さないぞ、と思うのに、またどこかで戦争がはじまる。人間はそれをくり返して来た」
「どうして悪いこととわかって、同じことをくり返してきたんですか」
妙子が聞いた。
「それはな、皆がヤコブのように人と人が争うことが醜いこととわかっとらんからだ。ヤコブはこの島で髪の毛が赤かっただけで石を投げられた。修平、もし君がそんなことで石を投げられたら、どうする?」
周一郎が修平に聞いた。
「わしは、そいつに石を投げ返したる」
修平が怒ったように言った。
「そいつがまた石を投げ返したらどうする?」
「また投げ返してやる」
「そうか、投げ返すか‥‥。なぜ投げ返すか?」
「そりゃそいつが憎ったらしいからじゃ」
「憎いか」
「憎いに決まっとる」
修平が本気で怒り出した。
「それが戦争のはじまりじゃ」
「戦争の?」
「そうじゃ、人が人を憎いとか、悪い奴じゃと決めたところから戦争がはじまるんじゃ。戦争はな、国と国が争うように見えるが、本当は人間のこころの中からはじまっとるんじゃ」
「ようわからんの」
「君たちが大人になって、日本という国がまた立派になった時、誰かがあそこの国が悪いとか、憎ったらしいとか言い出した時に、本当にそうなのかをよく考えられる人間になっとらねばいかん。自分が正しいと思ったら、それを実行できる人間になることじゃ。ヤコブがなぜ何も言わずに死んだのかを考えてほしい」
「なぜなの?」
洋子が聞いた。
「それはな、あの時代に、ヤコブが戦争はいけない、と言い出したら、きっとひどい目に遭わされたからじゃ。島の人間もこころの奥では戦争はいけないこととわかっとった者もおる。けどそれを口にしたら、皆からいじめられ、石を投げられたんじゃ。いいか、君たちが大人になった時、正しいと思ったらそのことをはっきり口に出して言える人に、私はなってほしい。相手に石を投げられたり、蹴られても、それをすぐやり返さずに我慢ができる人になってほしいんじゃ。本当に強い人間は決して自分で手を上げないものじゃ」
子供たちが一斉に誠吾の方を見た。
誠吾は黙って、うつむいていた。
<引用ここまで>
※伊集院静著『機関車先生』(講談社文庫)P.178〜P.180より
‥‥そんなワケで、この少し前に、この地域の小学校の子どもたちの描いた絵の展覧会が本土で行なわれたので、校長先生と機関車先生は、子どもたちを連れて連絡船で本土での展覧会を観に行っていた。その時、チンピラたちにからまれている女学生を助けた機関車先生は、チンピラたちに殴られても蹴られても手を出さずに、ずっと我慢をしていた。
剣道の達人で、体も大きくて、子どもたちにとってはスーパーマンのような存在だった機関車先生だから、チンピラの2人や3人、あっと言う間にやつけてくれると思っていた子どもたちは、殴られても蹴られても、顔にツバまでかけられても手を出さずにジッとしている機関車先生の情けない姿に失望してしまった。そして、「機関車先生は弱虫じゃ」と言って、島に帰って来てからも、あれほど大好きだった機関車先生と、距離を置くようになってしまった。
だけど、今の校長先生の話を聞いて、子どもたちは分かったのだ。機関車先生が、なぜチンピラたちを殴り返さなかったのか。なぜ我慢し続けたのか。それは、機関車先生が本当に強い人間だからこそ、本当に優しい人間だからこそ、憎しみの連鎖の発端となる「反撃」を我慢することができたのだと。言葉を話すことができない機関車先生は、自らの体を使って、子どもたちに「人と人が争うことの醜さ」を、「戦争の愚かさ」を教えてくれたのだ。
‥‥そんなワケで、この子どもたちと同じくらいの年齢の「戦争を知らない世代」が大人になり、政治家になり、今、この国を動かしてるワケだけど、残念なことに、今、この国の舵を握っている船長は、「あそこの国が悪い」とか「あそこの国が憎ったらしい」という気持ちだけで船を進めてるようにしか見えない。だから、せめてあたしたち乗組員だけでも、半世紀前の校長先生の言葉をしっかりと胸に刻んでおき、この船が間違った方向へ進まないようにしたいと思う今日この頃なのだ。
「君たちが大人になって、日本という国がまた立派になった時、誰かがあそこの国が悪いとか、憎ったらしいとか言い出した時に、本当にそうなのかをよく考えられる人間になっとらねばいかん。自分が正しいと思ったら、それを実行できる人間になることじゃ。ヤコブがなぜ何も言わずに死んだのかを考えてほしい」
▲上へ ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK169掲示板 次へ 前へ
 スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。