http://www.asyura2.com/14/kokusai9/msg/667.html
| Tweet |
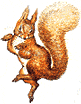
1本の映画がこれほどまでに制作会社(と国家)に影響を与えたことはない(私にとっても、ほとんどの人が目にすることがないであろう映画を論評するのは初めてだ)。もちろん「ザ・インタビュー」は単なる映画ではない。がさつな美学に基づくバディ・コメディで、衝撃的な現実の出来事を挑発する形になった。現時点では映画の質は問題とされていないようだ。しかしその見るに堪えない質は、この作品とそれに付随する危機を生み出した発想を象徴している。
最初のシーンはかなり笑える。北朝鮮の子供が、かわいい顔に明るい笑みを浮かべて「米国は死ね」という残忍な歌を歌っている。しかし、ここから悪化の一途をたどる。それは、セス・ローゲンとジェームズ・フランコが演じる相棒同士(バディ)が金正恩第1書記を暗殺するために米中央情報局(CIA)によって北朝鮮に送り込まれたという理由だけではない(彼らは第1書記がファンであるワイドショー「スカイラーク・トゥナイト」の真面目なプロデューサー、アーロン・ラパポートと司会者デーブ・スカイラークを演じている)。眠れない夜に見る「サタデー・ナイト・ライブ」を考えてみるがいい。さらに潔癖症の強迫観念のばかばかしさ(具体的には北朝鮮指導者の体質)、ドラッグジョーク(エクスタシー、それに暗殺計画には不可欠のリシンなどを含む)、芸能界のギャグ(エミネムはこのテレビショーでゲイであることを告白し、ロブ・ロウは頭がはげていると言われる)、それにデーブのCIAコールサイン「ダンビートル(ふんころがし)」にふさわしい口汚い対話もある。
ランドール・パークは、自分に自信がなく、ばか丁寧な第1書記を演じることで、若き独裁者をとても笑える存在にしている。第1書記はデーブにかわいらしい犬をプレゼントしたあと、彼に「私は私。私はベストを尽くす」と言う。だがジェームズ・フランコは、彼が笑える存在だと観客が理解できるように恥ずかしげもなく大げさな表情をする。しかし、彼はおかしくない。脚本全体が、風刺的な(少なくとも茶番劇風な)ストーリーを不愉快なおふざけにしてしまうのだ。現実の世界では、何が拷問で何が拷問でないかについて議論されているが、映画の世界に議論はない。「ザ・インタビュー」を見ることは、ほとんど最初から最後まで拷問だ。
このような駄作がどうして公開されようとしていたのだろうか。その答の大きな部分は、数十年前に始まった観客のレベル低下にある。マーケティング部門が丁寧な仕事さえすれば、週末に子供たちがほとんどどんなジャンク映画でも見に行くことに制作会社が気付いたのだ。ポップカルチャーを粗悪なものにしたのは映画だけではないが、映画は熱心な観客を伴ってその道を先導した。観客のレベルを低下させることは何年間もうまくいき――それは少数の人気スターのおかげなのだが――その結果、映画自身のレベルも落ち、現実と無謀な空想との違いが容易に識別できないほど矮小(わいしょう)化されてしまった。「ザ・インタビュー」はハリウッドで作られるべくして作られたのだ。
http://jp.wsj.com/articles/SB11501383225136704765104580346273467810774?mod=trending_now_2
 スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。