03. 2015年1月14日 00:43:40
: nJF6kGWndY
負担増で手取りが減り、インフレで実質が減れば当然だなhttp://diamond.jp/articles/-/64818
老後のお金クライシス! 深田晶恵
【第8回】 2015年1月14日 深田晶恵
年収800万円でも実際使えるお金は600万円!
あなたは自分の「手取り年収」を知っている?
「手取り収入」は13年間で約9%も減っている! まずは、下のグラフを見ていただきたい。
※40歳以上で専業主婦の妻と15歳以下の子どもが2人いる会社員の例。健康保険は協会けんぽ加入として試算
これは、「額面年収800万円、専業主婦の妻と15歳以下の子ども2人」の会社員について、2002年からの手取り年収の推移を表したものだ。手取り年収とは、勤務先が支払う額面の給料から所得税・住民税と社会保険料を差し引いた金額のことである。
手取り年収は一部の年を除き下がり続けているので、グラフは見事に「右肩下がり」となっている。例に挙げた年収800万円のケースだと、2002年に662万円あった手取り額が、今年は603万円になる。13年間で約9%、金額では59万円も「使えるお金」が減っているのだ。 読者のみなさんは「なぜ2002年からの13年間の推移なのだろう」と疑問に思うかもしれない。きっかけは、2003年にボーナスからも毎月の給料と同じ料率で社会保険料が引かれるようになったこと。40代以上の人なら、ボーナスの手取り額がグンと減ることになったのを覚えている人も多いだろう。筆者はこの改正が実施されたとき「手取り収入はこれからも下がり続けるかも」と思い、それから毎年、年収・属性ごとに手取り額を計算し、推移を見ることを続けている。 手取り収入を減らす改正は
毎年のように実施されてきた 「手取りを減らす要因」は、所得税・住民税の増税と、社会保険料のアップだ。これまでのおもな制度改正を振り返ってみよう。 【2003年】
・社会保険料の総報酬制の導入
・厚生年金・健康保険・介護保険についてボーナスの保険料負担アップ
→これにより、ボーナスの割合の多い人ほど手取りが大きく減った 【2004年】
・所得税の配偶者特別控除の一部廃止
→専業主婦または年収103万円以下の妻がいる世帯の夫の手取り額が減少
・厚生年金保険料率のアップ
→0.177%(本人負担分)ずつ毎年引き上げられる(2017年まで) 【2005年】
・住民税の配偶者特別控除の一部廃止
→所得税に1年遅れて実施 【2006年・2007年】
・定率減税の縮小(2006年)&廃止(2007年)
→所得税税額20%減税の措置が2年かけて廃止(住民税は最大4万円の減税が廃止)。この増税の影響は大きかった 【2010年】
・健康保険料のアップ
→協会けんぽの例では、全国平均の料率は8.2%から9.34%(本人負担はこの半分)にアップ 【2011年・2012年】
・「子ども手当」の財源捻出のために15歳以下の年少扶養控除が廃止&16〜18歳の特定扶養控除の縮小。2011年は所得税、2012年は住民税が増税。
→高校生以下の子どもがいる世帯の所得税と住民税が増税に。この増税の影響も大きい 【2013年】
・復興特別所得税(復興増税)」がスタート。この年から25年間にわたり、所得税額が2.1%上乗せされる 【2014年】
・復興増税として、住民税の均等割が10年間にわたり1000円アップ この他に昨年は消費税増税が実施されたので、増税分「使えるお金」は減っている。消費税がかかる支出が年間400万円ある世帯なら、3%の増税の影響は年12万円。年収700万〜800万円の手取り年収はおよそ530万〜620万円なので、住宅ローンや家賃、保険料など消費税のかからない支出や貯蓄額を差し引くと、消費税がかかる支出額は400万円前後と見積もることができる。ちなみに貯蓄に回すお金が少ない家庭ほど消費に回る金額が多いので、増税の影響は大きい。 年収800万円でも
「使えるお金」は600万円程度 ここまで読むと、今年の手取り年収の「自分の場合」が知りたくなるだろう。いくつかのケースを試算してみた。
配偶者の収入や、子どもの年齢により所得税・住民税の額が決まるため、額面年収が同じであったとしても手取り年収は家族の属性により異なる。たとえば額面年収800万円の場合、税務上の扶養家族が妻と高校生と大学生の子どもが2人なら、表のB欄にある通り手取り年収は627万円だが、扶養控除額がゼロになるC欄の属性だと手取りは591万円。同じ年収なのに、なんと年36万円も手取りが少なくなるのである。
以前は、子どもの扶養控除の額は、0〜15歳が38万円、16〜22歳は63万円だった(いずれも所得税の控除額)。高校生と大学生等の間は教育費負担等を考慮して控除額が拡大されていたのだ。 2011年以降は、0〜15歳が控除額ゼロで、16〜18歳が38万円、19〜22歳は63万円に改正。高校卒業までの子がいる世帯は控除額がゼロまたは減額されたことにより増税になっている。 2010年に民主党政権が導入した「子ども手当」の財源の確保のために控除額の減額を実施した。子ども手当は導入された当初「所得制限なし、0歳〜中学生まで一律月額1万円3000円」であったが、「バラマキだ」と批判を受け、その後は所得制限を設けた「児童手当」に様変わりし、金額も変更になっている。 中学生以下の子の扶養控除廃止による増税分は児童手当の支給でカバーできているのか試算してみると、年収500万円で廃止前に比べ年1万円の手取り減少、年収700万円だと年5万円の手取り減少という結果になった(小学生、中学生の子どもが2人のケース)。 高校生(16〜18歳)の扶養控除が減額になったのは、同じく民主党政権時に「公立高校の授業料無償化(私立高校は年収350万円以上の世帯で月額9900円支給)」の制度導入によるもの。それも2014年4月入学以降は、所得制限が設けられ「高等学校等就学支援金」制度に変更になっている。年収ベースでおおむね910万円以上の世帯は支援金を受けることができなくなった。 扶養控除の廃止・縮小は、「子ども手当」や「公立高校の授業料無償化」の導入のバーター取引だったわけだから、受けられる恩恵が少なくなったのなら扶養控除の見直しがされるべきだが、今回の税制改正大綱の検討項目にも入っていない。 年収がアップした分
「使えるお金」が増えるわけではない 昨年は転職に成功した人も多かったようで、飲み会の席などで「深田さん、転職したら年収が100万円アップしたんですよ。その分、使えるお金が増えるってことですよね!何買おうかな」とうれしそうに言う人が何人かいた。 酔っているからうっかり言えること。しらふなら「年収が上がったからといって支出を増やしてどうするの!」と私に一喝されることは十分想像できるため、うっかり発言はしないはずだ(笑)。 年収がアップしても、その金額分の手取りが増えるわけでないことを忘れてはいけない。先の図(2)を見てみると、年収800万円で属性がA欄の人の手取りは602万円。転職や昇進により年収が900万円になったとすると、手取りは664万円に増える。しかし、年収が100万円アップしたとしても、手取り増は62万円にとどまる。 手取り額が収入アップに比例しないのは所得が増えると所得税の税率が高くなるからだ。年収900万円前後から、児童手当や高等学校等就学支援金の所得制限にも引っかかるようになるので、年収アップしたからといって喜んでばかりもいられない。 2分でできる
「手取り計算シート」を活用しよう このように額面年収と手取り年収は、年収が高くなるほど乖離が大きくなる。となると、額面年収で予算を立てたとしても絵に描いた餅になってしまう。お金が貯まる家計運営を実現させるためには、年に1度の「手取り年収」の計算は欠かせない作業だ。手取り収入は、どこかに書いてあるわけでなく、自分で計算しないと算出できない。 こう書くと「計算、面倒かも」と思うかもしれないが、記入式のシートを用意したので、ぜひ活用して欲しい。用意するのは、昨年分の源泉徴収票と昨年のどこかの月の給与明細だけで、下記シートを使うと2分もあれば計算できる。
記入したシートを眺めてみると、税金の額もさることながら、社会保険料の負担は思ったより大きいことがわかるはずだ。手取り額が把握できたら、今年1年間で貯める金額を決めて、積立を実行しよう。
―― 今週のミッション!――
◆2014年の手取り収入を計算しよう!
◆2015年に貯める金額を決め、積立の手続きをしよう! |
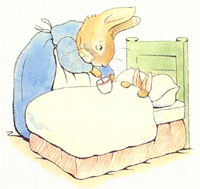
 スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。