01. 2014年12月12日 06:42:46
: jXbiWWJBCA
【第534回】 2014年12月12日 寺島英弥 [河北新報社編集委員]
「減収1000万円」米価暴落が被災地農家を襲う アベノミクス選挙が忘れた被災地の現実
――河北新報社編集委員 寺島英弥
津波に耐えて残った、北上川のヨシ原
Photo by Hideya Terashima
安倍政権の経済政策「アベノミクス」をめぐる論戦に明け暮れる衆院選から、被災地は忘れられたかのようだ。震災から復旧しつつある農地を懸命に背負う住民を、本年産米の米価暴落が襲った。多くが営農を断念した地域を支える宮城県石巻市の農家は、減収が約1000万円に上る。「支援が消えれば、地域で踏ん張ろうとする担い手もいなくなる」と訴える。
作付け復活後急速に増えた
営農断念農家からの耕作委託
石巻市の北上川(追波川ともいう)下流域は、追波(おっぱ)湾に至る川面にかつて十数キロにわたってヨシが茂って「日本一のヨシ原」といわれ、風にそよぐ葉音が環境省の「残したい日本の音風景100選」に選ばれた。2011年3月11日の東日本大震災の津波は北上川沿岸をも襲い、同市釜谷地区では大川小学校の悲劇を生んだ。両岸ではいまなお延々と築堤と道路造りが続き、ヨシ原も「干潮時も水が引かない所が増えた。震災前の3分の2が生えなくなった」と地元の人は話す。ボランティアらの支援で少しずつ復元作業中だ。
北岸にある同市北上町の橋浦地区は広々とした水田地帯で、やはり津波にのみこまれた後、大規模な復田工事が続いてきた。農林水産省がまとめた岩手、宮城、福島の被災3県の農地復旧状況は、14年度初めの時点で、計画される1万7590ヘクタールのうち、66%が終了した。被災農地が最も多かった宮城県は、復旧対象の72%に当たる1万90ヘクタールが復旧したが、被害が深刻だった北上川下流域はまだ数年を要するという。
大内産業」の看板を掲げ、震災前には20ヘクタールまで広げた。 大内弘さん(52)は橋浦地区の農家で、現在45ヘクタールの水田を耕作している。17年前、住宅設備会社を辞めて就農し、父親の70アールの水田を引き継いだ。当時、橋浦地区では1ヘクタール規模の圃場(ほじょう)整備事業が始まり、「減農薬の大型農業をやろう」と決意した。高齢化と後継者不足に悩む地元農家から頼られる存在となり、耕作委託を意欲的に増やした。「米工房
面積が一挙に倍増したのは、震災後、作付けが復活した12年春。高台の集落にある大内さんの家と農業機材、施設は津波の被災を免れたが、営農再開を断念する農家が地元で相次いだ。
「水田が復旧しても、農業をやめる人が大勢いた。家も機械も流され、犠牲になった人もいる。1台千数百万円のコンバインを買い直せる農家だっていない」「復旧田を休耕にすれば、被災農家の収入はなくなり、農地は荒れる。今は請け負うことが地域を支えることになる」。受託先も震災前の30戸から70戸に増え、作業量は限界を超えた。名取市の宮城県農業実践大学校で学んだ長男竜太さん(26)が家に戻り、親戚に手伝いを頼み、新たな農機具を市の支援の無償リースで借り、2チームをつくって2年を乗り切った。
アベノミクスの恩恵とは
どこの世界の話なのか
「減収は1000万円。赤字だ」。12月初め、袋詰めした新米の山を前に、大内さんは厳しい表情で言った。全農(全国農業協同組合連合会)が9月、農家に前払いする本年産米の概算金(米価)を発表。大内さんの主力銘柄ひとめぼれが8400円(60キロ)で、前年比25%減の大幅下落となり、ササニシキも25.2%減と同様だ。東北の銘柄米はおしなべて過去最低まで暴落した。
「北上川のヨシ腐葉土米」の新米を手に、思い悩む大内さん
Photo by Hideya Terashima
被災地で作られている岩手産あきたこまちは29.5%減、福島産コシヒカリに至っては浜通り産が37.8%減、中通り産が35.1%減だった。コメの民間在庫数量が222万トン(6月末)というコメ余りが背景にあり、「コメの需要減と過剰在庫、東日本の豊作予想が重なり、一気に価格破壊を招いた形だ」(9月21日の河北新報記事より)。
「5月の田植えのころから、米価の値下がりを予想はしていたが、これほどとは」と大内さんは話す。「小作料のほかに震災前の圃場整備の負担金、機械の消耗分、手伝いの人の手当、上がる一方の燃料代もあり、10アール当たり9俵(540キロ)取れても、純利益が1万円残るかどうか」と覚悟の上で、地域を支える使命感でやってきたという。
2年前に初めて取材した折、大内さんが語った言葉を思い出した。「津波の後、当時請け負った田んぼは潮とヘドロをかぶり、土地改良区から別の地区の田を借りて1年をしのいだ。新米は旧北上町の仮設住宅全戸に配った。お互いさまで生きて、生かされてきたのだから」。
北上町内ではこれまで、被災農地294ヘクタールのうち204ヘクタールが営農可能となり、今後、さらに30ヘクタールの復田が予定されている。うち10ヘクタールを大内さんが引き受け、受託先は80戸以上に増えることになっている。残りを地元の2つの農業法人が受託する予定だといい、地元の担い手は既に一握りになった。
「TPP(環太平洋連携協定)への参加に向けて小さな農家を一掃するのが、米価暴落の背景にある政府の狙いでは、と勘ぐりたくなる」。北上川対岸でも長面、針岡両地区を合わせて計画面積約400ヘクタールの水田復旧が進む。「いくら復興予算で農地が戻ってきても、被災地への国の配慮や支援が消え、地域で踏ん張る担い手、支え手が経済原理に投げ込まれれば、残る者は誰もいなくなる。地域は崩壊する。アベノミクスの恩恵とは、どこの世界の話なのか」
経済原理という名の大波が
被災地を再び飲み込む
ヨシ腐葉土米」の文字がプリントされている。北上町には、いまもヨシ刈りを生業とする住民がおり、毎年、冬枯れのヨシを刈っている。震災前、見渡す限りにあった河川敷の湿地は「日本最後」のヨシ刈り場だった。 大内さんが手にした新米の袋には、「北上川の恵(めぐみ)
満潮のたびに追波湾の海水が川に入り交じり、栄養分豊かな汽水を生み、シジミも白魚もウナギも捕れ、まさに北上川の恵みが土地の1年の暮らしを潤していた。汽水の塩分はヨシの繊維を引き締めて良質の屋根材とし、かやぶき民家が姿を消した後も、全国の神社仏閣などから注文が来た。日本中の川と湖沼が護岸工事や開発によって破壊されてきた中で、奇跡的に残った自然と暮らしの風景そのものが未来の日本への遺産だった。
ヨシ刈り場から、大内さんは売り物にならないヨシの切れ端を毎年何十トンと引き取り、寒風の吹く冬田の一角で堆肥にし、次の春のコメ作りの準備として田にすき込んできた。北上川の自然と人の生態系の中に地元の農家も生き、生業を守ってきた。アベノミクスの経済とは別の世界の「なりわいの経済」があった。ヨシ原復活に向けても、大内さんはその貴重さを訴えてきた。3年8ヵ月前の震災に続いて経済原理という名の大波が、懸命に立ち上がり、生き直そうと模索する東北の被災地を再び飲み込もうとしている。「被災地の現実に足を踏み入れ、復興への方策を語る声を、この選挙戦でまだ聴いていない」と言う。
てらしま・ひでや
海よ山よ、いつの日に還る」(同)など。ブログ「余震の中で新聞を作る」。 希望の種をまく人びと」(明石書店)、「東日本大震災3年目 『河北新報』編集委員の震災記録300日」(講談社)、「東日本大震災 河北新報社編集委員。1957年、福島県相馬市生まれ。早大法卒。著書に「悲から生をつむぐ
http://diamond.jp/articles/-/63638 「ニッポン農業生き残りのヒント」
もう一歩深く、農業の世界へ 「もう後ろ盾はいらない」 2014年12月12日(金) 吉田 忠則 もう一歩深く、農業の世界へ――。コメの生産と販売を手がける越後ファーム(新潟県阿賀町)の社長の近正宏光が、兼務していた東京・新宿の不動産会社の社長をやめた。「ぼくも、社員にも甘えがあった」。それをふっきるため、農業一本で立っていくことに決めたのだ。 東京の神田駅の近くの事務所を訪ねると、目に飛び込んできたのが赤ちゃん用のベッドだった。近正が女性社員に「あずける場所に困っているなら、連れてくればいい」と言って置いたものだ。9月末に産声をあげたばかりの“新生”越後ファームの雰囲気を映していた。
不動産会社から独立した越後ファームの近正宏光さん(左)、新しい事務所には赤ちゃん用のベッドが(右):(東京都千代田区の事務所)
楽しいことしか、がんばれない
これまで、この会社のことは連載で何度か取り上げてきた(4月11日「『1キロ5400円』超高級米のつくり方」)。簡単におさらいすると、都内の不動産会社に勤めていた近正は社長の指示で新潟に農業法人をつくり、稲作を始めた。2006年のことだ。 役場や農家の集まりでつれなく追い返されるなど、はじめは農地を借りるのに苦労したが、まじめにコメをつくっているうちに地域の農業の担い手になった。農薬と肥料をいっさい使わないなど、ブランド化に努め、百貨店で高級米として売ることに成功した。条件の悪い棚田でがんばっている各地の篤農家のコメも、あわせて売り始めた。 新規参入の農業者として着実に地歩をかためてきた近正には、もうひとつ別の顔があった。不動産会社のほうの社長にもなったのだ。引き続き実権をにぎるオーナーの前社長が、若く行動力のある近正に、本社ビルの建て替えをふくめ、会社の仕組みを新しくする仕事をまかせたのだった。 そうしたオーナーの思惑とは裏腹に、近正は農業をやることがどんどん楽しくなっていった。まだ売り先に困っていたころ、シンガポールの日系百貨店で店頭販売をやった。そのとき、現地のひとが試食して「おいしい」と言ってくれた。「素晴らしい仕事だ、農業は」。そう素直に喜ぶことができた。
コメづくりは新潟県の中山間地の田んぼで
「一生の仕事はどっちなんだろう」。5、6年前から、そんなことを考えるようになった。答えはもちろん、農業。二つの会社で社長をやることが、負担になってきた。「楽しいことしか、がんばれない」。仕事を農業にしぼりたいという思いをおさえきれなくなった。
近正は越後ファームのコメづくりを「純化」してきた。安全・安心をかかげる以上、農薬と肥料をどちらも使わない自然農法に挑戦する。コメを傷つけないように、機械ではなく、昔ながらの千歯扱きで脱穀する。鮮度を保つため、雪で保冷する貯蔵施設をつくり、モミのまま保管する。減反に参加せず、補助金をあてにしない。 妥協をゆるさず稲作に取り組んできた近正にとって、不動産会社の経営という「後ろ盾」があることへの違和感が強まったということもある。各地の農家から仕入れたコメはいったん不動産会社が仕入れる形にしたことで、越後ファームはキャッシュフローの負担は軽くなっていた。 越後ファームはできて10年たたない小さな会社なのに対し、不動産会社には100年の社歴がある。近正がその社長を兼務していることで、越後ファームの信用力が補完されていた面はまちがいなくある。その結果、生まれる甘えを排除し、農業できちんと利益を出せる経営をつくろうと考えたのだ。 一生懸命が報われないのはおかしい コメ業界の「闇」を知ったことも、近正の背中を押した。産地をごまかし、「魚沼産コシヒカリ」と言って売る。精米年月日を偽装する。「新米に古米をうまく混ぜるのは、米屋の腕だ」。業者からそう言われたこともある。近正は「そんなことをやってきたから、消費者にそっぽを向かれたんだ」と憤る。 越後ファームが仕入れ、販売している農家のコメも、ほかの売り先で混米の被害にあっていることを知った。もし、食べた人がおいしくないと感じたら、自分の名前を出して売っているこの農家の評判を落とすことになる。 「本当に一生懸命やっている人がむくわれないのはおかしい」。まじめに稲作をしている農家のコメが、正当に評価される仕組みをつくりたいという思いも、これ以上、不動産業との間で「二足のわらじ」をはき続けるのはやめようという決意につながった。 一方で、コメを出荷する農家にも言いたいことがある。ときに、農家から「これだけ経費がかかったんだから、この値段で売ってくれ」と言われることがある。「自動車メーカーなら、値段と利益を考えてから、経費はこの範囲内で収めようと努力する。そういう発想が欠けている農家がいる」。 同社はいま、農家からコメを買い取って百貨店などで販売している。農協がやっているコメの委託販売とは違い、リスクを負うのは越後ファームだ。しかも農協とは異なり、自分でもコメをつくっているから、一気通貫でコメのことが分かる。そんな同社にとって、「経費は保証してくれ」と言わんばかりの農家の要求は、身勝手にもみえる。 そういう農家には「こだわりは分かるけど、消費者には必ずしも分かってもらえていないよ」と伝える。なあなあでやっていたら、次の世代に経営をバトンタッチできるような稲作は実現できないと思うからだ。農家には、売り場や消費者のことを考えながらコメをつくってくれるように要求する。 時代の追い風はある。小売業界は、混米をはじめとした既存のコメ流通の怪しさを知っていたのだろう。百貨店の中元やお歳暮、カタログ販売などでコメ卸に代わり、越後ファームが選ばれることが増えてきた。近正はこのあたりの事情を冷静にみている。「百姓には、愚直といったイメージがある」。それが、みずからの強みだと自覚している。 社長業より農業 近正が不動産会社から独立したときの思いを整理すると、以上のようになる。企業の農業参入のタイプの一つだった越後ファームは、いまや若い社員からなるベンチャー企業に変身した。田んぼのある新潟と販売拠点の東京を合わせ、26人の社員がいるが、43歳の近正が最年長だ。 個人的な話になるが、記者というのは脇役の仕事だとつくづく思う。主役はあくまで取材対象であって、彼らの言うことに耳をかたむけ、その中から意味のあることを探す。だから、取材をするときの気分やモチベーションは、取材対象のそれに少なからず影響される。 そこで農業に話をもどすと、農家や農業経営者たちから活力をもらうことが多いのだ。この連載で何度もふれたことだが、日本の農業全体を見わたせば、未来は楽観できるものではない。だが、経営について生き生きと語る彼らと接していると、時間を忘れることが少なくない。これは、かつて役所や金融機関を取材していたときにはほとんど味わったことのない感覚だ。 越後ファームの新たな船出も、そんな気持ちで取材した。だから農業の将来は明るいと短絡するつもりはないが、会社社長という安定した立場を捨てる決意を近正にさせた、農業の魅力を伝えていく意義はあると思う。(文中敬称略) このコラムについて
ニッポン農業生き残りのヒント TPP(環太平洋経済連携協定)交渉への参加が決まり、日本の農業の将来をめぐる論議がにわかに騒がしくなってきた。高齢化と放棄地の増大でバケツの底が抜けるような崩壊の危機に直面する一方、次代を担う新しい経営者が登場し、企業も参入の機会をうかがっている。農業はこのまま衰退してしまうのか。それとも再生できるのか。リスクとチャンスをともに抱える現場を取材し、生き残りのヒントをさぐる。
http://business.nikkeibp.co.jp/article/report/20141209/274950/?ST=print
|
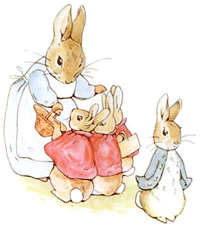
 スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。