http://www.asyura2.com/14/hasan91/msg/801.html
| Tweet |
(回答先: NY金(21日):3週ぶり高値、中国利下げに反応−銀も高い (Bloomberg) 投稿者 五月晴郎 日時 2014 年 11 月 25 日 06:34:52)
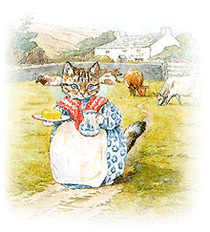
http://www.bloomberg.co.jp/news/123-NFKIQ36K50Y501.html
11月24日(ブルームバーグ):ヘッジファンドによる金相場上昇を見込む買い越しが6月以降で最大の増加を示した。中国や日本、欧州の中央銀行の動きなどにより相場下落が食い止められたことが背景。
米政府のデータによれば、ニューヨーク市場の金の先物とオプションの買越残高 は18日終了週に2万1634枚(56%)増加し6万307枚となった。売りポジションが2カ月ぶりの低水準に落ち込む一方、買いポジションは4週間ぶりに増加した。
中国が2012年7月以来の利下げに踏み切ったことを受け、金相場は今月21日、3週間ぶりの高値を付けた。
USAAプレシャス・メタルズ・アンド・ミネラルズ・ファンドの資産運用者、ダン・デンボー氏は21日の電話インタビューで「中国や欧州などの景気刺激に向けた動きが金需要を下支えする以上の影響を及ぼしている」と指摘。「金は上下に動く泡のようだ。ドルの動向に重点が置かれている日には泡は押し下げられるが、刺激策が発表されれば押し上げられる」と述べた。
原題:Bullish Gold Bets Gain as China Rate Cut Eases Rout: Commodities(抜粋)
記事に関する記者への問い合わせ先:ニューヨーク Joe Deaux jdeaux@bloomberg.net
記事についてのエディターへの問い合わせ先: Millie Munshi mmunshi@bloomberg.net Patrick McKiernan, John Deane
更新日時: 2014/11/25 09:56 JST
 スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。