02. 2014年11月20日 07:29:33
: jXbiWWJBCA
世界経済を苦しめる需要低迷の呪い
ユーロ圏と日本で特に顕著な「慢性的需要欠乏症候群」
2014年11月20日(Thu) Financial Times
(2014年11月19日付 英フィナンシャル・タイムズ紙) 英国のデビッド・キャメロン首相は「世界経済のダッシュボードにある赤い警告灯が再び点灯している」と述べている。今回の警告灯は2008年の時ほど赤くはない。 とはいえ、キャメロン政権が推奨している緊縮財政がもたらす困難は、日本とユーロ圏で特に明らかになっている。 驚くほどの鈍い高所得国の需要回復 景気が低迷しているこれらの高所得国は今や、世界経済の最も弱い環になっている。その理由を理解するには、今日の経済が抱える最も重要な病、すなわち慢性的需要欠乏症候群を分析しなければならない。 オバマ米大統領、次期財務長官にルー氏を指名へ
米国のジャック(ジェイコブ)・ルー財務長官〔AFPBB News〕 米国のジャック・ルー財務長官は、先週末にオーストラリアで開催された主要な高所得国20カ国・地域(G20)の首脳会議に向かう途中でシアトルに立ち寄って講演し、聴衆がはっとするような厳しい見方を披露した。 それによると今日の世界経済は、2009年にピッツバーグの首脳会議で約束された「強固で持続可能かつ均衡ある」成長にはほど遠い状況にある。 世界経済の回復は「一様でなく、たどる軌道が大幅に異なっている」とルー氏は指摘した。「米国では、内需が2012年第1四半期に金融危機前の水準を突破し、現在は危機前の水準を約6%上回っている。日本と英国の内需も約2%上回っている」と付け加えた。 「しかし、ユーロ圏の需要は危機の間の落ち込みをまだ回復しておらず、危機前の水準を4%以上下回ったままだ」 中央銀行は歴史上最も積極的な金融政策を取ったが・・・ ここでルー氏が付け加えなかったことが1つある。それは、この弱々しい景気動向――6%という米国の実質需要の増加でさえ6年以上の歳月がかかっており、過去の基準に照らせばお粗末だ――は、歴史上最も積極的な金融政策が取られていたにもかかわらず生じたということだ。 米連邦準備理事会(FRB)、欧州中央銀行(ECB)、および英イングランド銀行の市場介入金利は、2008年後半以降、0%を大きく上回ったことがない。ECBは2011年にこれを1%超の水準に引き上げようとしたものの、その後、0%近辺に引き戻されてしまった。日銀は0%に近い金利水準を20年間続けている。 しかし、これでも全く足りなかった。上述の中央銀行はいずれもバランスシートを急拡大させた。米国と英国では、その拡大ペースが安定した。ユーロ圏では2012年以降の縮小傾向が反転しつつあり、日銀のバランスシートは国内総生産(GDP)の80%相当額という経済的な成層圏へ向かって膨らみ続けている。 この需要の弱さ、特にユーロ圏と日本のそれは、一体どう説明すればよいのだろうか。これが分からなければ、正しい治療法を選び出すことなど、とてもおぼつかない。根本的な説明としては、次の3つが挙げられる。 極端な需要低迷に対する3つの説明 第1の説明は、危機後に生じた民間部門の過剰債務と、金融システムの突然の崩壊による信頼感への打撃を重視する。今や標準的になった対策は、バランスシートの整理と、ストレステストを踏まえた上での銀行システムへの資本の強制注入である。いずれも、金融システムは信用力を取り戻したと人々に納得してもらうためだ。 この施策には、財政・金融政策による需要のてこ入れを追加すべきだ。この見方に従えば、経済成長は速やかに再開されるはずだ。 第2の説明は、第1の説明の末尾にある提案を否定する。その論旨は以下の通りだ。まず、危機前の需要は持続不可能だった。なぜなら、これは官民の巨額の債務に依存したものであり、特に民間の債務は不動産価格のバブルに関係するものだったからだ。 夕暮れの東京タワーと富士山
日本は1990年のバブル崩壊以降、民間部門の債務が増加から減少に転じた現象に苦しめられた〔AFPBB News〕 日本は1990年のバブル崩壊以降、民間部門の債務が増加から減少に転じた現象に苦しめられた。米国、英国、スペインでも2008年以降に同じ状況が見られた。 これらの事例は、各国経済は危機後のバランスシート不況だけでなく、危機前の規模の需要を借り入れ主導で創出できない状況にも苦しめられることを示唆している。 危機前の需要を持続できないことの背景には、世界経済の不均衡があり、所得分布の変化があり、構造的に弱々しい投資がある。日本とユーロ圏で見られる民間部門の慢性的な資金余剰(所得が支出を上回っている状態)は、その1つの現れだ。 第3の説明は、人口動態の変化、生産性拡大ペースの鈍化、弱い投資の何らかの組み合わせによって潜在成長が鈍化したことを指し示している。 だが、この最後の説明は2番目の説明に直接からんでくる。潜在供給量の伸びが鈍ることが予想される場合、消費と投資は弱くなる。それが需要の弱い伸びを生み出す。中央銀行がこれと戦えば、バブルになる。一方、中銀がこれを受け入れれば、供給の弱い伸びは自己成就的な予言と化す。 根深い病、米国は軽症、日本とユーロ圏は重症、中国にも不安 高所得国はこれら3つの病すべてに苦しめられている。その程度には差があり、米国は病状が軽く、日本とユーロ圏は重い。中国でさえ、他国・地域よりはるかに高い成長率が予想されるとはいえ、やはり2つ目と3つ目の懸念に悩まされている。中国が金融危機に見舞われなかったにもかかわらず、だ。 中国の実質的な成長の減速を考えると、同国の近年の成長は、持続不能なほど急激な債務の積み上げと持続不能なほど高い投資率が原動力となってきた。 極端な政策にこれほど効果がなかった理由は、各国経済がこれほど根深い病に苦しめられているためだ。問題は供給の弱さだけではない。だが、需要の弱さだけでもない。さらに言えば、問題は過剰債務や金融のショックだけでもない。各経済が苦しめられている病は、その組み合わせも異なるのだ。 人口動態がよりダイナミックなうえ、民間の貯蓄率が低い革新的な経済国として、米国が正常な政策状況に逃げ込めるチャンスは、ユーロ圏や日本よりも大きい。同じように、キャッチアップの潜在性がある経済国として、中国の調整は管理できるものになるはずだ。 しかし、ユーロ圏と日本は、健全な成長を取り戻すうえで、他国よりはるかに大きな課題に直面する。なぜなら、双方の民間部門は、生み出したいと思っている貯蓄を使うことができないからだ。その結果、両者に残されるのは非伝統的な政策の選択肢であり、恐らくは、これまでに試した政策以上に非伝統的なものとなるだろう。 こうした政策をさらに推し進めることがもたらす結果は、ユーロ圏では特に政治的に破壊的なものになるかもしれない。そうした可能性がどんなものなのか、なぜ極めて大きな痛みを伴うのかは、来週のコラムのテーマとしたい。
By Martin Wolf
http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/42253
ドイツのパラレルワールドの奇怪な経済学
ケインズが何だ? ユーロ圏に全くそぐわない「オルド自由主義」
2014年11月20日(Thu) Financial Times
(2014年11月17日付 英フィナンシャル・タイムズ紙)
諸外国から見ると、ドイツのマクロ経済は別世界(写真:Thomas Wolf, www.foto-tw.de)
ドイツの経済学者とエコノミストは、大雑把に2つのグループに分けられる。ケインズを読んだことがない人たちと、ケインズを理解していない人たちだ。
ドイツの経済的主流派を保守派と表現することは、的外れだ。確かにドイツの主流派には、米国その他諸国の新古典主義、または新保守主義の学派と重なるところがある。 だが、ドイツの主流派と米国のティーパーティー運動との比較がどれほど説得力があるように見えたとしても、検証には耐え得ない。ドイツの正統派の経済学は、中道左派と中道右派にまたがっている。多少なりともケインズ主義の知識を持つ唯一の政党は旧共産党だけだ。 投資不足や過剰な経常黒字を全く批判しない経済諮問委員会 正統派の教義を示す好例が、政府に助言する公的機関「ドイツ経済諮問委員会」が先週発表した年次報告書である。委員会は、投資不足や過剰な経常黒字、過度に熱心な財政規律を批判しなかった。その代わり、最低賃金と、年金受給開始年齢の若干の緩和を批判した。 言い換えれば、委員会はアンゲラ・メルケル首相率いるドイツ政府が一段と厳しい姿勢を取ることを望んでいるのだ。 ドイツ人には、ドイツ独特の経済的枠組みを表す言葉がある。「オルド自由主義」がそれだ。 その起源は完全に理にかなっていた。1933年の自由民主主義の崩壊に対し、ドイツのリベラルなエリート層が出した答えだったのだ。 オルド自由主義は、制限のない自由主義体制は本質的に不安定であり、自らを支えるためには規則と政府の介入が必要だとの見解から生まれた。政府の仕事は、市場の欠陥を正すことではなく、規則を定め、執行することだというわけだ。 1945年以降、オルド自由主義は中道右派の支配的な経済原理となった。1990年代になると、ドイツ社会民主党(SPD)がオルド自由主義を取り入れ始め、最終的にゲアハルト・シュレーダー首相による2003年の労働・福祉改革に至った。 現在、政府はオルドリベラルだ。野党もオルドリベラルだ。大学はオルドリベラル派の経済学を教えている。その間、ドイツとそれ以外の国々のマクロ経済は、まるでパラレルワールドも同然になっている。 実際には、ドイツのマクロ経済の例外主義は大して問題にならなかった。ただし、それも、こうした例外主義が非常に重要になり始めた最近までは、の話だ。 通貨同盟に加わった途端に事情が一変したのに・・・ 「祝!定年生活」、通行人に1ユーロ配る ドイツ
自国通貨を持っていれば、奇怪なイデオロギーはその国の問題だった〔AFPBB News〕 自国の通貨を持ち、主に貿易を通じて世界各国とかかわっている時には、奇怪なイデオロギーはその国の問題だ。通貨同盟に加わると状況が変わり、その時点で政策立案者たちが互いに協力しなければならなくなる。 誰もこの問題に大きな関心を払ってこなかった。ユーロ圏に関する初期の論理的議論の大半は、最適通貨圏の概念に集中していた。つまり、通貨同盟に参加するのに適している国はどこか、という問題だ。 ところが実際、ふたを開けてみれば、それよりもはるかに重要だったのは、人々が互いに意思疎通を図り、一緒に行動できるようにする共通理解だった。 例えば、ドイツのオルドリベラル派は、中央銀行が市場金利に影響を与える力を失う流動性の罠の存在を決して認めない。1950年代にドイツ経済相として尊敬されたルートヴィヒ・エアハルトは、カルテルの観点から大恐慌を説明しようとしたことがある。それは自分たちが明確な説明を持たないことを、自分たちの思考の枠組みに取り込もうするオルドリベラル派の試みだった。 エアハルトの代々の後継者は、自分たちが財政規律の欠如の物語と見なすユーロ圏危機で同じ間違いを繰り返した。 オルド自由主義の3つの問題 オルド自由主義については現在、大きな重要性を持つ根本的な問題が3つある。 まず、オルドリベラル派は、恐慌――1世紀の間に1度か2度しかない大惨事――に対処する首尾一貫した政策を持たない。恐慌が起きた場合どうすればいいのかとオルドリベラル派に問うたびに、その答えには大抵、「創造的破壊」への何らかの言及が含まれる。 2番目に、オルドリベラル派は、独自の首尾一貫した金融政策の枠組みを持っていない。彼らはかつてマネタリストだった。現在の立場は、大部分において矛盾している。 筆者の3番目の批判は、もっと根本的なものだ。オルドリベラル派の教義を、ドイツのように比較的小規模で開放的な経済から、ユーロ圏のような大規模で閉鎖的な経済に移転できるのかどうか、まったく分からないという点だ。 オルドリベラルの世界観は非対称だ。経常収支の黒字は赤字より好ましいと考えられている。ルールは国内法に基づいているため、オルドリベラル派は自国の経常黒字が諸外国に与える影響など気にしない。ドイツがユーロを採用した時、突然、諸外国が問題になり始めたのだ。 危機解決の経済的コストが高くつく結果に オルドリベラルの教義は、ドイツにとってはうまくいった可能性もあるが、筆者としては、ドイツの経済的な成功は、経済政策よりも、むしろ主に技術と高いスキルと一部の優良企業の存在によるところが大きいのではないかと思っている。 ドイツはユーロ体制の支配を通じて、オルド自由主義のイデオロギーを他のユーロ圏諸国へ輸出している。これほど多様な法律の伝統と政治体制、経済状況を持つ通貨同盟にとって、これ以上に不適当な教義を思い浮かべるのは難しい。 その一方で、ドイツがこれをあきらめるのを想像するのも同じくらい難しい。その結果、危機の解決に要する経済的なコストは非常に大きなものになるのだ。 By Wolfgang Münchau
http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/42255
「1937年」の真の教訓とは何か
金融政策依存という罠、このままでは「新冷戦」どころか「新熱戦」に
2014年11月20日(Thu) 藤 和彦
「世界に幽霊が出る、『1937年』という幽霊である」
マルクスとエンゲルスによって書かれた「共産党宣言」の冒頭の有名な一文「欧州に幽霊が出る、共産主義という幽霊である」のパロディーであるこのフレーズは、米国連邦準備制度(FRB)が10月30日に量的緩和を終了したため「世界経済は再びリセッションに陥るのでは」という懸念を表したものである。 1929年の株式市場の大暴落を引き金に大恐慌に陥った米国経済は、8年後の1937年に再び悪化した。インフレを懸念するFRBが1936年後半から金融引き締め政策に転換したが、時期尚早だったために、米国をはじめとする世界経済は再びリセッション(景気後退)に逆戻りしたとされている。深刻なダメージを受けた世界経済は、第2次世界大戦という極めて大きな代償(6000万人超の命が奪われた)を払ってようやく回復した。 「現在は1937年に似ている」と指摘する代表的な論客の1人にイエール大学教授のロバート・シラー氏がいる。シラー氏によれば、現在は「ニューノーマル(新たな常態)」という言葉が「経済の長期停滞」を表すキーワードになっている。一方、1937年当時は「secular stagnation」(注)という造語が人々の絶望の表現として人口に膾炙していたという。 (注)「secular」は世代や世紀を意味するラテン語に由来する言葉。「stagnation」は沼地や湿地を意味し、毒性の強い危険を生み出す温床を暗示している。 将来に不安を感じる人々は、今後迎える困難な時期のために過剰な貯蓄に走りがちだ。これによりさらに投資は縮小し、景気をより一層悪化させる。この現象は「過少消費」と呼ばれ、失われた20年を経験した日本人にとって既知のことだが、この言葉が誕生したのも1937年頃の米国のようである。 経済活動が中核を成す近代市民社会では、人々の生活水準の向上なしには社会の安定が保てない。大恐慌時代の研究を皮切りに新自由主義経済学(金融政策重視)の「大御所」となったミルトン・フリーマン氏は、「経済成長の低迷が人々の間で不寛容を生じさせ、それが攻撃的なナショナリズムとなり、そして戦争を引き起こした」としている。 貧富の差が1820年代と同水準まで拡大 経済成長も確かに大事だが、現在の主要先進国にとって成長自体の鈍化よりも頭が痛いのは、貧富の差の拡大の問題ではないだろうか。 ユーロ圏をデフレから守ろうと闘う欧州中央銀行(ECB)のドラギ総裁は、政策金利がほぼゼロの今、資産購入によってインフレ率を押し上げようとしている。しかしECBの講じる方法が米国や英国、日本型の量的緩和(QE)に近づけば近づくほどエコノミストの間で悩みが深まっている。中央銀行の資産購入の目的はあくまで経済の安定と実体経済の回復だが、貧富の差の拡大という副作用が避けられない。「金持ちをさらに金持ちにしかねない」との批判が高まることが必至だからだ。 イングランド銀行(英中銀)は「2012年5月までに実施した3250億ポンドの資産購入が英国の家計資産を6000億ポンド以上増やした」との試算を発表した。しかし、家計の5%に過ぎない富裕層が株式や債券、不動産などの資産の約40%を所有しているため、その恩恵は富裕層に大きく偏っていることだろう。 FRBのイエレン議長も10月17日、高等教育の費用増加など機会均等の欠如を招く原因について複数言及し、その上で「所得と富の格差は過去100年で最大の水準に近い。こうした傾向が我が国の歴史に根ざした価値観(機会の平等)に照らしてどうなのかを問うことが適切だ」と現状を憂慮する異例のコメントを述べている。 経済協力開発機構(OECD)は10月2日、「世界の富裕層と貧困層の格差の拡大は1820年代と同じ水準にまで悪化している」との報告書を公表し、こうした変化は過去200年で「最も憂慮すべき」事柄の1つだと警告した。 この調査は、25カ国の1820年以降の所得水準を調べ、世界が1つの国であるとみなしてデータを突き合わせて行われた。調査の結果、世界の所得格差は、共産主義の台頭などに代表される20世紀半ばの「平等主義革命」によって急速に縮小した後、グローバル化が進み始めた1980年代以降急速に拡大し、2000年までに1820年と同じ水準にまで広がったことが分かったという。 日本でも同様のことが起きている。アベノミクスによる金融緩和の影響もあり、2013年の日本の富裕層(資産100万ドル以上)人口は、前年比22.3%増の232万7000人となった。富裕層の人数は米国に次いで世界2位だが、伸び率は世界最大であった。 金融政策の効果を薄める高齢化の進展 世界では高齢化の進展により金融政策自体の効果が薄れてきているとの見方も出てきている。 日本ではあまり知られていないが、2013年9月に国際通貨基金(IMF)は、人口動態と金融政策の関係性に関する興味深い研究論文を発表した。 金利が1ポイント動いた際に失業率とインフレ率に与える影響が、各国(米国・英国・カナダ・ドイツ・日本)の高齢人口(65歳以上の人口/20〜64歳の人口)の比率でどのように変化したかを過去50年にわたって検証したものだ。その結果「高齢化の進展により金融政策の効果が弱まった」との見方が裏付けられたという。 その理由としてIMFは、「高齢の貯蓄生活者は若者に比べて借金が少ないため、金利の変動によるインパクトを受けにくい」としている。高齢化が進む中で、中央銀行は実体経済の改善のためにこれまで以上に大幅(危険?)な政策の実施が必要となりそうだ。 また、「高齢者は年金等が実質的に目減りするインフレに対する嫌悪感が強い」ことも要因の1つとして挙げられている。 日本では2014年4月からの消費税増税と円安等による物価上昇で、年金生活者が財布のひもを締めたために、日本銀行の金融緩和の効果が薄れ、景気回復が想定以上に遅れている。その現状は典型的な証左ではないだろうか。 シャドーバンキングの規模が拡大 金融緩和は次の「危機の火種」も育てつつある。 主要国・地域の中央銀行や監督当局で構成する金融安定理事会(FSB)は、10月30日、「シャドーバンキング(影の銀行)の規模が世界全体で昨年5兆ドル拡大して約75兆ドルになった」とする報告書を発表した。 これは過去最低水準の金利を背景に、投資家が利回りを追求しているためである。ヘッジファンドや不動産、不動産投資信託(REIT)などを含む影の銀行業界の規模は、世界のGDP比120%前後、金融資産全体の4分の1に相当する規模にまで達したという。 落ち込んだ経済を立て直すのは公共投資 1937年の景気後退に話を戻すと、財政均衡論者だったルーズベルト大統領が、新設の社会保障税を20億ドル取り立てるとともに、公共事業などの財政支出を大幅に削減する方針をとったことが、FRBの金融引き締め以上に景気回復にとって大きなマイナス要因になっていたことはあまり知られていない。 11月4日、IMFは「2010年の段階で、各国政府に対し金融危機後の景気刺激策を改め緊縮策を求めたことは誤りだった」とする内部監察の結果を公表した。IMFは10月の年次総会で既にこれまでの姿勢を変化させ、成長を支える上で利用可能な数少ない残された政策手段として「インフラ支出の拡大」を提言していた。 IMFは2003年当時、「インフラ投資に対する日本の巨額支出が日本経済に対する押し上げと同じぐらい負担にもなった」と否定的な見方をしていた。だが今年の報告書では、「日本の公共投資は効果がなかったという見方は不当に強すぎる」としている。日本の公共事業プログラムの経済史を書き換えようとしているかのようである。 2008年以降の6年間に経験にかんがみ、「厳しく落ち込んだ経済を刺激して景気後退から引き上げるには、金融政策よりも財政政策の方が力を発揮する」との見方が高まりつつあるのだ。 緊縮財政路線を取る欧米諸国 しかし各国の政策への反映は「道遠し」である。 11月の米国の中間選挙で共和党が大勝したが、同時に実施された「最低賃金の引き上げに関する住民投票」が共和党が強い4つの州でも可決された。リーマンショック後の米国で「格差は拡大し、最低賃金は他人事ではない」という感覚が広がっているためだ。 発足当初のオバマ政権は巨額の財政政策(減税や公共事業)を実施したが、当初期待されたほどのの雇用の創出や格差の改善には結びつかなかった。このため「怒った」有権者達は、財政政策の上乗せではなく「税金の無駄遣いを抑えて欲しい」として民主党に「ノー」を突きつけた。ルーズベルト政権と同じように、今後、緊縮財政に舵が切られる可能性が高い。 欧州でも、ドイツ政府の緊縮財政重視の考え方は変わらない。各国からの強い要請で11月6日ショイブレ財務相は「100億ユーロ規模の追加公共投資を行う」と表明したが、連邦財政を均衡化させる目標を堅持したため、その規模は著名エコノミスト等が求めていた水準を大きく下回り、IMFやECBなどの失望を誘った。しかも、今回発表した投資の実行は2016年以降であり、直面する経済危機の対応に間に合わない。 格差拡大に対処できない国を待ち受けるもの 11月上旬に発表されたスペインの世論調査によれば、極左政党ポデモスの支持率が急上昇し、トップに躍り出た(18%)。同党はギリシャで現在支持率トップの急進左派連合にならって設立された政党である。その躍進の背景には、緊縮財政や格差の拡大に対する国民の不満があるのは間違いない。長期低迷が懸念視されるユーロ圏全体で反ユーロ政党が躍進しており、2年前に比べてユーロ圏の解体のリスクが高まっているとの声も出始めている。 アジアに目を転じると、香港のデモ参加者たちが自由選挙を要求している背景には、世界でも最大級の富の不平等の存在があると言われている。賃金の伸びが長年にわたって停滞し、不動産価格が急騰して、学生や中産階級の間で欲求不満が募っていたためだ。 「1937年以降の不満の蔓延が、アドルフ・ヒトラーやベニート・ムッソリーニの台頭をさらに後押しした」とするシラー氏だが、今の米国も対岸の火事ではない。格差拡大に対処できない国の政治がコントロール不能に陥る可能性が高いからである。 冷戦終結の立役者、ゴルバチョフ元ソ連大統領は11月8日、「ベルリンの壁」崩壊25周年に合わせて訪問中のベルリンの催しに出席し、「米国を中心とする西側諸国が『勝利主義』におぼれたために、既に“新冷戦”が始まっているという見方さえ出ている」と危機感を表明した。確かにウクライナ情勢はコントロール不能に陥る恐れが出てきている。11月15日に豪州で開催された20カ国・地域(G20)首脳会合でも、欧米側は本来の議題である経済問題よりもウクライナ情勢を巡るロシアに対する批判に終始した感が強かった。 このままでは「世界は『新冷戦』どころか『新熱戦』の危機を迎える」と主張するのは言い過ぎだろうか。
【あわせてお読みください】
・「ゴルバチョフの「新冷戦」説は間違っている」
( 2014.11.17、Financial Times )
・「社説:緊縮財政を巡る長い戦い」
( 2014.02.18、Financial Times )
・「米国雇用市場の成功が告げる量的緩和の終焉」
( 2014.10.28、Financial Times )
http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/42228
|
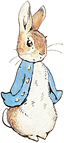
 スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。