02. 2014年10月23日 07:38:43
: jXbiWWJBCA
本当はよくわかっていない人の2時間で読む教養入門 やりなおす経済史
【第3回】 2014年10月23日 蔭山克秀
なぜあの時、世界大戦へと突入したのか?
今、ざっくり読んでおきたい世界経済史
第3回 バブルから恐慌、戦争へとつながる経済要因
なぜバブルから世界恐慌になったのか? なぜ恐慌から第二次世界大戦へと向かったのか? そもそも不況時にバラマキ政策が行われるのはなぜか? 当時と今日の時代的な共通点が指摘されるなか、戦争へとつながる経済要因を、歴史の流れから読み解こう。代ゼミの人気No.1講師が面白くわかりやすく教える、教養としての「経済史」学びなおし講義。さあ、ドイツからGNP 20年分をむしり取れ! 前回(第2回)で見たように、世界に先んじた産業革命によってイギリスが世界の親分として君臨した「パックス・ブリタニカ」時代。イギリスは、アダム・スミスをはじめとする古典派経済学に後押しされるかたちで、自由放任経済を推し進めた。 しかし、世界の生産力が追いついてくると、ドイツ、フランス、ロシアなどの列強は新たな市場を求め“国盗りゲーム”が過熱する。その獲物は中国から次第にバルカン半島に移り、ついに第一次世界大戦へと突入した。 そして、1919年、第一次世界大戦の講和条約として、「ヴェルサイユ条約」が締結された。ここでの注目点は一つ。敗戦国ドイツがどこまでむしられるかだ。 この戦争は、史上初の世界大戦だ。27ヵ国も参戦している。しかも終盤ではドイツが潜水艦でイギリス付近を固め、近づく船を片っぱしから潜水艦攻撃するというムチャまでやった。もう欧米列強はカンカンだ。 だからドイツは、戦後賠償としてはギネス級にひどい目にあった。そのひどさは、もはやブルガリアの比ではない。あっちが丸裸なら、こちらは臓器や骨髄、血液から毛髪に至るまで、列強にすべてバラバラにされたあげく、根こそぎ持っていかれた。もはやイジメなんてレベルではない。猟奇殺人だ。 ドイツはこの条約で、海外の領土と植民地をすべて奪われた上、軍隊は破壊的レベルでの縮小、徴兵制の廃止、武器弾薬の保有は砲弾数や銃の種類まで指定しての制限、毒ガス・戦車・潜水艦などは研究すら禁止、そして極めつけは、なんと1320億金マルク(金本位制下でのマルク紙幣)もの賠償金だ。 1320億金マルク!! 当時のドイツのGNP20年分だよ! いくら戦争賠償金の目的が“国力を削ぐこと”とはいっても、これは削ぎすぎ。もはや土に還るレベルだ。よく「鮭は捨てるところがない」なんて言うけど、ドイツが分割された後は、その鮭以上に捨てるところがない。 そしてドイツは、その賠償金の支払いに案の定、困ることになる。ドイツは最初、「こんな冗談みたいな巨額の賠償金、ムリです」と支払いを渋ったが、渋るや否やあっという間にフランスからルール地方を占領された。 これって闇金に拉致られたとき、半笑いで払えないって答えたら、その瞬間生ヅメを2枚ベリベリッと剥がされたようなもんだ。ヤベェ、こいつら本気だ。次は埋められる……。フランスも第一次世界大戦で国土が荒廃し、焦っていたのだ。これはもう払うしかない。 でも、いざ払うとなっても、当然そんなふざけた額のマルク紙幣は存在しない。そこで仕方なくマルク紙幣を膨大に増刷し、その後とてつもないハイパーインフレに苦しめられ続けることになる。 今ハイパーインフレと言ったが、どれくらい凄まじいインフレだったのか? その頃ドイツは、マルク紙幣を発行しすぎて価値がどんどん暴落し、ついに為替レートは驚きの「1ドル=4兆2000億マルク」にまで達していた。 4兆2000億マルク!! それ絶対財布に入んないわ。コーラ1本買う程度の金が財布に入んないって、どういうこと? それたぶん、荷物多めの独り暮らしの引っ越し用トラックぐらいないと運べないぞ。 そこで、どんどん高額のマルク紙幣・貨幣を発行せざるをえなくなり、ついには幻の1兆マルク銀貨、100兆マルク紙幣なども登場するほどになった。 僕も以前、魔が差して有楽町のコインショップでその1兆マルク銀貨を買ったが、そのとき店主に「これって当時、どれくらいの価値だったんですかね?」と聞いたら、「さあ、80円分ぐらいは買い物できたらしいですよ」と言われたのを今でも覚えている。 でも、さすがにここまで法外な賠償金は、やりすぎだ。しかもルール地方の占領って、ドイツ一の工業地域を取り上げちゃ金の稼ぎようがない。ドイツを破綻させたいんならともかく、搾取したいんなら「生かさぬよう、殺さぬよう」だろ? おい列強、お前ら封建制出身なら、絶対“わが国の家康公”みたいなやつがいるだろ? そういうやつからいっぺん、真綿で首を締めるような理想的な搾取レクチャーでも受けてこい。さもなくば「慶安の御触書」でも読んどけ。こういうムチャな追い込み方をしたら、そのうち必ず一揆(ヒトラーの出現)が起きるぞ。 他国が戦うほど対岸の火事で儲かるアメリカのしたたかさ 第一次世界大戦中、日本はうまく(というか狡猾に)立ち回った。中国のドイツ権益を手にし、欧州勢がすっからかんでお留守になったアジア市場を独占したおかげで、製造業や造船業を中心に「成金」という言葉も生まれた。 でも日本、その後はパッとしなかった。第一次世界大戦が終わる直前には、シベリア出兵(1917年のロシア革命からくる社会主義の波及を食い止める)による米需要の増加を見越した買い占めや売り惜しみから「米騒動」が起こったし、戦後は工業製品の輸出が目に見えて減り、しかも1923年には関東大震災まで起こった。というわけで、日本経済は尻すぼみ、不況が深刻になっていった。 これに対してアメリカは、まさに経済絶好調だった。第一次世界大戦中、自国が戦場になっていないメリットを活かして、三国同盟・三国協商の双方に軍需物資を売りまくったアメリカは戦後、世界一の債権国になっていた。 しかもその流れは、そのまま戦後復興物資の販売にもつながり、アメリカにどんどん富が集中した。今やアメリカは、労働力は豊富(大戦中戦火を逃れた欧州移民が労働者に転化)な上、株式市場も発達し、しかも世界の工業生産の4割と世界の金の44%を保有するという、新しい“世界の親分”となっていた。 1920年代のアメリカは“黄金の20年代”と呼ばれる繁栄期に入っており、消費も生産も絶好調で、一般大衆はラジオ・映画・プロ野球などの大衆娯楽を心ゆくまで楽しみ、住宅・自動車も飛ぶように売れた。 戦勝国、敗戦国ともにボロボロでストレスは最高潮へ 一方、イギリスは、戦争被害と戦時中の産業停滞などがたたり、完全に“世界の親分”の地位をアメリカに奪われてしまった。国内は不況ムード一色で、失業率が悪化し、労働者のストが頻発した。 そのような時代の流れを受けて、政治の舞台では労働党が躍進し、年金や失業保険など社会保障が充実した。それに伴い、これまで保守党(元トーリー党)・自由党(元ホイッグ党)の二大政党制だったイギリスは、「保守党と労働党の二大政党制」の国になった。 ロシアは、第一次世界大戦終盤の1917年、国内でロシア革命が起こってロマノフ王朝が倒れたため、もう三国協商どころではなくなっていた。ちなみに、ロシア革命は最終的に1922年に史上初の社会主義国家「ソビエト社会主義共和国連邦」の誕生にもつながる。資本主義国vs社会主義国というのは第二次世界大戦後の大きな対立軸となって新たな抗争へとつながるが、その話はまた後でするよ。 この頃は日本のシベリア出兵も含め、社会主義の拡大を恐れる連中が攻め込んできては、大戦後の国内再建のため戻って行くという迷惑なことが続いたため、この後ロシア改めソ連は、しばらくは国土の建て直しと社会主義国家の建設に全力を注ぐことになる。 フランスは第一次世界大戦後、かなり弱っていた。国土が戦場になったせいでボロボロに荒廃し、ロシアに貸した金は革命で不良債権化。その上ドイツまでもが、賠償金の支払いを待ってくれと言い出した。 さすがにこれにはカッとなって思わずルール地方を占領したが、本当はこんなことより、ただ金がほしいだけ。結局フランスは、1926年発足のポアンカレ内閣が財政再建とフランの切り下げ(「フラン安=フランスのモノは安い」になり輸出有利に)を行い、ようやく経済が回復に向かい始めた。 イタリアは実は、大戦初期からドイツ・オーストリアを裏切り、三国協商側に寝返っていた。つまりは戦勝国だ。にもかかわらず分け前が少ないことに、強く不満を抱いていた。しかも国土は戦乱で荒れ、国民の生活は苦しく、ソ連から社会主義思想が入ってきたせいで、労働者や農民の暴動やストが頻発していた。 そしてドイツは、賠償問題に苦しんだ。絶対に払えるわけのない金額なのに、フランスみたいに本気でアテにしている国があるからタチが悪い。この賠償金に振り回されて、ハイパーインフレは起こるわ、ルール地方は占領されるわ、もう国民のストレスは頂点に達していた。 特需景気からバブル、そして崩壊へと向かうアメリカ経済 アメリカ経済は、第一次世界大戦後もしばらくは好調だった。これは、ヨーロッパからの軍需物資の注文が、そのまま復興物資の注文に変わったからというのが最も大きな理由だ。アメリカはヨーロッパから地理的に遠く離れている上、当初「モンロー主義」を採っていたからね。だからみんながボロボロになっているなか、一人だけ涼しい顔してモノを売り続けることができたのだ。 しかし、1920年代の前半から、次第にモノが売れなくなってきた。これは、各国の戦後復興が終わりつつあること、アメリカ経済の生産規模が拡大しすぎて世界の消費が追いつかないこと、そしてソ連が社会主義化して商品の買い手ではなくなったことなどが、原因として考えられる。 いずれにせよこの時期、アメリカでつくられるモノは明らかに世界の市場では「生産過剰」となった。にもかかわらず、アメリカの証券市場は過熱し続けた。第一次世界大戦中から終戦直後は軍需物資が売れまくっていたため、どの銘柄も株価は下がらず、人々に富を与え続けた。そして豊かになった人々は住宅と自動車を欲し、自動車による移動距離の拡大は、さらに人々の住宅圏を拡大させて不動産の売れ行きを伸ばしていく。 こうなると、欲望まみれの人間は、ある種のスイッチが入るようにできている。そう、バブルのスイッチだ。つまり、市場は「株価は永久に上がり続ける」という楽観論に支配され、一般市民も株式ブームに浮かれ、実体経済の規模を明らかに上回る投機資金が株式市場を暴走し始めているのに、誰も気づかず誰も止められなくなっていたのだ。 いや正確には、みんな薄々「今俺たち、ヤバい暴走列車に乗ってるなあ」と自覚し、そこに不安を感じつつも、欲ボケのせいで降り時がわからなくなり、とにかく他人よりも先に列車から降りて自分だけ損をするのだけはイヤだという“煩悩チキンレース”状態になっていたのだ。 地価も相当ヤバい上がり方になっていたが、より手軽な投機対象である株価の方が上がり方が異常で、ダウ平均は実体経済が冷え込み、生産過剰が顕著になってきたはずの1920年代前半から1929年までの間で、実に5倍も値上がりした。そして1929年10月24日、ダウ平均が史上最高値を更新したわずか2ヵ月後、相場は一気にクラッシュした。 GMの株価下落を引き金に、それまで水面下で渦巻いていた不安心理、新聞報道、大きな投機筋の売りなどが市場にパニックをもたらし、ウォール街は完全に“売り一色”となった。そしてそのわずか5日後には、ダウ平均は2ヵ月前の約半分にまで下がってしまったのだ。 ケインズ経済学を実践したアメリカの「恐慌対策」やいかに? この未曽有の大恐慌に対し、時のアメリカ大統領ハーバート・フーヴァーは、自己の信じる「自由放任主義」を貫いた。 でも、バブルが崩壊したのに政府が無策というのは、ありえない。確かに経済は「好況→後退→不況→回復」の4局面の繰り返しだから、普通の不況ならば放っておけば“回復”する。ただし、それはあくまで“実体経済で起こる普通の不況”の話であって、バブル崩壊ではこうはいかない。 バブル崩壊は、人間の欲望でパンパンに膨れ上がった巨大なマネーの風船玉が、バチーンと弾ける現象だから、その後をチマチマとモノづくりで埋めようったって、そんなのスケールが違いすぎて無理に決まっている。隕石落下でできたクレーターを、トンカチと釘と板で何とかしようとするようなもんだ。 結局、フーヴァーの無策は対応の遅れにつながり、恐慌は世界に波及し、ドイツとオーストリアは賠償金の支払いに苦しんだ。 そこで遅ればせながら、1930年には「スムート・ホーリー法」に基づく保護関税政策で自国産業を守る政策を採りつつ、1931年には「フーヴァー・モラトリアム」でドイツとオーストリアの債務支払いを猶予したが、対応が後手後手で、さしたる効果は得られなかった。 その後1933年、アメリカ大統領はフーヴァーからフランクリン・ルーズベルトになった。フランクリンはセオドアの甥だ。彼は大統領に就任すると、これまでの自由放任主義とは真逆の政策「ニューディール政策」を実施した。 ニューディール政策とは、ケインズ経済学の「有効需要の原理」を具体化したもので、不況で有効需要(=お金を使う国民)が不足すると、政府が供給してやるという政策、つまりは“お金のバラマキ”だ。 前回見たように、古典派経済学などに代表される自由放任経済は、政府は経済活動にはノータッチだった。好況だろうが不況だろうが、ただただ政府は、自由経済を守るためのガードマンにすぎず、軍隊と警察さえあればよしの「夜警国家」が基本だった。 しかし、ケインズは発想を逆転させ、不況時には政府が積極的に役割を担って国民生活を助けていく「大きな政府」を提唱した。そして、その理論の中核をなす考え方が「有効需要の原理」だ。 有効需要とは、単に欲しがるだけじゃなく、「それをほしいから“買う”」にまでつながる需要だ。つまり有効需要は、「お金を使う国民」と言い換えてもいい。そう考えると、ケインズ経済学に出てくる「不況時に有効需要が不足すると、政府が創出する」という考えは、「不況時に金を使う国民が減れば、政府が金をバラまいて、それをつくり出してやる」という意味になる。 そして、その金をバラまくための手段が、公共事業や社会保障だ。そう、結局ケインズ経済学とは、不況時に政府が公共事業や社会保障でお金をバラまくという、今日的にはとてもありがちな経済政策のことなんだ。 でもこれ、実はなかなか浮かばない発想だぞ。だって不況になれば、普通誰でも「節約しないと」と思う。個人も国家も同じだ。でもケインズは、「不況時こそ国民のために金を使え」だ。 そして、政府が金を使う国民(有効需要)をつくれば消費が伸び、消費が伸びれば企業の生産が活性化する。そして企業が元気になれば、世の中から非自発的失業は消え、完全雇用が実現する……。 つまり「世の中、需要が供給をつくり出して(=買い手を増やせばモノはつくられて)景気は良くなるんだから、まずその最初の需要創出のために、政府が率先して金をバラまけ」ってことだ。 ルーズベルトはこれを実施するために、まずテネシー川流域開発公社(TVA)をつくり、大々的な公共事業を実施した。そしてその後も、農業調整法(AAA)、全国産業復興法(NIRA)、社会保障法、全国労働関係法(ワグナー法)と、これでもかとばかりに「大きな政府」で国民のために金をバラまいた。 結論から言うと、このニューディール政策は、政府がバラマキをやめる“見切り”が早すぎ、政策後、再び景気は停滞している。本格的な景気回復は、第二次大戦による軍需景気まで待たなきゃならなかったが、もっと思い切りよくバラマキを続けていれば、おそらく効果は出たと思われる。不況のときに金をバラまくなんて、かなり勇気のいる政策だけど、このニューディール政策がその後の不況対策に与えた影響は大きい。 世界標準の通貨システム「金本位制」とは? 生産と消費の中心であるアメリカ経済がクラッシュすると、それは世界中に波及し、アメリカのバブル崩壊は「アメリカ発の世界恐慌」となってしまった。これに各国はどう対応したのか? 結論から言えば、最悪の結末に向かって舵を切るんだけど、ここでは少し遡って、世界を牛耳る通貨体制の背景から、ここまでの流れを少し整理してみよう。 世界の主要国は、第一次世界大戦前まで、当時の組長であるイギリス主導で「金本位制」を採用していた。これは通貨の価値を金との交換で保証する制度で、19世紀にイギリスの発案により世界に広まった。 1817年、貨幣法に基づいてソブリン金貨が発行されたのが、金本位制の始まりだ。その後、欧州でイギリスとつき合いの深い国が徐々にこの制度を導入し、日本も1897年、金本位制を採用した。金本位制を採用している国の通貨(=兌換紙幣)は、銀行に持って行くと、何グラムかの金と交換してくれる。例えば、日本も19世紀末から採用していたが、その当時の交換比率は「1円=0.75グラムの金」だった。 では、この制度は何のために生まれたか? それは世界貿易の拡大とともに、他国通貨を受け取る局面が増えてきたからだ。19世紀、産業革命のおかげで「世界の工場」となったイギリスには、貿易でよその国に売りたい商品は山ほどあった。 ところが、そんなイギリスにとって頭の痛い問題が一つあった。それは、他国通貨の価値がわからないという問題だ。普段からつき合いの深い国、例えばフランスのフランやドイツのマルクなら大丈夫だ。困るのは日本みたいな謎の国から、突然1円札なんて見たこともないものを受け取ってしまったときだ。 小柄でちょこまかした連中から、突然渡された謎の紙切れ。どれだけ価値があるのかと聞いても、ニコニコ笑って「ダイジョーブ、ダイジョーブ」と繰り返すのみ。ダイジョーブじゃねーよ、ヘラヘラしやがって。こっちは商品渡してんだぞ。この紙切れ、本当にちゃんと価値あるんだろうな? 通貨は「額面価値=素材価値」じゃない。だから正直、変な国の通貨は受け取りたくない。でも貿易は拡大したい。そこでこの考えが出てきた。「世界共通の価値が認められるもの(=金)と通貨の交換を、各国が保証することにしよう」と。これが金本位制の始まりだ。 前述したように、イギリスは世界にさきがけ1817年に金本位制を導入した。すると、ポンドが価値の安定した国際通貨と認められるようになり、ポンドを用いた貿易が促進した。そして、金保有量に余裕のある国が徐々に金本位制を導入し始め、1870年代にはドイツやフランス、1990年にはアメリカが金本位制に移行し、日本も1897年より金本位制を導入するに至ったのだ。 金本位制を導入すれば、その国の通貨は国際社会で信用され、貿易が促進する。なるほど、金には世界共通の価値があるから、日本のことはいまいちわからなくても、誰も日本との貿易を拒まなくなるってわけだ。 しかも金本位制下では、通貨価値が非常に安定する。この制度下では原則、円高や円安は発生しない。つまり、貿易を不安定にする「為替リスク」(=円高・円安などの進行に伴う不利益)がない。もうどこまでいっても「1円=0.75グラムの金」だ。これが変わることがないなら、利益の計算も安心だ。 しかし、この制度は維持が大変だ。なぜなら、金と通貨の交換保証を確実にする以上、もし世界貿易できるほど多額の通貨を発行したいなら、まずその国は莫大な量の金を保有しないといけないことになるからだ。 これに日本は当初、苦しんだ。だってそんな金ないもん。イギリスには植民地から集めてきた金があるだろうけど、かつての黄金の国・ジパングには、今やそんな金はない。マルコポーロが『東方見聞録』で「掘れども尽きず」と表現した、岩手の玉山金山は江戸時代に閉山し、佐渡金山を始めとする他の金山も1970〜1980年代あたりに閉山し、今は鹿児島の菱刈鉱山だけが辛うじて生きている金山だ。 結局、日本が本格的に金本位制を導入できたのは、日清戦争(1895年)後。つまり、日清戦争で得た金2億両という賠償金を使って、日本の金本位制は始まったのだ。 これで日本も、世界の主要国と対等に貿易できる! でもこの制度、何かモヤモヤとした不安が感じられる。その不安の正体とは一体何なのか? 金本位制は全然ダイジョーブじゃなかった! 金本位制は、金の価値に依存して、通貨価値を保つ制度だ。しかしそうすると、常に二つの不安要素がつきまとう。 まず一つは「もしその国の金が足りなくなったら、どうなるのか?」。そしてもう一つは、「もしその国の経済がガタガタになったら、果たして世界は、その国の金本位制を信用してくれるのか?」だ。 前者はいたってシンプルな物理的不安だ。金が足りなくなれば、その国の通貨は金と交換できない。金と交換できなければ、その国の通貨は紙くず同然だ。よってそうなれば、その国とはもう貿易できない。 「うちの通貨は金と換わらなくなったけど、うちの国内では使えますよ。ダイジョーブ、ダイジョーブ」 全然ダイジョーブじゃない。国内での信用なんて、その国と運命共同体の自国民との間だけの約束事だ。もしお前らの国で改革でも起こって、通貨が変わったらどうすんだよチョンマゲ! そうなりゃ信用できるのは紙切れより金だろーが。ふざけたことぬかしていると、黒船で駆逐するぞ。 金本位制がシビアな制度である以上、通貨と金の交換保証がなくなったら、もう貿易は存続できない。どの国もそうなることを覚悟した上で、ふだんから金不足に陥らないよう注意しなければならない。 でも実は、金本位制で最も怖いのは後者、すなわち心理的不安だ。これは具体例があった方がわかりやすいので挙げてみよう。例えば、今の日本が金本位制を採っているとする。そんななか、もしもバブル崩壊みたいな、国の信用が一気に消し飛ぶほどの出来事が起こったら、貿易相手の外国人はどう思うか? メチャメチャ不安になるね。なぜなら彼の財布の中には、日本との貿易用に1万円札がギッシリ入っているんだから。彼は思う。今日本は瀕死の状態だ。下手すると、明日には通貨と金の交換ができなくなるかも。でも今日ならまだできる。なら今のうちに銀行に行って、手持ちの1万円札を全部金に換え、日本とのつき合いをやめないと。 その結果、何が起こるか? 金の海外流出だ。これで金がどんどん出て行ってしまえば、結局金不足から制度が崩壊することになる。つまり金本位制下では「不安でたまらない1万円札なんかより、安心できる金を」と思われたらアウトってことだ。 実際の世界でも、まさにそれが起こった。1回目は、第一次世界大戦の開戦に伴う金本位制からの離脱、そして2回目は、世界恐慌だ。前者は戦争中だから、他国は基本信用できないし、戦費の捻出には金保有量にしばられない紙幣の増刷や国債の発行も必要になる。あまりよろしくない理由ばかりだが、ここでの離脱はある意味当然だ。 しかし、やっぱり戦争での離脱は、後処理が大変だ。結局このときは、大戦が“対岸の火事”だったアメリカだけが1919年に早々に金本位制に復帰しているけど、他国は戦後の国債処理やインフレ収束、金保有量回復に手間取り、金本位制への復帰は、1924年にドイツ、1925年にイギリス、1928年にフランスと、だいぶ遅れてしまっている。 そして世界恐慌だが、こちらは完全に金本位制が崩壊するきっかけとなった。1929年、ニューヨークのウォール街で突然弾けたバブルは、世界に深刻なデフレ不況をもたらした。 これに対する対策として、前に紹介したようにアメリカのフーヴァー大統領はスムート・ホーリー法に基づき、自国産業を守るために“輸入品が高すぎて売れなくなる”よう、輸入品に高い保護関税をかけたが、これが大失敗だった。 アメリカへの輸出に依存している国々は、高関税でモノが売れなくなるのを避けるためには、金本位制を捨てて通貨価値を切り下げ、モノを安くするしかなくなってしまった。つまり日本で言うなら、まず人為的に円安にする。すると、「円安=日本のモノは安い」だから、これで日本のモノが再び売れるようにするってこと。こういう自国通貨の不当な切り下げを、「為替ダンピング」という。 具体的には1931年、イギリスが金本位制を離脱し、ポンドの価値を切り下げたのをきっかけに各国も追随し、1930年代半ばのヨーロッパは為替ダンピングだらけとなった。そしてついに1937年、最後まで踏ん張っていたフランスが金本位制を離脱し、世界から完全に金と交換できる通貨が消滅してしまった。 金本位制が消えてしまうと、そこに残るのは、ダンピングによる小さなメリットと、他国通貨への不信感という大きなデメリットになる。金という絶対的なモノサシを失った各国は、もはや他国通貨を受け取ること自体が怖くなり、アメリカ以外の国々も「保護貿易」(保護関税や為替制限)を始めることになる。 ブロック経済は戦争へのカウントダウン ここで、保護貿易の中身について、ちょっと説明しておこう。まず関税とは、政府が取るショバ代みたいなものだ。つまり、「うちの国で商売させてやるんだから、政府にショバ代払え。金額は、商品一個売るごとに、その価格の○○%」みたいな取り方だ。これが高ければ、他国はその国で商売するメリットがなくなって輸入品を撃退でき、自国利益が外国に吸収されるのを防げる。 また為替制限とは、通貨交換の制限、つまり、例えば円とドルの交換を禁止したり制限したりする措置だ。確かにそうなれば、アメリカとの貿易そのものができないから、もうダンピングにおびえる必要はなくなる。 このように通貨価値の混乱は、世界経済を手探りの闇の中へと追い込んだ。しかし世界は脆いね。通貨価値を測るモノサシがなくなっただけで各国は動揺し、世界貿易は、みるみる縮小したんだから。 これって、中が見えない箱に手を入れて、中身を当てるゲームみたいだ。視覚というモノサシを失った僕らはたちまちチキンになり、大福に触っただけで「ひゃあ動いた!」などと悲鳴を上げる。 しかし、貿易がまったくできないのは困る。世界経済の規模は、昔と比べて格段に大きくなっているのだから、今さら貿易がまったくなかった自給自足体制に戻ることは不可能だ。ならば各国はどうするか? そこで出てくるのが「ブロック経済」だ。ブロック経済とは、共通通貨を使う「自国と植民地の間だけ」で行われる排他的な貿易体制のことだ。確かにこれならば「同じ通貨を使うエリアでのやりとり」だから、為替リスクは避けられる。 しかしブロック経済は、戦争へのカウントダウンに等しい。なぜなら絶対、植民地の少ない国が不平不満を言い始めるからだ。ちなみに、植民地を多く持っている「持てるブロック」の代表格は、イギリスのスターリング・ブロックやフランスのフラン・ブロック、アメリカのドル・ブロックなど。 逆に「持たざるブロック」は日本の円ブロック、さらには第一次世界大戦で敗戦国となったドイツなどは、ヴェルサイユ条約のせいで植民地すら持っていない。こりゃ、ドイツがヴェルサイユ条約を破棄して軍備増強を始めるのもわかるよ。 この後、当然日本やドイツなどの「持たざるブロック」は、植民地の再分割を求めて暴れ出し、それを止めようとするイギリス、アメリカ、フランスらとぶつかることになる。 こんな具合に世界恐慌後、“外へ外へと拡張”するのが植民地の少ない国、「持たざる国」の行動パターンね。一方、「持てる国」であるアメリカやイギリスの方は、自国と植民地のみでガッチリ結びつく「ブロック経済」で、排他的な貿易圏を形成した。この「持てるブロック」と「持たざるブロック」の小競り合いは結局どうなるのか? そう、もはや戦争しかない。 日独伊の「持たざる国」が戦争へと向かった理由 世界恐慌後、お尻に火がついた「持たざる国」は三つあった。まずは日本。第一次世界大戦では対岸の火事で大儲けした日本だったが、その後は経済が冷え込み、世界恐慌ではここまでの儲けをすべて吐き出してしまった。 局面打開のためには、植民地拡大しかない! 軍部の台頭めざましかった日本では、1931年に関東軍(満州駐留の日本軍)が独断で起こした柳条湖事件(満鉄爆破事件)を中国側のせいにして満州事変を起こし、清朝最後の皇帝・溥儀を執政とする傀儡政権「満州国」を建国した。 しかしそれが、国際連盟派遣の「リットン調査団」によって侵略行為と認定され、日本は1933年、国際連盟脱退を通告された。金に困ってやんちゃして親から勘当されたら、向かう先はもう決まっているね。 日本は1936年にドイツと手を組んで日独防共協定を締結、翌1937年には盧溝橋事件(中国側からの発砲)をきっかけに日中戦争が始まった。そして、その中国から手を引けと言ってきたアメリカから経済制裁を受けた後、ついに1941年、日本軍がハワイの真珠湾に奇襲攻撃を仕掛ける。こうして太平洋戦争は始まった。 二つ目の国はドイツだ。第一次世界大戦に負け、鬼のような賠償金を請求されたドイツは、アメリカの手助け(経済復興資金を借りたり賠償額を軽減してもらったり)で、本当に辛うじて人の心を保っていた。 ところが世界恐慌を境に、アメリカからギリギリ垂らされていたクモの糸もブチッと切れ、ついにドイツは祟り神に……ではなく、ナチス党が第一党になり、1933年にはヒトラー内閣が誕生した。 ヒトラー内閣がめざすものは「ヴェルサイユ体制からの解放」、つまりヴェルサイユ条約で課された巨額の賠償金をチャラにし、ハンニバル・レクター教授なみにがんじがらめにされた再軍備への足かせを外すことだった。 ナチス党は、その実現のためには「全体主義」が必要であると訴えた。全体主義とは、最終的にみんなが幸福になるために、国民すべてが国家に奉仕し、国家の繁栄をめざすという、言うなれば“極右の社会主義思想”みたいな考え方だ。 世の中が平和に安定しているときなら、そんな個人の自由のない思想は見向きもされなかっただろう。でも今のドイツには、敗戦国特有の卑屈な気分と閉塞感が充満している。ここから抜け出すためなら、人々は何でもしたい。そこに、ゲルマン民族の優越を訴え、景気回復への具体的な道筋を示し、演説と宣伝の巧みなカリスマが現れたら、人々は心をつかまれる。それがヒトラーであり、ナチス党だった。 ナチスは1933年、国際連盟を脱退し、公約通りヴェルサイユ条約を破って再軍備と徴兵制を復活した。そして国民に福祉や娯楽を提供しつつ、軍需産業と公共事業を続けることで、経済力と軍事力を回復させ、大衆の心をつかんでいった。 ほら、やっぱり“重すぎる年貢”は一揆の元だって。みんなレクターに共鳴しちゃったじゃん。ドイツを追い込みすぎたツケは大きいぞ。 ついにドイツは1938年、オーストリアを併合し、チェコの一部も併合して、ポーランドにもちょっかいを出した。イギリスとフランスはそれを止めようとし、1939年、第二次世界大戦は始まった。 最後はイタリア。第一次世界大戦後、不況とインフレに苦しむイタリアでは、ロシア革命も刺激となって社会主義運動が激化し、ストライキが頻発した。彼らは反革命的なファシスト党(資本家層が支持)と対立するが、ストでは生活改善できないことに失望し、やがてすべてがファシスト党へとのみ込まれていく。 その圧倒的支持(+反対者への直接的な暴力)を背景に、1922年に党首ムッソリーニは「ローマ進軍」(クーデター)を行い、国王の支持を取り付け首相となる。以後20年間、イタリアはファシスト党の一党独裁体制となる。ファシスト党は反社会主義の全体主義的政党で、ナチスよりも暴力的な要素が強い。 世界恐慌後、ムッソリーニは大規模公共事業で失業者救済を図るが、資源に乏しい現状を打破するため、1935年エチオピアに進軍。国際連盟はこれに抗議して、イタリアに経済制裁するも、抑えきれず、翌年エチオピアは併合される。 翌1937年、イタリアは国際連盟を脱退したが、国連が弱体化したのを世界に見せつけた後に脱退とはやるね、イタリア。もともとヒトラーは、ムッソリーニの「ローマ進軍」を真似て「ミュンヘン一揆」(1923年、政権奪取をめざすも失敗。投獄中に『わが闘争』を執筆)を起こしたほどムッソリーニのファンだから、この後必然的に両者は接近していき、この流れで日独伊の枢軸同盟が結ばれていく。 結局、第二次世界大戦の経済的要因とは何か? 結局わかったことは、通貨価値の混乱からくる世界貿易の縮小こそが、第二次世界大戦の経済的な主要因だったということだ。もちろん政治的にもいろいろな要因があったこともわかったと思うけど、経済的要因の方はここまでシンプルな太い軸にまとめることができるんだ。 ならば今後、戦争を経済の側面からなくしたいと思うなら、どうするか? そう、通貨価値の混乱を避けるため、通貨の価値をガッチリ固定させることだね。だから戦後の通貨体制は、「固定相場制」から始まるんだ。 (※この原稿は書籍『やりなおす経済史』から一部を抜粋・修正して掲載しています)
http://diamond.jp/articles/print/60474 |
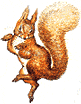
 スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。 スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。