05. 2014年10月14日 06:58:31
: jXbiWWJBCA
「河合薫の新・リーダー術 上司と部下の力学」
「直感に頼るのは愚か者?」 中村修二氏の怒りとオトナへの警句人間の直感こそ常識に囚われない根源的で自由な思考 2014年10月14日(火) 河合 薫 “夢の青い光”を創りだした3人の化学者たちが、ノーベル賞を取った。すごい! 自分がいつも使っているモノを創りだした人たちの受賞なので、なおさらそのすごさが実感できる! 小柴先生のときには、何度説明されてもどれだけ大きな窯を見せられても、ちっともニュートリノが理解できなかったし、小林先生と益川先生のときには、素粒子というものがとにかく一番小さいってことはわかったけど、「で?」という域から脱することができなかった。ノーベル化学賞の田中耕一さんとは対談までさせていただいたのに、やっぱり最後まで何だったのかわからずじまい。なんとも情けない。 だが、今回は、LED。アノ青い光だ! 家にあるし、胸ポケットの中にもある(私の場合はお尻のポケットですが…)! って、携帯にLEDが使われているのは今回初めて知ったのだが……。 「幻想的な月の灯りと、青い光のコラボですね!」と興奮気味にはしゃいでいたテレビキャスターのコメントは、私にはよくわからなかったけど、青い光が都会的で近代的な感じがするのは、20世紀中には無理と言われたものを見ているからなのだろうか(嗚呼、この私のコメントもわからないですね……)。 いずれにしても、称賛と共にメディアでは例のごとく「切り出したモノ」が飛び交っている。キャッチーな言葉やエピソード。それだけが一人歩きすると、ときにめんどくさいことになる。 「これでまた、好きな仕事を探す学生が増えるぞ」
「僕は流行りの仕事はやりたくないです! なんて部下に仕事拒否されたりして」
「やりたい仕事ができないからって辞めるヤツ増殖!」
「電話にも出ない? ただでさえ電話に出ないヤツが多いのに……」
「会議をサボる輩も増えたりして」 そんなことを思った人も多かったかもしれない。 ただ、私は、「流行りのものをやるのでなく、やりたいものをやりなさい」という赤崎教授の若い研究者に向けたメッセージは、若者というより、今の日本の大学やキャリア教育、日本社会に向けたメッセージだったと受け止めた。目に見える成果ばかり求めていいのか。短期的な結果ばかり追いかけすぎてはいないか、と。 でも、おそらく当の“本人たち”はそんな風に受け止めず、「やりたいこと探しキャリア教育」「成果命社会」は、ますます過熱するに違いない。 そして、その勘違いの刃は若者たちに向けられるのだ。 先月から後期の講義が始まり、既に2年生たちが「やりたいこと探し」に疲れ、「自分の強み探し」に苦悩していて、なんだか可哀そうになった。必死に就活本を読み、キャリアセミナーに参加し、ネットで情報を得て……。まだ、2年生なのに、大学生活を楽しむ間もなく、就活に囚われ、自信を失い、やる気をなくしていた。大学は就職予備校か? しかも、「面白そう!とか、やってみたい! って思ったら、なんでもやってみなさい。就活とか関係ないことでも、就活にちっとも役に立たないことでも、やりたい!って思ったら、やりなさい。ただし、とことん一生懸命やりなさい」と私が言うと、 「ホントにやりたいことやっていいんですか?」と聞いてくる。
「私、ダンスが大好きでもっとやりたいんですけど、就活が始まるから止めなきゃって思ってたんです」なんて具合に。 彼らが「探しなさい」とオトナたちから言われている、やりたいこと探しっていったい何なのだろう? 私には訳がわからない。 「自分の強みを探す」って、一体何?
まだ20年そこそこの人生、その半分の年月に意識すらない彼らに、強みもへったくれもあったもんじゃない。 そもそも、必死に「やりたいこと探し」だの、「好きな仕事探し」をしたところで、そんなもの見つかるわけがないじゃないか。 「やりたい!」とか、「好き!」という感情は、自分の意志とは関係なく、無意識に湧き立つモノ。「好きだ」と思った時に、「なぜ、好きなのか? どこが好きなのか?」を論理的に説明することほど難しいことはない。「ただなんとなく」――そんな答えしか出せない。だって、無意識に湧き立った感情で、実にフワフワしたものなのだ。 いわゆる、直感。そう、直感。直感に、あれこれ理由などない。 この人間の直感こそが、まさしく常識に囚われない、根源的かつ自由な思考であり、困難を乗り越えるパワーのトリガーになることを多くの人たちは忘れている。 20世紀中には不可能と考えられていた青い光が灯ったのも、ノーベル賞を取った先生たちの直感があってこそ。 そこで今回は、「直感」について、あれこれ考えてみようと思う。 直感で選んだ方が、最後の満足感は高い まず、直感が人の心理に及ぼす興味深い実験を紹介する。 バージニア大学のティム・ウィルソンらは、「直感と満足感」に関する調査を行っている。 この実験は、被験者たちに「自宅に飾るポスターを1枚選んでもらう」という、シンプルなもの。ポスターは5種類。モネ、ゴッホの2つの芸術作品と、動物の絵が描かれた3つの作品である。ちなみに、被験者たちは、「芸術のことなど、これっぽっちもわからない」人たちである。 最初に、被験者をAとBの2つのグループに分ける。 そして、Aグループの被験者には、「5つのポスターから、1枚、いいなと思ったものを選んでください」と指示を出した。つまり、直感で選んでもらうようにしたのである。 一方、Bグループには、「5つのポスターから、1枚選んでください。その際、その絵を選んだ理由を説明してください」と指示を出した。 その結果、Aグループでは、ほとんどの人が芸術作品を選んだのに対し、Bグループでは動物の絵を描いた絵を選んだ人が大半を占めた。 この選択の違いについて、ウィルソンらは次のように説明している。
「モネやゴッホの作品を選んだ理由を説明するのは、素人には難しい。だが、動物であれば、『カワイイ』とか、『野性的』など、何らかの選択の理由を説明することができる。実際、ゴッホを手に取った人も、選択理由を説明する段階でゴッホの絵を戻し、動物の絵に変える人が多くいた」。 さらに、被験者たちに、選んだ絵を自宅の壁に飾るよう指示を出した。そして、3カ月後。絵の満足度の調査を行ったのだ。すると…… 2つのグループで、満足度に明らかな違いが認められた。直感に従って絵を選んだAグループの被験者はほぼ全員が、「この絵を選んで良かった」と満足していたのに対し、論理的に選択を行ったBグループの被験者たちは、「この絵は趣味じゃないと気付いた」「毎日、この絵を見なきゃいけないことを悔やんでいる」など、絵に対する満足感が低かった。 どちらも個人の意志で絵を選択したにもかかわらず、直感だけに頼って選んだほうが満足度が高いことがわかったのである。 日本は、勘や直感に頼るのを嫌いがちだが…… また、新入社員を対象に行われたアメリカの調査でも、直感と満足感の興味深い関係性が示されている。 就職活動で会社を選ぶ際に、収入、昇進の機会など、その会社に入るメリット・デメリットを徹底分析したり、キャリアカウンセラーに頻繁に相談したり、キャリア会社が発表する企業ランキングなどを参考にした学生と、そういった客観的指標に頼ることなく、「この会社に入りたい!」と思った、まさしく直感で会社選びをした学生の仕事満足度を比較した。 その結果、後者の直感だけで決めた学生のほうが満足感が高い、という結果が得られたのである。 前者の学生のほうが年収が2割以上高かったにも関わらず、満足感が低く、多くの学生が、「ホントに自分の選択が正しかったのだろうか?」と、自分の選択に確信が持てないでいた。客観的データを用い、専門家の意見を参考に慎重に選んだにも関わらず、だ。 もちろんこれらの調査結果だけで、「論理的に考えるな!」などと言うつもりはない。だが、直感という人間の心理機能が、その人の内面に潜む持続する嗜好性から引き出され、腑に落ちる感覚をもたらす、極めて大切な感情であると解釈することは十分可能だ。 中村修二さんは直感に従った 「日本では勘や直感に頼るのを、どういうわけか嫌うところがある。理論を話したり理詰めに考える人を見ると、この人は大したものだということになってしまうことが多い。
確かに理詰めに説明されたりすると、こちらにそれを上回る理論でもない限りは納得せざるを得なくなり、この人は理論家だ、頭がいいという具合になってしまう。そういう意味では理論というのは確かにすごいものだと思うし、特に新理論を打ち立てる人は大したものだと思う。
しかし、だからといって、勘や直感を理論より下に置いてもいいのだろうか。勘に頼るからダメだと決めつけてもいいものだろうか」 これは中村修二さんが著作『考える力、やり抜く力 私の方法』(三笠書房)の中で綴っている文章である。 中村さんが、「青色発光ダイオードの開発に乗り出す!」と宣言し、その材料に窒化ガリウムを選択した時、同僚や上司たちの反応は、「アホと違うか?」という感じだった。それでも、中村さんは「自分にはこれしかない」という、自分の直感を信じたという。 そんな中村さんに、多額の研究開発費をボンと出した日亜化学工業の元小川社長(故人)は、晩年、次のように語っている。
「私は『チャンスを与えれば、必ず期待した結果が返ってくる』という自分の信条に従っただけだ」 そう。小川社長も直感を信じた。まだ何者でもない、一介の研究者だった中村さんに投資したのは、直感以外の何ものでもなかったのである。 直感――。ときに、心をキラキラ輝かせ、胸を激しく鼓動させる、この感情はいったい何? それは長年、心理学者たちの疑問だった。ところが最近、脳科学の研究の発達に伴い、だんだんとその正体がわかり始めている。直感は、「経験してきた過去に脳が一瞬で検索をかけ、その場に適した最もよいであろう選択に脳が導き出した答え」とされているのだ。 脳科学を研究している先生に、興味深い話を聞いたことがある。 人間の記憶の箱は2つあって、1つは「思い出すことができる記憶」。もう1つは、「思い出すことのできない記憶」の箱だ。 例えば、「子供のころ、父親に連れられて上野動物園のパンダを見に行き、母親が作ってくれたお弁当をおサルさん見ながら食べておいしかった」といった非日常的で、エキサイティングな経験は、「思い出すことができる記憶」の箱に記録される。 一方、両親とは毎日、顔を合わせ、母が作った食事を毎日食べているにも関わらず、“日常の1ページ”を思い出すのは容易ではない。だが、思い出せない=記録されていない わけじゃない。思い出せない記憶は「思い出せない記憶」として、確実に記憶の箱に刻まれる。 この思い出せない記憶こそが、人間の価値観を養うのだそうだ。 思い出せない記憶が生きる力を育む 私はこの思い出せない記憶が、人間の生きる力(=Sense Of Coherence)を育むと解釈している。 Sense Of Coherenceは、直訳すると首尾一貫感覚。つまり、腑に落ちるという知覚(perception)であり、感覚(sense)である。それは、自分の生活世界や人生に対する見方・向き合い方の確信。単なる思い付きや思い込みではなく、自分の生き方の土台である。 「経験してきた過去に脳が一瞬で検索をかけ、その場に適した最もよいであろう選択」である直感は、この「思い出せない記憶の箱」が開いた瞬間なんじゃないだろうか。 自分の中に潜む、価値観や生きる力。だからこそ、直感には漠然とした確信を持てる。 そして、その直感が、まだ手元にない、未来に向けられたものであるとき、私たちはそれを「夢」と呼ぶ。 中村さんは、窒素ガリウムで青い光を作る夢を見た。
小川社長は、中村さんがきっと何かやってくれるぞ!という夢を見た。 赤崎教授にも夢があった。「戦後の荒野をさまよう日本の産業に貢献したい」――。その夢があったからこそ、「実用化の見通しが全くない青色LEDこそ自分のやるべき仕事だ」と確信し、流行りものに流されずにやり続けることができた。 85歳の赤崎教授は記者会見で、「今後の目標は?」と聞かれ、 「窒化ガリウムにはまだまだポテンシャルがある。青色発光ダイオードとかレーザーダイオードはできましたけど、まだ十分可能性を生かしきれてない。だからやることいっぱいあるんです」と答えている。
今も尚、夢を追いかけている。なんてステキなんだろう。 夢――。 「夢」と言う言葉は、綺麗過ぎて、私自身は滅多に使うことがない。くすぐったいというか、なんというか。とにかく、私には夢と言う言葉を上手く自分に当てはめる自信がないのだ。 だが、未来に向けた直感=夢 と解釈すれば、私にも夢がある。あまりに幼稚で、「アホか!」と笑われそうで、絶対に公言できないけど、その“夢”が、今までも、そして現在も私の原動力になっていることは紛れもない事実だ。 「夢」が見つかったら、ひたすら具体的に動く なぜ、もっと夢を学生たちに、見させてあげられないのだろう? なぜ、将来の夢を語るべき若い人たちが、閉塞感を抱くような教育ばかりになってしまうのだろう? 彼らにも、夢を見る瞬間があるはずなのに。なぜ、「その気持ちを大切にしなさい」とオトナたちは言ってあげられないのだろう。 アレコレやっているうちに、「夢」ができることもあるだろうし、ふとした瞬間に夢が見つかることもある。中には、ボ〜っとしているうちに、はたと夢が現れた! なんて人もいるかもしれない。 どちらが先であっても、ちっとも構わない。大切なのはその瞬間を大切にし、「夢」が見つかったら、そのあとはひたすら具体的に動くことだ。 努力すること。勉強すること。考え続けること。失敗を恐れないこと。冒険をすること。孤立を恐れないこと。自分の直感を信じ、ひたすら頑張る。 それは決して楽なことではないかもしれない。しんどいことだってあるだろう。乗り越えなくちゃいけない壁に、逃げ出したくなることもあるに違いない。 でも、その起点となった直感を信じ、そのときのワクワクした気持ち、そのときの熱い気持ちを思い出せば、再び、頑張れる。 それでも折れそうになったときに、サッと背中を押したり、手を引っ張ってくれる他者がいれば、再び、踏ん張れることができる。 「自分ひとりでできたわけじゃない。支えてくれる人がいたからです」――。3人の先生たちも、そう語っていた。おそらく先生たちにも、折れそうになった経験があるんだと思う。 で、そうやって頑張っていると、直感はますます磨かれ、奇跡を起こす。“ひらめき”だ。 天野教授は、窒化ガリウムの結晶を作る炉の調子が悪くなったときに、「低温で確かめよう」とひらめいた。 「炉が壊れて良かったですね!」なんて、ノー天気なコメントをするキャスターがいたが、炉が壊れなくとも、何らかの出来事をきっかけに、天野教授は成功していたと思う。 先輩研究者の、「きれいな結晶をつくるには、汚したほうがいいことがある」と言う言葉を思いだしたのも、夜も昼も研究に没頭し、「思い出される記憶」と「思い出せない記憶」の箱に、たくさんのものが蓄積されていたからこそ。炉が壊れたのは、たまたまそれが、ひらめきのスイッチとなっただけだ。 偶然じゃなくて、必然。磨かれた直感がひらめき、奇跡を引き寄せたのである。 「なんとなく……」。そんな説明のつかない一瞬のひらめきに、実は大きな価値があることを、私たちはもっと認めたほうがいいのかもしれません。 このコラムについて
河合薫の新・リーダー術 上司と部下の力学 上司と部下が、職場でいい人間関係を築けるかどうか。それは、日常のコミュニケーションにかかっている。このコラムでは、上司の立場、部下の立場をふまえて、真のリーダーとは何かについて考えてみたい。
http://business.nikkeibp.co.jp/article/manage/20141010/272429/?ST=print |

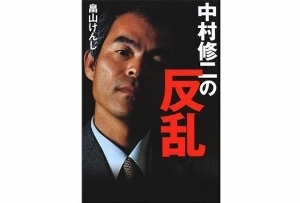
 スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。