04. 2014年10月10日 07:38:22
: jXbiWWJBCA
「ニッポン農業生き残りのヒント」
補助金ビジネスの甘いワナなぜ彼らは会社を去ったのか 2014年10月10日(金) 吉田 忠則 「1×2×3=6」とか「1+2+3=6」などと書く。小学校の算数のようなこの数式が、なにを意味するかご存じだろうか。 農林水産省が旗をふる「6次産業化」を示す方程式だ。農業を含め、きびしい状況にある1次産業が、2次産業の加工や、3次産業の販売と一緒になることで「化学反応」を起こし、息を吹き返すことを期待している。 6次産業化は「切り札」になれるのか 今回の見出しを「甘いワナ」としたのは、農業再生の切り札とされる6次産業化が想像ほど簡単ではないと思っているからだ。兼業農家の意義とその限界について考えた前回と同様、今回も「常識」を疑ってみたいと思う。 今回、登場するのは、ある大手食品メーカーと、地元ではそれなりに実績のある農業生産法人だ。両者が組んで、野菜を貯蔵し、加工するための大型施設を数年前につくった。6次産業化のパターンのひとつだ。いまでも続いているプロジェクトなので、施設のある場所や企業名はふせることにする。
収量と質を安定させるのが農業の課題
巨大施設をつくった理由は2つある。農業法人のほうは、天候にふり回されない経営を実現したいと思っていた。例えば、あまりに豊作だと値段が下がるから、作物の一部を畑に捨てることがある。これを処分せず、保管できれば、足りないときに需要にこたえることができる。大型の貯蔵・加工施設があれば、出荷を平準化できるはずだと考えた。
メーカー側は、中国など輸入作物が不人気になったため、国内で農産物を調達できるルートをほしがっていた。施設が稼働する前に取材したとき、こんな説明を受けた。「『あんたんとこ、まだ中国産使ってるの?』っていう電話が来るんです。国内調達の取り組みはしっかりしていませんでした。いま踏み出さないと、機会を逸してしまいます」。 事業費はおよそ10億円。大手メーカーが参加するこの事業に、農水省は補助金4億円を大盤振る舞いした。メーカーは5億円強を負担し、農業法人は数千万円を出した。6次産業化を象徴する、官民あげてのプロジェクトになった。 結論から言おう。食品メーカーと農業法人がこの事業にあてた担当者は、どちらもすでに会社を去った。2年続けて1億円を超す赤字を出し、さらに運営上の混乱もあって会社に居づらくなったのだ。メーカー側は後任をあてた。どうして、そんなことになったのか。
6次産業化は生産と加工、販売の連携がカギをにぎる
奇妙なのは、この農業法人を悪く言う声が農業界の一部に広まったことだ。「あの食品メーカーは組んだ相手が悪かったよね」と。一方で、当時の取材メモを開くと、農業法人の担当者のこんなセリフが出てくる。「大企業は農業に対し『だからおまえらは、だめなんだ』って、どうして上から目線なんでしょう」。
たしかに、1年目も2年目も施設はフル稼働しなかった。計画通りに作物が入荷されなかったからだ。いくら立派な施設をつくっても、設備が動かなければ利益は出ない。そこで食品メーカーの内部で「決められた数量が、きちんと納品されていない」という批判が高まった。そして、この噂が業界に広まった。 農業法人と大手メーカー、“夢幻”のコラボ 少なくとも1年目に関しては、真相は違った。当時、関係者はつぎのように打ち明けた。「販売のほうがまったくついてこなかった」。だから、農業法人が野菜を出荷しようとすると、「ちょっと待ってくれ」と断られることがあった。倉庫がいっぱいで入れる余地がなかったからだ。倉庫で腐らせた作物もあった。やむなく、せっかくつくった施設に出さず、ほかに回した分もあった。 作物を自らつくり、あるいはグループの農家から集めて出荷するのは当然、農業法人の役割だ。これに対し、売り先を開拓するのはメーカーの仕事だった。農業法人は当初、「ネームバリューのある大手がやったほうが、営業はうまくいく」と期待していた。 これが出足でつまずいた。しかも、食品メーカーが当初、見つけてきた先は、利幅の薄いところばかりだった。そのまま売れば原価割れだ。一方、農業法人がもともと自分で売っていた先はもっと利益の出る優良チェーンだったが、食品メーカーの営業担当は自ら探した売り先を優先しようとした。 施設に入れた作物を出荷する方法も、ぎくしゃくした。例えば、たとえ倉庫のなかに在庫があっても、新たに入荷した分を先に売り、在庫は加工などに回すべきときがある。鮮度を考えれば、そのとき高く売れるものを優先したほうがいいからだ。ところが、メーカー側は先に倉庫に入れた分から順番に売っていく方法にこだわり、相場をみて機動的に対応することはあまりなかった。 そうこうしているうちに、メーカー側で妙な不満が出始めた。「農業法人が、グループ農家からの買い取り価格に3、4割上乗せして出荷している」。根も葉もない噂で、農業法人の手数料はせいぜい数%しかなかった。メーカーが開拓した売り先で利益が出ないのは、農業法人が不当にサヤを抜き、仕入れコストが高いからと言いたかったのだろうか。 どろどろした話はまだまだあるが、今回は象徴的なエピソードにとどめておきたい。ちなみに、以上の話は時間をかけて複数に取材しており、とくに農業側のかたをもつつもりでインタビューしていたわけではない。 「工業のルールとは違う」「仕事を農家に教えないと」 だた、農業法人の担当者が会社を去る前に語ったつぎの言葉を思い出すと、はなばなしく宣伝された食農連携のプロジェクトの裏で、なにが起きていたのかを考え込まざるをえない。 「農業が変わらなくていいとは思っていませんよ。でも、まず農業がどういう仕組みで動いているのかを理解すべきではありませんか。工業製品でできあがったルールをそのまま当てはめれば、それで農業が変わるってことではないんじゃないですか。いきなり農業のシステムそのものを変えてくれって求めるのは、尊大ではありませんか」 かれが話したのは、農業と加工や販売業者が組むときの「契約」の難しさだ。当時の契約をかいつまんで言えば、作物をつくる面積と値段はおおよそ事前に決めておき、数量はかっちりとは決めない。収量はどうしても天候で左右されるからだ。本来なら、それをわかったうえで、販売と在庫、収量の情報をつき合わせて柔軟に対応すべきだが、両者はうまく連携できなかった。 こうして担当者はどちらも会社を離れた。その後、メーカー側の新しい担当に取材すると、しきりに強調した。「お互いに緊張感を持つべきです。仕事っていうのはこういうものだよっていうのを、農家さんに教えないといけない」「この事業の趣旨をきちんと理解してもらわないと」。やはり、問題は農業側にあると言っているようにしか聞こえない。 ここで農水省が6次産業化を進める動機を整理してみよう。食品産業の生産額は年に78兆円ある。これに対し、農業の生産額は約9分の1の8兆5000億円しかない。この数字を見ると、農業関係者はいちようにこう思う。「農業はじり貧なのに、なぜ食品産業はこんなに巨大なんだ。おかしいではないか」と。ひと昔前なら、「搾取」という言葉で説明したかもしれない。 食品78兆円、農業8.5兆円…利益のゆがみは直る? そこで、生産と加工と販売が結びつけば、食品産業が得ている巨額の(不当な?)利益を農業の現場に回すことができるかもしれない。利益の分配のゆがみを直せば、農業の衰退を食い止められるという発想が背景にある。 ではどうやって6次産業化を実現するのか。農家がコメや野菜の生産だけでなく、加工や販売も一手にこなせれば簡単だ。実際、そういう例もないことはないが、ほとんどは規模が小さすぎて、残念ながら「農業の再生」をかかげるには力不足。そこで「餅は餅屋」となる。生産と加工、販売のプロが直接手をにぎり、利益を分け合う仕組みをつくる。 今回のケースはその意味で、典型的な事例であり、関係者の多くが行方を注視していた。それがスタートダッシュで混乱を極めた理由はいくつかある。 まず、メーカーと農業法人との間で、必ずしもコミュニケーションが円滑に進んでいなかった。じつはメーカーの新しい担当者が「お互い緊張感を持つべきだ」と語ったのも一理ある。たとえ収量は天候次第でも、あらかじめ決めた目安をもとに、実際はどうなるかについて時々刻々情報を共有すべきだった。 そのためにも、両者の信頼関係が決定的に重要だった。ところが、ある時点でメーカー側はべつの有名な農業法人に立て直しを相談し、自分が組んだ農業法人に直接会わせてアドバイスを頼むということをやった。提携相手に対し、誠実なやり方だったのだろうか。
補助金に依存しないビジネスモデルが求められる
農業法人の側も、ある種の甘えがなかったとは言いきれない。「値段だけ決めて数量は決めず、できた分はすべて施設が引き取る」という手法は、あまりに農家にとって都合がいい。だが両者の出資額の差からすれば、収量が見込みを大幅に下回ればメーカー側は当然、べつの仕入れ先の確保に動く。そうならないための「緊張感」は感じられなかった。
だが、いちばん問題なのは、まるで「無から有を生み出す」ような事業計画だ。本来は、両者が小さなアライアンスから始めて少しずつ信頼関係を築き、つぎのステップに進むべきだった。 メーカー側の販路の開拓も同様だ。多くの業者が競い合う流通の世界に突然わって入っても、優良な売り先が簡単にみつかるはずがない。だが、売り先も信頼関係もないままに、巨大な箱だけ一気につくり、それで新しいビジネスモデルをつくれると期待した。そして、農水省の巨額の補助金が背中を押した。 形式と補助金より、信頼とノウハウ 結論に移ろう。農業再生の切り札として6次産業化を考えることじたいは間違ってはいない。だが、事業というのは本来、漸進的にノウハウを蓄積し、それがある「いき値」を突破したときに、つぎの飛躍を目指すべきものだろう。はやりに乗って形だけ生産と販売と加工が結びついても、うまくいくはずがない。 そんなことは重々分かっているはずの大手企業でも、なぜか農業となるとそうした過ちを犯す。もちろん農業界の側も、自分の身の丈を超えたビッグビジネスに期待することは禁物だ。 そして最後にひとつ。安易に補助金の誘惑に乗ってはいけないのだ。補助金が出るからといって、需要をシビアに見定めずに大きな施設をつくる。そして、施設が十分稼働せずに、資金繰りで行きづまる。そうなっても、もちろん農水省は責任をとってはくれない。農水省が6次産業化の旗をふるのは勝手だが、その風に吹かれ、将来性のある農業者が背伸びをして痛手を負うようなことはあってはならない。 このコラムについて
ニッポン農業生き残りのヒント TPP(環太平洋経済連携協定)交渉への参加が決まり、日本の農業の将来をめぐる論議がにわかに騒がしくなってきた。高齢化と放棄地の増大でバケツの底が抜けるような崩壊の危機に直面する一方、次代を担う新しい経営者が登場し、企業も参入の機会をうかがっている。農業はこのまま衰退してしまうのか。それとも再生できるのか。リスクとチャンスをともに抱える現場を取材し、生き残りのヒントをさぐる。
http://business.nikkeibp.co.jp/article/report/20141008/272288/?ST=print |
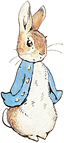
 スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。