http://www.asyura2.com/14/hasan90/msg/808.html
| Tweet |
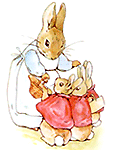
アベノミクスの「不協和音」を警戒、高まらない日銀緩和期待
http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPKCN0HW0NI20141007
2014年 10月 7日 18:19 JST
[東京 7日 ロイター] - アベノミクスの「不協和音」を市場は警戒し始めている。円安への警戒感をにじませる安倍晋三首相に対し、黒田東彦日銀総裁はメリットを強調するなど、当局者間で違いが目立ち始めているためだ。景気や物価動向の不透明感は強まってきているが、円安を加速させかねない日銀の追加緩和に対し、市場の期待感は以前ほど高まらなくなっている。
<要人発言に神経質な市場>
足元の円安が日本経済に与える影響については、エコノミストの間でも見方が分かれている。「正解」が見出しにくい問題であり、立場により意見が異なるのは否めない問題でもある。しかし、アベノミクスを担う政府・日銀当局者の間で、意見が異なり始めていることで、投資家は要人発言に神経質になっている。
日銀決定会合当日に異例の国会出席となった黒田総裁が7日、「一般論として、円安は輸出やグローバル企業の収益・設備投資にプラス」などと発言。これをきっかけに、同日午前の東京市場では、ドル/円が109円台に浮上、日経平均.N225も主力輸出株に買い戻しが入りプラス圏に浮上した。
しかしながら、安倍首相が同じく7日午後の参院予算委員会で、円安のデメリットについて、ガソリン・燃料費の上昇で家計や中小規模の企業に負担になるとの見解を示すと、一気に円高・株安が進行。ドル/円は108円半ばに下落、日経平均は100円以上のマイナスとなった。
安倍首相と黒田総裁だけでなく、甘利明経済再生担当相と麻生太郎財務相の間でも円安に関して意見の違いが目立ってきている。
麻生財務相は、10月1日開催の経済財政諮問会議で、1ドル=108・109円の為替水準について「リーマン・ショックの前でその水準だから、やっとそこまで戻っただけで、今が取り立てて円安であるというほどではない」と述べていたことが明らかになった。
一方、甘利担当相は同じ経済財政諮問会議後の記者会見で、「経済実態を反映していない過度の円高・円安あるいは急速すぎるレートの変動はその国の経済のプラスにはならない」と述べ、足元の円安に警戒感を示している。円安のレベルとスピードという観点の違いはあるものの、「温度差が感じられる」(国内証券)発言だ。
<海外投資家が敏感に反応>
こうした違いに敏感なのが海外投資家だ。「これまでアベノミクスはみなが同じ方向を向いて政策を進めてきた。しかし、ここにきて円安をめぐり意見が分かれるなど、不協和音が目立ち始めている。一部の海外投資家はこうしたベクトルの違いを感じ始めており、円安・株高の持続性を疑問視し始めている」(邦銀トレーダー)という。
ドル/円はここ2カ月間で、102円台から110円台に上昇。日経平均も1万4700円台から1万6300円台に上昇した。足元、108円台と1万5700円まで下落してきたが、3分の1押しにも至っていない水準であり、調整の範囲内ともいえる。
ただ、その円安・株高を主導したのはいつものように海外投資家である。IMM通貨先物(9月30日)での投機筋の円売り越しは12万枚と今年初めの水準まで拡大、8月第2週以降の海外投資家の日本株買い越しは2兆5000億円(現物と先物の合計)に達している。足元の相場調整は「海外投資家の売りによるものだろう。キャッシュが豊富な個人投資家は下値で買っている」とケイ・アセット代表の平野憲一氏は指摘する。
<安倍首相の調整手腕に期待>
ただ、こうした市場の反応を敏感に感じてか、黒田総裁の発言トーンが微妙に違ってきたとの見方もある。
黒田総裁は、7日の参院予算委員会で、円安のプラス効果を指摘しつつも「円安は非製造業の収益を押し下げる」と発言した。「円安デメリットへの言及は初めてではないか。決定会合後の会見でも円安のプラス面を強調することなく、水準や先行き、スピードについてのコメントを差し控えた。安倍首相の考えに配慮したのかもしれない」とSMBCフレンド証券・投資情報部チーフマーケットエコノミストの岩下真理氏はみる。
とはいえ、市場の日銀追加緩和期待は盛り上がらない。黒田総裁会見を経た7日夕方の市場でも日本株先物やドル/円は日中安値水準で推移したままだ。
大和証券・金融市場調査部シニアエコノミストの野口麻衣子氏は「黒田総裁の景気や物価に対する強気姿勢からみると今年度はおろか、来年度も追加緩和はないかもしれない。消費再増税が決まれば見た目上であっても、物価は上昇するので、消費者の物価観の動向をじっくりと見極めるのではないか」と話す。
円安に対する意見の違いは、「立場」の違いにも由来する。「マクロ経済を政策の対象とする日銀は、マクロ経済において円安がプラスであるとみれば、円安メリットを重視する。一方、地方選挙を控える政治家は、中小企業や個人を重視する発言になりやすい」(国内投信エコノミスト)。
SMBC日興証券シニアマーケットエコノミストの嶋津洋樹氏は「デフレ脱却、経済再生という目標に近づいていることで、立場の違いによる意見の相違が鮮明になってきたといえるだろう。いわゆる総論賛成・各論反対だ。こうした意見の違いをうまくまとめることができるかが、今後のアベノミクスのカギを握る」と指摘している。
(伊賀大記 編集:宮崎大)
 スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。