http://www.asyura2.com/14/hasan89/msg/831.html
| Tweet |
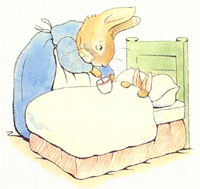
7月貿易収支は9640億円の赤字、輸出は3カ月ぶり増加=財務省
http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPKBN0GK00920140820
2014年 08月 20日 09:52 JST
[東京 20日 ロイター] - 財務省が20日に発表した7月貿易統計速報によると、貿易収支(原数値)は9640億円の赤字となった。輸出が3カ月ぶりにプラスに転じる一方で、輸入も2カ月連続で増加し、25カ月連続の赤字となった。
輸出は前年比3.9%増の6兆1886億円。自動車(8.1%増)、金属加工機械(35.7%増)、科学光学機器(9.8%増)などが増加した。
輸入は同2.3%増の7兆1526億円。2カ月連続で増加した。
原粗油(6.9%増)、液化天然ガス(7.4%増)、石油製品(23.3%増)などが増加した。
地域別では、米国向け輸出が前年比2.1%増で3カ月ぶりに増加。中国向け輸出は前年比2.6%増と16カ月連続で増加した。EU向けは同10.2%増と14カ月連続で増加した。
貿易赤字(季節調整値)は前月比4.1%減だった。
ロイターが民間調査機関を対象に行った調査では、予測中央値は7025億円の赤字。輸出は前年比3.8%増、輸入は同1.7%減だった。
市場では7月貿易収支について「輸出面での今後の焦点は欧州向けの動向だろう。今回は欧州向けが非常に伸びたが、ウクライナでの地政学的リスクの関係で欧州経済自体が悪くなってきている。欧州が低調になれば中国経済が悪影響を受け、ひいてはアジア経済にも影響が及びかねない」(ニッセイ基礎研究所シニアエコノミスト、上野剛志氏)との声が出ている。上野氏は、輸入面では原油価格の下落で前提条件が変わってきたとし、「輸入の縮小要因になる可能性があり、国内需要とのバランス次第とはいえ、一方的に貿易赤字が膨らむ様子ではない」と指摘している。
|
|
|
|
|
|
 スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。