06. 2014年7月02日 11:36:21
: nJF6kGWndY
改革はなされず実質賃金は下がり続けるのがメインシナリオということだ
http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPKBN0F704Y20140702
企業の物価見通しは1年後で+1.5%、5年後も日銀目標に届かず
2014年 07月 2日 11:18 JST
[東京 2日 ロイター] - 日銀が2日発表した6月調査の「企業の物価見通し」では、企業が想定す
る消費者物価(CPI)の前年比上昇率は平均で1年後がプラス1.5%となり、前回3月調査と同水 準となった。 3年後は1.6%上昇で前回比0.1%ポイント低下、5年後は1.7%上昇と前回比横ばいだった。 先行き上昇率を高めていくとの見方は維持されているものの、日銀が目標に掲げる2%には届いていな い。 企業の物価見通しは、日銀短観の調査項目として前回3月分から導入した。消費税率引き上げの影響を 除いたベースでの回答を求めており、2回目となった6月調査には前回とほぼ同様の1万0300社弱 が回答した。 <物価見通し、大企業低め・中小企業高め> 消費者物価見通しの構成比をみると、1年後では「プラス1%程度」を見込む企業が29%と最多で、 次いで「プラス2%程度」21%、「ゼロ%程度」18%の順となっている。前回と比べて1%上昇を 見込む企業の割合に変化はなかったが、2%上昇、ゼロ%の見通し割合がともに若干上昇した結果、平 均は前回調査と同水準の1.5%上昇となった。 大企業と中小企業に分けてみると、大企業が平均で1.1%(前回1.1%)上昇だったのに対し、中 小企業は1.7%(同1.7%)上昇と高めとなっている。これはグローバルな価格競争に直面してい る大企業が販売価格の下落圧力を受けやすい一方、中小企業は原材料価格や人手不足に伴う賃金上昇な どがより意識されやすいためとみられている。 3年後は平均が1.6%上昇と前回調査に比べて0.1%ポイント低下したが、「プラス1%程度」と 「ゼロ%程度」の構成比がそれぞれ1%ポイント上昇したことなどが影響した。もっとも、3年後と5 年後については「イメージなし」との回答が最多となるなど、日銀では「傾向をつかむには、少なくと も8四半期分のデータの蓄積が必要」(調査統計局)としている。 <販売価格見通し、3・5年後が小幅上昇> 同時に調査している自社製品・サービスの販売価格見通しは、現在の水準と比較して1年後1.1%( 前回1.1%)上昇、3年後1.9%(同1.8%)上昇、5年後2.3%(同2.1%)上昇となり 、前回よりも3、5年後が小幅上昇した。大企業非製造業が3、5年後ともに前回比で0.3%ポイン ト見通しを上昇させていることが影響したとみられる。 1万社規模で企業の物価見通しを調査するのは、世界的にも例がない。日銀では、2%の物価安定目標 を2年程度で達成するため、昨年4月に異次元緩和を導入しており、実現には企業や家計の期待の転換 が不可欠と位置づけている。今後も四半期ごとの短観でデータの蓄積を続け、日本の経済・物価動向の 分析や金融政策運営などに役立てる方針だ。 (伊藤純夫 編集:山川薫)
http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPKBN0F506U20140702
コラム:デフレ脱却で実質賃金は上昇するか=河野龍太郎氏
2014年 07月 2日 11:00 JST
河野龍太郎 BNPパリバ証券 経済調査本部長
[東京 2日] - かねて指摘している通り、日本の潜在成長率は0.3%程度まで低下している。労働 力一人当たりの潜在成長率は0.9%程度だが、女性の就業率上昇を勘案しても労働力が年率0.6% 減少するためである。ところが、2013年度の成長率は2.3%と、その8倍もの高い成長を達成し た。 高成長の主因は、日銀ファイナンスによる追加財政と消費増税前の駆け込み需要である。後者の効果は 反動減まで考慮すると差し引きゼロで、前者の追加財政についても、その本質は国債発行による「将来 所得の前借り」であって、新たな付加価値が生み出されているわけではない。つまり、潜在成長率が高 まったわけではないのだ。 潜在成長率が低迷する中で高成長となったため、需給ギャップが一気に改善し、日本経済の供給能力の 天井がさほど高くないことを、多くの人が認識し始めている。建設だけでなく、運送や小売といった労 働集約産業で人手不足を訴える企業が現れ始めたのはこのためだ。実質ベースで相当な円安なのに、実 質輸出の回復が遅れているのも、緩慢な海外経済の回復だけでなく、製造業が供給制約に近づいている ことも影響している。 このまま日銀ファイナンスによる追加財政を続ければ、15年半ばにも経済は完全雇用の閾値を超え、 賃金上昇を伴ったインフレ上昇が始まる。14年後半、円安効果の剥落でインフレ率はいったん1%前 後まで低下する可能性があるが、需給ギャップは着実に改善し、経済は徐々に完全雇用の領域に入って いく。そうした中で、日銀が金融緩和に踏み切るのだろうか。大いに疑問である。 すでに現在、財政政策、金融政策はフル回転となっている。スラック(余剰)はほとんどないため、こ れらの政策効果によって総需要に火が付けば、起こるのは価格上昇である。15年半ばを待たずして賃 金上昇を伴ったインフレ上昇が始まる可能性も否定できない。 では、賃金上昇が始まれば、家計部門の実質購買力が増し、実質消費も増えるのだろうか。残念ながら 、そう簡単に事は運ばない。名目賃金が上昇しても、インフレ率と同程度にとどまり、実質賃金はほと んど上昇しない。むしろ、マイナスの実質金利を背景に円安が進展すれば、インフレ率の上昇幅が大き くなり、実質賃金が低下する可能性もある。デフレから脱却すると、実質賃金も上昇すると考える人が 少なくないが、以下では、必ずしもそうはならないことを論じる。 <実質賃金は2000年代に7%減少> まず、一人当たり実質賃金の動向を見る。ここで論じる実質賃金は、残業代やボーナスなどを含んだ、 一人当たりの所得(現金給与総額)を消費者物価で実質化したものだ。 実質賃金の累積変化率は、80年代が16%、90年代は0.9%、2000年代はマイナス7%だっ た。90年代は豊かになれず、2000年代は貧しくなったというのが多くの人の実感だが、一人当た り実質賃金の動きはそれを裏付ける。 90年代以降の実質賃金の低迷は何によってもたらされたか。一人当たりの実質賃金の変化率は、1) 一人当たりの労働生産性上昇率、2)交易条件の変化率、3)労働分配率の変化率の3つに分解できる 。実質賃金の低迷を招いた最大の要因は労働生産性上昇率の鈍化だ。80年代に39.5ポイントだっ た寄与度は、90年代に10.9ポイント、2000年代には10.4ポイントへと大幅に低下した。 労働生産性上昇率が大幅に低下し、80年代の4分の1になったために、90年代以降の実質賃金が低 迷した。つまり、我々の働きぶりが以前に比べて悪くなったために、実質賃金が低迷したのである。た だし、重要な点だが、90年代に比べると2000年代の生産性上昇率の寄与度は悪化していない。こ のため、2000年代の実質賃金の悪化については、別の要因を探る必要があるが、この点は後述する 。 しかしなぜ、90年代に生産性上昇率が急低下したのか。80年代後半に始まった「時短」で労働時間 が短くなったこともあるが、それだけではない。一つはよく知られている通り、不良債権問題が影響し ており、金融部門が追い貸しを続け、一方で成長分野への貸し出し努力を怠った結果、低生産性部門に 経済資源が滞留し、生産性上昇率の著しい低下をもたらした。労働者に目を向けても、日本のすでに高 い実質賃金水準をより高めるには、新たな技術や環境に対応すべく人的資本を高め、生産性上昇率をよ り高める必要があったが、残念ながらそうはならなかった。 前述した通り、13年度の高い成長は日銀ファイナンスによる追加財政によるもので、生産性上昇率が 改善したわけではない。この政策を続けることで、経済が完全雇用に達し、名目賃金の上昇が始まって も、生産性上昇率のトレンドが高まらないのなら、実質賃金の上昇は持続しない。このことは、インフ レ率が高まっても、潜在成長率は低いままであることと対応している。デフレ脱却で名目賃金は上昇す るが、潜在成長率や生産性上昇率が改善しないため、実質賃金はほとんど上昇しないのである。 <2000年代の実質賃金を悪化させた交易条件> 2つ目の要因は、交易条件だ。結論を先に言うと、2000年代の実質賃金悪化の主犯は、交易条件の 悪化である。それによって、実質賃金は2000年代に9.9%も押し下げられた(90年代はマイナ ス6.7%)。 周知の通り、2000年代は、原油などコモディティの価格が大幅に上昇したが、それがコモディティ 産出国への大幅な所得移転をもたらし、日本の実質賃金を押し下げた。一般的に言えば、日本のように 、技術進歩の速い加工組立セクターに比較優位を持つ場合、輸出財の相対価格が低下するため、交易条 件がある程度悪化することは止むを得ない。 さらに、2000年代は新興国でブームが続き、その旺盛な需要によってコモディティ価格が大幅に上 昇、一次産品を輸入する日本は交易条件の悪化で実質国内総所得(GDI)が低迷し、実質賃金が減少 したのである。2000年代半ばは輸出が増え、実質国内総生産(GDP)は膨らんだが、海外への所 得の漏出で実質GDIの改善は限られていた。 あまり認識されていないが、2000年代に消費者物価は概ね横這いで推移し、GDPデフレーター( 名目GDP/実質GDP)は大幅に下落した。年間の下落ペースは、消費者物価がマイナス0.2%、 GDPデフレーターがマイナス1.2%。実は、この差が交易条件の悪化に他ならない。 やや専門的な話だが、GDPデフレーターは、消費者物価や企業物価などの物価統計とは多少性格が異 なる。「三面等価の法則」(生産・分配・支出の3つの側面から算出した額は等しくなる)から明らか なように、GDPデフレーターは名目GDPの代わりに名目GDIを用いて、「名目GDI/実質GD P」と表すこともでき、1単位当たりの財・サービスの生産で、どれだけの名目所得が得られたかを示 してもいる。 物価が下落しない場合でも、GDPデフレーターは低下するケースがあるが、それは、交易条件の悪化 で海外へ所得が漏出し、名目GDIが悪化するケースである。2000年代はまさにそのことが起こっ た。2000年代のGDPデフレーター低下の主因は、物価下落ではなく、交易条件の悪化だったので ある。 多くの人は、2000年代にデフレで貧しくなったと考えた。だから日銀を責め立て、そのことが現在 の「量的・質的金融緩和」の採用にもつながっている。貧しくなったのは事実だが、主因は交易条件の 悪化によって海外に所得が漏出し、実質賃金が減少したことであり、金融緩和では対応できない問題だ った。 さらに、当時は円安が資源高による交易条件の悪化を助長した。量的・質的金融緩和が採用された背景 には、円安誘導でデフレを解消する意図もあったと思われるが、適切な判断だったのか悩ましいところ である。 繰り返しになるが、労働生産性上昇率が改善しなければ、デフレから脱却し、名目賃金が上昇しても、 実質賃金は変わらない。筆者の基本シナリオは、デフレから脱却しても、潜在成長率にも労働生産性上 昇率にも大きな変化が現れないため、名目賃金上昇率は均してみればインフレ率と同程度にとどまり、 実質賃金はほとんど上昇しない(消費増税分は低下する)というものである。 ただ、リスクとして考えておかなければならないのは、交易条件の悪化で、実質賃金が低下する可能性 だ。昨今の地政学リスクを考えると、コモディティ価格が上昇し、交易条件の悪化で、2000年代ほ どではないにせよ、実質賃金が低下する恐れはある。つまり、輸入物価の上昇によって、名目賃金以上 にインフレ率が上昇する可能性がある。 中国、シリア、イラク、ウクライナ情勢など、ここにきて地政学上の問題が頻発しているのは偶然では ない。中国の経済的、軍事的な膨張や米国が世界の警察官としての役割を低下させていることに伴い、 世界的に軍事的なパワーバランスが大きく崩れていることが背景にある。今後、地政学リスクが高まる ことはあっても、低下することは期待できそうにない。 また、日本では、デフレ脱却後、財政への配慮から、金融抑圧政策の採用は不可避だと考えているが、 それが生み出すマイナスの実質金利によって、円安が進む可能性があり、そのことも交易条件の悪化を 助長する。 むろん、円安が実質輸出の改善をもたらすのなら、実質賃金は必ずしも低下しないが、相当程度、スラ ックが解消していることを考えると、実質輸出はあまり増えず、円安は実質賃金の低下要因となるので はないだろうか。 <グローバリゼーションの影響> 3つ目の要因は、労働分配率だ。これが、交易条件の悪化に次いで、2000年代の実質賃金を押し下 げる要因だった。90年代には2.6%押し下げ、2000年代には6.3%も押し下げている。80 年代も12%押し下げたが、それは70年代に労働分配率が大きく上昇したことの調整だった。 70年代はオイルショックによって、産油国に所得移転が進んだにもかかわらず、実質賃金の高い伸び が維持され、労働分配率が大幅に上昇、企業収益は低迷が続いた。2000年代も同様で、90年代は バブル崩壊の後、企業の収益性が大幅に低迷したが、十分に実質賃金が調整されなかったため、調整が 2000年代までずれ込んだ。 では、今後、どうなるのか。国内を見れば、経済が完全雇用に到達することで、労働者側のバーゲニン グパワーが多少改善し、労働分配率への低下圧力が和らぐ可能性はある。人材確保のため、非正規雇用 を正規雇用にシフトする動きも広がっていくと思われるが、そのこと自体は労働分配率の低下圧力を和 らげる。 ただし、国外に目を向けると、グローバリゼーションの進展が引き続き労働分配率の低下圧力となる。 過去20年間、とりわけ中国などの新興国が世界経済に組み込まれる過程で生じた要素価格均等化圧力 は、先進国の労働分配率を低下させる強い要因だったと思われる。様々な要因が労働分配率に影響する ため判断は難しいが、広い意味で付加価値を生み出すための現在の生産技術は労働分配率を低下させる 傾向にあると考える。 中国が中所得国に仲間入りし、賃金水準が上昇してきたことなどから、従来に比べれば圧力は和らいで はいる。しかし、グローバリゼーションの進展は今後も続き、要素価格均等化圧力を通じ、労働分配率 の低下を助長すると見られる。世界金融危機の後、先進各国で、資本分配率の上昇に対する政治的な反 発が広がっているが、今のところ生じていることはグローバリゼーションのスピードを減速させる程度 で、ディ・グローバリゼーションへ急転換させるほどのムーブメントは生じていない。 大企業に賃上げを要請した安倍政権にしても、成長戦略では法人税の実効税率引き下げ、ホワイトカラ ーエグゼンプションの一部導入など、企業の資本収益率の上昇を促す施策を打ち出している。資本収益 率を高める政策が必ずしも資本分配率を高め、労働分配率を低下させるとは言えないが、少なくとも労 働分配率を高める政策ではないだろう。この点は、改めて論じたい。 *河野龍太郎氏は、BNPパリバ証券の経済調査本部長・チーフエコノミスト。横浜国立大学経済学部 卒業後、住友銀行(現三井住友銀行)に入行し、大和投資顧問(現大和住銀投信投資顧問)や第一生命 経済研究所を経て、2000年より現職。 *本稿は、ロイター日本語ニュースサイトの外国為替フォーラムに掲載されたものです。(here) |
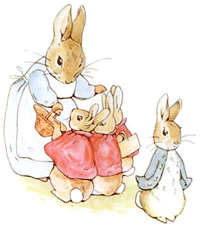
 スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。 スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。