02. 2014�N5��27�� 10:21:01
: nJF6kGWndY
QE�������I�Ȍo�ςւ̌��ʂ������iMF���ʂ����ɏ������j�Ƃ����͓̂��{�̂悤�ɒZ���[�������ł���A�ߎ��Ƃ��ẮA�����Ԉ���Ă͂��Ȃ������ҁi���@�Ȃǁj��ʂ������ʂ͓��R�傫�����A���������̈����������ʂ����邩��A���S�ɂO�Ƃ͓��R�����Ȃ� �������A�������Ƃ̂悤�ȍ����x�o���A�i�C�h�����ʂ������Ƃ����炩 �d�v�Ȃ̂́A�A���E�i�C�@�Ƃ�����1�r�b�g�̒萫�I�c�_�͎~�߂āA��ʓI�ɁA����̃R�X�g�p�t�H�[�}���X�𑪒肵�A�v�Z���A�����邱�Ƃ�
http://ikedanobuo.livedoor.biz/archives/51899125.html�@
�o��
�A�x�m�~�N�X�ł������̂́u���̖�v����������
���t���h�̌��c�����A�o���}�L�h�̓��䑏����ᔻ���Ă���B���䎁�͕����I�ɂ͐��������A���c���͑S�ʓI�ɊԈ���Ă���B
���䎁�́u�l�c�G�ꎁ�⌴�c���̂����}���f��=�t���~���O�E���f�����������Ƃ���A�������Ƃō�����������オ���Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ����A�����������ۂ͋N�����Ă��Ȃ��v�Ƃ����B����͔ނ̂����Ă���}�̒ʂ萳�����B�ʓI�ɘa�ʼn~���ɂȂ��Ėf�Ս�����������Ƃ���MF���f���ɂ��l�c���̎咣���A���̋t�ɂȂ����B
�Ƃ��낪���c���́u���������Ōi�C���h���������̂Ȃ�A�����ɋ��Z���ɘa���Ȃ���Ό��ʂ͂Ȃ��v�Ƃ����B����Ȃ�A�������Ƃ̌��ʂ͂������̂ł͂Ȃ����B�ނ́u���ݍH����⌚�ݘJ���҂̒������オ���Ă���Ƃ������Ƃ́A���̕���ł͂��͂⎑�ނ�l�͗]���Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃł���v�Ƃ������A�l��s���ɂȂ����̂͌������Ƃ̂��������B ���܋N�����Ă���l��s���̌����́A������F�߂�悤�ɁA�����͂̕s���ɂ������M���b�v�̏k���ł���B���ɐk�Ђ̌���ő�K�͂ȕ����H���������Ă��邱�Ƃ��P���J���҂̎������^�C�g�ɂ��A�T�[�r�X�Ƃ̒������オ���Ă���B�悭���������A��������͂������̂��B �����A���c���̂������Z����̌��ʂȂ���͉̂����������Ă��炸�A�u���ؓI�ȕ��@�ɂ���Č���������̂́A���Ȃ蕡�G�Ȏd���ɂȂ�v�Ƃ������������Ă��邾�����B�������オ���������́A�ނ��F�߂�悤�Ɍ����H���̐l��s���Ɖ~���ƃG�l���M�[���i�̏㏸�ŁA���Z����̌��ʂł͂Ȃ��B �v����ɓ��䎁���w�E����悤�ɁA�A�x�m�~�N�X�ł������̂́u���̖�v�̌������Ƃ����Ȃ̂��B����͓���������F���ł���B������i�C���悭���邱�Ƃ������ړI�Ȃ�A�ی��Ȃ��o���}�L���������B������ꂪ�����̕���p���Ƃ��Ȃ����Ƃ͌��c���̂����ʂ肾���A����͂����Ȃ������Ƃ����_���ɂ͂Ȃ�Ȃ��B
http://shuchi.php.co.jp/article/1916?p=1�@
�m�A�x�m�~�N�X���̖�n���ɖ\���ꂽ�������Ƃ̌��ʁk�P�l2014�N05��10�� ���J
���c�@�ׁi����c��w�����j�s�wVoice�x2014�N6�������t
���{�̂f�c�o�͌��������������Ă��������Ă���@�P�C���Y����̑O����Ă���
�@�A�x�m�~�N�X�̑��̖�A�@���I�ȍ�������̌��ʂ͏������A�Ƌc�_���邱�Ƃɂ͔���������悤���i�{��2014�N5�����A���䑏�u���ɖ\���ꂽ�G�R�m�~�X�g�́w���U�x�v�j�B�������A���ꂪ�����ł���ȏ�A�����咣���邵���Ȃ��B
�@�Ȃ������ł���ƍl���邱�Ƃ��ł���̂��A���������O�ɁA�A�x�m�~�N�X�̑��Ƒ�O�̖�ɂ��Ă��ȒP�ɏ����Ă��������B�����ɂ��ẮA�{��2013�N5�����uTPP���Q�����S����{�v�A2014�N3�����u�@�l�Ō��ł�TPP�ŕ���������{�v�ł����������Ƃ����A���̌�̐i�W������̂ŁA�lj��I�ɐ������������Ƃ�����B
�@���̖�A��_�ȋ��Z�ɘa�ɂ��ẮA�������邱�Ƃ��m���ɂȂ��Ĉȗ��A�ٗp�A���Y�A����A���ׂĂ̌o�ώw�W���D�]���A����ҕ����㏸����1�����ăf�t���E�p���m���ɂȂ��Ă���̂�����A���ʂ̂��邱�Ƃ͖��炩�ł���B
�@�����オ���Ĉꕔ�̋��������������Ă��邾�����Ƃ����ᔻ�����������A4��1���ɔ��\���ꂽ����Z�ςł��A�������Ƃ̋Ƌ����f�i�u�ǂ��v-�u�����v�j���A22�N�Ԃ�Ƀv���X�ƂȂ����B�������Ɗg��̉��b���Ă��錚�ƁA�����̎�Ƃ������ĕ��ς�����Ă��v���X�ɂȂ��Ă���B����͐��Œ��̌i�C�ƂȂ���������t���̌i�C�ł��Ȃ������i������A�����Ȃ��i�C�Ƃ���ꂽ�j�B���Z�ɘa�̌��ʂ�������Ƃɂ܂Ŕg�y���Ă���Ƃ������Ƃł���B
�@��O�̖�ɂ��ẮA�����헪���K���ɘa�A�f�ՁE�����̎��R���A�ٗp�̑��i�Ȃ���ʂ����邪�A����̎Y�Ƃɕ⏕����t���Ă����܂��͂����Ȃ��A�Ǝ��͏������B�K���ɘa�͏d�v�ł��邪�A�Ȃ��Ȃ��傫�Ȍ��ʂ�������̂����o���͓̂���B�����̊��p�ATPP�A�@�l�Ō��łȂǂ͑傫�Ȍ��ʂ�����Ǝ��͍l���Ă��邪�A���{�����̕����Ɍ������Đi��ł����悤�ł���B
�@���̖�A�@���I�ȍ�������ɂ��Ă͌��ʂ��������Ə������B���̌�̐i�W������ƁA���̐�����������ɖ��炩�ɂȂ��Ă���B����́A���ݍH����オ���Ă��邱�Ƃł���B
�@�P�C���Y�́A���Ǝ҂�����̂�������A�����@���Ă܂����߂�悤�Ȏd���ł��A���Ƃ����Ă������}�V���Ƃ������B�^���͂��Ȃ����A�ꗝ�͂���B���Ǝ҂ɂ���������z���Đ����ł���悤�ɂ�����A���������ق����悢��������Ȃ��i�������A�L�v�Ȍ������Ƃ�����Ȃ�����悢�j�B
�@�������A���ݍH����⌚�ݘJ���҂̒������オ���Ă���Ƃ������Ƃ́A���̕���ł͂��͂⎑�ނ�l�͗]���Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃł���B�P�C���Y������s�Ȃ��O����Ă���B
�Ȃ��������Ƃ̌��ʂ͏������̂�
�@���ݍH����㏸���Ă���Ƃ������Ƃ́A�����l���Ă����ȏ�Ɍ��ʂ��������Ȃ��Ă���Ƃ������Ƃ��B�ł́A�Ȃ����͌������Ƃ̌��ʂ��������Əq�ׂĂ����̂��B���̗��R�͈ȉ��̂Ƃ���ł���B
�@�܂����ɁA�������Ƃ�����Ƃ́A���ݍ����o���Č��ݓ���������Ƃ������Ƃ�����A��������Ȃ��ꍇ���������オ���āA���Ԃ̓����������̂��Ă��܂�����ł���B����̓N���E�f�B���O�E�A�E�g�Ƃ�������̂ł���B
�@���ɁA�������オ��Ύ��{���������ĉ~���ɂȂ�B�~���オ��ΗA�o���������āA�������Ƃ̎h�����ʂ����E���邩��ł���B����̓}���f�����t���~���O�E���f���Ƃ�������̂̌��ʂł���B�Ȃ��A�N���E�f�B���O�E�A�E�g�A�}���f�����t���~���O�E���f���̈Ӗ�����Ƃ���́A�u���������Ōi�C���h���������̂Ȃ�A�����ɋ��Z���ɘa���Ȃ���Ό��ʂ͂Ȃ��A�������͌��E�����v�Ƃ������Ƃł���B
�@��O�ɁA���ʂ̏������������Ƃ�������ꂾ�������͕n�����Ȃ�Ƃ������Ƃ�����A�������B�����{��k�Ђ̕����H���ŋ���Ȗh����⍂��̒c�n�����Ă��邪�A�����ɏZ�ސl�͂��Ȃ��Ƃ��������܂�邾�낤�B������ЊQ�������Ă��A�����ׂ��l�����Ȃ���Ζ��ʂȓ����Ƃ������ƂɂȂ�B
�@��l�ɁA���̎؋���������Ώ����ɂ͑��ł��K�v�ɂȂ�킯������A���̂��߂ɂ��ܒ��~���ď����̑��łɔ�����̂ŏ������B���̐����ɑ��đ����̓ǎ҂́A����Ȃ��Ƃ͔��I���Ǝv���邾�낤���A�N���⍂��ɂȂ����Ƃ��̈�Ô�A����Ȃǂɂ��čl����A����قǔ��I�ł��Ȃ��B���̎؋������z�ɂȂ�A���Ƃ͏����̎Љ�ۏ�x�o��d���Ȃ��̂ŁA�����ŏ������邵���Ȃ��A���Ȃ킿�A���~���邵���Ȃ��Ǝv���Ă�����͑������낤�B
�@��܂́A���łɏq�ׂ��������Ƃ����Ԃ̌��ݓ����������o���Ă��܂����ʂł���B���݃N���E�f�B���O�E�A�E�g�ƌĂԂ��Ƃɂ��悤�B���{�ɂ́A�����{�����A�����������̂̏����A�����I�����s�b�N�Ƃ����A���Ȃ���Ȃ�Ȃ����ݍH��������B��Вn��̐��������߂����߂ɂ́A�Z��Ƌ��`�␅�Y���H���Ȃǂ̍Č����������K�v���B��������������˔\���R��Ȃ��悤�ɂ��邽�߂ɂ́A�n���������ꍞ�܂Ȃ��悤�Ɏ�����Ր��ǂň͂܂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�j�R������菜�����߂ɂ͋���ȃN���[��������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����I�����s�b�N�̂��߂ɂ͎a�V�ȃf�U�C���̐V�������Z��A���̑��̉��A��ʃC���t���̒lj��I�Ȍ��݂����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�v����ɁA����Ȍ��ݎ��Ƃ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@�������s�v�s�}�̍H��������ΒP�����オ���āA���̕K�v�Ȍ��ݍH���̖W���ɂȂ�B���̖�̍����g�吭��͍čl���ׂ��Ƃ��ł���B�����ԍ�̍����}���V�����ŏ㉺�����ɕK�v�ȃp�C�v��ʂ������J���Ă��Ȃ��������́A���m�����ɎV��������H���Ŏ��҂��o�����́A�����͓��{�̌��Ƃ̐l�ނ����ꂵ�Ă��邱�Ƃ�����������̂ł���B���{�́A�������Ƃ��팸������O���l�J���͂ɂ���Č������Ƃ����悤�ƍl���Ă���炵���B�������̌ٗp�����邽�߂Ȃ瑽���̔�����ɂ��Ӗ������邪�A�����l�̂��߂ɂ�������K�v�͂Ȃ��Ǝ��͎v���B
�@���{�x�o�Ōٗp������Ȃ�A�ł��邩�������̎x�o�ɕ�Ȃ��ق����]�܂����B����̎x�o�ɌX���A�����̃{�g���l�b�N�����܂�ĉ��i���㏸���A�ٗp�g����ʂ�j�Q����B
�@���łȂ���A���������s�v�c�Ɏv���Ă��邱�Ƃ�����B�������Ƃ̍D���ȃG�R�m�~�X�g�͗���I�ɉE�h�ł�����������B�E�h�Ȃ�������Ƃ��h�q��z�ɗ͂�����ׂ��ł͂Ȃ����B�h�q���i�̐����͍L�͂ȎY�Ƃ������A���q���ł���Ί�]�҂������B�{�g���l�b�N���C�ɂ��邱�ƂȂ��A�i�C�h�����ʂ���͂����B�������Ƃɍ���𓊂���A�h�q��̑��z������Ȃ�B
�������y�[�W>>�@���̕s���v�������O���čl����ׂ�
���������������Ă�GDP�͑����Ă��Ȃ�
�@�ȏ�A�����܂Ŗ{����26�s�����ă��f���̎��،��ʂɂ��ď��������Ƃ́A���Ƃ��ʓ|�Ȃ��Ƃ����ē������ʂ�����M�p���Ă���A�Ƃ����Ă��邾���ł���B����ł͖{���̓ǎ҂ɂ͔[�����������Ȃ����낤�B�܂��A�����A�����������Z����ɖ{���Ɍ��ʂ�����̂Ȃ�A����قǖʓ|�Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ă����ʂ̂��邱�Ƃ��������邱�Ƃ͂ł���͂����Ƃ����c�_�͂��肤��B
�@�����ŁA�ȏ�q�ׂ����Ƃ��O���t�ɂ���Ď��������B
�@�}1�́A1980�N����95�N�܂ł̎���GDP�A�������������i���I�Œ莑�{�`���j�A�}�l�^���[�x�[�X�����������̂ł���B�}�Ŗ��炩�Ȃ��Ƃ́A�����ɐL�тĂ���GDP��90�N��ȍ~�A����Ă��邱�Ƃł���B�}�l�^���[�x�[�X��GDP�̒�ɐ旧���A�L�т��݂��Ă���B��������A�}�l�^���[�x�[�X�̒��GDP��̌�����������Ȃ��Ǝ��������B����A�������Ƃ�1987�N�ɂ�GDP�������グ���ƌ����Ȃ����Ƃ��Ȃ����A���̌�A�L�т�����Ă���ɂ�������炸GDP�͐L�тĂ���B����ɁA91�N�㔼����������Ƃ��������Ă���ɂ�������炸GDP�͑������Ă��Ȃ��B
�@�}2�́A1996�N����2014�N�܂ł̃f�[�^�����������̂ł���B2001�N����06�N�܂Ń}�l�^���[�x�[�X�����傷��ɂ���������GDP�������Ă���B�������A2006�N����}�l�^���[�x�[�X���������Ă���ɂ�������炸�AGDP����������̂͂��ꂩ��2�N�����Ă���ł���B2�N�̃��O�͒������邩��A�}�l�^���[�x�[�X��GDP�̊W�͂��̊��Ԃł͋����Ȃ��Ƃ�������B�������A�A�x�m�~�N�X���n�܂��Ă���́A�}�l�^���[�x�[�X�̐L�т�GDP�̐L�т������炵���悤�Ɍ�����B
�@���������̓O���t�̊��Ԓ��A�قڌp���I�ɒቺ���Ă���Ȃ��ŁAGDP�͉��Ƃ��L�тĂ���B�������A1998�N��GDP�̒ቺ�ƌ������Ƃ̒ቺ�͘A�����Ă���B�܂��A�A�x�m�~�N�X���n�܂��Ă���ł́A�������Ƃ̊g��ƌi�C�͘A�����Ă���B
�@�ȏ�̂悤�ɁA�O���t�������Ƃ���ł́A�}�l�^���[�x�[�X��GDP�ƘA�����Ă�����Ԃ��A����������GDP�ƘA�����Ă�����Ԃ��������B���̂��Ƃ��A�����Ȏ��ؕ��͂ɂ���āA���Z����͌��ʂ����邪�A��������̌��ʂ͏������Ƃ������_�ɂȂ闝�R�ł��낤�B
�@���Ȃ݂Ɍ���������GDP�̊W�𑊊W���Ƃ������v�I�ړx�i1�ł���Ί��S�ɘA�����A�[���ł���ΊW���Ȃ��A�}�C�i�X1�ł���Ί��S�ɋt�ɘA�����Ă���j�Ō���ƁA1980�`95�N�ł�0.849�A1996�`2013�N�ł̓}�C�i�X0.886�ƂȂ�B���W�����}�C�i�X�ł���Ƃ́A���������������������GDP�͑��傷��W������Ƃ������Ƃł���B����͐}2������Γ��R�̌��ʂł��낤�B���������������Ă�GDP�͑����Ă��邩��ł���B
�@����A�}�l�^���[�x�[�X��GDP�̑��W���́A1980�`95�N�ł�0.991�A1996�`2013�N�ł�0.766�ƂȂ�B����͊W������Ƃ������Ƃł���B
�������y�[�W>>�@2006�N�ɂ����֊W�͌�����
2006�N�ɂ����֊W�͌�����
�@�ȏ�̐����ł́A���͕����ƍ������Z����̊W�͏d�����Ă��Ȃ��B���̗��R�́A�P�͗^����ꂽ�����̐����A�������Z���d�v�Ȃ̂́A����ɂ���ĕ������オ�邱�Ƃł͂Ȃ��āA����GDP���㏸���邱�Ƃł��邩�炾�B�������Z���������グ�邾���Ȃ�A����Ȑ��������K�v�͂Ȃ��B
�@1990�N��ȍ~�̐����_���ŕ������グ�邱�Ƃ��ۑ�ƂȂ����̂́A�f�t����GDP�����������Ă��邱�ƂŁA���̍������d�v�ڕW�ƂȂ�������ł���B���̌��ʁA�������Z����ŕ������グ�A����ɂ���Ď���GDP���オ�邩�ǂ��������ƂȂ����B�������A���Z����̌��ʂ́A���������łȂ��A�בփ��[�g�⎑�Y���i���A�����̌o�H��H���Ď���GDP�ɉe����^������̂ł���B���̂悤�Ȉ��ʂ̘A�����~�X�����A�˂邱�Ƃɂ́A�{���͂ӂ��킵���}�̂ł͂Ȃ����낤�i����ɊS�̂�����͑O�q�̌��c�Ȃǂ̘_����ǂ�ł������������j�B�v����ɁA�����͒��ԖڕW�ŁA����GDP�ƌٗp�̊g�傪�ŏI�ڕW�ł���B�������Z����Ɍ��ʂ����邩�́A����GDP�������グ�邩�ǂ����Ŕ��f���ׂ��ł���B
�@�������A�P�����w�E���Ă��������B�}3�͎s��W�҂̗\�z�C���t�����i�u���[�N�E�C�[�u���E�C���t�����ƌĂ����́j�ƃ}�l�^���[�x�[�X�����������̂ł���B�\�z�C���t�����ƃ}�l�^���[�x�[�X�̃O���t���������āA�u�\�z�C���t�����ƃ}�l�^���[�x�[�X��2009�N�ȍ~�ł͊W�������Ă��A����ȑO�ł͊W���Ȃ��ł͂Ȃ����v�Ƃ����c�_������B�������A2006�N�̃}�l�^���[�x�[�X�̏k���ƂƂ��ɁA�\�z�����㏸�����ቺ���Ă���B����������̂��A�}�l�^���[�x�[�X�Ɨ\�z�C���t�����̊W�������W���𐄌v���āA���ꂩ�瓾����\�z�C���t�������v���b�g�������ł���B����ɂ��A�}�l�^���[�x�[�X�̏k�����\�z�C���t�������������������Ƃ͖��炩�ł���B
�@���Ȃ݂ɁA�\�z�C���t�����ƃ}�l�^���[�x�[�X�̑��W���́A2004�N����08�N8���i���[�}���E�V���b�N���O�܂Łj�ł́A0.627�ƂȂ�B�}����3�J���̃��O������悤�Ȃ̂ŁA���̃��O��t�����0.801�ƍ����Ȃ�B
�@�������A���[�}���E�V���b�N�̂Ƃ��̃C���t�����̒ቺ�̓}�l�^���[�x�[�X�ł͐����ł��Ȃ��B�v����ɁA�\�z�C���t�����ƃ}�l�^���[�x�[�X�͊W�����邪�A���̊W���̓��[�}���E�V���b�N�̑O�ƌ�Ƃł͕ς���Ă��܂����Ƃ������Ƃł���B�������A���{�̎����A�o�������Ō���4������������ȂǁA���ꂾ���̑傫�ȏo����������Ες���Ă��܂��͎̂d�����Ȃ��ł͂Ȃ����B
�S�[�X�g�^�E�����Љ�ۏ�Ɩh�q���
�@����������GDP�������グ�Ȃ��A�܂��͂��̌��ʂ͏������ƍl������5�̗��R���������B�������ɁA���x�������ɂ͌������Ƃ̌��ʂ͑傫���������낤�B���H��S��������A�H�ꂪ���āA�d�����ł���B�l�тƂ͂����œ����̂�����A������������B�Ƃ��낪�A���̌�A�������Ƃ����Ă��l�����Ȃ��悤�ɂȂ��Ă��܂����B�T�^�I�Ȃ̂́A�k�БΉ��̌������Ƃł���B��_�E�W�H��k�Ђʼn�œI�Ȕ�Q�������c��ɉߑ�ȏ��Ǝ{�݂����������A�e�i���g�����炸�S�[�X�g�^�E���ɂȂ��Ă���B�_�˂ł��S�[�X�g�^�E���ɂȂ�Ȃ�A��Q�������k�̒��X�������Ȃ邾�낤�B�{���Ɍ��ʓI�Ȑk�Е�������l���Ȃ���Ȃ�Ȃ��i�ڂ����́A���c�ׁw�k�Е��� �\�Ԃ̍\�}�x�V���ЁA2012�N���Q�Ƃ��ꂽ���j�B
�@1980�N��ȍ~�̃f�[�^�����S�Ɍ��Ă��A��������̌��ʂ��������Ȃ��Ă���͖̂��炩�ł���A���Z�����ł��A�i�C�͎h�������Ƃ킩�����B�ł���Ȃ�A�i�C��͋��Z����𒆐S�ɍl���A��������͐Ŏ��̐�����l�����āA�����I�ɕK�v�Ȏx�o�ɐU������邱�Ƃ��̐S�ł���B���{�́A�Љ�ۏ�x�o�̊g�傾���łȂ��A�h�q��̑�����K�v�ɂȂ�\���������B�S�[�X�g�^�E��������]�T�͂Ȃ��B
���ҏЉ�
���c�@�ׁi�͂炾�E�₷���j
����c��w�����o�ϊw������
1950�N�A�����s���܂�B1974�N�A������w�_�w�����B�o�ϊ�撡�A�����ȁA��a�����Ȃǂ��o�āA���ݑ���c��w�����o�ϊw�������B�������c��Ȍ������������B
�����ɁA�w���{���̌����x�i���{�o�ϐV���Ё^��29����X�R��܁j�A�w�s�o�o�ł���ɋ����Ȃ���{�x�i�o�g�o�������^�������c�Ƃ̋����j�ق������B
�֘A�L��
• �u�D�ʐ�v�l�v�ŋ������{�����߂�
�������l�i�]�_�ƁA���{���c���ʌږ�j
• �m�A�x�m�~�N�X�n��[�̊i�����������ŋ��̂R�{�ڂ̖�k�P�l
�|�X�r���i�c��`�m��w�����j
http://shuchi.php.co.jp/article/1877�@
�m���{�i�C�̍s���n ���ɖ\���ꂽ�G�R�m�~�X�g�́u���U�v�k1�l2014�N04��10�� ���J
�s�wVoice�x2014�N�T�������t�\�u���Z����v�Ɓu��������v���Ƃ��ɏd�����Ă����o�ς͍Đ�����@
�u15���~�K�́v�̌o�ς̊R�@����@���@�i���s��w�����j
�@�ϋɓI�ȋ��Z����A�@���I�ȍ�������Ɛ����헪�̎O�{�̖��Ȃ�A�x�m�~�N�X�́u���ʁv�Ƃ��Ă��܁A�f�t���E�p�������ɐi�݂���B�����A�����A���Ɨ���|�Y�������̊e�w�W�͊ԈႢ�Ȃ��A�傫�����P���Ă���B
�@�������A����ł��u�����v����͒������Ƃ����̂�����̓��{�o�ς��B���Ƃ��A2013�N��10������12�����̎���GDP�̐�������0.2���Ƃ�������̊W�҂̊��҂�啝�ɗ��鐅���������B�������u�J���҂̕��ϋ��^�v�i�������^���z�j��1990�N�̒����J�n�ȍ~�A�u�Œᐅ���v���X�V�����B�����܂���Ȃ�u�f�t���E�p��������v�Ƃ͉��l����Ƃ��f��ł��ʏ��낤�B
�@�������A����ȂȂ��ŏ���ł����ł����B�����3�����܂Ŏ��s����Ă���10���~���̕�\�Z��5.5���~�ɏk�������B����ɓ����\�Z�̕ϓ��A�����đ��łɂ��8���~�K�͂̒��ړI�Ȏ��v�k�ތ��ʂ����Ă���ƁA�s��11���~���x�́u�o�ς̊R�����v�k�ށv���ł�������B����ɂ���ɁA3���܂ł́u�삯���ݎ��v�v�̉e������������ƁA�g�[�^���Łu15���~�K�́v�i�I�j�̌o�ς̊R���\�������̂ł���B
�@�ȏ�ɉ����āA�C�O�̓����Ƃ����łɃA�x�m�~�N�X�Ɂu�O���āv���Ă���̂ł͂Ȃ����Ƃ������ʂ��͊e���ŕ���n�߂Ă���B�����ĉ��B�⒆�������N�_�Ƃ��郊�[�}���E�V���b�N���̌o�ϊ�@��������댯���猜�O����Ă���B
�@�܂�A���܂킪���̌o�ς́A�f�t���s���̊������������Ȃ��A����ő��łƕ�\�Z�팸�Ƃ����_�u���p���`�ɂ��15���~�K�͂̌o�ς̊R�ɎN�����Ɠ����ɁA�C�O�����Ƃ̓��{�����茜�O�Ɛ��E�I�Ȍo�ϊ�@�̃��X�N�ɎN����Ă���̂ł���B
�u�������������_�v�͑Ó����H
�@���̐[���ȁu���{�o�ς̊�@�v�����z���邽�߂ɂ́A�A�x�m�~�N�X���u�ő�Ɍ��ʓI�v�ɐi�߂邱�ƁA���Ȃ킿�A���A���A��O�̖���u�œK�v�Ȃ������őg�ݍ��킹�A�ʊ��Ɏˊт����Ƃ��K�v���B�����Ă���ȁu�œK�v���l���邤���ŕK�v�Ȃ̂��A�v�����݂����ς�p�����u��Â������I�ȋc�_�v���B���Ă͖{�e�ł́A����ȗ����I�c�_�ɍv�����邱�Ƃ���}���A����܂łɎ咣����Ă����o�ςɊւ����ʓI���������������グ�A�����܂ł��u��w���̓k�v�u��w�ҁv�̗���ɂĂ������q�ϓI�Ɍ��������Ǝv���B
�@�܂��A�f�t���E�p���߂���c�_�̂Ȃ��Œ����_������Ă����̂��A���������A���Ȃ킿���̖�̗L�������߂���c�_�ł���B���Ƃ��A���Z������d������u���t���h�v�ƌĂ��l�тƂ̑�\�I�_�q�ł���l�c�G�ꎁ�́A��N�o�ł����w�A�x�m�~�N�X��TPP���n����{�x�i�u�k�Ёj�ʼn��L�̂悤�Ɏ咣���Ă�����B
�@�u���{�ɂ�����o�ϊw�̊ԈႢ�́A�����ƁA�����A�W���[�i���X�g�������A�Â��o�ϊw���w���ƁA��������V�����m���ɍX�V����Ă��Ȃ����Ƃɂ��N�����Ă���Ǝv���܂��B����܂ŁA���{�̑ǎ��߂Ă����l�����́A�w�s�����͍������������Ȃ��x�Ƃ����̂̃P�C���Y�o�ϊw��������Ă��܂����B�������P�C���Y�͈̑�Ȍo�ϊw�҂ł����A�w�s�����ɂ͍������������Ȃ��x�Ƃ����̂͌Œ葊�ꐧ�̎���ɂ͐������Ă��A�ϓ����ꐧ�ł͓��Ă͂܂�܂���v�B
�@�܂�l�c���́A�u�ŐV�̗��_�Ɋ�Â��A���o�̌��ʂ͂��܂�M�p���Ă͂Ȃ�Ȃ��v�Ǝ咣���Ă���̂����A�c�O�Ȃ��炱�̎咣�͍����̓��{�ɂ́u���Ă͂܂�Ȃ��v�^�`���Z�����B�ȉ��A���̗��R��������悤�B
�@�܂��A���̕l�c���̎咣�́A�}���f���E�t���~���O���f���i�ȉ��AMF���f���j�Ƃ����o�ϊw�̗L���ȗ��_�Ɋ�Â��Ă���B���̃��f���͊Ȍ��ɏq�ׂ�ƁA�ϓ����ꐧ�ł͎��̂悤�Ȉ��ʃv���Z�X�ŁA����������������邱�Ƃ��咣����B����͂��Ȃ킿�u�����o���������s�ɂ������̏㏸���C�O���{�̗������ʉݍ����A�o�����ƗA�������ɂ����o���ʂ̌��E�v�Ƃ������̂��B
�@�������c�O�Ȃ���A���̈��ʃv���Z�X�̊̂ł���u�����o���������s�ɂ������̏㏸�v�Ƃ������i�K�ڂ̉��肪�A���܂̓��{�̌����Ɓu�����v���Ă���̂����ؓI�ɖ��炩�Ȃ̂ł���B
�@�}�P�������������������B���̐}�����m�Ɏ����Ă���悤�ɁA���{���f�t���ɓ˓����Ĉȍ~�A�����s�z�����������ŋ������㏸���Ă���ǂ��납�A���̐^�t�ɒቺ���Ă���B
�@����́A�f�t�����ł͎������v���Ⴍ�A���A���Z�ɘa�����i�߂��Ă���ł́A���{���ǂꂾ�����s���Ă������͏㏸���Ȃ��Ƃ��������āu���R�v�̌��ۂȂ̂����AMF���f���͂��́u���R�v���l�����Ă��Ȃ��̂ł���B
�@�ނ��A���̂��Ƃ�MF���f�����̂��̂̌����w�E������̂ł͂Ȃ����A���Ȃ��Ƃ��A���܂̓��{�ɂ́u�K�p�ł��Ȃ��v���Ƃ������Ă���B
�@�Ȃ��A�{����ł����e�������Ă�����ѓc�הV�����A�M�҂Ƃ̌��J���_�̂Ȃ���MF���_���u���݂̓��{�o�ςɋ�����p���Ă���Ƃ͍l���Â炢�v�Ɩ������Ă����邵�A�������{���ɑ�����e���Ă����錴�c�����܂��wWEDGE�x�i2014�N3�����j��MF���f���ɂ��ĊT�����������ŁA�u���Z�ɘa���s�Ȃ��Ă���̂ŁA�����͈���v���Ă��邱�Ƃ��q�ׁAMF���f�������܂̓��{�ɕK�������Ó����Ȃ����Ƃ��������Ă���B
�@�܂�l�c����MF���f���ɏ���������������̖����_�́A�ނ̌��t�����Ȃ當���ǂ���u�V�����m���ɍX�V����Ă��Ȃ����Ɓv�ɋN�����Ă���^�`���Z���Ȃ̂ł���B���̓_�ɂ��āA�l�c���A�Ȃ�тɌ����Ȃ�ǎҏ��Z�́A���������f����邾�낤���H
���Ƃ̎v�����݂͌�����
�@�������A�uMF���f���͐������A���������̌i�C�h�����ʂ͂Ȃ��v�Ƃ������Ƃ̎v�����݂͌������B��ɏЉ�����c���́A��L�Ɠ������e�ɂāA�u1990�N�ȍ~�A���{�x�o�̑���Ōi�C�h������s���Ă����Ƃ��v�ɂ́AMF���f���̉e���ŁA�������Ƃɂ����ʂ́u�قƂ�ǂȂ������v�ƒf�����Ă���B
�@���������ۂ̃f�[�^������A���̌��c���̋L�q�����炩�Ɏ����Ɓu�����v���Ă��邱�Ƃ͖������B���ɁA��ɐ}�P�Ŏ������悤�ɁA���c���̂����u1990�N��v�ɂ����Ă��A�u�����s�z�̑����ɔ��������̏㏸�v�Ƃ���MF���f�����\�z������ʂ͌����Ă��Ȃ��B
�@����͐�Ɏw�E�����Ƃ��肾���A�����ʼn����Đ}�Q�������������������B����́A���c�����u���{�x�o�̌��ʂ͂قƂ�ǂȂ������v�ƒf���Ă���u1990�N��v�ɂ�����A����GDP�Ɛ��{�n�̌��ݓ����z�̐��ڂ��B�����̂悤�ɁA���{�n�����z���E���オ��ŐL�тĂ��邤���͖���GDP���L�сA���̌����ǖʂł͖���GDP���������Ă����B
�@�����āA���҂̈�v�x�𑊊W���i�v���X�P�̏ꍇ�Ɋ��S���ւ��Ӗ�����ړx�j�Ŋm�F����ƁA���Ƀv���X0.82�Ƃ������ɍ��������ł������B
�@�����������ʂɂȂ������R�́A���c�����g���q�ׂĂ���u�������Ƃ́A���ꎩ�̂̌i�C�h�����ʂƁA�����������グ�A�~���㏸������i�C�}�����ʂ����v�Ƃ���������������ł���B���Ȃ킿�A�}�P�Ɏ����ꂽ�悤�Ɂu�����������グ�A�~���㏸������i�C�}�����ʁv�͌����ɂ͑��݂��āu���炸�v�A���������āu�i�������Ɓj���ꎩ�̂̌i�C�h�����ʁv�������������䂦�Ȃ̂��A�Ɛ����ł��悤�B
�@�܂�A�u��������̌��ʂ͏������v�Ƃ������c���́u�f��I�����v�́u���v�ł���A���A���̌��͌��c���{�l�̘_���Ő����\�ł���A�Ƃ����\��������悤�ɕM�҂ɂ͎v����̂ł��邪�\�\���c���A�����Č����Ȃ�ǎҏ��Z�͂������������ɂȂ�̂��낤���H
���k�Q�l�ɂÂ���
���͊��Ԃ͓K�����H
�@���̂悤�ɕl�c���⌴�c�����_������̖���߂���u�������������_�v���A���Ȃ��Ƃ����܂̓��{�ɂ͓��Ă͂܂�Ȃ��^�`�����݂��Ă���킯�����A����ŁA�ނ炪�������낦�Ď咣����u���Z�ɘa�̌o�ό��ʁv�ɂ��Ă͂ǂ����낤���H
�@�܂��M�҂̌������q�ׂ�Ȃ�A���Z�ɘa�̌o�ώh�����ʂ͊m���ɑ��݂�����Ɗm�M���Ă���B������������Ƃ����āA���Z�ɘa�̌��ʂ��u�ߑ�]���v����悤�Ȃ��Ƃ������Ă͂Ȃ�Ȃ��B���ܕK�v�Ȃ̂́A�R�{�̖�́u�K�ȁv�o�����X�����炾�B
�@�����ōĂѕl�c���ƌ��c���A�����āA�����╛���ق̊�c�K�v�j���ɂ��o�d�����������ƂƂ��悤�B�ނ�͂R�l�̕Ғ��҂Ƃ��āw���t�������{�o�ς�������x�i�����o�ώЁj�Ƃ������Ђ����Ă�����̂����A�ނ�͂��̏��Ђɂċ��Z���f�t���E�p�̗v�ł��邱�Ƃ��������Ă���B���̂Ȃ��ŏd�v�O���t�̂P�Ƃ��ēo�ꂷ��̂��}�R�Ɏ������O���t�ł���i���̐}���쐬������c���ɓ]�ڂ�\���o���Ƃ���A��������Ȃ������̂ŁA�����ł͂��̃C���[�W���������}���f�ڂ���j�B�����̓}�l�^���[�x�[�X�i�ȉ�MB�F���₪��������ʉݗʁj�̑ΐ��ł���A�c�����u�\�z�C���t�����v�̎ړx���B�\�z�C���t�����Ƃ́A�s��W�҂����ɂ��u�����ǂꂭ�炢�C���t���ɂȂ�̂��H�v�Ƃ����\�z�ŁA���ꂪ�オ��Ύ����Ɛl�тƂ̓����͊g�債�A�f�t���E�p�Ɍq�����Ă����ƍl�����Ă���B���̏��Ђł͂��̃O���t�́uMB�����N�ԑ���������ƁA���̊��Ԃ̕��ϓI�ȗ\�z�C���t�����͏㏸���邱�Ƃ������Ă���v�Ɖ������Ă���B�܂�A���m�ɁuMB���\�z�C���t�����v�Ƃ����u���ʊW�v�����݂��邱�Ƃ��A���̃O���t���u�����v�Ƃ��āu�f��v���Ă�����킯�ł���B
�@�������ɁA���̃O���t�Ɋ�Â��咣�ɂ͐����͂�����悤�Ɍ�����B�������A���̃O���t�́u2009�`2012�N�v�̌���I�Ȋ��Ԃ̂��̂ł���B�M�҂͂��̃O���t��ڂɂ����Ƃ��A�u����ɒ������Ԃ����ƁA���҂̊W�͂ǂ��Ȃ̂��H�v�Ɗ������B
�@���ẮA�����5�N�O��2004�N���獡���܂ł́A��蒷�����Ԃ́A���ϐ��̊W���m�F�����̂��}�S�ł���B
�@���̐}������ƁA�������ɁA���̏��Ђ����グ�Ă���u2009�`2012�N�v�̊��ԁA���ϐ��͋������ւ��Ă���B���������́u���O�v�܂ł�5�N�Ԃł́A����ȊW�͂܂����������Ȃ��i���[�}���E�V���b�N�Ƃ�������v���̉e����������2004�`2008�N�����ɒ��ڂ��Ă��A��͂�A���҂̂������ɖ��m�ȊW�͌����Ȃ��j�B
�@�Ƃ�킯�A�����2006�N��MB��啝�ɒቺ�����Ă���̂����A����ɂ���ė\�z�C���t�����͑傫���ቺ���Ă͂��Ȃ��B���̂��Ƃɂ��āA��c���͂��߁A�Ғ��҂̂R���͂ǂ�������̂��낤�H�@�����A��c���͐�ɏЉ���}�R�̃O���t��������������ŁA�uMB��������������c�i���j�c�\�z�C���t����������������v�Ɩ������Ă��邪�A���̐����������Ȃ�2006�N��MB�̑啝�Ȓቺ���\�z�C���t�����ɑ傫�ȃC���p�N�g�������炷�͂��ł���B
�@���̓_�ɂ��āA�����uMB�̕ω��̉e���ɂ͂˂Ɏ��Ԓx��i�^�C���E���O�j������A���������āA2006�N�̈������ߍ�̉e���͂����ɂ͐����Ȃ������v�Ƃ�����|�̋c�_��ڂɂ���B���������������Ȃ�A�Ȃ��A2009�N��MB�����̂Ƃ��ɂ͂��̃^�C���E���O�����������i���邢�͔��N���x�̃��O�Łj�A�����ɗ\�z�C���t�����͌��サ���Ɗ�c���́u�����ł����v�̂��낤�B�܂�A���O�Ƃ���������s���悭�p������p���Ȃ������肷�邱�Ƃ́A�������ł���̂��낤���H
�@������ɂ��Ă��M�҂́A�u�}�S�̉E�����̃f�[�^�������g���Đ}�R������A�����MB���\�z�C���t�����̈��ʊW�̏؋��Ƃ��Ę_����v�Ƃ�����c���̃A�v���[�`�̓K�����A�������ɂ��Ă̗����I�����I�������A���ЂƂ����f���������Ǝv���B
�������y�[�W>>�@���Z�ɘa�u�����v�ł̓f�t���E�p�͊��҂ł��Ȃ�
���Z�ɘa�u�����v�ł̓f�t���E�p�͊��҂ł��Ȃ�
�@�Ƃ͂����A���Ɉȏ�̕M�҂̎w�E�������ł��AMB���\�z�C���t�����ɋy�ڂ��e���������ɔ�������̂ł͂Ȃ��B�������A���Z�ɘa���f�t���E�p�ɋy�ڂ��e���́AMB���\�z�C���t�����Ƃ������ʊW�����łȂ��A�u���Y���ʁv�u�ב��ʁv�Ȃǂ��܂��܂ȉe�����l������B�������l����A�f�t�����ɂ����Ă�MB�̑������f�t���E�p�Ɋ�^���Ă���\���͏\���ɂ���B�����A���c���͐�Ɉ��p�����wWEDGE�x�̌��e�ŁA�u2001�`2006�N�v�ɂ͎���GDP��MB�Ƃ̂������Ɂu�v���X�v�̑��֊W��������O���t�������A������A���Z�ɘa�̌o�ό��ʂ̏؋��f�[�^�Ƃ��ďЉ�Ă���B
�@�������M�҂͍ĂсA�u����ɒ������ԁv�i�f�t���ɓ˓�����1998�N�ȍ~�j���Ƃ�A���A�f�t���E�p�ɂ����ĉ������d�v�ȃf�t���[�^�i�����A��1�j��MB�Ƃ̊W�͂��Ă݂��Ƃ���A���c���̎咣�Ƃ͋t�̌X�������݂��邱�Ƃ����炩�ƂȂ����B
�@�}�T�������������������BMB�̑������f�t���E�p���ʂ����̂Ȃ�AMB��������f�t���[�^�i�����j����������͂��Ȃ̂����A���������X���͂܂����������Ȃ��B�Ƃ��������ނ���A�����̂悤��MB�͊�{�I�Ɋg�債�Ă������ŁA�f�t���[�^�͂����Ђ�����Ɍ������Ă���̂����ԂȂ̂��i���W���̓}�C�i�X0.75�A��2�j�B�Ȃ��A����GDP�ɒ��ڂ���A���c�����G����ŕ\�������ꕔ���Ԃł͂�������MB�̓v���X�̑��ւ������Ă���悤�Ɍ����Ȃ����Ȃ����A98�N�ȍ~�̑S�̂̌X���͂�͂�A�}�C�i�X�̑��ւł��邱�Ƃ͖������i���W���̓}�C�i�X0.45�j�B
�@�܂�ȏ�̃f�[�^�́A�uMB�����Ƃ������Z�ɘa�ɂ��f�t���E�p���ʁv�Ȃǂ͂܂����������Ă��Ȃ����Ƃ������Ă���̂ł���B
�i��1�F������������GDP�́A�f�t�����[�������ĕ�����������u�㏸�v���鐔�l�ł��邽�߁A�f�t���E�p�̐[������c������ɂ̓f�t���[�^���d�v�ƂȂ�j
�i��2�F�O�̂��߂ɐ\���Y����ƁA���̌��ʂ͂ǂ�ȁg�^�C���E���O�h��z�肵�Ă������s�\���j
�f�[�^��ǂޒm���ƗǐS��₤
�@�{�e�`���ŋ��������悤�ɁA���{�o�ς͂��܁A�����ǂ���́u��@�v�ɒ��ʂ��Ă���B�����͉��Ƃ��Ăł����̊�@�����z���˂Ȃ�Ȃ��B
�@�{�e�Ŏ��グ���l�c���A���c���A��c���́A���̊�@�����z���邽�߂ɂ́u���Z������d�����A����������y�����ׂ����v�ƁA���ځE�Ԑڂɂ��܂��܂ɌJ��Ԃ��咣���Ă���ꂽ���X�ł���B�������A�ނ炪�������������𐳓������邽�߂Ɋ��p���Ă����f�[�^�◝�_�̂Ȃ��ɂ́A�u�Ȋw�I�Ó����v�����݂��Ă��Ȃ����̂��܂܂�Ă���u�^�`�v���\�\������荹������Ă���Ȋw�_�����Ɠ��l�Ɂ\�\�{�e�̌����疾�m�Ɏ�����Ă��܂����B
�@�����ł��̂R���̍����̉e���͂̋��傳�Ɋӂ݂�A���̌��،��ʂ͂���߂ďd��ȋA���������Ă���B����͂��Ȃ킿�A�u���Z������d�����A����������y������v�Ƃ����R���̌o�ϊw�I�ԓx�������A�f�t���E�p�̋���ȏ�Q�ƂȂ��Ă���\���ł���B�����Ă���Ɠ����ɁA����́u��_�v�ł͂Ȃ��A�u�����̌o�ρv���������Ȃ�������Ƌ��Z�̓K���ȃo�����X���ċᖡ����K�v���𖾂炩�ɂ��Ă���B
�@������ɂ��Ă��\�\�{�e�Ŏ��グ���R���i���邢�͂R����i�삷��_�҂̊F���ܕ��j����́A�M�҂��w�E������L�̊e��^�O�ɑ���u�����I�Ȏ҂Ȃ�ΒN�����[�������邲�����v���i���ꂪ�\�ł��邩����ɂ����āj���ЂƂ����f���������Ǝv���B����͂��łɌo�ϊw�̗��_��̋c�_�ł͂Ȃ��B�f�[�^��ǂޒm���ƗǐS�̖��ł���B�]�ނ炭�͂��������ǎ�����c�_��ʂ��āA�o�ς��߂���i�G�R�m�~�X�g�������܂߂��������ނ́j�����̔F�������x�����A�L���ȍ����o�ς����ۂɎ������Ă����ߖ������A�S����F�O�������Ǝv���B�@
����@���i�ӂ����E���Ƃ��j
���s��w�����E���t���[�Q�^
1968�N�A�ޗnj����܂�B���s��w��w�@�H�w�����ȏC����A���������A�����H�Ƒ�w�����Ȃǂ��o�āA���E�B���͍��y�v��_�A���������_�A�y�؍H�w�B�Љ�I�W�����}�����ɂāA���{�w�p�U����܂Ȃǎ�ܑ����B�ߒ��ɁA�w����n�k�y���K�N�G�C�N�z�]�f�[�x�i�����Ёj���Ȃǂ���B
�֘A�L��
• �A�����J���A�x�m�~�N�X�ɖ������闝�R�k�P�l
��䍎�l�i���ۊ����w�q�������j
• �@�l�Ō��łƂs�o�o�ŕ���������{�k1�l
���c�@�ׁi����c��w�����j
• �K������Ă���u����n�k�v�ɔ�����
����@���@�i���s��w�����E���t���[�Q�^�j
________________________________________
���f�ڎ��Љ
2014�N5����
���V�A�ɂ��N���~�A�����́A�������������̂��낤���B�m�`�s�n�������̓��������ɑ��āA�h�q���͂�����������A���������̐��ق�����ق畷�����邪�A�ǂ������������Ă���B�������̑��͓��W�́A�u�E�N���C�i��@��v�̐��E���ɂ�ŁA�u���I�̖\�����~�߂�v�B�����P�����́u���ɐ��E�����̖{�i�I�ȑ�ϓ����n�܂����v�Ƃ��A���j�̕K�R�Ƃ��āu���ɉ��v������Ɛ����B�����`�����́A�I�o�}�哝�̂̎��Ȃ���O�����v�[�`���哝�̂̃N���~�A�ւ̐N�����������Ƃ��A�q�b�g���[�̑䓪���������E�B���\���哝�̂Ɣ�r���Ă݂����B�������v���́u���������V�A�̃N���~�A������͂Ƃ��āA��t�����ɋ����𑗂荞�݁A�������ی�𗝗R�ɐ�̂��n�߂鋰�ꂪ����v�ƌx����炷�B�܂��A���{�����ɂ��ׂ��́A�T�[�r�X�f�Ջ��肪���Ƃő�p�������ɓۂݍ��܂��̂ł͂Ȃ����A�Ƃ������Ƃ��B����v���́A�u���V�A���N���~�A����������ȒP�ɑ�p�������ɋz������Ă��܂��v�ƁA��p�̑�w�����̒k�b���Љ���B�n�����ꎁ�ƌ��P�Ԏ��̑Βk�ł́A�����ꒆ���͊؍��𖡕��ɒu���A�k���N��ғ�����̂ł͂Ȃ����ƓǂށB�g����`���т����I�́A�N���~�A�����ɑ��鍑�ێЉ�̔��������Ȃ���Վ�ἁX�Ǝ��̈����l���Ă���B
�����W�́u�_���E���{�i�C�̍s���v�B�u�V�E�A�x�m�~�N�X�v�������c���������́A�u�f�t���E�p�v�u�\�����v�v�u�����ĕ��z�v�Ȃǂ̃L�[���[�h�������A�u���Ƃ��Ă̌ւ�v�����߂����߂Ɍo�ϐ����̕K�v������������B�܂��A���t���[�Q�^�̓��䑏���́A�u��������̌��ʂ͏������v�Ƃ����G�R�m�~�X�g�ɑ��Ė��w���Ř_������������B����ŁA��ƌo�c�̌����m��s�������쒆�莟�Y���ƈ����b�s���́A�Βk�œ��{�̎Y�ƊE�̃C�m�x�[�V�����Ɩ����ɂ��ēO�ꓢ�_�����B
�����}�̖�c���q������ƍ��s���c������ɁA�����玁���a�荞���k����c�_�����M�����B�}�O���̂����̓�����A�������p����W�c�I���q���A�����Q�q�܂ł��ӌ����������B
���j�}���K�w�e���}�G�E���}�G�x�Ńu���C�N�������}�U�L�}������́A�u���ϐl�v���F�߂��Đ��������[�}�ւ̈�������B�u�Ⴂ���������Ƃ����j�́A�����̓o�J���Ƃ����Ă���悤�Ȃ��́v�u�l�Ԃ͋����Ă��ē�����O�v�c�c�A���{�l�ւ̎h���I�ȃ��b�Z�[�W�Ɏv�킸���Ă��܂��B���ЁA����ǂ��B
|
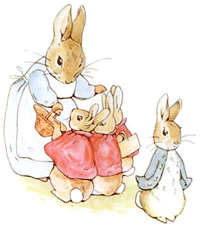
 �X�p�����[���̒����猩���o�����߂Ƀ��[���̃^�C�g���ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B
�X�p�����[���̒����猩���o�����߂Ƀ��[���̃^�C�g���ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B