01. 2014年4月22日 09:44:30
: niiL5nr8dQ
>年功賃金の一因は高い教育費負担http://business.nikkeibp.co.jp/article/opinion/20140418/263158/?ST=print
「記者の眼」
高収入×専業主婦の方が高学歴の子供が育つのか?「ウォール街のご意見番」に、子育ての悩みをぶつけてみた 2014年4月21日(月) 武田 安恵 4月11日、筆者はブラックストーン・アドバイザリー・パートナーズ副会長であるバイロン・ウィーン氏の小規模ミーティングに出席する機会に恵まれた。 バイロン・ウィーン氏は「ウォール街のご意見番」ともいえる大御所だ。長年モルガン・スタンレーのストラテジストを務め、2005年にヘッジファンドのピークス・キャピタル・マネジメントへ移籍、2013年から資産26兆円を運用する資産運用会社、ブラックストーンの副会長を務めている。 彼が有名なのは、1986年から30年近く毎年「世界10大びっくり予想」を出していること。ここでの「びっくり」とは、「平均的な投資家は3分の1程度の確率でしか起こらないと考えているが、ウィーン氏が2分の1の確率で起こると考えていること」と定義されている。 突拍子も無いシナリオも多いため、的中率はそれほど高くない。だが毎年何かが必ず当たるため、毎年年初になると「びっくり予想」は業界内で話題を集める。2013年は、日本株の大幅上昇や1ドル=100円台を予想し、それを見事に的中させた。彼は今年も日本株に対して強気で、「年末に日経平均は大幅に上昇し、1万8000円台になるだろう」「為替は1ドル=120円となる」などと予想している。 所得格差は教育格差 ミーティングでは、2014年のびっくり予想の解説や、ウィーン氏がそう考える根拠を一通り聞いたわけだが、それについては別の機会に譲ろう。彼のマーケット予測はもちろん興味深かったが、私はそれ以上にミーティングの後半で彼が「格差問題」について触れたことに興味を持った。 ウィーン氏は、米国で今最も問題となっていることの一つに「格差の拡大」を挙げた。IMF(国際通貨基金)の調査によれば、米国の人口の上位10%の所得層が米国全体の所得に占める割合は1980年代に30%だったが、足元では48%にまで増えた。ピュー研究所が実施した世論調査によれば、65%の米国民が「ここ10年間で格差は拡大した」と答えているという。 ウィーン氏は、その要因をいくつか挙げた。まず指摘したのが、新興国などの経済発展により国際競争が激しくなった結果、企業が経営の合理化を進め、賃金や雇用を削減したこと。そして、数学的な能力が及ぼす影響にも言及した。 米国は教育にお金をかけている割には、学生の数学の力が世界平均を下回っている。高収入の仕事は数学的能力を要するものが多いが、世の中を数学的なセンスで認識できる人が減っているというのだ。 論点の一つひとつを私なりに整理していくうえで感じたのは、「子供の学力を高めることがより収入の高い仕事に就く可能性を広げる。そしてその積み重ねが経済成長につながる」ということだ。 またウィーン氏は「家族やコミュニティーといった存在が子供にとって大きな助けになる」とも語っていた。まっとうな考えであり、ごくごく当たり前のことである。でも現実に格差が拡大しているということは、これらの「当たり前のこと」を実現するためのハードルが高くなっている、すなわちそれだけ社会構造や価値観が変わっているということでもある。 現にウィーン氏は、米国の未婚女性の出産率がここ30年の間に18%から41%に上昇していることを挙げた。「家計を維持しながら子供を導き意欲を起こさせるための時間を見つけるのは気の遠くなるようなこと」と、ウィーン氏は単親世帯の大変さ、困難さを話すと共に、それが長期的には子供の教育や就業に影響を与えると話す。 時間のない共働き世帯はどうなるのか その話を聞きながら「やっぱり教育はお金と時間に余裕がある家庭の方が有利なんだな」と素朴な疑問がわいてきた。これは痛い話だ。私には1歳の子供がいる。毎日子育てしながら仕事を続けるのは大変だとは聞いていたが、仕事に復帰して1年。本当に毎日大変だ。 毎日早起きして食事の準備、洗濯を済ませる。子供にご飯を食べさせ、一緒に遊びながら自分の身支度をする。保育園に連れて行った後、大急ぎで仕事へ向かう。 帰りは午後6時までに保育園に迎えに行く。食事を食べさせ、入浴して寝かせた後、再び午後10時くらいから会社で片付けられなかった仕事をする。そして翌日の食事の下ごしらえ、保育園の荷物の準備をして寝る。寝るのは毎日午前2時くらい。なので慢性睡眠不足である。 地域社会で子供を育てるのも一手? こんなに苦労しているのに「子供と一緒に過ごす時間が少ないから、将来は子供の学力に影響が出るでしょう」なんて言われたら、たまったもんじゃないと思った。私が苦労するのはどうでもいいが、親の働き方のせいで子供の可能性を摘むことだけは絶対にあってはならない。なんだかモヤモヤしてきたので、質問することにした。 「日本はこれから人口が減る中で、女性の就労がますます求められ、共働き世帯が増えるだろう。子供に接する時間が減っていくことが予想される。だがその一方で、日本の東大合格者の多くが高収入の夫、専業主婦の妻、という世帯の子供であるとするデータもある。お金と時間がある方が高学歴の子供が生まれやすい現状をどう見るか」(別に、東大こそすべてというわけではないが、高学歴の象徴として分かりやすいたとえで質問してみた) ウィーン氏は笑いながら「そうなんです。この問題について私も長年考えてきました。でも残念ながら、時間とお金がある家庭の方がよい教育を受けられる。そしてこのことが就業格差、所得格差につながっていく。これは事実です」と答えた。 その上で「日本は良い大学に入るためには必ず学力が高くなくてはならない。でも米国の大学、たとえばイェールやハーバードには、音楽やスポーツといった他のアクティビティーで秀でていれば入れるといった側面もある。要は学力だけではない。でも日本は学力がすべて。ここがジレンマなんです。だから“タイガーマザー”、いわゆる教育ママがいる家庭の方が有利になるでしょう。これは香港や韓国など、アジア諸国によく見られる傾向でもあります」と話してくれた。 なんだかスッキリしない回答ではあったが、言っていることもよく分かる。「学力偏重」の教育システムにも問題があるということだ。そして、母親がそばにいた方が、筋の良い子供が育つ確率が高くなる。これは間違いない。だとすれば、これから共働きが多くなっていく社会の中で、教育の質はどのように担保されなければならないのか。帰り道、いろいろ考えてしまった。 代替手段として有望なのは、やはり地域コミュニティーの力なのではないかと思う。おじいちゃん、おばあちゃんが両親の代わりに面倒を見てくれるのがありがたいけれども、核家族や都市への人口集中といった現実を見る限り、それは難しいと思う。 「働くお母さんは偉大です」 だとすれば、「地域で子供の面倒を見る」といったシステムを構築すればよいのではないか、と思う。そうでもしない限り、将来の日本は午後3時を過ぎたら習い事や学童保育といった、いわゆる「放課後の子供の居場所」に入るお金のない子供はどうすればよいのか。社会問題になるんじゃないかと思う。 まだ自分でも考えがまとめられていないが、この問題は私が働き続ける限り、考えなければならないものになるだろう。最後、「今日は貴重なお話ありがとうございました」と言いに行くと、ウィーン氏は私に「働くお母さんは偉大です」と言ってくれて、メールアドレスを教えてくれた。別に偉大でなくてもいいが、子供だけはちゃんと育てたい。いずれ、考えがまとまったらまた疑問をぶつけてみたいと思う。 このコラムについて
記者の眼 日経ビジネスに在籍する30人以上の記者が、日々の取材で得た情報を基に、独自の視点で執筆するコラムです。原則平日毎日の公開になります。 http://diamond.jp/articles/print/51976 悶える職場〜踏みにじられた人々の崩壊と再生 吉田典史
【第39回・最終回】 2014年4月22日 吉田典史 [ジャーナリスト]
「おれより偏差値が低いあいつらが記者なんて!」通信社の支局で劣等感の炎を燃やす“嘆きの営業マン” ?本連載『悶える職場』も、今回が最終回となる。最終回は、筆者が専門学校で文章指導をしている20代半ばの会社員を取り上げたい。この男性は、大手報道機関で働いている。だが、花形の記者ではなく営業の仕事をしている。彼は記者になりたいと密かに思っているが、壁は高いようだ。 ?失意を抱きつつ、会社には籍を置く。そんな悶々とした日々を送るなか、彼の心を支えてくれるのが、過去の栄光である。口癖が、「自分よりも偏差値の低い連中が記者なんて……」。こうした言葉を発することで、何とか自分のプライドを守ろうとしているのだ。 ?この男性は、決して奇異な存在ではない。形を変えて、似たタイプの人があなたの職場にもいるはずだ。コンプレックスの裏返しで周囲をバカにする彼のような会社員が陥る「悶え」とは、いったいどんなものなのか。その心は救われることがあるのか。読者諸氏も、一緒に考えてみてほしい。 「もう辞めたい」「東京に戻りたい」
通信社の支局で働く営業マンの劣等感 「タクシーは来ているのか?……おい!?聞いているだろう?」 ?支局長の飯田(43歳)が、店の出入口付近に出てきた。酔っていることもあり、ぶっきらぼうな物言いになっている。 ?田口が(25歳)がうつむいたまま、「ええ」と小さく答える。飯田が睨みつけるような表情を見せて、料亭の座敷に戻る。 ?その部屋には、大手銀行の支店長や副支店長、総務課長がいた。田口の会社の取引先であり、3時間ほど前からこの3人の接待を彼らはしている。 ?田口は、玄関のほうをぼんやりと眺める。15分ほど前に電話で呼んだタクシーを待っている。宇都宮市内(栃木県)は午後10時を過ぎると、繁華街ですらタクシーをあまり見かけない。市のやや外れにあるこの料亭の付近は、明かりが少なく、外は真っ暗だ。 ?田口はため息をつくことをこらえながら、思っていた。「こんな会社はもう、辞めたい」「東京に戻りたい」。ここ2年で、数え切れないほどに考え抜いた。 ?店の外の冷たい風が頬にぶつかる。わずか数秒で酔いが冷めていく。実は、それほど酒は飲んでいなかった。 ?接待の場であり、酒を飲み、酔える身ではない。目の前に座る3人には、酒を注がなくてはならない。時間を見計らい、それぞれを自宅に送るタクシーも手配をしないといけない。1人で話し続ける飯田の横で適度にうなづき、かすかに笑うこともせざるを得ない。 記事を書く記者たちを横目に
ひたすら企業を営業で回る屈辱 ?田口は、この通信社の支局員6人の中で最も若い。他の5人は記者である。田口だけが営業職だった。記者たちと机を並べながらも、取材をしたり、記事を書いたりすることはできない。ひたすら、栃木県内の金融機関をはじめとする企業を回る。そして、会社が発行する情報誌や雑誌、さらには情報端末やそのソフトを売り歩く。 ?2ヵ月に一度のペースで行う主要な取引先への接待には、上司である飯田に付き添い、参加する。今日はその日だった。 ?社員数が1500人を超える大手報道機関にいながら、記者ではなく営業マンをする。挙げ句に、10代の頃から住み慣れた東京を離れ、北関東の小さな支局に勤務する。宇都宮市内で賃貸マンションを借りているが、訪ねて来る人はいない。 ?学生時代に数年間にわたって交際していた女性とは、この1年ほどの間に関係が疎くなった。ここ数ヵ月は、電話で話し合うことすらない。女性が東京から泊りに来ることもなくなった。 営業職と記者職の間に横たわる
同じ会社とは思えないほどの格差 ?田口は2年前、一流と言われる私立大学の法学部を卒業した。就職活動では、全国紙や大手通信社を中心に受験した。記者になりたかった。 ?だが、1つも内定を得ることができない。いずれも筆記試験で落ちた。それでも、金融機関やメーカーなどを受けることはしなかった。記者の仕事をさほど知らなかったが、記事を書いて生きていきたいと思っていた。 ?大手の新聞社に記者職で入社することは、いつの時代も難しい。田口は筆記試験の勉強をしていなかっただけに、そのハードルはなおさら高かった。 ?就職活動のシーズンが終わろうとしているとき、大手通信社が営業職を募集していることを知った。その時点で、内定はなかった。いつかは記者職に移ることができるのではないかと思い、その会社を受験した。筆記試験はなく、たった一度の面接で内定となった。 ?大手報道機関とはいえ、営業職の倍率は数倍でしかない。記者職は、1200〜1400倍になる年もある。二十年前は、1500倍を超えていたときもある。はるか以前から、双方の間には同じ会社とは思えないほどの「差」がある。 ?田口は内定を得た後、キャンパスで誇らしげに大手報道機関に入ることを話していた。だが入社早々、辞めたいと思うようになる。どうやら、営業から記者に移ることはできないらしい。 ?聞くと、過去30年ほどで1人もいないようなのだ。採用からして別々に行われ、賃金体系も異なる。学生時代の田口には、その現実が見えなかった。 ?入社早々の研修では、記者職の内定者10人前後は国会などに見学で行ける。かたや営業職は、セールスをする雑誌や情報端末の説明を受ける。 ?研修を終えると、夜は居酒屋で記者職の同期入社組と酒を飲む。「自民党の代議士の〇〇を見た」「首相官邸にも見学で行った」と話す姿を見ると、疎ましく思えた。 ?営業職の同期生たちが、「いい記事を書いてくれよ。どんどんと売るから」などと言う。その横に座りつつも、声が出なかった。記者職の同期生は、「おお、頼むぞ」と答える。中には、「何で営業職で入ったの?」とタバコをくわえ、小バカにしたような表情を見せて尋ねる者もいた。営業の同期生は、顔を少しひきつらせる。 ?すでにこの時点で、営業と記者の間には大きな壁がある。上から目線の記者に対し、卑屈な思いの営業。田口は、自らが営業マンであることに、悶々とした思いを強くしていく。 「同じ大学でも偏差値は自分が高い」
過去の栄光を持ち出し自己弁護の日々 ?さらに気になったのは、それぞれの出身大学だった。 ?記者の内定者10人ほどのうち、半分ほどが東大卒。残りが入学難易度の相当に高い国立大学だった。私立大学出身者はわずか1人。その男性は、田口と同じ大学出身だった。 ?田口が「〇〇大学だろう??俺もだよ……」と近づくと、男性は「マンモス大学だからな……」と答えるのみ。「営業の君とは深く話さない」といった様子を見せるという。田口はこのあたりの描写になると、筆者の前で雄弁になる。 「〇〇大学といえ、自分が法学部で、あの男(記者)は商学部卒。偏差値で言えば、3〜4ランクは法学部のほうが高い」 ?過去の栄光を持ち出したところで、空しさは残る。現実は変わらない。営業をする身であり、記者にはなれないのだから。 ?本社での研修を終えると、北関東の支局に配属された。支局では、先輩の社員は皆記者であり、田口のみが営業。そこにも同じ大学出身者がいたが、声をかけられることすらなかった。 ?たった一度、「私も〇〇大学を卒業しました」と話しかけたが、「ああ……」と返事なのかつぶやきなのか、区別もつかぬ反応が返ってきただけだった。 いいか、営業と記者の2つの顔を
使い分けることが必要なんだ ?支局長は営業出身だった。だが、社外ではそれを隠す。あたかも、記者の仕事を十数年してきたかのような口ぶりをする。支局に戻り、記者がいないときを見計らい、2人だけになるとこんな説明をする。 「支局長だから、みんなは俺のことを記者だと思い込む。営業と記者の2つの顔を使い分けることが必要なんだ。お前も支局長になったら、使い分けるんだ」 ?田口には滅入る言葉だった。まさか自らの職業を隠し、生きていくとは思いもしなかった。支局長はプロフィールを尋ねられると、「札幌や岡崎(愛知県)にいました」と答える。そこから、「〜という取材をしていた」とは言わない。墓穴を掘ることを警戒しているのだろう。 ?同じ支局にいる記者たちの平均年齢は、30歳前後。40代前半の上司である支局長を、「営業出身」ということで軽く扱う。しかし実際のところ、支局の記者は経験が浅く、一本立ちしているとはおよそ言えない。 ?東京本社の政治、経済、社会部からは、少なくも「使える記者」と認められてはいないのである。だからこそ、大きな事故などが起きると、本社からその支局に「戦力になる記者」が送られて来る。 ?田口は、報道機関のこんなからくりを知っていた。だが、支局の記者たちはそれに気づいていないのか、「営業は過酷だよね」「よく、そんな仕事をするな」と冷笑する。 自分よりも偏差値の低い
連中が花形の記者なんて…… ?支局に赴任し、半年が過ぎた。地方の支局に散らばる同期の営業マン6人のうち、3人が辞めた。記者を中心とした社内の体制に嫌気がさしたり、記者との間の「格差」に幻滅を感じたことが、大きな理由だったという。 ?田口は、辞めていく3人に電話をして話をし、不満を言い合うと、泣きたくなるほどに空しくなった。学生時代に思い描いていた夢は、綺麗に粉々に潰れていく。 ?田口は入社3年目を迎える今年、秘めた思いがある。秋までには転職先を見つけようと思っている。年末には、辞表を出したい。そうでないと、いよいよ次の支局へ人事異動になる可能性がある。来春まで残ると、すでに今の支局に3年間、在籍したことになる。 ?田口は筆者にこう話す。 「次の支局に移っても、営業をすることになる。この会社に残る限り、永遠に記者にはなれない。このチャンスを逃したらずるずると進み、40代では支局長のように経歴詐称をして生きていくことになる」 ?狙いは、大手全国紙の中途採用。当然、記者職である。ただし、いわゆる「キャリア採用」ではない。大学在学中の学生と同じ土俵で競う、純然たる「新卒採用」になる。 ?昨年も、倍率は相当に高かったという。実は昨秋、有給休暇を消化して会社を休み、都内で試験を受けたことがある。結果は、筆記試験で落ちた。3年前の学生の頃と同じ結果だった。なかなか面接に進めない。最終面接まで、4回ほどの面接があるという。 ?田口は今、都心にある大手マスコミを狙う学生向けの専門学校の通信教育も受けている。作文を書いては、現役の記者たちに添削をしてもらう。点数は合格圏内とは言えないが、夏までには何とか浮上させたいと願っている。 ?記者になって、何を訴えていきたいのか。そもそもなぜ、記者という仕事にそこまでこだわるのか……。その回答は、今もない。口から出てくるのは、こんなセリフばかりだ。 「自分よりも偏差値の低い連中が記者なんて……。自分は〇〇大学法学部卒。記者の連中は〇〇大であっても、〇〇学部レベルが多い。そこは、法学部よりも偏差値が3〜4ランクは低い。もっと低い、〇〇大学や〇〇大学出身もいる。そんな会社で営業の仕事なんかして、会社員人生を終えたくない」 ?辞めよう、辞めたいと思いながら、田口は今日も営業をしている。 踏みにじられた人々の
崩壊と再生 ?このエピソードを連載の最終回で紹介したのは、特に20〜30代の会社員にとっては共感できるケースなのではないか、と思えたからだ。少なくとも、いじめやパワハラ、退職強要、解雇などよりは身近に感じられるのではないか。 ?大手報道機関の官僚的な体質や、営業と記者との「格差」などは、他の業界で見かけるものではないと思う。だが、20代の社員が自らの仕事の内容、会社のあり方に幻滅を感じるプロセスや、学歴にしがみつことでしか現状を乗り越えていくことができない姿は、多くの職場で見受けられるものではないか。 ?筆者は、ここ8年ほどは主に出版業界に身を置いている。仕事で付き合った20〜30代の編集者120人ほどうち、その8割は今回の事例に出てくるような20代の男性と、同じような考えを持っているように見えた。 ?なぜ、ここまで悶々としながら生きていく人たちが目立つのだろう。1つは、新卒時の就職活動のあり方に問題があるように思える。20〜22歳になっても、明確な職業意識に乏しく、依然として「就社意識」しか持ち合わせていない若者が多いのだ。世の中ではあらゆる仕事が高度化しているにもかかわらず、「職業意識」がないようでは、自ずと「悶える人」は増えていくだろう。 ?筆者は2006年から、マスコミを目指す学生たちに文章の書き方を専門学校で教えている。8年間で計500人ほどに接してきたものの、明確な職業意識を身に付けていると思えるのは数人しかいなかった。大半は、「何となく、マスコミを受けておこう」といった類のものでしかない。 ?若い層に媚びる、また媚びないとビジネスになり得ない一部のビジネス雑誌とそこで活躍する識者たちは、「今の学生は真剣に就活をしている」と言い切る。筆者には、その意味がわからない。そのような学生をほとんど見たことがないからだ。 就職ではなく「就社」を続ける若者
働き手の意識と職場の理解とのズレ ?筆者は、決して就社意識を否定するものではない。様々な部署や職種を経験させ、幹部候補として育成する層を雇うことも、企業にとっては必要だろう。一方で、強烈な職業意識を秘めた人を雇い入れることも大切だと思う。また、1つの仕事でエキスパートになるような人材の育成も進めないといけない。 「悶える職場」を生み出す大きな理由の1つに、働き手の意識と職場や会社の論理との間にズレが見られることがある。本来、メディアはそれを問題視しないといけない。だが、メディアは伝統的に労働問題を苦手として、この働き手の意識と職場や会社の論理にズレにメスを入れることがいつまでもできない。 ?今回のケースで男性が悶えるのは、根拠なきプライドを持っているものの、職業意識がないために苦しむという現状だ。「記者になりたいがその理由がない」ならば、職業意識がないのと同じことだ。結局、記者になろうとする理由が、学歴コンプレックスを克服するものでしかないならば、悶えるのは当然のことだろう。 ?そして、40代の支局長もまた、職業意識に乏しい。自らの仕事に自信を持てず、隠しているようでは、職業意識が相当に低いと言わざるを得ない。実は、中高年失業者の失業期間が長くなり、深刻な問題に発展していることは、このあたりに一因がある。 ?つまり、こうした中高年は明確な職業意識がなく、何となく「就社」し、命令通りにいくつかの部署を渡り歩く。だが、30代後半になっても社外で通用し得る技術や技能を持ち合わせていない。20代前半から1つの職種にこだわり、それに関わる技術を身に付けていないからである。 ?さらに言えば、今回のケースに出てくる営業職を小バカにする記者のような人たちにも、明確な職業意識がない。一見すると「記者」という職業をまっとうしているように見えるが、実際は本社にある政治、経済、社会部などと地方支局との往復をして、会社員人生を終えていくことがほとんどだ。 ?日本の大手新聞社や通信社は、専門記者を育成していない。相変わらず、いくつかの部署を渡り歩くように仕向けている。激しい倍率を潜り抜けて入社した割には、「冴えない会社員記者」で終わっていく人が大半を占める。 ?会社との間に職業を媒介とした契約がなく、いわば自らを「商品」として契約する雇用形態が続いている。これでは、今回のケースに出てくるような人たちは今後も現れ得る。 真実は「会社 VS 社員」ではない!
悶える職場は今後も生まれ続ける 「悶える職場」を考えるとき、多くのメディアや識者は「会社 VS 社員」「上司 VS 部下」というくくりで捉える。そして、「常に会社員は会社から搾取され、悲惨な扱いを受けている」と唱える。それも1つのアプローチであろうが、筆者にはそれは1960年代のような、古い時代感覚に基づくものにしか見えない。 ?筆者は、そこまで単純には考えていない。会社は利害関係が複雑であり、「会社 VS 社員」という側面だけでは見据えることができないことが少なからずある。社員の側にも、大いに問題がある場合もあるだろう。今回の男性も支局長も、その一例ではないだろうか。 ?筆者はこの連載で、利害関係が複雑化した今の時代に即した課題を炙り出したいと思い、記事を書き続けてきた。その評価は、読者に委ねられるものだとは思う。これからも、「なぜ人々は職場で悶えるのか」を考え、問題提起を続けて行きたい。
?
?長い間ご愛読いただいた読者諸氏に、改めてお礼を申し上げたい。 |

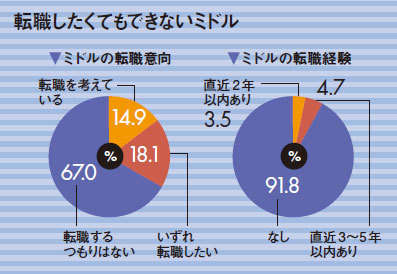
 スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。