01. 2014年8月25日 23:37:10
: hRJT7V2jFA
(がん新時代:66)医師と患者が学校訪問 怖がらず、正しく知って
2014年8月25日05時00分子どもの意識調査/「がん教育」の主な内容
http://www.asahi.com/articles/photo/AS20140825000209.html ◇がんを学ぶ 子どもたちが、がんを学ぶ機会が増える。文部科学省は今年度、がん教育のモデル事業を全国70の小中高校などで始める。生活習慣の大切さを学べる一方、家族に患者がいる児童・生徒を傷つけない配慮も求められている。 京都府は、国に先駆けて昨年度から「生命(いのち)のがん教育」事業を始めた。医師とがんの経験者が講師として、学校を訪ねる。医師ががんの基本知識を解説し、経験者が闘病を通して生きる大切さを語る。昨年度は小中高20校で実施した。 京都市の洛星中学校では、今年6月に2年生が授業を受けた。 「がんってどんな病気やと思う?」 冒頭、府健康対策課医務主幹で医師の堅田和弘さんが問いかけた。堅田さんは洛星中の卒業生でもある。 「怖い」「絶対死ぬ」……。生徒たちから次々と声が上がった。 堅田さんは「がんは一生のうちに2人に1人がかかり、3人に1人が死亡する身近な病気」と説明。発症や進行には喫煙や飲酒のほか、睡眠、運動、食事といった生活習慣の影響が大きいと述べた。「がんになりにくくするには、中学生のうちから規則正しい生活をすることが大事なんやね」 続いて、がん経験者の富永和重さん(59)が「私、がんになりましたけど、元気に生きていますよ」と語りかけた。 富永さんは15年前に悪性リンパ腫になり、腎臓がんや前立腺がんも発症した。いまは落ち着いた状態で、今年2月に京都マラソンを完走したことを披露した。「家族や医師らのサポートがなかったら、私はここにいないでしょう」 白井俊也さん(13)は、小学2年の時に身近な人をがんで亡くしたことを思い出したという。「今から健康的な生活をしておくことが大事なんだと改めて感じた」と感想を語った。 夏休みの期間中には、大学や病院でも、がんを学べるイベントが開かれる。 帝京大学医学部では、小学5、6年生を対象にしたサマースクールがあった。題は「がんを知ろう!」。 児童たちは実習で、がん細胞と正常細胞を顕微鏡で見比べたり、内視鏡手術で使うはさみを操作したりした。病院では、手術ロボットのダ・ヴィンチや放射線治療装置のリニアックなどを見ながら、進歩するがんの治療法の説明を受けた。 内科の授業では、医師や看護師でなくても、病気の人の背中をさすって声をかければ「助ける人」になれると学んだ。 企画した有賀悦子教授(緩和医療学)は、最後の授業で呼びかけた。「どんなに気をつけてもがんになってしまうことはある。それは失敗じゃない。病気にとらわれず、自分の体や心を大事にし、支え合う社会の一員になってください」 ■子どもの心に配慮を 2012年に閣議決定した「がん対策推進基本計画」は、がん教育のあり方を検討し、推進することを盛り込んだ。 文科省は、今年度にモデル事業として全国70校で実施したうえで、16年度までに学習指導要領の改訂の必要性を含めて検討する。 背景には、がんが1981年以降、日本人の死因のトップになっているのに、関心が低く、正しく理解されていないことがある。 聖心女子大学の植田誠治教授(保健教育学)らが小中高校生を対象に実施した調査では、がんについて「怖い」「どちらかというと怖い」という回答を合わせると8割を超えた。がん検診はどんな人が受けるのかという質問に、正しく「健康な人」と答えたのは小学生が38・0%、中学生は60・9%だった。 植田さんは「子どもたちは、がんの正しい知識を持たないまま、いたずらに怖いと感じていることがうかがえる。発達段階に応じた具体的な教育内容の検討が必要だ」と指摘する。 ただ、学校でのがん教育には課題もある。 一つは、専門性が高く、教師の負担が大きくなることだ。 12年度から小学6年生と中学3年生に実施している東京都豊島区は、教師の負担を軽くするため、区独自の教材や指導手引を専門家らと一緒につくった。 日本女子体育大学の助友裕子准教授(公衆衛生学)らは、厚生労働省研究班が08年に作成した小学生向けの副読本「がんのことをもっと知ろう」に沿った指導書をまとめた。指導の狙いや留意点、児童への問いかけ例を盛り込んだ。 助友さんは「がん教育は学校だけが担うのでなく、がん診療連携拠点病院や患者会などにも協力してもらってもいい」と語る。 また、学校には家族の中にがん患者がいる子や、小児がんを経験した子がいる場合がある。そうした子には配慮が欠かせない。 筑波大学の野津有司教授(学校保健学)は「学校は保護者にあらかじめ授業について伝えて、家庭でもがんについて話をしてもらうなど、子どもが授業で不安にならないようにする連携が必要だ」と話す。(宮島祐美) ■治療変えた薬、理解深めて 「がんと分子標的薬」講師・照井康仁さん(アピタル夜間学校から) 従来の抗がん剤は、がん細胞だけでなく正常な細胞も攻撃してしまうため、効果が限定的で時に激しい副作用を伴うという面が否めませんでした。その欠点を補うべく登場したのが「分子標的薬」。その名の通り特定の分子を狙う薬のことで、分子標的薬が登場する前と後では、化学療法の世界はまったく別物といってもいいくらい、一変しました。 私の専門である血液のがんでは、「Ph染色体陽性」というタイプの白血病は治療が難しく生存率も低かったのですが、イマチニブの登場で、逆にほかのタイプより生存率がよくなりました。骨髄移植も一部を除いてほぼ必要なくなるなど、治療方針も大きく変わりました。 ただ、分子標的薬も万能ではありません。患者さんの遺伝子タイプなどによって「効く」「効かない」がはっきりしており、誰もが恩恵を受けられるわけではありません。歴史が浅いため、長期間使い続けても安全かどうかも検証していく必要があります。また、本来効くタイプの患者さんでも使い続けているうちにだんだんと効き目が小さくなっていく「耐性」の問題への対処も課題です。 残念ながら副作用もゼロではありません。もし治療を受ける場合は分子標的薬とはどんなものか、患者さん自身にも理解してほしい。今回の夜間学校では、そんな思いもお伝えしたいと思っています。(聞き手・田之畑仁) ◇ 照井さんが講師を務める「もっと知ってほしい がんと分子標的薬のこと」は、9月17日午後7時半から、医療サイト「アピタル」で無料で視聴できます。 * がん研有明病院血液腫瘍(しゅよう)科担当部長。自治医大卒。米ハーバード大医学部、自治医大講師などを経て、2007年から現職。 ◆日本対がん協会だより 「たばこは体に悪いのに、どうしてお店で売っているのですか?」。小学生の率直で鋭い質問が続きました。 7月27日、東京で講演会「朝小健康教室 親子でたばこについて考える」を朝日小学生新聞と協力して開催しました。小学生の親子21組50人が参加しました。 講師は、テレビ出演でおなじみの山王病院副院長で呼吸器センター長の奥仲哲弥先生。肺がん専門医で、禁煙を訴える講演100回を超すベテランです。 講演後、参加者にアンケートで何が印象に残ったか答えてもらいました。例えば、1日たばこ20本を1年間吸うと、牛乳瓶1本分のタールが体に入り、肺の中が真っ黒になること。喫煙は本人だけの問題ではなく、受動喫煙・副流煙の影響が軽視できないこと。がんが見つかって早く手術する必要があっても禁煙期間を1カ月以上設けないとできない場合があること。汚れた肺の写真などを使い、先生がわかりやすく挙げた具体例に衝撃を受けたようです。 同伴の親御さんには喫煙者もいました。奥仲先生は「禁煙できないのは意志が弱いから」と責めたりはしません。ニコチン依存症なので適切に治療すべきであることを強調し、家族で応援しようと呼びかけました。厚生労働省の2013年の調査では、「喫煙している20歳以上」は21・6%。男性は33・7%でまだ3人に1人が喫煙者です。 教室は8月3日に大阪でも開催し、9家族26人が参加しました。息長く続けていきたい催しです。(協会事務局長・伊藤正樹) http://www.asahi.com/articles/DA3S11315369.html?iref=comtop_list_ren_n05 |

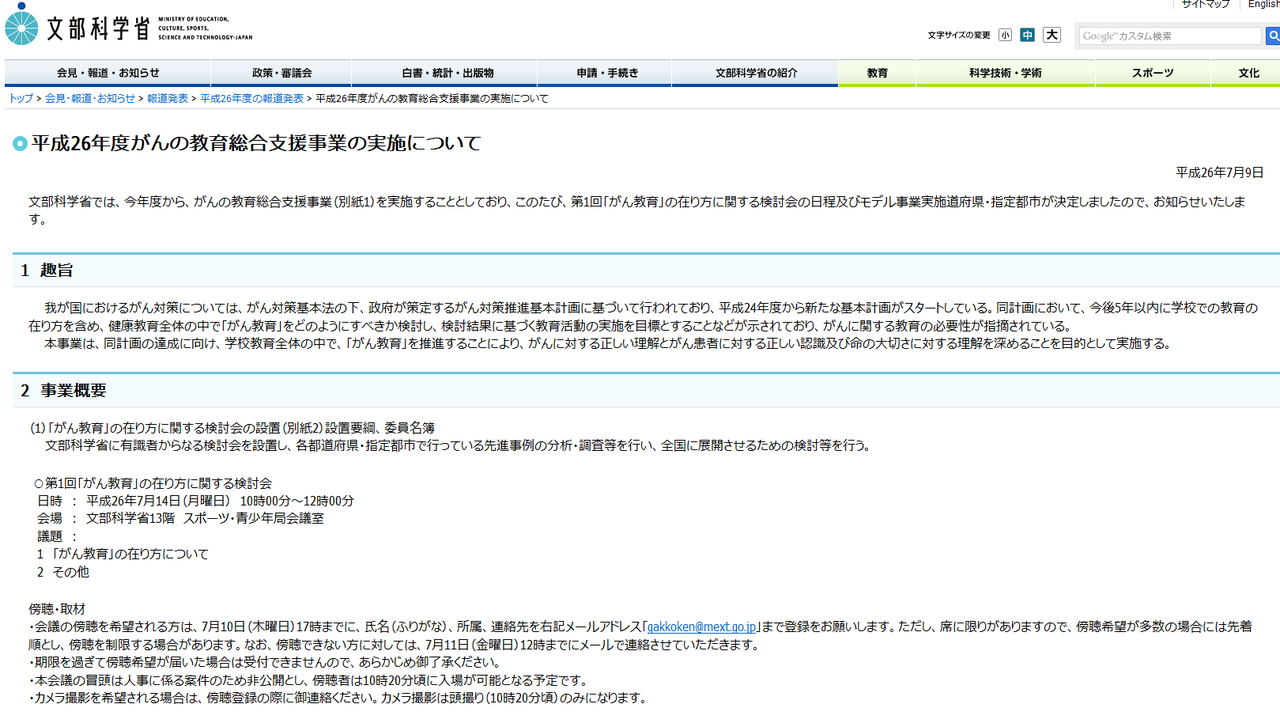
 スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。 スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。