01. 2014年1月16日 11:40:47
: e9xeV93vFQ
靖国で「しめた!」と叫んだ韓国だが・・・米副大統領の叱責が効き始めた 2014年1月16日(木) 鈴置 高史 2013年末の安倍晋三首相の靖国参拝。韓国は「しめた!」と叫んだ。これを言い訳に米韓関係の悪化を食い止められると思ったからだ。だが年が明けてから、韓国には失望感が広がった。 参拝を世界で一番喜んだ韓国人 12月26日に安倍晋三首相が靖国神社を参拝して、世界で一番喜んだのは韓国人だったのではないか。 12月6日に米国のバイデン副大統領から米中間での二股外交を露骨に指摘されたうえ「米国側に戻れ」と言い渡された朴槿恵大統領。韓国人はすっかりしょげ返っていた(「北朝鮮に『四面楚歌』と嘲笑された韓国」参照)。 そこに靖国参拝。駐日米国大使館は直ちに「失望した」と論評、米国務省も同じ表現で日本を批判した。韓国には「米国に叱られたのは我が国だけではない」との奇妙な安心感が広がった。そして「これは米韓関係改善のテコに使える」との期待が一気に盛り上がった。 韓国は、日本との軍事協力を強化するよう求める米国に対し「日本の右傾化」を理由に断ってきた。しかし、米国からは「日本の右傾化とは言い訳で、本当は中国が怖いのだろう」と見透かされてしまった。バイデン発言はその象徴である。 世界標準からは奇妙な告げ口外交 米国に対してだけではない。就任以来、朴槿恵大統領は世界中で日本の右傾化を言って歩く「告げ口外交」を展開してきた。しかし、韓国は世界から「奇妙な国」と冷ややかな目で見られるようになっていた。 韓国の価値観からすると別段、おかしくはない。しかし、隣国の悪口を国家元首が言って回る国は、世界標準からすればやはり変な国なのだ(「なぜ、韓国は東京五輪を邪魔したいのか」参照)。 韓国人には靖国参拝こそは救世主に見えた。なぜなら米国に対し「ほらこの通り、日本は右傾化しているでしょ。だから私は日本と軍事協力できないのです」と、言い訳の絶好の証拠を差し出せると思ったのだ。 二股外交を反日で偽装するという朴槿恵外交が限界に突き当たっていた時だから、韓国紙には「安倍外交は死んだ」「日本のオウンゴールを生かそう」「米国と共闘し日本を追い詰めよう」などと喜びの声が満ち溢れた。 「早読み 深読み 朝鮮半島」書籍化第2弾、好評発売中
『中国という蟻地獄に落ちた韓国』 まるで中国という蟻地獄に落ちたかのように、
その引力圏に引き込まれていく韓国。
北の核威嚇で加速する韓国の「従中」は、
日米との同盟に引き返せないところまで来てしまった。
日本は、米国はどう動くのか。 第1弾『中国に立ち向かう日本、つき従う韓国』に
続編が登場。最新の情報が満載です。
「靖国」は韓国の自爆兵器 もちろん、韓国政府もこの機会を逃さなかった。世界に向け「野蛮で危険な国家、日本」と「被害者、韓国人の怒り」を宣伝した。 1月に予定されていた日韓財務担当相会談を取り止めたうえ、次官級戦略対話や局長級の安全保障政策協議会の開催のための実務協議を中断することを決めた(「靖国参拝で全対話凍結 国際協調で『日本孤立作戦』」=朝鮮日報12月28日)。 韓国国会も12月31日「靖国参拝と日本政府が狙う集団的自衛権の行使容認は、侵略戦争を美化し軍国主義を復活するたくらみ」との非難決議を採択した。 朴槿恵大統領も1月2日、潘基文国連事務総長と電話で話し「過去を直視できずに何度も周辺国を傷つけるなら、不信と反目を助長する」と日本を非難した。潘基文事務総長の対日批判も引き出した。 もっとも「靖国」は韓国にとって自爆兵器でもある。それが侵略戦争の象徴としても、韓国は日本と戦ったことはないからだ。 威張る朝鮮系日本人 それどころか日本の「侵略戦争」には、当時の朝鮮人も日本の軍人・軍属として多数参加している。もちろん彼らは靖国神社に祀られているし、中には捕虜虐待の罪で戦犯とされた人もいる(注1)。 (注1)「洪思翊中将の処刑」(山本七平、昭和61年)に詳しい。 連合国の軍人の中には太平洋戦争中に捕虜収容所で朝鮮人に酷い目にあわされた人もおり、米軍など組織の記憶となっている。 韓国が「靖国」を掲げて自らを被害者と主張すれば「本当は加害者だったではないか」と逆に糾弾されかねない。そこで国会決議では批判の対象に「集団的自衛権」を含めて、合わせ技にしたのであろう。 「靖国」に絡めた大統領の非難談話も被害者を「周辺国」とぼかし「韓国」とはしていない。やはりそれが理由の1つと思われる。 一方、中国は日本孤立策の先兵として韓国を利用したい。日米離間を実現するには中国だけではなく、米国の同盟国でもある韓国に日本批判させるのがより効果的だからだ。 しかし中国国民、ことに満州国が存在した東北部の人々には「威張り散らす朝鮮系日本人」への記憶が残っている。「靖国」を契機に、中国のネチズンが反韓的言説を展開しないとも限らない。そこで韓国を「完全な被害者」として認めてやる必要があったのだろう。 「二股外交するな」 中国の陳海・駐韓代理大使は1月8日付中央日報に、安倍首相の靖国参拝を批判する記事を寄稿した。 そこでは「日本軍国主義の侵略はアジア各国の国民にあまりに大きな厄災となった。中でも中国と韓半島の国民が最大の被害者だった」と、軍国主義を主語としたうえ韓国人を最大の被害者と認定した(注2)。 (注2)この記事の日本語版はここで読める。 もっとも、韓国は中国から呼びかけられた共闘に逡巡した節がある。12月31日に中韓外相は電話会談した。中国側は会談後に「両外相は安倍首相の行為を厳しく批判した」と発表したが、韓国側は「最近の北東アジア情勢など関心事を協議した」との文言に留めた。 それを解説した聯合ニュースは「日本と協力する分野もあり、韓米日の協力の必要もある」「歴史問題で中国と全面的に連携するのは望ましくない」との政府の中の意見を紹介した。 韓国には「二股外交するな」というバイデン発言が効き始めたのだろう。これまでなら会談後、直ちに中国と声を1つにして日本批判したうえ、国民にも外交成果として大いに誇ったものだ。 今度それをやったら米国から「まだ、中国のお先棒を担ぐつもりなのか」と言われかねない。「中国と組んで日本を叩く」構想はとりあえず棚上げせざるを得なかったのだろう。 空振りに終わった日本叩き 代わりに韓国人は「米国と組んで日本を叩く」ことに希望を見出した。聯合ニュースは1月2日配信の「韓国と日本が新年から対米外交戦」で以下のように書いた。 ・韓国政府は(靖国参拝で)米国を動かす名分を手にした。ワシントンの外交筋も1日「米国で今ほど日本に対する批判の気運が高まったことはないと思う。民主主義と自由、平等など人類普遍の価値を同盟の礎石とする米国としては容認しがたい行為だった」と話す。 ・(現地時間1月7日の米韓外相会談で)尹炳世(ユン・ビョンセ)外相が米国との対話の中で日本に向けた何らかのメッセージを引き出すなど、韓日の歴史問題においてそれなりに意味ある転換点を作りだす期待感がある。 もっとも、韓国人のその熱い期待も空振りに終わった。米韓外相会談後の記者発表で、ケリー米国務長官は“日本問題”に関し一切触れなかった。 それどころか発表では記者からの質問は受け付けないという異例の措置をとった。韓国人記者が“日本問題”に関し聞くに決まっている。ケリー長官がどう答えても対日批判に聞こえるから、というのが韓国紙の見立てだ。 それに尹炳世外相自身も発表の席で日本を名指しして批判しなかった。韓国紙はこれに関しては何も書いていないが、米国の強い要望の結果だった可能性が極めて高い。 日本への懲戒手段はない 韓国紙には不満が溢れた。会談を報じた中央日報の記事の見出しは「水も漏らさぬ韓米同盟……安倍への言及はなかった」(注3)。 (注3)この記事の日本版はここで読める。 「水も漏らさぬ両国の関係」(Without an inch of daylight between us)とはケリー長官の言葉だ。そう言う割には、米国は安倍批判をしてくれなかった――という韓国人の悔しさが伝わる見出しだ。 もっとも、韓国紙の米国特派員はそれ以前から「米韓による日本包囲網」への過剰な期待を諌めていた。米国の事情や本音をよく知るからだ。 その1つが朝鮮日報のワシントン特派員、イム・ミンヒョク記者の書いた「米国、安倍に厳しく警告したものの……」(12月31日)だ。興味深いのは以下の部分だ。 ・米国の懸念は「安倍の歴史認識」そのものよりも「(日本の)周辺国との対立」にある。この点で韓米間には根本的な認識の差があり、今後解決を巡って意見の違いが露わになる可能性が高い。 ・ニューヨークタイムズが「韓中は日本と首脳会談をすべきだ。安倍の参拝に『ライセンス』を与えたのは韓国と中国の(会談拒否という)圧迫だった」と社説に書いた。同紙論説委員と米外交当局者がしばしば会っていることを考えると、無視すべきではない。 ・「北東アジア戦略の中心軸」たる日本を米国は放棄できない。安倍に痛烈な警告はしたが、さらなる懲戒手段はほとんどない。結局、韓中に「(日本との)対話により、自分たちで解決しろ」と言ったに等しい。 米国の本音を直視せよ 中央日報ワシントン支局長のパク・スンヒ記者も12月31日に「米国の本音」という記事を載せた。以下である。ちなみに原文の「本音」はハングルで「ホンネ」と表記。日本語そのままだ(注4)。 (注4)この記事の日本語版はここで読める。 ・2期目のオバマ政権は、野党との政争で厳しい日が続く。内政の疲労は外交力も失わせた。シリアの状況が端的な例だ。 ・米国にとって同盟とは道徳や価値のような情緒ではなく国益だ。我々が貴重なものと考える韓米同盟も、米国の国益の中にある時が安全地帯だ。 ・「失望」声明に喜ぶあまり、米国が安倍の日本を嫌うことを韓国人は望んだ。しかし、その米国の国防長官は長い間の悩みだった普天間基地の移転問題が解決されるや否や「強い米日同盟」に言及した。 ・米国の財政赤字は2013年11月基準で1352億ドルに達する。米国はこの赤字を埋めるためなら何でもする姿勢だ。中国に対抗せねばならない米国は、依然として安倍の日本を必要とするほかない。米国の本音を直視せねばならない。 同盟は情緒ではない この記事のハイライトは「同盟は情緒ではなく国益だ」の部分だ。外交を感情で考えがちな韓国人に対し、筆者は「野蛮だが、カネを出す日本を大事にする米国」という現実を伝えたかったのだろう。 同時に「米国を実利で満足させないと、韓国は見捨てられるかもしれない」と警告を発したかったに違いない。「韓米同盟も……」の部分からそれが伺える。 確かにそうなのだ。日本の集団的自衛権の行使容認に対し、韓国政府は反対の姿勢を強くにじませている。日本との軍事協定も署名当日にドタキャンした。米国の強く求めるミサイル防衛(MD)にも参加しない。ことに後者は日本の右傾化とは全く関係がない。 韓国は守ってくれている米国ではなく、旧宗主国の中国の顔色を見て動くようになった。まさに「韓米同盟が米国の国益から外れ始めている」のだ。 「このままでは同盟が危機に瀕する」「日本問題など語っている場合ではない」と危機感を抱く韓国の知識人がようやく出てきたということだろう。 ただ、韓国の空気は「同盟は情緒」のままのようだ。それを背景に1月9日、最大手紙の朝鮮日報は「『歴史と安保は別』という米国の対日認識は誤り」という社説を載せた。 ケリー長官が日本批判をしなかったことを非難するために書かれたものだ。要は「靖国神社に首相が参拝し(戦争ができる国にするため)憲法を変えようとする日本を、米国は叩き直せ」という主張だ。 甘い言葉を耳元でささやく中国 もちろんこの論説自体は「情緒的」とばかりはいえない。「日本に対する貴重な外交的武器である歴史カードを、米国に陳腐化させられてはいけない」との国益を主張したものだからだ。 「中国と共闘できる歴史カードをきっちりと維持してこそ、米中二股外交が可能だ」という韓国なりの計算もそこにはある。 ただ、中国との対決に全力を挙げる米国人の目には、日本の軍国主義復活を騒ぎたてる韓国人の言説は「情緒そのもの」と映るであろうし、この訴えを米国が聞くこともないだろう。 今、中国は毎日のように「一緒に日本を叩こう」と韓国の耳元にささやいている。それは韓国人の情緒からすれば実に魅力的な呼びかけだ。 米国に叱られて「離米従中」の歩みをいったん止めたかに見えた韓国人の心は揺れるであろう。とすると韓国は、再び中国傾斜を始めるのかもしれない。 このコラムについて
早読み 深読み 朝鮮半島 朝鮮半島情勢を軸に、アジアのこれからを読み解いていくコラム。著者は日本経済新聞の編集委員。朝鮮半島の将来を予測したシナリオ的小説『朝鮮半島201Z年』を刊行している。その中で登場人物に「しかし今、韓国研究は面白いでしょう。中国が軸となってモノゴトが動くようになったので、皆、中国をカバーしたがる。だけど、日本の風上にある韓国を観察することで“中国台風”の進路や強さ、被害をいち早く予想できる」と語らせている。 サムスンのプロジェクト失敗に学ぶこと 技術部門とマーケティング部門が馴れ合いではダメ 2014年1月16日(木) 佐藤 登 少し遅くなりましたが、新年おめでとうございます。2013年は本コラムを18回執筆し、その反響もまちまちでした。コメント欄を眺めると賛同を得る部分と反論・異論を招く部分とが混在し、それぞれが参考になりました。反論・異論に対しては、そんなことはないと思う部分がありながらも、見方が変われば見解も変わるだろうということで、自身の立ち位置を客観的に眺めることができました。このうち3回のコラムは、その日のアクセスでトップとなったことは、自身でも驚くことでした。いずれにしても、本コラムへアクセスを頂いた方々に感謝の意を表します。
2013年を振り返れば、自然災害で多くの方々が犠牲となる悲しい出来ごとがあった。一方、日本にとって嬉しく元気が出る年であったことも事実だ。2020年の東京オリンピック開催決定、和食が世界無形文化遺産に認定、アベノミクス効果による円安方向への動きと株価上昇、産業界の活況――等々。これからの日本が上昇気流に乗れるような予感を映し出した。あとは、このような現状に水を差さないように、アメリカ財政のデフォルトが起こらないことを願っている。 東京でのオリンピックと言えば、前回開催時1964年の開会式において、陸上自衛隊音楽隊30名の奏者によるオリンピックファンファーレが国立霞ヶ丘陸上競技場に高らかに鳴り響いたのを、小さいながらに記憶に残っている。一般のトランペットではなくファンファーレ用トランペットを使用したため、音量が出しにくいことでこれだけの人数が必要だったと、ファンファーレを直接吹いた知人(辺見敏夫氏:現在、福島県白河市在住でファンファーレの楽譜所有)から聞いた。 聞いただけにとどまらず、辺見氏とは社会人ビッグバンド「YOKOTE HEROES」(秋田県横手市にゆかりのあるメンバーで構成し、東京を中心に活動中。YouTubeにも動画あり)でご一緒させていただいている。その公演にて、6本のトランペット(筆者もその1人)で、昨年は3回、このファンファーレを披露した。特に3回目となった12月21日のクリスマス・チャリティコンサート(会場:六本木T-CUBE)で演奏したファンファーレは、辺見氏が「こんな素晴らしい響きは初めて」と絶賛してくれたことが印象的だった。2020年までの新しいファンファーレが鳴り響くまでの6年間、しばらくは公演の度にファンファーレを披露しようとして考えている。 ともかく、2020年はもちろんのこと、それまでにも世界各国から多くの観光客に日本へ来ていただき、日本の素晴らしさを実感してほしい。和食を筆頭に、温泉や名所・旧跡・観光地、世界一の清潔度、ホテルの綺麗さ、公共交通機関の正確さ、マナーの良さなど。それぞれが「おもてなし」の文化なので、日本の素晴らしい部分を体感いただきたい。中でも清潔度や綺麗さ、マナーの良さは各国へ積極的に水平展開していただきたいものである。 ただ昨今の外交、特に近隣の中国、韓国との関係が冷え切った状態に陥っていることは気になるところだ。特に2004年から5年間住んで業務を担っていた韓国との関係の底冷えは懸念材料の1つだ。赴任した2004年は正に韓流ブームの真っただ中にあり、それ自体が日韓交流の大きな役割を担っていたが、今はそれも影を潜めている。最近、ソウル市内を歩いていても、ひところ多かった日本人の姿もまばらになっている。逆に、中国人のパワーが街にあふれてきた。 マーケティングと技術は技術経営の両輪 さて本論の「技術経営」であるが、これまでもいろいろな実態を述べてきた。そんな中で、最近、日本企業の幹部の方々から尋ねられることが多いのは、顧客を訪問する際のメンバー構成である。 日本企業の多くが口にするのは、マーケティングの領域はマーケティングに関連する人間だけで、技術領域はエンジニアだけでというスタイルだ。確かにそれも分かるような気がする。 技術経営は、成果が事業や製品に反映されるように運用しなければならない。製品は顧客のニーズに応えるもの、あるいはそれを超えるものでなければならない。すなわち、技術の押し付けであってはならない。 サムスンの場合、必ずしもそう決めているわけではないが、顧客との協議、特に製品に関する協議においては、マーケティング側と技術側が同席し、顧客のニーズをリアルタイムで両部門で共有することが多い。そうしないと、マーケティング側と技術側との間に温度差が生じ、的確な製品開発ができないばかりか、間違った方向に進んでしまうことにもなりかねないからである。すなわち、マーケティングと技術は両輪のような形で運営している。 とは言え、両輪で駆動するからすべてがうまく回るという保証はない。例えば、その両輪同士の仲間意識が強すぎて、お互いを客観的に分析できないと問題が起こる。 そういった問題が起きた事例として、レジャー用途の燃料電池開発を説明しよう。2006年のサムスンSDIにおける燃料電池の開発プロジェクトであったが、その典型であった。 プロジェクトの設定から運営までは部長級の研究員(首席研究員)が担当し、担当役員がフォローする体制で進められていた。このテーマを設定した根拠は、世界の市場でレジャー用途の燃料電池のニーズがあるはずという視点に基づいていた。 具体的な用途は、1つがキャンピングカー用の発電システムとしての燃料電池であり、もう1つは船舶用での発電システムとして使う燃料電池である。いずれも燃料電池の形式は、プロパンやブタンガス燃料を用いてシステム中で水素に改質し、固体高分子形燃料電池(PEMFC)で発電する方式である。 ではなぜ、それぞれにニーズがあると考えたのか。キャンピングカーでの行動は欧米を主体に休暇での移動と宿泊などで多用されていることに違いはない。発電機を用いると騒音が出るため、発電機の代わりに燃料電池システムを用いれば騒音もなくなるためニーズがあるはずという論拠である。一方の船舶用に対する燃料電池システムのニーズは、電源として搭載されている鉛電池に加えて燃料電池を適用すれば使用時間の拡大になる。よって、停泊時間や期間の延長になることからニーズがあるという論拠である。 こういうテーマ設定のもとで、ハードのシステム開発は着々と進められていた。しかし、研究開発戦略も担当していた筆者にとっては、本当にそのようなニーズとビジネスモデルはあり得るのかという疑問が浮上した。 開発の途中経過段階での評価会議でのこと、ハードシステムの説明とビジネスモデル、価格などに関する議論が数回にわたって繰り広げられた。ハードシステムの信頼性はともかく、機構的には成立するところまで進みだしていたものの、製造コストから算出する予想価格が60万円ほどになることが明らかになった。その時点で、そのような価格帯でのニーズがあるのかどうか、マーケティング部隊を巻き込んだ市場調査が行われた。 キャンピングカー用途に関しては米国市場での調査、船舶用は韓国内での船舶運営会社などの訪問によって意見を聞きだす方式で市場調査は行われた。マーケティング部隊は開発メンバーと共に調査にあたり、やがてその結果が報告されることになった。 意味がなかった市場調査 市場調査の結果だが、いずれの用途も市場性はあるということであった。キャンピングカーでの用途は、静粛性という環境面に配慮したシステムが顧客の購買意欲を掻き立てるという見方で、60万円はやや高いが購買層がいるという。 しかしより客観的に眺めると、大体、米国内のキャンプ場は至る所にあり、しかもそういう場所にはAC電源まで備えられている場合が多い。AC電源を使える所へ、多くのキャンピングカーは向かうわけだ。そうではない場合に、高価格なシステムが必要になるわけだが、もちろん新しいシステムに関心を持つ購買層もあるだろうが、決してニーズは多くはないという見方を筆者はしたし、主張した。 そこで、何千台、何万台分の販売が見込めるのかといった質問をした。しかし、定量的な答えは返ってこないのである。仮にAC電源がないキャンプ場に行くしても、発電機よりも価格が3〜4倍もするのであれば、あまり勝算がない。 もう一方のレジャー船舶用途では船舶事業を展開している複数の所へ出向いての結果は、価格は高いが可能性はあるという報告であった。しかし、可能性はあるとしても、本当に購入してシステムを組むかと言えば、これもまた疑問である。釣りなどのレジャーで発電を賄うのに、果たして60万円もの金額を払うのかという疑問だ。 そんな評価会の席上で発した筆者の意見は、「一部のオタクは購入するかもしれないが、高価な燃料電池を搭載するような購買層もビジネスモデルもほとんどない。電源をもっと使いたいなら、そんな高いシステムを導入するよりも、鉛電池をスペアで搭載して切り替える方が全く安いだろう、その方が現実的だ」と。 チーム側としては、いずれのケースも市場性に関する可能性は訴求したものの、定量性や客観性に欠けていたのである。その結果、筆者も含めて経営判断として市場性がないとの結論から、2008年3月にテーマはお蔵入り、いや実際にはお蔵にも入らず、テーマに終止符を打つことになったのだ。 この事例は何を意味するかと言えば、2つの教訓がある。会社側としてはマーケティング組織との連携を指示したものの、開発側と考えが類似した仲間意識をもつメンバー構成であったことから、何とか考え方を共有して同じ方向にもっていけないかという心理が働いた。こういった仲間意識は、ビジネスを進めるうえでは当然断ち切るべきで、それを徹底すべきだというのが、1つの教訓だ。 そして開発テーマとしては、何もしないよりは何かした方が良いとの考えがあったと思われる。可能性があるならば市場ニーズは高くないとしても、継続していくことの方が成果の可能性があるという考えの作用が働いたのだが、市場ニーズがなければ、いさぎよく撤退すべきなのである。これがもう1つの教訓だ ビジネスプロジェクトは、成果に結び付かなければ意味はない。それどころか、無理に進めれば無駄な経営資源を投じることになる。テーマ設定および推進当事者と、経営側の密な議論が必要なのではあるが、もっと重要なことは安易にテーマを設定しないこと。そういう提案があった時点で、技術経営の視点では深みにはまってからの判断ではなく、導入部での的確な判断が必要である。 このように市場性に絡む領域でのマーケティングと技術部門間の活動になると微妙なケースもある。しかし、直接の顧客対応時には、そのニーズや考え方を直接伝えられることから、両輪での対応は効果的、かつスピード感をもって推進できるメリットがある。 技術経営のセンスとは サムスンSDIのCTO(Chief Technology Officer)は研究所長(職位は常務から副社長級まで)が歴代務めてきた。研究所の運営のみならず、事業部の技術も含めた領域まで責任を取るので、CTOの役割は重要だ。 技術の価値判断、テーマ着手判断と運営、継続か撤退かの判断、経営資源の配分など、役割としては多々ある。筆者が韓国に住んでいた5年の間に、CTOは4人が入れ替わりで担当した。専門領域の出身別では、マネジメントであったり、ディスプレイ技術であったり、素材技術であったりとそれぞれであったが、個性や考え方がそれぞれ異なり、運営力や判断力には差が見られた。 先の燃料電池の件でも、時期ごとに異なるCTOと突っ込んだ議論を重ねてきた。同じような考えのCTOとは波長が合い、うまい具合に進めることができたが、そうでない場合には、遅々として進まない歯がゆさも感じた。大概、この後者の場合は、社長の考え方を把握した上で判断しようとするものだから、自ら積極的に方向付けをしないことが問題であった。 現在、筆者が在籍しているエスペックは、環境試験機器のメーカーであると同時に評価試験受託サービスも担い、グローバルにビジネスを展開している。この企業に在籍して感じていることは、顧客目線でのアンテナとセンサーを働かせて、ニーズを先取りしようという積極姿勢である。例えば、昨年11月22日に開所した宇都宮のエナジーデバイス環境試験所は、自動車業界、電池業界、パワーエレクトロニクス業界のニーズや意見に耳を傾け、経営判断として価値があると判断し着手した新事業である。 評価試験機器は自社が開発し、所有する既存装置のみならず、自動車メーカーの評価試験方法に関するニーズにいち早く応えるべく短期間で開発し、その実現性を具体的に自動車メーカーへ提案することで実行に移していった。その結果、新規に開発した評価試験システムは世界初として各業界からも大いに注目され期待されている。 技術経営は企業規模の大小如何で決まるものではなく、ビジネスモデルがどこまでチャンスとしてあるのかどうか、リスクヘッジをどう捕らえていくのか、その総合的判断力に依存する。そして顧客ニーズにスピード感をもって応える力、あるいはニーズ以上の提案力で期待値を最大に示す意欲もまた大きな要素である。 このコラムについて
技術経営――日本の強み・韓国の強み エレクトロニクス業界でのサムスンやLG、自動車業界での現代自動車など、グローバル市場において日本企業以上に影響力のある韓国企業が多く登場している。もともと独自技術が弱いと言われてきた韓国企業だが、今やハイテク製品の一部の技術開発をリードしている。では、日本の製造業は、このまま韓国の後塵を拝してしまうのか。日本の技術に優位性があるといっても、海外に積極的に目を向けスピード感と決断力に長けた経営体質を構築した韓国企業の長所を真摯に学ばないと、多くの分野で太刀打ちできないといったことも現実として起こりうる。本コラムでは、ホンダとサムスンSDIという日韓の大手メーカーに在籍し、それぞれの開発をリードした経験を持つ筆者が、両国の技術開発の強みを分析し、日本の技術陣に求められる姿勢を明らかにする。 朝鮮戦争の難民がつくった町に世界中が注目
町おこしに成功した釜山・甘川文化村を歩く
2014年01月16日(Thu) アン・ヨンヒ
新年に韓国の東南部にある韓国第3の都市、釜山へ行ってきた。プサンと言えば、長い砂浜の海雲台(ヘウンデ)やコンテナが集まる釜山港などが有名だが、今では海にかかる長い広安大橋や摩天楼のセンタムシティなど、海を臨む摩天楼も有名である。 朝鮮戦争の難民たちがつくった甘川文化村
釜山の観光名所となった甘川村
だが、筆者は近年町おこしに成功した「甘川(カムチョン)文化村」に興味があった。最近、若者やカメラマンたちが集まる場所として有名になっている。
また、昨年12月「民官協力フォーラム」主催、安全行政部(部は省に当たる)後援で行われた「2013民官協力優秀事例公募大会」で、甘川文化村は大賞である大統領賞を受賞した。 もともと甘川洞は、1950年代に太極道という信仰の信者たちや朝鮮戦争(1950〜53年)の難民たちが山岸に集まって形成したバラック村であった。 日本では丘の上の家と言うと幸せの象徴のように聞こえるかもしれないが、韓国で丘の上の村(ダルトンネ)と言うと貧しい村という意味になる。
ちなみにダルは月、トンネとは村や町のことだ。ダルトンネは、直訳すると月に近い村、つまり丘の上の村ということになる。
甘川もこのように貧民たちがその場しのぎの掘立小屋を建て、お金を稼いだ人たちはどんどん村から離れてしまう不便で小汚い場所であった。 だが、今では町全体が明るく色づき、その美しさを観賞するために訪問する観光客が年間で30万人を超す観光地となった。この背景には、地場のアーチストや村の住人たちが集まって始めた「マウル(村)美術プロジェクト」があった。 甘川文化村は韓国のサントリーニとかマチュピチュと呼ばれている。筆者はこうした韓国の何々と名づけるのには反対である。なぜなら途端にオリジナリティがなくなってしまうからだ。 せっかく戦争の痛みや太極道という独自のストーリーがあるのに、サントリーニとマチュピチュでは個性が感じられない。 だが、行ったことがない人にはどんな感じの場所かを伝えるには効果があるとも言える。サントリーニと言われるゆえんは、背山臨水でパステル調の家が不揃いに並んでいるからだ。 さて、筆者は行く前にいろいろなブログやマスコミを通じて甘川文化村に関する予習をした。山を一回りする覚悟で歩くためローファーに履き替え、ビューポイントやフォトポイントなども頭にたたきこんだ。韓国のストリートフードや釜山ならではのお菓子を売っている店もしっかり押さえた。 絵葉書のようなパステル調の村
町の人やアーチストが共同作業したアート作品の前で観光客が写真を撮っている
当日知人たちと一緒にタクシーに乗り込み「カムチョン・チョドンハッキョ(甘川小学校)」と告げると、急勾配の頂点にある小学校前に降ろしてくれた。
そこはほとんどの観光客が出発地点にしているらしく、周りには公営駐車場やバス停があり、その前に分かりやすく観光案内所があった。観光案内所で2000ウォン(約200円)の地図を購入し、現在地を確認した。 地図の販売は村のビジネスの一環なので村の収益につながる。実は地図は正確さよりも町を彩るパステル調がちょっとした記念品になりそうだ。そこにはお馴染みのスタンプを押す場所が記されているので、若者たちはスタンプをどれだけ早く多く押すかを競い合っているようでもある。 私の一行は急ぐこともないので、のんびりと町を観賞することにした。晴れ渡った冬空に映えるパステル調の町は絵葉書に出てくるようなきれいな場所である。 路地の階段を上がっていくと見晴台のような場所も設けてあるので、全体の様子がよく分かる。下の方を見下ろすと釜山の海が見える。西日にキラキラ輝きとてもきれいだ。ところどころで家の工事をしているのを見ると、町が潤ってきたので個人の家も改装しているようだ。 地図はあまりあてにならない。感覚に頼って行くと、あるポイントで地図を持っている人にはポストカードを渡してくれた。 そして、ここのコースをくまなく回るためには路地に沿っていったん坂を下りていき、また坂を上がってくることを勧めてくれた。 丘の下の案内所でご褒美にもう1枚のポストカードをくれるらしい。しかし、そこまでして欲しいカードでもなく、筆者はすでにきれいなポストカードを自前で買ったので未練がない。 それより、お手製のソーセージやら最近釜山で大流行の種入りホットク(ひまわりの種が入ったお焼き)が食べたい。知人は甘いお汁粉(ダンパッチュッ)が食べたいという。 こうした食べ歩きができるのも面白いので案内所の人の話を無視して楽な路地を歩いていた。すると、家の前に椅子を出して老人たちが日向ぼっこをしている。遠目には観光客を見下ろしている感じもする。 アフリカからも視察に来るほどの人気に
急勾配の坂が続く
彼らにとって、観光客はどんなふうに映るのだろうか。静かだった町の穏健さをかき乱す乱暴者に映るのかもしれない。実際、観光客が来て有名になったはいいが、ごみを勝手に捨てたり、昼夜なくうるさいので住みにくくなったと嘆く住人もいるらしい。
町を一回りして急勾配の坂道を降りていく途中、「老人保護」という道路標識と道路に書かれた表記を見つけた。先ほど私たちを見下ろしていた老人たちが「もっと年寄りを大事にしろ」と視線を送っているように感じる。 以前は各家にトイレや水道施設がなく、町全体でいくつかのトイレを共有する共同トイレや共同井戸を使用していた。まさに開発から取り残された地域であった。 2009年から「マウル(村)美術プロジェクト事業」を推進したことから画期的に変わってきた。甘川文化村の学生や作家、住人たちが積極的に参加して保存や再生のための文化事業を進め、2010年には「迷路美路(ミロミロ)路地プロジェクト」などを通じて持続的に住人たちが参加する事業が進められた。 今や中国、日本、アフリカのウガンダ、タンザニアなど海外からも視察が来るほど成功事例に挙げられている。 ソウルをはじめとする大都市には戦争難民や貧民が形成したダルトンネが多く存在していた。しかし、ソウルのダルトンネは一つずつ都市再開発によって開発され、昔の姿は跡形もなくなっている。 そして、最後に残っている「ペクサマウル」の場合は、途中で開発が中止されたため、住む人も少なく廃墟と化した。 だが、釜山の甘川文化村は、昔の懐かしい姿はそのままに残しながらも村全体に色をつけたり、風景に溶け込んだアート作品を足すことによって美しい街に生まれ変わった。
自閉的なブッシュ政権が米国の分裂と弱体化を招いている
あまりにも無思慮な米国の「テロとの戦い」 2014年1月16日(木) FINANCIAL TIMES,Clive Crook 10月初め、ブッシュ政権のテロ容疑者の取り扱いが再び非難の的となった。「米政府は拷問を行っていない」「我々は米国の法律と国際的義務を遵守している」。ジョージ・ブッシュ大統領は改めて、こう繰り返した。さらに、拘留者の取り調べ手段は「議会のしかるべきメンバーに遺漏なく開示されている」と語った。 これに対して、上院情報委員会の委員長を務めるジョン・ロックフェラー議員は憤りを露にした。 「こんな茶番にはうんざりだ。実際には、ブッシュ政権は拘留者の取り扱いを委員会全体に開示することを5年も拒んできた。重要な法的文書の引き渡しも初めから拒絶している。委員会が米司法省よりもニューヨーク・タイムズ紙から多くの情報を知らされるなんて、全く理解しかねる」 ブッシュ政権は「テロとの戦い」を遂行するに当たって、米国の法律や憲法上の制約を密かにかなぐり捨てようとしている――というのが今の一般的な見方で、政権側もそれを否定する素振りはない。 「テロとの戦い」ではなく「ブッシュ政権とテロの戦い」 ただの「テロとの戦い」ではなく、「ブッシュ政権のテロとの戦い」と言うべきかもしれない。この概念は次第に支持を失っており、政権が法外な権力を行使し、議会と司法の力を弱めるための口実にすぎないと見なされているからだ。 これは無法政権だ、と批判は続く。人権団体「憲法権利センター(CCR)」の代表を務めるマイケル・ラトナー氏は、カレン・グリーンバーグ、ジョシュア・ドラテル両氏が編集した書籍『The Torture Papers: The Road to Abu Ghraib(拷問の記録:アブグレイブへの道)』の書評の中で、この書は「米政府の無法ぶりを白日の下にさらした、史上最も重要かつ痛烈な記録だろう」と述べている。 この分厚い書籍には、ブッシュ政権の法に対する初期の見解のほか、編者らが骨折って集めた囚人の取り扱いに関する国内法及び国際法のデータが収められている。 「無法」ではない・・・法律には執着している しかし、「無法」という表現は適切ではない。ブッシュ政権に対する一連の非難には、思い違いがある。この政権は政権を非難する側と同様、法律に取りつかれ、法律を遵守することで頭がいっぱいなのだ。そしてこの点こそが、ブッシュ政権の安全保障政策の拙さの原因なのである。 法にかなっているかどうかに執着するあまり、何が賢明かつ適切で、道義的であるかという点に思いを巡らす時間や知的資源が残されていない。同じことは政権を非難する側にも当てはまる。ただ、批判派は権力の座に就いていないがゆえに、それほど問題にならないだけのことだ。 ブッシュ政権のこうした傾向について詳しく知りたければ、最近出版されたばかりのジャック・ゴールドスミス氏による回顧録『The Terror Presidency: Law and Judgment Inside the Bush Administration(テロ時代の大統領:ブッシュ政権内の法と司法判断)』を読むといい。 2003年後半から2004年にかけての1年足らずの間、ゴールドスミス氏は司法次官補を務め、大統領に対して法的に遂行可能な活動範囲について助言する司法省法制局のトップに立っていた。ゴールドスミス氏は頻繁に政権スタッフと衝突した。 特に、当時ブッシュ大統領の法律顧問を務めていたアルベルト・ゴンザレス氏やディック・チェイニー副大統領の法律顧問デビッド・アディントン氏と対立、周囲の人間に悪感情を残して政権を去った。 この回顧録は、私がこれまで読んだブッシュ政権の病理についての書籍の中で最も興味深く、示唆に富むものだ。私はある日の夕方から読み始め、夜を徹して終わりまで読んでしまった。 書評によると、回顧録は現政権への「痛烈な批評」ということになっている。確かにそうだ。ただし、批判の意図は、評論家が意味するところとは違う。 ゴールドスミス氏は保守派であり、現政権に同情的だ。そして、「テロとの戦い」という言葉が問題を適切に捉えた表現であると考えている。米国を襲うテロの脅威が深刻であり、テロに立ち向かうためには通常の刑事裁判の手法では明らかに不十分であることを示唆しているからだ。 ゴールドスミス氏は、ブッシュ政権内の強硬派は、米国が重大な危機に瀕しているとの確信から、誠実に職務を遂行したと強調する。強硬派は、テロへの対応を妨げるような憲法解釈が可能だという考えを頑として受け入れなかった。彼らはまた、自分たちの行動が憲法に沿うものであることに終始心を配ったという。国民の反応を気にしてではなく(それについては意に介さなかったことを回顧録は明かしている)、彼ら自身にとって憲法が大きな意味を持っていたからだ。 米国の国益とは? ブッシュ政権内の法律専門家にとって受け入れ難いのは、テロに対する措置が憲法及び判例に沿うものでありながら、それでも「間違っている」可能性があるという点だ。これは政権の外部から批判する者にとっても同様だろう。 法律だけに配慮し、法律家に政策を任せてしまうのなら、テロ容疑者に関する議論は必然的に、「拷問」とは何か、「苦痛」とは何か、あるいはジュネーブ条約における「非人道的な取り扱い」とは何かを巡って展開されることになる。 法治国家である以上、このようなおぞましい疑問も検討せざるを得ない。しかし同時に、非米国市民の権利を軽視する態度を示したり、米国人が相手であれば不当行為と見なされるような方法でテロ容疑者を手荒に扱うことで、米国の国益がより大きく損なわれるという点を忘れてはならない。 「無法」ではない・・・「無思慮」なのだ ゴールドスミス氏は、エイブラハム・リンカーン大統領とフランクリン・ルーズベルト大統領は、国家の安全保障上必要だと思われた時には憲法をないがしろにしたと指摘している。ブッシュ政権との違いは、両大統領が議会と国民の意思を――従って司法も――味方につけたことだった。 両大統領は支持を訴えるに当たり、自らの考えをはっきりと示し、証拠を挙げてその正しさを説明しなければならなかった。そのため、両大統領は、適法か違法かという点だけでなく、何が賢明な行為であるかについて心を砕かざるを得なかったのだ。 ブッシュ政権はそういった面倒を避けてきた。これは「無法」ではなく、「無思慮」である。拘留者の取り扱いは法に沿ったものかもしれないが、道義的ではない。 他人の助言に耳を貸さないブッシュ政権の自閉的態度や、何でも知っている自分たちだけで内々に事を進めようする偏執的な頑なさは、米国の分裂と弱体化を招いている。ブッシュ大統領が守ると誓ったのは、まさにその米国ではなかったか。(Clive Crook)
ベトナムで強烈なプレゼンスを発揮する韓国
2014年01月16日(Thu) 細野 恭平
現在のベトナムに対する投資は、日本・韓国の2強によるマッチレースである。より正確には、韓国勢がずっとアグレッシブに投資を続けてきたなか、ここ最近、日本勢が少しずつ盛り返し始めていると言った方が正確だろう。 実は、ベトナム人の対韓感情というのは、あまり良いとは言えない。それにもかかわらず、拡大する韓国のベトナム投資の状況を概観してみたい。 2013年のベトナムへの投資額は、韓国が実質1位、日本が2位
(出所:ベトナム政府統計局)
2013年、日本からベトナムへの投資額は全体の1位。出光興産のギソン製油所(28億米ドル)など超大型案件があった。
一方、韓国は、統計上は3位だが、実質的には1位だ。サムスン電子による投資額20億米ドルの携帯電話の新工場案件が、同社のシンガポール法人経由のため、統計上はシンガポールにカウントされているからだ。 これ以外にも、サムスン電子の携帯電話工場(10億米ドル)、サムスン電機の携帯電話のIC・電子部品の製造工場(12億米ドル)、LG電子の生産拠点への投資(15億米ドル)などの大型投資があった。 ベトナムにおける韓国のプレゼンスには目を見張るものがある。 エレクトロニクスでは、サムスン・LGの前に日本勢がかなり劣勢を強いられている。特に、サムスン電子はベトナムをスマートフォン生産の一大生産拠点として位置づけ、近年、工場への投資を拡大している。 同工場の2013年の輸出総額は約2兆5000億円、ベトナム全体の輸出に占める比率の15%以上を1社で担う(参照:「トヨタがベトナムから撤退する日」)。工場労働者のために、半径100キロ以内に毎日500台のバスを運行させていると聞く。 日本人にはあまり知られていないが、ベトナムに進出した韓国企業の中で、最も従業員が多いのは泰光実業。「ナイキ」の下請けでスポーツシューズを生産しており、現在約4万人を雇用していると言われる。 Kポップをはじめとする韓流文化の輸出戦略は、特に20代前半以下のベトナムの若者に浸透している。ベトナム人の若者に知っている韓国人女優を聞くと、次々に名前が挙がる。 一方、日本人の女優を聞くと、残念ながら、いまだに「おしん」だ(おしんを女優というかはともかく)。 京南企業の建設したランドマーク72(同ビルのHPより)
Kポップの輸出の影響を受けて、韓国メーカーの化粧品も非常に人気があるように見える。日本の資生堂・コーセーなどのブランドは高級感を打ち出しているが、少し年齢層が高い印象を与えているのか、若者世代への浸透は芳しくない。 韓国人は人口も多い。日本人はベトナム全体で8000人前後と言われているが、韓国人はその10倍はいると言われている。 韓国のデベロッパーも活躍している。ホーチミン市で最も高い「ビテクスコ・フィナンシャル・タワー」は現代建設、ハノイで最も高い「ランドマーク72」は、京南企業による開発・建設だ。 残念ながら、日本政府のODA案件しか受注できない日系のゼネコンとの差は歴然としている。 韓・越の歴史的な関係 しかしながら、実はベトナム人の対韓国感情というのは、少し複雑だ。 この両国は、地理的にも歴史的にも共通項が多いため、仲が良さそうに見えるが、事情はそれほど簡単ではない。 両国とも中国に隣接する小国である。そして、隣接するがゆえに、両国の歴史は、たぶんに中国の影響を受けている。 例えば、中国の唐王朝が、朝鮮半島の平壌に安東都護府を置いたのと(668年)、ベトナムのハノイ近郊に安南都護府を置いたタイミング(679年)はほぼ同じである(この安南都護府の長官に、後に「天の原ふりさけ見れば」の歌で有名な阿倍仲麻呂が就任したが、その話は別稿に譲る)。 その後、この両国は、時期は異なるが、中国式の姓名を組み入れたり、科挙の制度を導入したり、中国化することで王朝の安定を保った点で共通している。平易な言い方をすれば、中国と戦いつつ、同時に同化することで国を保ってきた歴史がある。 一方、海を一つ隔てることで中国の直接的な軍事的脅威が少なかった日本は、日本人の体質・文化・制度に合うものだけを選択的に中国から輸入することができた。例えば、律令は導入しても、科挙は導入しないというように。 この点、日本は地政学的には、韓越両国より恵まれていたと言える。 こうした韓・越の地理的・歴史的な共通点を見ると、両国民の間には深い同情心のようなものがあるのかと勝手に想像しがちだ。しかし、実は近年まで、お互いに中国大陸を挟んだ反対側にある国を意識したことは、少なくとも民衆レベルではほとんどなかった。 ベトナムと朝鮮半島の民衆レベルでの接点は、ベトナム戦争時代という近代を待たねばねらない。 1965年、韓国政府が南ベトナム軍を支援すべく精鋭部隊をベトナムに派遣した。この時点では、少なくとも民衆レベルでは「韓国」という国を殆ど誰も認識していなかったようだ。 ベトナム南部では、かつて韓国人のことをダイハンと言った(今でも、ダイハンと言えば韓国のことだと多くの人は理解する)。ダイハンというのは、大韓民国の韓国語読みである。 大韓民国という表現には、大日本帝国とか大英帝国とかと同様、自国への尊称の意味が込められている。韓国軍の兵士が自らを「ダイハン」と胸を張ってベトナム人に主張した言葉が、そのままベトナム人の間に定着したようだ。 ベトナム戦争を知る世代にとって、「ダイハン」という言葉に、残念ながら、あまり良い響きはないようだ。 南ベトナムの人々にとって、北ベトナム軍は敵といえども同胞であり、同胞との戦いに送り込まれた韓国兵士を好ましく思わないという心理に至ったのは、いたしかたがない。 そういう意味では、韓国にとっては、ベトナムとの民衆レベルでの初めての接点がベトナム戦争という政治的な場であったことは、不幸なことだと言える。 マイナスイメージを跳ね返す韓国 韓国は、こうした様々な歴史上の不利にもかかわらず、ベトナムへの積極投資を継続している。様々なところで取り上げられている韓流文化の輸出戦略は、若年層を中心に全く新しい対韓感情を形成しようとしているように見える。 韓国がベトナムに対して積極投資を続けるのは、他の東南アジア諸国では、古くから進出している日本勢の牙城を崩すのが難しいという事情もある。 ただし、それ以上に、生産拠点としての賃金の安さや若年労働人口の多さというベトナムの魅力を理解し、果敢にリスクを取っている印象だ。たくましい、と思う。 一方、日本も、ここ数年ベトナムへの投資が加速しつつある。 実は、日本は韓国とは異なり、ベトナムとの歴史的なつながりには赤い糸を感じさせるような興味深い話が多い。現代の日本人に対するベトナム人の心象も非常に良い。つまり、国全体として見れば、日本の方が韓国よりも投資のための条件は整っていると感じられる。 次稿では、今回の韓国と対比しつつ、日越の歴史的接点と最近の日本企業の投資動向について、触れることにしたい。
南シナ海で中国監視船がベトナム漁船を襲撃
またも一歩踏み出した中国海洋戦略
2014年01月16日(Thu) 北村 淳
2013年11月23日、中国は東シナ海上空に防空識別圏(ADIZ)を設定し日本・韓国・米国との間の緊張を一方的に高めた。引き続いて12月5日、南シナ海の公海上で中国海軍空母練習艦隊を監視中のアメリカ海軍駆逐艦に、中国海軍揚陸艦が衝突危険距離まで急迫するというニアミス事件を起こし、アメリカとの緊張関係を再度一方的に高めた。 そして2014年元旦には、南シナ海の広大な中国“領域”を直接管轄する海南省が、中国国内法である「中華人民共和国漁業法」を実施する、という新規則を施行した(海南省が新規則を制定したのは東シナ海上空ADIZ設定から1週間後の11月29日だった)。 スタンガンや警杖でベトナムの漁民を制圧 南シナ海の“中国領”である島々・環礁ならびにそれらの周辺海域を管轄する海南省政
府の規則という形で制定された「海南省による『中華人民共和国漁業法』実施方法」に
よると、「中国の支配権が及ぶ南シナ海の海域内で操業する外国人、外国漁船や調査船は、事前に中国当局(国務院関連機関)の承認を受けなければならない。許可なく操業した外国船は、漁業法や出入国管理法に照らした処置が課せられる」とされている。 このルールが適用される海域は、およそ350万平方キロメートルの南シナ海のうち200万平方キロメートル以上、すなわち南シナ海の60%程度の範囲に及ぶ。そして、外国人や外国船に対して課せられる処置としては、強制退去、収穫物の没収、漁船や装備品の没収、それに罰金(最高50万元)の課金などが含まれる。
中国は九段線(緑点線)内の南シナ海の支配権を主張している(地図作成:米国中央情報局)
拡大画像表示
この海南省規則は、その大部分が国内漁業者向けであり、東シナ海上空でのADIZ設定のように対外的に公表されていない。そのため、いまだにこの新規則なるものは中国語バージョンしか公表されていない。しかし、その国内法の中には、国連海洋法条約をはじめとする国際法に抵触する上記規則が盛り込まれている。
そして、新規則施行直後の1月3日には、海南省規則ならびに中国漁業法が実際に発動され、南シナ海パラセル諸島(西沙諸島:中国が軍事的に支配中。ベトナム、台湾が領有権を主張)周辺海域で操業中のベトナム漁船を中国海洋監視船が“襲撃”し、スタンガンや警杖で漁民を制圧した中国官憲がベトナム漁船の漁具と収穫した5トンの魚を没収する、という事件が発生した。 この事件により、中国が勝手に主張している「中国政府により漁業活動が管理される南シナ海海域」で操業するベトナム、フィリピン、ブルネイ、マレ―シアそして台湾などの漁船に対して一方的に脅威を与えることが公になった。 アイスランドとイギリスの“タラ戦争” この種の漁業権の管理に関する領域紛争によって、武力衝突が引き起こされたり、その寸前に至った事例は少なくない。中でも有名な事例が、アイスランド周辺海域でのタラ漁を巡ってアイスランドとイギリスが3度にわたって対決した“タラ戦争”である。 1958年、アイスランド政府は主要産業であるタラ漁を保護するためにアイスランド領海幅をそれまでの4海里から12海里に拡大した。それに対して、アイスランド周辺海域で多数の自国漁民が操業していたイギリス政府は異議を唱え、イギリス海軍軍艦をアイスランド領海(12海里)に派遣してイギリス漁船を保護するとともに、武力を行使してでもアイスランドの領海拡大を撤回させようとした。 これに対して小国で正規海軍を持たないアイスランドは沿岸警備隊警備艇によって反撃し、イギリス海軍とアイスランド沿岸警備隊との間での小規模ながらも軍事衝突に発展した。 1958年9月から11月の間に、イギリスは駆逐艦やフリゲートを含む37隻の各種艦艇を派遣し、それを7隻のアイスランド警備艇と飛行艇1機が迎え撃った。両者の間で砲撃も行われたが、戦死傷者は発生しなかった。結局、1961年2月、NATOによる調停の成果もあり、イギリスはアイスランドの12海里領海を承認し“第1次タラ戦争”は終結した。 それから10年ほど経った1972年、アイスランド政府は自国のタラ資源を確保するために50海里のアイスランド漁業専管水域を設定した。これに対してイギリス政府と西ドイツ政府が反発し、再びイギリス海軍艦艇がアイスランド周辺海域に派遣され、イギリス海軍艦艇(駆逐艦1隻、フリゲート30隻、その他の艦艇11隻)やイギリス農水省武装タグボート(5隻)とアイスランド沿岸警備隊警備艇(6隻)ならびにアイスランド沿岸砲台などとの間で砲撃戦や軍艦同士の衝突戦が散発した(アイスランド側に戦死者1名)。 冷戦中の当時、アイスランドはNATO側にとって、ソ連潜水艦の動向を監視するために極めて重要な戦略要地であった。そこでアイスランド政府はNATOに対して圧力をかけたため、NATOによる仲介が実施され、イギリス側はアイスランドの主張の大枠を認める形で“第2次タラ戦争”も集結した。 50海里漁業専管水域を設定した後もタラ資源の減少に悩まされたアイスランド政府は、1975年、漁業専管水域を200海里に拡大した。これに異を唱えたイギリス政府は海軍軍艦と農水省武装タグボートをアイスランド周辺海域に派遣し、再びアイスランド警備艇との間で武力衝突が発生した。この“第3次タラ戦争”では軍艦同士の激しい衝突戦が頻発した。
イギリス海軍フリゲート「シラ」に体当りするアイスランド警備艇「オーディン」(手前の小型艦)、(写真:英国海軍)
イギリス側は22隻のフリゲートと7隻の補給艦それに9隻の武装タグボートを派遣し、アイスランド側は6隻の警備艇と2隻の武装トロール船で対抗した。
戦力増強のためアイスランド政府はアメリカから砲艦を購入する交渉を開始したがアメリカ側によって拒絶されると、ソ連と軍艦購入交渉を開始した。それと並行して、アイスランド政府が再びNATOに圧力をかけたため、イギリス政府は対ソ安全保障上の理由によってアイスランドの主張を認めることで “第3次タラ戦争”は終息した。 アメリカには多くを期待できない 3回にわたる“タラ戦争”で、アイスランドが主張しイギリスがしぶしぶ認めた12海里の領海と200海里の漁業専管水域は、現在は国連海洋法条約によって12海里領海と200海里排他的経済水域という形で幅広く国際社会に受け入れられている。 その国連海洋法条約が国際社会に定着しつつあった1995年、カナダとスペインの間でカナダのニューファンドランド沖のグランドバンクと呼ばれる海域でのヒラメ漁を巡る紛争が軍事衝突寸前までエスカレートした“ヒラメ戦争”が勃発した。 このように、漁業権を全面に押し出した海洋領域を巡るトラブルは、イギリスとアイスランドあるいはカナダとスペインといった友好国間でも軍事力行使にエスカレートしがちな深刻な対立と言うことができる。 このようなトラブルを友好国とは言えない中国相手に抱え込んでいる東南アジア諸国としては、海洋軍事力(海軍力・航空戦力・長射程ミサイル戦力)が中国に比べて圧倒的に劣勢である以上、当面は国連海洋法条約を盾にして中国の横暴を国際社会にアピールするしか対抗策はない。 しかしながら、東南アジア諸国にとって頼みの綱であるアメリカには、オバマ政権が「アジアシフト」を唱えているものの、多くを期待することはできない。 第1に、アメリカ自身がいまだに国連海洋法条約に加盟していない(参考:国連海洋法条約加盟国の一覧表。現在166カ国が加盟しており、中国や東南アジア諸国も加盟している)。したがって、国連海洋法条約を巡っての中国と東南アジア諸国間の交渉に、条約非加盟国アメリカが口を挟んでも説得力がないことになってしまう。 加えて、オバマ政権はアジア太平洋方面の軍事力強化と言ってはいるものの、その実際は、ヨーロッパ大西洋方面での軍事力を大幅に減少させるのとは違って、アジア太平洋方面
では少なくとも現状を維持させる、という程度のものである。無闇に海洋軍事力を強化させ続けている人民解放軍の戦力増大に比例して、アメリカが太平洋戦域に割くことができる海洋戦力が大幅に強化されることはない。したがって、相対的には西太平洋戦域での中国軍事力は強化され続け、アメリカ軍事力は低迷を続けることになる。このように、東南アジア諸国にとってはアメリカを当てにすることが極めて難しい状況が続くことが予想される。 中国の南シナ海支配は日本にも大きく影響 「中国漁業法」が南シナ海の広範囲にわたって適用されても、日本にとっては直接漁業権の問題は生じない。しかし、近い将来、東シナ海においても「中国漁業法」が何らかの形で適用される可能性は否定できない。その際には、日本の多数の漁船が現在以上に中国武装艦艇の直接的脅威に曝されることになる。 それ以上に問題なのは、中国が南シナ海で警察権を実際に行使し始めたということが、いよいよ海軍力を背景にして南シナ海の大半を直接的にコントロールする具体的ステップを踏み出したことを意味している、という点である。 すでに本コラム(「想像以上のスピードで『近代化』している中国海軍」)でも指摘したように、日本向け原油や天然ガスの大半が南シナ海を通過して日本にもたらされているため、南シナ海が中国にコントロールされることは日本のエネルギー資源の流れが深刻な影響を被ることを意味する。 さらに悪いことに、南シナ海でアメリカ海軍が中国海軍を抑え込むこともできなくなりつつある。強力なアメリカ海軍力を持ってすれば、南シナ海に限らず世界の公海における航行自由の原則は確保しうると自負していたアメリカは、国連海洋法条約に加盟することすら見送ってきた。ソ連海軍が消え去ってからは、アメリカ海軍力に脅威を与える海軍が誕生することなど想定もせず、中国海軍が南シナ海や東シナ海で大手を振って動き回る事態に適応するような海洋軍事戦略の構築を怠ってきた。 そして、急速に攻撃性をむき出しにしている中国海洋戦力に直面して、あわてて西太平洋方面の海軍力を強化しようにも、アメリカ自身が深刻な財政危機に直面しており、思ったようには海軍力の強化などできない状況に陥ってしまっている。 そこで、アメリカが推し進めたいのは、中国の脅威に直面している日本をはじめとするアメリカの同盟国・友好国の軍事力を強化して、それらのアウトソーシングを活用し、なんとか中国に対峙しようという戦略である。 日本としては、日本の生命線であるエネルギー資源航路帯としての南シナ海の自由航行を、横暴なる中国海軍戦略から保護するためにも、アメリカが希求する「アウトソーシング活用戦略」に協力する形で海洋戦力を飛躍的に強化させる必要がある。このことは、日米同盟の目に見える形での強化となり、同時に日本自身の自主防衛能力を大幅に強化させることを意味する。
http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/39672
[12削除理由]:関連が薄い長文 |
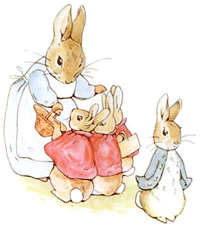

 スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。