05. 2013�N10��03�� 03:50:20
: niiL5nr8dQ
JBpress>�C�O>���V�A [���V�A]
��ɂ���Ⴄ�č��ƃ��V�A�A���̌�����T��
�����Ƃ̌y�������͖k���̓y���������点�邾���H
2013�N10��03���iThu�j W.C�@9���̒��{�ɁA�w���E�����W�̕��X�ɂ��P��́g���̍��h�K�I�c�ɎQ�������Ē������B1�T�Ԃقǃ��X�N���ɑ؍݂��A���N��������o�ς̕���Ń��V�A�̐��Ƃ����ƈӌ��������s���A�ނ̍��̃C���e���w�̌�����l���������߂Ċm�F����@����B�@�����̘b�肪�����ɊW�������̂ł��������Ƃ́A��N�܂łƕς��͂Ȃ��B����ȍ�����ڂ��鑊��ɂ́A�����Ɉُ킪�Ȃ��Ă��ώ@�̖ڂ��ɂ߂Ȃǂ��Ă͂��Ȃ��B�����Ƃُ̈킪���������Ă��Ȃ��̂ɁA���̖�肪���ƂȂ�����������悤�ȓ��{�Ƃ͑傫�ȈႢ���B �č��ɑ������A���߁A���� �Ԃ̍L����Ƃ炷�s��Ȍ��̃V���[
���N9���A���X�N���ŊJ�Â��ꂽ���یR�����y�t�F�X�e�B�o���̉ԉkAFPBB News�l �@�������A���N�͂���ɕ���ŁA�ĘI�W�ւ��b�����X�y�B�����Ȃ�̂����R���낤�B9��27���ɃV���A�̉��w����p��Ɋւ��鍑�A���ۗ��̌��c���o��܂ŁA�ĘI�͊O�����̏�ŋɓx�̐_�o��������Ă����B �@�č����g���߂��Ȃ������`�h�̍������ł��̖�肩��ꎞ����邱�ƂɂȂ������̂́A����ɕЂ������Ȃ�A�܂����뒆����肪�z�b�g�ɂȂ�̂�������Ȃ��B �@�č��ɂ��Ă݂�A���ƈ��S�ۏ�ǁiNSA�j�̃G�h���[�h�E�X�m�[�f�����Lj��̖S�������Ń��V�A�ɃJ���J�����Ă���Ƃ���ɁA�V���A���ł����̃��V�A�ɕ@�ʂ������ꂽ�悤�Ȃ��̂ł���B �@���V�A���V���A���牻�w����p��ւ̓��ӂ������A����Ɋ�Â��č��͌R���s�����~�߂ɒǂ����܂ꂽ�B���̋��J����{��͑z���ɗ]�肠��B �@��������f�B�A���u���V�A�O���̏����v�Ǝ��Ě����Ă��������ɁA��X�ƃ��V�A�̐��ƂƂ̖ʒk���s��ꂽ�̂����A�����Ĕނ炩��͂����������f�B�A�̕ɓ������鍂�g���͌��Ď��Ȃ������B �@�ނ���A�č��̖����ŗ����Ƃ͂��悻�����Ȃ������ɂ́A��������ȏ�������Ă͂����Ȃ��A�Ƃ���������A���߁A���̂̃j���A���X�����������̂��B �@�ĘI�̑Η��Ƃ͂悭�m���Ă���悤�ɁA�o�b�V���[���E�A�����A�T�h�����͂ɂ���Ăł��œ|���ׂ��ƕč����咣���A���V�A������ɔ����A�����܂ŊO���Ŗ��������ɓ���ׂ��A�Ɗ撣�����A�Ƃ����\�}�ł���B �@������{���̈���Ƃ��ē��s���ꂽ�A�č����������̌����҂̕��́A���̑Η����A�u�����s���v�Ƃ������̂ւ̕ĘI�̌����̑��Ⴉ������Ă���_���w�E����Ă����B �@�]���̍��ۖ@��ł́A�u�����s���v�͏��炷�ׂ��|�ł���B�����A�l���N�Q�A��ʔj��ۗ̕L��g�p�A����A�Ƃ�������肪�������ꍇ�ł��A�|������Ă���Ɋ����Ȃ����Ƃ��{���ɐ������I���Ȃ̂��A�ƕč��͋l�ߊ��B �@�������A���V�A�́u�����s���v�̌����ɌŎ�����B���̗��R�́A�傫���������2���낤�B �č��̍s���͎����̗��v�Nj��ɂ��������Ȃ� �@1�́A�����l���N�Q�ŁA������ʔj��ۗ̕L��g�p�ŁA�������킩���A���������N�����f����̂��A�Ƃ������ł���A�����č��ꍑ�Ɉς˂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��A�Ƃ�������B�����Ă���1�́A���ɕ��͂��s�g���Ă��A���̉����ɂ͂Ȃ�Ȃ��Ƃ���������`�҂Ƃ��Ẵv���O�}�e�B�b�N�Ȍ������B �V���A�k���̒��苒�A���̐��h�ƃA���J�C�_�n���� �Η��̔w�i
�V���A�k���A���b�|�Ő��{�������ɔ��C���锽�̐��h�̐퓬���kAFPBB News�l �@�O�҂́A���I����̈�Ɏx�z�Ƃ��̕���A���E�̑��ɉ��A�Ƃ������j�ςɎx�����Ă���B �@���V�A�͕������A�����͑䓪���A�r�㍑�����Ă��͂�č��̌����Ȃ�ɂȂ�Ƃ͌���Ȃ��B�č����������ɐU�镑���鎞��͂����I������̂��B �@����ɁA�č��Ɏv�����܂܂̓���������点���Ȃ�A���ł��D������ȗ��������āA���V�A���܂߂������ɍU�ߍ��ނ��Ƃ�F�߂錋�ʂɂȂ��Ă��܂��B �@MGIMO�i���X�N�����ۊW��w�j�̃g���C�c�L�[�y�����́A�č����ǂ������`�E���R�E�l���E�l����`�����`���悤�ƁA�����͌��ǂ̂Ƃ���A�����̋�̓I���v�Nj��̌�����ɉ߂��Ȃ��A�Ɛ��Ď̂Ă�B �@�o���N�E�I�o�}�哝�̂��A�u�č��͗�O�I�ȍ��v���J��Ԃ����ƂɁA���V�A�̕ێ�n���f�B�A�͂������Ă��̗B��Ƒ����U������B�E���W�[�~���E�v�[�`���哝�̎�����A9��11���t�j���[���[�N�E�^�C���Y�Ɋ�e���A�V���A�ւ̌R���s�����v���Ƃǂ܂�悤�č����ɑi�������A�č����O������댯�����w�E����ɓ������B �@����A��҂̃v���O�}�e�B�Y���Ƃ́A�����l�߂�Εč��̒�������ł̔��f�\�͂ɑ��ă��V�A���^�╄�����Ă���A�Ƃ������Ƃ��Ӗ����邾�낤�B �@���V�A�E�ĉ��������̃N�����j���N�������͌����B �@�u�A�t�K�j�X�^����C���N�̗������Ζ��炩�Ȃ悤�ɁA�č��͎����̎d�������킢�̌�n�����ł����ɂ���B���x�̓V���A�A�Ƃ����B�č����V���A���U������A�C�X���G����C�������ǂ��������\�z�����Ȃ��B���̌��ʂ̐ӔC��N��������̂��B�A�T�h������|���Ă��A���̌�ɂǂ̂悤�Ȑ��{������̂��A������\�z�����Ȃ��B�č��́A���x�͎n����������Ƃł������̂��낤���v �@���������c�_�̍���ɂ́A���V�A�̔�����Εĕs�M��������B���̕s�M���Ƃ́A1�ɂ͕č��ɌJ��Ԃ��ė����Ă����Ƃ����C���ł���B �@�{���X�E�G���c�B���哝�̂̎���ɁA�č��͖k�吼�m���@�\�iNATO�j�̓��i�͍s��Ȃ��Ɩ��Ă����ɂ�������炸�A���̕��������������݂̂Ȃ炸�A���\�A�̃o���g3���ɂ܂Ői�߂Ă����B ���������e���ł͂��������č����x�������̂ɁE�E�E �ē��������e������12�N�A�V���ɋ]����1�l�̐g���m�F
���E�f�ՃZ���^�[�r���Ւn�ŁA�e���]���҂̖��O�����܂ꂽ���j�������g�ɗ��Ă�ꂽ�č����kAFPBB News�l �@���X�N���E�J�[�l�M�[�Z���^�[�̃g���[�j�������Ɍ��킹��A �@�u�E���W�[�~���E�v�[�`�������哝�̂ɂȂ肽�Ă�2000�`2003�N�ɂ́A�č��̓������ɂ���Ȃ낤�Ƃ����B�����A���̌ネ�V�A�̔����������ăC���N�푈���n�߁A���V�A�{�y���ɐi�s���邩�̂��Ƃ��A�z�h���R�t�X�L�[��������Ӎ��ł̃J���[�v���i�O���W�A�A�E�N���C�i�A�L���M�X�j�������v �@�Ƃ������ƂɂȂ�B �@��q�̃v�[�`���哝�̂̊�e���̌f�ړ��t��9��11���ł��邱�ƂɁA���ӂ��K�v�����邾�낤�B���傤��13�N�O�̂��̓��A9.11�����̒���Ƀv�[�`���哝�̂͂ǂ̍����������e���r������ʂ��āA�u��X�͕č��Ƌ��ɂ���v�Ƃ����A�т̃��b�Z�[�W��č��ɑ����Ă���B �@�g���[�j�������͎��̂悤�ɂ������A���Ȃ킿�A �@�u����ꂽ�����ł͂Ȃ��A�č��̓��V�A���A�t�K�����ł��C�������ł��A�����ɓs���̗ǂ��悤�ɗ��p���邱�Ƃ����l���Ă��Ȃ��B���V�A��S�̂Ƃ��Č��悤�Ƃ����Ȃ��B�q�����[�E�N�����g���O���������̃A�W�A��A�����ɂ��A���V�A��1�s���o�ꂵ�Ȃ������B�I�o�}�ł��낤�ƃW�����E�}�P�C���ł��낤�ƁA�ǂ̕č��̐����Ƃ����V�A�Ƃ̑Θb�Ŗ��m�ȖڕW�������Ă��܂��Ă���v �@�e�Ĕh�Ƃ��ڂ���邱�̏������A�����܂ŕč���ᔻ����̂����ɂ����̂͏��߂Ă������B �@���W�I�����ǁu�G�[�z�E���X�N���C�i���X�N���̖ؗ�j�v�̃x�l�f�B�N�g�t�ҏW���́A���������č��̂����ɑΛ�������Ȃ����V�A�́A���炪�\���ɕێ�I�ł͂Ȃ��������炱������܂ő���������ꂽ�A�Ɖ��߂��A�ΕĐ���̊�{�́A�������v�����Ƃ����p���ɂȂ����A�Ƙ_����B �@����ɁA�O�o�E�N�����j���N�������́A�u�ċc��ł́A�č��������V�A���������Ă�20�N��̂��̌��ʂ܂��Ĕނ炪�č��Ɏ��������Ă��Ȃ��ƒN��������̂��A�Ƃ������c�_�����s���Ă���A�ΘI�x���S���̂Ă���Ă��Ȃ��v�Ǝw�E����B �@MGIMO�i���X�N�����ۊW��w�j�̃g���C�c�L�[�y�������A�č����������ȊO�̍��ɑ��Ă͒����I���v��^���悤�Ƃ͂����A�������烍�V�A�͌b�W�����҂ł��Ȃ��A�Əq�ׂ�B �P�Ȃ�J�����炵�ɂ��������Ȃ����V�A�̑Ή� �ĘI�A�V���A���w����Ɋւ�����ۗ����c�Ăō��� 27���ɂ��̌�
���A�����ɉ�k����W�����E�P���[�č��������i���j�ƃ��V�A�̃Z���Q�C�E���u���t�O���i2013�N9��24���j�kAFPBB News�l �@���̑Εĕs���A���邢�͕���A�ΕđΓ���v������C���ɏ����Ă����̂��낤���A�č����猩��A�匠���ƁA���ۗ��A�j�e���ł͂��ꂪ�������Ă���̂ɁA����ȏ�̉������V�A�����߂悤�Ƃ��Ă���̂�������Ȃ��A�ƑO�o�̓��{�̕č����������҂̕��͕č��̍��f���������B �@������Ȃ�����A���Ƃ��邲�Ƃɕč��̓������ז����悤�Ƃ��郍�V�A�̑ΕđΓ��v���́A�P�Ȃ�ΕėJ�����炵�ɂ��������Ă��Ȃ��A�Ƃ������ƂɂȂ�B �@���肪����Ȕy�Ȃ�A�����ɑ哝�͉̂����������Ă���̂��A�Ƃ����ᔻ���ċc��ŗN���N����B�����āA�č��̌��Ў��ĂȂǂƃ��f�B�A�ɒ@�����A����͉��Ƃ��Ă��䖝�Ȃ�Ȃ��B���V�A�͂����������̔s�퍑�ł���B���̔s�퍑�������̂����ɏ��҂̕č��ɏ|�˂��̂��B �@�����������͋C�f���Ă��A���钘���ȕč��̍��ۏ�]�_�ƂȂǂ́A���V�A�͍���̃V���A���ŏ���������������Ȃ����A�������̂͒N���x�����Ȃ��V���A�Ƃ����u�Ȃ炸�ҍ��Ɓv�Ƃ��J��[�߂����Ƃ����ł���A���E�ɂ܂݂ꂽ���N�̓~�G�\�`�ܗւ́A���̐��e���⓯�����ҍ��ʂƂ��������V�A�̐����p�������e�����ɂ��Ȃ肩�˂Ȃ����낤�A�Ƃ��q�X�e���[�C���̘_���Ă���B �@��قǁA�v�[�`���哝�̂ƃZ���Q�C�E���u���t�O���̃R���r�ɂ��Ă��ꂽ���Ƃ��A���ɐ������˂�̂��낤�B �@�v�[�`���哝�̂̊�e���ɑR���邩�̂悤�ɁA�}�P�C����@�c���͎���̎咣�����V�A���Y�}�@�֎��̃v�����_�Ɋ�e�i9��19���t�j�����B �@���Ńv�����_�H�Ȃ̂����A���̓��e�͎�������V�A�x���h�Ə̂��āA�u�����烍�V�A�����̂��߂ɂ��v�[�`���哝�̂�ǂ��o���ׂ��v�Ƃ������ᔻ��F�ł���A�v�[�`���哝�̂̊�e���ɔ�ׂ�A�ǂ��ɂ��i�������Ă���悤�ɂ��������Ȃ��B �@�O�o�̃x�l�f�B�N�g�t�ҏW���́A�����v�[�`�������č��ɐ��܂�Ă����Ȃ�A���a�}�E�h�ɑ����ă}�P�C�����ׂ̗ɍ����Ă������낤�A�ƕ]����B��e���̏o���̗ǂ������͂Ƃ������A2�l�͐����ƂƂ��Ă͈ӊO�ɋ߂��^�C�v�Ȃ̂�������Ȃ��B �@�����ʂŐ�������ᔻ����Ă��铯�����ҍ��ʂ͂��Ă����āA���̐��e���ɂ��ẮA9��7���ɍs��ꂽ���X�N���̎s���I�ŁA�����^�}���u���\�t�ƓD�_�̓}�v�ƌ������ᔻ���Ă����i���@�[���k�C�����A�s�ꂽ�Ƃ͂����\�z������P��Ƃ������ʂɂȂ����B�����̃��f�B�A�́A������v�[�`�������ւ̑Ō��ƌ��`����B �v�[�`������e�f�ڂ́u�j���[�X���v�d���̂��߁ANY�^�C���Y���ߖ�
�j���[���[�N�E�^�C���Y���̓v�[�`���哝�̂̊�e���f�ڂ������Ƃɑ���ߖ�����9��12���ɍڂ����kAFPBB News�l �@�����A���̃i���@�[���k�C���ɂ��Č�������V�A�̕����̐��Ƃ́A���𑵂��Ĕނ��ێ�Ȃ̂��v�V�Ȃ̂��͂܂�������Ȃ��A�Əq�ׂĂ���B �@�����œ|��ނ�����ł��A�����D�悵���ꍇ�̃v���O�����ɂ͕ێ�E�v�V�̑o���̃��j���[����荞�܂�A���̂��߂ɖ�̂悭������Ȃ����̂ɂȂ��Ă���Ƃ����B �@���X�N���E�J�[�l�M�[�Z���^�[�̃V�F�t�c�H�[���@�㋉�����o�c�ҁiSenior Associate�j�́A�ނ͌N�吭���ɔ��͂��Ă��炸�A�v�[�`���哝�̂ɔ����Ă���݂̂ł���A���x�����ł��狌�h�ł����h�ł��Ȃ��A�Ƒf�`����B �@�����Ε����قǁA���V�A���E���獶�ɑ傫���Ђ�����Ԃ�Ƃ������b�Ȃǂł͂Ȃ��悤���B���{�ɗႦ��Ȃ�A�������ߋ����̍��E���ނɂ͕K���������Ă͂܂�Ȃ��u�ېV�̉�v�ɋ߂����݂̂悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ��̂��낤���B �v�����m�̘b���������ł��Ȃ����{�̐����� �@���̓��{�ɂ��ẮA�����Ă��������͑����͂Ȃ������B�̓y���ɂ����炩��̎��₪�W���������߂��������낤���A����肪�����Ă��A�v�[�`���哝�̂�V�A���{�̎p���͊ȒP�ɂ͕ς��Ȃ����낤�A�Ƃ����ٌ������̓����ɏ��X�߂��Ă�����B �@���̒��ŃV�F�t�c�H�[���@���́A�u�I���ԂŃA���[���͂̓�������̓y��肪���������̂́A����閧���ɉ^����ł���A����ɔ�ׂĖk���̓y���̓I�[�v���ɂȂ�߂��Ă��܂��Ă���B�]���āA�o���Ƃ��ɏ���������v�Ɗ��z��R�炵���B �@�ӂƎv�����̂����A�ŋ߂̓��I�Ԃ̌��Ń��V�A�����A�u�Â��ȗ������������͋C�̒��ł̌��v�ƌJ��Ԃ��Ă���̂́A���̂��Ƃ��w���Ă���̂ł͂Ȃ����낤���B �@������A�����ɒm�炵�߂��ɐ��{�Ԃ����Ō���i�߂đÌ��Ɏ������ނ��Ƃ́A�������s�\�ł��낤�B���ɓ��{�ɂ����ẮA�ł���B �@�����A����Ƃ����銴��������܂�Ă��鍑����ۂ̉^�����A���ۂɗ̓y���������ł���̂��A�Ɩ₦�A���Ȃ��Ƃ�����܂ł́A���ΐ��_�_�Ƃł������ׂ��u�S�苭�����v�Ƃ������䎌�����c����Ă��Ȃ��������Ƃ��������낤�B �@���̌��������ׂďO�ڂɎN���`�ōs�����Ȃ�A���炭�܂Ƃ܂�b�͖��Ɉ�ɂȂ��Ă��܂��B���҂������Ɉ����Ȃ��Ȃ��Ă��܂����炾�B �@�ŋ߁A�r�U�Ȃ��n�q�Ŗk���̓y��K�₵�����{�̐����Ƃ��A�̓y�Ԋҗv�������ɂ������Ƃ����V�A�O���Ȃ���莋�����̂��A�ނ炪���{�ɑ��āA�u�������������ɂ��āA�{�i�I�ȃv�����m�̘b���n�߂悤�ł͂Ȃ����v�Ɨv�����Ă�����Ȃ̂�������Ȃ��B ������ė��̂��ۂ��B�Ђ���Ƃ������t���ւ̑Ώ�������ۑ肩������Ȃ��B
�@
�@
�@
�@
JBpress>���{��>���h [���h]
��t�̎����x�z���}��
���̂Ƃ��A�����J�͏����Ă���Ȃ�
2013�N10��03���iThu�j �k�� �~
�@����A�A�����J�̃V���N�^���N�i�E�B���\���E�Z���^�[�j�ŁA���ؐl�����a���Ɋւ���V���|�W�E�����J���ꂽ�B�e�[�}�́A�ŋ߂̓��V�i�C�Ȃ�тɓ�V�i�C�ł̓��ח̗L�����߂����Ă̒����̑Γ��{�A�����đt�B���s�����d�p���������ɉ��߂��ׂ����A�Ƃ������̂ł������B �@�f���}�[�N�̊w�ҁi�����f���}�[�N���h��w�����j�Ō��݃E�B���\���������ɂ��Ђ�u���Ă���I�h�K�[�h���m�i��������A�W�A�W�A��V�i�C�����j�́A�u�����̍s����ے�I�ɑ�����̂ł͂Ȃ��A�����ŗL�̓`���I�ȁg���a�I�����h�헪�𐄐i���Ă���Ƃ��������ő�����K�v������v�Ƃ�������|�̎��_��W�J�����B �Β��n�g�h�̊댯�ȋc�_ �@�ޏ��̂悤�Ȓ����Ɋ��e�Ȋw�҂̎咣�ɑ��āA���A�����J�C�R�����Ō��݃V���N�^���N�������iCNA�F���A�W�A�n��ƒ����C�R�����j�̃}�N�_���B�b�g�����́A�u�����̓�V�i�C�Ⓦ�V�i�C�ł̐N���I�s���͂ƂĂ����炩�̐헪�Ɋ�Â��Ă���ƌ��Ȃ����Ƃ͂ł��Ȃ��B�����͂��Ă͑��q�̂悤�ȑ�헪�v�z�Ƃݏo���A���̐헪�I�`�����p���ł���ƍl�����Ă������A�ƂĂ����݂̒����̐���҂����͑f���炵���헪�̓`���������p���ł���ƍl���邱�Ƃ��ł��Ȃ��v�Ɛ^�������甽�Έӌ����Ԃ����B
�I�h�K�[�h���m�̒����wChina and Coexistence�x
�@���́u�����̕��a�I�����헪�v�Ɋւ���c�_�́A�����ɂ�铌�V�i�C�Ɠ�V�i�C�ł̋��d�ȗ̈�m��s���Ɋ֘A���āA�����̐헪�i���邢�͐헪�炵�����́j���ǂ̂悤�ɕ]�����ׂ��Ȃ̂��H�@�Ɋւ���c�_�ł����āA���{��t�B���s���̑Β��R���A�A�����J�ɂ����{��t�B���s���ւ̎x����Ƃ����������I�ȋc�_�Ƃ͈�����悷����̂ł���B
�@�������Ȃ���A�����̓��V�i�C�Ȃ�тɓ�V�i�C�ł̍����̊g����`�I�s�����ǂ̂悤�ɉ��߂���̂��Ɋւ���A�J�f�~�b�N�ȋc�_�́A�A�����J���{�Ȃ�тɘA�M�c��A�Β��헪����ёΓ��E�t�B���s���x���헪�����肷��ۂɁA���Ȃ���ʉe��������ڂ����ƂɂȂ�B �@�A�����J�ŋ���Ȑ��͂�U����Ă��钆�����r�C�́A�u���a�I�����헪�v�̂悤�Ȓ����ɂƂ��čD�s���Ȉꌩ�g�w�p�I�h�咣���A�A�����J�̃��f�B�A�E�A�M�c��E���{���@�ւȂNJe���ʂɗ��z������ł��낤�B �@�����āA���������u���a�I�����v��ڎw���Ă��钆���ɑ��ē��{����Ȃȑԓx�Řb�������ɂ��������A�����̌������ɑ��đS���������������Ȃ����{���������{�ƒ����̂����ē��A�W�A�����̕��a�I������j�Q���Ă���A�Ƃ������v���p�K���_�𐄂��i�߂邱�Ƃ͖ڂɌ����Ă���B ��{�I�ɐ�t���ɂ͖��S�ȃA�����J �@�c�O�Ȃ���A���炪���{�h�q�Ɋ֗^���Ă���R�W�҂⌤���ҁA����ɃW���[�i���X�g�Ȃǂ������������̐l�X�������ẮA�A�����J�̈�ʍ����͂������̂��Ɛ����ƁA�R�W�ҁA���{�W�҂̑命���͐�t�������ւ̊S���Ȃ���Βm�����Ȃ��B �@�������A�A�M�c��Ő�t���������͂��߂Ƃ��ē��V�i�C���V�i�C�ł̒����R�ɂ��ڂɗ]��e����`�I�ȍs���ɑ�����c���Ȃ��ꂽ��A���{���������܋ꌾ��悷�邱�Ƃ͂����Ă��A��t�������ɍ����S����������ł̌��c�ł���킯�ł��^���Ȍ��O�̕\���ł���킯�ł��Ȃ��B �@�A�����J���{��A�M�c��ɂ���t���ɑ���R�����g�́A���E���́g���߂��Ɓh�Ɍ��o�����Ă����A�����J������I�ɌJ��Ԃ��Ă���u��O���Ԃ́g���߂��Ɓh�ɑ��āA�A�����J�͖ڂ����点�Ă��邼�v�Ƃ����|�[�Y��1�ɂ����Ȃ��̂ł���B �@�����āA�V���A����ɂ����鉻�w����g�p�ɑ���R��������ł��Ȃ������I�o�}�����̎��Ԃ́A���͂�A�����J�����̂悤�ȃ|�[�Y������Ă����ۂɌR���͂𓊓����邱�Ƃ͋ɂ߂Č�������Ԃł��邱�Ƃ����ێЉ�ɘI�悵�Ă��܂����̂ł���B ���ۏ펯�ł͐�t���߂���̓y�����͑��݂��Ă��� �@���̂悤�ɁA���Ƃ��Ɛ�t�������߂�����{�ƒ����̑Η��ɊS���m�����Ȃ��A�����J���{��A�M�c��A����ɕč����f�B�A�ɂƂ��ẮA�u���{�������̓y�Ƃ��Ď{�������s�g���Ă���Ǝ咣���Ă����t�����ɑ��āA�������Y�}���{����p���{�����ꂼ�ꎩ���̂ł���Ǝ咣���Ă���v�Ƃ����q�ϓI�����̑��݂����ŁA�u��t�����͗̓y�����n��ł���v�ƍl���Ă���͖̂�������ʂƂ���ł���B
�A�����J�E�G�l���M�[���ǂ��쐬�����n�}
�@�܂��āA���{�������̂Ƃ��Ă����t�������ӊC��ɁA��͂�̗L�����咣���钆���̌��D������y�����������x�����͒��܂Ńp�g���[���𖼖ڂɂ��ĂЂ�����Ȃ��ɐN�����Ă���A�Ƃ��������ɋN���Ă����Ԃ����āA�u��t�����Ɋւ���̓y���������݂��Ȃ��v�ƍl����A�����J���{�A�A�M�c��A�����ČR�W�҂͑��݂��Ȃ��ł��낤�B���ۂɁA�A�����J�̃V���N�^���N��f�B�A�͓��R�̂悤�ɐ�t�����Ȃ�тɎ��ӊC����u�����ԗ̈整���n�v�Ƃ��Ď�舵���Ă���B
NewYorkTimes���p������{�̗̓y�����n�}
�g��摜�\��
�@���{���{�ɂƂ��ẮA���ۊ��K�@�I�Ɍ��đS�����@�I�ɓ��{�̂ɑg�ݍ��܂ꂽ��t�����͉��̋^�O���Ȃ����{�̂Ȃ̂ł��邩��A�����������̗̗L���Ɋւ����ȂȂǑ���ɂ��ׂ��Ώۂł͂Ȃ��A���̂悤�Ȗ������ɑ��Đ��ʂ�����g�ނ��Ƃ́u��㞂Ȃ����@���v������̂ċ����Ă��܂��Ɖ��߂��ꂩ�˂Ȃ����߂ɁA�u��t�������߂����ē����Ԃɗ̓y���͑��݂��Ȃ��v�Ƃ̗�����������悤�Ƃ��Ă���B�����A�������̐�t���ӊC��ł̊��������ꂾ���P��I�ɂȂ��Ă��Ă��܂������݁A���{���{�̗��ꂱ�����ێЉ��͊�قɉf���Ă��܂��Ă���̂ł���B
�@�����ď�L�̂悤�ɁA�������r�C���t�����⒆���̖{���𗝉����Ă��Ȃ������҂�W���[�i���X�g�Ȃǂɂ���Ē����𗘂���悤�Ȍ������i�싞��s�E�̂��Ƃ��j�A�����J�⍑�ێЉ�ő���U���Ă܂���ʂ��ԂɂȂ肩�˂Ȃ��B ���{�̎{�����ւ̋^�` �@���{���{���g��ÂȑΉ��h�Ƃ����g������h�̉A�ɉB��āA�u�ϋɓI�ɓ��{�̕��a����������v�w�͂�����������Ă������߂ɁA�������D���p�ɂɉ䂪����Ő�t�������ӊC��̓��{�̊C��V�T����悤�Ȏ��ԂɂȂ��Ă��܂����B�����āA���ێЉ�ɂ͒ʗp���Ȃ����{�Ǝ��̘_���ɂ���āA�̓y�����͑��݂��Ȃ��ƌ����������Ă���A���̌��ʂƂ��āA������������g�ϋɓI�h�ȑR�����̓I�ɂ͎��{���Ă��Ȃ��B �@�i��̂��ꂽ���גD�҂Ƃ̐G�ꍞ�݂ŁA���㎩�q���ɐ������p��\�͂��\�z���悤�Ƃ��铮���������Ă��邪�A�c�O�Ȃ���A���̒��x�ł͓��גD�҂Ȃǂ܂��܂���̘b�ł��邵�A��t�����h�q�́A���̂悤�ȏ����̑Ώ��ł͕s�\�ł���A�h�q�V�X�e���̔��{�I�C�����K�v�ł���j �@���܂ł��A����̂悤�Ɍy�����͒����܂ޒ������D���P��I�ɐ�t�������ӊC���V�T����悤�ȏ������ƁA���ێЉ�̏펯�ł́u��t�����͓��{���{�ɂ��g�{���h���邢�͎����x�z����Ă���̂��H�v�Ƃ����^�₪������Ă��v�����Ȃ��B �@�������A��t�����ɉ��炩�̓��{���{�@�ւ≫��̊������{�݂��邢�͖��Ԃ̎{�݂����݂��Ă���ɂ�������炸�������D�����{�̊C�ɐN�����J��Ԃ��Ƃ����ł���Ȃ�A������P��I�ɒ����D���̊C�N�����J��Ԃ��Ă��A���{�̎{�����̑��݂��̂��̂ɂ͋^�`�͎�����邱�Ƃ͂Ȃ��ł��낤�B ��̓I�Ȏ{�����̍s�g���K�v �@��O���Ԃ̗̗L���ɂ͊֗^���Ȃ��Ƃ����`���I�ȊO����j�̓S�������݂��邽�߁A�A�����J���{�͐�t�����Ɋւ��Ă����̗̗L���ɂ��Ă̗���͖��炩�ɂ��Ă��Ȃ����A��������Ȃ��B�������Ȃ��猻�݂܂ł̂Ƃ���A��t�����Ɋւ���A�����J���{�����̃R�����g��A�M�c��c�Ȃǂł́u��t�����͓��{�̎{�����ɂ��邽�߁A���Ĉ��S�ۏ����5��K�p�̑ΏۂƂȂ肤��v�Ƃ���Ă���B �@���݁A�����ċ߂������ɂ����Ė�����ɂ������Ԃɖ{�i�I�푈��Ԃ������N������Ă��܂����ꍇ�ɂ́A����܂Ō��ʓI����h�q�\�͍\�z��ӂ��Ă������{�́A�ۂ����ł��A�����J�̌R���͂ɗ��炴��Ȃ��ɒu����Ă���B �@��t�����̗L��肪�������ƂȂ��ē����R���Փ˂��u�������ꍇ�u��t���������{�̎{�������ɂ������ɂ����Ắv�A�����J���{�i�I�R������ɓ��ݐ�\�������݂���i�������A���Ĉ��ۏ���5���Ɋ�Â��āA���{�ɉ��R�𑗂邩�ǂ����̈ӎv����́A�����I�ɂȂ����킯�ł͂Ȃ��j�B �@�Ƃ������Ƃ́A��t�����ɑ�����{�̎{�����s�g�A����������x�z�ɑ��āA���ۏ펯���猩�ċ^�`�������Ă���悤�ȏ��ɂ����ẮA�A�����J���{��A�M�c����ۏ��̓K�p���̂��̂������邱�Ƃ͂قڊԈႢ�Ȃ��B �@�{�R�����i9��26���A9��5���A8��8���Ȃǁj�ł��J��Ԃ��w�E���Ă���悤�ɁA�R���\�Z���k�����āA�ƂĂ���O���Ԃ̝��ߎ��ɌR���𑗂荞�߂Ȃ��Ȃ����A�����J�ɂƂ��āA����܂łɂȂ���K�͂Ȏx�����K�v�ɂȂ�ł��낤�����푈�ւ̌R������Ȃǂ́A�ł�����o�������Ȃ�������1�ł���B �@��t�����ɑ�����{�ɂ������x�z���ڂɌ�����`�Ō�������Ă��Ȃ��ꍇ�A�i���ݒ��ʂ��Ă��������@�������Ă������́j�R������ɓ��ݐ肽���Ȃ��A�����J�Ƃ��ẮA�u���{�̎{�������y��ł���Ƃ͔F�߂��Ȃ��v�Ƃ������������R���������Ă邱�Ƃɂ���āA�������ɑ���`���̗��s����������Ƃ������ۓI�M�p��ቺ�����邱�ƂȂ��A�NJO�������ێ����邱�Ƃ��\�ɂȂ�B �@���������āA���{���A�����J�̌R���I�x�������҂���̂Ȃ�A�����ɖڂɌ�����`�ł̍��ۏ펯�I�Ȏ����x�z�ɕK�v�ȍs�����K�v�ł���B �@���{�Ǝ��́g�K���p�S�X�������_���h�ɂ���āu�̓y�����͑��݂��Ȃ��v�ƌ��������Ď����x�z������s�������߂���Ă���ƁA���{�ɂ���t�����ɑ���{�����̍s�g�Ƃ����咣�͒����͂��Ƃ��A�����J��������ێЉ�������ɂ���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B �@�W�c�I���q���Ɠ��l�Ɏ{�����́A�u�����Ă���v�Ƃ����Ă��s�g���Ȃ���Ύ����x�z�Ƃ͌����Ȃ��̂ł���B
�@
http://jbpress.ismedia.jp/articles/print/38823 |
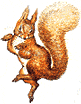

 �X�p�����[���̒����猩���o�����߂Ƀ��[���̃^�C�g���ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B
�X�p�����[���̒����猩���o�����߂Ƀ��[���̃^�C�g���ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B