http://www.asyura2.com/13/jisin19/msg/604.html
| Tweet |
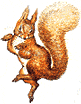
首都直下地震 専門家が警鐘「5年以内にM7以上が17%」
http://gendai.net/articles/view/newsx/148641
2014年3月12日 日刊ゲンダイ

試算した東北大の遠田晋次教授/(C)日刊ゲンダイ
3・11から丸3年たったが、依然として地震活動は活発だ。気象庁は10日、大震災後、青森から千葉にかけての沿岸や沖合を震源に発生した余震数を発表したが、M5以上は56回(1年間)で、前年の84回からは減少したものの、震災前の年平均19回の約3倍に上っている。そんな中、改めて注目されているのが首都直下地震の確率だ。東北大の遠田晋次教授らの試算によると、「5年以内にM7以上が17%」というから怖くなる。
首都直下地震の予測といえば、震災の半年後に東大の地震研究所が「4年以内に70%」という数字を出して、大騒ぎになった。政府見解は「南関東でM7は30年以内に70%」だ。
■最新データに基づく試算
算出方法は似ていて、一定のエリアを定めて、M3クラス以上の地震の頻度を調べる。統計的に地震の数はMが1つ上がると10分の1になるので、M3の頻度からM7以上の数を推計できる。研究機関によって確率が変わるのは、エリアの取り方や集計の時期によって、地震の数が変動するからだ。震災直後の余震が多い時期に広いエリアで集計、解析すれば、当然、確率は上がる。東大の70%はそんな背景から出てきたものだが、東北大の遠田教授の予測は「最新データに基づくもの」だ。それでもまだ、確率がこんなに高い。そこに注目すべきである。
遠田教授は「17%という数字は震災後2年間、首都圏100キロメートルの立方体の中で発生したM3以上の地震を調べて、算出した」という。立方体とは、縦横100キロ、深さ100キロのエリアという意味だ。震災後2年たっても、地震が大して減っていなかった。
「3・11以前はM3以上の地震は1日当たり平均0.15回でした。それが大震災以後、約4倍に増えた。それで17%という数字になったのです。そうしたら昨年11月、関東地方でM5クラスの中規模地震が3週連続で起きた。もう一度、地震の回数を調べたら依然として、1日平均で震災前の3倍近く頻発していて、高止まりしていた。今年の3月8日までのデータも調べてみましたが、若干、減ってはいるものの、高止まりの傾向は変わりませんでした」(遠田晋次教授)
■東北大の試算は脅しではない
首都圏の地盤がいかに緊迫しているかがよくわかる。とくに昨年11月の3週連続地震の震源は、1921年の龍ケ崎地震(M7)や1855年の安政江戸地震の震源に近かった。ますます不気味になってくる。
「こうした地震の多さをどう見るかです。大震災で生じたプレートのひずみが関東まで伝わっていて、房総沖でゆっくり滑っている。その速度が速まり、勢いがついている可能性があります。小さな地震が頻発すると、ひずみが解放されるという考え方もありますが、危険です。小さい地震が起これば、大きな地震が起こり得る。17%という数字にとらわれず、震災前に比べて、危険度が2、3倍になっていることを自覚すべきです」(遠田晋次教授)
首都圏に住むのは依然として、命懸けなのである。
 スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。