03. 2013年9月11日 09:49:45
: niiL5nr8dQ
「本当はいまが研究のチャンス」、原子力規制委員会・島崎邦彦委員長代理に訊く「南海トラフ巨大地震」は予知できる!? 地震予知の“最前線”でズバリ聞く(3) 2013年9月11日(水) 渡辺 実 、 水原 央 内閣府の南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ(以下、南海トラフWG)が「確度の高い地震の予測は困難」と発表して以来、メディアでは「もうどうせ予知なんてできないだろう」という否定的な見方が広まった。東海地震の予知・予測のため約40年間、黙々と観測をつづけてきた気象庁さえ、このまま現体制での業務を続けられるかは未知数で、「いまはまな板の上の鯉の気分」と話した。では、地震研究に長年携わってきた研究者たちは、この発表をどう受け止めたのか。現在は原子力規制委員会の主要メンバーとして活躍する元日本地震学会会長、そして元地震予知連絡会会長の島崎邦彦氏を直撃した!
「知ってるかい水原くん。先日、NHKが放送した地震特番の『MEGAQUAKE III』の視聴率、同時間帯のTBSのドラマ『半沢直樹』にボロ負けだったそうだよ」 六本木にほど近い、原子力規制庁が入るビルの前で待ち合わせた“防災の鬼”、防災・危機管理ジャーナリストの渡辺実氏は、やぶからぼうにそう言った。 「まあ、『半沢直樹』は大ブームですからねえ。面白いし……」 と言いかけたライター水原に、渡辺氏の雷が落ちる。 「まさかとは思うが、君も『半沢』派かね! 防災の取材を志すものが、地震よりドラマとは!」 いえいえ、ドラマはビデオに録ったんですよ〜。しかし、東日本大震災から、はや2年半。巨大地震が日本に与えたショックは次第に収まり、地震・防災への関心も、残念ながら低下しつつある。 「危険だよ水原くん。みんながまたあのときの恐怖を忘れて、反省を活かせなければ、再び多くの人が命を落としてしまう。ぶら防だけは、地震や防災の話を伝えつづけなければ……」 と、いつもにまして勇ましい足取りで原子力規制庁内に向かう渡辺氏だ。
超多忙のスケジュールにもかかわらず時間を割いてくれた島崎氏
取材会場は真新しい机の並ぶ会議室。新設された原子力規制庁は、体制の拡充を図るため、大手町からここ六本木近くの新しいオフィスビルに移転したばかり。官庁というより企業のオフィスのようにたたずまいが洗練されている。
チームぶら防が席に着くと、間をおかず、 「やあ、渡辺さん。本当にお久しぶりですね」 と、今回の取材相手が現れた。原子力規制委員会で委員長代理を務める、島崎邦彦氏だ。日本地震学会、そして地震予知連絡会の会長を歴任した、日本の地震学界のオーソリティである。 取材時間はきっかり30分! にこやかに席に着いた島崎氏。我らが“防災の鬼”、渡辺氏とは旧知の仲だ。だが、島崎氏が地震予知連絡会の会長を辞して、原子力規制委員会のメンバーになってからは、あまりの多忙さに連絡を取るタイミングもなかったという。 「今回の取材も、きっかり30分だけとうかがっていますから……」と、ふたりが旧交を温める暇もなく、取材は始まった。
信頼し合う仲の島崎氏だからこそ、忌憚のない意見を訊きたいと意気込む渡辺氏
実は、取材の申込みを取り次いでくれた原子力規制庁の職員によれば、取材時間は本来、きっかり20分。ただ、今回は渡辺氏の取材ということで、島崎氏が10分間、時間を延長してくれたのだ。
「今回の取材は、いま島崎先生が取り組んでいられる原発関係の話ではないんです。
内閣府の南海トラフWGが『巨大地震の予測は困難』と発表したことについて、地震の予知・予測の研究にずっと向き合ってこられた研究者の立場から、どう考えているか。東海地震の予知体制、そして大震法には、どんな影響があるか。お忙しいのは重々分かったうえで、ぜひご意見をうかがいたいと思って来ました」 渡辺氏が口火を切ると、島崎氏は穏やかに話し始めた。 「そうですね。何からお話ししたらいいか……。
40年前、大震法ができて、東海地震予知のための観測が始まったときには、いまより非常に楽観的な考えがありましたね。つまり、前兆すべり(プレスリップ)をとらえられれば、巨大地震が来ることがわかるだろうと、シンプルに考えていた。
しかし、これまでの地震や、東日本大震災の経験から、地震現象はもっと複雑だな、そう一筋縄にはいかないなと、地震学界のなかで広く認識されるようになった。あの内閣府の最終報告書は、そういう学界の状況を素直に書いたものだと思いますよ」 島崎氏は少し息をついて、こう言葉を継いだ。 「私は結局、40年前、最初に東海地震に備えようとしたときの期待が、少し大きすぎだったのではないかと思うんです。
日本ではときにそうしたことが起こりがちですよね。大震法という、予知の手続きを盛り込んだ法律、規則を作ったことで、逆に行政的には、予知はできるものだとか、これから予知は確実になっていくんだという意識が生まれてしまった。
しかし、地震学の立場から言えば、実力よりも少し上のレベルで法律ができてしまったということだった。
阪神・淡路大震災や東日本大震災を経験して、このごろは気象庁でも内閣府でも、予知・予測には空振りもあれば見逃しもあるんだよ、とはっきり言われるようになっています。この最終報告書もそういう流れに沿って出されたものではあると思います」 大震法は地震学の実力以上のことを求めている――。学問的なオーソリティの真摯な言葉に、渡辺氏もうなるしかない。 島崎氏はつづける。 「研究者の立場からすれば、あの最終報告書と、大震法制定の頃の予知に対する感覚の違いは、同じものを別の角度から見ているだけ、という気もします。
『地震学が役立つ可能性があるなら』という楽観的な見方と、『確実じゃないなら無理なんだろう』という悲観的な見方。しかし、見ているものは、『地震の予知・予測は難しい』という、まったく同じ事実なんです」 しかし、先生は実際、予知・予測は「できない」と考えているわけじゃないんですよね? 水原の質問に島崎氏は静かにうなずいた。 専門家にも見えない内閣府の意図
てきぱきと、しかし静かに、はぐらかさず。真摯に質問に向き合ってくれる島崎氏との対話は、知的で、どこか心癒されるものだった
島崎氏は言葉を選びながらも語り続ける。
「本当に予測はできないのか。最終報告書にあるように、『確度の高い予測』とがっちり言ってしまえば、それは難しいでしょう。
ただ、もっとゆるく、『何らかの情報を事前に掴めるか』という意味では、まるきり望みがないわけではない。
いま、はっきりとこういうことを世間に向かって言える研究者が少ないのは、地震学界全体が自信喪失しているからかもしれません。
やや科学的ではないかもしれないけど、東日本大震災があって、一種のバッシングと言うんでしょうか、『予知できなかったじゃないか』と言われたこともあると思うのです」 しかし、と渡辺氏は問いかける。 「ゆるい形で何らかの情報がわかったとしても、それを使ってどうするのか。先ほどおっしゃったように、いままでの大震法にもとづく防災体制が、予知の確実性に頼りすぎているとしたら、ますます、いまのままではいけないわけですね。
この連載でも何度も指摘してるんですが、現在の大震法では、ひとたび地震の前兆が見つかったとなれば、警戒宣言が出されて、強化地域内の工場も学校も鉄道も、日常生活のあらゆるものが機能停止してしまう。けれども、ゆるい予測の情報しか出せないなら、そこまでのことをやっていいのか。そのコスト、責任を誰が負うのかという問題が出てくる」 島崎氏は、そうですね、とうなずく。 「地震の予測は、まったくできないわけではないけれども、外れたり、予測できない場合もあって、市民をがっかりさせる可能性が高い。
ならば、その不確実な予知・予測がなされたときには、いまみたいにがっちりした対応を、はたしてとる必要があるのか。例えば、子供とか高齢者の方とか、災害弱者になるような人々だけを、万が一に備えて避難させるというようなことではいけないのか。
地震への対応は画一的ではありません。ではそのなかで、どういう方法を選び取っていくのか。これは、科学者だけではなくて、行政、そして一般市民がディスカッションしていかないと、決まらないのではないかと思うんですね。
しかし、この最終報告書は、ある意味で、それを行政が決めちゃっているようにも見える。 今回の報告書を、内閣府はどういう位置づけで持ってきたか。おそらく、彼らには彼らなりに、内々で考えていることが、すでにあるんだと思うんです。
しかし、その内容がどういったものであるにせよ、本当に行政側からの、上からの決定でいいのか。こういう重大なことを決めるときには、やっぱり研究者や住民も含めた、いろんな人がディスカッションして、それぞれの立場や意見が明らかになったうえで、決めていくものではないかと思うんですね。
そういうことをやらずに、行政がとにかく先に進んでしまうというのは好ましくないのじゃないかと思います」 いま研究を止めるのはナンセンス? 内閣府が描く、予知・予測とこの国の地震防災体制の未来がまだ見えないと話す島崎氏。渡辺氏は元日本地震学会会長である島崎氏に、別の質問をぶつけた。 「ところで、1995年の阪神・淡路大震災のあと、世間ではやはり地震の短期・直前の予知はできないんじゃないか、という話が出ましたね。行政でもそれまでの対応が見直されて、科学技術庁にあった地震予知推進本部が解散して、総理府に地震調査研究推進本部が新設された(現在は文部科学省所管)。
あの頃、地震学界でも、短期・直前予知の研究に注力しすぎてきたんじゃないかということになった。そこで当時、日本地震学会の会長だった島崎先生の主導で、短期・直前予知よりも、発生確率を重視する研究に学界全体がシフトした。
現在、政府などが出している地震の予測で、『30年後までに何%の確率で発生する』としている表現がそれですね。
いま、研究者のコミュニティーでは、何かあの阪神・淡路のときのような大きな方針転換が起ころうとしているんですか?」 島崎氏は一瞬、考えてからこう答えた。 「いまのところ、あのときのような大きな体制の変更はないんですね。ある意味、原発の問題があまりに大きくて、地震に関する問題は表から隠れてしまったような形です。
阪神・淡路大震災後は、行政の側で大きな体制変更があったことも変革のきっかけになりましたが……」 今回はまさに、そのきっかけとなる行政側の方針が不明瞭なのだ。 渡辺氏は、「やはりすべての疑問は、内閣府の方針が明かされないかぎり、解消できないな」とつぶやき、こう語りだした。 「やはり僕は、内閣府がいまなぜ、これを言ったのかということがひっかかっているんだよね。
東日本大震災以降、地震研究や防災に関する動きは、非常に行政主導型になってしまったと思う。島崎先生もおっしゃるように、専門家や自治体、住民との議論もいまだに行われる気配がない。
そういう行政の先走りの行き着くところが、今回の『東海地震の予知も困難である』という発表なんじゃないか、という印象です。
気象庁でも聞いてきたんですけど、稠密な体制で観測を40年間やってきたわけです。その観測・学問領域と、強化地域の自治体の取り組みが、車の両輪のようにかみ合って経験を積み重ねてきたのが、東海地震予知の体制だった。
シンプルに考えれば、いまは予知・予測が難しいとは言っても、今後研究が進んだり、新しい機器が開発されたりして観測の精度がどんどんあがるということであれば、むしろ国はもっと予算を入れて予知・予測に取り組まなければならないでしょう。
そんなタイミングで、予知は困難と言い切ってしまって、あたかも東海地震の予知・予測体制を切り捨ててしまうかのような印象を世間に持たれるのは、まったくのナンセンスだと思うんですね」 大震法の体制を壊さず、ゆるめることができないか さらに、渡辺氏はつづける。 「大震法を作るとき、主導したのは当時の国土庁でしたが、気象庁の担当者も専門家もみなひざを突き合わせて議論をしましたよね。
ところが、今回、気象庁で話を聞くと、自分たちもこの先のビジョンというのはわからない。内閣府次第です、というんです。
何というか、いまは連携すべき人々の間に、線が引かれてしまっているように見えるんですよねぇ」 島崎氏もこれには大きくうなずいた。“防災の鬼”は、島崎氏の考える今後の東海地震や南海トラフ巨大地震の観測のあり方を問うた。 「東日本大震災までの地震の経験で、大地震は前兆すべりがありました、はい大地震です、なんて、そんな単純に起こるものではないとわかった。
ならば、次のステップとしては、もっと充実した研究体制を作るなり、前向きな行動をとることもできるんじゃないか。
気象庁では、シンプルに考えれば、東海地震から南海トラフに観測対象が広がるならば、観測態勢も広がるのではという意見もありましたよ。つまり、大震法にもとづく強化地域自体も、広げる方向性もあるのではないか、と」
かつては学界を主導した島崎氏。いま、一歩引いた立場からは、日本の地震研究の状況がどう見えているのだろうか
それもひとつの考え方でしょう、と島崎氏は答える。
「先ほども言いましたが、僕自身は、東海地震に関するいまの体制は、いったん緩めたほうがいいんじゃないかと思うんです。
あれがあるために、いろんなものが動かない。動かせない。つまり、予知・予測に近いことがこの研究でできますよ、となってくると、じゃあ、それで警戒宣言を出すのか、外れたら責任はどうとるのか、というような話が、研究者にのしかかってきてしまう。
そうやって、研究者もみんな、ある意味でがんじがらめになるんですね。だから、ちょっとゆるめた形はありえないのか、ということを、まずみんなを集めて議論することがいいんじゃないかと思う。
それは、せっかくつづけてきた観測や訓練を、ゼロにしてしまうというんじゃないんです。ゴッソリと取り去ってしまうのはもったいない。だけど、いまのままの形で続けていくのは非常に難しい」 “防災の鬼”はするどく突っ込んだ。 「それではやはり、大震法全体を見直すということになりますか」 島崎氏はそうですね、と穏やかに答える。 「あれ自身を見直さないと。大震法はかなり、がっちりと研究者も自治体も住民も縛っていますから」 予知研究はいまやるべきテーマ 約束の取材時間30分も終わりに近づいた。“防災の鬼”、渡辺氏はため息がちに問いかけた。 「しかし、今回の最終報告書は、どうしてこういう形で情報発信をすることになったんでしょうねぇ。メディアでは『予知は困難』という話ばかりが取り上げられたけれども、内閣府だってそういう風にメディアが単純化して伝えることは、わかっていたと思うんですよ」 島崎氏も苦笑して答える。 「この報告書を作るときには、それほど内閣府が何か意図をもって介入したとも思えないんですね。素直に専門家の意見を聞いたんでしょうけども、我々研究者にはメディアでうまく取り上げてもらうようにするとか、そういうセンスはありませんからね……。
繰り返しになりますが、取りまとめる側が、どういう意図でこれをやったのかは、見えないですね。困っちゃいますね」 渡辺氏は地震予知連絡会の会長でもあった島崎氏にこう問いかけた。 「先生だったら、どうされます? もし、先生がいまの状況で予知連のヘッドだったら、内閣府から『予知は困難』と出てきたときに、どういう対応をされますか」 そうですねぇ、と島崎氏は思案顔になる。 「たとえ、予知連で議論したとしても、学問レベルで予知・予測の現状を評価してみれば、この最終報告書とそれほどちがった結論は出ないと思いますよ。
その意味で、この報告書は妥当と言うか、それほど研究の現実から離れたことを言っているわけじゃない。
メディアでは、この最終報告書の予知に否定的な面が強調されていますけど、じっくり読めばポジティブな面も書かれているんですね。
地震を起こすプレートというのは、いつ、どこでも同じ状態ではない。東北は予知しにくい特徴があったけれども、南海トラフは予知しやすいほうに属しているんだとも書いてある」 島崎氏はむしろ、学術的に見れば、いまこそが地震研究のチャンスなのだと語る。 「予知研究にしても、何にしても、地震の研究で一番の困難というのは、例が少ないということなんです。
しかし、東日本大震災があったことで、本当に多くの貴重なデータが取れました。研究者としては、この経験を無駄にしてはいけないと思います」 これまでは見るべきものを見ていなかった! 研究はこれからが本番だ 「巨大地震が来てほしい、などと願うことは絶対にありませんが、データが取れたいまこそ、地震学が飛躍的に進歩するチャンス」と話す島崎氏
「地震の研究者がこれからやるべきことはたくさんありますが、まずひとつ目は、やはり研究対象になる例をもっと集めることです。
そのためには日本だけでなく、海外の地震にも目を凝らしていく必要がある。海外は観測網のよくないところも多いので、観測体制の整備にも協力していくべきでしょう。
しかし一方で、日本はこれだけ密度が高く、精度もいい観測網を持ってはいますが、きちんと見張っていくということをしないと、せっかくの機会を見逃してしまう。
東日本大震災でも、後からデータを見ると前兆らしいものがあって、ああだったこうだったと過去形で語られていますけれども、やっぱりデータを十分見ていなかったということですよ、はっきり言って。
南海トラフはこれだけ注目されているわけですから、研究者は本当にそこで何が起きているかをしっかりと、常に観測していることが重要だと思います。
気象庁による東海地域の観測は方法も地域も非常に限定的で、ある意味では近視眼的に観測しているけれども、これからは歴史的に見て何が起きてきたかとか、観測対象とする地域を広げるとか、もっともっと総合的な視点を持つ必要があるでしょう。
地震の前に電磁気的な変化が出るという研究もあって、今回の最終報告書でも言及されていますが、それもとにかくきちんと見ていく。何かの方法だけで観測していればいいというわけではないんです。
ですから、いずれにしても予知をするか、しないかに関係なく、観測だけはしっかりしていく必要があると思います」 しかし、若手の研究者のなかでは、「もう予知研究をしても研究費がつかないのではないか」「この分野は当たってもよろこばれない、外れたら怒られるばかりで、研究しても損ばかりだ」と敬遠するむきもあるようですが……、と水原が問うと、 「それこそ、東日本大震災の経験を無駄にしてしまうことですよ!」と島崎氏は言葉に力を込めた。 いまこそ若い研究者に地震学の世界に入ってきてほしい 「いま、地震学の研究に使われるデータは、本当によくなりました。精度も高いし、観測地点も多い。ですから、それを見て新しいことをいろいろ考える人に、どんどん出てきてほしいのです」 先生が若い頃とは、大違いですか? 「いやもう、ぜんぜん、ほんとに、ちがいます。格段のちがいです。僕が若い頃は、『アメリカでは何であんなにちゃんと観測できるんだろう』とうらやましく思っていたけれど、いまではアメリカの研究者もみんな、日本のデータを使っている。
東日本大震災と同じようにM9を超えるような巨大地震が、近年、アラスカやスマトラでも起こっています。しかし、『あとから計算すると、こういうことが起っていたはずだよね』というシミュレーションはできたりしましたが、実際の現場で、地殻がどう動いたかは、ほとんどデータがなかった。
そのデータが、観測体制の整備された日本で取れたんです。これによって、地震学はものすごく進歩するだろうと思います。
我々の業界で言うと、東大に安芸敬一先生という非常に有名な地震学の先生がいました。でも、安芸先生は2005年、1000年に一度とも言われる、この東日本大震災を見ずに亡くなった。これは地震学者としては非常に残念なことなんです。
地震学者にとって、これほどの機会はありません。ですからいまこそ、地震学の研究に若くて優秀な力が必要なんです」 取材中、終始、穏やな語り口を崩さなかった島崎氏だが、この言葉には力がこもっていた。地震学、そしてそのなかにいる予知・予測の研究者は、委縮している場合ではない。いまの機会を逃さずに研究を進めるべきだという強い意志を感じる一言だった。 残念ながら、取材はここでタイムアップ。時間はぴったり30分だ。この日も島崎氏は複数の会議を重ね、原発の敷地に活断層があるか、再稼働に向けた安全審査に移るべきかなど、日本の将来にかかわる事案と向き合っていく。 原子力規制庁の職員に囲まれて、あわただしく退室していく島崎氏に、渡辺氏は「先生!」と最後に一言声をかけた。 「お身体だけは気をつけてください! なんだか少しお痩せになった気がしますよ」 職員の波に押されるように遠ざかっていく島崎氏は、 「ありがとうございます、いまのところ大丈夫です。渡辺さんもお元気で!」 怒涛の30分を終え、ほっとひと息ついたチームぶら防。さすがに“防災の鬼”、渡辺氏も少し疲れた声を出した。 「あー、あっという間の30分だったな。次はもうちょっとゆったりと、どこか景色のいいところに取材に行きたいものだけど……」 「はい、お任せください!」とライター水原。我が意を得たりと声を上げた。 「な、何だい水原くん。ヤケにうれしそうじゃないか!?」 「そうなんです。次回のぶら防は、久しぶりの遠征ですよ。なんと世界遺産に登録されたばかりの、富士山のふもと、三保の松原に向かいます」 なんだって、と渡辺氏は目を丸くした。 「海の幸も楽しみで結構だけど、三保の松原が地震予知とどう関係するんだい、水原くん」 「いやいや、実は三保の松原のすぐ隣に、日本での電磁気による地震予知研究で有名な、東海大学海洋学部の長尾年恭先生の研究室、地震予知研究センターがあるんですよ。
長尾先生は、内閣府の南海トラフWGで、予知・予測の現状をまとめた、『南海トラフ沿いの大規模地震の予測可能性に関する調査部会』のメンバーでもあるんです」 それを聞いて、渡辺氏はなるほど、と笑う。 「科学少年・水原くんはどうしても地震予知の最新研究が見たくてしょうがないんだな。
よし! いま地震予知技術はどこまで来ているのか、長尾先生の話を聞きに行こうじゃないか。富士の絶景とおいしい鮨も楽しみなことだし……」 え? 何ですって? こうしてチームぶら防は、東海道を一路、清水を目指して旅だったのであった。はたして、最新研究はどこまで進んでいるのか。次回もぶら防から目が離せません! このコラムについて
渡辺実のぶらり防災・危機管理 正しく恐れる”をモットーに、防災・危機管理ジャーナリストの渡辺実氏が街に繰り出し、身近なエリアに潜む危険をあぶり出しながら、誤解されている防災の知識や対策などについて指摘する。まずは東京・丸の内からスタート。 |
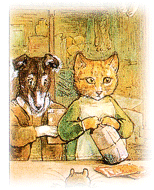
 スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。