http://www.asyura2.com/13/health16/msg/703.html
| Tweet |
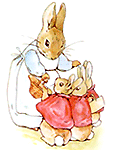

いよいよ忘年会シーズン/(C)日刊ゲンダイ
牛乳、ラーメン、生卵? 巷に溢れる「二日酔い対策」大検証
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/155356
2014年11月30日 日刊ゲンダイ
忘年会シーズンだ。仕事に響く二日酔いは断固阻止するのがサラリーマンの務め。しかし、巷にあふれる対策は、はたして医学的根拠があるのか。「二日酔いの特効薬のウソ、ホント。」(日東書院)の著者である新宿「なかやまクリニック」院長の中山健児医師に聞いた。
「一番の対策は肝臓の代謝能力を超える量のアルコールを飲まないことです。ただ、それができないから、巷には“こうすれば酔わない”“翌日はスッキリ”といった対策があふれているのでしょう。医師の目からみると玉石混交で、バカげたものも結構ありますね」
中山院長いわく、(1)アルコールの分解で大量に消費された水とエネルギーを補給する(2)肝臓の代謝機能を高める成分を摂取する(3)尿や汗、呼気などによってアルコールを体外に排出する――いずれかのメカニズムに沿っていないものは、基本的に眉ツバだ。
その視点で、まずは〈予防法〉について。
●牛乳を飲むと胃に膜ができて酔わない → △
「医学的には全く根拠がありません。ただし、牛乳に含まれるタンパク質には肝機能をアップさせ、アルコール分解を促進する作用がある。あらかじめ飲んでおくことは有効です」
●締めのラーメンは予防になる → ×
「“アルコールのせいで失われた塩分の補給のため”と考える人もいるようですが、医学的には正しくありません。塩分や水分を補給したければ、スポーツドリンクやシジミのみそ汁の方がよほど効果的です」
“締めはカレー”なんて人もたまにいるが、こちらは医学的根拠あり。
「カレーに含まれるターメリックはウコンのこと。ウコンに含まれるクルクミンという成分は、肝機能を高めてくれます」
意外にもオススメは「おしるこ」だ。
「小豆に含まれるカリウムやサポニンという成分は、利尿作用を促して余分な水分や有害物質を体外に排出する働きがあります。さらにサポニンには肝機能を向上させる効果も。砂糖は、アルコール代謝で疲れた肝臓に、エネルギーである糖分を補給してくれます」
●頭痛予防に市販薬を飲んでおく → ×
「消炎鎮痛剤の服用は予防にはなりません。二日酔いになってからのひどい頭痛には効果が期待できます」
副作用の危険もあるので、飲酒時の服用は避けたほうがいい。
気をつけていても朝起きたら頭はガンガン、吐き気もする。どうにかして!
●熱いシャワーを浴びる → ×
「体温が上がると発汗が促され、体内の水分が減ります。ただでさえアルコール代謝で水分が減っている体にはダメージ。心臓への負担も高くなります。ぬるいシャワーか、ぬるま湯に半身浴のほうがいいでしょう」
熱い風呂やサウナもご法度。逆に冷水を浴びるのも、心臓に急激に負担をかけるため、自殺行為となる。
●深呼吸する → ○
「アルコールは尿や汗だけでなく、呼気によっても体外に排出されます。ですので、深呼吸は二日酔い解消に効果的です」
呼吸でアルコールを排出する方法はお酒を飲んでいる途中でも効果的。オススメは「カラオケ」だ。大声で歌おうとすれば、平常時よりも多めに呼吸を繰り返さなければならない。ノリノリで歌えばアルコールを排出できるため、二日酔いのリスクは減る。
●生卵をのむ → ○
弁護士役のポール・ニューマンが、酔い覚ましに生卵をのむ。映画「評決」で印象に残るシーンだ。
「卵黄に含まれるシステインという成分は、有害物質アセトアルデヒドの分解を促進します。卵白のタンパク質にも、肝機能を高める効果がありますよ」
医学的な根拠があったのだ。
ほかにも二日酔いの朝に取るといいのが、「ジャガイモのすりおろし汁」。ジャガイモに含まれるビタミンCが、アルコール分解で発生した活性酸素を除去してくれる上、利尿作用のあるカリウムも豊富に含む。「マイタケのみそ汁」も、マイタケに含まれるβグルカンが肝機能をアップする。意外や「コーラ」も、もともと二日酔い用の薬として発売されたものなので、けっこう効果があるそうだ。
これで年末年始の連チャンも怖くない。
|
|
|
|
▲上へ ★阿修羅♪ > 不安と不健康16掲示板 次へ 前へ
|
|
 スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。