05. 2013�N9��30�� 09:13:27
: niiL5nr8dQ
�y��372��z 2013�N9��30���@���є��� [�J���o�σW���[�i���X�g]
���Y���g�l���݁h�ƂȂ�����ÁE���ُ̈�Ȍ���
���̃}�^�n���E��Ŗ�����D���鏗�������i���j
������{�̐E��ɂ����āA�Z�N�n���A�p���n���ƕ���3��n���X�����g�Ƃ���Ă���}�^�n���i�}�^�j�e�B�E�n���X�����g�j�B���̔�Q�ɑ����Ă���̂́A��ʊ�Ƃ̏����Ј�����ł͂Ȃ��B��ÁE���E�ۈ�Ȃǂ̐��E�Ő��E�Ƃ��ē��������̑����́A�D�Y�w�̕ꐫ�ی�ւ̑܂�ōu�����Ȃ��ߍ��ȐE��ŁA���Y�Ɨׂ荇�킹�̐����𑗂��Ă���B�O��́u��ʊ�ƕҁv�ɑ����A���E�̐E��ʼn��s����u�}�^�n���v�̎��Ԃ����`�����悤�B���l�̖�����낤�Ɠ��镱�����鏗���������A���̂��߂Ɏ��炪�h�����M�����������Ă��܂��\�\�B����ȗ��s�s�ȏ������ɂ��Ă������A���q������i�ޓ��{�̎Љ�ɖ����͂Ȃ��B�i��ށE���^�W���[�i���X�g�E���є���j�u2�l�ڂ����痬�Y���Ă���������Ȃ��v
�}�^�n������ԉ�������E�ُ̈�Ȑ��E
��ÁE�����͂��ߏ��������E�Ƃ��ē����E��ł́A��������ԉ����Ă���B�ꐫ�ی�ւ̈ӎ����\���Z�����Ă��Ȃ���������Ȃ��Ȃ��Ƃ����B�iPhoto:�A�t���j
�}�^�j�e�B�E�n���X�����g�i�}�^�n���j�́A��ʊ�Ƃ����̘b�ł͂Ȃ��B�ނ���A1980�N��Ɂu�����E��ꍆ�v���a��������ʊ�Ƃ����A�����ƈȑO���珗�������Ă����Ō�t����E�Ƃ�������ÁE�����̐�啪��ł́A�l��s������}�^�n���͋N�����Ă����B�����āA���肵���E�Ƃ̑㖼���ł�����������̐��E�ɂ��A�}�^�n�����N�������B
���Ƃ��A�����䗦�̍������E�B���E�͓��{�S�̂Ŗ�133���l�̏A�J�l��������A����7�`8���������ƂȂ�B�Q������̍���҂�������肷��d���͑̂ւ̕��S���d���A�ؔ����Y��4�l��1�l�Ƃ������i���{��ØJ���g���̒������j�B���R�A�����ɂ��}�^�n����Q�����������݂���B �u2�l�ڂ̔D�P�����炢������Ȃ��B�F�A���Y���Ă�����v ���E�̉������b����i�����E30�j�ɂƂ��āA���̌��t�͈ꐶ�Y����Ȃ��h���v���o�ƂȂ��Ă���B���Y�����̂́A����6�N�O�ɂȂ�B��1�q���o�Y��A�Җ]�̑�2�q���h�������A����ޏ��̐V��������D�����̂����R�������B �k�֓��̘V�l�ی��{�݂œ������b����B�Q������̍���҂���삷��̂͏d�J�����B���Y���Ȃ����S�z�������b����́A��1�q�̔D�P�����A��i����u���E���Ȃ̂�����A�D�P��������Ƃ����Ė���ł��Ȃ��Ȃ�Č����Ȃ��B�݂�Ȗ�����Ă���̂�����A���v�v�ƌ����A����Ə�����邱�Ƃ͂Ȃ������B ���ǁA�Y�O�x�Ƃɓ��钼�O�܂Ŗ�ɑg�ݍ��܂�A�ؔ����Y��ؔ����Y�̒����������̂́A��1�q�͖����ɏo�Y���邱�Ƃ��ł����B ����1�N��A���̔D�P���킩�������A���ς�炸��͖Ə�����Ȃ��B�l��s������A�x�Ԃ�������10��ȏ���ۂ���ꂽ�B��i����A�u������Ȃ玫�߂邩�p�[�g�ɂȂ邵���Ȃ��v�Ƃ܂Ō���ꂽ�B ���E�̗��b����ƊŌ�t�̕v�̔N�������킹�āA���ю����͔N�Ԃ�500���~�B�Ƃ̃��[���A�ʋ���Ɍ������Ȃ��Ԃ̈ێ���A��̎q�̕ۈ痿���l����ƁA���b�����߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B ���錩�邤���ɏo�����n�܂�A
���̉�ƂƂ��ɑَ����c�c �D�P9�T�ځA��Ζ����̕��ɂɌ��ȗ\���������B���錩�邤���Ɏq�{����̏o�����n�܂�A�َ������̉�ƂƂ��ɉ����o���ꂽ�B���ꂪ���Y���Ƃ������ς������Ă��M�������Ȃ��B �Y�w�l�Ȃɋ삯���ނƁA���Y�������Ƃ�������ꂽ�B�E��ɗ��Y�̕�����Ɓu2�l�ڂȂ��炢������Ȃ��B���̎d���ŗ��Y�͓�����O�v�ƌ��������ꂽ�B �u����q�ǂ��̖���D�����B���̖��̏d�݂�1�l�ڂ�2�l�ڂ��Ȃ��v�ƁA���b����͍��ł��v���Ď~�܂Ȃ��B ���ꂩ��2�N��A3�x�ڂ̔D�P���킩�����B�E��͕̏ς�炸�A���E���ł���ȏ��͖Ə�����Ȃ��B���x�����Y�̊댯������A�����ӎv�������ď�i�ɖ�ΖƏ���\���o��ƁA�u����ł��Ȃ��Ȃ�āA���ʈ����͂ł��Ȃ��B���݂����Ȏv����������́c�c�v�ƁA�x�E��]�V�Ȃ����ꂽ�B ���Ə��������Ă��炤���Ƃ��ł���A�d���͑�����ꂽ�B�ؔ����Y�̐f�f�����o�Ă���Ԃ͏��a�蓖�����炤���Ƃ��ł������A���Âɂ��ďǏ��܂�Ɨ��b����̎����͂Ȃ��Ȃ�A�Љ�ی����̎��ȕ��S���������}�C�i�X�ɂȂ��Ă����B�v�̎��������ł͉ƌv���ێ��ł����A���ɑ�1�q�̕ۈ痿��ؔ[����Ɍ���ԂɊׂ����B �Y��A�玙�x�Ƃ�1�N�擾���ĐE�ꕜ�A����\�肾�������A�ƌv�̏��甼�N�ŐE��ɖ߂邱�ƂƂȂ����B��i������ĎO�ɂ킽���āu�l������Ȃ��B�����߂�Ȃ����v�Ɠd�b������B ���b����͐���6�����̓���������A�Ăі�ΐl���ɑg�ݍ��܂ꂽ�B�u�D�w�����Ȃ��}�^�n���E��ł́A�Y��̎q��Ē��������d�ł����҂��Ă���v�ƒɊ����Ă���B10�N�ȏ㓭���Ă��A������Ȃ��Ă���ƌ�����20���~�ɓ͂����ǂ����B�d�������߂����Ǝv���Ă��A�����̂��߂Ɏ��߂��Ȃ��B �u�Ǘ��E��x�������l�A�����Ƃ́A��x�ł��������Â̌���ɗ��Ė�̐h���A���̉ߖ��J����̌����Ăق����B�������x��������Ɖ��P���Ȃ�����A�l��s���͑����A�}�^�n���Ȃ�ĂȂ��Ȃ�Ȃ��B�����āA���ꂩ��l�͂��Ȃ��Ȃ�v�ƁA���b����͐؎��ɑi����B 2025�N�ɂ͒c�オ��ĂɌ������҂ƂȂ�A������Љ���}���邪�A�����_�ł����E�͂������A�Ō�E�ȂǕ������Â��x������E�͐l��s���̏��B�D�P��o�Y�A�q��Ċ��ɘJ���s�ꂩ��E������P�[�X�́A�����ď��Ȃ��Ȃ��B ���ߋΖ����Ε��S�ő�ʗ��E
�q�ǂ����Y�߂Ȃ��Ō�̐E�� ����������20�l��1�l���Ō�E�i�ی��t�A���Y�t�A�Ō�t�A�y�Ō�t�j�B�Ō�E�Ƃ��ē����l�͌��ݍ��v�Ŗ�145���l����A���̖�94���������ƂȂ�B���E�Ƃ��Ă������̐E�ƂƂ��Ă���\�I�ȃ{�����[���ƂȂ邪�A��͂藣�E�̗��R�̃g�b�v�́u�D�P�E�o�Y�v�i30���j�ƂȂ��Ă���B �����āA�Ζ����Ԃ̒����A���ߋΖ��̑����A��Ε��S�̏d�����������Ă���i���{�Ō싦��̒������j�B���̔w��ɂ́A�}�^�n���̔�Q�������B�ꂷ��B ���{��ØJ���g���A����́w�Ō�E���̘J�����Ԓ����x�ɂ��A�Ō�E�̐ؔ����Y��2009�N��34.3���ƂȂ��Ă���A1988�N��24.3������10�|�C���g���������Ă���B�����J���Ȃ́w�Ō�E���A�Ə����Ԓ����x�i2010�N�x�j�ł́A�u��1�q�̔D�P�E�o�Y�E�玙�̍ۂɎ������������Ȃ������x���E���x���v��q�˂Ă���A��ʂɂ́u��̖Ə��܂��͖�Ή̌y���v�u���ԊO�J���̖Ə��v���������Ă���B �������ɂ��A�Ō�E�̖Ƌ��������Ă��Ă��Ō�E�Ƃ��ē����Ă��Ȃ��l�̒ʎZ�A�ƔN���́u5�`10�N�����v�i19.3���j���ł������A�����Łu5�N�����v�i18.1���j�ƂȂ�A�o���N��10�N������6�����߂�B ���̂��Ƃ�����A������ËZ�p�̐i���ɔ����������������Ȃ���Â╟���̌���ł́A�D�P���̃}�^�n�����N����₷���A���E�𑣂������ƂȂ��Ă��邱�Ƃ�����������B ����Ə�����Ă������O����
�u���̂܂܂ł͗��Y���Ă��܂��v �u��肪�Ђǂ��Ă��A�����O������߂����Ă��炦�Ȃ������v �s���̖��ԕa�@�œ����Ō�t�̓c���獁�q����i�����E28�j�́A�u����������������i���悤�Ƃ����v�����v�ƐU��Ԃ�B �獁�q����̖��߂�a�@�ł́A�D�P���łȂ��Ă����i����Ō�t���ߍ��ȘJ�����������Ă���B�z�����ꂽ�a���ł́A�V��������Q�����荂��҂̊Ŏ��A�~�}�������ꂽ�ً}���@�܂ŁA�ǂ�Ȋ��҂ł�����Ă���B �ʏ�ł���A�a���͂�����x�����ʂɋ敪������邪�A�a�@�o�c�ɂƂ��Ă̓x�b�h�ғ����������̗v�B����̑̐��Ȃǖ������āA�x�b�h�ɋ�����Ύ��X�Ɗ��҂����@��������B 24����365�����Â��ێ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��a�@�B���1����3�ɕ�����3��㐧���A2�ɕ�����2��㐧���嗬�ƂȂ�B�獁�q����̕a���ł́A�ϑ�2��㐧�x���~����A��͂��������������ԘJ���ƂȂ�B���i8��30���`17��30���j�Ɩ�i16��30���`��9��30���j�ɉ����āA�u�����O���v�ƌĂ��8��30������21��30���܂ł̋Ζ����V�t�g�ɑg�ݍ��܂��B ��͊Ō�t2�l�̐��ŁA�����A���Ă��܂��Ɗ��҂̗[�H�⌟���A�}�ώ��̑Ή��Ȃǂɐl�肪����Ȃ��Ȃ�B���̂��߁u�����O���v�Ƃ����A����݂Ȃ��c�Ƃ��Z�b�g�ɂȂ����悤�Ȍ`�̃V�t�g�ŁA�Z�������ԑт��J�o�[����ړI������B ���ʂ̓��͌���8���Ԃ����A�����O����13���Ԃ̓��ƂȂ�A���v���X5���Ԃł����Ă��c�Ƒオ�o��킯�ł͂Ȃ��B�Ζ����͏��u����މ@�A�����Ȃǂɒǂ��āA�Ō�L�^���������Ԃ��Ȃ��A�����O���ΏI����ɂ���ƃp�\�R���Ɍ������ċL�^���A�I���̂�23���߂��B�����̓T�[�r�X�c�Ƃ��B �{���D�Y�w�́A�J����@��j���ٗp�@��ϓ��@�ȂǂŎ���Ă���A�E��ɖ�ΖƏ���Ɩ����S�̌y����\���ł��錠��������B�������A�����������A�D�w������Ƃ����Č����������킯�ł͂Ȃ��A�}�^�n�������s����B �獁�q����́A��肪�Ђǂ��Ƃ���������Ə����ꂽ���A����́u��È��S������Ȃ��v�Ƃ������R�ł����Ȃ������B2�l�̐��̖�Ő獁�q�������Ȃ��Ȃ�ƁA�y�A�ɂȂ����Ō�t��������1�l��40�l�ȏ�̊��҂��łȂ���Ȃ�Ȃ����炾�B���̕��̌����߂�������悤�ɁA���Αтł̒����ԘJ����������ꂽ�B ��肪�Ђǂ��A�u�Ȃ�Ƃ������O������߂����Ă��炦�Ȃ����v�ƊŌ�t���i�a���̐ӔC�ҁj�ɐ\���o�Ă��A�u���̊Ō�t���ƒ�̎���łł��Ȃ�����v�ƁA�V�t�g�ɑg�ݍ��܂ꂽ�܂܁B��肪�����܂�Ɩ����������A��4��̖�Ƀ����O����5�`6��Ƃ����������B�����ԉߖ��J���ŁA��ɂ����������ăJ�`�J�`�̏�Ԃ������B 1���������������Ēɂ݂������A�Y�w�l�Ȃ���f����ƁA��t����u���Y����\���������B�Ȃ�ׂ������Ȃ��ŋx�ނ悤�Ɂv�ƒ������ꂽ�B���������Ă��A�a���X�^�b�t�ɗ]�T���Ȃ��B��t����͂�������������x�e����悤�w�����ꂽ���A�Ζ����ɉ��ɂȂ邱�ƂȂǕs�\���B ���̂܂�3���قǂ���ƁA���悢�挃�������ɂɌ�����ꂽ�B�����ł���Ǝt���Ɂu�ؔ����Y�̊댯������v�ƌ����Ă��A�u����1���f���Ă݂���v�Ɨ₽�����������ꂽ�B�Y�w�l�ȂŐf�f����������Ă���Ƌx�ɂ��Ƃ�A�\���葁���Y�O�x�Ƃɓ��������A�獁�q����́u���̂܂ܓ����Ă�����A���Y���đ�ςȂ��ƂɂȂ����ɈႢ�Ȃ��v�ƁA�k����v�������Ă���B �l���l��ɂ���E�Ƃł́A������E�����ԘJ�����P�퉻���Ă��邱�Ƃ���A�l�����s�����������B����́A��Ȑl����̌����ƂȂ����V��f�Õ�V�Ƃ������̐��x�̐��������n�����炾�B���������l��s���̏��D�Y�w���}�^�n���ɒǂ����݂₷�����Ă���B����͉���Ō�Ɍ��炸�A�ҋ@�������[��������ۈ�̐��E�ł����l���B �l��s���̔����ł��撣�����̂Ɂc�c
�D�P������ސE�𑣂����ۈ珊�̌��� �u�ۈ�m�Ȃ̂ɁA�����̎q�ǂ����Y�݈�ĂȂ��瓭���Ȃ��v �s���̖��ԕۈ牀�œ����������q����i�����E26�j�́A����Ȗ����ɔY��ł���B22�ŕۈ�m�Ƃ��ē����n�߁A3�N�ڂɂ̓N���X�̐ӔC�҂ɂȂ����B����Ƃقړ����ɁA�w�����ォ����ۂ��Ă������l�ƌ����B�q�ǂ����D���ł��̋ƊE�ɓ��������q����́A�u���������̎q�ǂ�����ĂĂ݂����v�Ƃ������҂��c���ł����B �������A�E������n���Ύq��Ē��̕ۈ�m�͂��Ȃ��B���Ԃ̕ۈ牀�ł͐l���������ė��v���o�����Ƃ���X���������A�l����̂����ޒ�����x�e�����͐��E���Ƃ��Čق��Ȃ����Ƃ������B ���q����̐E��ōŔN���́A29�̒j���ۈ�m�B���q����̐E��Ɍ��炸�A�ҋ@���������̂��߂ɖ��ԕۈ牀�����X�ƊJ�݂���邪�A�ۈ�m�̋������ǂ��t�����A�X�^�b�t�̂قƂ�ǂ��V����o���̐�����B�����͎���16�`18���~�Ɣ������B 1�Ύ��N���X�������q����B�q�ǂ������́A�悭������邪�܂��ӎv�a�ʂ�}�邱�Ƃ��ł���قǘb�͂ł��Ȃ��B�댯�Ȃ��Ƃ̕��ʂ����Ȃ��N��ŁA���ɂł��������������ߖڂ������Ȃ��B���䂪�萶���Ă��邽�߁A���̉������Ђ���������A���݂����������B�܂��܂��Â������N��ŁA�ۈ�m��1�`2�l�̎q�ǂ�����������Ă��₷���Ƃ�����B����Α̗͏����̎d���ł�����B �����ł��l���ɂ͗]�T���Ȃ��B�ۈ�ɂ͎��������@�ɂ��l���z�u�������A�����̕ۈ牀�����̍Œ����肬��ł̉^�c�ƂȂ��Ă���B0�Ύ�3�l�ɂ��ۈ�m1�l�A1�`2�Ύ�6�l�ɂ���1�l�A3�Ύ�20�l�ɂ���1�l�ȂǁB ���q����̃N���X�ł́A1�Ύ�����2�̒a�������}����q�ǂ�13�l��3�l�̕ۈ�m���S���B�ۈ牀�͒�7��30�������8��30���܂ŊJ�����Ă��邽�߁A����3�l�ő��ԁA�x�Ԃ����Ȃ����Ƃ���A�ۈ�m2�l��13�l���݂鎞�ԑт�����B�y�j�̏o�������Ă��A��x�͂��炦�Ȃ����B ���������Ȃ��ŏ��q����̔D�P���킩��ƁA�����́u�q�ǂ��������������ǂ���������B���Y���̑������Ă���̂ɁA����Ă�����H�v�Ə��q����ɑސE�𑣂����B �u���݂܂���A���f�͂����܂���v
�D�Y�w���������Ďd�����x�߂Ȃ����� �N���X�̐ӔC�҂ɔ��F����A�Y������������Ǝv���Ă������q����́A�u���݂܂���B���f�������Ȃ��悤�撣��܂��v�Ǝӂ�A�D�P�O�ƕς��Ȃ��悤�������������A�q�ǂ������Ɣ�蒵�˂��肷�邱�Ƃ�A���X���10�`11���܂ő����c�ƂŁA���̔�J�͔D�P���̐g�ɂ͐h�������B �܂��A�����͖����̂��߁A���q����̔D�P�Ɍ��������Ȃ��B��肪�Ђǂ��ċx�e���Ƃ��Ă���Ɓu1�l����ݐ�Ȃ��I ���ڂ��ĂȂ��ő������āI�v�Ƌ��ԁB�ۈ�m�̃C���C�����q�ǂ��ɓ`���A�q�ǂ������������n�߂�ƁA�X�^�b�t���m�̕��͋C�������B ���̂������q����̑̒��Ɉٕς��N����A��������������o�����n�܂�悤�ɂȂ������A�����͋C�����l�q���Ȃ��u�ӔC�҂Ȃ̂�1�l�O�Ɏd���ł��Ȃ��v�ƉA�������������悤�ɂȂ����B����������u����̐搶����ςɂȂ邩��A�o�Y�Ǝq��ĂɌ����Đ�O�����ق����ǂ��̂ł́H ���������ė��Y������������v�ƌ����A�ސE�ɒǂ����܂ꂽ�B ����̑㖼���������������̐��E�Ɉٕ�
���ΐE���̑����Łu�D�P���فv������ �}�^�n����Q�́A�Љ��K�v�Ƃ���镪��ł����s���邪�A����̑㖼���Ƃ������Ă����������̐��E�ł��ٕς��N�����Ă���B���ΐE�������������ƂŁA�u�D�P�E�o�Y�C�R�[���ق��~�߁v�Ƃ����}�����ł��Ă��܂����炾�B �s���̎����̂œ����{�c�O�q����i�����E32�j�́A��w�@���o����A���̌������Ƃ��č̗p���ꂽ�B1�N���Ƃ̌_��X�V�ŁA�ō���5�N������̌ٗp�B����4�N�ڂɔD�P���킩�������A�E��ŏo�Y���o���������ΐE�������Ȃ������B ���Œx���⌇��������ƁA��i����́u�Ζ��ԓx�̕]���ɋ����v�ƌ���ꂽ�B���̂����u�����Ŕ����o�Y������͂Ȃ��B���������Ȃ�x�ނȁv�ƁA�����肪�����Ȃ��Ă������B �O�q����́u�ł���Έ玙�x�Ƃ��Ƃ��ē������������v�ƍl���Ă������A�O�q����̎��N�x�̌_��͍X�V���ꂸ�A�ق��~�߂ɑ������B�\�����̗��R�́u���N�x�̎��Ɨ\�Z�����Ȃ��v�Ƃ������Ƃ��������A���̓����̑�����5�N�Ԃ͋ߏグ�Ă������߁A������́u�D�P���فv���Ƃ������Ƃ͖����������B ���A�����̎����̂ł͔K�ٗp�������Ă���B�����J�́w�n�������̐E���̋Ζ����Ԓ����x�i08�N9�����\�j�ɂ��A�����̂̐E����27.6�����K�ٗp�ŁA4�l��1�l�̊����ɏ��B���Ɏs�����ł͑������������A3������Ƃ����B2012�N�̒����ł́A����3�l��1�l�Ƃ���ɑ����Ă���B �玙���x�Ɩ@�ł́A�Ј��ɂ��玙�x�Ƃ��擾���錠�������荞�܂�Ă��邪�A�u�@����̎��Ǝ�Ɉ��������ٗp���ꂽ���Ԃ�1�N�ȏ�ł��邱�Ɓv�u�A�q��1�ɒB������i�a�����̑O���j���Ĉ��������ٗp����邱�Ƃ������܂�邱�Ɓi�q��1�ɒB���������1�N���o�߂�����܂łɘJ���_����Ԃ��������A�X�V����Ȃ����Ƃ����炩�ł���҂������j�v�Ƃ��������ɂȂ��Ă���A�n�[�h���������B ���ɁA�D�P��]�ގ����ɔЈ��ł���ƁA�A�ƌp���͂�荢��ɂȂ�B��1�q�D�P�O�ɔЈ��i�p�[�g�E�h���Ј��j�������ꍇ�ɁA�玙�x�Ƃ𗘗p���ďA�ƌp�����������́A������o���̔N��2005�`09�N�̃P�[�X�ł�����4���ɂ����Ȃ��i�����Љ�ۏ�E�l����茤�����́w��14��o��������{�����i2010�N�j�x�ɂ��j�B����͂��͂�A��ʊ�Ƃ����̘b�ł͂Ȃ��Ȃ����B �D�P�͖{���u���߂ł����v���ƂŁA�q�ǂ��͎��͂���u���߂łƂ��v�ƌ����Ă�����Đ��܂�Ă�����́B�����������Ƃ��āA�����������D�P����Ɓu���݂܂���v�Ǝӂ�Ȃ���Ȃ炸�A�@����߂�ꐫ�ی�K��͖�������A�}�^�n���̍ň��̃P�[�X�Ƃ������闬�Y�Ɨׂ荇�킹�̏ŋΖ����Ă���̂����B ���R�A�����ȏo�Y��]�߂A�u�g���u����X�g���X���������́v�ƑސE���ċ����Q���肷��P�[�X��������B���ꂪ���I�Ȑ��E�ɂ��������Ă���Ƃ������Ƃ́A���A�Ō�A�ۈ��K�v�Ƃ���Ƒ�������ʊ�Ƃ̐l�X���x����l�ނ��������ƂɂȂ���A�Љ�ۏ�̋@�\��ቺ�������˂Ȃ��B ���̂悤�Ȏ��Ԃ��i�߂A�Ƒ����݂邽�߂ɗ��E��]�V�Ȃ�������Ј��������A��Ƃ���̐Ŏ����������ނȂǁA���ƃ��x���ł��[���Ȗ�������邱�ƂɂȂ�B����Ƌ����Ƃ��ē����قǘJ���ӎ����������E���̃}�^�n�����E�́A��ʊ�ƎЈ��̃}�^�n�����E�Ƃ͂܂�������Ӗ������B �q�ǂ��̉��l��F�߂Ȃ��Љ��
�l�Ԏ��̂ɉ��l��F�߂Ȃ��Љ�Ɠ��� ��������l�ނݏo���X�^�[�g�n�_�ł���D�P�B�E��̊Ǘ��҂ɂƂ��Ă��A���I��邩�킩��Ȃ����A�����邩�킩��Ȃ������ȂǂƔ�ׁA���������̔D�P����q��Ċ��͌��ʂ������₷���A�̗p�v���[�N�V�F�A�����O�̕��@��͍����₷���͂����B �}�^�n���ɂ��Ă̒m�������m����A�@�����炳��邾���ŏ͈�ς��邾�낤�B�����A�J���W��I�ȐE�ƂقǁA�������ƍ��̐��x���������Ă���A�X�̐E��ł̓w�͂ɂ����E������B �D�Y�w���ɂł����A�}�^�n�������s����E�ꂪ�����Ƃ������{�̎Љ�́A�q�ǂ��̉��l��F�߂Ă��Ȃ��̂Ɠ����ł͂Ȃ����B����́A�u�l�Ԃ��̂��̂ɉ��l��u���Ȃ��Љ�v�Ƃ������������邾�낤�B �������Ń}�^�n������u���A�e�F����悤�Ȃ��Ƃ������ẮA���̊�Ղ��̂��̂��h�炮�Ƃ������Ƃ�Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��B ���u���̃}�^�n���E��Ŗ�����D���鏗�������i��j�v�������Ă��ǂ݂��������B |
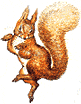
 �X�p�����[���̒����猩���o�����߂Ƀ��[���̃^�C�g���ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B
�X�p�����[���̒����猩���o�����߂Ƀ��[���̃^�C�g���ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B