03. 2013年9月14日 12:42:27
: niiL5nr8dQ
賃金の動向について〜最近の所定内給与・特別給与の変化:マンスリー・トピックス NO.0231.はじめに
我が国の景気は 2013 年に入り持ち直しに転じているが、本年1−3月期、4−6
月期のGDP速報をみると、過去の持ち直し局面と比べ、個人消費の寄与が大きく
なっている。もっともこれまでの消費の好調さは資産効果やマインドの改善を背景
としている側面が強く、今後、引き続き個人消費が上向きのトレンドを維持するた
めには、雇用の拡大とともに賃金の上昇がカギとなってくる。また、賃金の持続的
上昇はデフレ脱却を実現するための重要な基盤でもある。
そこで、本稿では、今回の景気持ち直し局面において、賃金の上昇がどのような
形で生じつつあるのかを確認するため、2013 年に入ってからの所定内給与1
の動向と 今夏の特別給与2の動向について分析する。 2.所定内給与の動向
(賃金改定はおおむね6月までに決定) 本稿の一部では、4−6月期の所定内給与について分析を行うが、多くの企業が
4−6月期に給与の改定を行うことをあらかじめ確認しておく。日本の企業の賃金
改定3は一般的に会社側と労働組合側による協議の上決定される。年初から「春季生
活闘争」と呼ばれる労使交渉が行われ、妥結した企業から賃金改定を適用する。
1
労働協約、就業規則等によってあらかじめ定められている支給条件、算定方法によって支給さ
れる給与でいわゆる基本給などのことを指す。
2
賞与等の一時金のことを指す。
3
賃金の改定には、賃金水準を引き上げる「ベースアップ」、賃金水準を引き下げる「ベースダウ
ン」、企業の昇給制度に従って行われる「定期昇給」、能率手当や役付手当等の「諸手当の改定」、
ある一定期間につき、一時的に賃金を減額する「賃金カット」が含まれる。
決定した賃金改定の適用時期を月別に確認すると、調査産業計では6月までに 85.3%
の企業が妥結された賃金の改定を適用している。特に製造業の適用時期は早く、そ
の中でも機械・輸送については 98.2%が6月までに賃金の改定を適用している(図1)。
図1 産業別賃金改定の適用時期別企業割合
(2013 年のベア実施率は上昇)
(備考)1.厚生労働省「平成24年賃金引上げ等の実態に関する調査」により作成。
2.賃金の改定を実施し又は予定していて額も決定している企業についての数値。
今年度の賃金引上げ状況を確認するために、賃金水準の引き上げを意味する「ベース
アップ(以下、「ベア」という)」を実施した企業の割合を確認する。厚生労働省調査、
日本労働組合総連合会(以下、「連合」という)調査いずれにおいても、リーマンショッ
ク前は 20%を超える企業がベアを実施していたものの、リーマンショック後は厚生労働
省調査では 10%前後、連合調査では 10%を下回る水準で推移してきた。しかし、2013
年の連合調査では 10.7%と5年ぶりとなる二桁の水準に達している(図2)。
図2 ベア実施率の推移
(備考)厚生労働省「賃金引上げ等の実態に関する調査」、日本労働組合総連合「春季生活闘争」
により作成。2013年「春季生活闘争」については、8,770の組合に対して集計を行い、既に協定が妥結し
ている5,575組合のうち594組合(10.7%)が賃金改善を獲得している。3 (一般労働者の所定内給与は増加) 多くの企業で6月までに賃金の改定を適用していることから、以下では 2013 年4
−6月期に焦点を当て、実際の賃金動向について見てみよう。 まず、全ての就業形態を合計した所定内給与をみると、2013 年4−6月期は前年
同期比 0.4%減と前年を下回っている。もっともこれは、比較的賃金水準の低いパー
トタイム労働者(以下、「パート」という)が労働者全体に占める割合が高まってき
ていることが押下げ要因として働いたためと考えられる。そこで、所定内給与を一
般労働者の賃金要因、パートの賃金要因、パート比率要因に分解して確認したとこ
ろ、一般労働者の賃金要因は 2013 年4−6月期においてプラスに寄与しており、伸
び率は前年同期比で 0.1%増と前年を上回っている(図3)。 図3 所定内給与の就業形態別寄与度分解 (備考)厚生労働省「毎月勤労統計調査」により作成。4
(非正規雇用者の増加が所定内給与の減少に影響)
一般労働者の所定内給与の上昇は確認できたが、4−6月期の伸びは前年同期比
0.1%増にとどまっている。こうした弱い伸びの背景として、一般労働者の中に正規
雇用者と非正規雇用者が混在4しており、正規雇用者と比べて賃金水準の低い非正規
雇用比率が上昇していることにより、一般労働者の平均賃金を押下げている可能性
があると推察される5
。
4
「労働力調査」においては、勤め先での呼称によって雇用者を区分しており、「正規の職員・従
業員」以外の者をまとめて「非正規の職員・従業員」としている。また、「毎月勤労統計調査」
では、常用労働者(期間を定めずに、又は1か月を超える期間を定めて雇われているもの等)
のうち、パートタイム労働者(一日の所定労働時間が一般の労働者より短い者等)以外の者を
一般労働者としている。
なお、労働力調査(詳細集計)によると、非正規雇用比率は近年上昇傾向にあり、
2013 年1−3月期は 36.3%、4−6月期は 36.2%と 1984 年から調査を始めて以来
最も高い水準にまで達している。非正規雇用者の増加要因を把握するため、非正規
雇用者数の増加に対する年齢別寄与を見ると、2013 年以降各年代で増加傾向にある。
特に、55 歳〜64 歳で非正規労働者数が増加に転じ、雇用形態別に見ると、パート・
アルバイトに次いで、契約・嘱託が増加要因となっていることには、2013 年4月よ
り施行された高年齢者雇用安定法の改正が影響していると考えられる6
(図4・図5)。
図4 非正規雇用者数の前年比寄与度分解 図5 雇用形態別非正規雇用者の 前年比寄与度分解
(正規雇用者の所定内給与は 2005 年以来の伸び)
(備考)総務省「労働力調査(詳細集計)」により作成。5 以上のように 2013 年に入り非正規雇用者は増加しており、一般労働者の平均賃金
の押下げ要因となっている可能性がある。このため、一般労働者の所定内給与につ
いて、正規雇用者及び非正規雇用者の賃金要因、非正規雇用比率要因に分解すると、
非正規雇用比率要因は、2013 年4−6月期に前年同期比 0.6%ポイント減となって
おり、2四半期連続して平均賃金の押下げ要因となっている。
非正規雇用者比率の影響を除いた正規雇用者自体の賃金要因の寄与をみると、
5
戸田・帯刀(2012)を参照。
6
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律(平成 24 年法律第 78 号)」で
は、継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止や継続雇用制度の対象者が雇用される企
業の範囲拡大等が規定されている。
2013 年4−6月期ではプラスの寄与、伸び率では前年同期比 0.8%増となっており、
2005 年 10-12 月期以来の高い伸びを示している。非正規雇用者については、正規雇
用者と異なり、出勤日数による影響を受けている可能性もあるため、その影響を除
く必要がある。このため、出勤日数を一定と仮定したときの非正規労働者の所定内
給与の寄与を算出すると、2010 年以来となる前年同期比プラスとなっており、非正
規雇用者においても賃金の改善がうかがえる(図6)。
なお、こうした賃金の改定は、ベアのほかにも年齢構成の変化による影響も受け
ると考えられる。このため、厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」の年次データ
を使用して、正規雇用者かつ一般労働者の年齢構成変化の影響について確認した。
この結果、年齢構成による影響は、団塊世代の退職による大幅な年齢構成変化によ
り平均賃金が押し下げられた7
2007〜2008 年を除き、おおむね前年比 0.2%ポイント
の寄与で推移している。2013 年4−6月期の正規雇用者の賃金改定率が前年同期比
0.8%増加しており、このうち年齢構成による影響が 2012 年と同程度であると考え
れば、ベースアップも相当程度行われていると推察される(図7)。 図6 一般労働者所定内給与の雇用形態別寄与度分解
(備考) 厚生労働省「毎月勤労統計調査」、「賃金構造基本統計調査」、総務省「労働力調査(詳細集計)」
により作成。6 7
戸田・帯刀(2012)において、定年を迎えた 60 歳の雇用者の賃金は、退職、継続雇用のいずれ
の場合も平均賃金に対して押下げ要因に働いているとの指摘がある。
図7 一般労働者(正規雇用者)所定内給与の年齢構成変化による影響
(製造業、運輸・郵便、卸・小売の伸びが顕著) (備考)厚生労働省「賃金構造基本統計調査」により作成。7
次に、一般労働者の正規雇用者の所定内給与について業種別の動向を確認すると、
2013 年4−6月期で幅広い業種において上昇が見られ、特に製造業(前年同期比
1.3%増)、運輸・郵便(同 2.7%増)、卸・小売(同 1.5%増)において高い伸びが
確認できる。製造業に関しては、昨年末以降の為替の円安方向への動きなどを反映
して、自動車産業を中心に業績が大幅に改善したことが要因と考えられる。また、
運輸・郵便については国内旅行の増加、卸・小売については個人消費の持ち直しや
エネルギー・資源価格の上昇が背景にあると考えられる。また情報通信業について
は、2013 年も前年比 1.3%増と高い伸びを示している8
(図8)。
8
情報通信産業は、2011 年度は同 2.6%増、2012 年度は同 1.1%増と比較的堅調に伸びており、
2013 年度に特別の動きではない。
図8 正規雇用者の業種別所定内給与
(製造業の所定内給与は前年度の企業収益に連動) このように製造業を中心として幅広い業種で賃金の上昇が確認できたが、企業は
賃金改定の決定にあたりどのような要素を重視しているのかを調べてみる。賃金改
定の決定にあたり重視した要素別企業割合を確認すると、半数以上が「企業の業績」
と回答していることが確認できる(図9)。
そこで、一般労働者の正規雇用者の所定内給与と前年度の経常利益との関係を見
ると、おおむね前年度の経常利益との相関関係が確認できる(図 10)。 図9 賃金改定の決定にあたり最も重視した要素別企業割合 (備考)厚生労働省「毎月勤労統計調査」、「賃金構造基本統計調査」、総務省「労働力調査(詳細集計)」によ り作成。 (備考)1.厚生労働省「賃金引き上げ等の実態に関する調査」により作成。 2.賃金の改定を実施し又は予定している企業及び賃金の改定を実施しない企業についての数値。8 図 10 産業別の一般労働者(正規雇用者)所定内給与と前年度経常利益との関係
(備考)厚生労働省「毎月勤労統計調査」、「賃金構造基本統計調査」、総務省「労働力調査(詳細集計)」、
財務省「法人企業統計」により作成。9 3.特別給与の動向 以上のように所定内給与については、2013 年4−6月期に、製造業を中心とした
幅広い業種で増加していること、また、企業収益が所定内給与と連動していること
が確認できた。
一方、特別給与については、より業績に連動させて変動させると考えられること
から、これまでの特別給与の推移や規模別・業種別の額などを見ることで、今夏の
特別給与の特徴やその要因を概観することとする。
(1)現金給与総額の推移
(現金給与総額は、特別給与の増加により6月・7月ともに前年比プラス)
まず、現金給与総額は 2013 年6月・7月については特別給与が大きくプラスに
寄与したことにより、6月は前年同月比 0.6%増、7月は同 0.4%増となっている
(図 11)。 図 11 現金給与総額の寄与度分解
(備考)厚生労働省「毎月勤労統計調査」より作成。2013年7月は速報値。 2013 年の6月及び7月の特別給与は、ともに前年同月比 2.1%のプラスとなって
おり、3年ぶりの増加となった。特別給与を一般労働者及びパート労働者の特別給
与、パート比率に分けて見ると、パート比率の上昇が特別給与の押下げ要因になっ
ている一方、一般労働者の特別給与は押し上げ要因となっており、伸び率は6月が
前年同月比 2.6%、7月が同 2.3%の増加となった(図 12)。 図 12 特別給与(6〜8月)の就業形態別寄与度分解 (3)企業収益が特別給与に与える影響 (経常利益が1%改善すると、ラグをもって特別給与が 0.12%改善)
ここでは、企業収益が特別給与にどのような影響を受けるのか分析するために、
前年度と前々年度の経常利益に対する当該年度の特別給与の弾性値を推計した。結
果を見ると、調査産業計では、弾性値が 0.12 となり、前年度と前々年度の経常利益
が1%改善すると、当該年度の特別給与が 0.12%改善することがわかる。また、業
種別に見ると、統計的に有意に推定された業種については、全て弾性値がプラスと
なっており、業種別に見ても、前年度以前の経常利益が改善すると当該年度の特別
給与が増加する傾向にあることがわかる(図 13)。 (備考)厚生労働省「毎月勤労統計調査」により作成。2013年7月は速報値。 図 13 特別給与に対する経常利益の弾性値9 (4)事業所規模、業種別の特別給与 (建設業、金融業・保険業、運輸業・郵便業などで特別給与が増加)
2013 年4−6月期の特別給与を業種別にみると、建設業、金融業・保険業、運輸
業・郵便業などで前年比から大きく増加している(図 14)。建設業については、復興
需要や緊急経済対策等の公共投資、首都圏の再開発を中心とした建設需要の高まり、金
融業・保険業については、昨年末から続く株高の効果などで企業収益が改善してい
る。また、運輸業・郵便業でも、昨年末から続く円安の効果により外国人旅行客が
増加したことなどから企業収益が改善している。一方、電気・ガス業については、
原子力発電所停止に伴い業績が厳しいことなどから大幅に特別給与を削減している
(図 15)。
前回の景気持ち直し局面との比較では、製造業の特別給与額の増加幅が小さくな
っている 10 1 0。2013 年についても、昨年秋以降の為替相場の円安傾向により製造業の
9
長期的に、経常利益に対する特別給与の割合が低下する結果となったことについては、今後の分
析の課題である。
10内閣府「景気動向指数の改定及び景気基準日付について」において、第 14 循環における景気の
谷は 2009 年3月であると判定されている。 (備考)1.財務省「法人企業統計」、厚生労働省「毎月勤労統計調査」により作成。
2.業種別弾性値は下記式により算出。 ln(Bonus(t))=10.39+0.080ln(Profit(t=1))+0.040ln(Profit(t=2))-0.027NRR(t)-0.08D(t)
(係数は調査産業計の値) Bonus:夏季賞与 (円)(6〜8月特別給与)
PRofit:経常利益(百万円) ※推計にあたっては、経常利益のラグパターンについてアーモンラグ法を用いている(次数2、前年・前々年の2 期間、終点制約有り) NRR:非正規雇用比率(%)D:リーマンダミー(2009年〜2012年についてD=1とした) 推計期間:1990年〜2012年(食料品、情報通信、運輸・郵便、卸・小売、不動産
については2000年〜2012年)
※白抜きの業種は有意ではない。 3.非正規雇用比率の2001年以前は2月調査の値、2002年以降は1−3月期の値。
4.夏季賞与は6〜8月の特別給与の平均値。12 収益が改善しているが、2010 年については、2009 年から始まったエコポイントの活
用によるグリーン家電普及促進事業やエコカー減税といった政策効果があったため、
特別給与の改善幅は今回よりも大きくなっていると考えられる11
。
図 14 業種別の特別給与(6・7月)(前回の景気持ち直し局面との比較)
図 15 2012 年度の経常利益の対前年度比の伸び(業種別) (備考)厚生労働省「毎月勤労統計調査」により作成。2013年7月は速報値。
(備考)1.財務省「法人企業統計」により作成。
2.電力・ガスは前年度経常利益が1.0兆円の赤字であったため、伸び率を算出できなかった。
11 財務省「法人企業統計」によると、2009 年度の経常利益は輸送用機械で前年比 142.5%増、電
気機械で前年比 78.3%増となっているが、鉄鋼の大幅減少などにより、製造業全体の経常利益
は 10.5%減となっている。
(中小企業で特別給与が増加)
次に特別給与の動向を事業所規模別にみると、2013 年の特別給与は、500 人以上
の事業所で前年比 2.2%増、100〜499 人の事業所で同 0.2%増、5〜99 人の事業所
で同 4.2%増となっている。直近の景気持ち直し局面である 2010 年は、リーマンシ
ョック後の反動増から全体的に特別給与の対前年比の上昇幅が大きいが、同年は資
本金規模の大きい事業所で経常利益が改善しており、このことから事業所規模の大
きい事業所においてより特別給与の上昇幅が大きくなっている。一方、2013 年につ
いては、資本金規模が小さい事業所においても 2012 年の経常利益が改善していたた
め、2013 年6月・7月の特別給与は従業員規模が小さい事業所でも改善している(図
16、図 17)。 図 16 事業所規模別の特別給与(6・7月)(前回の景気持ち直し局面との比較)
図 17 資本規模別の経常利益の伸び(前回の景気持ち直し局面との比較、対前年比)
(備考)厚生労働省「毎月勤労統計調査」により作成。2013年7月は速報値。 (5)小規模事業所における企業業績と特別給与の関係 (小規模事業所では、建設業、運輸・郵便業などで特別給与にプラスに寄与) 次に、特に小規模事業所(5〜99 人)における特別給与に焦点を当て、事業所規
模別に見た特別給与の対前年度比に対する業種別寄与を見た。その結果、建設業が
1.7%ポイントと最も大きく寄与していた。また、運輸・郵便業(0.7%ポイント)、
学術研究・専門・技術(0.7%ポイント)、学習支援業(1.1%ポイント)などもプラ
スに寄与していた(図 18)。 図 18 事業所規模別特別給与(6・7月)の業種別寄与度分解
(備考)厚生労働省「毎月勤労統計調査」により作成。2013年7月は速報値。
(それぞれの業種が特別給与総額に与える影響は、パート比率により異なる)
また、小規模事業所の特別給与と前年度収益の関係を業種別にみると、特別給与への
寄与が大きくかつパート比率が低い建設業、運輸・郵便、学術研究等については、2012
年度の売上高利益率がプラスとなっていることが確認できる(図 19)。したがって、前
年度の好調な企業収益を受けて、当該年度の特別給与を引き上げられたものと推測され
る。
一方、宿泊・飲食業については、2012 年度売上高利益率が前年比で大幅なマイナスに
なっているが、業種全体の特別給与総額への寄与は限定的である。これは、宿泊・飲食
業がパート比率の高い業種であるため、そもそも特別給与を支払う対象者が少なく、収
益の変動があったとしてもそれが業種全体の特別給与総額に影響を与えていないものと
考えられる。特別給与に対する経常利益の弾性値の分析(図 13)でも分かるように、当 該年度の特別給与はそれ以前の企業の収益の状況によって変動し、業種全体の特別給与
総額に与える影響はパート比率の差異によって大きく異なっていると考えられる。 図 19 小規模事業所(5〜99 人)の特別給与と前年度収益・パート比率
(備考)財務省「法人企業統計」、厚生労働省「毎月勤労統計調査」により作成。2013年7月は速報値。
3.まとめ 本稿では、2013 年に入ってからの景気持ち直し局面において、賃金がどのような形で
上昇しつつあるのかを確認するため、2013 年に入ってからの所定内給与の動向と今夏の
特別給与の動向について考察を行った。さらに、賃金が企業の収益にどのように影響を
受けているのかについて分析を行った。本稿で得られた主な結果は以下のとおりである。
○2013 年4−6月期の所定内給与については、全ての就業形態を合計すると前年か
ら減少しているが、パート比率の上昇の影響が大きく、一般労働者については対
前年同期比で増加していた。さらに、近年非正規雇用者が増加傾向にあるため、
その影響を除いて一般労働者でかつ正規雇用者の所定内給与の動向をみると、
2013 年4−6月期は 0.8%増と明確に増加となった。これには、年齢構成の変化
による平均賃金の増加の影響も入っていると考えられるが、それを考慮してもな
お企業によるベースアップが相当程度行われていることが推察される。
○企業の収益と賃金の関係を分析したところ、前年度の企業の経常利益が増加する
と、当該年度の一般正規雇用者の所定内給与が増加する傾向にあることがわかっ
た。また、特別給与についても、多くの業種で前年度及び前々年度の企業の経常
利益が増加すると、当該年度の特別給与が増加することが推計された。
○特別給与については、今年の6月、7月で3年ぶりに前年同月比で増加となった。
今回の特別給与の特徴としては、比較的従業員規模が少ない事業所についても
2012 年に業績が改善していたため特別給与が増加していること、建設業、金融業・
保険業、運輸業・郵便業などでの業績の改善、特別給与の増加が顕著であったこ
となどが挙げられる。 以上の分析を踏まえると、2013 年1−3月期や4−6月期の企業収益の改善を受けて、
2014 年度の所定内給与や夏季賞与も引き続き増加が期待される。 17
〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・
(参考文献)
厚生労働省「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律(平成 24 年法律第
78 号)の概要」
(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/
dl/tp0903-gaiyou.pdf)
戸田卓宏・帯刀雅弘(2012)「賃金の動向とその物価への影響について」マンスリートピックス
No.8(2012)、内閣府
(http://www5.cao.go.jp/keizai3/monthly_topics/2012/0614/topics_008.pdf)
内閣府(2011)「景気動向指数の改定及び景気基準日付について」
(http://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/di/111019siryou4.pdf)
内閣府(2013)「平成 25 年度年次経済財政報告」
(http://www5.cao.go.jp/j-j/wp/wp-je13/index_pdf.html) http://www5.cao.go.jp/keizai3/monthly_topics/2013/0913/topics_023.pdf |
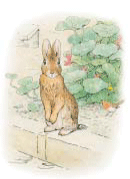
 スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。 スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。