http://www.asyura2.com/13/hasan81/msg/881.html
| Tweet |
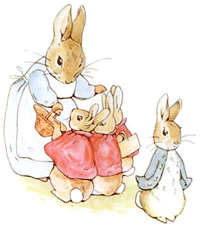
「倍返しだ!」人気ドラマ 『半沢直樹』の世界は本当だった 銀行マンの出世争いはこんなにエグい
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/36711
2013年08月23日(金) 週刊現代 :現代ビジネス
理不尽な上司、不毛な派閥争い、計画倒産する取引先、家族の不満。かつて"エリート集団"と崇められた銀行が、ここまで"ブラック"だったとは。世間の常識が通用しない実録『半沢直樹』の世界。
■部下の手柄は上司のもの
「銀行マンにとって何より大事なのは組織内の序列です。最初の配属からその序列は決まっています。たとえば東京の日本橋支店だと同期内の序列はトップ10圏内ですが、評価が下位なら田舎の支店に配属される。だから序列を上げるのに必死で、とにかく長いものにからめ取られ、ガマンを競うのが銀行マンという生き物なのです」
大手金融機関や総合商社などを何社も渡り歩いた経験を持つ経済評論家の山崎元氏は、銀行マンの世界をこう評する。
そんな銀行を舞台に、上司にたてついてでも筋を通す型破りなヒーローを描いたドラマ『半沢直樹』(TBS系列・日曜21時~)が、評判を集めている。
バブル末期に入行し、20年ほど経った現在、融資課長を務める半沢直樹はある日、支店長から鉄鋼会社への5億円もの融資を無担保で行うよう厳命される。半沢は反対するが、功を焦る支店長に押し切られてしまう。融資からわずか3ヵ月で同社は倒産。銀行から資金をだまし取ろうとした計画倒産だった。
支店長は、全責任を半沢に押し付けようと画策するが、半沢は「やられたらやり返す。倍返しだ!」と、債権の回収と上司の責任追及に闘志を燃やす。
「バブル世代にとって、上司たちは鬱陶しい存在です。銀行業界を不況に陥らせた戦犯にもかかわらず、責任を取らない、といった具合に。だけど今、管理職の立場になったバブル世代は、超氷河期に就職活動を強いられたロスジェネ世代の目にはバブル時代に楽な就職をした無能力者と映っている。いつだって世代間の闘争はあるものです。だから『半沢直樹』の世界は、銀行だけでなく、うちの会社にも当てはまると、世代と男女を問わず働く大人たちに感じてもらっているのではないでしょうか」
ドラマの原作『オレたちバブル入行組』『オレたち花のバブル組』の著者・池井戸潤氏はこう言うのだ。
それにしてもドラマで描かれる銀行マンの世界はエグい。そもそも半沢直樹の父は町工場の社長で、銀行からの融資を打ち切られたために首吊り自殺を選ぶという救いのない設定だ。
では、銀行マンの現実はどうなのか。理不尽な上司がかつては数多く存在したと証言するのが、40代目前のメガバンク中堅行員だ。
「20代の頃は、直属の上司から『アホ』『バカ』『死ね』などと言われました。苦労してまとめた融資案件の稟議書を、『財務分析ができていない。ダメだ』と罵倒されながら、目の前で破られたこともあります。それで追い詰められて精神を病むケースもよく聞きました。
最近は銀行にもパワハラの相談窓口があるため、エグい叱責はなくなりましたが、自分の成績を上げて出世第一に行動するという銀行マンの体質は変わっていません。ドラマにも出てきますが、『部下の手柄は上司のもの。上司の失敗は部下の責任』という風潮は今も残っているのです」
■家を買ったら転勤
顧客を第一とし、経営者の資質や事業計画を見て、融資を行い、回収する。銀行マンにとっての理想だが、こんなことは建て前に過ぎない。ドラマの中で、融資先の倒産によって連鎖倒産する下請け企業の社長に、半沢直樹がこうられるシーンがある。
「銀行は、晴れた日に傘を差し出し、雨の日には傘を取り上げる。銀行員の常識は世間の非常識だ」
三井住友フィナンシャルグループのある行員(30代後半)は、実際に同じことを入社してすぐに先輩から言われたという。ただし、その後に「そうならないよう気をつけろ」と続くのだが、実態は違う。上司から「融資を引き上げろ」と命じられて、逆らえる銀行マンなどいない。なぜそこまでがんじがらめにされるのか。同行員が自虐的にこう続ける。
「銀行には『家を買った人は転勤になる』というジンクスがあるんです。住宅ローンを抱えるから、転勤させても辞めることなく頑張って働くはずだというのが、その理由です。実際、同期の中には家を買った途端、片田舎に転勤になった男もいます。その人事に不満を漏らすことはあっても、最終的には従うしかありません。そうしないと自分の人事評価に影響しますから」
そんな環境で「半沢直樹」流を貫くとどうなるか。ベテラン金融担当記者はこんなケースを紹介する。
「まれに半沢直樹のような銀行マンもいるんですが、上司をやり込めることはありえない。某メガバンク支店長は、本部からの『融資先の業績が不振だから、貸出金利を上げろ』という指示に対し、『お客様が第一です。次期決算では業績改善されますから、それはできません』と突っぱねた。途端に支店長から外され、本部の人事部付きになって、仕事も与えられず退職に追い込まれました。周囲は出世レースから一人ライバルが消えたとほくそ笑んでいました」
そんな銀行内で出世していくには、まずはミスをしないこと、その上で成果を上げることが求められる。
「銀行は減点主義です。一度でもバツがつくとそれが出世に響く。だから、上司からどんな理不尽なことを言われても、目標を達成するために歯を食いしばって耐えるしかない。
しかも、社宅に入れば、会社でのヒエラルキーがプライベートにも持ち込まれますから、息が詰まることこの上ありません。たとえば、毎日のゴミ出しや週末の草むしりといった場面で、夫の会社での上下関係を妻も思い知らされます」(メガバンクベテラン行員)
■40代から「黄昏研修」
ドラマではまだ詳しく描かれていないが、池井戸氏の原作では、メガバンク内の「派閥」も物語の重要なファクターになっている。
「どんな世界にも派閥はあるが、とくに銀行はその傾向が顕著です。銀行は人脈と派閥の世界そのもので、中心派閥に入れなかった者は出世の望みはないし、反主流派は粛清されます」(元メガバンク幹部)
派閥はどうやって作られるのか。多くの場合、若手行員の時代から先輩の"引き"によって自然と派閥が生まれていく。
「先輩が出世して支店長などになったときに、人事部にスペシャルオーダーを出して、かつて一緒に働いたお気に入りの後輩たちを呼び寄せるわけです。銀行マンにとって人事は絶対ですから、後輩に断る権利はありません。そうして自然と派閥が形成されていきます。いったんバラバラになっても、年に一回程度、『昔の支店長を囲む会』といった体裁で集まる。都合がつけばといいますが、これはもちろん強制ですね(笑)。出世をするには、どの上司に気に入られるかが肝になりますし、上司も優秀な後輩たちに担いでもらえないと役員まではなれない。
一方で、先輩や上司から引きのない行員は、派閥に入ることさえできず、出向対象としてリストアップされます」(前出・中堅行員)
同期との成績争いや派閥争いに負け、出世レースから脱落すると、40代から「研修」と呼ばれるセミナーが待ち受けている。他の業界よりも「肩たたき」=出向が早いのも銀行の特徴である。一般の企業なら働き盛りの40代半ばで、第二の人生、そして老後の生活設計を考えることを強いられるのだ。
「どんな銀行マンも入行した当初は、『俺は部長くらいまで出世するぜ』という勢いで仕事をしているのだけれど、そのうち振り落とされて『黄昏研修』に行き着くわけです。『銀行以外に友達はいますか。いないと大変ですよ。部下も辞めて2年くらいは付き合ってくれるけど、それを過ぎたら誰も付き合ってくれませんよ』などと言われて、初めて外部に目が向く。それが銀行員の宿命みたいなものです」(前出・池井戸氏)
実際にそれを体験してきた別のメガバンクの行員(40代)が嘆く。
「40歳になると『黄昏研修』に参加しなければなりません。表向きは能力開発のための研修ということになっていますが、実際は出向など今後の人生設計について考えさせるための研修です。40歳で1回目の研修を受け、1~2年後に2回目の研修を受けます。外部講師が来て、今後の収入や退職金、年金、住宅ローン、子どもの教育費などについての講義を受け、2回目の研修で、自分はどうなるのかのシミュレーションを行う。
この研修を受けたら最後、いやでも出向から老後のことまで考えさせられる。夕日を見ながら第二の人生に思いを馳せるイメージですかね。だから『黄昏研修』と呼ばれるのでしょう」
銀行の場合、同期入行の行員が100人いたとすると、50歳で残れるのはわずか3人。役員にまで昇りつめるのは、せいぜい1人だ。あぶれた97人は、必然的に「出向」ないしは「転籍」となる。それまで、融資先や顧客から、銀行の威光を背景に「エリート扱い」をされてきた銀行マンたちが、日の当たらない存在へと立場を移すのである。そのとき、彼らのプライドは打ち砕かれ、受け入れ先に対して卑屈になってしまうとしても仕方がないだろう。一般の人よりも一足先にやってくる、サラリーマンの"黄昏"時だ。
再就職先は基本的に銀行が世話をしてくれるが、給料は銀行員当時の6掛けが相場だという。
ただし、これも保証の限りではなくなってきた。
「これまで出向先は会社があてがってくれていましたが、ポストが減ってきた。自分で出向先や転籍先を探してくる人も少なくありません。ラインに残れなかった者は、40歳を過ぎた頃からは次の職場を探すことが大きな仕事になります」(元三菱東京UFJ銀行幹部)
出向の場合、社員としての本籍は、とりあえずは出身銀行にある。ただしそれは2年間限りの名目であって、実際には行ったきりの「片道切符」だ。
とはいえ、傑出した能力と本社からの強烈な引きがあれば、復活がまったく不可能というわけでもない。
今春、三井住友銀行の人事が経済界で話題になった。同行から消費者金融のSMBCコンシューマーファイナンス(旧・プロミス)に出向していた久保健社長が、副頭取に抜擢されて三井住友銀行に復帰したのだ。
「久保氏はもともと出世競争で負けて出向した人。それを引き戻したのは、リテール(小口金融)分野の強化を目指す三井住友に、『リテールの久保』とまで呼ばれた彼の力が必要と判断したからでしょう。それにしても異例中の異例です」(前出・金融担当記者)
こんなケースはまずありえない。ほとんどの銀行マンにとっては、出向先があるだけまだマシというのが、今の銀行の実情なのだ。
■怒りを飲み込む日々
銀行マンが神経をすり減らす場面はまだほかにもある。国税や金融庁など、所轄官庁との対決がそれだ。
ドラマでは国税局査察部統括官が、計画倒産した企業のカネの流れを調べるため、ネチネチといやらしい手口で半沢直樹を追い詰める。もちろんキャラクター造形はフィクションだが、当局の検査の実態は恐ろしいものだという。
「国税が支店に入るのは、ドラマのように、法人や個人の脱税などを調べるためです。カネの流れを解明するために『あれ出せ』『これ出せ』と上から目線で指図されるため、非常に不愉快です。しかも、査察先をカモフラージュするために、関係のない資料をどっさりと要求する。業務の妨げになるばかりか、自分より年下の国税マンに横柄に言われるとが煮えくり返りますよ。国税が何を調べているのかは、わからないケースがほとんどです」(別のメガバンク中堅行員)
やはり半沢直樹のように、「倍返し!」のタフな精神で立ち向かわないと、生き馬の目を抜く銀行業界では勝ち残れないのだ。
最後に池井戸氏が、半沢直樹のようなヒーローが今、多くの人を惹きつける理由をこう分析する。
「かつては銀行マン=エリートと思われていたけれど、今やそんな特別視される存在ではありません。昔は侍のようなバンカーもいました。'50年代に倒産寸前に陥ったホンダに、重役たちの反対を押し切って融資を継続したという三菱銀行のバンカーの存在は、今も伝説として語られています。
しかし、今は企業の財務しか見ませんから、こんなことはできないでしょう。だからこそ、上司と対峙して、理不尽には徹底的に抗い、ときには汚いやり方にも手を染める、清濁併せ呑むヒーロー『半沢直樹』に熱狂的なファンがついているのではないでしょうか」
「週刊現代」2013年8月17日・24日号より
 スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。