02. 2013年8月08日 09:21:12
: e9xeV93vFQ
消費税:安倍政権の決断を望む
増税が成長率を低下させるとは限らない2013年8月8日(木) 小黒 一正 安倍晋三首相は近々、消費増税が景気にもたらす影響を再検証する「場」を設けるよう指示する見通しだ。この場には、増税慎重派の浜田宏一内閣府参与らが参加する案が有力であり、これを受け、市場関係者の間で消費増税の方向性に一時的に波紋が広がった。消費税は2014年4月に8%に、15年10月に10%に増税されることになっている。これに対して、「(1)消費税率を予定通り2段階で引き上げる、(2)最初に2%上げ、その後1%ずつ引き上げる、(3)5年間で毎年1%ずつ引き上げる、(4)増税を当面見送る――の4案の影響を検証する作業に着手」(日経新聞・電子版2013年7月27日)する模様である。 だが、日本の財政に増税を見送る余裕などはない。1997年に消費増税を行ってから今回の増税法案の成立まで、約15年も経過している。もし今回の増税を先送りする場合、次の政治的な合意に至るまで何年が必要となるのか。また、前回のコラムで説明したように、社会保障費を抑制せず、消費税を5%に据え置いたままでは、2028年に財政は限界に近づくとの試算もある。増税はもはや不可避であり、重要なのは、そのショックをどう緩和するかである。 97年の景気減速は、実は金融危機の影響が大 増税に関して、日本やOECD諸国の過去のデータを見る限り、「増税が成長率を低下させるとは限らない」という客観的事実を認識することが重要だ。 「増税が成長率を低下させるとは限らない」という簡単な事例として、まず、日本のケースを見てみよう。以下の図表1を見てほしい。日本は過去に消費増税を2回行った。1989年4月の消費税導入時(3%)と、97年4月の増税(消費税率3%→5%)である。実はあまり知られていないが、この2回の増税では、実質GDP成長率のその後の動きが異なる。 「増税は必ず成長率を低下させる」という主張の根拠として頻繁に利用される97年の増税での動きは、図表1の赤線で囲った部分である。増税前後の96年から98年までの3年間で、実質GDP成長率は2.6%(96年)→1.6%(97年)→▲2%(98年)と推移し、一貫して低下している。 だが、89年の消費税導入時の動きは全く違った。図表1の赤線の囲みのとおり、増税前の88年から89年にかけて、実質GDP成長率は7.15%(88年)→5.37%(89年)と一時的に低下しているものの、増税後の90年には5.57%に上昇している。なお、91年以降に実質GDP成長率が急低下しているのは、バブル崩壊の影響である。 以上の客観的事実は、「増税が成長率を屈折させるとは限らない」という1つの証拠である。むしろ、拙著『アベノミクスでも消費税は25%を超える』でも説明しているように、97〜98年は三洋証券や山一証券、長銀や日債銀といった金融機関の破綻が相次ぎ、不良債権処理や貸し渋りの影響が出始めた異常な時期に増税を行ってしまったことが経済を低迷させたというのが、最近の経済学者の標準的な見方である。 図表1:実質GDP成長率の推移(日本) (出所)IMF (2012) World Economic Outlook Databases
海外のデータでも「増税=経済減速」は必然ではない では、海外でのケースはどうか。その客観的事実を見るため、以下では、1965〜2011年におけるOECD諸国の年次データを利用する。人口成長率や物価上昇の影響を取り除き、厳格に評価するため、成長率の指標として「1人当たり実質GDP成長率」を見る。また、VAT(付加価値税)の税収(対GDP)の変化が0.45%ポイント以上増加している場合は何らかの増税を行ったとみなす。このようなデータに基づき、「VAT税収(対GDP)の変化」が「1人当たり実質GDP成長率」や「1人当たり実質GDP成長率の変化」に及ぼした影響を見たものが、以下の図表2と図表3である。 図表2:「VAT税収の変化」と「1人当たり実質GDP成長率」の関係 (出所)OECD StatExtractデータ
まず、図表2である。この図表の横軸は「VAT税収(対GDP)の変化(前年と比較した際の増減)」、縦軸は「1人当たり実質GDP成長率」を表す。日本のケースで考えると、GDPが500兆円弱で、消費増税1%の増税収は約2.5兆円であるから、その税収(対GDP)は約0.5%に相当する。 図表2のプロット・データ全体を見ると、VAT税収(対GDP)の変化が2%以上(日本のケースでは消費税4%分の増税に相当)でも、1人当たり実質GDP成長率がプラスの領域に収まっているケースが多いことが分かる。 図表3:「VAT税収の変化」と「一人当たり実質GDP成長率の変化」の関係 (出所)OECD StatExtractデータ
次に図表3である。この図表の横軸は図表2と同じであるが、縦軸は「1人当たり実質GDP成長率の変化(前年と比較した際の増減)」を表す。このため、付加価値税(VAT)の増税が1人当たり実質GDP成長率を低下させたケースは、「1人当たり実質GDP成長率の変化」がマイナスの領域にプロットされることになる。逆に、付加価値税(VAT)の増税を実施しても1人当たり実質GDP成長率が低下しなかったケースは、「1人当たり実質GDP成長率の変化」がプラスの領域にプロットされている。 図表2と同様、プロット・データ全体を見ると、VAT税収(対GDP)の変化が2%以上でも、1人当たり実質GDP成長率が低下していないケースが5割程度も存在することが分かる。 以上の客観的事実は、「消費増を増税しても成長率が屈折とは限らない」ことを示す1つの証拠である。 参院選で大勝した安倍政権がまず初めに直面する難題が「秋の増税判断」だ。日本財政が限界に近づきつつある現状を踏まえると、将来世代の利益も視野に入れた決断が望まれるところである。安倍政権の責任は重い。 このコラムについて
子供たちにツケを残さないために、いまの僕たちにできること この連載コラムは、拙書『2020年、日本が破綻する日』(日経プレミアムシリーズ)をふまえて、 財政・社会保障の再生や今後の成長戦略のあり方について考察していきます。国債の増発によって社会保障費を賄う現状は、ツケを私たちの子供たちに 回しているだけです。子供や孫たちに過剰な負担をかけないためにはどうするべきか? 財政の持続可能性のみでなく、財政負担の世代間公平も視点に入れて分析します。
また、子供や孫たちに成長の糧を残すためにはどうすべきか、も議論します。
楽しみにしてください。もちろん、皆様のご意見・ご感想も大歓迎です。
http://business.nikkeibp.co.jp/article/topics/20130802/251872/?ST=print |
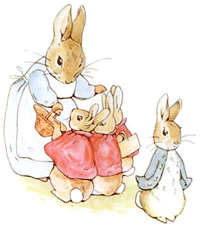
 スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。