http://www.asyura2.com/13/hasan81/msg/453.html
| Tweet |
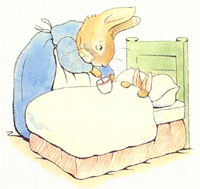
http://www.zakzak.co.jp/economy/ecn-news/news/20130731/ecn1307310724003-n1.htm
2013.07.31 ZAKZAK
日本郵政と米保険大手のアメリカンファミリー生命保険(アフラック)が26日、がん保険事業で提携合意した。すでに郵政グループは約1000の郵便局でアフラックの商品を扱っているが、今秋から順次取り扱いを広げ、簡易郵便局を除く全国約2万の郵便局と、約80のかんぽ生命保険直営店でアフラックの商品を販売する計画だ。
政権交代を機に日本郵政の経営陣が一新され、社長が坂篤郎氏から親米派の西室泰三氏に交代して以降、劇的な変化が予想された。まさに「昨日の敵は今日の友」とも言うべき戦略のコぺルニクス的な転換だ。
日本郵政は、昨年の郵政民営化改正法成立と前後して新規業務への進出を模索してきた。焦点のひとつが、かんぽ生命によるがん保険など「第三分野」(医療保険)への進出だった。実際、日本郵政は日本生命と共同でがん保険の商品開発を終え、いつでもスタートできる状態にあった。
だが、待ったをかけたのが日本のがん保険で約7割のシェアを誇るアフラックだった。すでに日本郵政はアフラックのがん保険を郵便局で販売していたが、あくまで品ぞろえの1つでしかなかった。一方、アフラックにとって日本郵政は有力な「売り子」。そこにかんぽ生命が日本生命と共同でがん保険を開発して進出してくればどうなるか。シェアを大きく浸食されかねないアフラックの危機感は強かった。
アフラックの政治力は抜きんでている。力の源泉には、アフラック日本法人の創設者で現最高顧問の大竹美喜氏がおり、「大竹氏の人柄に魅了された政・財・官界の人脈は華麗そのもの」(関係者)と指摘される。その大竹氏がアフラックの日本代表に招聘(しょうへい)したのが、米国の元USTR(通商代表部)日本部長であったチャールズ・D・レイク氏だった。USTRはTPPを推進する米国の窓口で、レイク氏は米日経済協議会会長を務めている。
いうまでもなく日本郵政とアフラックの劇的な接近の背景には、TPP交渉が影を落としている。交渉に遅れて参加する日本政府にとって、日米2国間協議で日本の要望に理解を得るには交渉材料が不可欠。それが日本郵政・アフラック提携の本質で、「安倍政権が引けない農産物の聖域(5分野)とのバーターに日本郵政が使われた可能性が高い」(野党議員)という。これで日本郵政の「第三分野」への進出は消え、日本生命とのがん保険はお蔵入りすることになろう。
他方、並行して見逃せない決定があった。主要国の金融監督当局で構成する金融安定理事会は18日、「グローバルにシステム上重要な保険会社(G−SIIs)とその政策措置」を発表した。G−SIIsには追加の資本充実を課すという内容だ。
当初、日本生命のリスト入りも指摘されたが、結果的に日本の保険会社は外れた。規模やリスク取引の大きさから基準に達していないとの判断だが、裏には政治的な駆け引きがあったとみられている。
■森岡英樹(もりおか・ひでき) 1957年、福岡県出身。早大卒。経済紙記者、埼玉県芸術文化振興財団常務理事などを経て2004年4月、金融ジャーナリストとして独立。
 スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。