02. 2013年7月23日 00:46:50
: niiL5nr8dQ
円安は4−6月期の企業収益の押し上げにも寄与「Jカーブ」で見る国際収支 2013年7月23日(火) 権田 直 2012年11月末以降、ドル円レートは約20円程度減価し、急激な円高修正の動きがみられる。しかしながら、我が国の2012年1−3月期の貿易収支は、約3.1兆円の赤字となっており、赤字幅が拡大している。2011年の東日本大震災以降、原油やLNGといった鉱物性燃料の輸入が増加したこと、海外経済の減速などを背景として輸出が低迷したことなどが背景にあると言われている(図1)。 一般に、円安になれば、輸出品の価格を引き下げやすくなるため、海外での販売競争力が高まり、日本の輸出産業に有利になる。また、海外からの輸入品の価格は上昇するため、国内では国内産業に有利になり、輸入は減少する。このため、輸出が増え、輸入が減ることから、貿易収支を改善させると考えられるが、逆の現象が起きているのはなぜだろうか。 これは「Jカーブ効果」という現象で説明できる。以下では、為替レートの変化が貿易収支に対して与えるメカニズムとして「Jカーブ効果」を紹介するとともに、企業収益にどのような影響を及ぼすか考える。 図1 我が国の貿易収支の推移 円安は貿易収支の赤字幅を一時的に拡大させる 「Jカーブ効果」とは、どのような現象のことを指すのだろうか。 まず、円安になれば、外貨建ての輸出価格は不変でも、円換算した輸出額は増加するため、当初、輸出金額は増える。また、輸入品の円建て価格が上昇するため、一時的に輸入金額は増加する。我が国の輸出の外貨建て契約比率は約6割であるのに対し、輸入は約8割である。このため、輸出価格よりも輸入価格の上昇幅が大きくなる。 一方、円安になると、円建て取引額を維持しつつ、外貨建て契約価格をある程度切り下げて価格競争力を上げ、現地での販売数量の増加につなげることができる(輸出数量の増加)。また、円安により輸入品の価格が上昇すると、競合する国内産品の価格競争力が増すため、徐々に輸入品は国内品に代替されるようになる(輸入数量の減少)(図2)。 当初は数量が変化せず、価格の変化が起きるので、これによる輸入金額の増加が輸出金額の増加を上回り、むしろ円安は貿易赤字を拡大させる。このように、為替レートが変動した時に、短期的に予想される方向とは逆の現象が起こることを「Jカーブ効果」と呼ぶ。時間の経過に伴う貿易収支の推移をグラフに表すと、いったん下がってから上がり、グラフ上に描かれる曲線がJの字を描くことから「Jカーブ」呼ばれる(図3)。 図2 円安が輸出入に影響を与えるメカニズム(概念図) 図3 Jカーブ効果(概念図) 円安約9カ月後から赤字幅縮小に寄与 我が国の貿易収支は、「Jカーブ効果」により赤字幅が拡大していると考えられるが、昨年末以降の円安方向への動きが貿易赤字幅縮小に寄与するのはいつ頃だろうか。 内閣府では、2012年11月の水準で円ドルレートを一定とした場合の貿易収支をベースラインとし、2012年12月から2013年3月まで実際の為替水準(11月の水準から14円、約15%の円安)を与え、4月以降は3月の水準で一定とした場合の貿易収支をインパクトケース(円安効果が発現したケース)として、その差から最近の円安の貿易収支への影響を試算している。 それによると、当初、鉱物性燃料などの円建ての輸入価格が上昇し、貿易収支の赤字幅拡大に寄与するが、価格競争力向上により、徐々に輸出数量が増加し、逆に国内での輸入数量が減る(収支にはプラス)ことによって、2013年4月には反転し、8月には貿易収支の赤字幅縮小に寄与するという(図4)。 図4 最近の円安の貿易収支への影響(内閣府による試算) (備考)佐藤亮洋、中島岳人(2013)「経常収支の黒字縮小の要因と最近の円安の影響」マンスリートピックNo.18、により作成。
工作機械分野ではより早い時期から数量効果が現れる このように、円安の動きは、当初貿易赤字幅を拡大させるが、徐々に輸出数量の増加に伴って赤字幅縮小に寄与する。この輸出数量効果は、業種ごとに異なるだろうか。我が国の輸出総額に占めるシェアの高い工作機械、具体的には自動車などの輸送用機器、半導体やテレビなどの電気機器、建設機械や産業用機械などの一般機械について、業種別のJカーブ効果を試算した(注1) (注1) 各産業の推計値には、他部門(原油価格上昇など)の影響は含まれていない 輸入よりも輸出の多い業種では、輸入価格の増加を通じた短期的な赤字幅拡大の影響が小さく、当初から輸出増加に伴う赤字幅縮小の効果のみが寄与するため、貿易収支への影響は必ずしもJの形にはならないと推察される。 実際に、試算結果を見るといずれの業種においても、2011年11月以降の円安方向への動きは、2013年1−3月期から赤字幅縮小に寄与している。これは、我が国の工作機械の輸入金額は、輸出金額に比べて相対的に大きいためである(図5)。 また、円安による貿易収支改善額の水準を業種別に比較すると、輸送用機器が最も大きく、次いで電気機器、一般機械となっている。電気機器や一般機械に比べて輸出金額の多い輸送用機器では、相対的に収支改善効果が大きくなっていると考えられる。 図5 工作機械3分野(輸送用機器、電気機器、一般機械)におけるJカーブ効果(試算) 近年では所得収支を含めて影響をみる必要 以上が従来のJカーブ効果の議論であるが、近年では企業のグローバル展開が進み、企業が海外から得られる収益の源泉は、輸出だけでなく、海外子会社からの受取配当金などの投資収益が相対的に大きくなっている。 ここで、投資収益が外貨建てで決まっている場合、円安分だけの評価益が発生することとなるが、これはタイムラグなしに直ちに現れるはずである。これは、企業のグローバル化が進展した現在では、円安方向への動きの国際収支への影響を、貿易収支だけについて見るのではなく、投資収益(所得収支)を含めた経常収支で見るべきであるということを示している。 最近の経常収支の動きを見ると、2013年1−3月期の貿易収支赤字幅は拡大している一方、所得収支の黒字幅が拡大していることから、経常収支の黒字幅は貿易赤字ほどに悪化しておらず、上記の想定通りの動きとなっている。 図6 我が国の経常収支の推移 2013年1−3月期は製造業加工業種を中心に増益 円安方向への動きの影響は、当初、Jカーブ効果により貿易収支を悪化させる一方、所得収支を改善させる。では企業収益にはどのような影響があるだろうか。2013年1−3月期決算における上場企業の経常利益額を見てみよう。 まず、上場企業全体で見た経常利益の合計額は、前年同期比13.3%と大幅な増益となっている。これは、個人消費の持ち直しなどを背景とした内需の底堅さ、新興国などとの競争激化や国内市場の縮小を意識した企業が収益重視の堅実な経営姿勢を維持したことなどに加え、一部業種では円安による収益押し上げ効果が現れていると考えられる。 業種別の動向を見ると、非製造業に比べて製造業の増益幅が大きかったことが分かる。特に、電気機械や輸送機械を含む加工系業種の収益改善幅は、化学や鉄鋼といった素材系業種に比べて大きい。 このように、足下の企業収益は、円安の動きを受けた数量効果が現れたこと、海外子会社からの円建ての受取配当金の増加などを通じて、加工系業種の収益増加につながっている側面があると考えられる。 また、今後Jカーブ効果が、さらなる輸出数量の増加につながれば、2013年4−6月期以降の収益押し上げ要因になると考えられる。 図7 業種別に見た上場企業の経常利益額 以上見てきた通り、最近の円安方向への動きは、Jカーブ効果により、短期的に我が国の貿易収支を悪化させていると考えられる。ただし、輸出産業については、円建ての輸入価格の増加に伴う短期的な赤字幅拡大の影響が全体と比べて小さいため、数量効果の発現により、収支改善時期は早まると考えられる。 また、ここで紹介した試算は、あくまで簡易的に試算した結果であり、赤字幅縮小への寄与に転じる時期やその大きさについては幅をもってみる必要があるが、今後、数量効果が現れることで、全体の貿易収支についても赤字幅縮小に転換していくものと考えられる。 また、既に述べたように最近の円安方向への動きは、貿易収支よりも早く所得収支の改善につながる。このことは、グローバル時代における為替レートの国際収支への影響は、貿易収支だけなく、所得収支を含めた経常収支で見るべきであることを示している。 さらに、これを企業収益の観点から見ると、数量効果や投資収益の改善は、加工業種を中心に2013年1−3月期の収益押し上げ要因になっていると考えられる。今後、の円安方向への動きは、さらなる数量効果を通じて、2013年4−6月期以降の企業収益押し上げ要因になると考えられる。 (本コラムの内容は筆者個人の見解に基づいており、内閣府の見解を示すものではありません) このコラムについて
若手官庁エコノミストが読む経済指標 内閣府の若手エコノミストがさまざまな経済指標を読み解き、日本経済や日本経済を取り巻く状況について分かりやすく分析する。多くの指標を精緻に読み解くことで、通り一遍の指標やデータだけでは見えてこない、経済の姿が見えてくる。
http://business.nikkeibp.co.jp/article/opinion/20130717/251191/?ST=print
「会社が儲かる理由って何?」に経営学者が出した答え 大切なのは産業構造なのか、それとも個々の戦略なのか 2013年7月23日(火) 入山 章栄 本連載では、米ビジネススクールで助教授を務める筆者が、海外の経営学の知見を紹介していきます。 さて、私は昨年『世界の経営学者はいま何を考えているのか』(英治出版)という本を刊行し、大きな反響をいただきました。そして複数の方々から「この本を書くにあたって、影響を受けた経営書はあるのですか」という質問を頂戴しました。 拙著を書くにあたって私が影響を受けたのは、経営書ではありません。それは東京大学の宇宙物理学者、吉井譲教授が2006年に書かれた『論争する宇宙』(集英社新書)という、宇宙物理学の歴史をわかりやすく紹介した本です。 物理学はド素人の私ですが、数年前にたまたま手に取って感銘を受けたのです。そして、経営学で似たような本が書けないだろうか、と考えるようになりました。 『論争する宇宙』で印象深かったことが、宇宙物理における「理論と実証のせめぎあい」です。 宇宙物理の世界では、たとえばアインシュタインのような理論家が、彼の信じる宇宙法則を記述した「理論」を構築します。他方でその理論が本当に正しいのか、宇宙の実態はどうなっているのかを「実証」する必要もあります。宇宙物理なら、たとえばそれは高性能の望遠鏡を使って星や銀河の動き・明るさ・色などを丹念に「観測」することです。 このように、多くの「科学」と名のつく学問では、観測・実験・フィールドワーク・統計分析などを通じて、地道な実証研究が行われます。そしてこれは、社会科学であることを目指す世界の経営学者が行っていることでもあるのです。 今回はそのような地道な、 しかしとても興味深い、実証分析に関する話題を紹介しましょう。それは「結局のところ、儲かる要因って何?」という、経営の根本を問う疑問なのです。 重要なのは、産業か、企業そのものか 企業の「儲かる・儲からない」を決める要因とは、結局は何なのでしょうか。 まず、産業による違いは大きいかもしれません。たとえば米国では、製薬業は全体的に収益率が高いと言われます。他方、航空業界は過当競争といえる状態にあり、多くの企業が厳しい経営を強いられています。 とはいえ、同じ産業でも会社ごとに業績は違います。全体的には厳しい米航空業界でも、サウスウェスト航空やジェットブルー航空は、それぞれ固有の戦略を背景に高い利益率を出しています。 では、おしなべてみると企業の収益率を決めるのは「どの業界にいるのか(=産業効果)」なのでしょうか、それとも「企業ごとの特性・戦略(=企業効果)」なのでしょうか。 この問いに答えるため、世界の経営学では、企業収益性の要因を地道に「測定」する実証分析が積み重ねられてきました。 エポックメーキングだったのは、1985年に経済学のトップ学術誌である「アメリカン・エコノミック・レビュー」に掲載された、マサチューセッツ工科大学(MIT)のリチャード・シュマレンジー教授(以下シュレマンジー)の論文です。シュマレンジーは企業業績を決める要因を測定するために、Components of Variance(COV)という、当時としては画期的な統計手法を用いました。 ここではCOVの仔細には立ち入りません。「大規模サンプルをもとに、企業収益のバラツキ(分散)の要因を分解する手法」とご理解ください。 シュマレンジーが75年の米企業1775社の資産利益率(ROA)データをもとに、COV手法を使って得た結果は驚くべきものでした。彼の分析では利益率のバラツキの約20%だけを説明できたのですが、その20%のほぼすべてが「企業がどの産業にいるか(=産業効果)で規定される」という結果になったのです。 経営戦略には意味がない? この結果に衝撃を受けたのは、経済学者より、むしろ経営学者だったといえるでしょう。 考えてみてください。この結果が本当なら、「儲かるかどうかは『企業がどの業界にいるか』でほぼ決まってしまう」ということになります。そもそも企業独自の特性とか戦略とか、そういったことは意味がないと言っているようなものです。 経営学の存在意義を否定したようにすら思えるこの結果が確かなのか、さらに検証することが経営学者に求められました。より大規模なデータや分析手法の改良を通じて、この測定結果を「追試」することが盛んになったのです。 そしてその牽引者こそが、あのハーバード大学のマイケル・ポーター教授(以下ポーター)、そしてカルフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)のリチャード・ルメルト教授(以下ルメルト)だったのです。 ルメルトの追試 この連載で何度も登場しているポーターについては、説明の必要はないでしょう。他方、ルメルトも黎明期の経営学を支えてきた大物です。昨年は『良い戦略、悪い戦略』(日本経済新聞出版社)という本を出版し、日本でも話題になりました。 そのルメルトが91年に「ストラテッジク・マネジメント・ジャーナル(SMJ)」に発表した論文は、まさにタイトルも「産業効果はどのくらい重要か?」(筆者訳)という、シュマレンジーの結果に挑戦するものでした。 ルメルトは、「シュマレンジー手法」の問題点を指摘し、さらに75年の1年だけのデータを使ったことを問題視しました。1年だけの分析では、その年の景気の影響などを考慮できません。そこでルメルトはCOV手法を精緻化し、74年から77年の複数年データを使い、観測数を6931に拡張して再分析をしました。 その結果、シュマレンジーが20%しか説明できなかった企業利益率のバラツキを、ルメルトの分析では 63%も説明できる、という結果になりました。そして63%の内訳の約8割が企業効果である、という結果になったのです。産業効果は2割に留まりました。 この結果は、経営学者を勇気づけるものでした。「企業ごとの経営特性・戦略は収益率を決める上で重要である」といえるからです。 やはり経営学は意味がある、というわけです。 他方で一部の学者からは、ルメルトの結果に対して、「いくらなんでも産業効果が小さすぎる」という批判も出てきました。たしかに現実には、儲かる業界と儲からない業界の間には、かなり差がある気もします。産業効果が企業効果の4分の1しかないというのは本当でしょうか。 そこでさらなる追試を行ったのが、ポーターです。 ポーターが現カナダ・トロント大学のアニータ・マクガハン教授と97年にSMJ誌に発表した論文では、さらに包括的なデータベースから85年から91年の米企業データを取り出し、観測数約5万8000の大規模サンプルで測定しました。 そしてこの分析により企業利益率のバラツキの約50%を説明できること、その内訳は産業効果が4割ぐらいで、企業固有の効果は6割ぐらいに留まる、という結果を得たのです。2人が2002年に「マネジメント・サイエンス」に発表した論文でも、同じような結果を得ています。 ポーターの追試とSCP理論 興味深いのは、このポーターの結果は、まさに彼の生み出した経営理論にぴったりあてはまるものだったことです。 ポーターが中心となって80年代に確立したSCP理論(Structure Conduct Performance Model)では、「企業の競争優位には二重のポジショニングが重要である」とされます。第1に「収益性の高い産業を選ぶべき」というポジショニングであり、第2に「その産業内で、自社が他社と比べてユニークなポジショニング(競争戦略)をとるべき」というものです。 SCP理論はこのように「産業も、戦略も重要」と主張しているわけで、まさにポーターが自ら得た「産業効果が4割、企業効果が6割」という測定結果と整合的です。みなさんも、この結果には肌感覚として納得できるかもしれません。 多角化は効果がないのか? ところが、話はこれで収まりませんでした。今度は「コーポレート効果があまりにも小さいのではないか」という批判が出てきたのです。 「コーポレート効果」とは、企業が複数の産業をまたいでビジネスをすることで得られる追加効果(=多角化の効果)のことです。実はルメルトやポーターの研究は、このコーポレート効果も測定していました。そしてその結果は、どちらも「コーポレート効果はほとんど存在しない」というものだったのです。 これは、とくに多角化戦略の重要性を説く学者には納得できないものだったでしょう。2001年にペンシルベニア大学のエドワード・ボウマン教授達がSMJ誌に発表した論文では、過去の研究手法に疑問を呈し、これまでの研究はコーポレート効果を過小評価しているのではないか、と主張しています。 さらに、「国の違いによる効果」もあるのではないか、という研究も出てきました。 この論文を2004年にSMJ誌に発表して話題を読んだのが、香港中文大学の牧野成史教授、慶応ビジネススクールの磯辺剛彦教授という、2人の国際的に活躍する日本人経営学者です(香港大学クリスティン・チャン教授との共同論文)。 牧野氏たちは、 観測数2万8000の多国籍企業の海外子会社データでCOV分析を行いました。この分析では、海外子会社の利益率のバラツキの50%強を説明することができて、「国の違いによる効果」だけでその2割を占めるという結果となっています。 日本企業の「儲かる要因」についての研究 日本企業についてはどうでしょうか。私の知っている範囲では、青山学院大学ビジネススクールの福井義高教授と牛島辰男教授が、2011年に『ジャーナル・オブ・ジャパニーズ・アンド・インターナショナル・エコノミーズ』という経済学の学術誌に掲載した論文があります。 この研究では、1998年から2003年までの日本企業データ(観測数約2万4000)について、COV分析で測定をしています。そして、この分析では企業利益率のバラツキの70%弱を説明できて、内訳は企業効果が7割を超え、産業効果とコーポレート効果は比較的小さいという結果となっています。日本でもやはり各企業の特性・競争戦略は重要なようです。 地道な実証こそ、経営学者の役割である 今回は「収益率を決める要因は何か」という根本的な問いに対して、経営学者が地道に蓄積してきた実証研究を紹介してきました。多くの学者がデータを充実させ、分析手法を改良することで、より精度の高い結果を求めようとしているのです。 本稿を読んで「こんな研究、私のビジネスには何の意味もない」という方もいらっしゃるでしょう。 たしかに、こういった研究はみなさんのビジネスに直接は役立たないかもしれません。しかし、「企業経営を科学的にとらえる」のなら、このような根本的な問いを地道に測定する作業はやはり重要なはずです。 前出の『論争する宇宙』によると、1930年代に天文学者のハッブルが地道に天体の観測を続け、「宇宙は膨張している」という事実を発見したことが、アインシュタインに彼の宇宙理論を放棄させるきっかけとなりました。そして数十年後、今度は別の天文学者の地道な観測によってダークマターという正体不明の物質が宇宙に満ちていることがわかり、それがアインシュタインの放棄した「宇宙定数」を理論に復活させる動きの契機となったのです。 経営学でも、ポーターの測定結果が彼自身の理論の下支えになったことは想像に難くありません。そもそも、ポーターやルメルトがシュマレンジーに対抗する結果を出したことが、企業の特性や戦略に注目する「経営学」の重要性を裏付けてきたともいえます。 みなさんの中には、ポーターやルメルトの経営書をお読みなった方もいるかもしれません。一見華々しい本を書く著名経営学者が、実はこういう地道な研究もしてきたということは、知っておいて損はないのではないでしょうか。 このコラムについて
米国発 MBAが知らない最先端の経営学 ピーター・ドラッカー、フィリップ・コトラー、マイケル・ポーター…。日本ではこうした経営学の泰斗は良く知られているが、経営学の知のフロンティア・米国で経営学者たちが取り組んでいる研究や、最新の知見はあまり紹介されることがない。米ニューヨーク州立大学バッファロー校の助教授・入山章栄氏が、本場で生まれている最先端の知見を、エッセイのような気軽なスタイルでご紹介します。
中堅企業の目に映る日本経済の今
英EIU報告書〜日本の中堅企業 その競争力と成長の条件(2)
2013年07月23日(Tue) Economist Intelligence Unit
国内経済の見通し 主要海外市場での需要低迷による輸出企業の収益減少や、競合国の台頭による市場競争力の低下、対中外交関係の悪化など、日本経済は世界金融危機の発生後、国外で様々な課題に直面してきた。また国内でも、デフレや政治的混乱や未曾有の大震災をはじめとするマイナス要因に直面した。
日本のGDPは、世界的な景気低迷のあおりを受けた2009年の翌年に4.7%の回復を見せたものの、2011年には実質GDPが0.5%のマイナス成長を記録。復興需要の後押しを受けたにもかかわらず、2012年の成長率も1.8%にとどまり、年末にかけて過去5年に3度目となる景気後退の懸念が広まった(表2.1参照)。
しかし、新たな自民党政権が掲げる経済政策などを背景に、2013年に入ると国内では楽観的ムードが強まった。 緊急経済対策や日本銀行によるデフレ対策のさらなる強化、様々な構造改革など、政府が打ち出した一連の経済政策(いわゆる“アベノミクス”)は、過去数十年に例を見ないほど市場の期待感を高めている。 これまで輸出企業の頭を悩ましてきた円高は、2012年11月から2013年5月の間に見られた対ドル為替レートの27%下落により大幅に改善され、日経平均株価も今年最初の4カ月で37%上昇した。これにより、日本経済の先行きには明るさが戻ったように見える。
だが、EIUによる予測では実質GDP成長率がわずか1.2%にとどまるなど、マクロ経済分野での2013年の見通しはそれほど明るいものではない。
中国との緊張関係や、政府の新たな景気刺激策が膨大な財政赤字に与える影響など、依然として大きな懸念材料も残っている。またアベノミクスがもたらした市場の楽観ムードは、今回の調査結果に反映されていない。 しかしEIUが作成した「国内中堅企業の景況感指数」によると、国内中堅企業は今後の業績や経済動向に関し、過去数年よりも楽観的な見通しを持っている。 主要な調査結果 【良好な収益見通しは中堅企業の柔軟な対応能力を反映】 今回の調査結果によると、日本の中堅企業は企業全体と比べて優れた業績を上げているようだ。中堅企業による2011年の平均収益は、損益分岐点である指数100を下回るレベルまで低下した。しかし、2012年には100をわずかに上回るところまで回復し、2013年の収益予測指数は103.3まで上昇している。この背景の1つとして考えられるのは、新政権の積極的な経済政策に対する好感ムードだ。 また中堅企業は、日本企業の中でも非常に柔軟な対応力を持っているようだ。今回調査の対象となった企業幹部の多くは、過去3年間の自社製品・サービスに対する需要(そして業界全体の景況)が経済全体の傾向と比較して良好だったと考えている(表2.3参照)。 これは、全ての指標が100を下回るマイナスとなっていることを考えても興味深い結果だ。第1章で明らかにしたように、2008〜10年に中堅企業が上げた収益の平均値は大企業を上回るものだった(名目平均値は大企業・中堅企業共にマイナス値)。上述の結果は、こうしたトレンドに沿ったものだろう。
■国内中堅企業の景況感指数:調査方法について■
国内中堅企業の景況感指数は、今回EIUが実施したアンケート調査の結果から作成したものだ。同調査では回答者に対して、収益や雇用水準など数値化可能な業績評価指標が過去3年に増加・減少したのか、あるいは2013年に増加・減少するかといった質問への回答を求めた。さらに、総需要や市況、業界あるいは経済全体の景気動向などの質的要因が過去3年に改善したか悪化したか、2013年にどのように変化するかといった質問も行った。 調査対象者は、こうした全ての設問に1から5の5段階評価で回答している(1=大きく改善(増加)、2=ゆるやかに改善(増加)、3=変わらない、4=ゆるやかに悪化(減少)、5=大きく悪化(減少))。 この調査結果から1年毎に単一の指数を導き出すために、1から5までの数字を選択した回答者の割合にそれぞれ1.5・1.25・1・0.75・0.5を掛け、その結果にさらに100を掛けた数値を求めた。例えば100以上の指数[最大150]は、その年の(例えば成長に関する)センチメントがプラスであったことを示している。また100以下の指数[最低50]は、ある項目に対するその年のセンチメントがマイナスであったことを示している(例えば景気後退など)。 標準的な調査方法によって導き出されたこれらの指数は、サブグループごとに比較可能だ。ただし、2010〜12年までの指数が実際のパフォーマンスから導き出された値であるのに対し、2013年の指数は同年1月時点での予測であることに留意されたい。今回の調査結果では、2013年に関する指数の多くが、予想に反して大幅なプラスになっている。この理由の1つとして考えられるのは、調査対象となった経営幹部の多くが、今後の見通しに対して希望的観測を行っていることだ。 【輸出収益は増加の見込み】 今回の調査結果によると、輸出を行う中堅企業(全体の42%)は2013年の業績見通しに楽観的で、海外収益指数(104.2)が国内収益指数(102.6)を上回った(表2.4参照)。この結果の理由の1つとして考えられるのは、2011〜12年のほとんどの期間で、競合国の通貨(特に韓国ウォン)と比べた日本円の割高感が強かったことだ(表2.5参照)。 しかし、日本銀行にさらなる金融緩和を求める政府の圧力が強まったことなどを背景に、円が調査実施直前の数週間で大きく下落した。楽観ムードの背景には、この円安傾向によって国内企業の輸出競争力が向上したことがあると考えられる。
【雇用水準は横ばい状態】
しかし中堅企業の収益増加が、雇用拡大につながる見込みは低いようだ。2012年を通じて雇用水準は大きな変化を見せておらず、2013年も横ばい状態が続く可能性は高い(指数100.8)。これは、2013年は有能な人材の新規採用を重点的に行うとした回答者が全体の47%に上ったという調査結果と相反するものだ(重点的に行わないとした回答者は9%)。 有能な人材の新規採用が重点事項であるかないかにかかわらず、中堅企業の雇用水準が大幅に改善する可能性は低い。仮に期待に見合った収益拡大が実現しても、この傾向は変わらないようだ(表2.6 )。
【資金調達環境は改善の兆し】
外的要因が及ぼす影響に関して、中堅企業による2013年の見通しは控え目だ。2011〜12年のセンチメントと比較すると改善が見られる。しかし競争・規制環境が2013年をつうじて変化しない、あるいは悪化すると答えた調査対象者は、依然として半数を超えている(表2.7参照)。 一方で、資金調達環境に対するセンチメントには明らかな改善の兆しが見られた。2012年・2013年の両方で、楽観的な回答者がそうでない回答者の割合を上回っている(指数は101.8から103.9に上昇)。 今年3月の中小企業金融円滑化法の失効を考えれば、これはある意味で予想に反する結果だ。2009年12月に施行された同法は、中小企業が返済期間延長や利息軽減といった形で返済負担の軽減を要請した場合に、可能な限り貸付条件変更の努力を行うよう金融機関に求める法律だ。小企業だけでなく、同法の恩恵を受けた中堅企業も少なからず存在することが想像できる。 今回調査を実施したのは、同法の失効が目前に迫る時期だったが、新たなマクロ経済政策により資金調達環境の改善を期待するムードが広まったのも確かだ。日本では超低金利が長年続いているものの、実質金利はデフレによる高止まりの状態にある。 しかし2013年に入り、日本銀行がさらなる量的金融緩和政策やデフレ対策強化の姿勢を打ち出したことで、市場の期待感は急速に高まっている。今後の資金調達環境について、中堅企業がより楽観的な見方を示しているのはこのためだ。 【製造業は今後の見通しに悲観的】
調査参加企業で全体の24%と最も多くの割合を占めた製造業は、2011〜12年にかけて最も大きな業績低迷を経験したグループだ。2013年の見通しについても、最も悲観的な見方を示している。
2010年に98だった製造業の平均年間売上高指数は、2011年には96、昨年は93と継続的に下落している。 2013年の見通しに関しては98.6とやや上向きの傾向も見られるが、依然として収益低下を予想する回答者が半数を上回っている。製造業は2013年の指数が100を下回った唯一の業種だった(表2.8参照)。 これは、ある意味で予測可能な結果だといえるかもしれない。過去3年間、日本の製造業は様々な困難に直面してきた。特に円高が続いたことで、輸出競争力は大きく削がれる結果となっている。 また製造業の中堅企業は、他業種と比較しても海外市場への依存度が高い。海外市場で収益を上げる中堅企業は全体の42%であるのに対し、製造業では59%に上っている。また今回の調査では、収益全体の10%以上を海外市場で上げている中堅製造業が全体の37%に上る一方で、中堅企業全体ではその割合が26%にとどまった。 しかし、直接輸出による収益の落ち込みは理由の1つにすぎない。日本の中堅製造業の多くは、(例えば自動車産業など)多くのセクターで大企業のサプライヤーとして機能している。円高や中国など一部主要市場での反日感情の高まりを背景に、大企業の輸出が近年落ち込んだことで、中堅企業が大きなあおりを受けた可能性は高い。 しかし海外市場で収益を上げる企業の半数以上が、輸出環境に関して楽観的な見通しを示していることは好材料だ。製造業では依然として100を割り込んでいるものの、海外収益に関する2013年の指数は全体で102.4とプラス値になっている。 【最も良好な業績を上げ、今後の見通しに楽観的なのはヘルスケアセクター】 製造業とは対照的に、国内中堅企業の中で最も楽観的な見通しを示したのは、ヘルスケア・製薬・バイオテクノロジー業界だ。同セクターに属する企業の総収益指数は、過去3年連続でプラスとなっており、2013年も収益の伸びを予想する回答者が半数以上を占めた。 今年の指数は107と金融サービスや建設・不動産業界と並んで最も高い値だが、2012年・2011年の指数(109・112)に比べると若干見劣りする。しかし、楽観的な見方を示した回答者が半数を大きく上回っている点は変わらない。 こうした楽観ムードは、基本的に国内経済の状況を反映するものだ。急速に進む人口の高齢化やイノベーション・投資促進に向けた政府の施策を背景に、同セクターは最も有望な成長分野の1つとなっている。このことは、自社製品・サービスに対する需要の伸びを期待する中堅企業の多さからも明らかだ。製造業の指数が99だったのに対し、同セクターでは108となっている。
またヘルスケア・製薬・バイオテクノロジー分野では、2012年の厳しい状況と比べ今年の競争環境が改善するという見方を示した回答者が最も多かった。
雇用水準の分野では、同業界とその他業界の差が特にはっきりと現れている。ヘルスケア・セクターでは、過去3年間の指数が連続して108を上回っているのに対し、他のセクターが記録した最高数値は104にとどまった(表2.9参照)。 2013年に有能な人材の新規採用に力を入れると答えた同セクターの回答者は約60%で、全体平均の47%をはるかに上回っている。 また、「当社は自社でキャリアを全うする若い人材の育成に真剣に取り組んでいる」という記述に同意した回答者も、同セクターでは約52%に上っている(全体平均は41%)。 ■オンコセラピー・サイエンス:独自の道を切り拓くために■ オンコセラピー・サイエンスは、東京大学医科学研究所から派生した創薬ベンチャー企業で、ヒトゲノム解析をベースに副作用の少ないガン治療薬の開発を専門に行っている。2011〜12年度に約63億円の売上を予想する同社は、2003年に東証マザーズへ上場。自ら治験は行わず、自社が開発するガン治療新薬の製造・販売権を製薬会社に供与するというモデルに基づいてビジネスを展開している。これまでのところ、ライセンス供与の対象は日本企業に限られているが、海外の製薬企業とも現在交渉を行っている。 同社が本社を構えるのは、神奈川県を含む官民の共同出資によって設立され、主に創業まもないベンチャー企業の拠点となっている「かながわサイエンスパーク」(川崎市)だ。同社の代表取締役社長をつとめる角田卓也氏によると、中堅企業が対象となる金融支援策も存在する。しかし、あまりに数多くの義務や制限事項があるため、実際にこうした支援策を活用することはきわめて難しいという。 「例えば政府や自治体から支給された助成金は、3月の年度末までに全て使い切らなければならない。もし助成金から利益が上がれば、速やかに返納する必要がある。我々が必要としているのは、研究活動に再投資できるような資金だ」と角田氏は語る。 他の中堅企業やベンチャー企業と同じく、オンコセラピー・サイエンスも有能な人材の確保という課題に直面している。しかし日本最高の学術機関の1つである東京大学と共同研究を行っているため、同学の人材を比較的雇用しやすい環境にある。角田氏によると、バイオテクノロジー企業ではテストで高い点数を獲得する能力よりも、既成概念にとらわれない発想力が重要になることが多いという。 同氏は、パイプラインと成長力強化に向けたM&Aを視野に入れている。しかし「大企業」になることには関心がなく、今後も革新的治療薬の開発企業という立場でビジネスを行う意向だ。同氏によると、日本のバイオベンチャーが直面する問題の1つは、大企業へと成長を遂げたロールモデル(手本)となるような企業が存在しないことだ。「我々は政府の手を借りずに、他企業の手本となるような企業を目指したい」と同氏は語る。 【建設・不動産セクターも今後の見通しに楽観的】 今後の見通しに楽観的なもう1つのセクターは、2013年の総収益予測で2番目に高い指数107.7を記録した建設・不動産業界だ(1位はヘルスケア・製薬・バイオテクノロジー業界)。また同セクターに属する中堅企業は、業界を取り巻く2013年の環境についても指数106と、ヘルスケアセクターを上回る最も楽観的な見通しを示している。 しかし復興需要の後押しにもかかわらず、過去3年間の市場環境に関して「悪化した」と考える回答者は「改善した」と考える回答者を大幅に上回った。 同セクターで見られる楽観ムードの背景の1つとして考えられるのは、自民党の政権復帰という短期的な要因だ。建設・不動産業界は、歴史的に見ても自民党と密接なつながりを持っており、先の総選挙で同党が大勝したことがセンチメントを改善させた可能性は高い。1月に政府が発表した10.3兆円規模の緊急経済対策では、予算のかなりの部分がインフラ整備や建設などの公共事業に充てられている。 こうした背景を考えれば、建設・不動産業界が今年の雇用拡大に積極的なのは当然のことかもしれない。雇用水準に関する同業界の指数(104)は、ヘルスケアセクターに次いで2番目に高い値となっている。 【金融・専門的サービス業界は海外収益の持続的な伸びを予測】
今回の調査結果によると、海外市場で収益を上げる中堅企業は、全体として今年の輸出収益の見通しに楽観的だ(最近の円安傾向が理由の1つであることは間違いない)。
最も楽観的な見通しを持っているのは、調査対象企業のうち35%が海外で収益を上げる金融・専門的サービス業界だ。 非常に好業績だった昨年の数字には見劣りするものの、2013年の指数は107で、海外収益の拡大を予想する回答者が半数を大幅に上回っている(表2.10参照)。 同業界は過去数年、(例えば製造や小売など)他業界の輸出企業よりも優れた業績を上げているようだ。その理由の1つとして考えられるのは、日本の大企業が積極的にM&Aを行ったことだ。 2012年初頭からEIUがアンケート調査を開始した12月中旬にかけて、日本企業は489社の海外企業を買収している(1990年の463件を上回る記録)。M&Aアドバイザリー企業レコフのデータによると、買収総額は6.89兆円(約80億米ドル)と過去3番目に多い。それぞれの案件には金融・専門的サービス企業が関与するため、海外案件の支援能力を持つ中堅企業が恩恵を受けた可能性は高い。 【小規模中堅企業のセンチメントは比較的低調】 近年の業績や今後の見通しに関する小規模中堅企業(年間売上高10億〜100億円)のセンチメントは、より規模の大きな中堅企業と比べて低調だった。この結果は、日銀短観をはじめとする景況調査と同様の傾向を示している。 またEIUの調査結果では、大規模中堅企業(500億〜1000億円)による2012年の指数が、中規模中堅企業(100億〜500億円)を下回った。しかし大規模企業は2013年の見通しにより楽観的で、総収益に関する指数(109)は小規模・中規模企業(約102)を上回っている。 【新興企業の見通しはより楽観的】 創業10年以内の新興中堅企業とそれ以上の歴史を持つ中堅企業を比較すると、前者は今年の見通しについてはるかに楽観的で、2012年の業績も大幅に上回っている(表2.11〜2.14参照)。
■ライフネット生命:成熟市場がもたらす機会■
2008年に創業したライフネット生命は、日本に戦後初めて誕生した独立系生命保険会社だ。日本の生命保険市場では、世帯加入率が約90%に達しており、膨大なリソースを持つ老舗大企業が圧倒的なシェアを誇っている。一見すると、新規参入企業に有利な条件が整っているとはいいがたい環境だ。 しかしネット専業の生命保険会社である同社は、革新的なビジネス戦略をつうじて急速な成長を実現している(2012年12月31日現在の保有契約に基づく年換算保険料は約63億円)。 同社の共同創業者で現在代表取締役社長をつとめる出口治明氏によると、日本経済が低迷する中で「低廉な価格の保険商品に対する需要は(特に若者世代で)大きい」という。このニッチ市場を開拓するため、同社はインターネットを主な販売チャンネルとし、保険価格を大幅に引き下げるとともに、ネット利用率の高い若者世代をメインターゲットに据えた。出口氏によると、同業界の既存大企業は「急速な経済成長と人口増加を背景に、膨大な販売ネットワークをつうじて高価な商品を販売するという20世紀のビジネスモデルに未だに依存している面がある」という。 世帯加入率90%と飽和状態にある生保市場の現状にも関わらず、同社は先行きに楽観的な見通しを持っている。出口氏によると、「当社の契約件数は約17万件で、顧客数にすると約10万人だ。しかし、今年の新成人が約120万人いることを考えれば、ごくわずかな値に過ぎない」という。「当社にとって、日本の生保市場はブルーオーシャンだ」と同氏は語る。 新興企業の楽観ムードは、国内・海外収益、所属業界全体の動向、自社製品・サービスへの需要といった分野でも明らかだ。また規制・競争環境や、(歴史の長い企業が優位だと考えられる)資金調達環境などの外的要因についても、新興企業ではより楽観的なセンチメントが見られた。 しかし新興中堅企業の楽観ムードについては、いくつかの点に留意する必要がある。その1つは、こうした調査の結果が、比較的小さなデータセットの傾向に基づいていることだ。調査対象企業に占める新興企業の割合は、7.3%と少数にとどまっている。また新興企業・産業では収益の増減幅がより大きいため、楽観的な見通しが現実を反映しているとは限らない。 (大企業になるのではなく)中堅企業としての規模を維持する企業で、急速な成長を遂げる見込みが低く、非常に楽観的な見通しを持つ経営者の数も少ないのはある意味自然なことだ。しかし創業50年以上の企業は、2013年を通じた日本経済全体の先行きに最も明るい見通しを持つ傾向が見られた。 この結果は、自民党の政権復帰に対する楽観ムードを反映しているのかもしれない。戦後の自民党政権下で創業した中堅企業の経営者にとっては、同党の返り咲きが期待感を抱く要因になっているのかもしれない。 【地方の中堅企業にはより悲観的な傾向が見られるものの東北企業のセンチメントは改善の兆し】 日本銀行による最新の地域経済報告[さくらレポート]によると、北海道は地方の中で唯一、景気低迷から脱却の兆しを見せている。しかし同地域を拠点とする中堅企業のセンチメントは楽観的とは言いがたい。北海道と九州・沖縄は、今回の調査で2013年の収益予測指数が100を下回った(つまり悲観的な見方が優勢な)唯一の地域だった。 一方、東北地方を拠点とする中堅企業の景況感には、好転の兆しが見られるようだ。東日本大震災の被災地であるという明白な理由もあり、東北企業のセンチメントは楽観的とはほど遠い状態で、2012年の収益・雇用水準指数では最も低い数値を記録している。 しかし企業のムードは最悪の状態から好転しつつある。同地方の中堅企業は、2012年の国内収益指数で最高の値を記録し(107.4)、総収益の分野でも2番目に高い指数(106.1)を示した。また、2013年の資金調達環境についても110.8と非常に楽観的な傾向が見られ、2番目に高い関西地方の指数(104.8)をはるかに上回っている。 (第3章は明日へ続く) http://jbpress.ismedia.jp/articles/print/38263 |
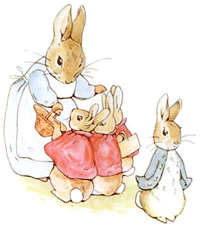

 スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。