04. 2013年7月01日 11:24:01
: e9xeV93vFQ
倉都康行の世界金融時評
急変する各国中銀の「市場との対話法」熟考された修正なのか、意図せざる結果なのか 2013年7月1日(月) 倉都 康行 中央銀行と金融市場の間の対話の必要性と重要性が注目され始めてから、筆者が記憶する限りにおいて、もう10年以上になるだろうか。その主要な舞台は米国であり、主役はグリーンスパン前議長であった。インフレ封じ込めに議長生命をかけて、有無を言わさぬ引き締め政策を敢行した前任のボルカー氏と違い、グリーンスパン氏は「巧みな話術」を通じて政策の微妙な舵取りを遂行したことで知られる。 もっとも同氏が同時に「難解な表現」でしばしば市場を翻弄したことも事実であり、お世辞にも「円滑な双方向の対話法」であったとは言い難い。筆者も、現役ディーラー時代に同氏の言葉の意味が分からなくて隣の英国人に尋ねた際に、「俺もよく分からない」と返答されて困ったことがある。 その後継者として2006年に米連邦準備理事会(FRB)議長に就任したバーナンキ氏は、グリーンスパン氏の手法とは対照的に「透明性」を重視した対話法を採り、政策内容やその決定の背後にある議論やプロセスなどを市場に対して丁寧に説くことを主眼に置いた。時には小さな失敗もあったが、その説明責任を重視する手法は日欧などの中央銀行にも大きな影響を与えており、市場もこれを歓迎している。結果として中銀は、自身の打ち出した政策が市場に理解されているかどうかを、その動向によって確認することが可能になったのである。 最近の例として中銀と市場との対話が最もよく活かされたのが、2007年夏のサブプライム・ローン問題発生時であった。震源地の米国よりも一足先に動いたのは欧州である。当時欧州中央銀行(ECB)の総裁であったトリシェ氏は、欧州市場での異変に気付き、巨額の資金供給を行って市場の動揺を鎮めようとした。 あまりに巨大に積み上がった世界的レバレッジの解消という過程で、結果的にその後の大混乱を回避することは出来なかったが、まずECBが市場の危機を読み取り、市場に流動性を与え、市場がECBの本気度を確認したというプロセスは、両者間の対話機能が活かされている証左だ、と筆者は当時実感した。 またサブプイライム・ローン問題を過小評価して初期対応としては失態を演じたFRBのバーナンキ議長も、2008年秋には市場で値が付かなくなったモーゲージ債やエージェンシー債を大量に買い取る英断を下し、FRBが壊れかけた住宅債券市場へのフルサポートを行うという明確なメッセージを発した。 当時日銀総裁であった白川方明氏も徹底的に流動性を供与する姿勢を示し、欧米で発生した金融危機が日本に波及することを予防した。もともと邦銀による米国証券化商品への投資額は少なかったのは事実だが、そうした油断が一気にシステミック・リスクを誘発する可能性はゼロでは無かったのである。ここでも「市場との対話」は活かされた、と言って良いだろう。 悪夢を思い出させたバーナンキ氏のサプライズ だが昨今のグローバルな金融市場を眺めていると、その中銀と市場とのコミュニケーションに大きな齟齬が発生しているように思われる。その最も典型的な例が、5月22日のバーナンキFRB議長による議会での「緩和縮小可能性への言及」であり、6月19日の米連邦公開市場委員会(FOMC)後の同議長の記者会見における「緩和縮小・停止へのスケジュール明示」であった。心の準備が出来ていなかった債券市場は、このサプライズに唖然とし茫然となった。 このやり方は、少なくとも従来の「バーナンキ流対話法」とは異なるものであり、米国債市場は、まだ中銀との対話の土壌が出来ていなかったグリーンスパン時代の1994年、半年で長期金利が2%以上も上昇した「債券メルトダウン」の悪夢を思い出したのである。 同議長の一連のアクションは金融緩和縮小・停止に向けた地ならしが主目的であり、銀行などに対して「金融緩和依存体質からの脱却準備」を強く要請したメッセージとして捉えられたものの、超緩和気分に馴れ切っていた市場にとって、その内容は「事前通告」の域を超えるものであった。今回、対話は成立しなかったのである。 確かに、緩和縮小・停止シナリオはFRBが描く経済回復のシナリオが正しければ、という前提のもとで実施されるのであり、その「甘い見通し」には個人的には大きな疑問符を付けたい誘惑に駆られているが、市場は9月にも緩和が縮小されるとの見方をもとに、完全な防衛体制に入っている。 その中で長期金利は急上昇してジャンク債金利は急騰、地方債やモーゲージ債の利回りも上昇して、こうした債券を大量に保有する大手米銀は蒼ざめており、過去最高値を更新してきた株式指数は頭打ちとなり、為替市場では全面的にドル買いが進んでいる。この間、最も厳しい影響を受けたのは、米国の金融政策変更に打たれ弱いブラジルやトルコ、南アフリカ、インドなどの新興国市場であった。 異例の批判的発言を行った地区連銀総裁 市場には「議長の緩和縮小・停止への急速な傾斜は不自然だ」との見方が少なくない。FOMC内部からも、異例の議長批判が挙がっている。セントルイス連銀のブラード総裁は「今年の景気見通しを下方修正し、インフレ率が低下するという危険な状況の中で緩和政策の転換シナリオを示すのは間違っている」と、議長発言の矛盾を鋭く突いている。 また長期金利が一方的に上昇し始めたのを危険視して、ミネアポリス連銀のコチャラコタ総裁が「FOMCがタカ派に傾いたと見るのは間違いだ」、「出口という言葉は適切でない」などと述べて火消しにかかり、ダラス連銀のフィッシャー総裁は「仮にQE3は縮小されても緩和は継続中なのだ」と説明し、市場は「野生のブタがあちこち走り回るように」過剰反応している、と指摘している。リッチモンド連銀のラッカー総裁も「FRBのバランスシート縮小時期はまだ遠い」と同様の見方を示している。 投票権を持たない地区連銀総裁が、FOMC直後に相次いでこうした批判的発言を行うのは極めて異例のことだと言って良い。さらにFRBの重鎮ともいうべきニューヨーク連銀のダドリー総裁すらも「米国はかなり緩和政策を進めてきたが、結果的にそれほど効果が上がっておらず、緩和は十分でない」とまで述べて、市場の動揺を抑えに掛かっている印象すら受ける。 なぜバーナンキ議長がそこまで緩和縮小の可能性を訴えたかったのか、については、先月筆者の推論(「FRBは「緩和停止」ではなく「緩和微調整」へ」)を記しておいたが、市場では「依然として明確な理由が分からない」という声も少なくない。一部には、中国が短期金利急騰容認の姿勢に転換したことを受けて、その穴埋めに米国の金融緩和を利用されたくないのだ、といった解説までまことしやかに流れている。そんな邪推に過ぎないような観測が出るほどに「議長の行動原理は不可解だ」と評価されているのだ。議長の「対話法」は明らかに崩れている。 さて次に問題なのが、その中国の人民銀行だ。中国はこれまで、民間の日中資金不足に関しては、例外なく人民銀行が流動性を供与して需給バランスを取り、金利の安定化を図ってきた。だが6月に入って突然として短期金利が急騰し、市場を驚かせたのである。 市場では6月10日からの休日である端午節を前にしての季節的な需給逼迫と解釈されたが、人民銀行が積極的に資金供給しなかったことに違和感を抱いた向きは少なくなかった。そして19日には1カ月ものの銀行間金利は一気に9%を超えてしまった。ちなみにこの金利は4月には3%台であった。翌日物が13%台、レポ・レートが20%超という異常な水準になっても、人民銀行は金利水準を押し下げるオペには出動しなかったのである。 想定外だった「中国不安」に対する大きな反応 24日になってから漸く人民銀行は「流動性の管理は銀行自らの努力で行うように」という通達を発した。それは、既に本コラムでも報じた「シャドウ・バンキング」の抑制に本格的に着手したことを意味するものであったが、これまで不足する流動性は「天から降ってくるもの」と甘く考えていた銀行経営には、青天の霹靂だったのかもしれない(「中国マネーの流れは正常ではない」を参照)。 過剰融資が噂される中小銀行を巡り、破綻懸念で株価が30%以上も下落するケースが出始めたとあっては、さすがに人民銀行も声明を出さざるを得なくなった。日欧米の市場がこの「中国不安」に大きく反応したことも想定外だったのかもしれない。人民銀行のウェブでの説明に拠れば、資金が逼迫した一部の銀行には個別に資金供給を行っており必要があればさらに対応する、という。 この対応には、「中国版リーマン・ショック」を絶対に回避すべしとの強い警戒感が働いたような印象を受ける。だがすべての問題銀行を公的に救済するのは、成長を多少犠牲にしても過剰投資体制を変革しようとする習近平主席の政治姿勢の本質から外れるものだ。不可視的に膨れ上がった不良債権を支えるほどの財政余力もない。 問題視されている「富裕層向け商品(Wealth Management Products)」のかなりの金額が6月末に償還時期を迎えたとの推測もあり、7月以降の「中国金融危機」の観測はまだ消えてはいない。日本株が上海株の乱高下に揺さぶられる日はまだ当分続きそうだ。 バランスシート管理は自分の責任で、というのは当たり前の話であるが、突然のルール変更に戸惑う金融機関からは人民銀行を批判する声も出ている。どっちもどっちの感は否めないが、これもFRBと同様に、中央銀行の対話手法の急変が金融システムの混迷に拍車を掛けたものと見ることが出来るだろう。 効能が薄れ始めた「ドラギ・マジック」 小康状態が続いているユーロ圏でも、欧州中銀の対話法に対する疑念が生じている。昨年マリオ・ドラギ総裁は「ユーロを守るためには何でもやる」と宣言し、南欧国債を念頭に置いた国債の無限買入れ制度を導入した。銀行同盟への期待感とも合わせ、この市場に対するメッセージが市場不安を一掃したことで、欧州に漸く安定感がもたらされたのである。 だが、ユーロ圏が抱える基本課題の解消はまだそれほど進んでいない。ドラギ総裁の魔術も、そろそろ効能が薄れ始めている。欧州中銀には、利下げや中銀預金へのマイナス金利、量的緩和導入などまだ追加緩和の検討余地は残っているが、その発動へのコンセンサス作りはドイツなどの反対が強く、実施はかなり困難だとの見方が強い。 市場がドラギ総裁の言葉に「苦悩」を感じたのは、6月初の理事会後の記者会見であった。年初に総裁が示した「下半期に景気回復」との見通しは外れつつあり、南欧諸国の中小企業金融支援として検討してきたABS市場の育成策も行き詰まっている。 5月の記者会見で同総裁は「次の一手」を検討しているというメッセージを発していたにもかかわらず、追加の緩和策を打ち出さなかったのは、「追加策を採ろうにも採れなかったから」と見られても仕方がない。 市場の「ドラギ・マジック」への期待は大きく後退してしまった。その背景には、依然としてバイトマン独連銀総裁との政策を巡る確執があるものと思われるが、市場は「何でもやる」といったドラギ総裁の勇ましい姿はもうどこにも見えなくなってしまった、という印象すら受けているのではないだろうか。 ドラギ総裁も、バーナンキ議長と同様に市場との対話を重要視してきた。その姿勢が急変したようには思えないが、思うように対話が出来なくなってきた、という歯痒さや辛さは外野席からも手に取るように分かる。 ユーロ危機がすぐに再発する可能性は乏しいが、亀裂が入ったまま逆に悪化の気配すら窺えるユーロ圏内の南北問題は、銀行同盟への議論をも揺さぶっている。市場の唯一の拠り所であった欧州中銀が市場との対話力を失うことは、あまり想像したくないシナリオである。 「日銀の対話力」は他にない独特のスタイル さて最後になったが、読者が最も気になるのはやはり「日銀の対話力」であろう。残念ながら筆者の見る限り、黒田総裁は主要国の中でも「市場との対話に最も関心が薄い中銀総裁」である。それは記者会見の節々に現われており、ここであえて説明する必要はないかもしれない。総裁の言葉から受ける印象は「市場とはコントロールする対象である」という認識であり、白川スタイルと全く異なるばかりでなく、他の中銀総裁にも見られない独特のスタイルと言える。 黒田日銀は4月に華々しいスタートを切ったが、国債市場に関して言えば「混乱を招いただけ」と酷評する向きは多い。一時は急伸した株価や103円まで上昇したドル円も「元の木阿弥」状態になり、米国の長期金利上昇傾向を受けて不安定化する長期国債市場を宥めるのに、日銀の現場は大変苦労しているようだ。長期金利や市場変動率を、官僚組織運営と同じようにコントロールすることは不可能なのだ。 想定外とも言える巨額の国債購入の結果として市場が流動性を失ったことも、対話方式終了の一つの代償であった、と言えるかもしれない。もっとも、国債を7割購入すれば市場を管理できるのは当然、といった当初の威圧的ムードは消えており、黒田総裁も今では「現実の市場は想定とは違う」という思いを抱いているようにも見える。 今後の焦点は、日銀と国債市場との対話の土壌が修復され再生されるかどうか、に絞られよう。これに対して、いま確固たる答えを書く自信はない。それは実は、米国FRBや欧州中銀、そして中国人民銀行に対して抱いている不安と全く同じ感覚なのである。一度崩れた対話の関係を修復するのが難しいのは、人間関係と同じである。
倉都康行の世界金融時評
日本、そして世界の金融を読み解くコラム。筆者はいわゆる金融商品の先駆けであるデリバティブズの日本導入と、世界での市場作りにいどんだ最初の世代の日本人。2008年7月に出版した『投資銀行バブルの終焉 サブプライム問題のメカニズム』で、サブプライムローン問題を予言した。理屈だけでない、現場を見た筆者ならではの金融時評。
|
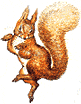
 スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。