01. 2013�N6��24�� 07:54:02
: e9xeV93vFQ
�y��821��z 2013�N6��24���@�T���_�C�������h�ҏW��
���s��ŕ��o���n�߂�
���c����ɉQ�������]�Ɠ{�����Z�@�ւ̃g���[�_�[�ɂ͈݂��ɂނ悤�ȓ�������
Photo by Satoru Okada
�����̕s����ȏ�Ԃ��������s��ŁA���{��s�ɑ���T�ς����s�������X�ɕ\�ʉ����n�߂��B 6��11���A�ߑO11��50���B���₪���Z�ɘa��̌���ێ������߂����Ƃ��`���ƁA�ꕔ�̋�s����́u���lj������Ȃ��̂��v�ƁA�[�����ߑ����R�ꂽ�B ���̑O���܂ŁA���₪0.1���̒ᗘ�ŋ��Z�@�ւɎ�������������u�Œ�����I�y�v�̊��ԉ����ȂǁA�s��̈��艻�Ɍ������Ή���ɓ��ݐ�A�Ƃ̊ϑ����L�����Ă������߂��B ������������́u�[���v�ɑ��邽�ߑ����A����ɓ{��ɕς�����̂��A����15��30������n�܂������c���F���ق̋L�҉���B���ł����Z�@�ւ̕s�������̂��A�u�i�����́j�{���e�B���e�B�i�ϓ����j�͂����Ԏ��܂��Ă��Ă���v�Ƃ��������������B �Ȃ��Ȃ�A���������s��،���Ђ͍��Ȃ��A���������ɂ���đ傫���ϓ����Ȃ���A���肶��Ə㏸���邱�ƂŁA�u���X�N�ʂ̑���ɓ���Y�܂��Ă���v�i�e�r�N�Y�E���n����s�����j���炾�B ���ۂɁA���敨�ʼnߋ��i�q�X�g���J���j�⏫���i�C���v���C�h�j�̕ϓ������v������f�[�^�����Ă��A�u�ɘa�O�Ɣ�r����ƁA�܂����ɍ��������ɂ���v�ƁA�������P���E�݂��ُ،��V�j�A���X�g���e�W�X�g�͎w�E����B ����ɁA�����̋����㏸�ɂ��Ă��A���c���ق͉�̒��Œ��ڂ̌��y�����X�ɔ����A�u���������I�y���d�˂Ă������Ƃɂ���āA���X�N�v���~�A�������k����i������ቺ������j���ʂ�����ɋ��܂��Ă����v�Ƃ����A�]���̐����ɏI�n�����B ���Z�@�ւƂ��ẮA�[���̑���ɁA���߂ċ����̈��艻�Ɍ������������b�Z�[�W���邱�Ƃ����҂��Ă��������ɁA�u���s������܂�y�����Ȃ����������v�i���s�����j�ƁA����Ɍx�����鐺�����o�n�߂Ă���B ���������x�����Î����邩�̂悤�ɁA���Z�����̗�12���ɂ́A�������������钆�ł��A�����������ꎞ0.9���ƁA2�T�ԂԂ�̐����ɂ܂ŏ㏸�����B ��x���o�������c����ւ̕s���Ɠ{��̃}�O�}�́A�ȒP�ɂ͎��܂肻�����Ȃ��B 14��15�����B������4�K�̑�O���ʉ�c���ɁA��s�Ə،���Ђ̒S��������g���[�_�[�ȂǁA�v24�l���W�߂�ꂽ�B ����n�܂�ƁA�����Ȃ̒S���҂͂܂��A�َ����ɘa�ɑΉ���������̍����D�̕��j��A�����A���̔��s�v��ɂ��Đ����B���̌�A�����̍��s��̓����ɂ��āA�Q���҂���ӌ������߂��B ���̒��ŏo�Ă����̂́A���c���ق��錾���Ă���u2�N���x�ŕ����㏸��2���̒B���Ƃ������ƂƁA�C�[���h�J�[�u�i�����Ȑ��j�S�̂�����������Ƃ����͕̂��������Ⴄ�v�Ƃ����A�ɘa��̌��_��˂�����A�u���s��̃{���i�ϓ����j�͂܂����~�܂肵�Ă���A����ቺ����͓̂���̂ł͂Ȃ����v�Ƃ����A�s���˂��������悤�Ȑ��������B �B�E���d�̍����� �ł́A���̔��s���ǂƂȂ�����Ȃ͓���َ̈����ɘa���A�ǂ����Ă���̂��B ���̎v���������Č�����Ƃ��āA�s��W�҂̊ԂŘb��ƂȂ��Ă����̍��q������B�����Ȃ�4�����ɔ��s�����u���{���j���[�X���^�[�v���B �N4�s���邱�̍��q�́A�\���ɂ���V�����̗��ŁA���N�x�̍����s�v�����Ǘ��̕��j�Ȃǂ��f�ڂ��Ă��邪�A4�������s�������͎������B 1�y�[�W�ڂœ���َ̈����ɘa��̊T�v�����������A���̌�̎s�ꓮ���Ƃ��āA�傫���������������������ƍ��敨�̉��i�̐��ڂ��O���t�Ōf�ځB����ɁA�敨�̃O���t��ł́A������ꎞ���f����u�T�[�L�b�g�E�u���[�J�[�v���������Ŕ����������Ƃ��A�������ԂƉ܂ōׂ��������ďЉ���̂��B �����≿�i�̉ߓx�ȕϓ��̗}���ƈ�������ɁA�_�o�����茸�炵�Ă�������Ȃ��A����ɑ��y�������𓊂����悤�Ɍ����邪�A���ۂ́u����ȏ�ɁA�������肵�߂�悤�Ȏv���̐l������v�Ɠ��Ȃ̊����͖������B �َ����̋��Z�ɘa����2�����]��B�܂����A6���͍��̑�ʏ��҂�����A�u20���~�K�͂̏��Ҏ������o��v�i�����ȁj�B���̎����͖{���A�ēx�A���ւ̓����Ɍ������͂������A�v�����悤�Ȕ���������ɂ����A���s��̓��h�͑����Ă���B ����ŁA�u�s��̊��҂ɓ���������v�i���c���فj���Ƃ�_��������ב֑���́A�ɘa�O�̐����ɂ܂ňꎞ�t�߂肵�Ă��܂����B �u�s��̊��҂ɓ����|����Ƃ������t���A������s���s����v���ʂ�ɓ������Ƃ����Ӗ��ł���Ƃ���A���������s��ρA����ςɎ��͊낤����������v ����ւ̕������肪���X�ɋ��܂钆�ŁA��������O���ق̑ޔC��ł̂��̔������A���ɂȂ��āA���c���ق��͂��ߐV���s���̃����o�[�ɁA�d���̂��������Ă��Ă���B �i�u�T���_�C�������h�v�ҏW�� �������B�j �@ �@ �y��14��z 2013�N6��24���@�ɓ����d [������w��w�@�o�ϊw�����ȋ����A���������J���@�\�i�m�h�q�`�j������]
���܁A�A�x�m�~�N�X���C������K�v�͂܂������Ȃ��I
�s��̍���������Ƃ��������j����������
���{�̓A�x�m�~�N�X�A
�č��̓A�x�R�x�m�~�N�X�H �č��̒�����s�ł���e�q�a�i�A�M�������x������j���p�d�i�ʓI�ɘa�j����̏o����T���Ă���Ƃ������ƂŁA�s�ꂪ�傫�ȍ������N�����Ă���B���{�����̉e�����A�ŋ߂͈בփ��[�g���傫���~�������ɓ����A�������傫�ȉ������N�����Ă���B ����ł��A���{�������������Ă���̓����Ō���A�܂������͍������A�בփ��[�g��80�~�O��̉~�������Ɣ�ׂ���Ȃ�̉~�������ł͂���B�������T�Ԃ̎s��̓��h�̌����͖��炩�ɕč����ł���A���̎��_�ł̓A�x�m�~�N�X�ɏC�����ׂ��_������Ƃ͎v���Ȃ��B �Ƃ͂����A����̓W�J���l����A���A���E�̎s��ʼn����N���Ă���̂������Ă����K�v�͂��邾�낤�B ���̎s����A�A�x�m�~�N�X���������āu�A�x�R�x�m�~�N�X�v�Ɩ��Â����l�������B�o�ϊw�̋��ȏ��ɏ����Ă���̂Ƃ͋t�̎��Ԃ��N���Ă���Ƃ����Ӗ��ŃA�x�R�x���Ƃ����̂��B��������C���킹�ŃA�x�m�~�N�X���������Ă͂��邪�A�A�x�R�x�Ȃ͓̂��{�ł͂Ȃ��č��̌o�ς��w���Ă���B �č��ł͍ŋ߁A�o�ς����Ɍ����ł���Ƃ̎w�W���o��ƁA������������h���͈����Ȃ�Ƃ��������ɂȂ�B�t�ɁA�č��o�ς���ł���Ƃ̎w�W���o��ƁA�����E�h�����ƂȂ�̂ł���B�o�ϊw�̋��ȏ��Ƃ͂܂������t�̂��Ƃ��N���Ă���̂��B �����������Ԃɑ���s��̉��߂͎��̂悤�Ȃ��̂��B �č��̌o�ώw�W�ŕč��o�ς������ɉ��Ă�����̂��o��A�s��͂e�q�a�̏o���헪�i�ʓI�ɘa�̏I���j�̎��������܂�Ɨ\�z����B�ʓI�ɘa���o���Ɍ������A�č��̌i�C�ɂ̓}�C�i�X�̉e�����o�邾�낤�B������A�����͉����邵�A�h���������鄟���Ƃ������Ƃ̂悤���B �t�Ɍi�C�����҂����قǐi��ł��Ȃ��Ƃ����w�W���o��A�o���̎����͒x���Ȃ�Ƃ̌��ʂ����L����A�בւ̓h�����A�����������Ȃ�X���ɂ���B �܂�A������בփ��[�g�́A�o�ς̎��̂̓����Ƃ������́A����ɑ�����Z����̓������ӎ������W�J�ƂȂ��Ă���B���傫���ω����邩������Ȃ��Ƃ������O���A�s���傫���������v���ƂȂ��Ă���̂��B �ʓI�ɘa�ւ̔ᔻ��
�u�e�C���[�E���[���v ���[�}���V���b�N��A�e�q�a����_�ȋ��Z�ɘa������Ƃ��Ă������Ƃɑ��ẮA�o�ϊw�҂̊Ԃł��^�ۂ�������Ă���B�m�[�x���o�ϊw�܂���܂����v�����X�g����w�̃|�[���E�N���[�O�}��������R�����r�A��w�̃W���Z�t�E�X�e�B�O���b�c�����͗ʓI�ɘa����x�����Ă��邪�A�n�[�o�[�h��w�̃}�[�e�B���E�t�F���h�V���^�C��������X�^���t�H�[�h��w�̃W�����E�u���C�A���E�e�C���[�����Ȃǂ́A�ᔻ�I�ȋc�_�����Ă���B��҂̐l�����͋��a�}�ɋ߂�����ɂ���A���Z����ɂ��Ă��ێ�I�Ȏp�����т��Ă���B �o�ϊw�̐��E�̌��t���g���A���Z����̓��[���Ɋ�Â��ׂ��ł���A�ٗʓI�Ȗʂ����߂Ă͂����Ȃ��A�ƃe�C���[�����͎w�E����B�u�ٗʓI�Ȑ���^�c�v�Ƃ́A������s���o�Ϗ����Ȃ����_�ɋ��Z�ɘa����Z�������߂��s���p�����w���Ă���B ����ɑ��āu���[���Ɋ�Â�������^�c�v�Ƃ́A���Ԋ�Ƃ�����\���\�ȃ��[�����������Ɩ������A����Ɋ�Â�����^�c���s���p�����w���B���Ƃ��A�C���t���E�^�[�Q�b�g�́A���[���Ɋ�Â�������^�c�̓T�^���B�����㏸����������̖ڕW�����Ɏ��߂�悤���Z��������p����Ƃ�����@�ł���B �č��ł́A�]���A���Z����́u�e�C���[�E���[���v�ƌĂ����̂Ő����ł���`�ɂȂ��Ă����Ƃ����c�_������B�e�C���[�E���[���Ɋւ���ڂ��������͏ȗ����邪�A������������ۂ̕����㏸��������f�c�o�̓����ɍ��킹�Ē�������Ƃ������[���ł���B����͏�q�̃e�C���[�����ɂ���Ē��ꂽ���̂��B�����̂e�q�a�̐���^�c�������ȈӖ��Ńe�C���[�E���[���ɉ����Ă����Ƃ����킯�ł͂Ȃ����A����^�c�ɑ傫�ȉe���͂������Ă������Ƃ͊m�����B �C���t���E�^�[�Q�b�g�ł���e�C���[�E���[���ł���A���Z�������������[���Ɋ�Â��ĉ^�c����Ă���A�s��̂ق�������̐����W�J�̕����ɂ��Ă�����x�\�z���邱�Ƃ��ł���B���������\�z�\�����s������艻�����ŏd�v�ȈӖ������̂��B ���[�}���V���b�N��A�e�q�a���s���Ă������x�̗ʓI�ɘa����́A�����������[������E�������̂ŁA������s�̍ٗʂ��F�Z���o������ƌ�����B�s��͓��R�A�e�q�a�����ɑł��o�����ǂ̂悤�Ȃ��̂��^�S�ËS�ƂȂ�B���݂̕č��̏ł́A����ȏ�̒lj��ɘa���\�z����l�͏��Ȃ��A�s��̊S�͏o������ł���ɘa�̏I�������Ȃ̂��A���邢�͂ǂ̒��x�̋��Z�������߂ɂȂ�̂��Ƃ������ƂɂȂ�B �����ɂ͂e�q�a�ɂ��ٗʂ̗]�n���傫���̂ŁA�s��̗\�z���U��邱�ƂɂȂ�B�e�C���[�������e�q�a�̗ʓI�ɘa�̐���^�c�ɔᔻ�I�Ȃ̂��A���̓_�����邩�炾�B�܂��A�č��ɂ�����o���헪�ւ̗\�z�̐U�ꂪ�A�s���s���艻�����Ă��邱�Ƃ������ł���B �����̈Ⴄ���Z�����
���ɖ߂���� ���Z����ɂ��Ă͂ł��邾�����[���Ɋ�Â�����^�c���D�܂�����������͂��̂Ƃ��肾�낤�B�������A����͕����ɐ��藧���Ƃł���B�e�q�a����_�ȗʓI�ɘa����Ƃ����`�ōٗʓI�Ȑ���^�c�������̂́A���[�}���V���b�N�Ƃ������ĂȂ����������Z��@�ɑΉ����邽�߂ł���A�����ăf�t���Ɋׂ��@��邽�߂ł������B �܂�A�����ł͂Ȃ������̂��B��펞�����炱���A�����đ�_�ōٗʓI�ȋ��Z�ɘa����Ƃ����B����͂܂��Ɏ����̈Ⴄ���Z����ł������B�����āA���ꂪ����t�����B���[�}���V���b�N�̈��e�����ŏ����ɂƂǂ߁A�č��o�ς��{�i�I�ȃf�t���Ɋׂ邱�Ƃ��Ȃ������B �e�q�a�̏o���헪�́A����������펞���畽���ւ̓]���Ƃ������Ƃł�����B�P�Ȃ���Z�������߂ł͂Ȃ��B�e�q�a�͎s��ɑ��Ă��܂��܂ȃ��b�Z�[�W�𑗂�Ȃ���A�����ւ̈ڍs�̃^�C�~���O���͂����Ă���B����Ɏs�ꂪ�傫���������Ă���B�傫�����锽���ƌ����Ă��悢��������Ȃ��B �A�x�m�~�N�X�ōs��ꂽ���Z������A���{��s�ɂ���_�ōٗʓI�ȋ��Z�ɘa��ł���B���̈Ӗ��ł́A�č��Ǝ����ʂ�����B�����܂ł��Ȃ����A�������������ٗʐ������������炱���A�s��ɑ傫�ȉe�����y�ڂ����ʂƂ��Ȃ����B�בփ��[�g�⊔�����傫���������̂��B���̑�_�ȍٗʐ��������A����ȑO�̒�����s�̋��Z����^�c�Ƃ̈Ⴂ�ł���ƌ����Ă��悢��������Ȃ��B �č��Ƃ͈قȂ�A�����_�̓��{�ŏo���헪�ɂ��Č��̂͑�������B���ʂ́A��_�ȋ��Z����ɂ���ăf�t������̒E�p���O���ɏ�邩�������茩�ɂ߂鎞���ł���B�����헪�Ȃǂɂ���Čo�ς̊g�傪�����ȋO���ɏ���悤�ɂ��邱�Ƃ��d�v�ł���B ���̎��_�ŁA�A�x�m�~�N�X���C������K�v�͂܂������Ȃ��B��_�ȋ��Z�ɘa���ێ����Ȃ���A�����헪��i�߂Ă����B���͂���o�ς̏���������������Ǝ������ƂŁA���ԓ����̑����𑣂��Ă����B�����Čo�ύĐ��ƍ����Č��̍D�z��ڎw���B�s��ɑ����̍��������邩�炱���A�A�x�m�~�N�X�̐���̃X�^���X����������ێ����Ă������Ƃ��d�v�ƂȂ�B �Ƃ͂����A�č��ł̏o���헪�ւ̎v�f�������炵���O���[�o���o�ς̓��h�́A���{�ɂƂ��đ傫�ȋ��P�ł������B���E�o�ς��[���A�����Ă���A���{�ȊO�̐��E�̂ǂ����ő傫�ȓ������������ꍇ�ł��A���ꂪ���{�ɉe����^�����˂Ȃ����Ƃ��킩�������炾�B �C�O�ɂ͂��܂��܂ȃ��X�N�v��������ł���B���B�̍�����@�͏��N��Ԃɂ��邪�A���܂��ĔR���邩�킩��Ȃ��B�����o�ς���������\�����w�E������Ƃ������Ă��邪�A��������{�ɂƂ��Ă͑傫�ȃ��X�N�v���ł���B���{�o�ς���ɂ��������O����̃��X�N�ɂ��炳��Ă��邱�Ƃ�Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��B �����炱���A�ł��邾�������f�t������E�p���A���{�o�ς������Ȑ����O���ɏ悹�邱�Ƃ��d�v�ƂȂ�B�O���[�o���o�ς̓��h�ւ̑Ή��Ƃ��ẮA�A�x�m�~�N�X���C������̂ł͂Ȃ��A�A�x�m�~�N�X���������ƌ������A�����헪�������������邱�ƂőΉ�����̂��]�܂����B �@ �@�y��34��z 2013�N6��24���@�����u [�j���[�z���C�Y�� �L���s�^�� ���������В�]
�����헪�Ɍ����Ă���
���X�N�}�l�[�����������z���P�̎��_
���{�����̐V�����헪���]������Ȃ����������́A���܂�ɑ��ԓI�Ŏ{��̑S�̑����̌n�I�ɐ�������Ă��Ȃ��������ƁA��Ƃ̊������ɕK�v�ȃA���ƃ��`�̐���̃o�����X�����Ă��Ȃ��������ƁA�����āA�������Y�Ƃ̐V��ӂ̌��ł���u���X�N�}�l�[�̋����v���A�����z�̉��P�̊ϓ_�����̓I�Ɍ���Ă��Ȃ����Ƃł���B���ɁA���I�N�����̉^�p���l��������ɐi�߂邱�Ƃ����A���v�́u�꒚�ڈ�Ԓn�v�ł���B ���{�����̐����헪��
�Ȃ��]������Ȃ��̂� 6��14���A���{�����̐����헪�u���{�ċ��헪�|JAPAN is BACK�|�v���t�c���肳��A����ł�����O�{�̖�̍ŏI�͂����\���ꂽ���ƂɂȂ�B�������Ȃ���A���̗v�|�����炩�ɂȂ���6�����{�ȍ~�A�����s��̓l�K�e�B�u�ɔ������Ă���B�܂��A�u�������̐����헪�v�i�w�T���_�C�������h�x2013.6.22���j�Ƃ܂ō��]����A�t�c�������]���͖F�����Ȃ��B �������Ȃ���A�M�҂́A����94�y�[�W�̐����헪�ɂ́A���̒������҂��Ă��������̂��̂����Ȃ�܂܂�Ă���ƍl���Ă���B���Ƃ��A�ٗp���s�ɂ��ẮA���ًK���̊ɘa������̓I�ɓ���Ȃ��������A�ٗp�ێ��^����J���ړ��x���^�ւ̐����]����搂��Ă��邵�A�����̊���̂��߂̈玙�x���ɂ��Ă��A���m�Ȑ��l�ڕW���f�����Ă���B���̂ق��ɂ��A�ݔ��̉������p�̋��e�A�h�s�̊��p�A����A����̑n�݁A�d�͋K�����v�ȂǑ����̐����荞�܂�Ă���B �������A���́A�@�����̐��̌n�I�ɂǂ��A�ւ��Ă���̂��̑S�̑��������Â炢�̂ŁA���ԓI�Ȉ�ۂ�^���邱�ƁA�A���Ԃ̊��͂��������ƌ����Ȃ���u�A���v�i�K���ɘa�j�ɑ���u���`�v�i��Ƃ̃K�o�i���X���v���j�̎{���ݍ��ݕs���ł��邱�ƁA�B�_�Ɛ���ɂ����āA�_�n�W�Ƃ������������i�_�Ƃɑ���u���`�v�j�ɓ��ݍ��߂Ă��Ȃ����ƁA�C��Ƃ̐V��ӂ𑣂��ƌ����Ȃ���A�]���r��Ƃ𖠉��i�͂т��j�点�Ă��鍪�{�I�Ȍ����ł����s�̊Â����Y�����̌������ɓ��ݍ���ł��Ȃ����ƁA�D�S�̂�ʂ��ĕK�v�ƂȂ鎑���ƁA������ǂ̂悤�ɘd���̂��A���ɗa���E�N�����ɕ݂���ƌv����̋��Z���Y���A�ǂ̂悤�Ɋ��p����̂�����̓I�Ɏ�����Ă��Ȃ����ƁA�ł͂Ȃ����낤���B ���ɁA�����ʂɂ��ẮA���ׂĂ̎{��ɉe��������ł���A�\�Z�������Ă��钆�A�����z�̉��P�ł�����ǂ��d���̂��́A�{���́A�S�̑��Ƌ��ɖ`���ɂČ����ׂ������헪�̍����������͂��Ȃ̂ɁA���ꂪ���������Ă��邱�Ƃɂ͋�����a�����o����B�M�҂͗\�Ă����I�N�����̉^�p���l�������ɁA���{�̎����z�\����ς��āA��Ƃɑ��郊�X�N�}�l�[�̋��������I�Ɋg�傷�邱�Ƃ��d�v�Ǝ咣���Ă����B �{�e�ł́A�Ȃ��A���A���I�N���̉^�p���l���������헪�̒��ōł��d�v�ȉۑ�Ȃ̂��ɂ��ĉ��߂čl����Ƌ��ɁA���̎{�����ʂ�u�꒚�ڈ�Ԓn�v�ł���Ƃ������Ƃ����{�^�}����̖��m�ȃ��b�Z�[�W�Ƃ��ďo����邱�ƂɊ��҂�����̂ł���B ���{�̌��I�N����
�^�p�\���͋ɂ߂čd���I ���{�̌��I�N�����^�p���Ă���N���ϗ��Ǘ��^�p�Ɨ��s���@�l�i�f�o�h�e�j�̎��Y�^�p�̊�{�|�[�g�t�H���I�i���Y�z�������j�́A�����J����b����߂�u�����ڕW�v�ɏ]���A�f�o�h�e���쐬����u�����v��v�ɂ���Ē�߂���B���݂͂��̌������̃T�C�N����5�N���ł���A�������^�p���Y�̍\�������́A����܂�3��̌��������o�Ă��قƂ�Ǖω����Ă��Ȃ��B ���̊�{�|�[�g�t�H���I�̓���́A���炭������67���A��������11���A�O����8���A�O������9���A�Z�����Y5���ł��������A6��7���ɁA��������60���A��������12���A�O����11���A�O������12���ւƂ킸���Ȃ���ύX���ꂽ�B�������A����͍����̊�������̏㏸�ɂ��]�����ɂ��A�����I�ɕۗL�����̊��������������߁A�������ǂ�������̂ɉ߂����A�ϋɓI�Ȑ����I�Ӑ}���������ύX�ł͂Ȃ��B �����헪�ɂ����ẮA����A���{���ݒu����L���҉�c�Ō��I�N�����̎��Y�z�����j���c�_����邱�ƂɂȂ��Ă��邪�A�{���A�N���̉^�p���j�́A���X�N�̑��Ǔ��A����̌v�Z�����ł͂Ȃ��A������Ɛ헪�Ƃ��đ��ʓI�ɍl�@�����ׂ����̂ł���B�����āA���̏ꍇ�̎��_�́A�@���X�N�Δ䃊�^�[���̌���A�A�c�����s�g���[���̊m���A�B�����Y�Ƃ̐V��ӑ��i�ɂ�鍑�Ɨ��v�̒B����ʂ����������I�^�p���т̌���A�C�f�o�h�e���N���^�p�҂̍X�Ȃ�v���t�F�b�V���i�����A���ł���B�{�e�ł́A�ȍ~�A��Ƃ��ć@�ƇB�̎��_�ƁA����Ɋ֘A���鎖���ɂ��Ę_����B �č��ł͔N�������Ɛ헪�Ƃ���
�Y�Ƃ̐V��ӂ𑣂��Ă��� �A�ڑ�22�� �A23��ŏڂ����_�����悤�ɁA�č��ł�1974�N�ɔN�������҂̗��v��ی삷�邽�߂ɃG���T�@�i�]�ƈ��ސE�����ۏ�@�j�����肳��A���x���̉������o�Č��݂Ɏ����Ă���B�{�e�Ƃ̊֘A�ŏd�v�Ȃ̂́A79�N6���ɖ��m�����ꂽ�v���[�f���g�}���E���[���i�����Ɋւ���`�����߂����́j�A�y�сA88�N�ɘJ���Ȃ��炩�甭�s���ꂽ�u�G�C�{���E���^�[�v�i�c�����s�g���u����ҐӔC�v�Ɩ��m���������́j�ł��낤�B ���Ȃ킿�O�҂͔N������̕��U�������`���t���A��Ƃ̍Đ���ĕ҂�S���v���C�x�[�g�E�G�N�C�e�B�i�o�d�j��A�V�K�Y�Ƃ̈琬��S���x���`���[�E�L���s�^���i�u�b�j�ɑ��z�̓�����������������_�@�ƂȂ������̂ł���A��҂́A�c�����s�g�ɂ���Ċ�Ƃ̌o�c�Ď������߂邱�Ƃɂ���āA�R�[�|���[�g�K�o�i���X�̌���𑣂��Ă����B 79�N�̃v���[�f���g�}���E���[���̎{�s�ɂ���āA78�N�������������N��5���h�����x�ł������č��̂o�d�E�u�b�ւ̎����������A80�N�㔼�ɂ͑�������10�{��50���h�����x�ɂ܂ŋ}�g�債�A�č��̂o�d�E�u�b�̎������̂����N���������߂銄���́A78�N���_��15���ł��������̂��A80�N��ȍ~��50���O��ɂ܂ō��܂����B�ŋ߂͕č��̌��I�N���́A�o�d�ւ̓�������w���������Ă���A���^�p���Y��10�����O���o�d�ɓ������Ă���B���ɁA���Y�K�͂�50���h�����N���́A�����Y��12.7�����o�d�ɔz�����Ă���i�v�r�i�E2013�N1��24���j�B ���ł͕č��̂o�d�E�u�b�ւ̎��������́A���[�}���V���b�N�O��07�N���_�łf�c�o��3.9���A���[�}���V���b�N���11�N�ł�1���ł���̂ɑ��A���{�͂��ꂼ��0.4���A0.2���ɉ߂��Ȃ��B���̏����������ʁA�č����\�����ʂo�d�́A������3�`5���~���x�̉^�p���Y�������A�č��͂�����E���̊�ƍĐ���ĕ҂ɋ@���I�ɑΉ����A�v�����Ă���B ����ɑ��A���{�ł�1000���~�ȏ�̃t�@���h���^�c�������Ƃ�����o�d�͐�����قǂ����Ȃ��ł���A���{���\����o�d�ł����Ă��A�����_�ł̉^�p�\�z�͏��z�ł���A�����Ɋ�ƍĐ���ĕ҂��K�v�ȋƊE���Ƃ����邱�Ƃ��킩���Ă��Ă��A�������܂܂Ȃ�Ȃ��̂�����ł��邪�A���̎�����N���̓����s���̍��ł��邱�Ƃ͖��炩�ł���B���̂܂܂ł́A�Z�p�����������{��Ƃ������ݎ����͂ɏ���C�O��Ƃ�t�@���h�ɔ�������邱�Ƃɂ��Ȃ肩�˂Ȃ��Ƃ�����@�����A���{�͋��L���Ă��邾�낤���B �����Ɨ��n�o�d�E�u�b�ւ�
���Y�z���̏d�v�� �N���̕��U�����́A�u�`���I���Y�v�ƌ������ꊔ������ɕ邱�ƂȂ��A�u��֓I���Y�v�ƌ�����o�d�E�u�b�E�C���t���E�s���Y�Ȃǂɓ����͈͂��L���邱�Ƃ��d�v�ł���B�Ƃ��낪�A���{�ł́A���I�N���́A�O�q�����u��{�|�[�g�t�H���I�v�ŁA��֓I���Y�ւ̓����͔F�߂��Ă��Ȃ��B��ƔN���̈ꕔ�ɂ͑�֓I���Y��������铮�������邪�A�������Ƀw�b�W�t�@���h�ɕ��Ă���A�o�d�ƕs���Y����ȓ����ΏۂƂ���č��̊�ƔN���Ƃ́A�S���قȂ����s���p�^�[���ɂȂ��Ă���B ��֓I���Y�̒��ł��o�d��u�b�ւ̓����𐄂��i�߂邱�Ƃ́A�Y�Ɛ����ɂ߂ďd�v�ł���B������w�b�W�t�@���h�֓������邱�Ƃ��A�s��ւ̗����������Ƃ��������͂�����̂́A�����̓����͐V���ȏo���ł͂Ȃ��̂ŁA��Ƃւ̃��X�N�}�l�[�A�܂��Ƃ��ԍς��C�ɂ����ɐ�����ĕ҂̓����Ɏg���邨���ɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ��B��Ƃɒ��ڐV�K�̃��X�N�}�l�[�������\�Ȃ̂͂o�d��u�b�ł���A���̋@�\����{�̓Ɨ��n�o�d�E�u�b�Ɏ������邽�߂ɂ́A���{�̂o�d�E�u�b�ɁA�č����݂̊����ŔN������̎����𓊉����ׂ��Ȃ͖̂��炩���B �N���^�p���Y�Ɛ���̈�ő����邱�������l�����ɂ͈٘_�����낤�B�������A�����ڂŌ���A���{�S�̂̎Y�Ƃ̐V��ӂ�i�߂邱�ƂŌo�ϑS�̂̒�グ���s�Ȃ����Ƃ́A�N���҂̗��v�ɂ����Ȃ����̂ł���B ���ɁA�č����\������I�N���ł���J���p�[�X�i�J���t�H���j�A�B�������ސE�N������j�́A�o�d�E�u�b�ւ̎��Y�z���ڕW�l��14���ƒ�߂Ă���B�J���p�[�X�́A�o�d�E�u�b�ւ̓�����ϋɓI�ɍs�����R�Ƃ��āA�@�s��A���^���Z���i�Ƃ̒Ⴂ���ցA�A�ߋ������ɘj�郊�^�[���̈��萫�A�ƕ��сA�B�����E���B�o�ς̌o�ώY�ƈ琬�������Ă���B�C���e���A�A�b�v���A�O�[�O���ȂǁA�J���t�H���j�A�̃x���`���[��Ƃ̔��W�Ɍ��I�N�����ʂ����������͌v��m��Ȃ��B�������A���ꂪ�J���p�[�X�̔N���҂̒������I�ȈӖ��ł̗��v�ɂ��Ȃ������Ƃ͌����܂ł��Ȃ��B �Ȃ��A�u���{�ɂ͏\���Ȏ��т�ςo�d��u�b���Ȃ��v�Ƃ����c�_���U������邪�A����́u�����{���v�Ƃ����A�܂��Ɂu���߂ɂ���c�_�v�ł���B�č��ł��A�G���T�@�ŕ��U�����`������߂��Ăo�d��u�b���}�g�債��80�N�O��̎��_�ŁA���т�ςo�d��u�b�Ȃǐ�����قǂ����Ȃ������̂ł���B ��֎��Y�ւ̕��U������
���X�N�Δ䃊�^�[�������P������ �u�N���������o�d�E�u�b�Ȃǂ̑�֎��Y�ɕ��U����v�Ƃ����ƁA�����̐����Ƃ��u�����̑厖�Ȏ��Y�����X�N�̂��铊���ɉȂǂ��������v�Ƃ����_����B�������A����͍��{�I�ɊԈ�����F���ł���B�J���p�[�X���o�d�ւ̓������R�ŏq�ׂĂ���悤�ɁA�o�d�E�u�b�́A��������Ȃǎs��A���^���Z���i�Ƃ̑��ւ��Ⴂ���߁A�o�d�E�u�b�ւ̓������s�Ȃ��ƁA���͓����|�[�g�t�H���I�̉��l�̕ϓ����}�����A���X�N���ጸ�����̂ł���B ����}��������ɁA���Ȍ����J����b���u����100���ł̉^�p�v���咣�������Ƃ͋L���ɐV�����B�������A���Ђ������ɘj��č��y�ѓ��{�̃f�[�^��g�ݍ��킹�ĎZ�o�������ʂɂ��A����100���ł̉^�p�����A�^�p�ɂo�d���������������X�N�͒Ⴍ�A�������A���^�[���͂����ƍ����Ȃ�i�}�Q�Ɓj�B���Ȃ킿�A���X�N�Δ䃊�^�[���͈��|�I�ɉ��P���邱�Ƃ����҂ł���̂����A����������Ƃ̐���ς��Ɏ����Ă��Ȃ��悤�Ɏv����B
�g��摜�\��
�Y�Ƃ̐V��ӂ�i�߂邽�߂�
�֘A����Ƃ̗L�@�I�A�g��
�ȏ�̂悤�ɁA�����ł͌��I�N���𒆐S�ɔN���̕��U�����̂������_���Ă������A���̎������g�����Y�Ƃ̐V��ӂ��Ƃ̊��������̐����I���ʂ��m���Ȃ��̂ɂ��邽�߂ɂ́A�@�Ɨ������I�C�̋`�����ȂǃR�[�|���[�g�K�o�i���X�̋��� �A��s���ޏo���ׂ���Ƃ��Ɏx�������邱�ƂŁA��Ƃ̑ޏo��j�ތ����ƂȂ��Ă�����Z���̎��Y�����̌��i�� �Ȃǂ̎{��������Ď��{�����ׂ��ł���i�A�ڑ�32��j�B �܂��A�]���̋�s�哱�̃R�[�|���[�g�K�o�i���X���A���E�W���̓����Ǝ哱�̃K�o�i���X�ɕϊv���A��Ƃ�^�Ɉ�ĂĂ������߂ɂ́A���I�N���̉^�p���v����ʂ��Đ��{���琬���ׂ��o�d�E�u�b�́A��s����u�����Ƃ��Ɂv�Ɨ��������̂ł���K�v������B��s���֗^����o�d��u�b�́A���s�̍��ۑS�Ƃ̊Ԃŗ��v����������A�����ƕی�̏�Ŗ�肪�����B �����́A��Ƒ����猩�����u���`�v�̐���ł��邪�A�o�d�E�u�b�̈琬�ɂ�郊�X�N�}�l�[�̋�����A����̋��Z�ɘa�Ȃǁu�A���v�̐����ł͊�Ƃ̊������͓���B����琭�������̌n�I�Ɍ��\����A���{����邱�ƂɊ��҂������B
http://diamond.jp/articles/print/37808 �@ �@ �@ �@
�y13/06/29���z 2013�N6��24���@�T���_�C�������h�ҏW��
�ً}�Βk�@�R�茳 vs. ������
�u����������@��邩�H �~��邩�H�v
���Ɍo�ς̐��Ƃł���A�����ƂƂ��Ă��L�x�Ȍo�������R�茳���Ə����ю��B�����s��ɑ傫�ȉe����^���Ă���u�َ����̋��Z�ɘa�v�ɑ��A��������ӌ������_�҂ł�����B����������̍s���Ɠ����Ƃ����ׂ��s�����i�Βk��6��12���J�Áj�B �����ŋ߂̊����s��̏��ǂ��݂Ă��܂����B ���� ���炩�Ƀo�u���ł��B�����痝�R�Ȃ��オ�邵�A���R�Ȃ�������B�����Ƃ́A���ꂪ�Z���Ԃɐ����ŏオ��Ƃ����O��Ŕ����āA�����ɏ���Ăǂ����Ŕ��肽���A�ƍl���Ă���B���ꂪ�܂��Ƀo�u���Ȃ�ł��B�F����ɏ���Ă����������Ƃ����~�]�œ����Ă��邩��A�o�u�������ꂻ���ɂȂ�A�ł邵�p�j�b�N�ɂ��Ȃ�B�������������₷���ł��B �R�� �o�u���ʂɒ�`����u�����I�ɂ͌p������悤�ȁA���Y���i�̑�K�͂ȍ������ہv�Ƃ������Ƃł��B�t�@���_�����^���Y�i���S�̂̌o�ς�A�ʊ�Ƃ̏�������b�I�Ȏw�W�j�̗��Â������������Y���i�̍����Ȃ̂ł����A���������Ӗ��ł́A���݂̊����͂܂��o�u���ł͂Ȃ��B �ł�5��23������̊��������͂Ȃ����̂��Ƃ����ƁA�ЂƂ��ɗ��H���̏W���Ƃ������Ƃł��傤�B���܂�ɂ���{���q�ŏオ���Ă����e�����傫�������B ���� �o�u���ɂ��ẮA�R�肳��̒�`����ʓI�ł��B�������l����`����o�u���́A�t�@���_�����^���Y�Ƃ̔�r�ł͂Ȃ��A�����Ƃ��㏸�̊��҂Ɋ�Â��Ĕ����Ă���A�܂�F���������甃���Ƃ������Ƃł��B ��������ɂ��Ă͂ǂ��݂܂����B �R�� ���Z�ɘa��w�i�ɂ�����K�͂Ȋ����㏸�ł́A���������������o�Ȃ���オ����̂ł��B����͑啝�ŋ}���ł͂���������ǂ��A�������בփ��[�g���A���ʂ̒������Ɨ������Ă��܂��B ���� �ꗬ�ɁA�F�o�u���ɏ�肽���Ƃ����~�]������́A��{�I�ɂ͕ς���Ă��Ȃ��B�ł�����A�o�u���͂܂����S�ɏI������킯�ł͂Ȃ��āA����������Ƒ����B �o�u���ł��낤�ƂȂ��낤��
�����㏸�̔g�͂�����x����ė��� ��������͂�����x�㏸����Ƃ��������ł͈�v�ł��ˁB�����Ƃ͂ǂ����ׂ��ł����B �R�� �����Ŕ��邩�������Ƃ����ϓ_�ɗ��ƁA���������������A��Ƃ̗��v�Ȃǂɑ��č����̂������̂��Ƃ������Ƃ��l����ׂ��ł��B�Ⴆ���A���o���ς�1��3000�~���炢�̊����ɑ��āA��������15�{�O��̂o�d�q�i�������v���j�ł���ˁB�����f���Ɍ���ƁA�����͗��v�ɑ��Ăނ�������Ƃ�����B�Ⴆ�Ύ����ԃ��[�J�[��90�~���x�̈בփ��[�g��O��ɂ��Ă���悤�Ȃ��Ƃ���l���Ă��A��Ƃ̗��v�\�z�ɂ͂܂��]�T�����肻���ł��B ���������Ӗ��ł́A�A�b�v�_�E���͌���������ǂ��A���������ōl���Ă���悤�Ȑl�����́A���̂܂����Ă��Ă������B ���� ���A�t�@���_�����^���Y���猩�Ċ������������́A�ӌ����������Ǝv����ł���B�ł����̋c�_�́A���͂��̐��ǂނɂ����Ă͂��܂�W�Ȃ��B�o�u���������Ċ����ɂȂ�\�����A�t�@���_�����^���Y�̉��P�Ɋ�Â��đÓ��Ɋ������オ��\�����A�ǂ��������킯������B �����A��x����Ă���̂ŁA����͕��͋C���Ⴄ�Ǝv���܂��B�F�s�����c��݂₷��������A���܂ł̂悤�ɓ��{�s�ꂾ����{���q�ŏオ��Ƃ������Ƃ͂Ȃ��āA�����₷���B ���̂܂I����Ă��܂�����ł͂Ȃ��B������R�A�ǂ����ł���ł��傤�B���������̎R���������Ⴂ���͌������������B�l�͂��܂荂���͂Ȃ�Ȃ��Ƃ݂�̂ŁA���̒�����������P�ނ��Ă������̂ł́A�Ǝv���܂��B ���Ȃ��̊��̔Y�݂ɃY�o����
�u�m�h�r�`�v�̌������p�@���Љ�
2�l�̑Βk�͂��̌�A���Z�ɘa�ɂ�銔���㏸�͎����\�Ȃ̂��Ƃ����_�������Ĕ��M���Ă����܂��B�����͖{���łǂ����B
�w�T���_�C�������h�x6��29�����́A����������ɐU����l�����Ƃ̔Y�݂ɃY�o����������W�ł��B 5��23���̊����\���O�ɍ��l�Ŕ����Ă��܂��܂ݑ��B���肷�ׂ����B�\����ɒ�l���Ǝv���Ĕ�������������ɉ����B����������܂ő҂ׂ����B����ɏ��x�ꔃ�����тꂽ�B�����甃���Ă����v���B�����̓����Ƃ������邱��ȔY�݂ɁA�������̊�{�S����������Ȃ���A1�ЂƂ����Ă����܂��B �ŋߌl�����Ƃ̊S�����܂��Ă���A���z������ېŐ��x�u�m�h�r�`�v�i�j�[�T�j�̌������p�@���Љ�܂��B2013�N���ŏ،��D���Ő����p�~�����̂ɑ����āA14�N1�����瓱�������m�h�r�`�́A��ېŊ��Ԃ�5�N�ŁA�N��100���~�܂ł̓������瓾����z�����E���z���┄�p�v����ېłƂȂ邨�g�N�Ȑ��x�ł��B�͂����茾���āA������������Ȃ�g��Ȃ��Ƒ��ł��B ����������ŁA�g�����肪�����C�����Ȃ��Ƒ�������ꍇ������܂��B�����������ӓ_���}���ł킩��₷��������܂����B ���łɋ��Z�@�ւł͂m�h�r�`�����J�݂̎t�����n�܂��Ă��܂����A�܂����x�����܂Ŏ��Ԃ͂����Ղ肠��܂��B�܂��m�h�rA�Ƃ͂ǂ�Ȑ��x�Ȃ̂��A�������ǂ�ȏ��i�ʼn^�p�������̂�����������l������ŋ��Z�@�ւ�I��ł��x���͂���܂���B ���̂ق��A���{�s���|�M����C�O�w�b�W�t�@���h�̐��́A�����������ɂԂ�Ȃ������������X�g�ȂǁA�R���e���c�͐����R�ł��B ����������łǂ��s�����ׂ����Y��ł�����A�Q�Ăē����O�Ɉ�x�����~�܂��āA���Ђ��̓��W������ǂ��������B �i�w�T���_�C�������h�x���ҏW�� �O�c ���j �@
�@
�����헪�͍앶�W�B��{�������Ȃ�
���c���Y�E��t���ȑ�w�w���ɕ��� 2013�N6��24���i���j�@ ���� ���j �@���Z�ɘa�A��������ɑ����A�x�m�~�N�X�́u��3�̖�v�Ƃ��Đ����헪���܂Ƃ܂����B��������s�ꂪ�s����ɂȂ钆�A�����Ɍ������i�H�͒�܂����̂��B�V���[�Y��1��͌��c���`�m��w�����ŁA��t���ȑ�w�w���̓��c���Y���ɁA���̘J���o�ϊw�̎��_����ۑ�����B ���{�������܂Ƃ߂������헪��100�_���_�ō̓_����ƁB ���c�F��ڂɂ���60�_�Ƃ����Ƃ���ł��傤���B���{�W�O�̃��[�_�[�V�b�v�͕]���ł��܂����A�Ő���K�����v�Ȃǂ�����ƁA�o�ώY�ƏȂ��͂��߂Ƃ��鏊�NJ����̍앶�W�B����z�b�`�L�X�����W�Ƃ�������ۂł��B��Ƃ̋��������⍑���̐����{�I�ɉ��P���邽�߂̊�{�������Ă��܂���B����̎��������i�̃l�b�g�̔����ւ�ό��U���Ȃǂ������A�唼�̖ڕW���Ԃ�10�N��Ƃ����̂ł͒x�����܂��B����̋�̓I�Ȑ�������������āA40�_�����̌��_�����Ăق����Ǝv���܂��B TPP�i�����m�o�ϘA�g����j���Ɍ����A�_�Ƃ̋����͂�K���ɘa���ۑ�ł��B ���c�F���{�̐H����������40���ƌ����܂����A����͔_�ѐ��Y�Ȃ̋\�Ԃƌ��킴��܂���B�ʕ����Ɍ���Ύ�������90�����܂��B�_�Ƃ̑����Y�z��10���~�K�͂ŁA���̂���������2�`3���قǂł�����s��K�͎��̂͑傫���͂��ł��B����ŏ��q�����ߑa���œ��{�̔_�Ƃ͋����͂��Ȃ��Ƃ�����B���l���ɐ�߂�_�Ƃ̊�����1.6���ł����A�č���p����1����ɂ�������炸�_�Y����A�o���Ă���B���͓��{�̔_�Ƃ͑������炢�Ȃ̂ł��B
���c�@���Y�i���܂��E�͂邨�j��
��t���ȑ�w�w���B1960�N�c���`�m��w�o�ϊw�����ƁA�����w�@���o�ĕăE�B�X�R���V����w�Ŕ��m���i�J���o�ϊw�j���擾�B�c�勳���A�x�m�ʑ����o�ό������������Ȃǂ��o��2007�N��茻�E�B�u�f�t���͍����������Z����ʼn����ł�����̂ł͂Ȃ��v�����_�B�u���Ԃ̒���v���e�[�}�ɋK�����v�̕K�v������Ă���B�i�B�e�F�|��r���B�ȉ����j
��̓I�Ȑ헪�́B
���c�F�_�Ƃ��Y�ƂƂ��ċ������Ă����q���g������܂��B��̓I�ɂ�165���˂�����_�Ƃ̂����A�R��������Ă����Ɣ_�Ƃ�30���˂قǂ�������܂���B����135���˂����Ɣ_�ƂȂ̂ł����A�����ł̐��Y�͑S�̂�5���ɂ����܂���B�܂菭���̐�Ɣ_�Ƃ����Y�̑唼��S���Ă���B�����琶�Y���̖F�����Ȃ����Ɣ_�Ƃ͕ʂ̐헪�����ׂ��ł��B���{�́u�y�n�o���N�v��ݗ����āA��ׂȌ��Ɣ_�Ƃɓy�n�����o���Ă��炢�����̗ǂ���K�͂Ȑ�Ɣ_�Ƃɐ��Y��C������ǂ��ł��傤�B �@���Y���̍����_�Ƃ͋����͂�����܂��BTPP�ň����ȊO���Y�������Ă��Ă���R�͂�����܂��B �������������Z�ɘa�̃A�i�E���X���� �@�ł͌��Ɣ_�Ƃ͂ǂ�����ׂ����B�ЂƂ͕����_�Ƃł��B�y�n�݂͑��Ă��邪�A������Ƃ�����Ŗ�����Ȃǂ��Č��N���ێ�����B�q��������鋳��_�ƁA�n��U���Ɗ֘A�t�����ό��E�ό��_�Ƃ��L�]�ł��B���������V��������ɕ⏕�����o���āA���Ɣ_�Ƃɓ]�����Ă��炤�̂ł��B�[�c������i���v�Ɂj���t���Ȃ��Ƃ����̂͏�Ȃ��B ��Õ���͂ǂ��ł����B ���c�F�ی��f�Âƕی��O�f�Âp�ł���u�����f�Áv�̑S�ʉ��ւ���������ȂǁA���ݍ��ݕs���͔ۂ߂܂���B��ÁE����͍ő�̐����Y�Ƃɂ�������炸�A�f�Õ�V���x�͉��i�K���̍ł�����̂ł��B���̐��x�ł͕a�@�̐��ʁA�܂莡�Â̌��ʁA�a�C�₯�����������̂��Ƃ��������ł��Ȃ��̂ł��B����҂���p�Ό��ʂ��m���߂��Ȃ��d�g�݂͂��������B �@��ÁE����̎s��@�\�����߂邽�߂ɂ͌��I�ی��Ɉˑ�����̂���߂āA���ԕی���啝�Ɋ��p����ׂ��ł��傤�B���{�̈�Ô�͔N200���~�B���̂���130���~�����ԕی��ɂ����̂ł��B�����g�Q���͓�S���\�~�Ȃ̂ɁACT�X�L�����ɂȂ��10���~�߂��ɂȂ邱�Ƃ�����܂��B��Â̕��σ��x�����ێ����Ȃ���A����ɏ㎿�Ȃ��̂����߂�l�ɉ�����d�g�݂Â��肪�]�܂�܂��B�A�����J�ł͈�Ô��70���ԕی��ŒS���Ă��܂��B �ٗp�K���ɂ��Ă͂ǂ̂悤�ɍl���܂����B
���c�F���ًK���̌��������摗�肳��܂����B�����50�N�O�̖@�������܂��ɐ��������Ă��܂��B�����͍��x�o�ϐ�������Ŏw�����ق͂ł��Ȃ��������A�Љ�I�ɂ��ł��ɂ������y������܂����B���������͌ٗp�����������Ă��܂��B��w�����̐��E�ł����ʂ��グ��l�A�グ�Ȃ��l�̓�ɉ����i��ł���悤�ɁA���Ԋ�ƂȂ�Ȃ�����ł��傤�B���ꎑ�i�E��������Ƃ����l���������߂āA����J���E��������̓�����i�߂�ɂ͑�K�͂ȋK���ɘa���K�v�ł��B
�����헪�̌��\��A���Z�s��ŕs����Ȓl�����������Ă��܂��B ���c�F���Z�ɘa�̃A�i�E���X�����g���ʂ�5�����̊����\���Ŕ����������Ƃ݂�ׂ��ł��傤�B�����헪�����Ґ�s�ɏI��������ƂŁA���o���ϊ����͓���1��1000�~����1��4000�~�ōr���ۂ��l�����������ł��傤�B���͈בցB���@�̓����������A��{�I�ɉ~����Ő��ڂ���͂��ł��B �@�Ȃ����B�����{��k�Јȍ~�A���q�͔��d���̒�~�ŐΒY��LNG�i�t���V�R�K�X�j�̗A���������Ă��邩��ł��B���{�̖f�Վ��x�͍\���I�ȐԎ��ɂȂ�A���ꂪ�o����x�ɂ��e�����Ă��܂��B�č���������ȃV�F�[���K�X���A������Ă��A�吨�͕ς��Ȃ��ł��傤�B �����㏸���|���l�ނ̗��o �i�C�A���Z�s��Ƃ��Ɉ����V�i���I��z�肵�n�߂��Ƃ������Ƃł����B ���c�F�~���A�C���t���A�ϋɍ����̉��ł͋����㏸���������܂���B�����㏸�͐��{����Ⴞ����ɖc��܂��Ă����܂��B����1100���~�̍�������Ă���A1���̋����㏸�͍���11���~���������܂��B3�`4���̏㏸�͑��Ŏ��ɑ�������C���p�N�g�B���{���玑�{�������邱�Ƃ͑z�肵��������܂��A�����Ƃ��|���̂͐l�ނ����o���邱�Ƃł��B �@7���̎Q�@�I�ō����������}�ɑ傫�Ȋ��҂����ĂȂ���A�O�Q���@�́u�˂��ꌻ�ہv�������ł��܂���B�u���߂��Ȃ������v�����A���{�������ő�̗v���Ȃ̂ł��B
�A�x�m�~�N�X�̐^����₤
�@
�@
�ꑧ���Ď���ɂ߂����ł����ؕԂ���H�炢�܂��� �~������Ƃɂ����炷�^�̉e���i��5��j 2013�N6��24���i���j�@ ���a�@���i �@��Ƃ̃r�W�l�X�������ē��X�����j���[�X�̒��ɂ́A����̊�ƌo�c����ς�����傫�Ȓ���������ł���B���̉\�����߂������I�Șb���1�e�[�}�Ƃ��Ď��グ�A�����L���̃r�W�l�X�X�N�[���̊Ŕ����������ǂ݉����A�V���ȃr�W�l�X�������o���Ă����B
�@�����̃e�[�}�́A���{�W�O���������i����o�ϐ���u�A�x�m�~�N�X�v�ɂ���ċ}���ɐi�~���B��Ƃ̗A�o�����A�Ɛт̉�ٗp�̊g��ɂȂ���Ƃ��������R����A�~�������}���鐺���������A�ʂ����Ė{���ɂ����Ȃ̂��B�~����������Ƃɂ����炷�^�̉e���ɂ��āA�����r�W�l�X�X�N�[���̋��d�ɗ���4�l�̘_�q�����Ɏ��_���I���Ă��炤�B
�@����2��ɂ�������ĉ~���̐^�̉e����_����̂́A�ꋴ��w��w�@���ۊ�Ɛ헪�����Ȃ̖��a���i�����B�~���Ő����Ƃ̈ꕔ�͈ꑧ�������A�����ň��S���Ă��܂����Ƃ����O�B�u�C�O�V�t�g�̎���ɂ߂Ă͂����Ȃ��v�Ƌ�������B
�i�\���͏��� ���ぁ���C�^�[/�G�f�B�^�[�j
�@��N�I��肩�獡�N�t�܂ł̋}���ȉ~���́A�����Ƃ̈ꕔ�Ɉꑧ���]�T��^���܂����B�������Ԃ��Ȃ��A���܂�ɂ��ɒ[�ȉ~���ɓ˓����Ă������ƂŁA�����̐����Ƃ͔敾���Ă����B���Ɏ����ԁA�d�@�B�Ȃǂ̋ƊE�ŁA�����Ƀ}�U�[�H�������Ƃ���{�ŕ��i�����Ă����Ƃ́A�~���ɂȂ��ď��������ʂ͂���ł��傤�B �@�t�ɁA���������Ƃł����Y���_�̊C�O�V�t�g�𑊓��ɐi�߂Ă�����Ƃ́A�~���Œɂ��v�������Ă��܂��BODM�i�����u�����h�ɂ��v�����j��t�@�u���X�Ŏ��Ƃ�i�߂Ă�����ƂɂƂ��āA�~���̓f�����b�g�ł�������܂���B���i�̂قƂ�ǂ��p�Ő��Y���Ă���p�\�R�����[�J�[�̒��ɂ́A6���ɓ�����10���l�グ����Ƃ��낪�o�Ă��܂����B�H�i���[�J�[�≻�w���[�J�[�ȂNJC�O����A�����錴�ޗ���������ƂɂƂ��Ă��A�~���̓R�X�g�A�b�v�v���ł��B �@�~���ŏ����Ă���̂́A���{�S�̂�2���قǂ̊�Ƃɉ߂��܂���B���̏����Ă����ƂƂ����̂��A�����ԁA�d�@�B�ȂǓ��{�̋������ے�����Y�Ƃ̊�ƂȂ̂ŁA�u�~���ɂȂ��ėǂ������v�Ƃ����]�����Z���������ł����A�S�̂ōl������}�C�i�X�̉e���̕����傫���̂ł��B �A�x�m�~�N�X�ւ̑Ή��ł��قȂ鍂��x�T�w�Ǝ�N�w �@�~���ɂȂ��Ă����ǖʂł͊������オ��A���Y�̖c�����ʂŏ���g�傷��Ƃ������҂����܂�܂����B�����A�S�ݓX�̐l�����Ƙb�����Ă݂�ƁA�����P���Ȃ��̂ł͂Ȃ��悤�ł��B�ǂ����A�u2%�̃C���t���ڕW�v���f����A�x�m�~�N�X�ɑ��āA50��ȏ�̕x�T�w�Ǝ�N�w�̏���s���ɂ͑傫�ȍ�������悤�Ȃ̂ł��B �@50��ȏ�̕x�T�w�͂��ẴC���t���̎����m���Ă��܂��B���m�̒l�i���ǂ�ǂ��Ȃ��Ă�����1970�N��A80�N����v���o���A�u�������Ă����������g�N���v�Ƃ������o�ɂȂ�܂��B���������Ă���悤�ȏ���҂͑S�̂�10�����x�ł��傤���A�����㏸�Ŏ��Y����������A�c����ƂŁA������Ƃ������������悤�Ƃ�������s���ɖ߂�₷���B�S�ݓX�ŋM������u�����h�i�����ꂽ�̂́A���������v������ł��B �@����A��N�w�̓C���t����m��Ȃ��̂ŁA�s���Ɨ��Ă��܂���B�u���A����������1�N��ɔ��������g�N���v�Ƃ������z�����Ȃ����߁A�ł��邾�������ėǂ����m�����Ƃ������s���͕ς��Ȃ��̂ł��B���ǁA�ނ�̊Ԃł͂��܂荂�����m�͔���Ă��Ȃ������ł��B �@���������̑����V�j�A���オ�A����܂ł́u�悪������Ȃ�����v�ƃ^���X�ɐQ�����Ă����������g���n�߂�悤�ɂȂ�Ȃ�A�x�T�w�����[���^�[�Q�b�g�Ƃ���S�ݓX�̂悤�ȋƎ�ɂ͈��̌��ʂ����邩������܂���B�����A�u�������b�`�ɂȂ����C���v�Ƃ��A�u���A����Ȃ��Ƒ��v�Ƃ��������Ƀ����^���Ȃ��̂ɍ��E����Ă���̂ŁA���ꂽ�Ƃ��Ă��ꎞ�I�Ȍ��ۂɂƂǂ܂�\��������܂��B �@�u�Ɠd�̃G�R�|�C���g���x�v�ł����Ƃ��ꂽ�悤�ɁA���v���H�����Ă���̂�������܂���B5���㔼�ȍ~�̊����̗������ŁA����ҐS�����Ăї₦���ފ댯��������܂��B�����i�����ꑱ����Ƃ͎v��Ȃ����������ł��傤�B �@�~���ɂȂ��Ĉꕔ�̐����Ƃ͈ꑧ�����Ƃ��ł����Ǝw�E���܂����B����ǖ��́A���̈ꑧ�����Ƃ��ł�����Ƃ����̌�ɂǂ����邩�ł��B �@����܂œ��{�̐����Ƃ̑����́A���Y���_�̊C�O�V�t�g��i�߂Ă��܂����B�}�U�[�H���m���ɂ����ău���b�N�{�b�N�X�ɂ��ׂ����̈ȊO�́A�ǂ�ǂ�O�ɏo���Ă����̂ł��B���ꂪ�~���ňꑧ�������Ƃň��S���Ď���ɂ߁A�C�O�V�t�g�̃X�s�[�h��݉������Ă��܂��ƁA��ł����ؕԂ���H�炢�܂��B �@�Ⴆ�A����OA�@�탁�[�J�[�́A�~���̎����ɃR�A���i�̐������C�O�ɃV�t�g���悤�Ɠ����Ă��܂����B�������~���ɂȂ������Ƃł��̓������~�߂Ă��܂��B�������A�~�����������ۂ��͕�����܂���B�����Ăщ~���ɂȂ������A�����œ������~�߂����Ƃ��傫�ȏo�x��Ƃ��Ē��˕Ԃ��Ă���\��������܂��B �@�g���^�����Ԃ͂���܂Ŋ�{�I�ɍ����Ő��Y���Ă����u���N�T�X�v��č��⒆���ł����Y���悤�Ƃ��Ă��܂��B�~���ɐU���ƁA�u�C�O�Ő��Y����K�v�͂Ȃ�����Ȃ����v�Ƃ����������o�Ă��邩������܂���B����ǁA�����ڂŌ���A��͂�u�n�Y�n���v�ɂ��Ă����͎̂��R�̗���B���{�ł������Y�ł��Ȃ��̐��̂܂܂ɂ��Ă��������s���R�ł��B�בւ̕ϓ��ɍ��E���ꂸ�A���܂Œʂ�A�C�O�V�t�g��ϋɓI�ɐi�߂�ׂ��ł��B �V�����̃N���C�W�[�ȗv�����琶�܂��C�m�x�[�V���� �@�Ȃ��n�Y�n�����K�v�Ȃ̂ł��傤���B�u���o�[�X�C�m�x�[�V�����v�Ƃ������t�Ō����悤�ɁA�V�����Ő��܂ꂽ�v�V�I�Ȑ��i��T�[�r�X����i���ɋt�����鎞��ɂȂ��Ă��邩��ł��B��i���Ŕ����Ă���l�i��10����1�A100����1�̒l�i�ł�������Ȃ��s��ɍ������m�������悤�Ƃ�����A�[���x�[�X�ōl���Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B����ɂ́A���[�U�[�ɋ߂����n�̐l�����ƈꏏ�Ƀ��m����i�߂邱�Ƃ��K�v�ł��B �@��������Đ������܂��傤�B�C���h�̃^�^�E���[�^�[�Y���J���E�̔�����10�����s�[�i���\�����̃��[�g�Ŗ�28���~�j�̎����ԁu�i�m�v�ɂ́A���{���[�J�[����B��A�f���\�[�̕��i���̗p����Ă��܂��B�[�������̂̓��C�p�[�B�ʏ�A�����Ԃɂ�2�{�g�����C�p�[���u1�{�ɂ��Ă���v�Ƃ����v�����A�������܂����B���S�W���Ȃǂ��l����ƕ��ʂł͂Ȃ��Ȃ��ł��Ȃ����Ƃł��B����ǁA���������N���C�W�[�Ƃ��v����v�����琶�܂��C�m�x�[�V����������܂��B��Ƃ͈ꗬ�̃G���W�j�A�𓊓����A���n�̗v���ɉ����邱�Ƃ��d�v�ł��B �@���o�[�X�C�m�x�[�V����������͕̂ă[�l�����E�G���N�g���b�N�iGE�j�ł����A���Ђ͒�����C���h�ȂǐV�����Ŏ��Ƃ�i�߂�ɓ�����A�v�}��Y�Z�p�ȂǓ��Ђ����m�E�n�E�����ׂăI�[�v���ɂ��܂����B�����āA���n��Ƃɑ��A�u���̍ޗ����g���v�u�N�I���e�B�[�����v�Ƃ��������Ƃ͈�،����܂���ł����B�Z�p��m�E�n�E�ɃA�N�Z�X���錠���͗^���������ŁA���������������Ȃ��\�\�B���̎�@���A�����ėǂ����m�����錍�ł���A���o�[�X�C�m�x�[�V�����́g�́h�ł��B �@���{��Ƃ͌��n��Ƃ��w������ہA���{���������������ł��B���̎�@�����߂Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B �@�Q�l�ƂȂ肻���Ȃ̂��z���_�̗�ł��B�z���_�͂��āA�����Ńz���_�̋U���o�C�N���o����������ɁA�R�s�[���[�J�[��1�Ђ����A�����Ď��̍����o�C�N�����m�E�n�E���w�ڂ��Ƃ������Ƃ�����܂��B�Ƃ��낪�A���̌�A�z���_�̃G���W�j�A���z���_���ɂ��̉�Ђ���߂Ă��܂��A���ʓI�ɃR�X�g���̐��i������ЂɂȂ��Ă��܂��܂����B �@�z���_�͂��̌o���Ȃ��A���̌�A�L�B�Œ�����ƂƂ̎����Ԃ̍��ى�Ђ�ݗ������ہA�����l�����̃`�[����Ґ����ăN���}����点�܂��BGE�Ɠ������A�z���_�̋Z�p�̓I�[�v���ɂ��邯��ǂ����o���͂��Ȃ��B�����������j���т��܂����B �@���̌��ʁA���܂ꂽ�̂��u���O�v�Ƃ��������Ԃł��B�z���_������肸���ƈ����A�����l�e�C�X�g�ɏo���オ��܂����B�������Ēa�����������Ԃ́A��������{�ŃC���t����m��Ȃ��Ⴂ����Ɏ������\��������܂��B �@�t�@�[�X�g���e�C�����O�͍��A�o���O���f�V���ŃO���~����s�ƈꏏ�ɃO���~�����j�N���Ƃ�����Ђ�����A1�h�������̌��n���i��T�V���c��o�����Ƃ��Ă��܂��B���݂̂Ƃ���AT�V���c�����ɂ͂ǂ��撣���Ă�2�h��������B�����f�ނ�D���A���H�����������Ƃ�1�h���ɂ��悤�Ƃ��Ă��܂��B�����ł���Α�ςȃC�m�x�[�V�����ł���A���E���Ɏs�ꂪ�L����܂��B ��@�����Ȃ��Ȃ邱�Ƃ���Ԋ�Ȃ� �@��Ƃ͈בփ��[�g�̐����ɍ��E���ꂸ�A�u���������v��Nj����邱�Ƃ��d�v���Ǝv���܂��B�}�U�[�H���v�ȂǓ��{�ł����ł��Ȃ����Ƃ���{�Ɏc���A���Ƃ̎��Y�͊C�O�Ɉڂ��Đ��E���Ŏ��v���l������̐����\�z����B�u�����ėǂ����m�v�Ƀt�H�[�J�X����B�������������Ԃꂸ�ɓ˂��i�ނ��Ƃł��B �@����܂œ��{��Ƃ͉~���Ƃ����n���f�B��w�����Ȃ���؍��A�����ȂǐV�����̊�ƂƋꂵ���킢���J��L���Ă��܂����B����͔��Ɍ��������̂肾��������ǁA�l�X�ȉ��v��i�߂Ă������ƂŁA�����͂͑傢�ɒb���グ���܂����B���������������̂��Ǝv���܂��B �@�~���ɂ���Č������̐�����̎��v���c��݁A�ꑧ�����r�[�A���v���~�߂Ă��܂��Ƃ�����A����͑傫�Ȗ��ł��B��@�������鎞�ɂ͉�Ђ͈�v�c�����ĐV���������ւ̉��v�����₷���Ȃ�܂����A��@���������Ə]�ƈ���[��������̂�����Ȃ�A�u���v���Ȃ��Ă�������Ȃ����v�ƋC�����������܂��B��@�����Ȃ��Ȃ��Ă������Ƃ���Ԋ�Ȃ��Ǝv���܂��B �@����͊�Ƃ��C�O�V�t�g��i�߂�ۂ̃��m���̂�����ɂ��Ę_�l���܂��B �i�����6��24�����j���ɖ��a�����̘_�l�̌�҂��f�ڂ��܂��j
MBA�Ŕ������ǂރr�W�l�X����
�@
�@
|

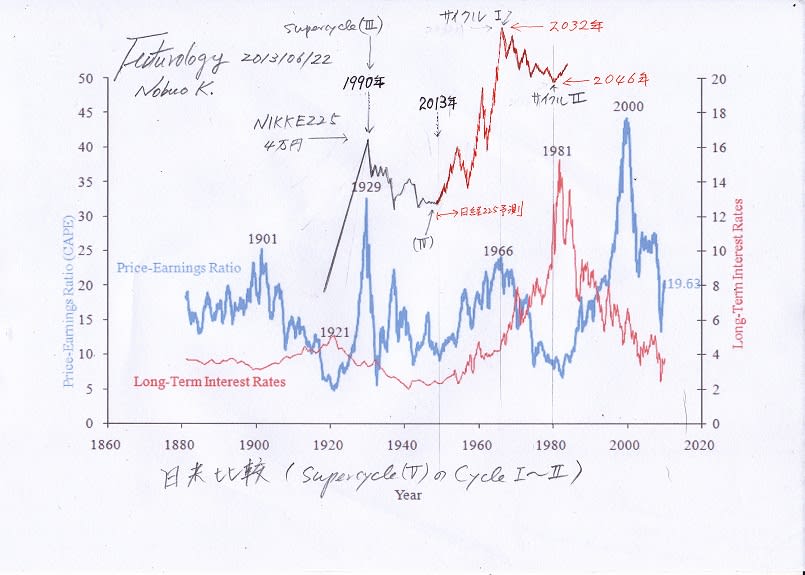
 �X�p�����[���̒����猩���o�����߂Ƀ��[���̃^�C�g���ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B
�X�p�����[���̒����猩���o�����߂Ƀ��[���̃^�C�g���ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B