03. 2013年6月18日 06:51:11
: e9xeV93vFQ
"俺"ではなく"俺たち"を自慢しがちな日本人
[橘玲の日々刻々]
1
2
アメリカの高校生にリーダーシップがあるかどうか質問すると、7割が「自分は平均以上」と答えます。大学教授を対象とした調査では、94%が「自分は同僚より優秀だ」と回答します。平均より優れたひとは半分しかいないはずですから、これは明らかにおかしな現象です。 心理学では、無意識のうちに自分を過大評価することを「平均以上効果」といいます。私たちの住む世界では、ほとんどのひとが平均以上に知能が高く、平均以上に公平で、平均以上に車の運転がうまいのです。 自分に根拠のない自信を持つ傾向は、「ポジティブ・イリュージョン」として知られています。といっても、“幻想(勘違い)”なんだから矯正すべきだ、といいたいわけではありません。 子どもに対して「もっと現実を直視しなさい」と説教する親や教師がいますが、自己評価と他者の評価が一致している、すなわち“勘違いしていない”ひとの典型はうつ病患者です。あらゆる出来事をネガティブにとらえてしまうのがうつ病だとされていましたが、最新の研究では、彼らの自己認識は正確すぎてポジティブな勘違いができないのだと考えられるようになりました。 「日本人はうつ病にかかりやすい」という話を前にしましたが、このことは国際比較調査において、日本人の自己評価の低さとして表われています。 日米中3カ国の高校生約3400人を対象に行なわれた調査では、「私は他人に劣らず価値のある人間である」という質問に肯定的に答えた高校生はアメリカで89%、中国で96%だったのに対し、日本ではわずか38%でした。その一方で、「自分にはあまり誇りに思えるようなことはない」と答えたのは、アメリカ24%、中国23%に対して日本の高校生は53%と半数を超えます。 これを見ると“自己卑下(正確な自己認識)”が日本人の特徴といえそうですが、大学生を対象とした調査では、明らかに自分を「平均以上」だと答える項目が見つかっています。男女を問わず日本の大学生が「自分は他人より優れている」と思っているのは、“優しさ”“真面目さ”“誠実さ”です。知能や容姿のような比較が容易なものではなく、評価基準があいまいなものには過剰な自信を持てるのです。 次のページ>> 個人ではなく関係性を重視する日本人
だとすればこれは、「日本人は現実を直視できる」という話ではなく、ポジティブ・イリュージョンの表われ方が文化や社会によってちがっているのかもしれません。 社会心理学の研究によれば、日本人のもうひとつの特徴は、「人間関係を仲介として自分自身を高く評価する傾向」が顕著なことです。自分は平均以下かもしれないけれど、自分の夫婦関係や友人との関係は平均以上だと思っているのです。 個人ではなく関係性に依存するというのは、よい面も悪い面もあります。 日本人は“俺”ではなく“俺たち”を自慢しがちです。これが「自分はたいしたことないけど会社は一流だ」とか、「俺はリア充じゃないけどニホンは世界から尊敬されている」という意識につながっているとしたら、心当たりのあるひとも多いのではないでしょうか? 参考文献:菊池聡『「自分だまし」の心理学』 『週刊プレイボーイ』2013年6月10日発売号に掲載
http://diamond.jp/articles/-/37583
得るには、「小さな成功」を積み重ねること
2013年06月18日
テレサ・アマビール,スティーブン・クレイマー
BacknumberProfile
アマビールとクレイマーは論文「進捗の法則」で、日々の小さな前進が社員の生産性を高めることを実証した。この小さな前進は、社会問題から個人の私生活にまで広く有効であることが多くの研究で明らかにされているという。
とても乗り越えられないような困難にぶつかったら、それを小さく分解するとよい。ミシガン大学の心理学者カール・ワイクの名著論文「小さな成功」によれば、大規模な社会問題は小さな単位に分解し、それぞれに達成可能な具体的目標を設定すべきであるという。たとえば失業問題のような大きな社会問題は、あまりに深刻なため解決不可能に見えるかもしれない。そのため、人は問題を避けて通ろうとするか、あるいは奏功するはずのない、ただ1つの壮大なる計画に行き着いてしまう。大きな問題を、小さいが最終的な目標へと続くステップに分解することで、恐れが減り、方向性が明らかとなる。そして早い段階で好ましい結果が生じる確率が上がり、それ以降の取り組みを助けることになる。
この「進捗の法則」――小さな成功の威力――は、企業の問題に対しても同じように当てはまる。筆者らが最近行った調査では、複雑な仕事に取り組んでいるチームや個人にとって、小さな成功を定期的に経験することの重要性が明らかとなった。真に重要な問題には、挫折が付きものである。どんなに小さな前進でも、またはその日の失敗から得た発見にすぎなくても、人は何らかの有意義な進捗を日々感じなければ、やる気を失ってしまう。小さな前進の追求は、長期的な目標の達成を促進する。スタンフォード大学教授のロバート・サットンは、名著Good Boss, Bad Boss(邦訳『マル上司、バツ上司』講談社)で次のように述べている。「社運を賭けた大胆な目標」(BHAG)は困難なだけでなく、往々にしてあまりにも単純で大ざっぱであるため、日常業務レベルで有効な指針に落とし込まれることがない。同様に、作家ピーター・シムズは著書Little Bets(邦訳『小さく賭けろ!』日経BP社)で、目標を段階的に設定することの重要性を力説している。 こうした意見には、ある意外な共通点がある。それは、感情面での健全性を維持するには、私生活においても小さな成功を経験する必要がある、という見解だ。Feeling Good(邦訳『フィーリングGoodハンドブック』星和書店)の著者デビッド・バーンズ博士は、大きな成果だけでなく一見些細に見える成果についても、記録をつけ、振り返り、プラスに評価することの重要性を説いている。小さな成功に注目することは、不安や悲しみからの脱却につながるのだ。これは認知行動療法の原則のひとつである。たとえば、深く落ち込んでいる人は、身体を動かせば不安が軽減されるとわかっていても、運動プログラムをやり通すことが難しいと感じる場合がある。それゆえ、毎日ジムで1時間汗を流す、といった目標は実現不可能に思え、決して実行に移すことはない。バーンズは、「1度にすべてをやり遂げなくてはならない、と思い込んでいるのが原因である。そうではなく、作業を実行可能な小さい単位に分解し、1つずつクリアしていけばよい」と記している。つまり、近所を散歩するというような控えめな目標から始めるほうが、はるかに効果的であるということだ。したがって深く落ち込んでいる人は、小さな目標の達成を記録してみずからを称えることにより、新たな目標を立て、より多くの大きな成功を期待できるようになる。 私生活における小さな成功は、私たちを常に前向きな気持ちにさせる。一方で、多くの研究によれば、生活上の大きな出来事は、主観的な幸福感を長続きさせる効果がほとんどない。たとえば宝くじに当選しても、長期的な幸せに結びつくわけではない場合が多い。マサチューセッツ工科大学スローン・スクール・オブ・マネジメント教授のダニエル・モーションらは、ごく当たり前の活動から得られる、定期的で些細な進捗には、持続的で蓄積的な効果があることを発見した。たとえば、定期的に礼拝に出席する人が感じる幸福感は、時とともに蓄積されていく。そして、礼拝に出る頻度が多くなればなるほど、幸福感も大きくなる。この結果は、定期的な運動やヨガについても同様であった。 日々多くのストレスや悩みを抱えて生活する私たちは、自分の小さな前進を容易に見過ごしてしまう。この数日間を振り返ってみよう。レーダーが感知しなかった成功はないだろうか。もし思い当たるなら、少し時間を割いて自分を祝福するとよい。そしてもし気が向いたら、その成功を私たちにも教えてほしい。喜びを分かち合うために。
HBR.ORG原文:Small Wins and Feeling Good May 13, 2011
テレサ・アマビール(Teresa Amabile)
ハーバード・ビジネススクール(エドセル・ブライアント・フォード記念講座)教授。ベンチャー経営学を担当。同スクールの研究ディレクターでもある。
スティーブン・クレイマー(Steven Kramer)
心理学者、リサーチャー。テレサ・アマビールとの共著The Progress Principle(進捗の法則)がある。
http://www.dhbr.net/articles/-/1895
「人命よりも企業?!」 過労がなくならない日本の歪んだ価値観 経済も活性化したフランスの「ブルムの実験」に学べ 2013年6月18日(火) 河合 薫 今回は、「なんでニッポン人は、そんな働かなきゃならないのか?」ってことについて、考えてみようと思う。 先月、国連の社会権規約委員会が日本審査の最終所見を発表し、長時間労働などが原因の過労死・過労自殺について、「立法措置を含む新たな対策を講じるように」と、異例の勧告を行った。 同委員会は、「多くの労働者が長時間労働に従事していることと、過労死や精神的なハラスメント(嫌がらせ)による自殺が職場で発生し続けていることを懸念する」とし、長時間労働の防止を強化することや、労働時間の制限に従わない場合は制裁を科すよう求めたうえで、「必要な場合は、職場におけるあらゆるハラスメントの禁止・防止を目的とした立法、規制を講じるよう勧告する」としている。 社会権規約は世界人権宣言に基づく条約で、守るべき労働条件に「休息、余暇、労働時間の合理的な制限」などを明記。日本を含む締約国160カ国には、取り組みを国連に報告する義務があるため、日本政府は何らかの改善措置を迫られることになる。 政府はちゃんと、長時間労働がなくなる“措置”をやってくれるのだろうか?
長時間労働を強いている企業は、この勧告をどう受け止めたのだろうか? ううむ、何となく表向きの措置だけが取られて、長時間労働や過労死が改善されることはない。そんな鬱屈とした気分になってしまうのはなぜなのだろう。 改善されているとは言い難い過労を巡る状況 KAROUSHI──。 「日本において働き過ぎが原因で、心身ともに消耗して死に至ること」と定義されるこの言葉が、英語辞書の最高峰と言われている「オックスフォード・イングリッシュ・ディクショナリー」に追加されたのは2002年、今から10年ほど前のことだ。 数年前に比べると、過労死に関する記事も減り、小さな囲み記事程度の扱いになってしまっているが、登場回数が減ったからといって過労死が減っているわけではない。 厚生労働省の統計によると、2011年度に脳や心臓の疾患などで死亡し、過労死として請求されたのは302件で、2003年の319件から改善されたとは言い難い(死亡者の請求数が記録されているのが2003年以降)。 また、そのうち労災認定されたのは121件で、発症の直前6カ月間で過労死認定の基準となる月平均の時間外労働が80時間を超えたのは93件。長時間労働が課されている実態は、この数字からも明らかである。 長時間労働は、平均化された数字の上では、確かに減ってはいる。 政府目標として年間総実労働時間1800時間が掲げられた1988年と比べると、300時間ほど短くなり、1800時間前後で推移しているとされている(1980年代は2080時間程度)。しかし実際には、パート・アルバイトなど非正規社員の増加によるところが大きく、実態はとらえられていない。また、年齢、企業規模、職種によって、“長時間労働格差”なるものが広がっている。 さらに、東京大学社会科学研究所の黒田祥子氏の試算によれば、1976年〜2006年までの30年で、平日(月曜日から金曜日まで)の労働時間を比較してみると、1日当たりの労働時間は増加していていることがわかった(週休2日が徹底されたことで、土曜日の労働時間が平日にシフトした)。
平日10時間以上労働の割合は、1976年には17%だったものが、2006年には42.7%まで増加していたのである。 1日の労働時間が増えれば、必然的に睡眠時間は減ることになる。黒田氏の調査でも、平日10時間以上働いている人の睡眠時間は、そうでない人に比べて低いことが確かめられている。 おまけに、今は“人”よりも“企業”が、大切にされる世の中。 特に最近は、企業側は、“ブラック企業”と言われることを恐れているので、“不都合な事実”を隠ぺいする方向に傾く恐れもあり、長時間労働問題は、むしろ深刻化しているようにさえ思う。 人の命と企業の社会的信用が天秤に? 今年の初めに、「社員の命か、企業の信用か 裁判所はどちらを向く」という見出しの記事が新聞の紙面で大きく扱われたことがあった(以下は産経新聞に掲載された記事の概要)。 「悲惨な過労死を少しでも減らしたい」「ブラック企業と評価される」─。社員が過労死した企業名の開示をめぐり、大阪地・高裁で判断が分かれた。「全国過労死を考える家族の会」代表の寺西笑子さん(63)が、社員が過労死の認定を受けた企業名を大阪労働局が開示しなかったのは違法として、国に対して不開示決定の取り消しを求めた訴訟。1審大阪地裁は企業名の開示を命じたが、2審大阪高裁は原告側の請求を棄却する逆転敗訴の判決を出した。寺西さんは「企業名が開示されるようになれば過労死に歯止めがかかる」と訴えており、最高裁に上告。最後まで戦い抜く決意を固めている。 これは裁判所の判断であり、企業が隠ぺいしたわけではない。だが、「人の命」と「会社の社会的評価」が天秤に掛けられてしまうのは、何とも言えない違和感を覚える。 いずれにしても、“人”の命を脅かすような働かせ方はあってはならない。国連の警告があろうとなかろうと、長時間労働というものがいまだに存在し、その結果、身体も心もボロボロになり、命を削りながら働かなかなくてはいけないような社会は異常だ。 どんなに経済が強くなろうとも、人が命を削りながら働かなきゃいけないような社会がいいわけがない。 そもそも、なぜ、長時間労働はなくならないのか? 「業務量が多い」
「生産性ばかりにこだわるから、必然的に残業をしなければならなくなる」
「システム化できるところに、会社が投資しない」 こうした企業の事情を指摘する人もいる。 「国民性でしょ?」
「そうそう、日本人はもともと勤勉だからね」
「帰りたくても帰れない雰囲気がある」
「残業をしている人の方が評価される」 こうした日本や日本人の特有の問題とする人たちもいる。 で、実際残業をしている人たちに理由を尋ねると(2010年に企業30社を対象に私が行った調査)、残業をする理由のトップは、「業務量が多くて終わらないから」で、「帰れない雰囲気がある」が2位。それに「自分の仕事をしっかり仕上げたかった」「自分の能力開発のため」という、積極的な理由が続いていた。 長時間労働を続けているとSOSも出せなくなる 確かに長年働いていると、自らの意志で、働きすぎてしまうこともある。「猛烈に仕事がしたい!」という欲求に駆られることもあるし(まぁ、ごく稀ではありますが)、自分がただただ納得できなくて、遅くまで仕事をしてしまうこともある。 だが、そこに個人の意思があろうとなかろうと、長時間動労が、心身を蝕んでいくということには何ら違いはない。働く時間が長くなれば、睡眠時間も減る。身体が疲弊すれば、心だって疲れ果てる。エネルギーは消耗されるばかりで、心理的プレッシャーも強まっていく。仕事のパフォーマンスも落ちるし、ミスだって多くなる。 過労自殺に至った方たちの多くが、「会社に迷惑をかけて申し訳ない」「自分が至らなかった」と、会社を非難するどころか、自分を責める傾向にあるとされている。長時間労働を続けていると、「助けて!」とSOSを出すことすらできなくなってしまう危険が潜んでいるのである。 日本の長時間労働は国際的にも有名であるが、労働時間の国際比較を行うと、次のような具合になる。 ・韓国は日本以上に、長時間労働。
・アメリカは、日本ほどではないにしても、欧州に比べると長時間労働。
・ヨーロッパは軒並み低く、特にフランス、ドイツ、オランダが低い。 フランス人の労働時間の短さは国際的に有名だが、昔からそうだったかといえば、どうやらそうでもないらしい。100年前のフランス人は、今の日本人同様、長時間働いていて、働きすぎで身体を壊す人も多かった。 そんなフランスで、休暇が充実したのは、第2次世界大戦の後の、ある政治家の大英断だったと言われている。 レオン・ブルム氏──。 彼は、3度にわたって首相を務めたフランスの政治家で、とりわけ1936年に成立したフランス人民戦線内閣の首班を務めた人物として知られている。 当時、フランスでは大戦後に大恐慌の痛手から立ち直ることができず、経済は低迷し、街には失業者があふれていた。 そこでレオン・ブルム内閣は、長引く不況に対して「もっと働くこと」ではなく「もっと休むこと」で立ち向かうことを決断したのだ。 不況時に「もっと休め!」だなんて非難ごうごうで、彼の労働政策は、「ブルムの実験」と揶揄されたそうだ。 労働時間を短縮する政策が招いた“成果” しかし、ブルム氏はいかなる反発にもぶれることなく、週40時間労働制を推し進め2週間の有給休暇を保証するマティニョン法(通称「バカンス法」)を制定したのだ。 で、結果は……。 何と、余暇が増えたことで、フランスではサービス産業が大きく成長し、内需主導型経済への脱皮を果たすとともに雇用も拡大。「もっと休め!」政策は、経済の回復に大きな役割を果たした。経済も、人も、元気になったのである。 「もっと休め!」というブルム氏のスローガンは、その他の欧州の国々にも広がった。さらに、労働組合は賃金だけでなく、休日や余暇の拡大を勝ち取るべく戦ってきたとされている。しかも勝ち取った休日は、「100%消化して当たり前」。勝ち取ったものは、使うもの。そういう考え方が基本なのだ。 日本と欧州の働く時間の考え方の違いは、法律を比べると分かりやすい。 例えば、日本では、1日8時間、週40時間労働が原則とされているが、労働基準法で労働者と使用者が協定を結べば、それ以上働かせることができる「36(サブロク)協定」と呼ばれるものが存在している。 協定を結んでも、時間外労働は月45時間以内にすることと定められているのだが、36協定には、特別条項というものがあり、一定期間に仕事が集中するような場合には、月45時間以上の残業を命じることができる。 本来、これは「特別な理由」の場合を想定したものだが、実際の運用では月100時間までの残業を6カ月命じることができるといった36協定もあるとされ、過労死ラインとされる月80時間を超えている。 ある調査では、東証一部上場の売上上位100社の7割が、過労死ライン以上の時間外労働が可能な協定を結んでいたとの報道もあった。 「休む権利」を尊重し実行しているヨーロッパ 一方、労働時間の短いヨーロッパでは、残業も含めて週48時間以上働かせてはいけないというルールがある。さらに、24時間につき最低連続11時間の休息を設けなければならないといった、次の仕事までのインターバルを定めている。 ちなみに、日本では時間外労働が、年間平均160時間超であるのに対し、フランスでは年間平均50時間程度。週平均に換算すると1時間余りでしかない。「労働時間の上限規制」だけではなく、「休息時間の下限」も決めているので、必然的に長時間労働が規制されるというわけだ。 おまけにヨーロッパでは、最低でも12日程度の連続休暇を保証することが一般的であるため、夏休みを誰もが長期にわたって取得する。 日本では、「時間外労働ありき」という前提の法律で、「残業手当」などの賃金とパッケージでとらえる傾向にあるが、ヨーロッパでは、労働時間そのものを問題にし、休む権利を重視しているのだ。 長時間労働問題は、賃金とセットで考える問題ではなく、身体とセットと考えなくてはならない問題のはずだ。 長時間労働が続くと睡眠時間が減っていくから、身体は必然的に疲弊する。本来人間は疲れると、前頭葉にある「疲れの見張り番」から、「疲れているので、休んでください」という信号が送られるのだが、その指令を無視して活動し続けると、見張り番自体が疲弊してしまい「休んでください」という指令すら、送れなくなる。 過労死する人のほとんどがその直前まで、死に至るほど「疲れている」という自覚症状がないまま、過酷な状況に慣れてしまっているケースが多いのも、この見張り番の疲弊によるものだと考えられている。 長時間労働問題は、生産性だの、残業手当だの、企業の体力とか関係ない。人が人として、すべての人がより良く生きられるために、人の尊厳を守るために、問題にしなくてはならないし、長時間労働はそれ自体が問題なのだ。 だが、残念なことに、「長時間労働問題そのもの」を問題にする流れに、今の日本はない。 厚労省では、全国1万社を対象に、労働時間の実態調査を始める方針を固めた。といっても、調査の目的は、実際の労働時間に関係なく賃金が払われる「裁量労働制」の拡大のため。 再びホワイトカラー・エブゼンプションまで俎上に 思い起こせば、年収など一定の条件を満たすホワイトカラーから労働時間規制の適用を免除しようとし、「過労死促進法」と批判されたホワイトカラー・エグゼンプション(ホワイトカラー労働時間規制撤廃制度)の導入が議論されたのは、第1次安倍晋三政権時代。 当時の安倍さんは、「残業代が出ないのだから従業員は帰宅する時間が早くなり、家族団らんが増え、少子化問題も解決する」と反論し、厚労相だった升添要一さんも、「家庭団らん法」と呼び変えるよう指示をしたとされていた。 現安倍政権でも、産業競争力会議で、民間委員の三木谷浩史・楽天会長が、ホワイトカラー・エグゼンプションの導入を強く主張しているとの報道もある。 裁量労働制も、国連からの異例の勧告も、とても大切なことだと思うのだが、どういうわけかあまり報じられていない。 長時間労働をなくすには、労働時間の規制だけではなく、休暇日数の下限、休息時間の下限を設定することが必要。強制的に休みを作る。長時間労働は、人権問題。こういう時こそ欧州を見習って、グローバルスタンダートを持ち出すべきなんじゃないだろうか。
http://business.nikkeibp.co.jp/article/manage/20130616/249728/?ST=print
ストラテジーとタクティクス:仕事ができる人に大切なのはどっち? 2013年6月18日(火) 杉浦 正和 このコラムでは、ビジネスリーダーに「本当の意味」を理解してほしいビジネス用語ついて解説していきます。拙著『ビジネスマンの知的資産としてのMBA単語帳』(略称『MBA単語帳』)に掲載した言葉の中から、毎回2つか3つの言葉をピックアップして解説し、「組み合わせ」の形で紹介していきます。 2回目の今回は、タクティクス(tactics)とストラテジー(strategy)。漢字では戦術と戦略。「それって何ですか」と日本人に聞くと、「戦い方」とか「勝つための方策」といった言葉が返ってきます。確かに、どちらも「戦」という漢字が入っていますから「戦うこと」に関係すると思うのは当然。でも、本当にそのニュアンスでいいのでしょうか? 「ワラライ」って何のこと? 私自身、英語が自分の言葉になったと感じられるようになったのは、仕事で英語を使ってずいぶん時間がたってからのことです。 そのピークは早稲田大学ビジネススクールのシンガポールにおけるプログラムの責任者になった時でした。ただでさえ難しい英語での授業を「アウェー」で行ったり、現地関係者とのハードな折衝をしたりして、苦労の連続。朝起きると家族に「英語で寝言を言ってたわよ」。そんな修羅場の経験を経てやっと英語の世界に「入り込む」ことができた気がしました。 その前には、外資系の会社で人事部長として勤務していました。イギリス人の日本法人トップから「このタクティクスをワラライで成し遂げるように」と指示されて、「ワラライって何?」と考え込んでしまった経験もあります。後になって、「ワラライ」と聞こえた言葉はウォータータイト(watertight)だったと分かりました。時計や携帯電話の場合には「防水」という意味になります。 戦術が防水――??。最初は全く意味不明でしたが、そのうちタクティクスをウォータータイトで行うとは、「水も漏らさぬように」「手抜かりなく」遂行するということらしいと分かってきました。そして、その時に初めて私には「タクティクスとは何か」がストンと腑に落ちたのです。 それでは、読者の皆さんに質問です。私が「ワラライ」で成し遂げるように命じられた「タクティクス」は、日本語にすると、どういう意味でしょうか? タクティクスの最も一般的な訳語は「戦術」ですが、「方策」や「策略」などの訳もあります。漢字から考えると、「戦いに勝つために策を巡らせる」といったイメージがわくのは当然です。しかし、「ワラライで」の使い方から考えると、タクティクスは必ずしも「戦う」ことだけに関わるわけではなくまた「謀りごと」のニュアンスだけというわけでもないのです。 配置」と「抜かりなさ」 「タクティクス(tactics)」の語源は、「配置する」を意味するギリシャ語で、そこから「(兵の)配置」、すなわち「戦術」となりました。「タクティカル(tactical)」は「戦術的」ですが、「駆け引きがうまい」という意味もあります。 よく似た響きを持つ言葉に、「如才なさ」を意味する「タクト(tact)」とその形容詞で「気が利く」を意味する「タクトフル(tactful)」があります。これらは「触る」が元となった言葉です。 英語そのものを学ぶ時には「これらの言葉は似て非なるものだから気をつけましょう」と注意されます。一方で、ビジネスの現場では、それらのニュアンスはむしろお互いに混ざり合い、補完し合っているように私は感じられます。「タクトフル・タクティクス(気の利いた戦術)」なんていう言葉遊びをする人もいますが、それこそ気が利いています。 タクトフルとは、相手の立場に立ち、気持ちをよく理解し、時には先回りして効果的に対応すること。例えば、何かしてほしいと言わなくても、「これをしておきましょうか?」と言ってくれる。何かがなくて困っている時に、「これが要りますか?」と横から差し出してくれる。何をすべきか迷っている時に「これはどうでしょう?」と気がつかなかった点を指摘してくれる。 こんな人がいてくれれば、どんなに仕事が進むでしょうか。そして、それでこそ戦術も遂行できるというもの。気が利かなければ戦術も台無しなのです。 「気がつく人」は多いけれど「気が利く人」は少ない 「気がつく人」はそれなりにいるのですが、さらに適切なアクションが伴わないと「気が利く人」にはなれません。しかも「出すぎた真似」にならない程度に。しかし、そんなことができる人は決して多くはありません(ちなみに、私も家庭内では「気が利かない人」の代表だそうで、「今度連載で『気が利く』について書くよ」と言ったら「気が遠くなる」と言われました)。 タクトフルであるということは、その「場」と「時」の状況に適した行動を取れるということですから、大所高所というよりは個別具体的な判断です。タイミングも決定的に大切ですから、ある種の勘の良さも必要です。 現場に立脚していることを、英語ではハンズ・オン(hands-on)と言います。「きちんと手を置いて」という意味です。具体の「体」、立脚の「脚」、ハンズ・オンの「手」。アタマの中だけで考えたのではなく、体にも脚にも手にもきちんと神経が通っており、確かな感触を確かめながら「手を打つ(take action)」ことです。 「現場に精通して、細部において手抜かりなく、上司や顧客のニーズに先回りして応え、競争や交渉の相手とはうまく駆け引きしながら」仕事を遂行すること――。それが、タクティクスというという言葉について私が現場で感じてきたニュアンスです。 かつての上司が言った「ワラライのタクティクス」は、まさに「戦術」としてのタクティクスと「手抜かりなく」のタクトが混ざり合ったような言葉だったなぁと今にして思います。タクティクスとタクトのニュアンスは良い意味で響き合っているし、またそうであるべきなのだと私には思えるのです。 ただ、「ワラライ」の印象が強すぎて、私は本の中では混同して書いてしまいました。「2つの似て非なる言葉だけれども、実際の使われ方では響き合っているように思う」のが正確なところですので、この場を借りてお詫びとともに訂正させていただきます。文字通り「生兵法(生煮えのタクティクス?)は怪我のもと」と、改めて自戒しています。 戦略とは「総帥としての仕事」 では、ストラテジー(strategy)はどうでしょう。定番の訳は言うまでもなく「戦略」。しかし、この言葉のニュアンスも、「戦」を含む日本語とそれを含まない英語では微妙に異なっている場合があるように思います。言葉の成り立ちから考えると、英語の方は必ずしも戦うことのみを意味するのではないからです。 ストラテジーの元となったのはギリシャ語の「ストラテゴstrategos」という言葉。これはアテネにおける「総帥」あるいは「総司令官」の職の名前です。作家の塩野七生さんは「国家政戦略担当官」と訳しています。そこから派生したstrategiaは「総帥が下す命令」や「采配」となり、フランス語で「戦略」を表すstrategieを経て、この英語となりました。 最も著名なストラテゴは、世界史の教科書にも登場する古代アテネのペリクレス(Pericles, BC495-BC429)。ペリクレスはこの地位に長らく選出され続け、その大半を議長として過ごしました。海軍国で陸上の戦いには弱いアテネが、厳しい軍事訓練で鍛えられた強力な陸軍を持つスパルタにいかに対抗するか ――。ペリクレスの「戦略」は、陸での戦いにならないように、港を含む海岸に長い城壁を造り、市民すべてを壁の内側に置くことでした。方針・方策を立てて実行・実践したわけです。 ペリクレスが将軍(ストラテゴ)として採用したストラテジー(戦略)は戦いを指揮することだけではありませんでした。役職者を平民の中からも抽選で選ぶ制度を設けたことは、必ずしも戦いとは関係のない「制度作り」といえるでしょう。また、ペリクレスはパルテノン神殿を完成させました。私たちがギリシャ文化として理解している「アテネの黄金時代」は、ペリクレスがストラテゴであった時代のことです。 組織の黄金時代を作るのは、戦略・組織・制度から文化に至るすべての面にわたる総帥としてのストラテゴの仕事。それこそが「ストラテジー」の背後にある本来的なニュアンスなのかもしれません。 戦略と戦術は合わせて一つ 戦略的意思決定(strategic decision making)とは、様々な条件を勘案して、長期的かつ大所高所から考えて、限りある資源の最適配分を行うことです。岐路に立った時に、どのような判断をするか。目の前にある道を行くのか行かないのか――。そのことを、英語では“Go/No go”と言います(最初にこの言葉を聞いた時に「ゴーノゴー」と聞こえて、「いったい何のことですか?」と聞き返した覚えがあります) 進むか退くか。右に行くか左に行くか。あちらを取るかこちらを取るか。戦いに関係あろうとなかろうと、戦略とは「何をするかを決めること」です。それは同時に「何をしないかを決めること」でもあります。 ですから、ストラテジーは“What(何を)”の問題だと言い換えることもできます。それに対してタクティクスは“Where(その場)”や“When(その時)”に“How(いかにして)”行うかに関係する問題だと対比できると思います。具体的な裏づけのない戦略は絵に描いた餅。意思決定の前提になるのは、選択した戦略の実行可能性がそれなりに高いと見込めるかどうかです。 戦略を策定するストラテゴが信を置くのは、タクトを持ってタクティクスを遂行できる(そしてタクトフルな)人。そのような意味でも、ストラテジーとタクティクスは相補的。ストラテジーからタクティクスに落とし込むことも、タクティクスを積み上げてストラテジーとなることもあります。表題を自ら否定するようですが「どちらが大切か」ではなく、「どちらも大切」、そして「合わせて一つ」なのです。
仕事で誤解を招かないためのビジネスリーダー英単語帳
http://business.nikkeibp.co.jp/article/skillup/20130612/249564/?ST=print
いまや高リスク職業になったサラリーパーソン
大量早期退職時代、「身の丈起業」への道のり〜その1
2013年06月18日(Tue) 大山 充
昨今、アベノミクスの記事が報道紙面をにぎわす一方で、日本を代表する大手電機メーカー各社が、相次いで大規模な早期退職者の募集を進めている。さらに、厳しい国際競争の現場で勝ち組と言われる企業までが、若手の登用や人事の刷新などを掲げて早期退職制度を常態化させている。
グローバル時代を生き抜くために企業側がドライに徹していると言える。一方で、雇用される側の個人は、雇用だけを頼みとするサラリーパーソンであることが高リスクの職業に変化したことを自覚できずにいる。
シャープやパナソニックなど電機大手の人員削減計画が相次いだ〔AFPBB News〕
私自身、56歳で会社を早期退職し、2005年以来8年にわたり大手再就職支援企業で独立起業を目指す人々の支援に携わってきた。 これまで延べ1万2000人あまりを対象に、「独立起業支援セミナー」を開講するとともに、毎年、個別に30社を超える独立起業の支援を継続している。その経験を踏まえて、こうしたサラリーパーソンが早期退職した後の独立起業の実態を、3回に分けて報告する。 まずは、私がこの目で見てきた独立起業のトレンドを振り返ってみたい。 バブル崩壊から終身雇用制度の終焉へ 日本型経営の基礎にあったと言える終身雇用制度は、バブル崩壊(1992年)の後、数年を経て雇用を支え切れず崩壊した。 誘因として1995年に日本経営者団体連盟(現・日本経済団体連合会)が提言した「新時代の『日本的経営』」がある。その中で今後の企業・従業員の雇用に関する考え方を、3つのグループに分けて運用することを提言していた。 1つ目は長期雇用するグループ。長期的に蓄積した能力を活用する人材で、管理職、総合職、技能部門の基幹職を対象とする。2つ目の中期的雇用は高度な専門能力を活用する人材で、企画、営業、研究開発などの専門家を対象とする。 3つ目の短期的雇用は、雇用柔軟型人材であるホワイトカラーの一般職、流通・サービス業の営業職などを対象とする。これら3つのグループに分けて労働力の運用を図ることを提言するものであった。 一方、規制緩和政策のもとで労働者派遣法の改正が1997年と2004年に行われ、一気に非正規雇用者の採用が緩和されたことも正規雇用者の調整を可能にした。 やがて、人を最大の資源とする経営理念の松下電器産業(現パナソニック)の人員削減、企業再生を至上命題とした日産自動車のゴーン改革などの象徴的な人員削減を契機として、日本の大手企業の人事政策が早期退職制度の活用に大きく転換した。 小泉改革と景気回復の頃:団塊世代の起業の傾向
独立起業支援コンサルタントの大山 充氏
私が再就職支援企業で、独立起業の希望者向けに創業支援のコンサルティングをスタートした2005年当時は、4年目を迎えた小泉政権の時代だった。
財政改革とグローバル化に耐える競争力を強化する政策のもと、“雇用なき繁栄”と言われた緩やかな好景気が続いていた。大手企業のバブル後遺症としての人員削減が徐々に減少する一方で、人事サイクルとして早期退職制度の活用による団塊世代の削減が進められていた。 団塊世代以前の退職では、経験技術や人脈を活用した業界内の独立が多く、前職企業の周辺で仕事を続けるスタイルが多かった。また公的年金に加えて企業年金などが手厚く支給される層は、社会活動を主体にNPOなどを設立することも見られた。 2005〜2007年にかけて早期退職に応募した層は、2007年の団塊世代の60歳到達を前に、景気回復の市場を見ながら起業を果たそうとする層であった。 これまでの世代と異なるのは、ITを経験した世代としてITを活用した起業テーマが増えたことが挙げられる。しかもそれまでの情報システムを構築・加工するといった整備側ではない。自らITを活用して仕事に生かす新規事業や、SOHO事業者としての独立が目立ってきた。 またこの時期、団塊の世代のアクティブな性格から、大量の独立起業者の増加も期待されたが、意外に堅実な職場転換や転職が進んだ。 団塊の世代は、ライフスタイルとして初めて、若い時代に音楽や野外レジャーを楽しんだ世代だ。この世代の独立起業の特徴としては、面白いことに挑戦したいとする意識が出てきたことが挙げられるだろう。 リーマン・ショックと東日本大震災の頃:前職キャリア以外の起業も増加 2008年にアメリカで発生したリーマン・ショックと呼ばれる金融危機は、瞬く間に欧州に飛び火し世界恐慌の様相を呈した。 当初日本は対岸の火事のような態度で政府や日銀の対応が遅れた結果、2008年日本の10〜12月期のGDPは、年率12.7%減と世界の主要国で最大の落ち込みとなった。そこでまず、輸出の主役である自動車、電機、素材関連が雇用調整に入った。 この時期、日本の大企業は軒並み苦境に陥ったが、2009年度は最大250万人が雇用調整助成金の活用により雇用継続され、2010〜2011年にかけて雇用調整が進んだ。 独立起業の分野としては、堅実に前職のキャリアを生かす業界内の仕事で独立する人も多かったが、高齢化や少子化のニーズに対応する介護関連事業や高齢者向け給食宅配、また保育園や託児所などの開業も増えている。 一方、フランチャイズ系事業は、ひと頃のコンビニエンスストア経営のように確実に繁盛する時代を過ぎて、開業の初期投資が大きい分だけ、慎重な選択をする人が多くなった。 2011年3月の東日本大震災と福島原発災害では、東北及び北関東を中心に大きな被害が出た。節電の要請が出て小売りや飲食業が影響を受け、首都圏でも食材の安全性などを懸念して飲食系の開業を諦める者も出た。 2011年後半から2012年にかけて、独立起業に関しては市場の様子を伺うなど自粛ムードが広がった時期でもある。 最近の大規模な雇用調整と「身の丈起業」への流れ
アベノミクスの先行きは・・・〔AFPBB News〕
2012年の後半から半導体業界や電機業界の大規模な雇用調整が始まり、早期退職による独立起業の志願者も増加した。こうした業界の出身者は、電子・IT関連の先端分野で活躍した人材も多く、他の業界の場合より独立起業を目指す比率も高い。 昨年12月の安倍内閣の誕生以降は、アベノミクスによる円安株高の効果で景気がいくぶん持ち直した。先行きの明るさを感じ取って、不動産や農業関連の起業も増えている。 また、近年の単身世帯の増加やライフスタイルの多様化を狙った、癒やし系サービスや生活支援などの個人向けサービス事業を始める起業者も増えている。 全般に早期退職からの独立起業では、無理な投資をしないSOHOスタイルの専門家ビジネスや、ITを活用した個人向け販売・サービス事業を選ぶことが増えてきた。営業系の販売代行業や業界知識を生かすコンサルタント、各種のインストラクターや講師といった仕事で独立する人も多い。 初めは小さく始めて、その人の努力や工夫次第で成長を見込む。若年層の起業と違って生活基盤が既にできており、間もなく年金などの収入も見込めるが故の、急がず慌てずの起業スタイルと言える。こうした「身の丈起業」と呼ぶべきスタイルの定着が見られてきた。 終身雇用制度の崩壊と年金支給年齢引き上げのダブルパンチ 今やサラリーパーソンというのはリスクの高い職業である、というのが今の私の偽らざる認識だ。 サラリーパーソンは、大きな企業に入ったらもう定年まで安心だという、終身雇用制度というものがかつてはあった。しかしそれはバブルの崩壊とともに終焉している。 かつての日本型経営はもう十数年前に止まってしまった。バブルが弾けてすぐではなくて4〜5年たってからだ。こらえきれず大手企業の大多数は日本的な終身雇用制度を取り止めていったという流れがある。 もう1つ、国の年金政策によって支給年齢が引き上げられた。これは実際働いてきたサラリーパーソンにとっては一番大変なことだ。昔だったら定年したら年金が間近にあって、切れ目なくお金をもらえるという感覚でいたのが、いつの間にかどんどん支給開始年齢が引き上げられた。 国としては65歳まで定年延長だと、いかにも受けのいい政策をしている。しかし、現実には年金支給開始年齢が引き上がるので企業に雇用を延長してくれと無理に義務を課しているわけだ。 企業としては、これは結構つらい。現実問題、高年齢層向けの職域が創造できていない。だから企業はその代償として、自由意思による早期退職制度というものを一般化し、雇用者に正面から提案するようになってきたのだ。 つづく
http://jbpress.ismedia.jp/articles/print/37978
|
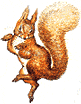
 スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。 スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。