http://www.asyura2.com/13/hasan79/msg/407.html
| Tweet | پ@ |

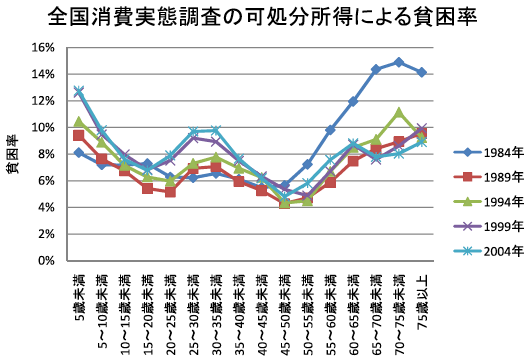
‚±‚±30”N‚إ‚Q‚Oپ|‚R‚O‘م‚جژل”N‘w‚ج•nچ¢—¦‚ح‚Uپ“‚©‚ç‚P‚Oپ“‹ك‚‚ةڈمڈ¸‚µ‚½پB
ˆê•û‚إپAگlگ””ن‚ھ‹}‘‚µ‚½‚ة‚à‚©‚©‚ي‚炸پAچ‚—îژز‚ج•nچ¢—¦‚ح‚P‚Tپ“‚©‚ç‚Wپ|‚P‚Oپ“‚ض‚ئ’ل‰؛‚µ‚½پi‰آڈˆ•ھڈٹ“¾ƒxپ[ƒXپjپB
Œ´ˆِ‚ئ‚µ‚ؤ‚حپAچ‚—îژزŒü‚¯‚ة‚ح”N‹àگ…ڈ€‚جƒfƒtƒŒ‚ة‚و‚éژہژ؟“Iڈمڈ¸پAگ¶ٹˆ•غŒى‚ب‚ا‚جژذ‰ï•غڈل‚جڈ[ژہ‚ھچàگگشژڑ‚ً–³ژ‹‚µ‚ؤŒp‘±‚µ‚½‚±‚ئپAژل”N‘w‚إ‚حژ¸‹ئپA”ٌگ³‹K‰»پA’ہ‹à’ل‰؛پAگإپEژذ‰ï•غڈل•‰’S‚ھڈمڈ¸‚µ‚½‚±‚ئ‚ھ‚ ‚°‚ç‚ê‚éپB
‚ـ‚½•nچ¢‰ًڈء‚ج‚½‚ك‚ج•ûچô‚ئ‚µ‚ؤ‚حژ¸‹ئ—¦‚جڈمڈ¸‚ً”؛‚¤چإ’ل’ہ‹àƒAƒbƒv‚و‚è‚àپAگ¶ٹˆ•غŒى‚âژq‹ںژè“–‚ب‚ا‹‹•t‚ج‹‰»‚ھ—LŒّ‚إ‚ ‚邱‚ئ‚àژ¦‚³‚ê‚ؤ‚¢‚éپB
http://www.rieti.go.jp/jp/projects/program/pg-07/001.html
کJ“ژsڈêگ§“x‰üٹvƒvƒچƒWƒFƒNƒg پ@
چإ’ل’ہ‹à‚ئ•nچ¢‘خچô
ژ·•Mژز ‘ه’| •¶—Y (‘هچم‘هٹwژذ‰ïŒoچدŒ¤‹†ڈٹ)
2009”N‚ةŒْگ¶کJ“ڈب‚ھ“ْ–{‚ج‘ٹ‘خ“I•nچ¢—¦‚ھ15.7%‚ئ‚¢‚¤چ‚‚¢گ…ڈ€‚ة‚ ‚邱‚ئ‚ً”•\‚µ‚½پBژہ‚حپA“ْ–{‚ج‘ٹ‘خ“I•nچ¢—¦‚ھگوگiچ‘‚ج’†‚إ‚حچ‚‚¢•û‚إ‚ ‚邱‚ئ‚حپAOECD‚جŒ¤‹†‚إ‚à–¾‚ç‚©‚ة‚³‚ê‚ؤ‚¢‚éپB•nچ¢‰ًڈءژè’i‚ة‚حپAŒi‹C‰ٌ•œ‚ة‚و‚éڈٹ“¾ڈمڈ¸پAڈٹ“¾چؤ•ھ”zگچô‚ة‚و‚é’لڈٹ“¾ژز‚جڈٹ“¾ڈمڈ¸پA’لڈٹ“¾ژز‚ة‘خ‚·‚éگE‹ئŒP—û‚ة‚و‚éگ¶ژYگ«ڈمڈ¸‚ئ•ہ‚ٌ‚إپAچإ’ل’ہ‹à‚جˆّ‚«ڈم‚°گچô‚ھ‚µ‚خ‚µ‚خ‹“‚°‚ç‚ê‚éپB2009”N‚جڈO‹c‰@‘I‹“‚إ‚ح–¯ژه“}‚ھچإ’ل’ہ‹à‚ً1000‰~‚ةˆّ‚«ڈم‚°‚ؤ‚¢‚‚±‚ئ‚ًŒِ–ٌ‚ةگي‚ء‚ؤپAگŒ ‚ًژو‚ء‚½‚ج‚ح‚»‚ج“TŒ^‚إ‚ ‚éپBچإ’ل’ہ‹à‚جˆّ‚«ڈم‚°‚حپAڈ‚ب‚‚ئ‚à’Zٹْ“I‚ة‚حچàگژxڈo‚ً‘‚₳‚ب‚¢گچô‚إ‚ ‚èپAچàŒ¹‚ًٹm•غ‚·‚é•K—v‚ھ‚ب‚¢‚ج‚إپAگژ،“I‚ة‚àچD‚ـ‚ê‚éگچô‚إ‚ ‚éپB
چإ’ل’ہ‹àˆّ‚«ڈم‚°‚حپA–{“–‚ة•nچ¢‰ًڈءچô‚ئ‚µ‚ؤ—LŒّ‚ب‚ج‚¾‚낤‚©پBŒ‹ک_‚©‚çڈq‚ׂé‚ئپAچإ’ل’ہ‹àˆّ‚«ڈم‚°‚ح•nچ¢‘خچô‚ئ‚µ‚ؤ‚ ‚ـ‚è—LŒّ‚بژè’i‚إ‚ح‚ب‚¢پBگىŒûپEگX(2009)‚جژہڈط•ھگح‚ة‚و‚ê‚خپA“ْ–{‚ة‚¨‚¢‚ؤچإ’ل’ہ‹àˆّ‚«ڈم‚°‚إŒظ—p‚ھژ¸‚ي‚ê‚é‚ئ‚¢‚¤ˆس–،‚إ”يٹQ‚ًژَ‚¯‚ؤ‚«‚½‚ج‚حپAگV‹Kٹw‘²ژزپAژqˆç‚ؤ‚ًڈI‚¦‚ؤکJ“ژsڈê‚ةچؤژQ“ü‚µ‚و‚¤‚ئ‚µ‚ؤ‚¢‚éٹùچ¥ڈ—گ«پA’لٹw—ً‘w‚ئ‚¢‚ء‚½Œ»ژ“_‚إگ¶ژYگ«‚ھ’ل‚¢گl‚½‚؟‚¾پB•nچ¢‘خچô‚ئ‚µ‚ؤچإ’ل’ہ‹à‚ًˆّ‚«ڈم‚°‚ؤ‚àپA‰^—ا‚گE‚ًˆغژ‚إ‚«‚½گl‚½‚؟‚حڈٹ“¾‚ھ‚ ‚ھ‚é‚©‚à‚µ‚ê‚ب‚¢‚ھپAژdژ–‚ًژ¸‚ء‚ؤ‚µ‚ـ‚¤گl‚½‚؟‚حپA•nچ¢‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚µ‚ـ‚¤پB‚±‚¤‚µ‚½گl‚½‚؟‚جڈA‹ئ‹@‰ï‚ھژ¸‚ي‚ê‚é‚ئپAژdژ–‚ً‚µ‚ب‚ھ‚ç‹Zڈp‚â‹خکJڈKٹµ‚ًگg‚ة’…‚¯‚邱‚ئ‚à‚إ‚«‚ب‚‚ب‚éپBچإ’ل’ہ‹àˆّ‚«ڈم‚°‚إŒظ—p‚ھژ¸‚ي‚ê‚é‚ئ‚¢‚¤ژہڈط“I‚بŒ‹‰ت‚حپAکJ“ژsڈê‚ھ‹£‘ˆ“I‚بڈَ‹µ‚ة‚¨‚¯‚éچإ’ل’ہ‹àˆّ‚«ڈم‚°‚ةٹض‚·‚é—ک_“I‚ب—\‘ھ‚ئ‘خ‰‚µ‚ؤ‚¢‚éپB‚½‚¾‚µپAچإ’ل’ہ‹àˆّ‚«ڈم‚°‚ة‚و‚ء‚ؤژdژ–‚ًژ¸‚¤‚ج‚ھپA—¯•غ’ہ‹à‚ھچ‚‚¢کJ“ژز‚©‚ç’ل‚¢کJ“ژز‚ئ‚¢‚¤ڈ‡”ش‚إ‚ ‚ء‚½‚ئ‚·‚ê‚خپAŒظ—p‚ھژ¸‚ي‚ê‚邱‚ئ‚ة‚و‚éژذ‰ï“I—]ڈè‚جŒ¸ڈ‚و‚è‚àپAŒظ—p‚ًˆغژ‚إ‚«‚½گl‚½‚؟‚ج’ہ‹à‚ھڈمڈ¸‚·‚éŒّ‰ت‚ة‚و‚é—]ڈè‚ج‘‰ء‚ج•û‚ھ‘ه‚«‚‚ب‚é‰آ”\گ«‚ھ‚ ‚é (Lee and Saez(2012))پB
چإ’ل’ہ‹à‚جˆّ‚«ڈم‚°‚و‚è‚à•nچ¢‘خچô‚ئ‚µ‚ؤپAŒoچدٹwژز‚ج‘½‚‚ھ—LŒّ‚¾‚ئچl‚¦‚ؤ‚¢‚éگچô‚حپA‹‹•t•t‚«گإٹzچTڈœ‚â‹خکJڈٹ“¾گإٹzچTڈœ‚إ‚ ‚éپB‹‹•t•t‚«گإٹzچTڈœ‚حپA’لڈٹ“¾‘w‚ة‘خ‚·‚é’èٹz‚ج‹‹•t‚ھپA‹خکJڈٹ“¾‚جڈمڈ¸‚ئ‚ئ‚à‚ة‹خکJڈٹ“¾‚ج‘‰ءٹz‚جˆê•”‚ھŒ¸ٹz‚³‚ê‚ؤ‚¢‚‚ئ‚¢‚¤‚à‚ج‚إ‚ ‚éپBŒ»چs‚ج“ْ–{‚جگ¶ٹˆ•غŒىگ§“x‚حپA‹خکJڈٹ“¾‚ھ‘‚¦‚é‚ئ‚ظ‚ع‚»‚جٹz‚ھ‹‹•tٹz‚©‚猸ٹz‚³‚ê‚éپB‚»‚جڈêچ‡‚ة‚حپA‹خکJˆس—~‚ً•غ‚آ‚±‚ئ‚ھ“‚¢‚ئ‚³‚ê‚ؤ‚¢‚éپB‹‹•t•t‚«گإٹzچTڈœگ§“x‚حپAƒJƒiƒ_‚إڈء”ïگإ‹tگiگ«‘خچô‚ئ‚µ‚ؤ“±“ü‚³‚ꂽ‘¼پA•ؤچ‘پA‰pچ‘پAƒJƒiƒ_پAƒIƒ‰ƒ“ƒ_‚إژ™“¶گإٹzچTڈœ‚ئ‚µ‚ؤ“±“ü‚³‚ê‚ؤ‚¢‚éپiگXگM(2008)پjپBˆê•ûپA‹خکJڈٹ“¾گإٹzچTڈœ‚حپA‹خکJڈٹ“¾‚ھ’ل‚¢ڈêچ‡‚ة‚حپA‹خکJڈٹ“¾‚ة”ن—ل‚µ‚ؤ‹‹•tٹz‚ھ“¾‚ç‚êپA‹خکJڈٹ“¾ٹz‚ھˆê’èٹzˆبڈم‚ة‚ب‚ê‚خپA‚»‚جٹz‚ھˆê’è‚ة‚ب‚èپA‚³‚ç‚ة‹خکJڈٹ“¾ٹz‚ھ‘‚¦‚ê‚خپA‹‹•t‚ھڈ™پX‚ةŒ¸ٹz‚³‚ê‚ؤڈءژ¸‚µ‚ؤ‚¢‚‚ئ‚¢‚¤گ§“x‚إ‚ ‚éپB‚±‚جگ§“x‚حپA‹‹•t•t‚«گإٹzچTڈœ‚و‚è‚àپAکJ“ˆس—~‚جژhŒƒŒّ‰ت‚ھ‹‚¢‚ئ‚³‚ê‚ؤ‚¢‚éپB‹خکJڈٹ“¾گإٹwچTڈœگ§“x‚حپA•ؤچ‘‚ئ‰pچ‘‚إ“±“ü‚³‚ê‚ؤ‚¢‚éپBLee and Saez(2012)‚حپA‹خکJڈٹ“¾گإٹzچTڈœ‚ئ’ل‚ك‚جچإ’ل’ہ‹à‚ج‘g‚فچ‡‚ي‚¹‚ھ–]‚ـ‚µ‚¢‚±‚ئ‚ًچإ“Kڈٹ“¾گإ‚جکg‘g‚ف‚إژ¦‚µ‚ؤ‚¢‚éپB
“ْ–{‚ة‚¨‚¢‚ؤ•nچ¢‘خچô‚حچ‚—îژز‘w‚ةڈW’†‚µ‚ؤ‚«‚½پBچ‚—î‘w‚ج•nچ¢—¦‚جگ…ڈ€‚حچ‚‚¢‚à‚ج‚جپA•nچ¢—¦‚حŒِ“I”N‹à‚جڈ[ژہ‚ج‚¨‚©‚°‚إ‘ه‚«‚’ل‰؛‚µ‚ؤ‚«‚ؤ‚¢‚éپBˆê•û‚إپAگ}‚ةژ¦‚µ‚½‚و‚¤‚ةپA‚©‚آ‚ؤ•nچ¢—¦‚ھ’ل‚©‚ء‚½20چخ‘مپA30چخ‘م‚ج”N—î‘w‚ة‚¨‚¯‚é•nچ¢—¦‚ھچ‚‚ـ‚ء‚ؤ‚«‚ؤ‚¢‚éپB‚»‚جŒ‹‰تپA‚»‚جژq‹ں‚ج”N—î‘w‚إ‚ ‚é10چخ–¢–‘w‚ج•nچ¢—¦‚ھڈمڈ¸‚µ‚ؤ‚¨‚èپA’†‚إ‚à5چخ–¢–‚ج”N—î‘w‚ج•nچ¢—¦‚ھچ‚‚ـ‚ء‚ؤ‚¢‚éپB‚±‚ج‚و‚¤‚بژq‹ں‚ج•nچ¢—¦‚جچ‚‚ـ‚è‚حپA20چخ‘مپA30چخ‘م‚جŒظ—pڈَ‹µ‚جˆ«‰»‚â—£چ¥—¦‚جچ‚‚ـ‚è‚ھ‰e‹؟‚µ‚ؤ‚¢‚éپB•غˆç‚⋳ˆç‚ئ‚¢‚ء‚½Œ»•¨ƒTپ[ƒrƒX‚ً’ت‚¶‚ؤپAژq‹ں‚ة‘خ‚·‚é•nچ¢‘خچô‚ً‚·‚é‚ئ“¯ژ‚ةپAژل”N‘w‚جŒظ—p‚ً‘£گi‚·‚éگچô‚ھ•K—v‚ئ‚³‚ê‚ؤ‚¢‚éپB‚»‚جچغ‚ةپA‹خکJڈٹ“¾گإٹzچTڈœ‚â‹‹•t•t‚«گإٹzچTڈœ‚ً‚ئ‚è‚¢‚ê‚ؤ‚¢‚‚±‚ئ‚ھŒّ‰ت“I‚¾‚ئچl‚¦‚ç‚ê‚éپB
گ}پF”N—îٹK‹‰•ت•nچ¢—¦‚جگ„ˆع
ڈoڈٹپF‘ه’|پEڈ¬Œ´(2011) پu•nچ¢—¦‚ئڈٹ“¾پE‹à—Zژ‘ژYٹiچ·پvٹâˆنچژگlپEگ£Œأ”üٹىپE‰¥•Sچ‡•زپw‹à—Zٹë‹@‚ئƒ}ƒNƒچŒoچدپxپA“Œ‹‘هٹwڈo”إ‰ïپApp. 137-153
http://www.rieti.go.jp/jp/publications/nts/13j014.html
چإ’ل’ہ‹à‚جŒˆ’è‰ك’ِ‚ئگ¶ٹˆ•غŒىٹîڈ€‚جŒںڈط
ژ·•Mژز ‹ت“c Œjژq (•ں‰ھ‘هٹw)
گX ’mگ° (‘هچم‘هٹw / “ْ–{ٹwڈpگU‹»‰ï)
Œ¤‹†ƒvƒچƒWƒFƒNƒg کJ“ژsڈêگ§“x‰üٹvƒ_ƒEƒ“ƒچپ[ƒhپ^
ٹضکAƒٹƒ“ƒN ƒfƒBƒXƒJƒbƒVƒ‡ƒ“پEƒyپ[ƒpپ[:13-J-013 [PDF:1.5MB]پB
پuکJ“ژsڈêگ§“x‰üٹvپvƒvƒچƒWƒFƒNƒg
–{ک_•¶‚إ‚حپAچإ’ل’ہ‹àگ§“x‚ج—ًژj‚جٹTٹدپAچإ’ل’ہ‹à‚ج–عˆہٹz‚¨‚و‚رˆّ‚«ڈم‚°ٹz‚جŒˆ’è—vˆِ‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚ج•ھگح‚ًچs‚¢پA‚³‚ç‚ةگ¶ٹˆ•غŒىگ§“x‚ة‚¨‚¯‚éگ¶ٹˆ•}ڈ•ٹîڈ€‚ھڈء”ïژہ‘ش‚ً‚ا‚ج’ِ“x”½‰f‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ج‚©‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚ج•ھگح‚ًچs‚ء‚½پB“ْ–{‚جچإ’ل’ہ‹àگ§“x‚حگR‹c‰ï•ûژ®‚ً‚ئ‚ء‚ؤ‚¨‚èپA’†‰›چإ’ل’ہ‹àگR‹c‰ï‚ھٹe“s“¹•{Œ§‚ج’n•ûچإ’ل’ہ‹àگR‹c‰ï‚ة‘خ‚µپA’nˆو•تچإ’ل’ہ‹àٹz‚ج‰ü’è‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚ج–عˆہ‚ً’ٌژ¦‚·‚邱‚ئ‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚éپB‚±‚ج–عˆہگ§“x‚إ‚حپA47“s“¹•{Œ§‚ًAƒ‰ƒ“ƒNپABƒ‰ƒ“ƒNپACƒ‰ƒ“ƒNپADƒ‰ƒ“ƒN‚ج4‚آ‚جƒ‰ƒ“ƒN‚ة•ھ‚¯‚ؤ–عˆہٹz‚ً’ٌژ¦‚µپA’n•ûچإ’ل’ہ‹àگR‹c‰ï‚ھ–عˆہٹz‚ًژQچl‚ة‚µ‚ب‚ھ‚çچإ’ل’ہ‹à‚جگ…ڈ€‚ًŒˆ’è‚·‚éپB–عˆہٹz‚ح–عˆہٹzŒˆ’è‚جچغ‚جژQچlژ‘—؟‚ئ‚³‚ê‚ؤ‚¢‚éپw’ہ‹à‰ü’èڈَ‹µ’²چ¸پx‚ةژ¦‚³‚ꂽ’ہ‹àڈمڈ¸—¦‚âŒoچدڈَ‹µ‚ًژ¦‚·—LŒّ‹پگl”{—¦‚ب‚ا‚ًچl—¶‚µ‚ؤŒˆ’肳‚ê‚ؤ‚¢‚é‚ئچl‚¦‚ç‚ê‚é‚ھپA•ھگح‚جŒ‹‰تپA–عˆہٹz‚ح—LŒّ‹پگl”{—¦‚ج‰e‹؟‚ًژَ‚¯‚ؤ‚¢‚邱‚ئ‚ھژ¦‚³‚ꂽپB’ہ‹àڈمڈ¸—¦‚ب‚ا‚ح–عˆہٹz‚ة‰e‹؟‚ً—^‚¦‚ؤ‚¢‚ب‚©‚ء‚½پB
’n•ûچإ’ل’ہ‹àگR‹c‰ï‚حپA’†‰›چإ’ل’ہ‹àگR‹c‰ï‚ھژ¦‚µ‚½–عˆہٹz‚ًژَ‚¯‚ؤ‘O”N‚©‚牽‰~ˆّ‚«ڈم‚°‚é‚©‚ًŒˆ’è‚·‚é‚ھپA‚»‚جˆّ‚«ڈم‚°ٹz‚حپA‰؛‚جگ}‚ةژ¦‚³‚ê‚ؤ‚¢‚é’ت‚èپA–عˆہٹz‚ة‚¨‚¨‚ق‚ثڈ]‚ء‚ؤ‚¢‚邱‚ئ‚ھ–¾‚ç‚©‚ة‚ب‚ء‚½پB’†‰›چإ’ل’ہ‹àگR‹c‰ï‚ھژ¦‚·–عˆہٹz‚حژQچlژ‘—؟‚إ‚ ‚èپA’n•ûچإ’ل’ہ‹àگR‹c‰ï‚ة‘خ‚µ‚ؤ‹گ§—ح‚ًژ‚ء‚ؤ‚¢‚ب‚¢‚ھپA–عˆہٹz‚ھ‘ه‚«‚ب–ًٹ„‚ً‰ت‚½‚µ‚ؤ‚¢‚邱‚ئ‚ھ•ھ‚©‚ء‚½پB‚ـ‚½پAڈء”ïژxڈoٹzپA’ہ‹àڈمڈ¸—¦پA’تڈي‚جژ–‹ئ‚جژx•¥‚¢”\—ح‚ةٹض‚·‚é•دگ”‚حˆّ‚«ڈم‚°ٹz‚ة‰e‹؟‚ً—^‚¦‚ب‚¢‚ھپA1998”Nˆبچ~‚ج•ھگح‚إ‚حپAژ¸‹ئ—¦‚حˆّ‚«ڈم‚°ٹz‚ة•‰‚ج‰e‹؟‚ً—^‚¦‚邱‚ئ‚ھژ¦‚³‚ꂽپB
ڈم‹L‚ج•ھگحŒ‹‰ت‚و‚èپA’nˆو•تچإ’ل’ہ‹à‚ح’n•ûچإ’ل’ہ‹àگR‹c‰ï‚ھŒˆ’è‚·‚邱‚ئ‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ھپA’nˆو•تچإ’ل’ہ‹à‚ح‚ظ‚ع–عˆہٹz’ت‚è‚ةŒˆ‚ك‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚邱‚ئ‚ھ–¾‚ç‚©‚ة‚ب‚ء‚½پB–عˆہٹz’ت‚è‚ةˆّڈم‚°ٹz‚ًŒˆ‚ك‚é‚ج‚إ‚ ‚ê‚خپA’n•ûچإ’ل’ہ‹àگR‹c‰ï‚ج–ًٹ„‚ھ–â‚ي‚ê‚邱‚ئ‚ة‚ب‚é‚ھپA’n•ûچإ’ل’ہ‹àگR‹c‰ï‚ح’†‰›چإ’ل’ہ‹àگR‹c‰ï‚و‚è‚»‚ꂼ‚ê‚ج’n•û‚جŒoچدڈَ‹µ‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚جڈî•ٌ‚ً”cˆ¬‚µ‚ؤ‚¢‚邽‚كپA’n•ûچإ’ل’ہ‹àگR‹c‰ï‚ح–عˆہٹz‚ًژQچl‚ئ‚µ‚آ‚آ‚àپA‚±‚ê‚ـ‚إ‚و‚è’n•û‚جڈَ‹µ‚ً”½‰f‚µ‚½ˆّ‚«ڈم‚°ٹz‚ًŒˆ’è‚·‚ׂ«‚إ‚ ‚낤پB
گ}پFˆّ‚«ڈم‚°ٹz‚ئ–عˆہٹz
ڈoڈٹپFپwچإ’ل’ہ‹àŒˆ’è—v——پxٹe”N
گ¶ٹˆ•غŒىگ§“x‚©‚çژَ‚¯‚é•ض‰v‚جگ…ڈ€پiگ¶ٹˆ•غŒىٹîڈ€پj‚ة‚آ‚¢‚ؤŒں“¢‚µ‚ؤ‚ف‚و‚¤پBگ¶ٹˆ•غŒىٹîڈ€‚ج’†‚إ‚àپA“ْڈيگ¶ٹˆ‚جژù—v‚ً–‚½‚·گ¶ٹˆ•}ڈ•ٹîڈ€‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپA2008”Nژ{چs‚ج‰üگ³چإ’ل’ہ‹à–@‚إ‚حپAگ¶ٹˆ•غŒىٹîڈ€‚ھچإ’ل’ہ‹à‚ًڈم‰ٌ‚ء‚ؤ‚¢‚éڈêچ‡‚حچإ’ل’ہ‹à‚ًˆّ‚«ڈم‚°‚ؤگ¶ٹˆ•غŒىٹîڈ€‚ئچإ’ل’ہ‹à‚جک¨—£‚ً‰ًڈء‚·‚邱‚ئ‚ئ‚³‚ê‚ؤ‚¢‚éپB‚·‚إ‚ةˆê•”‚ج’nˆو‚إ‚حچإ’ل’ہ‹à‚ج‘ه•‚بˆّ‚«ڈم‚°‚ھچs‚ي‚ê‚ؤ‚¨‚èپAچإ’ل’ہ‹à‚ئگ¶ٹˆ•}ڈ•ٹîڈ€‚حگط‚è—£‚¹‚ب‚¢‚à‚ج‚ئ‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚éپB‚»‚ج‚½‚كپAگ¶ٹˆ•}ڈ•ٹîڈ€‚ج‘أ“–گ«‚ة‚آ‚¢‚ؤŒں“¢‚·‚邱‚ئ‚حڈd—v‚إ‚ ‚éپB
گ¶ٹˆ•}ڈ•ٹîڈ€‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپA’لڈٹ“¾گ¢‘ر‚جڈء”ïژxڈo‚╨‰؟‚ج‰e‹؟‚ًژَ‚¯‚é‚ئچl‚¦‚ç‚ê‚éپBڈء”ïژز•¨‰؟’nˆوچ·ژwگ”‚ھچ‚‚‚ب‚é‚ئ“s“¹•{Œ§’Pˆت‚إچؤŒvژZ‚³‚ꂽگ¶ٹˆ•}ڈ•ٹîڈ€‚ھچ‚‚‚ب‚邱‚ئ‚ھژ¦‚³‚êپAگ¶ٹˆ•}ڈ•ٹîڈ€‚حپA•¨‰؟‚ج’nˆوچ·‚ً‚ي‚¸‚©‚ة”½‰f‚µ‚ؤ‚¢‚邱‚ئ‚ھژ¦‚³‚ꂽپB‚µ‚©‚µپAڈء”ïژxڈo‚â”Nژû‘و1پEŒـ•ھˆت‚ج”Nژû‚جگ…ڈ€‚ھ‰e‹؟‚ً—^‚¦‚ؤ‚¢‚é‚ئ‚¢‚¤‰¼گà‚حژxژ‚³‚ê‚ب‚©‚ء‚½پB
ˆبڈم‚و‚èپAگ¶ٹˆ•}ڈ•ٹîڈ€‚ھڈء”ïژہ‘ش‚ً”½‰f‚µ‚ؤ‚¢‚ب‚¢‰آ”\گ«‚ھچl‚¦‚ç‚ê‚éپBژذ‰ï•غڈلگR‹c‰ïگ¶ٹˆ•غŒىٹîڈ€•”‰ï[2013]‚إ‚àگ¶ٹˆ•}ڈ•‘ٹ“–ڈء”ïژxڈo‚ئگ¶ٹˆ•}ڈ•ٹîڈ€‚ھک¨—£‚µ‚ؤ‚¢‚邱‚ئ‚ھژ¦‚³‚ê‚ؤ‚¨‚èپA–{ک_•¶‚إ‚جŒ‹‰ت‚ھژxژ‚³‚ê‚ؤ‚¢‚éپB‚»‚ج‚½‚كپA2013”N‚©‚çٹJژn‚³‚ê‚éڈء”ïژہ‘ش‚ئ‚جک¨—£‚ج‰ًڈء‚ً–ع“I‚ئ‚µ‚½گ¶ٹˆ•}ڈ•ٹîڈ€‚ج‰ü’è‚ح‚ ‚é’ِ“x‘أ“–‚إ‚ ‚é‚ئ‚¢‚¦‚و‚¤پB‚½‚¾‚µپAگ¶ٹˆ•}ڈ•ٹîڈ€‚حپAچإ’ل’ہ‹à‚جگ…ڈ€‚âڈZ–¯گإ”ٌ‰غگإ‚ب‚اڈd—v‚بژ{چô‚جٹîڈ€‚ج1‚آ‚ئ‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚邱‚ئ‚©‚çپAچ،Œم‚àگ¶ٹˆ•}ڈ•ٹîڈ€‚ج‰ü’è‚ة‚حگTڈd‚©‚آŒµگ³‚ب‘خ‰‚ھ–]‚ـ‚ê‚éپB
ژQچl•¶Œ£
? ژذ‰ï•غڈلگR‹c‰ïگ¶ٹˆ•غŒىٹîڈ€•”‰ï[2013]پuگ¶ٹˆ•غŒىٹîڈ€•”‰ï•ٌچگڈ‘پvŒْگ¶کJ“ڈب
http://www.rieti.go.jp/jp/publications/nts/13j013.html
چإ’ل’ہ‹à‚ئکJ“ژز‚جپu‚â‚é‹Cپvپ\ŒoچدژہŒ±‚ة‚و‚éƒAƒvƒچپ[ƒ`پ\
ژ·•Mژز گX ’mگ° (‘هچم‘هٹw / “ْ–{ٹwڈpگU‹»‰ï)
Œ¤‹†ƒvƒچƒWƒFƒNƒg کJ“ژsڈêگ§“x‰üٹvƒ_ƒEƒ“ƒچپ[ƒhپ^
ٹضکAƒٹƒ“ƒN ƒfƒBƒXƒJƒbƒVƒ‡ƒ“پEƒyپ[ƒpپ[:13-J-012 [PDF:610KB]پB
پuکJ“ژsڈêگ§“x‰üٹvپvƒvƒچƒWƒFƒNƒg
–â‘èˆسژ¯
چإ’ل’ہ‹à‚ھ•د‚ي‚ء‚½ڈêچ‡پAچ،ژَ‚¯ژو‚ء‚ؤ‚¢‚é’ہ‹à‚ة‘خ‚·‚éٹ´ٹo‚ح‚ا‚¤•د‚ي‚邾‚낤‚©پBکJ“ژز‚حچإ’ل’ہ‹à‚ًژè‚ھ‚©‚è‚ة’ہ‹à‚ج—ا‚µˆ«‚µ‚ً”»’f‚·‚é‚©‚à‚µ‚ê‚ب‚¢پB‚»‚µ‚ؤ‚»‚ج—ا‚µˆ«‚µ‚ج”»’f‚حپAکJ“ژز‚جگ¶ژYگ«‚ض‚ئ‰e‹؟‚ً—^‚¦‚éپB‚½‚ئ‚¦‚خپAچإ’ل’ہ‹à‚ھڈم‚ھ‚ء‚½‚ة‚àٹض‚ي‚炸ٹé‹ئ‚ھ’ہ‹à‚ًگک‚¦’u‚¢‚½ڈêچ‡‚ة‚حپAکJ“ژز‚ج‚â‚é‹C‚ح‰؛‚ھ‚ء‚ؤ‚µ‚ـ‚¤‚©‚à‚µ‚ê‚ب‚¢پB
چs“®Œoچدٹw‚ج—§ڈê‚©‚çپAچإ’ل’ہ‹à‚ج‚و‚¤‚بگ§“x‚ھگS—–ت‚ة‰e‹؟‚ً—^‚¦‚é‚©‚ا‚¤‚©‚ًŒںڈط‚µ‚½Œ¤‹†‚ھگi‚ٌ‚إ‚¢‚éپB–{Œ¤‹†‚إ‚حپAژہŒ±Œoچدٹw‚جژè–@‚ً—p‚¢‚ؤپAچإ’ل’ہ‹à‚ھکJ“ژز‚جگ¶ژYگ«‚ة‰e‹؟‚ً—^‚¦‚é‚©‚ا‚¤‚©پA‚ـ‚½‚»‚ج‰e‹؟‚حژ¸‹ئ‚·‚é‰آ”\گ«‚ة‚و‚ء‚ؤ•د‰»‚·‚é‚©‚ا‚¤‚©‚ًŒںڈط‚µ‚½پB
ژہŒ±ژèڈ‡‚ئŒ‹‰ت‚ج—v“_
ژہŒ±‚إ‚حپA”يŒ±ژز‚حپuٹé‹ئپv‚ئپuکJ“ژزپv‚ة•ھ‚©‚êپA‚ـ‚¸ٹé‹ئ‚ھ’ہ‹à‚ً‘I‘ً‚µپA‚»‚جŒمکJ“ژز‚ھ“w—حگ…ڈ€‚ً‘I‘ً‚·‚éپi‘I‘ً‚µ‚½’ہ‹àپE“w—حگ…ڈ€‚ة‰‚¶‚ؤ•ٌڈV‚ھژx•¥‚ي‚ê‚éپjپB‚±‚جژèڈ‡‚ًŒJ‚è•ش‚·’†‚إچإ’ل’ہ‹à‚ج“±“üپE“P”p‚ًچs‚¢پA“w—حگ…ڈ€‚ھ•د‰»‚·‚é‚©‚ا‚¤‚©‚ًŒںڈط‚·‚éپB
ژہŒ±Œ‹‰ت‚ة‚و‚é‚ئپAکJ“ژز‚ةژ¸‹ئ‚·‚é‰آ”\گ«‚ھ‚ب‚¢ڈêچ‡‚حپA‚ ‚é’ہ‹à‚ة‘خ‚·‚é“w—حگ…ڈ€‚ح’ل‰؛‚·‚éپB‚±‚ê‚حپAچإ’ل’ہ‹à‚ھٹîڈ€‚ًڈم‚°پA“¯‚¶’ہ‹à‚إ‚à‚و‚舫‚¢‘ز‹ِ‚ج‚و‚¤‚ةٹ´‚¶‚ç‚ê‚邱‚ئ‚ھŒ´ˆِ‚إ‚ ‚é‚ئچl‚¦‚ç‚ê‚éپB‚ـ‚½پAکJ“ژز‚ةژ¸‹ئ‚·‚é‰آ”\گ«‚ھ‚ ‚éڈêچ‡‚ح‚±‚جŒہ‚è‚إ‚ح‚ب‚پA“w—حگ…ڈ€‚ح•د‚ي‚ç‚ب‚¢پi‚ـ‚½‚حپAڈم‚ھ‚éڈêچ‡‚à‚ ‚éپjپB‚±‚ê‚حپAچإ’ل’ہ‹à‚ھژ¸‹ئ‚ً‘‰ء‚³‚¹پA“‚‚±‚ئ‚ج‰؟’l‚ھچ‚‚‚ب‚邱‚ئ‚ھŒ´ˆِ‚إ‚ ‚é‚ئچl‚¦‚ç‚ê‚éپB
گچô“IƒCƒ“ƒvƒٹƒPپ[ƒVƒ‡ƒ“
چإ’ل’ہ‹à‚ھگS—–ت‚ة‰e‹؟‚ً—^‚¦پAکJ“ژز‚ج“w—حگ…ڈ€‚ً‰؛‚°‚é‚ج‚إ‚ ‚ê‚خپAگ¶ژYگ«‚ھ—ژ‚؟‚邽‚كٹé‹ئ‚ج—ک‰v‚حŒ¸ڈ‚·‚邾‚낤پBگ¶ژYگ«‚ھ—ژ‚؟‚é‚ج‚ً–h‚®‚½‚ك‚ة’ہ‹à‚ًڈمڈ¸‚³‚¹‚ؤ‚àپA‚â‚ح‚èٹé‹ئ‚ج—ک‰v‚حŒ¸ڈ‚·‚éپB
‚±‚جƒCƒ“ƒvƒٹƒPپ[ƒVƒ‡ƒ“‚حپAچ‚‚¢چإ’ل’ہ‹à‚ھٹé‹ئ‚ج—ک‰v‚ً’ل‰؛‚³‚¹‚é‚ئ‚¢‚¤چإ‹ك‚جŒ¤‹†‚ئگ®چ‡“I‚إ‚ ‚éپB
ˆê•ûپAچإ’ل’ہ‹à‚ھژ¸‹ئ‚ً‘‰ء‚³‚¹‚é‚ج‚إ‚ ‚ê‚خپA“w—حگ…ڈ€‚حŒ¸ڈ‚µ‚ب‚¢‰آ”\گ«‚ھ‚ ‚éپB
‚µ‚©‚µگ¶ژYگ«‚ةˆ«‰e‹؟‚ھ‚ب‚¢‚ئ‚µ‚ؤ‚àپA‚»‚à‚»‚àژ¸‹ئ‚ھ‘‰ء‚µ‚ؤ‚¢‚邱‚ئ‚©‚çپAچإ’ل’ہ‹à‚حژذ‰ï“I‚ةˆ«‚¢‰e‹؟‚ھ‚ ‚éپBگ}‚حپAکJ“ژز‚ةژ¸‹ئ‚·‚é‰آ”\گ«‚ھ‚ ‚éڈêچ‡‚ج’ہ‹à•ھ•z‚ًپAچإ’ل’ہ‹à‚ج—L–³‚إ•ھ‚¯‚ؤژ¦‚µ‚ؤ‚¢‚éپBچإ’ل’ہ‹àپi40پj‚ج“±“ü‚ة‚و‚èپA‚»‚ج•t‹ك‚ج’ہ‹à‚ھ‘‚¦‚ؤ‚¢‚邱‚ئ‚ھ‚ي‚©‚éپB‚µ‚©‚µپA‚»‚êˆبڈم‚ةŒظ—p‹‘”غ—¦پiکJ“ژز‚©‚猩‚½ڈêچ‡‚جژ¸‹ئ—¦پj‚ھ‘‰ء‚µ‚ؤ‚¢‚邽‚كپA‘S‘ج‚ئ‚µ‚ؤ‚حˆ«‚¢‰e‹؟‚ھ‚ ‚é‚ئ‚¢‚¦‚éپB–{Œ¤‹†‚إچs‚ء‚½•ھگح‚©‚ç‚حپAچإ’ل’ہ‹àڈمڈ¸‚ًگ³“–‰»‚·‚邱‚ئ‚ح“‚»‚¤‚إ‚ ‚éپB
http://www.rieti.go.jp/jp/publications/nts/13j012.html
چإ’ل’ہ‹à‚ئ’nˆوٹشٹiچ·پFژہژ؟’ہ‹à‚ئٹé‹ئژû‰v‚ج•ھگح
ژ·•Mژز گXگى گ³”V (—ژ–پE•›ڈٹ’·)Œ¤‹†ƒvƒچƒWƒFƒNƒg کJ“ژsڈêگ§“x‰üٹvƒ_ƒEƒ“ƒچپ[ƒhپ^
ٹضکAƒٹƒ“ƒN ƒfƒBƒXƒJƒbƒVƒ‡ƒ“پEƒyپ[ƒpپ[:13-J-011 [PDF:844KB]پB
پuکJ“ژsڈêگ§“x‰üٹvپvƒvƒچƒWƒFƒNƒg
–â‘èˆسژ¯
“ْ–{‚إ‚حپA2000”N‘مŒم”¼ˆبچ~پAٹiچ·گ¥گ³‚â•nچ¢چيŒ¸‚ھ‘ه‚«‚بگچôƒCƒVƒ…پ[‚ئ‚ب‚èپAچإ’ل’ہ‹à‚جˆّ‚«ڈم‚°‚ھ’iٹK“I‚ةژہژ{‚³‚ê‚ؤ‚«‚½پB“ء‚ة‘ه“sژsŒ—‚إ‘ه•‚بچإ’ل’ہ‹à‚جˆّ‚«ڈم‚°‚ھچs‚ي‚ꂽپB‚±‚ج‰ك’ِ‚إپAٹé‹ئپA“ء‚ة’†ڈ¬ٹé‹ئ‚©‚ç‚حٹé‹ئŒo‰c‚ض‚ج‰e‹؟‚ًŒœ”O‚µ‚ؤ‹‚¢”½‘خˆسŒ©‚ھ•\–¾‚³‚ê‚ؤ‚«‚½پBچإ’ل’ہ‹à‚جŒoچد“IŒّ‰ت‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپA‘½‚‚جŒ¤‹†‚ھŒظ—pپA“ء‚ة‘ٹ‘خ“I‚ة’ہ‹à‚ج’ل‚¢ژل”N‘w‚جŒظ—p‚ض‚ج‰e‹؟‚ةڈإ“_‚ً“–‚ؤ‚ؤ‚«‚ؤ‚¨‚èپAٹé‹ئژû‰v‚ة‹y‚ع‚·‰e‹؟‚ةٹض‚·‚錤‹†‚حڈ‚ب‚¢پB
گlŒû‚âŒoچد‹K–ح‚ج‘ه‚«‚¢‘ه“sژs‚ظ‚اگ¶ژYگ«‚à’ہ‹à‚àچ‚‚¢‚ئ‚¢‚¤پuڈWگد‚جŒoچدگ«پv‚ھ‘¶چف‚·‚邱‚ئ‚حپA“àٹO‚ج‘½‚‚جŒ¤‹†‚إٹm”F‚³‚ê‚ؤ‚¢‚éپB‹ك”N‚جچإ’ل’ہ‹àˆّ‚«ڈم‚°‚ج‹cک_‚إ‚حپAچإ’ل’ہ‹àˆّ‚«ڈم‚°‚ئگ¶ژYگ«Œüڈم‚ج‚¢‚¸‚ê‚ھگو‚©‚ً‚ك‚®‚ء‚ؤک_‘ˆ‚ھ‚ ‚ء‚½‚ھ پAگ¶ژYگ«‚ئ’ہ‹à‚جٹش‚ة‚ح‹‚¢ٹضŒW‚ھ‚ ‚èپAٹé‹ئ‚جگ¶ژYگ«ڈمڈ¸‚ب‚µ‚ة’ہ‹à‚جˆّ‚«ڈم‚°‚ً‹گ§‚·‚邱‚ئ‚ح’nˆو‚جکJ“ژsڈê‚ةکc‚ف‚ً‚à‚½‚炵پAŒoچدŒْگ¶‚ً’ل‰؛‚³‚¹‚é‰آ”\گ«‚ھ‚ ‚éپB‚ـ‚½پA‚»‚à‚»‚à’ہ‹àگ…ڈ€‚ً’nˆوٹش‚إ“Kگط‚ة”نٹr‚·‚邽‚ك‚حپA’nˆو‚ة‚و‚éگ¶Œv”ïپi•¨‰؟گ…ڈ€پj‚جˆل‚¢‚àچl—¶‚·‚é•K—v‚ھ‚ ‚éپB
‚±‚¤‚µ‚½ڈَ‹µ‚ج‰؛پA–{چe‚حپAپi1پj•¨‰؟گ…ڈ€‚ًچl—¶‚µ‚½ژہژ؟’ہ‹à‚جٹد“_‚©‚çچإ’ل’ہ‹à‚ج’nˆوٹشٹiچ·‚جگ„ˆع‚ة‚آ‚¢‚ؤپA“Œvƒfپ[ƒ^‚ةٹî‚أ‚ٹدژ@ژ–ژہ‚ًٹTٹد‚·‚é‚ئ‚ئ‚à‚ةپAپi2پjژہژ؟چإ’ل’ہ‹à‚ھٹé‹ئژû‰v‚ة‹y‚ع‚·‰e‹؟‚ً‘ه‹K–ح‚بƒpƒlƒ‹ƒfپ[ƒ^‚ً—p‚¢‚ؤژہڈط“I‚ة•ھگح‚µ‚½پB
ژہژ؟چإ’ل’ہ‹à‚ج’nˆوٹشٹiچ·
2007”Nˆبچ~پA‘ه“sژsŒ—‚ً’†گS‚ةچإ’ل’ہ‹à‚جˆّ‚«ڈم‚°‚ھ‹}‘¬‚ةگi‚ك‚ç‚ꂽŒ‹‰تپA–¼–عچإ’ل’ہ‹à‚ج’nˆوٹشٹiچ·‚حٹg‘هŒXŒü‚ة‚ ‚é‚ھپA•¨‰؟گ…ڈ€پiپپگ¶Œv”ïپj‚ج’nˆوچ·‚ً•âگ³‚µ‚½ژہژ؟چإ’ل’ہ‹à‚ج’nˆوٹشٹiچ·‚ح‹t‚ةڈkڈ¬‚µ‚ؤ‚¢‚éپB1990”N‘م‚ة‚ح–¼–عچإ’ل’ہ‹à‚ھچ‚‚¢“s“¹•{Œ§‚ظ‚اژہژ؟چإ’ل’ہ‹à‚ھ’ل‚¢‚ئ‚¢‚¤‹t‘ٹٹض‚ھ‚ ‚ء‚½‚ھپA2000”N‘م‚ة“ü‚ء‚ؤ‚©‚ç—¼ژز‚جگ³‘ٹٹض‚ھ‹‚ـ‚ء‚ؤ‚«‚ؤ‚¢‚éپBڈWگد‚جŒoچدگ«‚ة‚و‚è’nˆوٹش‚إگ¶ژYگ«‚╨‰؟گ…ڈ€‚ھˆظ‚ب‚邱‚ئ‚ًچl‚¦‚ê‚خپA–¼–عچإ’ل’ہ‹à‚ة’nˆوچ·‚ًگف‚¯‚ؤ‚¢‚é“ْ–{‚â•ؤچ‘‚ج‚و‚¤‚بژd‘g‚ف‚ة‚حچ‡—گ«‚ھ‚ ‚èپAگ¶ژYگ«‚âگ¶Œv”ï‚ج’nˆوچ·‚ًچl—¶‚µ‚½“Kگط‚بگ…ڈ€‚ةگف’è‚·‚邱‚ئ‚ھڈd—v‚إ‚ ‚éپB‚½‚¾‚µپAˆث‘R‚ئ‚µ‚ؤچإ’ل’ہ‹à‚جگlŒû–§“x‚ة‘خ‚·‚é’eگ«’l‚ح•½‹د’ہ‹à‚ج‚»‚ê‚ة”ن‚ׂé‚ئڈ¬‚³‚¢پB‚آ‚ـ‚èپAگlŒû–§“x‚ج’ل‚¢’nˆو‚إ‚ح‘ٹ‘خ“I‚ةٹ„چ‚‚بچإ’ل’ہ‹à‚ھگف’肳‚ê‚ؤ‚¨‚èپAچإ’ل’ہ‹à‹ك–T‚جکJ“ژز‚جŒظ—p‹@‰ï‚âٹé‹ئژû‰v‚ة‰e‹؟‚ً—^‚¦‚ؤ‚¢‚é‰آ”\گ«‚ھ‚ ‚éپB
چإ’ل’ہ‹à‚جٹé‹ئژû‰v‚ض‚ج‰e‹؟
1998پ`2009”N‚جٹé‹ئƒpƒlƒ‹ƒfپ[ƒ^‚ً—p‚¢‚½گ„Œv‚ة‚و‚ê‚خپAچإ’ل’ہ‹àپi‘خ•½‹د’ہ‹àپj‚ھژہژ؟“I‚ةچ‚‚¢‚ظ‚اٹé‹ئ‚ج—ک‰v—¦‚ھ’ل‚‚ب‚éٹضŒW‚ھ‚ ‚éپB‚ـ‚½پAچإ’ل’ہ‹à‚جٹé‹ئژû‰v‚ض‚ج•‰‚ج‰e‹؟‚حپA•½‹د’ہ‹àگ…ڈ€‚ھ’ل‚¢ٹé‹ئ‚ة‚¨‚¢‚ؤ‚و‚茰’ک‚إ‚ ‚éپB’ہ‹à‚ھ•½‹دƒŒƒxƒ‹‚جٹé‹ئ‚إ‚حچإ’ل’ہ‹à‚ھ1•Wڈ€•خچ·چ‚‚‚ب‚ء‚½‚ئ‚«‚جٹé‹ئژû‰v‚ض‚ج‰e‹؟‚حپ£0.37%ƒ|ƒCƒ“ƒg‚¾‚ھپA•½‹د’ہ‹à‚ھ1•Wڈ€•خچ·’ل‚¢ٹé‹ئ‚إ‚حپA—ک‰v—¦‚ض‚ج‰e‹؟‚حپ£0.50%ƒ|ƒCƒ“ƒg‚ئ‘ه‚«‚¢پi‰؛گ}ژQڈئپjپB‚ـ‚½پAژY‹ئ•ت‚ة•ھگح‚·‚é‚ئپAƒTپ[ƒrƒX‹ئ‚ة‚¨‚¢‚ؤچإ’ل’ہ‹à‚ھٹé‹ئژû‰v‚ة‹y‚ع‚·‰e‹؟‚ھ‘ه‚«‚¢پB
گ}پFچإ’ل’ہ‹à‚ئ—ک‰v—¦
‚±‚جŒ‹‰ت‚حپA‘ٹ‘خ“I‚ةŒoچدٹˆ“®–§“x‚ھ’ل‚¢“s“¹•{Œ§‚جŒoچدٹˆ—ح‚ة‘خ‚µ‚ؤپAچ‚‚ك‚جچإ’ل’ہ‹à‚ھƒlƒKƒeƒBƒu‚ب‰e‹؟‚ًژ‚ء‚ؤ‚«‚½‰آ”\گ«‚ھ‚ ‚èپAŒ»چف‚إ‚à‚»‚¤‚µ‚½‰e‹؟‚ھژc‚ء‚ؤ‚¢‚邱‚ئ‚ًژ¦چ´‚µ‚ؤ‚¢‚éپBگچô“I‚ة‚حپA‰ك‘ه‚بچإ’ل’ہ‹àگ…ڈ€‚جگف’è‚ً”ً‚¯‚邱‚ئ‚ھچإ‘P‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚ة‚ب‚é‚ھپA‰¼‚ةچإ’ل’ہ‹àˆّ‚«ڈم‚°‚ًڈٹ—^‚ئ‚·‚é‚ب‚ç‚خپA‰e‹؟‚ًژَ‚¯‚éٹé‹ئ‚ة‘خ‚µ‚ؤگف”ُ“ٹژ‘پAŒ¤‹†ٹJ”“ٹژ‘پAڈ]‹ئˆُ‚ج‹³ˆçŒP—û‚ض‚جڈ•گ¬‚ًچs‚¤‚ب‚ا•âٹ®“I‚بگچô‚ًچu‚¶‚邱‚ئ‚ھژں‘P‚ج‘خچô‚ئ‚µ‚ؤ•K—v‚ئ‚ب‚éپB
http://www.rieti.go.jp/jp/publications/nts/13j011.html
چإ’ل’ہ‹à‚ھٹé‹ئ‚جژ‘Œ¹”z•ھ‚جŒّ—¦گ«‚ة—^‚¦‚é‰e‹؟
ژ·•Mژز ‰œ•½ ٹ°ژq (‰ھژR‘هٹw)
‘êàV ”ü”؟ (“Œ—m‘هٹw)
‘ه’| •¶—Y (‘هچم‘هٹw)
’ك Œُ‘¾کY (ƒtƒ@ƒJƒ‹ƒeƒBƒtƒFƒچپ[)Œ¤‹†ƒvƒچƒWƒFƒNƒg کJ“ژsڈêگ§“x‰üٹvƒ_ƒEƒ“ƒچپ[ƒhپ^
ٹضکAƒٹƒ“ƒN ƒfƒBƒXƒJƒbƒVƒ‡ƒ“پEƒyپ[ƒpپ[:13-J-010 [PDF:684KB]پB
پuکJ“ژsڈêگ§“x‰üٹvپvƒvƒچƒWƒFƒNƒg
چإ’ل’ہ‹à‚جڈمڈ¸‚ھŒظ—p—ت‚ة—^‚¦‚é‰e‹؟‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپAکJ“Œoچدٹwژز‚جٹش‚إ‚àˆسŒ©‚ھ•ھ‚©‚ê‚éپBˆسŒ©‚ھ•ھ‚©‚ê‚é1‚آ‚ج——R‚حپAکJ“ژsڈê‚ً‹£‘ˆ“I‚إ‚ ‚é‚ئچl‚¦‚é‚©پA”ƒ‚¢ژè“ئگè“I‚إ‚ ‚é‚ئچl‚¦‚é‚©‚ئ‚¢‚¤Œ©•û‚جˆل‚¢‚ة‚ ‚éپB—ک_ڈم‚حپAکJ“ژsڈê‚ھ‹£‘ˆ“I‚إ‚ ‚éڈêچ‡پAچإ’ل’ہ‹à‚جڈمڈ¸‚حŒظ—p—ت‚ًŒ¸ڈ‚³‚¹‚邱‚ئ‚ھ—\‘ھ‚³‚ê‚éپBˆê•ûپAکJ“ژsڈê‚ھ”ƒ‚¢ژè“ئگè“I‚إ‚ ‚é‚ب‚ç‚خپAچإ’ل’ہ‹à‚جڈمڈ¸‚حŒظ—p—ت‚ً‘‰ء‚³‚¹‚邱‚ئ‚à‚ ‚邱‚ئ‚ھ’m‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚éپB‚µ‚½‚ھ‚ء‚ؤپAŒ»ژہ‚جکJ“ژsڈê‚ھ‚ا‚؟‚ç‚جƒPپ[ƒX‚ة“–‚ؤ‚ح‚ـ‚é‚ج‚©‚ً’m‚邱‚ئ‚حپAچإ’ل’ہ‹à‚ًڈمڈ¸‚³‚¹‚éگچô‚جگ¥”ٌ‚ًچl‚¦‚éڈم‚إڈd—v‚بƒ|ƒCƒ“ƒg‚ج1‚آ‚ئ‚ب‚éپB–{Œ¤‹†‚إ‚حپAپuچH‹ئ“Œv’²چ¸پvپiŒoچدژY‹ئڈبپj‚جŒآ•[ƒfپ[ƒ^‚ً—p‚¢‚邱‚ئ‚إپAŒ»ژہ‚ة‚ح‚ا‚؟‚ç‚جƒPپ[ƒX‚ھگ¬‚è—§‚ء‚ؤ‚¢‚é‰آ”\گ«‚ھچ‚‚¢‚ج‚©‚ًٹé‹ئچs“®‚ج“à–ت‚©‚çŒںڈط‚µ‚½پB
–{Œ¤‹†‚ج•ھگح•û–@‚ًٹT”O“I‚ةژ¦‚µ‚½‚à‚جپi‹£‘ˆ“I‚بکJ“ژsڈê‚ً‘z’è‚·‚éڈêچ‡پj‚ھˆب‰؛‚جگ}‚إ‚ ‚éپB‹£‘ˆ“I‚بکJ“ژsڈê‚ة‚¨‚¢‚ؤپA‚إ‚«‚邾‚¯—کڈپ‚ًچإ‘ه‰»‚µ‚و‚¤‚ئچl‚¦‚éٹé‹ئ‚حپA1گl‚جکJ“ژز‚ًŒظ‚¤‚±‚ئ‚ج’ا‰ء”ï—pپi’ہ‹à—¦wپj‚ئپA‚»‚جکJ“ژز‚ًŒظ‚¤‚±‚ئ‚إ“¾‚ç‚ê‚é’ا‰ء“I•ض‰vپiکJ“‚جŒہٹEگ¶ژY•¨‰؟’lVMPLپj‚ً”نٹr‚µپA‚؟‚ه‚¤‚ا—¼ژز‚ھ’ق‚èچ‡‚¤‚ئ‚±‚ë‚إŒظ—p—ت‚ًŒˆ’è‚·‚éپiگ}’†‚جE“_پjپB‚à‚µ‚àچإ’ل’ہ‹à‚جˆّ‚«ڈم‚°‚ة‚و‚ء‚ؤژsڈê‚إ—^‚¦‚ç‚ê‚é’ہ‹à—¦‚ھw‚©‚çw'‚ةڈمڈ¸‚·‚é‚ئپA—کڈپ‚ًچإ‘ه‰»‚·‚éŒہ‚èپAٹé‹ئ‚حگ}’†‚جE'“_‚ةˆع“®‚·‚é‚و‚¤‚ةŒظ—p—ت‚ًŒ¸‚ç‚·‚±‚ئ‚ھ—\‘ھ‚³‚ê‚éپB‚µ‚©‚µپA‰½‚ç‚©‚ج——R‚ة‚و‚ء‚ؤŒظ—p—ت‚ً’²گ®‚إ‚«‚ب‚¢ڈêچ‡پA’ہ‹à—¦‚ھکJ“ژز‚جچvŒ£•ھ‚إ‚ ‚éVMPL‚ًڈم‰ٌ‚邱‚ئ‚ة‚ب‚èپAپiLپ|L'پjگl‚جکJ“ژز‚حٹé‹ئ‚ج—کڈپ‚ً‘¹‚ب‚¤—]ڈèکJ“ژز‚ئ‚ب‚ء‚ؤ‚µ‚ـ‚¤پBٹé‹ئ‚ھ—کڈپ‚ًچإ‘ه‰»‚·‚é‚و‚¤‚بپu‚؟‚ه‚¤‚ا‚و‚¢پvگ”‚جکJ“ژز‚ًŒظ‚ء‚ؤ‚¢‚é‚©‚ا‚¤‚©‚ًٹشگع“I‚ة’m‚邽‚ك‚ة‚حپAVMPL‚ئ’ہ‹à—¦‚ھ‚ا‚ê‚ظ‚اک¨—£‚µ‚ؤ‚¢‚é‚©‚ًŒv‘ھ‚·‚ê‚خ‚و‚¢پB–{چe‚إ‚حپA‚±‚جچ·‚ًپuƒMƒƒƒbƒvپiپپVMPLپ|’ہ‹à—¦پjپv‚ئ‚µ‚ؤگ„’肵‚½پB
کJ“ژsڈê‚ھٹ®‘S‹£‘ˆ‚جڈَ‘ش‚ة‚ ‚ء‚ؤŒظ—p’²گ®”ï—p‚ھ‘S‚‚©‚©‚ç‚ب‚¢‚ب‚ç‚خپAچإ’ل’ہ‹à‚جˆّ‚«ڈم‚°‚ھ‚ب‚³‚ê‚ؤپA’ہ‹àˆّ‚«ڈم‚°‚ھچs‚ي‚ꂽ‚ئ‚µ‚ؤ‚àپA•‰‚جƒMƒƒƒbƒv‚حٹg‘ه‚¹‚¸‚ةپAŒظ—p—ت‚ھŒ¸ڈ‚·‚邾‚¯‚ة‚ب‚é‚ئ—\‘z‚³‚ê‚éپBˆê•ûپAکJ“ژsڈê‚ھ”ƒ‚¢ژè“ئگè“I‚إ‚ ‚éڈêچ‡پAچإ’ل’ہ‹à‚جڈمڈ¸‚ة‚ئ‚à‚ب‚ء‚ؤگ³‚جƒMƒƒƒbƒv‚ھڈkڈ¬‚µپAŒظ—p—ت‚ح‘‰ء‚·‚éڈêچ‡‚ھ‚ ‚éپBچإ’ل’ہ‹à‚جڈمڈ¸‚ھƒMƒƒƒbƒv‚ئŒظ—p—ت‚ة‚ا‚ج‚و‚¤‚ب‰e‹؟‚ً—^‚¦‚é‚ج‚©‚ً“¯ژ‚ةŒ©‚邱‚ئ‚إپAکJ“ژsڈê‚ھ‹£‘ˆ“I‚ب‚ج‚©پA”ƒ‚¢ژè“ئگè“I‚ب‚ج‚©‚ً”»’f‚إ‚«‚éپB
•ھگح‚جŒ‹‰تپAچإ’ل’ہ‹à‚جˆّ‚«ڈم‚°‚حپA‚à‚ئ‚à‚ئŒظ—p‚ًŒ¸ڈ‚³‚¹‚ؤ‚¢‚½ٹé‹ئ‚ة‚¨‚¢‚ؤپAچ،ٹْ‚ج•‰‚ج’ہ‹àƒMƒƒƒbƒv‚ًٹg‘ه‚³‚¹پAŒظ—p—ت‚ًŒ¸ڈ‚³‚¹‚邱‚ئ‚ھژ¦‚³‚ꂽپB‚ـ‚½پA•‰‚جƒMƒƒƒbƒv‚جٹg‘ه‚ج‰e‹؟‚حپAŒظ—p—ت‚جچيŒ¸‚ئ‚¢‚¤Œ`‚إپA•”•ھ“I‚ة‚ح1ٹْ‚إ’²گ®‚³‚ê‚ؤ‚¢‚é‰آ”\گ«‚ھ‚ ‚èپAˆسٹO‚ة‚àŒظ—p’²گ®‘¬“x‚ھ‘¬‚¢پB‚آ‚ـ‚èپA–{Œ¤‹†‚ج•ھگحŒ‹‰ت‚ح”ƒ‚¢ژè“ئگ艼گà‚ئ‚حگ®چ‡“I‚إ‚ح‚ب‚پA‚ق‚µ‚ëکJ“ژsڈê‚ھٹ®‘S‹£‘ˆ‚إ‚ ‚é‚ئ‚¢‚¤ƒ‚ƒfƒ‹‚ئگ®چ‡“I‚إ‚ ‚éپB
چإ’ل’ہ‹à‚جˆّ‚«ڈم‚°‚حپAٹm‚©‚ةکJ“ژز‚ج’ہ‹à‚ًˆّ‚«ڈم‚°‚邱‚ئ‚ة‚ب‚é‚ھپA‚»‚ê‚حپAٹé‹ئ‚جکJ“”ï—p‚ً‘‰ء‚³‚¹‚éپB‚»‚µ‚ؤپA‚»‚جچ‚‚ـ‚ء‚½کJ“”ï—p‚ئکJ“‚جŒہٹEگ¶ژY•¨‰؟’l‚ًˆê’v‚³‚¹‚邽‚ك‚ةپAٹé‹ئ‚ھŒظ—p—ت‚ًŒ¸ڈ‚³‚¹‚éپB‚±‚ج‚و‚¤‚بپA‹³‰بڈ‘“I‚بچإ’ل’ہ‹à‚ج‰e‹؟‚ھ“ْ–{‚جکJ“ژsڈê‚إ‚حٹدژ@‚³‚ê‚ؤ‚¢‚邱‚ئ‚ً‘O’ٌ‚ةپAچإ’ل’ہ‹àگ§“x‚ً‰^—p‚µ‚ؤ‚¢‚•K—v‚ھ‚ ‚éپB
گ}پFٹé‹ئ‚ج—کڈپچإ‘ه‰»چs“®‚ئƒMƒƒƒbƒv
http://www.rieti.go.jp/jp/publications/nts/13j010.html
چإ’ل’ہ‹à‚ئژل”NŒظ—pپF2007”Nچإ’ل’ہ‹à–@‰üگ³‚ج‰e‹؟
ژ·•Mژز گىŒû ‘هژi (ƒtƒ@ƒJƒ‹ƒeƒBƒtƒFƒچپ[)
گX —Iژq (“ْ–{ٹwڈpگU‹»‰ï)
پuکJ“ژsڈêگ§“x‰üٹvپvƒvƒچƒWƒFƒNƒg
–â‘è”wŒi
•nچ¢–â‘è‚ض‚جٹضگS‚ھچ‚‚ـ‚é’†پA•nچ¢‰ًڈء‚ج—L—ح‚ب‘خچô‚ئ‚µ‚ؤ‹cک_‚³‚ê‚ؤ‚¢‚é‚ج‚ھچإ’ل’ہ‹à‚جˆّ‚«ڈم‚°‚إ‚ ‚éپBژہچغ‚ةپA2007”N7Œژ‚ة‚حگ¬’·—ح’êڈم‚°گي—ھگ„گi‰~‘ى‰ï‹c‚جچ‡ˆس‚ھ‚ب‚³‚êپA2008”N‚©‚çژ{چs‚³‚ꂽ‰üگ³چإ’ل’ہ‹à–@‚ھ’nˆو•تچإ’ل’ہ‹à‚جŒˆ’è‚ة‚ ‚½‚ء‚ؤگ¶ٹˆ•غŒى‚ئ‚جگ®چ‡گ«‚ة”z—¶‚ً‹پ‚ك‚½‚±‚ئ‚ًژَ‚¯‚ؤچإ’ل’ہ‹à‚حڈم‚ھ‚ء‚ؤ‚¢‚éپB‹ï‘ج“I‚ة‚حپA2005”N‚ة668‰~‚إ‚ ‚ء‚½•½‹دچإ’ل’ہ‹à‚ح2011”N‚ة‚ح737‰~‚ةڈمڈ¸‚µ‚½پBچإ’ل’ہ‹à‚جˆّ‚«ڈم‚°‚حپA’ل’ہ‹àکJ“ژز‚ج’ہ‹à‚ً‰ں‚µڈم‚°‚邱‚ئ‚إ•nچ¢‚ًٹةکa‚·‚éŒّ‰ت‚ھٹْ‘ز‚³‚ê‚é‚ھپAˆê•û‚إŒظ—p‚ًŒ¸ڈ‚³‚¹‚éŒّ‰ت‚ھŒœ”O‚³‚ê‚éپB“ء‚ةŒoŒ±‚ھگَ‚¢10‘مکJ“ژز‚ض‚جŒظ—pŒ¸ڈŒّ‰ت‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپA‰¢•ؤ‚ج‘½‚‚جژہڈط•ھگح‚إژw“E‚³‚ê‚ؤ‚¢‚éپB–{Œ¤‹†‚ح‚±‚ج‚و‚¤‚بڈَ‹µ‚ً”wŒi‚ئ‚µ‚ؤپA2007”Nˆبچ~‚جچإ’ل’ہ‹à‚ج‘ه•‚بˆّ‚«ڈم‚°‚ھپA16-19چخ’jڈ—‚ج’ہ‹à•ھ•z‚âŒظ—p—¦‚ض—^‚¦‚é‰e‹؟‚ًŒںڈط‚µ‚½پB
Œ‹‰ت‚ج—v–ٌ
–{Œ¤‹†‚جŒ‹‰ت‚حˆب‰؛‚جگ}‚ةڈW–ٌ‚³‚ê‚éپB‚±‚جگ}‚حپA‰،ژ²‚ة2007”N‚ئ2010”N‚جچإ’ل’ہ‹à‚جژ©‘R‘خگ”’l‚جچ·پAڈcژ²‚ة“¯ٹْٹش‚ج16-19چخ’jڈ—‚جڈA‹ئ—¦(%)‚جچ·‚ًژو‚ء‚½‚à‚ج‚إ‚ ‚éپB2007”N‚©‚çژ{چs‚³‚ꂽگVچإ’ل’ہ‹à–@‚إ‚حپAچإ’ل’ہ‹àٹz‚ًگف’è‚·‚é‚ة‚ ‚½‚ء‚ؤپAگ¶ٹˆ•غŒىگ…ڈ€‚ئ‚ج‹t“]Œ»ڈغ‚ج‰ًڈء‚ھ‹پ‚ك‚ç‚ê‚é‚و‚¤‚ة‚ب‚ء‚½پB‚±‚جگ¶ٹˆ•غŒىگ…ڈ€‚جŒvژZ‚ج‚ب‚©‚ة‚حڈZ‘î•}ڈ•‚ھٹـ‚ـ‚ê‚ؤ‚¨‚è’nˆوچ·‚ھ‘ه‚«‚¢ڈZ‘î”ï‚ھ”½‰f‚³‚ê‚ؤ‚¢‚éپB‚»‚ج‚½‚كڈZ‘î”ï‚ھچ‚‚¢“Œ‹‚âگ_“قگى‚ئ‚¢‚ء‚½’nˆو‚إ‚حپAچإ’ل’ہ‹à‚ئگ¶ٹˆ•غŒىٹîڈ€‚ج‹t“]•‚ھ‘ه‚«‚‚ب‚èپA‚»‚ج‰ًڈء‚ج‚½‚ك‚ةچإ’ل’ہ‹à‚ھ‘ه‚«‚ˆّ‚«ڈم‚°‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚éپB
‚±‚جگ}‚ًŒ©‚é‚ئ‘ه‚ـ‚©‚ة‰E‰؛‚ھ‚è‚جٹضŒW‚ً”F‚ك‚邱‚ئ‚ھ‚إ‚«‚邽‚كپAچإ’ل’ہ‹à‚جˆّ‚«ڈم‚°‚ھ‘ه‚«‚©‚ء‚½“s“¹•{Œ§‚ظ‚ا16-19چخ’jڈ—‚جڈA‹ئ—¦‚ھ—ژ‚؟چ‚ٌ‚¾‚±‚ئ‚ھٹm”F‚إ‚«‚éپB‚µ‚©‚µ‚ب‚ھ‚çپA2007”N‚©‚ç2010”N‚ئ‚¢‚¤ٹْٹش‚ح‹à—Zٹë‹@‚ج‰e‹؟‚إکJ“ژsڈê‚ھ‹ة’[‚ة—₦چ‚ٌ‚¾ژٹْ‚ً‚س‚‚ٌ‚إ‚¨‚èپA‚»‚ج‰e‹؟‚ة’nˆوچ·‚ھ‚ ‚ء‚½‰آ”\گ«‚à‚ ‚éپB‚»‚±‚إپAچإ’ل’ہ‹àˆّ‚«ڈم‚°‚ج‰e‹؟‚ھ’¼گع‹y‚خ‚ب‚¢‚à‚ج‚جپAکJ“ژsڈê‘S‘ج‚جڈَ‹µ‚ً”½‰f‚·‚é‚ئژv‚ي‚ê‚é30-59چخ’jگ«‚جژ¸‹ئ—¦‚ًŒi‹Cڈzٹآ‚جژw•W‚ئ‚µ‚ؤ—p‚¢‚ؤپA‚»‚ج‰e‹؟‚ً’²گ®‚µ‚½•ھگح‚ًچs‚ء‚½پBŒ‹‰ت‚ح’nˆو•تچإ’ل’ہ‹à‚ً10%ˆّ‚«ڈم‚°‚é‚ئپA16-19چخ’jڈ—‚جŒظ—p—¦‚حڈ‚ب‚‚ئ‚à5.3%ƒ|ƒCƒ“ƒg’ل‰؛‚·‚é‚ئ‚¢‚¤‚à‚ج‚إ‚ ‚ء‚½پB‚±‚ê‚ح•ھگحٹْٹش’†‚ج16-19چخ’jڈ—‚ج•½‹دڈA‹ئ—¦‚ھ17%‚إ‚ ‚邱‚ئ‚ًچl‚¦‚é‚ئ–ٌ30%‚جŒظ—p‚جŒ¸ڈ‚ًˆس–،‚·‚éپB
گچô“IƒCƒ“ƒvƒٹƒPپ[ƒVƒ‡ƒ“
چإ’ل’ہ‹à‚جˆّ‚«ڈم‚°‚حچàŒ¹‚ً•K—v‚ئ‚¹‚¸ژہچs‚إ‚«‚é•nچ¢‘خچô‚¾‚ھپA–{Œ¤‹†‚ة‚و‚ء‚ؤ10‘م’jڈ—‚جŒظ—p‹@‰ï‚ً’D‚ء‚ؤ‚µ‚ـ‚¤‚ئ‚¢‚¤ƒRƒXƒg‚ً”؛‚¤‚±‚ئ‚ھژ¦‚³‚ꂽپBŒظ—pکJ“ژز‘S‘ج‚ةگè‚ك‚é10‘مکJ“ژز‚جٹ„چ‡‚حچ‚‚‚ب‚¢‚½‚كپAƒ}ƒCƒiپ[‚ب–â‘è‚إ‚ ‚é‚و‚¤‚بˆَڈغ‚ً—^‚¦‚é‚©‚à‚µ‚ê‚ب‚¢پB‚µ‚©‚µ‚ب‚ھ‚çپA10‘مکJ“ژزپA“ء‚ة’†ٹw‚âچ‚چZ‚ً‘²‹ئ‚µ‚ؤڈA‹ئ‚µژn‚ك‚½‚خ‚©‚è‚جکJ“ژز‚ة‚ئ‚ء‚ؤڈA‹ئ‹@‰ï‚ً“¾‚邱‚ئ‚حگE‹ئŒP—û‚ج‹@‰ï‚ً“¾‚邱‚ئ‚إ‚à‚ ‚èپAگ¶ٹU‚ة‚ي‚½‚ء‚ؤŒظ—p‹@‰ï‚â’ہ‹àگ…ڈ€‚ة‰i‘±“I‚ب‰e‹؟‚ً—^‚¦‚é‰آ”\گ«‚ھ‚ ‚éڈd—v‚ب–â‘è‚إ‚ ‚éپB‚±‚ج‚و‚¤‚ةچإ’ل’ہ‹àگ§“xˆّ‚«ڈم‚°‚ة‚و‚é•nچ¢‘خچô‚ح•›چى—p‚ھ‘ه‚«‚¢‚ج‚إپAچإ’ل’ہ‹à‚ة‘م‚ي‚é‘خ•nچ¢چô‚ج“±“ü‚ًŒں“¢‚·‚ׂ«‚إ‚ ‚éپB‚½‚ئ‚¦‚خپA•nچ¢گ¢‘ر‚جکJ“ژز‚ة‘خ‚µ‚ؤ‚جژہژ؟“I’ہ‹à•âڈ•‚ًچs‚¤گ§“x‚ئ‚µ‚ؤ‹‹•t•tگإٹzچTڈœ‚ھ‚ ‚èپA•ؤچ‘‚â‰pچ‘‚إ‚ح‚·‚إ‚ةˆê’è‚جگ¬‰ت‚ًڈم‚°‚ؤ‚¢‚éپB‚±‚جگ§“x‚ح’Pڈƒ‚ةŒ¾‚¤‚ئچ‘–¯‚جگإ•‰’S‚إ•nچ¢گ¢‘رکJ“ژز‚ج’ہ‹à‚ً•âڈ•‚·‚éژd‘g‚ف‚إ‚ ‚èپA’ہ‹à•âڈ•‚إ‚ ‚邽‚كگ¶ٹˆ•غŒى‚ج‚و‚¤‚ةژَ‹‹ژز‚ج‹خکJˆس—~‚ً‚»‚®‚ئ‚¢‚¤•›چى—p‚ھڈ¬‚³‚¢پB“ْ–{‚إ“±“ü‚µ‚و‚¤‚ئ‚·‚ê‚خپAچàŒ¹‚جٹm•غپA”[گإژز”شچ†گ§“x‚ج“±“üپAگ¢‘رƒxپ[ƒX‚إ‚ج‰غگإپE‹‹•t‚ةŒü‚¯‚ؤ‚جگإ‰üٹv‚ئ‚¢‚ء‚½گ”پX‚ج“ï–â‚ًƒNƒٹƒA‚µ‚ؤ‚¢‚©‚ب‚¯‚ê‚خ‚ب‚ç‚ب‚¢پB‚³‚ç‚ة’ہ‹à•âڈ•‚ھ’ل‹Z”\کJ“ژز‚جکJ“‹ں‹‹‚ً‘£گi‚µ’ہ‹à‚ً‰؛—ژ‚³‚¹Œظ—pژه‚ةگچôŒّ‰ت‚ھ‹A’…‚·‚é‰آ”\گ«‚ة‚à–ع‚ًŒü‚¯‚ب‚¢‚ئ‚¢‚¯‚ب‚¢پB‚³‚ـ‚´‚ـ‚بچ¢“ï‚ح”؛‚¤‚ھ•nچ¢–â‘è‚ًگ^Œ•‚ة‰ًŒˆ‚µ‚و‚¤‚ئ‚·‚é‚ج‚إ‚ ‚ê‚خ‹‹•t•tگإٹzچTڈœ‚ج“±“ü‚ًŒں“¢‚·‚ׂ«‚إ‚ ‚éپB
گ}پFچإ’ل’ہ‹à‚جڈمڈ¸‚ئڈA‹ئ—¦‚ج•د‰»پA16-19چخ’jڈ—
’چپF–{•¶’†‚جگ}3‚ةٹY“–پB
http://www.rieti.go.jp/jp/publications/nts/13j009.html
چإ’ل’ہ‹à‚جکJ“ژsڈêپEŒoچد‚ض‚ج‰e‹؟پ]ڈ”ٹOچ‘‚جŒ¤‹†‚©‚瓾‚ç‚ê‚é’¹لصگ}“I‚بژ‹“_پ]
ژ·•Mژز ’ك Œُ‘¾کY (ƒtƒ@ƒJƒ‹ƒeƒBƒtƒFƒچپ[)Œ¤‹†ƒvƒچƒWƒFƒNƒg کJ“ژsڈêگ§“x‰üٹvƒ_ƒEƒ“ƒچپ[ƒhپ^
ٹضکAƒٹƒ“ƒN ƒfƒBƒXƒJƒbƒVƒ‡ƒ“پEƒyپ[ƒpپ[:13-J-008 [PDF:688KB]پB
پuکJ“ژsڈêگ§“x‰üٹvپvƒvƒچƒWƒFƒNƒg
چإ’ل’ہ‹àگچô‚جگ¥”ٌ‚ًڈ„‚ء‚ؤڈd—v‚ب”»’fٹîڈ€‚ئ‚ب‚éŒظ—p‚ض‚ج‰e‹؟‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپA“ْ–{‚إ‚àژہڈط•ھگح‚ج’~گد‚ھگi‚ٌ‚إ‚¨‚èپA‘ه‹K–ح‚بƒ~ƒNƒچپEƒpƒlƒ‹ƒfپ[ƒ^‚ًژg‚¢پA‚و‚èچإ’ل’ہ‹à•د“®‚ج‰e‹؟‚ًژَ‚¯‚â‚·‚¢کJ“ژز‚ضچi‚ء‚½•ھگح‚حپA‚ظ‚عŒظ—p‚ض•‰‚جŒّ‰ت‚ًŒ©ڈo‚µ‚ؤ‚¢‚éپBˆê•ûپAƒAƒپƒٹƒJ‚إ‚جچإ‹ك‚جŒ¤‹†‚ً‚ف‚é‚ئپAگV‚½‚بƒfپ[ƒ^‚âژè–@‚ًژg‚¢پAگ³•‰‚ج‰e‹؟‚ًڈ„‚ء‚ؤک_‘ˆ‚ھ‘±‚¢‚ؤ‚¢‚éپB
‚µ‚©‚µپA’P‚ةŒظ—p‚ض‚ج•‰‚جŒّ‰ت‚ج—L–³‚ج‚ف‚ًڈ„‚ء‚ؤک_‘ˆ‚ً‘±‚¯‚邱‚ئ‚ح•s–ر‚إ‚ ‚낤پB‚ب‚؛‚ب‚ç‚خپA‘و1‚ةپAٹ®‘S‹£‘ˆ‚ً‰¼’肵‚½‚ئ‚µ‚ؤ‚àچإ’ل’ہ‹à‚جڈمڈ¸‚إ‚³‚ـ‚´‚ـ‚بƒŒƒxƒ‹‚إ‘م‘ضŒّ‰ت‚ھ‹N‚«پAپuڈںژزپv‚ئپu”sژزپv‚ھگ¶‚ـ‚ê‚邽‚ك‚إ‚ ‚éپBچإ’ل’ہ‹àڈمڈ¸‚حچإ‚àƒXƒLƒ‹‚ج’ل‚¢کJ“ژز‚ض‚جژù—v‚ًŒ¸ڈ‚³‚¹‚é‘م‚ي‚èپA‚و‚èƒXƒLƒ‹‚جچ‚‚¢کJ“ژز‚ج’ہ‹à‚ح‘ٹ‘خ“I‚ةٹ„ˆہ‚ة‚ب‚邽‚كپA”ق‚ç‚جژù—v‚ح‘‰ء‚·‚é‚ئچl‚¦‚ç‚ê‚éپB‚ـ‚½پAکJ“ƒRƒXƒg‚جٹ„چ‡پA’†‚إ‚àپAچإ’ل’ہ‹àکJ“ژز‚جٹ„چ‡‚جچ‚‚¢ٹé‹ئپiژه‚ة’†ڈ¬ٹé‹ئپjپEژY‹ئ‚ح‘ٹ‘خ“I‚ة•s—ک‚ة‚ب‚éˆê•ûپAƒXƒLƒ‹‚جچ‚‚¢کJ“ژز‚ً‚و‚葽‚Œظ‚¢پAƒXƒLƒ‹‚ج’ل‚¢کJ“ژز‚àچإ’ل’ہ‹à‚و‚è‚àچ‚‚¢’ہ‹à‚إŒظ‚ء‚ؤ‚¢‚é‰آ”\گ«‚جچ‚‚¢‘هٹé‹ئپEژY‹ئ‚ب‚ا‚ح‘ٹ‘خ“I‚ة—L—ک‚ة‚ب‚èپAŒظ—p‚ً‘‚â‚·‰آ”\گ«‚à‚ ‚é‚ج‚¾پB
‘و2‚حپAچإ’ل’ہ‹à‚ج‰e‹؟‚ًچl‚¦‚éڈêچ‡پAŒظ—p‚ض‚ج‰e‹؟‚ج‚ف‚ب‚炸پAڈٹ“¾چؤ•ھ”zپAٹé‹ئ‚جژû‰v‚â‰؟ٹiپA’·ٹْ“I‚ة‚حگl“Iژ‘–{‚ض‚ج‰e‹؟‚ـ‚إچl‚¦‚é•K—v‚ھ‚ ‚é‚©‚ç‚إ‚ ‚éپBŒظ—p‚ض‚ج‰e‹؟‚ھ‚ف‚ç‚ê‚ب‚¢ڈêچ‡‚إ‚àپAچإ’ل’ہ‹àڈمڈ¸‚ج•‰’S‚حپAکJ“ژز‚جگ¶ژYگ«‚ھڈم‚ھ‚ç‚ب‚¢Œہ‚èپAکJ“ژز‚جکJ“ژٹش‚ھŒ¸ڈ‚·‚é‚©پAٹé‹ئ‚جژû‰v‚ھˆ«‰»‚·‚é‚©پAٹé‹ئ‚ھ•‰’S‚ً‰؟ٹi‚ة“]‰إ‚إ‚«‚ê‚خپA‚»‚ê‚ًڈء”ïژز‚ھ•‰’S‚·‚邱‚ئ‚ة‚ب‚éپB‚آ‚ـ‚èپAچإ’ل’ہ‹àڈمڈ¸‚ح‚»‚ج•‰’S‚ً’N‚©‚ھ’S‚¤‚ي‚¯‚إ‚ ‚èپAŒˆ‚µ‚ؤپuƒtƒٹپ[ƒ‰ƒ“ƒ`پvپi‚½‚¾‚ج’‹”رپj‚إ‚ح‚ب‚¢پB
“ْ–{‚جچإ’ل’ہ‹àگچô‚ض‚جƒCƒ“ƒvƒٹƒPپ[ƒVƒ‡ƒ“‚حˆب‰؛‚ج’ت‚è‚إ‚ ‚éپB‚ـ‚¸پA‘و1‚حپAچإ’ل’ہ‹àڈمڈ¸‚ة“ء‚ة‰e‹؟‚جژَ‚¯‚â‚·‚¢‘w‚ض‚ج”z—¶‚إ‚ ‚éپB“ْ–{‚ج•ھگح‚إ‚à10‘مژل”N‚ھŒظ—p‚ض‚جˆ«‰e‹؟‚ًژَ‚¯‚â‚·‚¢‚±‚ئ‚ھ–¾‚ç‚©‚ة‚ب‚ء‚½‚ھپAƒˆپ[ƒچƒbƒpڈ”چ‘‚ج‚و‚¤‚ةپAژل”N‚à”N—îٹK‘w‚ة•ھ‚¯‚ؤˆظ‚ب‚éچإ’ل’ہ‹à‚ً“K—p‚·‚éپi‚و‚èژل”N‚جچإ’ل’ہ‹à‚جگ…ڈ€‚ً’ل‚‚·‚éپj‚±‚ئ‚àŒں“¢‚ة’l‚µ‚و‚¤پB“ْ–{‚جڈêچ‡پAOECDڈ”چ‘‚جچإ’ل’ہ‹àپE’†ˆتڈٹ“¾”ن—¦‚ھچ‘چغ“I‚ة‚©‚ب‚è’ل‚¢‚±‚ئ‚ًچھ‹’‚ة‘ه•‚بˆّ‚«ڈم‚°‚ج•K—vگ«‚ً‘i‚¦‚é‹cک_‚ھ‚ ‚é‚ھپAچإ’ل’ہ‹à‚جگ…ڈ€‚ًچw”ƒ—ح•½‰؟‚إ•]‰؟‚µ‚½ژہژ؟’ہ‹à‚إ‚ف‚é‚ئپAOECDڈ”چ‘‚ج’†‚إ‚ح’†’ِ“x‚إ‚ ‚èپiگ}پjپAگTڈd‚ب‹cک_‚ھ•K—v‚¾پB‘و2‚حپAچإ’ل’ہ‹à‚ًˆّ‚«ڈم‚°‚éڈêچ‡‚إ‚àپA‚ب‚é‚ׂٹة‚â‚©‚بˆّڈم‚°‚ةژ~‚ك‚é‚ׂ«‚إ‚ ‚邱‚ئ‚¾پB‘و3‚حپAŒظ—p‚ض‚ج‰e‹؟‚خ‚©‚è‚إ‚ح‚ب‚پAٹé‹ئ‚ض‚جƒ}ƒCƒiƒX‚ج‰e‹؟‚ًڈ\•ھ”Fژ¯‚·‚邱‚ئ‚إ‚ ‚éپB‘و4‚حپAچإ’ل’ہ‹àگ§“x‚ض‚جˆث‘¶‚حکJژgٹضŒW‚ج‹@”\•s‘S‚جڈغ’¥‚ئچl‚¦‚é‚ئپA’ل’ہ‹àکJ“ژز‚ج‘ز‹ِ‰ü‘P‚ًکJژgٹضŒW‚ج’†‚إ‚¢‚©‚ةژہŒ»‚³‚¹‚ؤ‚¢‚‚©‚ئ‚¢‚¤•ûŒü‚ج“w—ح‚àڈd—v‚إ‚ ‚邱‚ئ‚¾پB‘و5‚حپAچإ’ل’ہ‹àگچô‚àپuƒGƒrƒfƒ“ƒX‚ةٹî‚أ‚¢‚½گچôپv‚ض‚ج“]ٹ·‚ھ‹پ‚ك‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚邱‚ئ‚¾پBƒCƒMƒٹƒX‚إ‚حپAگV‚µ‚¢‘Sچ‘چإ’ل’ہ‹àگ§“x‚ج“±“ü‚ئ‚ئ‚à‚ةچإ’ل’ہ‹àگچô‚ج’ٌˆؤ‚ًچs‚¤’ل’ہ‹àˆدˆُ‰ï‚ً”‘«‚³‚¹پA’²چ¸پE•ھگح‹@”\‚ً‘ه•‚ة‹‰»‚µ‚½پBŒًڈآ‚جŒ»ڈê‚إ‚ ‚èŒِ‰vˆدˆُ‚ھکJژg‚ج’²گ®–ً‚ً‰ت‚½‚µ‚ؤ‚¢‚é“ْ–{‚ج’†‰›چإ’ل’ہ‹àگR‹c‰ï‚ة‚¨‚¢‚ؤ‚àپA‚±‚¤‚µ‚½ٹد“_‚©‚ç‚ج‘gگDŒ©’¼‚µ‚ھ•K—v‚إ‚ ‚낤پB
گ}پFژہژ؟چإ’ل’ہ‹àپiژٹش“–‚½‚èپAچw”ƒ—ح•½‰؟USƒhƒ‹•\ژ¦پj‚جچ‘چغ”نٹrپi2010”NپAOECDپj
http://www.rieti.go.jp/jp/publications/nts/13j008.html
”ٌگ³‹KکJ“ژز‚جŒظ—p“]ٹ·پ|گ³ژذˆُ‰»‚ئژ¸‹ئ‰»
ژ·•Mژز ‹v•ؤ Œ÷ˆê (–¼Œأ‰®ڈ¤‰ب‘هٹw)
’ك Œُ‘¾کY (ƒtƒ@ƒJƒ‹ƒeƒBƒtƒFƒچپ[)Œ¤‹†ƒvƒچƒWƒFƒNƒg کJ“ژsڈêگ§“x‰üٹvƒ_ƒEƒ“ƒچپ[ƒhپ^
ٹضکAƒٹƒ“ƒN ƒfƒBƒXƒJƒbƒVƒ‡ƒ“پEƒyپ[ƒpپ[:13-J-005 [PDF:868KB]پB
پuکJ“ژsڈêگ§“x‰üٹvپvƒvƒچƒWƒFƒNƒg
–â‘è‚ج”wŒi
”ٌگ³‹KŒظ—p‚ة‘خ‚µ‚ؤ‚حپA–³‹ئژزپEژ¸‹ئژز‚ًŒظ—p‚ة‚آ‚ب‚¬پA‚³‚ç‚ةگ³ژذˆُ‚ض“]ٹ·‚·‚éƒXƒeƒbƒv‚ئ‚µ‚ؤ‚ج–ًٹ„‚ھٹْ‘ز‚³‚ê‚ؤ‚¢‚é‚ھپA”ٌگ³‹KŒظ—p‚©‚瑼‚جŒظ—pŒ`‘ش‚ض‚ج“]ٹ·‚جژہ‘ش‚ح‚ا‚ج‚و‚¤‚إ‚ ‚낤‚©پB–{Œ¤‹†‚إ‚حپA2009”N1Œژ‚©‚ç6ƒJŒژ–ˆ‚ةŒv5‰ٌ‚ة‚ي‚½‚ء‚ؤپi“ئپjŒoچدژY‹ئŒ¤‹†ڈٹ‚ھژہژ{‚µ‚½پw”hŒکJ“ژز‚جگ¶ٹˆ‚ئ‹پگEچs“®‚ةٹض‚·‚éƒAƒ“ƒPپ[ƒg’²چ¸پx‚جŒ‹‰ت‚ً—p‚¢‚ؤپA”ٌگ³‹KŒظ—p‚©‚çگ³ژذˆُ‚ ‚é‚¢‚حژ¸‹ئ‚ة“]‚¶‚éڈêچ‡‚جŒˆ’è—vˆِ‚ة‚آ‚¢‚ؤژہڈط“I‚ة•ھگح‚µ‚½پB‹ï‘ج“I‚ة‚حپA”ٌگ³‹KŒظ—p‚جŒظ—pŒ`‘ش‚جڈعچׂبڈî•ٌ‚ً—p‚¢‚ؤپAŒظ—pŒ`‘ش‚جˆل‚¢‚ھگ³ژذˆُ‰»‚ة—^‚¦‚é‰e‹؟‚ج”cˆ¬‚ة“w‚ك‚½پB‚ـ‚½پA”ٌگ³‹KŒظ—p‚©‚çگ³ژذˆُ‚ـ‚½‚حژ¸‹ئ‚ض‚ج“]ٹ·‚ً”نٹr‰آ”\‚ب”حˆح“à‚إ•ھگح‚µ‚½پB‚³‚ç‚ةپAپiگl‚ر‚ئ‚ھ“‚¢‚ؤ‚à‚و‚¢‚ئچl‚¦‚é’ہ‹à‚إ‚ ‚éپj—¯•غ’ہ‹à‚ًژو‚èڈم‚°‚ؤپA•Wڈ€“I‚بƒWƒ‡ƒuƒTپ[ƒ`—ک_‚ھژ¦چ´‚·‚é—¯•غ’ہ‹à‚ج‘ه‚«‚³‚ھگ³ژذˆُ‚ض‚ج“]ٹ·‚âژ¸‹ئ‚ة—^‚¦‚é‰e‹؟‚ج—L–³‚ًٹm”F‚µ‚½پB
•ھگح‚جŒ‹‰ت
‘OگE‚جŒظ—pŒ`‘ش‚ئگ³ژذˆُ‰»پEژ¸‹ئ‰»‚جٹضŒW‚حپAگ}1‚ج’ت‚è‚إ‚ ‚ء‚½پBگ³ژذˆُ‰»‚µ‚½گl‚ج‘OگE‚حپAگ»‘¢‹ئ”hŒ‚âŒ_–ٌژذˆُپAژ¸‹ئ‚جٹ„چ‡‚ھچ‚‚پAژ¸‹ئ‰»‚µ‚½گl‚ج‘OگE‚حپAژ¸‹ئپAگ»‘¢‹ئ”hŒ‚ھ‘½‚©‚ء‚½پB‚±‚¤‚µ‚½ŒXŒü‚ً”cˆ¬‚µ‚½ڈم‚إپA‰ٌ‹A•ھگح‚ًچs‚ء‚½پB
گ}1پF‘OگE‚جŒظ—pŒ`‘ش‚ئگ³ژذˆُ‰»پEژ¸‹ئ‰»پi%پj
گ„ŒvŒ‹‰ت‚ً‚ـ‚ئ‚ك‚é‚ئ•\1‚ج’ت‚è‚إ‚ ‚éپB‘OگE‚ھŒ_–ٌژذˆُپA‘²‹ئ’¼Œم‚ةگ³ژذˆُپA‘OگE‚جکJ“ژٹش‚ھ’·‚¢پAٹé‹ئ‹K–ح‚ھڈ¬‚³‚¢پAگl“Iƒlƒbƒgƒڈپ[ƒN‚âƒCƒ“ƒ^پ[ƒlƒbƒg‚ً‹پگEژè’i‚ئ‚µ‚ؤٹˆ—p‚·‚é“™‚ج—vˆِ‚ھ”ٌگ³‹KŒظ—p‚©‚çگ³ژذˆُ‚ض‚ج“]ٹ·ٹm—¦‚ًچ‚‚ك‚ؤ‚¢‚½پB‚»‚جˆê•ûپA‘OگE‚جŒظ—pŒ`‘شپA‹ئژيپAکJ“ژٹش“™‚جڈA‹ئڈَ‘ش‚ح”ٌگ³‹KŒظ—p‚©‚çژ¸‹ئ‚ض‚ج“]ٹ·‚ة‰e‹؟‚µ‚ؤ‚¢‚ب‚©‚ء‚½پBŒظ—pŒ`‘ش•ت‚ة‚ف‚é‚ئپA‘¼‚جŒظ—pŒ`‘ش‚ئ”نٹr‚µ‚ؤپAژ¸‹ئژز‚©‚çگ³ژذˆُ‚ض‚ج“]ٹ·‚ھ‹N‚±‚è‚â‚·‚¢‚à‚ج‚جپAگ³ژذˆُ‚جگE‚ة‚±‚¾‚ي‚é‚ظ‚اژ¸‹ئٹْٹش‚ھ’·ٹْ‰»‚µ‚ؤ‚¢‚½پB
•\1پFگ„ŒvŒ‹‰ت‚ج‚ـ‚ئ‚ك
—¯•غ’ہ‹à‚ھچ‚‚¢‚ظ‚اگ³ژذˆُ‚ة‚ب‚è‚â‚·‚پA—¯•غ’ہ‹à‚ھ’ل‚‚ؤ‚àژ¸‹ئ‚ةٹׂé“_‚حپAƒWƒ‡ƒuƒTپ[ƒ`—ک_‚ج—\‘z‚ة”½‚µ‚ؤ‚¢‚½پBژ¸‹ئٹْٹش‚ً—ک—p‚·‚邱‚ئ‚ة‚و‚ء‚ؤƒWƒ‡ƒuƒ}ƒbƒ`ƒ“ƒO‚ًچ‚‚ك‚éˆê•û‚إپAگ³ژذˆُ‚جگE‚ض‚ج‚±‚¾‚ي‚è‚©‚ç‚‚éژ¸‹ئ‚ج’·ٹْ‰»‚حگl“Iژ‘–{‚ًŒ¸–ص‚³‚¹‚邱‚ئ‚©‚çپAژ¸‹ئ‚ًŒo‚邱‚ئ‚ب‚”ٌگ³‹KŒظ—p‚©‚çگ³ژذˆُ‚ض“]ٹ·‚إ‚«‚é‚و‚¤‚بƒIƒ“پEƒUپEƒWƒ‡ƒuپEƒTپ[ƒ`پiژdژ–‚ً‘±‚¯‚ب‚ھ‚çگE’T‚µ‚ًچs‚¤‚±‚ئپj‚جژx‰‡‚⑽—l‚بگ³ژذˆُگ§“x‚جگ®”ُ‚ھ–]‚ـ‚ê‚éپB
http://www.rieti.go.jp/jp/publications/nts/13j005.html
ƒmƒ“ƒeƒNƒjƒJƒ‹ƒTƒ}ƒٹپ[
ƒڈپ[ƒNƒ‰ƒCƒtƒoƒ‰ƒ“ƒX‚ة‘خ‚·‚é’ہ‹àƒvƒŒƒ~ƒAƒ€‚جŒںڈط
ژ·•Mژز چ•“c ڈثژq (‘پˆî“c‘هٹw)
ژR–{ ŒM (Œcœن‹`ڈm‘هٹw)
Œ¤‹†ƒvƒچƒWƒFƒNƒg کJ“ژsڈêگ§“x‰üٹvƒ_ƒEƒ“ƒچپ[ƒhپ^
ٹضکAƒٹƒ“ƒN ƒfƒBƒXƒJƒbƒVƒ‡ƒ“پEƒyپ[ƒpپ[:13-J-004 [PDF:590KB]پB
پuکJ“ژsڈêگ§“x‰üٹvپvƒvƒچƒWƒFƒNƒg
ٹT—v‚ئ–â‘èˆسژ¯
‚±‚ê‚ـ‚إپAٹé‹ئ‚ة‚¨‚¯‚éWLBژ{چô‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپA”ï—p‘خŒّ‰ت‚ھŒ©ڈo‚¹‚ê‚خٹé‹ئ‚حگد‹ة“I‚ةWLBژ{چô‚ً“±“ü‚·‚é‚ح‚¸‚إ‚ ‚é‚ئ‚جچl‚¦‚ج‚à‚ئپAWLBژ{چô‚ئٹé‹ئ‹ئگر‚جٹضŒWگ«‚ًŒںڈط‚·‚錤‹†‚ھ‘½‚‚ب‚³‚ê‚ؤ‚«‚½پB‚»‚ê‚ç‚جŒ¤‹†‚إ‚حپA•K‚¸‚µ‚àWLBژ{چô‚ھٹé‹ئ‹ئگر‚ً‰ü‘P‚·‚é‚ئ‚جƒRƒ“ƒZƒ“ƒTƒX‚ح“¾‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚ب‚¢پB‚½‚ئ‚¦‚خپAژR–{پEڈ¼‰Yپi2012پj‚إ‚حWLBژ{چô‚ج”ï—p‘خŒّ‰ت‚ھƒvƒ‰ƒX‚ة‚ب‚é‚ج‚حپA’†Œک‘هٹé‹ئ‚âگ»‘¢‹ئپAکJ“•غ‘ ‚ًچs‚¤ŒXŒü‚ج‹‚¢ٹé‹ئ‚ب‚ا‚إپA‚»‚êˆبٹO‚جٹé‹ئ‚إ‚حWLBژ{چô‚حٹé‹ئ‹ئگر‚ئٹضŒW‚ھ‚ب‚©‚ء‚½‚èپA‚ق‚µ‚ëٹé‹ئ‹ئگر‚ًˆ«‰»‚³‚¹‚é‰آ”\گ«‚à‚ ‚ء‚½‚è‚·‚邱‚ئ‚ھژw“E‚³‚ê‚ؤ‚¢‚éپB‚µ‚©‚µپAWLBژ{چô‚ج”ï—p‘خŒّ‰ت‚ھ‚ب‚¢ڈêچ‡‚إ‚àپAڈ_“î‚ب“‚«•û‚ئˆّ‚«ٹ·‚¦‚ةپAکJ“ژز‚ھ’ہ‰؛‚°‚ً‹–—e‚·‚邱‚ئ‚ً’ت‚¶‚ؤƒRƒXƒg‚ً•‰’S‚·‚é‚ئ‚¢‚¤•âڈ’ہ‹à‰¼گà‚جچl‚¦•û‚ھگ¬—§‚·‚é‚ب‚ç‚خپAژ{چô“±“ü‚ھگi‚ق‰آ”\گ«‚ھ‚ ‚éپB‚»‚¤‚ب‚ê‚خپAŒ»چف‚ج‚و‚¤‚ةپuŒظ—p‚ح•غڈط‚³‚ê‚ؤ‚¢‚é‚ھ’·ژٹشکJ“‚جگ³ژذˆُپv‚ئپuŒظ—p‚ح•sˆہ’肾‚ھکJ“ژٹش‚ح’Z‚ڈ_“î‚ب”ٌگ³‹Kژذˆُپv‚ئ‚¢‚¤“ٌ‹ة‰»‚µ‚½“‚«•û‚ج‚ظ‚©‚ةپA•ت‚ج“‚«•û‚ھ•پ‹y‚·‚éژ…Œû‚ًŒ©ڈo‚¹‚é‚©‚à‚µ‚ê‚ب‚¢پB‚»‚±‚إپA–{چe‚إ‚حپA”ï—p‘خŒّ‰ت‚جٹد“_‚©‚çٹé‹ئ‚جWLBژ{چô‚ًŒں“¢‚·‚éڈ]—ˆ‚جŒ¤‹†‚ئ‚حˆêگü‚ً‰و‚µپAWLBژ{چô‚جژَ‰vژز‚إ‚ ‚éکJ“ژز‚ھ‚»‚ج”ï—p‚ً•‰’S‚·‚éŒ`‚إWLBژ{چô‚ھ•پ‹y‚·‚é‰آ”\گ«‚ًŒ©‹ة‚ك‚邱‚ئ‚ًژه‚½‚é–ع“I‚ئ‚·‚éپB
–{چe‚إ‚حپA2‚آ‚جٹé‹ئپEڈ]‹ئˆُƒ}ƒbƒ`ƒfپ[ƒ^‚ً—p‚¢‚ؤپAWLBژ{چô‚ئ’ہ‹à‚ئ‚جٹش‚ة•âڈ’ہ‹à‰¼گà‚ھگ¬—§‚·‚é‚©‚ًŒںڈط‚µپAWLBژ{چô‚ةٹض‚·‚镉‚ج’ہ‹àƒvƒŒƒ~ƒAƒ€‚جŒv‘ھ‚ًژژ‚ف‚éپB‚·‚ب‚ي‚؟پAWLBژ{چô‚ئ’ہ‹à‚ئ‚جٹش‚ة•âڈ’ہ‹à‰¼گà‚ھگ¬—§‚µ‚ؤ‚¢‚é‚©‚ًٹé‹ئپEکJ“ژز‚جƒ}ƒbƒ`ƒfپ[ƒ^‚ً—p‚¢‚ؤŒںڈط‚µپAگ¬—§‚µ‚ؤ‚¢‚éڈêچ‡پA’ہ‹àƒvƒŒƒ~ƒAƒ€‚ًŒv‘ھ‚·‚邱‚ئ‚ة‚و‚ء‚ؤپAکJ“ژز‚âٹé‹ئ‚ھWLBژ{چô‚ج“±“ü‚ة‘خ‚µ‚ؤ‚ا‚ج’ِ“x‚ـ‚إ‚ج’ل‚¢’ہ‹àگف’è‚ھ‘أ“–‚ئچl‚¦‚ؤ‚¢‚é‚©پA‚ئ‚¢‚¤گ”’l‚ً“±ڈo‚·‚éپB
•ھگح‚ة‚¨‚¢‚ؤ‚حپAٹدژ@‚³‚ꂽƒfپ[ƒ^‚ئ‰¼‘zژ؟–âŒ`ژ®‚جƒfپ[ƒ^‚ج2‚آ‚جƒ^ƒCƒv‚جٹé‹ئپEڈ]‹ئˆُ‚جƒ}ƒbƒ`ƒfپ[ƒ^‚ً—ک—p‚µپA“`““IƒAƒvƒچپ[ƒ`‚ئچs“®Œoچدٹw“IƒAƒvƒچپ[ƒ`‚ج‘o•û‚ً—p‚¢‚éپB•ھگحڈم‚ج“ء’¥“_‚ئ‚µ‚ؤ‚حپAڈ]‹ئˆُƒfپ[ƒ^‚¾‚¯‚إ‚ح•â‘¨‚ھ•s‰آ”\‚بٹé‹ئ‘¤‚جڈî•ٌ‚ً–L•x‚ة—ک—p‚µ‚ؤ‚¢‚é“_پA‹خ–±گوٹé‹ئ‚ةWLBژ{چô‚ھ‚ ‚é‚©”غ‚©‚إ‚ح‚ب‚پAژ{چô‚ً‚»‚جڈ]‹ئˆُ‚ھ—ک—p‚µ‚ؤ‚¢‚é‚©پi‚ ‚é‚¢‚ح—ک—p‚µ‚½ŒoŒ±‚ھ‚ ‚é‚©پj‚ئ‚¢‚¤ڈî•ٌ‚ً—p‚¢‚ؤ‚¢‚é“_پAƒzƒڈƒCƒg—حƒ‰پ[گ³ژذˆُ‚ة‘خڈغ‚ًŒہ’肵‚ؤ‚¢‚é“_پA‰¼‘zژ؟–â‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپAڈ]‹ئˆُ‚¾‚¯‚إ‚ح‚ب‚‹خ–±گوٹé‹ئ‚ة‚à“¯‚¶ژ؟–â‚ًچs‚¢پA’ہ‹àƒvƒŒƒ~ƒAƒ€‚ةٹض‚·‚éکJژgٹش‚ج”Fژ¯‚جƒMƒƒƒbƒv‚ًŒںڈط‚µ‚ؤ‚¢‚é“_‚ب‚ا‚ھ‹“‚°‚ç‚ê‚éپB
•ھگح“à—e‚ئٹـˆس
–{چe‚ج•ھگح‚إ“¾‚ç‚ꂽŒ‹‰ت‚ً—v–ٌ‚·‚é‚ئپA‚ـ‚¸پAٹدژ@‚³‚ê‚éƒfپ[ƒ^‚ً—p‚¢‚½“`““IƒAƒvƒچپ[ƒ`‚ة‚و‚éگ„Œv‚إ‚حپAƒtƒŒƒbƒNƒXƒ^ƒCƒ€گ§“x‚ً—ک—p‚µ‚ؤ‚¢‚é’jگ«ڈ]‹ئˆُ‚ة‚آ‚¢‚ؤپA•âڈ’ہ‹à‰¼گà‚ھگ¬—§‚µ‚ؤ‚¢‚邱‚ئ‚ھ”F‚ك‚ç‚ꂽپB‚ـ‚½پAƒtƒŒƒbƒNƒXƒ^ƒCƒ€گ§“x‚ً—ک—p‚·‚邱‚ئ‚ة‚و‚镽‹د“I‚ب•‰‚ج’ہ‹àƒvƒŒƒ~ƒAƒ€‚حپAچإ‘ه‚إ9%‚ئ’ِ“x‚ئ‚ب‚邱‚ئ‚à‚ي‚©‚ء‚½پB‚±‚¤‚µ‚½Œ‹‰ت‚حپAƒtƒŒƒbƒNƒXƒ^ƒCƒ€گ§“x“±“üٹé‹ئ‚حپA”ٌ“±“üٹé‹ئ‚ة”ن‚ׂؤ1ٹ„ژم’ِ“x’ل‚¢’ہ‹à‚إ’jگ«کJ“ژز‚ًŒظ‚¦‚ؤ‚¢‚邱‚ئ‚ًژ¦چ´‚µ‚ؤ‚¢‚éپB‚½‚¾‚µپAڈ—گ«‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپAƒtƒŒƒbƒNƒXƒ^ƒCƒ€گ§“x‚â—¼—§ژx‰‡گ§“x‚ةٹض‚·‚镉‚ج’ہ‹àƒvƒŒƒ~ƒAƒ€‚حŒںڈo‚³‚ê‚ب‚¢ƒPپ[ƒX‚ھ‘½‚©‚ء‚½پB“ْ–{‚إ•âڈ’ہ‹à‰¼گà‚ھگ¬—§‚µ‚ة‚‚¢”wŒi‚ة‚حپA‚و‚è—ا‚¢کJ“ڈًŒڈ‚ً‹پ‚ك‚ؤگlپX‚ھکJ“ˆع“®‚ًچs‚¤‚و‚¤‚ب—¬“®گ«‚جچ‚‚¢کJ“ژsڈê‚إ‚ح‚ب‚¢‚±‚ئ‚àٹضŒW‚µ‚ؤ‚¢‚é‰آ”\گ«‚ھ‚ ‚éپB
‚»‚±‚إژں‚ةپAپu‰¼‚ةژ{چô‚ھ“±“ü‚³‚ꂽ‚ب‚ç‚خ‚¢‚‚ç‚ج’ہ‰؛‚°‚ھ•K—v‚©پv‚ئ‚¢‚¤‰¼‘zژ؟–âƒfپ[ƒ^‚ً—ک—p‚µ‚ؤپAچs“®Œoچدٹw“I‚بƒAƒvƒچپ[ƒ`‚©‚çپAگِچف“I‚بکJژg‚جƒjپ[ƒY‚ً’T‚邱‚ئ‚ئ‚µ‚½پB•ھگح‚جŒ‹‰تپAگ}‚ة‚ ‚é‚و‚¤‚ةپAڈ]‹ئˆُ‘¤‚حپuژ{چô“±“ü‚ج‘م‚ي‚è‚ج’ہ‰؛‚°‚حژَ‚¯“ü‚ê‚ç‚ê‚ب‚¢پi0%‚ج’ہ‹àƒvƒŒƒ~ƒAƒ€پjپv‚ ‚é‚¢‚حپu10پ`20%’ِ“x‚ج’ہ‰؛‚°‚ب‚çژَ‚¯“ü‚ê‚éپv‚ئ‚·‚é‰ٌ“ڑ‚ھ‘½‚©‚ء‚½‚ج‚ة‘خ‚µ‚ؤپAٹé‹ئ‘¤‚حپu“±“ü‚حˆêگطچl‚¦‚ç‚ê‚ب‚¢پi-100%‚ج’ہ‹àƒvƒŒƒ~ƒAƒ€پjپv‚ئ‚¢‚¤‰ٌ“ڑ‚ھˆ³“|“I‘½گ”‚¾‚ء‚½‚±‚ئ‚ھ–¾‚ç‚©‚ة‚ب‚ء‚½پB“ْ–{‚إپAWLBژ{چô‚ھ•پ‹y‚µ‚ب‚¢”wŒi‚ة‚حپAڈ]‹ئˆُ‘¤‚حژ{چô‚ً“±“ü‚µ‚½‚ئ‚µ‚ؤ‚à’ہ‹à‚حˆّ‚«‰؛‚°‚ب‚‚ؤ‚و‚¢‚ئچl‚¦‚ؤ‚¢‚éگl‚ھ‘½‚¢‚ج‚ة‘خ‚µ‚ؤپAٹé‹ئ‘¤‚حژ{چô‚ج“±“ü‚ً‘½‘ه‚بƒRƒXƒg‚ئچl‚¦‚ؤ‚¢‚éگو‚ھ‘½‚¢‚ئ‚¢‚¤پA”Fژ¯‚ج‘ه‚«‚بƒMƒƒƒbƒv‚ھ‚ ‚邱‚ئ‚ھ‚¤‚©‚ھ‚¦‚éپBŒ»ژہ‚جƒfپ[ƒ^‚ً—ک—p‚µ‚½گ„ŒvŒ‹‰ت‚إپA•‰‚ج’ہ‹àƒvƒŒƒ~ƒAƒ€‚ھŒںڈo‚³‚ê‚ة‚‚©‚ء‚½‚ھپA‚»‚ج”wŒi‚ة‚حپA‚±‚¤‚µ‚½”Fژ¯‚جƒMƒƒƒbƒv‚ھ‘ه‚«‚·‚¬‚ؤپAژ{چô‚ً’ہ‹à‚ًˆّ‚«‰؛‚°‚邱‚ئ‚إ”ƒ‚¢ژو‚é‚ئ‚¢‚¤ژوˆّ‚ھ‚ي‚ھچ‘‚إ‚حگ¬—§‚µ‚ؤ‚¢‚ب‚¢Œ»ڈَ‚ھ‚ ‚é‚ئ‰ًژك‚·‚邱‚ئ‚ھ‚إ‚«‚éپB
‚à‚ء‚ئ‚àپAپuژ{چô‚ً“±“ü‚µ‚½‚ئ‚µ‚ؤ‚à’ہ‰؛‚°‚حچl‚¦‚ç‚ê‚ب‚¢پv‚ئ‚·‚éڈ]‹ئˆُ‚ئپAپuژ{چô“±“ü‚حˆêگطچl‚¦‚ç‚ê‚ب‚¢پv‚ئ‚·‚éٹé‹ئ‚ًƒTƒ“ƒvƒ‹‚©‚çڈœ‚¢‚½ڈêچ‡پAگ}‚ة‚ ‚é‚و‚¤‚ةپAƒtƒŒƒbƒNƒXƒ^ƒCƒ€گ§“x‚ب‚ا‚جڈ_“î‚ب“‚«•û‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚جڈ]‹ئˆُ‘¤‚ج•½‹د’ہ‹àƒvƒŒƒ~ƒAƒ€‚ح-25%’ِ“x‚إ‚ ‚èپAˆê•û‚إٹé‹ئ‘¤‚ج•½‹د’ہ‹àƒvƒŒƒ~ƒAƒ€‚ح-12%’ِ“x‚إ‚ ‚邱‚ئ‚à–¾‚ç‚©‚ة‚ب‚ء‚½پB‚آ‚ـ‚èپAٹé‹ئ‚حژ{چô“±“ü‚ة‚ح1ٹ„’ِ“x‚ج’ہ‰؛‚°‚ھ•K—v‚ئچl‚¦‚ؤ‚¢‚é‚ھپAکJ“ژز‚ح•½‹د‚إ2ٹ„ˆبڈم‚ًˆّ‚«‰؛‚°‚ؤ‚إ‚à‚±‚¤‚µ‚½ژ{چô‚ج—ک—p‚ًٹَ–]‚µ‚ؤ‚¢‚邱‚ئ‚ًژ¦چ´‚·‚éپB‚±‚ê‚ç‚جŒ‹‰ت‚حپAکJ“ژsڈê‚ج—¬“®گ«‚ھ–R‚µ‚¢‚ي‚ھچ‘‚ة‚¨‚¢‚ؤ‚àپAٹé‹ئ‚ھکJ“ژز‚جگِچف“I‚بƒjپ[ƒY‚ً‚¤‚ـ‚‹‚‚ف‚ئ‚邱‚ئ‚ھ‚إ‚«‚ê‚خپAƒtƒŒƒbƒNƒXƒ^ƒCƒ€گ§“x‚ب‚ا‚ج“±“ü‚ة‚و‚èڈ]‹ئˆُ‚جŒْگ¶‚ًچ‚‚ك‚邱‚ئ‚ھ‚إ‚«‚邾‚¯‚إ‚ب‚پAگlŒڈ”ï‚ج‘ه•چيŒ¸‚ھژہŒ»‰آ”\‚ئ‚ب‚éƒPپ[ƒX‚à‚ ‚邱‚ئ‚ًژ¦چ´‚µ‚ؤ‚¢‚éپB
گ}پF‰¼‘zژ؟–â‚ة‚à‚ئ‚أ‚WLBژ{چôپiڈ_“î‚ب“‚«•ûپj‚ج’ہ‹àƒvƒŒƒ~ƒAƒ€‚ج•ھ•z
ژQچl•¶Œ£
? ژR–{ŒMپEڈ¼‰YژُچKپAپuƒڈپ[ƒNƒ‰ƒCƒtپEƒoƒ‰ƒ“ƒXژ{چô‚حٹé‹ئ‚جگ¶ژYگ«‚ًچ‚‚ك‚é‚©پHپ\ ٹé‹ئƒpƒlƒ‹ƒfپ[ƒ^‚ً—p‚¢‚½WLBژ{چô‚ئTFP‚جŒںڈط پ\پvRIETI Discussion Paper Series 11-J-032پA2011”N
http://www.rieti.go.jp/jp/publications/nts/13j004.html
2011”N“x‚جگ¬‰ت
RIETIƒfƒBƒXƒJƒbƒVƒ‡ƒ“پEƒyپ[ƒpپ[
? 11-E-078
"Employment Protection and Productivity: Evidence from firm-level panel data in Japan" (OKUDAIRA Hiroko, TAKIZAWA Miho and TSURU Kotaro)
? 11-E-077
"What Does a Temporary Help Service Job Offer? Empirical suggestions from a Japanese survey" (OKUDAIRA Hiroko, OHTAKE Fumio, KUME Koichi and TSURU Kotaro)
? 11-E-047
"Evidence of a Growing Inequality in Work Timing Using a Japanese Time-Use Survey" (KURODA Sachiko and YAMAMOTO Isamu)
? 11-J-061
پu”ٌگ³‹KکJ“ژز‚جچK•ں“xپv(‹v•ؤ Œ÷ˆêپA‘ه’| •¶—YپA‰œ•½ ٹ°ژqپA’ك Œُ‘¾کY)
? –{چe‚إ‚حپAƒEƒFƒuƒAƒ“ƒPپ[ƒg’²چ¸‚جŒ‹‰ت‚ً—p‚¢‚ؤپA“ْ–{‚ج”ٌگ³‹KکJ“ژز‚ة‘خ‚µ‚ؤ•K—v‚بگچô“I‘خ‰‚ة‚آ‚¢‚ؤپA‚»‚جژهٹد“IچK•ں“x‚جŒˆ’è—vˆِ‚ً•ïٹ‡“I‚ة•ھگح‚µ‚ؤŒں“¢‚µ‚½پB‹ï‘ج“I‚ة‚حپA”ٌگ³‹KŒظ—p‚ة‚¨‚¯‚é”hŒکJ“پEƒpپ[ƒg“™‚جŒظ—pŒ`‘شپA‚»‚ج‘I‘ً——RپAŒظ—pŒ_–ٌٹْٹشپA‰ك‹ژ‚جŒoŒ±“™‚جˆل‚¢‚ة’چ–ع‚·‚é‚ئ‚ئ‚à‚ةپAŒp‘±’²چ¸‚³‚ꂽƒfپ[ƒ^‚ج—ک“_‚ًٹˆ‚©‚µ‚ؤپAŒآگl‚جŒإ‘جŒّ‰ت‚ًچl—¶‚µ‚½ƒpƒlƒ‹ƒfپ[ƒ^•ھگح‚ًچs‚ء‚½پB
‚»‚جŒ‹‰تپAپi1پj–¢چ¥پAپi2پj’Z‚¢Œظ—pŒ_–ٌٹْٹشپAپi3پj”ٌژ©”“I”ٌگ³‹KŒظ—pپAپi4پjچ‚چZ‘²ˆب‰؛‚جٹw—ًپAپi5پj‰ك‹ژ‚جکJچذŒoŒ±‚ئ‚¢‚ء‚½کJ“ژز‚ج‘®گ«‚حپAژهٹد“IچK•ں“x‚ًˆّ‚«‰؛‚°‚ؤ‚¢‚½پB‚±‚ج‚±‚ئ‚حپAچ،Œم‚ج”ٌگ³‹KŒظ—p–â‘è‚ض‚جگچô‘خ‰‚ئ‚µ‚ؤپA‰ئ‘°گچô‚ئ‚جٹض‚ي‚è‚àچl—¶‚µ‚½ژ{چôپAŒظ—pŒ_–ٌٹْٹش‚ج‰„’·پA”ٌژ©”“I”ٌگ³‹KŒظ—pژز‚ة‘خ‚·‚éگ³‹KŒظ—p‚ض‚ج“]ٹ·پE“o—p“™‚جƒLƒƒƒٹƒAƒpƒX‚جگ®”ُپA‹³ˆç‹@‰ï’ٌ‹ں‚âڈAٹwژx‰‡پAگEڈê‚إ‚جˆہ‘S‘خچôگ„گi‚â‚»‚جŒم‚جƒPƒA‚ھپA”ٌگ³‹KکJ“ژز‚جژهٹد“IچK•ں“x‚ج‘گi‚ةژ‘‚·‚é‰آ”\گ«‚ًژ¦چ´‚µ‚ؤ‚¢‚éپB
? 11-J-060
پu—LٹْکJ“Œ_–ٌ–@گ§‚ج—§–@‰غ‘èپv(“‡“c —zˆê)
? 11-J-059
پuپw“¯ˆêکJ““¯ˆê’ہ‹àپx‚حŒ¶‘z‚©پHپ\گ³‹KپE”ٌگ³‹KکJ“ژزٹش‚جٹiچ·گ¥گ³‚ج‚½‚ك‚ج–@Œ´‘¥‚ج‚ ‚è•ûپ\پv(گ…’¬ —EˆêکY)
? 11-J-058
پu‹Kگ§‹‰»‚ةŒü‚¯‚½“®‚«‚ئ’¼ژ‹‚·‚ׂ«Œ»ژہپv(ڈ¬›¸ “T–¾)
? 11-J-057
پuپw‘½—l‚بگ³ژذˆُپx‚ئ”ٌگ³‹KŒظ—pپv(ژ瓇 ٹî”ژ)
? 11-J-056
پu•nچ¢‚ئڈA‹ئپ\ƒڈپ[ƒLƒ“ƒOƒvƒA‰ًڈء‚ةŒü‚¯‚½—LŒّچô‚جŒں“¢پ\پv(”َŒû ”ü—YپAگخˆن ‰ء‘مژqپAچ²“، ˆê–پ)
? ‚ي‚ھچ‘‚إ‚حڈA‹ئ‚µ‚ؤ‚¢‚ؤ‚à•nچ¢‚إ‚ ‚éگ¢‘ر‚ھ‘½‚¢‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚ھپA•nچ¢‚جچ‘چغ”نٹrŒ¤‹†‚©‚ç–¾‚ç‚©‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚éپB‚±‚ج‚و‚¤‚ب‚ي‚ھچ‘‚ج•nچ¢‚ج“ء’¥‚ً“¥‚ـ‚¦‚ؤپA–{چe‚إ‚حپAŒcœن‰ئŒvƒpƒlƒ‹’²چ¸پiKHPSپj2004-2010‚جƒfپ[ƒ^‚ً—p‚¢پA‚ي‚ھچ‘‚ة‚¨‚¯‚é•nچ¢‚ئڈA‹ئ‚ئ‚جٹضŒW‚ة‚آ‚¢‚ؤ•ھگح‚ًچs‚ء‚½پB•ھگح‚جŒ‹‰تپA‚ي‚ھچ‘‚إ‚ح”ٌگ³‹KکJ“ژز‚ئ‚µ‚ؤڈA‹ئ‚µ‚ؤ‚¢‚éگ¢‘ر‚ة‚¨‚¢‚ؤژ¸‹ئ‚â–³‹ئگ¢‘ر‚و‚è‚à•nچ¢—¦‚ھچ‚‚¢‚±‚ئپA‚µ‚©‚µ‚ب‚ھ‚çپA•nچ¢‘w‚©‚ç‚ج’E‹pٹ„چ‡‚ً‘O”N‚جڈA‹ئڈَ‘ش•ت‚ةŒ©‚é‚ئپA–³‹ئ‚إ‚ ‚ء‚½گ¢‘ر‚ة”ن‚×پA”ٌگ³‹KŒظ—p‚إ‚ ‚ء‚ؤ‚àڈA‹ئ‚µ‚ؤ‚¢‚éگ¢‘ر‚ج‚ظ‚¤‚ھ’E‹pٹ„چ‡‚جچ‚‚¢‚±‚ئ‚ھ‚ي‚©‚ء‚½پBˆê•û‚إپAگ³‹KŒظ—p‚ة‚¨‚¢‚ؤ‚حپA•nچ¢—¦‚ھ‚à‚ء‚ئ‚à’ل‚پA”ٌگ³‹K‚©‚çگ³‹KŒظ—p‚ض‚ج“]ٹ·‚ھ•nچ¢‰ًڈء‚ج1‚آ‚ج—LŒّ‚بچô‚إ‚ ‚邱‚ئ‚ھژ¦چ´‚³‚ꂽپB‚»‚±‚إ”ٌگ³‹KŒظ—p‚©‚çگ³‹KŒظ—p‚ض‚ج“]ٹ·‚ج‘£گi‚ة—LŒّ‚بگچôژx‰‡‚ً•ھگح‚µ‚ؤ‚ف‚é‚ئپAژ©ŒبŒ[”‚ًچs‚ء‚ؤ‚¢‚éگl‚ج“]ٹ·ٹ„چ‡‚ھ‚ئ‚‚ةڈ—گ«کJ“ژز‚ة‚¨‚¢‚ؤ—Lˆس‚ةچ‚‚¢‚±‚ئ‚ھ‚ي‚©‚èپAژ©ŒبŒ[”‚ئ‚¢‚ء‚½”\—حٹJ”‚ض‚جگê–ه‰ئ‚ة‚و‚éڈ•Œ¾‚âژ‘‹à“IپEژٹش“Iژx‰‡‚ھ—LŒّ‚إ‚ ‚邱‚ئ‚ھژ¦چ´‚³‚ꂽپB‚ـ‚½پAژ¸‹ئژز‚ج•nچ¢‘خچô‚ئ‚µ‚ؤپAژ¸‹ئ•غŒ¯ژَ‹‹‚جژ‘ٹi‚ج—L–³پA‚¨‚و‚رژہچغ‚ةژَ‹‹‚µ‚½‚©‚ا‚¤‚©‚ج•ت‚ة•nچ¢‚©‚ç‚ج’E‹pٹ„چ‡‚ً”ن‚ׂé‚ئپAژ¸‹ئ•غŒ¯‚ة‰ء“ü‚µ‚ؤ‚¨‚èپA‹‹•t‚ًژَ‚¯‚ب‚ھ‚çپAڈA‹ئژx‰‡‚ًژَ‚¯‚½گl‚إ‚»‚جٹ„چ‡‚حچ‚‚پA‰ء“ü‚µ‚ؤ‚¢‚ب‚©‚ء‚½گl‚إچإ‚à’ل‚¢‚±‚ئ‚ھ‚ي‚©‚ء‚½پB‚·‚ب‚ي‚؟پAژ¸‹ئ‹‹•t‚حژ¸‹ئژ‚جڈٹ“¾•غڈل‚ج–ًٹ„‚ً’S‚¤‚¾‚¯‚إ‚ح‚ب‚پA‚±‚ê‚ئƒZƒbƒg‚ئ‚µ‚ؤچs‚ي‚ê‚éڈA‹ئژx‰‡‚ة‚و‚èپA‚»‚جŒم‚جڈA‹ئٹm—¦‚àچ‚‚ك‚éŒّ‰ت‚ً‚à‚ء‚ؤ‚¢‚邱‚ئ‚ھٹm”F‚³‚ꂽپB‘¼•ûپAژ¸‹ئ•غŒ¯‚ة‰ء“ü‚µ‚ؤ‚¢‚ب‚©‚ء‚½ژ¸‹ئژز‚جڈêچ‡پA‚à‚ئ‚à‚ئŒظ—pڈًŒڈ‚ج—ا‚‚ب‚¢Œظ—p‹@‰ï‚ةڈA‚¢‚ؤ‚¢‚½گl‚ھ‘½‚پAچ،ŒمپA‚±‚¤‚µ‚½گl‚ض‚جڈٹ“¾•غڈل‚ئڈA‹ئژx‰‡‚ج‹‰»‚ھ‹پ‚ك‚ç‚ê‚éپB
? 11-J-055
پu”hŒکJ“‚حگ³ژذˆُ‚ض‚ج“¥‚فگخ‚©پA‚»‚ê‚ئ‚à•sˆہ’èŒظ—p‚ض‚ج“ü‚èŒû‚©پv(‰œ•½ ٹ°ژqپA‘ه’| •¶—YپA‹v•ؤ Œ÷ˆêپA’ك Œُ‘¾کY)
? 11-J-054
پu”hŒکJ“ژز‚ةٹض‚·‚éچs“®Œoچدٹw“I•ھگحپv(‘ه’| •¶—YپA—› ›h›N)
? 11-J-053
پuگlپX‚ح‚¢‚آ“‚¢‚ؤ‚¢‚é‚©پHپ\گ[–鉻‚ئگ³‹KپE”ٌگ³‹KŒظ—p‚جٹضŒWپ\پv(چ•“c ڈثژqپAژR–{ ŒM)
? 11-J-052
پu”ٌگ³‹KکJ“ژز‚جٹَ–]‚ئŒ»ژہپ\•s–{ˆسŒ^”ٌگ³‹KŒظ—p‚جژہ‘شپ\پv(ژR–{ ŒM)
? –{چe‚إ‚حپAپwŒcœن‹`ڈm‰ئŒvƒpƒlƒ‹’²چ¸پxپi2004پ`10”Nپj‚جŒآ•[ƒfپ[ƒ^‚ً—p‚¢‚ؤپAگ³‹KŒظ—p‚جگE‚ھ‚ب‚¢‚½‚ك‚ةژd•û‚ب‚”ٌگ³‹KŒظ—p‚ةڈA‚¢‚ؤ‚¢‚é•s–{ˆسŒ^‚ج”ٌگ³‹KŒظ—p‚جژہ‘ش‚ً–¾‚ç‚©‚ة‚·‚é‚ئ‚ئ‚à‚ةپAڈA‹ئŒ`‘ش–ˆ‚ةگlپX‚جژهٹد“IŒْگ¶گ…ڈ€‚ھ‚ا‚ج‚و‚¤‚ةˆظ‚ب‚é‚©‚ًŒںڈط‚·‚éپBŒںڈط‚جŒ‹‰تپA”ٌگ³‹KŒظ—p‚ج‘ه‘½گ”‚حژ©‚ç‘I‘ً‚µ‚ؤ‚¢‚é–{ˆسŒ^‚إ‚ ‚邱‚ئپA‚µ‚©‚µ•s–{ˆسŒ^‚ج”ٌگ³‹KŒظ—pژز‚حژ¸‹ئژز‚ج–ٌ1.5”{‚ئ–³ژ‹‚µ‚¦‚ب‚¢گlگ”‚إ‚ ‚邱‚ئپA•s–{ˆسŒ^‚ج”ٌگ³‹KŒظ—p‚ح“ئگgپA20چخ‘م‚ ‚é‚¢‚ح40پ`50چخ‘مپAŒ_–ٌژذˆُ‚â”hŒژذˆُپA‰^—AپE’تگMگE‚âگ»‘¢پEŒڑگفپE•غژçپE‰^”ہ‚ب‚ا‚جچى‹ئگE‚ب‚ا‚إ‘½‚پA‚ـ‚½پAŒi‹Cڈzٹآ‚ئ‚جٹضŒW‚إ‚ح•s‹µٹْ‚ة‘‚¦‚éŒXŒü‚ھ‚ ‚邱‚ئ‚ب‚ا‚ھ–¾‚ç‚©‚ة‚ب‚ء‚½پB‚±‚ج‚ظ‚©پAڈA‹ئŒ`‘ش‚ج‘I‘ًچs“®‚âڈA‹ئŒ`‘شٹش‚جˆعچsڈَ‹µ‚ً‚ف‚é‚ئپA•s–{ˆسŒ^‚ج”ٌگ³‹KŒظ—p‚حپA“¯‚¶”ٌگ³‹KŒظ—p‚إ‚ ‚ء‚ؤ‚à–{ˆسŒ^‚ئ‚ح‚»‚ج“ءگ«‚ھˆظ‚ب‚èپA‚ق‚µ‚ëژ¸‹ئ‚ئ‚ج—قژ—گ«‚ھچ‚‚¢‚±‚ئ‚ھ‚ي‚©‚ء‚½پBژں‚ةپAŒآپXگl‚جژهٹد“IŒْگ¶ژw•W‚ئ‚µ‚ؤگSگgڈاڈَپiƒXƒgƒŒƒXپj‚ج‘ه‚«‚³‚ً“_گ”‰»‚µ‚½ژw•W‚ًڈA‹ئŒ`‘شٹش‚إ”نٹr‚µ‚½‚ئ‚±‚ëپAگ³‹KŒظ—p‚و‚è‚à”ٌگ³‹KŒظ—p‚âژ¸‹ئپA”ٌکJ“—ح‚إƒXƒgƒŒƒX‚ھ‘ه‚«‚‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚邱‚ئ‚ھ‚ي‚©‚ء‚½پB‚µ‚©‚µپAŒآگl‘®گ«‚âڈA‹ئ‘I‘ً‚ج“àگ¶گ«‚ًƒRƒ“ƒgƒچپ[ƒ‹‚·‚é‚ئپAگ³‹KŒظ—p‚و‚è‚àƒXƒgƒŒƒX‚ھ‘ه‚«‚¢‚ج‚حپA•s–{ˆسŒ^‚ج”ٌگ³‹KŒظ—p‚ئژ¸‹ئ‚¾‚¯‚إ‚ ‚邱‚ئ‚àٹm”F‚إ‚«‚½پB‚آ‚ـ‚èپA”ٌگ³‹KŒظ—p‚¾‚©‚ç‚ئ‚¢‚ء‚ؤŒْگ¶گ…ڈ€‚ھ’ل‚‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ئ‚حŒہ‚炸پA‚»‚ج‘ه‘½گ”‚ًگè‚ك‚é–{ˆسŒ^‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حگ³‹KŒظ—p‚â”ٌڈA‹ئ‚ئŒْگ¶گ…ڈ€‚ح•د‚ي‚ç‚ب‚¢پBˆê•û‚إپA•s–{ˆسŒ^‚ج”ٌگ³‹KŒظ—p‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپAژ¸‹ئ‚ئ“¯’ِ“x‚ةپA‘¼‚جڈA‹ئŒ`‘ش‚و‚è‚àƒXƒgƒŒƒX‚ھ—Lˆس‚ة‘ه‚«‚‚ب‚ء‚ؤ‚¨‚èپAژù—v‘¤‚جگ§–ٌ‚ج‚½‚ك‚ةŒّ—p‚ھ’ل‰؛‚µپAŒ’چN”يٹQ‚ئ‚¢‚¤Œ`‚إ‚»‚ج‰e‹؟‚ھŒ°Œ»‰»‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ئ‰ًژك‚إ‚«‚éپB
? 11-J-051
پu”ٌگ³‹KکJ“ژز‚ح‚ب‚؛‘‚¦‚½‚©پv(گَ–ى ”ژڈںپAˆة“، چ‚چOپAگىŒû ‘هژi)
? ‰ك‹ژ20”N‚جٹش‚ةپA“ْ–{‚جŒظ—p‚ًژو‚èٹھ‚ڈَ‹µ‚ح‘ه‚«‚ب•د‰»‚ًگ‹‚°‚ؤ‚¢‚éپB”ٌگ³‹K‰»‚جگi“W‚حچإ‚àŒ°’ک‚بŒ»ڈغ‚ج1‚آ‚إ‚ ‚èپA1986”N‚ة‚ح17%’ِ“x‚إ‚ ‚ء‚½”ٌگ³‹KکJ“ژز‚ج”ن—¦‚حپA2008”N‚ة‚ح34%‚ـ‚إ‚ة‚à‘‘ه‚µ‚ؤ‚¢‚éپB–{چe‚إ‚ح‚±‚ج”ٌگ³‹KکJ“ژز‚ج‘‰ء‚ئ‚¢‚¤’·ٹْ“IŒXŒü‚ج‰ً–¾‚ًژژ‚ف‚éپB‚ـ‚¸“¯ژٹْ‚ة‚¨‚¯‚é”ٌگ³‹KکJ“ژز‚جگ³‹KکJ“ژز‚ة‘خ‚·‚é‘ٹ‘خ’ہ‹à‚ح”ٌڈي‚ةˆہ’è“I‚إ‚ ‚èپA‚±‚ج‚±‚ئ‚ح”ٌگ³‹KکJ“ژز‚ج‘ٹ‘خ“I‚بژù—v‚ج‚ف‚ب‚炸‹ں‹‹‚à‘‘ه‚µ‚ؤ‚¢‚邱‚ئ‚ًژ¦چ´‚µ‚ؤ‚¢‚éپB‚½‚¾‚µپAژY‹ئچ\‘¢‚ج•د‰»‚âکJ“گlŒûچ\گ¬‚ج•د‰»‚ح”ٌگ³‹KکJ“ژز‚ج‘‰ء‚ج4•ھ‚ج1’ِ“x‚µ‚©گà–¾‚µ‚ؤ‚¨‚炸پAژc‚è•”•ھ‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپAڈ—گ«کJ“ژز‚ج”ٌگ³‹KڈA‹ئٹm—¦‚جڈمڈ¸پA‚ ‚é‚¢‚ح‰µ”„پEڈ¬”„‹ئ‚âƒTپ[ƒrƒX‹ئ‚ة‚¨‚¯‚é”ٌگ³‹KŒظ—pژù—v‚ج‘‘ه‚ب‚ا‚ھ‘ه‚«‚ب—vˆِ‚ئ‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚éپB‚ـ‚½پAٹé‹ئƒfپ[ƒ^‚ً—p‚¢‚½•ھگح‚©‚ç‚حپA”ٌگ³‹KکJ“ژز‚ج‘‰ء‚ج6ٹ„’ِ“x‚ًپAژY‹ئچ\‘¢‚ج•د‰»‚ئگ¶ژY•¨ژù—v‚ج•sٹmژہگ«‚»‚µ‚ؤڈî•ٌ’تگM‹Zڈp‚ج“±“ü‚ة‚و‚ء‚ؤگà–¾‚إ‚«‚邱‚ئ‚ھژ¦‚³‚ꂽپB
پ¦–{چe‚حپA‰pŒê”إ‚جƒfƒBƒXƒJƒbƒVƒ‡ƒ“پEƒyپ[ƒpپ[پi11-E-021پj‚ً“ْ–{Œê”إ‚ة‚µ‚½‚à‚ج‚إ‚ ‚é
? 11-J-050
پu”hŒکJ“ژز‚جگ¶ٹˆ‚ئڈA‹ئپ|RIETIƒAƒ“ƒPپ[ƒg’²چ¸‚©‚çپv(‘ه’| •¶—YپA‰œ•½ ٹ°ژqپA‹v•ؤ Œ÷ˆêپA’ك Œُ‘¾کY)
? 11-J-049
پu”ٌگ³‹KŒظ—p–â‘è‰ًŒˆ‚ج‚½‚ك‚ج’¹لصگ}پ|—LٹْŒظ—p‰üٹv‚ةŒü‚¯‚ؤپ|پv(’ك Œُ‘¾کY)
http://www.rieti.go.jp/jp/projects/program/pg-07/001.html
گ¶ٹˆ•غŒىگ§“x‚ً‚ك‚®‚éچإ‹ك‚ج“®Œü
چ‘—§چ‘‰ïگ}ڈ‘ٹظ ISSUE BRIEF NUMBER 776(2013. 3.19.)
گ¶ٹˆ•غŒى‚جژَ‹‹ژز‚ح‹ك”N‹}‘‚µ‚ؤ‚¨‚èپA“ء‚ةپA‰ز“”\—ح‚ج‚ ‚éژَ‹‹ژز‚ج‘‰ء‚ھ
–â‘èژ‹‚³‚êپAگ§“x‰üٹv‚ح‹i‹ظ‚جگچô‰غ‘è‚إ‚ ‚éپB
–{چe‚إ‚حپAگ¶ٹˆ•غŒىگ§“x‚ً‚ك‚®‚éچإ‹ك‚ج“®Œü‚ًگ®—‚·‚éپB
Œ»ڈَ‚ئ–â‘è“_‚إ‚حپAژَ‹‹ژز“™‚جŒ»ڈَ‚ًƒfپ[ƒ^‚إٹTٹد‚·‚é‚ئ‚ئ‚à‚ةپA•ٌ“¹“™‚إژو
‚èڈم‚°‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚é–â‘è‚ئ‚µ‚ؤپA”N‹àژx‹‹ٹzپEچإ’ل’ہ‹àٹz‚ئ‚ج‹t“]Œ»ڈغپAˆم—أ•}ڈ•پA
•sگ³ژَ‹‹پAپu•nچ¢ƒrƒWƒlƒXپvپAگe‘°ٹش•}—{‹`–±‚جŒµٹi‰»–â‘è‚ًڈذ‰î‚·‚éپB
چ‘‚ئ’n•ûژ©ژ،‘ج‚جژ{چô‚إ‚حپAچ‘‚جژ{چô‚ئ‚µ‚ؤپAژ©—§ژx‰‡ƒvƒچƒOƒ‰ƒ€پAٹwڈKژx‰‡
‚جگ§“x‰»پA‘و2 ‚جƒZپ[ƒtƒeƒBپ[ƒlƒbƒgژ{چôپA’n•ûژ©ژ،‘ج‚جژ{چô‚ئ‚µ‚ؤ‚حپAژ©—§‘£
گiژ{چôپA•nچ¢‚جکAچ½‚ة‘خ‚·‚é‘خچôپA•sگ³ژَ‹‹‘خچô‚ًژو‚èڈم‚°‚éپB
‰üٹv‚ج‹cک_“™‚جڈَ‹µ‚إ‚حپAگ•{‚ةگف‚¯‚ç‚ꂽ•”‰ï“™‚إ‚ج‹cک_‚جڈَ‹µ‚ًگ®—‚µپA
‚»‚جک_“_‚ًٹTٹد‚·‚éپB
‚ح‚¶‚ك‚ة
‡T Œ»ڈَ‚ئ–â‘è“_
‚P ژَ‹‹ژزگ”“™‚جŒ»ڈَ
‚Q چإ‹كژو‚èڈم‚°‚ç‚ꂽ–â‘è
‡U چ‘‚ئ’n•ûژ©ژ،‘ج‚جژ{چô
‚P چ‘‚جژ{چô
‚Q ’n•ûژ©ژ،‘ج‚جژ{چô
‡V ‰üٹv‚ج‹cک_“™
‚P ژذ‰ï•غڈلگR‹c‰ïگ¶ٹˆ•غŒىٹî
ڈ€•”‰ï
’²چ¸‚ئڈî•ٌ
‘و‚V‚V‚Uچ†
‚Q گ¶ٹˆ•غŒىگ§“x‚ةٹض‚·‚éچ‘‚ئ
’n•û‚ج‹¦‹c
‚R ژذ‰ï•غڈلگR‹c‰ïگ¶ٹˆچ¢‹‡ژز
‚جگ¶ٹˆژx‰‡‚جچف‚è•û‚ةٹض‚·
‚é“ء•ت•”‰ï
‚S چàگگ§“x“™گR‹c‰ï
‚¨‚ي‚è‚ة
‚ح‚¶‚ك‚ة
گ¶ٹˆ•غŒى‚جژَ‹‹ژز‚ح‹ك”N‹}‘‚µ‚ؤ‚¨‚èپA“ء‚ةپA‰ز“”\—ح‚ج‚ ‚éژَ‹‹ژز‚ج‘‰ء‚ھ–â‘è‚ئ‚ب
‚ء‚ؤ‚¨‚èپA•sگ³ژَ‹‹‚âگ¶ٹˆ•}ڈ•ٹîڈ€‚ً‚ك‚®‚é•ٌ“¹پAگ§“x‰üٹv‚ض‚ج‹cک_‚ھ‘±‚¢‚ؤ‚¢‚éپB
–{چe‚إ‚حپAگ¶ٹˆ•غŒىگ§“x‚جŒ»ڈَ‚ئ–â‘è“_پAچإ‹ك‚جچ‘‚ئ’n•ûژ©ژ،‘ج‚جژ{چôپA‰üٹv‚ج‹cک_“™
‚جڈَ‹µ‚ًٹTٹد‚·‚éپB
‡T Œ»ڈَ‚ئ–â‘è“_
‚P ژَ‹‹ژزگ”“™‚جŒ»ڈَ
گ¶ٹˆ•غŒى‚جژَ‹‹ژزگ”‚حپA•½گ¬23 ”N3 Œژ––ژ“_‚إپA59 ”N‚ش‚è‚ة200 –œگl‚ً’´‚¦1پA‚»‚ج
Œم‚à‘‰ء‚ً‘±‚¯‚ؤ‚¨‚èپA•½گ¬24”N3Œژ––Œ»چف‚إ‚ح210–œ8096گl‚ئ‚ب‚ء‚½2(گ}1ژQڈئ)پB
گ} 1 گ¶ٹˆ•غŒىژَ‹‹گ¢‘رگ”پAگ¶ٹˆ•غŒىژَ‹‹ژزگ”پA•غŒى—¦‚جگ„ˆع
پiڈo“TپjŒْگ¶کJ“ڈبپw•½گ¬24”N”إŒْگ¶کJ“”’ڈ‘پx2012, p.517.
•½گ¬23”N“x‚ة‚¨‚¯‚éژَ‹‹گ¢‘ر‚ةگè‚ك‚éپuچ‚—îژزگ¢‘رپv‚جٹ„چ‡‚حپA42.5%‚ئˆث‘Rچإ‘½‚إ‚
‚éپBˆê•û‚إپAچ‚—îژزگ¢‘رپAڈلٹQژز“™گ¢‘رپA•êژqگ¢‘ر‚ج‚¢‚¸‚ê‚إ‚à‚ب‚¢پu‚»‚ج‘¼‚جگ¢‘رپv‚ھ
•½گ¬20 ”N“x‚ـ‚إ10%‘OŒم‚إ‚ ‚ء‚½‚à‚ج‚ھپA•½گ¬21 ”N“x‚ة‚ح13.5%پA•½گ¬22 ”N“x‚ة‚ح
–{چe‚ة‚¨‚¯‚éƒCƒ“ƒ^پ[ƒlƒbƒgڈî•ٌ‚حپA•½گ¬25”N3Œژ11“ْŒ»چف‚إ‚ ‚éپB
1 Œْگ¶کJ“ڈبپw•ںژƒچsگ•ٌچگ—لپi•½گ¬23”N3Œژ•ھٹTگ”پjپx(•½گ¬23”N6Œژ14“ْ)
<http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/gyousei/fukushi/m11/03.html>
2 Œْگ¶کJ“ڈبپw•ںژƒچsگ•ٌچگ—لپi•½گ¬24”N3Œژ•ھٹTگ”پjپx(•½گ¬24”N6Œژ13“ْ)
<http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/gyousei/fukushi/m12/03.html>
http://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_8094030_po_0776.pdf پ@
|
|
|
|
‚±‚ج‹Lژ–‚ً“ا‚ٌ‚¾گl‚ح‚±‚ٌ‚ب‹Lژ–‚à“ا‚ٌ‚إ‚¢‚ـ‚·پi•\ژ¦‚ـ‚إ20•b’ِ“xژٹش‚ھ‚©‚©‚è‚ـ‚·پBپj
پ@
پ£‚±‚جƒyپ[ƒW‚ج‚s‚n‚o‚ضپ@پ@پ@پ@پ@ پڑˆ¢ڈC—…پô > Œoگ¢چد–¯79Œfژ¦”آ
|
|
 ƒXƒpƒ€ƒپپ[ƒ‹‚ج’†‚©‚猩‚آ‚¯ڈo‚·‚½‚ك‚ةƒپپ[ƒ‹‚جƒ^ƒCƒgƒ‹‚ة‚ح•K‚¸پuˆ¢ڈC—…‚³‚ٌ‚ضپv‚ئ‹Lڈq‚µ‚ؤ‚‚¾‚³‚¢پB
ƒXƒpƒ€ƒپپ[ƒ‹‚ج’†‚©‚猩‚آ‚¯ڈo‚·‚½‚ك‚ةƒپپ[ƒ‹‚جƒ^ƒCƒgƒ‹‚ة‚ح•K‚¸پuˆ¢ڈC—…‚³‚ٌ‚ضپv‚ئ‹Lڈq‚µ‚ؤ‚‚¾‚³‚¢پB‚·‚ׂؤ‚جƒyپ[ƒW‚جˆّ—pپA“]چعپAƒٹƒ“ƒN‚ً‹–‰آ‚µ‚ـ‚·پBٹm”Fƒپپ[ƒ‹‚ح•s—v‚إ‚·پBˆّ—pŒ³ƒٹƒ“ƒN‚ً•\ژ¦‚µ‚ؤ‚‚¾‚³‚¢پB