http://www.asyura2.com/13/genpatu31/msg/567.html
| Tweet |
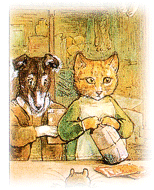
原子力規制委員会は日本原子力研究開発機構に対し、高速増殖炉原型炉もんじゅ(福井県敦賀市)の運転再開に向けた準備を停止させる検討を始めた。
昨年11月、もんじゅで1万点近い機器の点検漏れが発覚したためだ。この中には安全面で極めて重要な機器も50以上含まれていた。
その後の調査でも不備が見つかり、職員1人で数千点を点検するなど、管理不能な状態だったことを原子力機構自身が認めている。
これでは運転再開など論外であり、再開準備の停止は当然だ。
ただ、これまでの経緯を振り返れば、原子力機構の安全管理体制について、通り一遍の改善策を示せば済む問題ではない。
もんじゅは原子力政策に対する国民の不信を象徴する施設と言える。
初臨界直後の1995年にはナトリウム漏れ事故を起こし、当時の事業主体の動力炉・核燃料開発事業団が事故現場のビデオを改ざんするなど、隠蔽(いんぺい)体質が浮き彫りになった。
2010年に15年ぶりに運転を再開したが、トラブルで再停止した。
今回も点検漏れ発覚後、機構の鈴木篤之理事長が「形式的ミス」と発言し、規制委をあきれさせている。
看板を変えても、トラブルを過小評価する姿勢を改めない限り、信頼回復は到底無理だ。
そもそも運転再開の是非を論ずる前に、直視すべき問題がある。
もんじゅと、使用済み核燃料の再処理工場(青森県六ケ所村)を中核とする核燃料サイクル計画が破綻しているという現実だ。
高速増殖炉は使用済み核燃料から取り出したプルトニウムを燃料として発電し、理論上は消費した以上のプルトニウムを生み出す。
「夢の原子炉」とも呼ばれたが、失敗続きで実用化は絶望的だ。投じられた国費は既に1兆円に上る。
再処理工場の事情もほとんど同じで、操業のめどは立っていない。
核兵器に転用可能なプルトニウムの在庫を減らすため、ウランと混ぜて既存の原子炉で使うプルサーマル発電は割高で効率も悪い。
しかも、これらにかかる途方もない費用は税金や電気料金の形で国民が負担させられている。
政府は、核燃料サイクルの非現実性を国民に率直に明らかにし、もんじゅの廃炉と再処理からの撤退の道筋を探るべきだ。
サイクル関連施設を持つ自治体には別の地域振興策を用意し、使用済み核燃料を廃棄物として処分する方法も確立する必要がある。
日本の原子力行政が棚上げし続けてきた課題から、これ以上、目をそらしてはならない。
http://www.hokkaido-np.co.jp/news/editorial/465511.html
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます(表示まで20秒程度時間がかかります。)
▲このページのTOPへ ★阿修羅♪ > 原発・フッ素31掲示板
 スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。