http://www.asyura2.com/12/warb10/msg/331.html
| Tweet | �@ |
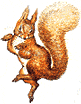
���ē����F���W���ꂽ����
2012�N10��23���iTue�j The Economist
�i�p�G�R�m�~�X�g���@2012�N10��20�����j
���ꌧ�������ē����̗��_�ɋ^��𓊂��|����V���ȗ��R����������B
�@����ɒ��������2��6000�̕��m�𑩂˂�ČR�i�ߊ������́A�s�^�Ɏ���Ă���Ɗ����Ă���B����A140���l�̉��ꌧ���̑����́A�č��l���̂��̂Ɏ���Ă���Ɗ����Ă���B
�@�ĊC�R�̕��m2�l���n���̏����ɐ��I�\�s���������e�^�őߕ߁A�������ꂽ�͖̂��ȃ^�C�~���O�������B����ł͊��ɁA�ČR��n�ɑ���R�c�̋C�^������オ���Ă����B���������͂���10���A�X��p�s�̕��V�Ԋ�n��12�@��MV22�I�X�v���C���z�����ꂽ���Ƃ������B�I�X�v���C�̓w���R�v�^�[�̂悤�ɗ��������A�Œ藃�@�̂悤�ɔ�s����B
�@�R�c�s���ɎQ����������Z���́A�u���E�ōł��댯�Ȋ�n�ɐ��E�ōł��댯�ȍq��@�v���z�����ꂽ�ƌ���B�č����́A�ł��댯�Ȋ�n�ł��ł��댯�ȍq��@�ł��Ȃ��ƈًc�������A����ōł��ƍߗ��������͕̂ČR�̕��m���Ƃ����咣���ے肵�Ă���B
�@����ł��A����N�������C�v�����́A�n���Z���̌������{��̉ɖ��𒍂������̂��̂������B
���V�Ԃɔz�����ꂽ�I�X�v���C
�ĊC�����̐����������A���@MV22�I�X�v���C�kAFPBB News�l
�@�I�X�v���C�Ɋւ��Č����A�s�^��2012�N�ɓ����Ă���̕ăt�����_�B�ƃ����b�R�̎��̂Ƃ����`�ŖK�ꂽ�B�I�X�v���C�����S�łȂ��Ƃ����͕̂s�����Ȉ�ۂ��ƕč��͌J��Ԃ����A2���̎��̂ł��̈�ۂ͂���ɋ��܂����B
�@�C�����ɂ��A�I�X�v���C�͂���܂łɕČR���z�������قƂ�ǂ̍q��@�����S���̎��т������Ƃ����B
�@�����āA�I�X�v���C�͉���ł̌R���\�͂�啝�ɍ��߂Ă����ƍl���Ă���B�V���������w���R�v�^�[�A�V�[�i�C�g�̑�ւƂ��ăI�X�v���C��z������A��s���x��2�{�ɁA�ύڗʂ�3�{�ɁA�q��������4�{�ɂł���B
�@����͂��ė��������ƌĂꂽ�̖{�����B���{��19���I�ɗ������������A��p�Ɍ����ē쐼��1000�L���ȏ�A�̓y���g�債���B����{���͓��Ă̈��S�ۏᓯ���̒��j�𐬂��A���{�ɒ�������ČR��3����2���W�����Ă���B
�@�č������E�ɂ�����R���헪���A�W�A�Ɂu����v���Ă��鍡�A����̈ʒu�Â��́A���ĂȂ��قǍ��܂��Ă���B����͒����Ƒ����m�̌��C�Ƃ̊Ԃɂ���u��1���v�ɑ����A��p�C����k�̒��N�����Ŗ�肪�������ۂɂ́A���������͈͂Ɏ��߂���ʒu�ɂ��邩�炾�B
�@�܂��A���{���U�������ۂɂ͕č����h�q�ɂ�����Ƃ�������̖͍��A�P�Ȃ鉼��ȏ�̈Ӗ������悤�Ɏv����B
�@���̂Ƃ���͂܂��A���{�̎{�����ɂ��鏬���Ȗ��l���̏W�܂��t�����i�����͒ދ����ƌĂ�ł���j����������Ԃ��a瀂��푈�ɔ��W���邱�Ƃ͂قڂ��蓾�Ȃ��悤�Ɍ�����B�����A���̗��R�́A��t���������ď��̑Ώۂł���ƕč����������Ă��邱�Ƃ��B
�@�č��h�Ȃ̈˗����ă��V���g���ɂ���V���N�^���N�A�헪���ۖ�茤�����iCSIS�j���쐬���A8���Ɍ��\�����č��̑����m�헪�Ɋւ���]�����́A���́u���ƂȂ�헪�I�Ȏ���v�Ɍ��y���Ă���B���̎���Ƃ́A�č������S�ۏ����A���{����n�̎g�p��F�߂�Ƃ������́B�܂�A���{���{�ɂ͉���ł̓{��̊g���S�z���闝�R������킯���B
�c��オ��n���Z���̓{��
�@���V�Ԋ�n�̃Q�[�g�O�ɂ́A���̐������������Ă�����̂́A����҂𒆐S�ɃI�X�v���C�z���ɔ�����l�X�������W�܂��Ă���B9����10���l����K�͂̃f��������A���̌���R�c�s���������Ă���̂��B
�@�ČR�����̗��j�Ɠ������炢��67�ɂȂ邠��Q���҂́A1982�N����ČR��n�ɔ�����R�c�����𑱂��Ă���Ƃ����B1982�N�Ƃ����̂́A�ꕔ�̒n�傪��n�̗p�n�̑ݎ،_���ł��낤�Ƃ��������B
�@������1995�N�A3�l�̕ĕ���12�̏������W�c���C�v�������������������ɁA����܂ł��ϋɓI�ɍR�c�����ɂ������悤�ɂȂ����B2004�N�A��n�̊O�̑�w�Ƀw���R�v�^�[���ė������i���҂͏o�Ȃ������j�����f���ɎQ�������B
�@�I�X�v���C�z���A�����č���N�������C�v�����͒��N�̍��݂��ĔR�����A�V���ȓ{��ɉ������B���ꌧ�m���������̖��g�i���́A������80�`90�����I�X�v���C�z���ɔ����Ă���Ɛ�������B���ď��̊m�ł���x���҂���O�ł͂Ȃ��Ƃ����B
�@�n���Z���̕s���̈ꕔ�́A��n���̂��̗̂��n�ɖ�肪���邱�Ƃ��痈�Ă���B�X��p�͊J�����i�݁A��n�����S�Ɉ͂ނ悤�Ɏs�X�n���L�����Ă���B
�@1996�N�A���ė����͕��V�Ԋ�n�̈ړ]�ō��ӂ��A2006�N�ɂ͈ړ]���Ӗ�ÂɌ��߂��B�Ӗ�Â͓��̖k���Ɉʒu���A�l������r�I���Ȃ��B
�@CSIS�̕��́A���V�Ԃ��u����ōō��̏ꏊ�v�A�Ӗ�Â��ق��̑I�����̒��ł͍őP�ƕ]�����Ă���B����́A�č��ɂƂ��Ĉړ]�̒x��͂قƂ�nj��O�ޗ��ɂȂ�Ȃ����Ƃ��������Ă���B�������A���V�Ԋ�n�ōq��c�̎w��������N���X�g�t�@�[�E�I�[�G���Y���́A�����Ɛ���̂Ȃ���n�Ɉړ]�������������ƍl���Ă���B
�@�ړ]���������邩�Ɍ����������������B�Ƃ��낪2009�N�A����}�V�����͊�n�����ꌧ�O�Ɉړ]����ӌ����������B����͌�ɓP��邱�ƂɂȂ������A���̎��ɂ͊��ɁA�����ł͐V��n�Ɋ�Ȃɔ����鐢�_���L�����Ă����B
�@���V�Ԋ�n�̈ړ]���Ïʂɏ��グ�����߁A���ė�����4���A2006�N�Ɍ��킵�����ӂ̂ق��̕�����藣���čl���邱�ƂɌ��߂��B���Ȃ킿�A����암�ɂ���ق��̊�n�̕Ԋ҂ƕ��V�Ԋ�n�ɒ�������C������9000�l�̃O�A���ړ]���B�������A������������ɂ킽��v��ŁA����������ɒx����Ă���B
��������A�Y���ꂪ���ȏꏊ
�@��2�����E���̖����A�ČR�Ɠ��{�R�̐퓬�ɂ���đ傫�ȋꂵ�݂𖡂�������ꌧ���́A�I�킩�炸���Ƃ��̒n�ɒu����Ă����ČR��n�́u���S�v��K���y������ƁA�����������Ă����B�������A���ł͂���ǂ��납�A�I�X�v���C�ƃ��C�v�������V���ȓ{��̉Ύ�ɂȂ��Ă���B
�@�����ɂ��鐭���Ƃ́A���ꌧ���̕s���Ɍ���œ��ӂ��Ȃ���A�J�l�ŕЕt������ƍl���Ă���悤�Ɍ�����B
�@���閯��}�c���́A�I�X�v���C�̔z����V�̌b�݂Ɗ��ł���B�V�[�i�C�g�̍q�������ł͓͂��Ȃ�������t���������͈͂ɓ���A�����ɑ���}�~�͂��啝�ɍ��܂邽�߂��B�܂��A���̃^�C�~���O�ŁA�����̈ꕔ�ŗ��������̗̗L�����咣���鐺���������A���{�̈��S�ۏ�ɑ��錻���I�ȋ��Ђ������Ă���Ƃ������Ƃ�����B����̓I�X�v���C�z���ւ̔���a�炰��͂����Ƃ����B
�@���������咣�ɂ��āA�m�������̖��g���́A���C�v�����̑O����u�Ƃ�ł��Ȃ��_���̔��v���ƍl���Ă����B���C�v�����́A��t���ӊC��ւ̒����̌R�͂̐N���Ɋւ���n�����f�B�A�̕������������ƂɂȂ邾�낤�B
�@�����������Ƃ�m��ƁA���V�Ԋ�n�ōR�c�s���ɎQ�����Ă�������Ⴂ�����̘b�̗��R�������Ă���B�F�l�����ƃr�[��������ł���ƁA�����ɉ���̓Ɨ��Ƃ����͂邩�Ȃ閲�̘b�ɂȂ�Ƃ����̂��B
http://jbpress.ismedia.jp/articles/print/36362
�č��哝�̂ɂ��܂Ƃ��u9.11�v�̒����e
2012�N10��23���iTue�j Financial Times
�i2012�N10��22���t �p�t�B�i���V�����E�^�C���Y���j
�@2001�N9��11���ȍ~��3�x�ڂƂȂ�č��哝�̑I���͏I�Ղɓ������B�������A�c�C���^���[�i���E�f�ՃZ���^�[�r���j�ւ̍U���������������e�́A���ł��قƂ�ǔ���Ă��Ȃ��B
�@22����ɍs����o���N�E�I�o�}�A�~�b�g�E�����j�[�����ɂ��Ō�̃e���r���_��ł́A���r�A�̓s�s�x���K�W�ł̕č��̎��ُP���������ł����������_�ɂȂ邾�낤�B�N���X�g�t�@�[�E�X�e�B�[�u���X�����r�A��g�ƐE��3�l���A�c�C���^���[�U���̂��傤��11�N��ɓ�����挎11���ɎE�Q���ꂽ�������B�����j�[���͂���ȍ~�����ƁA���̎����𗘗p���悤�Ǝ��݂Ă���B
�Ō�̃e���r���_��3����2�͒������
���N9��11���ɕ����W�c�ɏP�����ꂽ�x���K�W�̕č��̎��فkAFPBB News�l
�@�����j�[����22���A���_��̎i��߂�CBS�̃{�u�E�V�[�t�@�[��������K�v�Ȏx���i���邢�͍D���ɂł��鎞�ԁj�����炦�邱�ƂɂȂ�B
�@�V�[�t�@�[���́A���_��3����2�𒆓��Ɋ��蓖�ĂĂ���B�����ē��������グ��6�̃g�s�b�N�̂����A2�́u�����̃e�����Y���̐V�������ʁv�Ɋւ�����̂��B
�@�܂�A�x���K�W�̎����ɂ́u�����̑䓪�v����сu���E�ɂ�����č��̖����v�Ƃ���2�̃g�s�b�N�̍��v�Ɠ����x�̎��Ԃ���������\��������̂��B
�@�Ȃ��A����ȊO�ɂ̓C�X���G���ƃC�����̖��A����уA�t�K�j�X�^���ƃp�L�X�^���̖���2���g�s�b�N�ɑI��Ă���B
�@�V�[�t�@�[���̃��X�g�́A�č��哝�̑I���̓��_���9.11�����������e�𗎂Ƃ��Ă��邱�Ƃ�����ɂ��Ă���B�S�̓I�Ɍ����2012�N�̑哝�̑I���́A�č����܂��W���[�W�EW�E�u�b�V����������������Ă��邱�Ƃ��������̂ɂȂ��Ă���B2�l�̌��҂͊�{�I�ɁA�u�b�V���O�哝�̂��s���������^�c�̑ΏƓI�ȃp�^�[����L���҂ɒ�Ă��Ă���B
�u�b�V���O�哝�̂�1���ڂ�2���ڂ̈Ⴂ
�@�����j�[���́A�u�b�V��������1���ɐ��i�������j���e�����Y���i�P�Ǝ�`�j�ւ̉�A�����Ă���B�Ђ�I�o�}���́A�u�b�V�����̑�2�����y�����������̐����^�c������������邾�낤�B�L���҂ɑI������������Ă��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B��������́A�č������ʂ��邱��ȊO�̂��т����������̓��ɂ��ċc�_����ӗ~�����܂莝���Ă��Ȃ����Ƃ̗��Ԃ��ł�����B
�@�u�b�V������2001�N����2003�N�̊Ԃ�2�̐푈���n�߁A�搧�I�푈�̃h�N�g�����𐳎��ɍ̗p�����B�đI���ʂ�������2���ł̓f�B�b�N�E�`�F�C�j�[���哝�̂��������A�h�i���h�E�����Y�t�F���h���h�������X�R�����B���̌㊘�ɂ͊O�𐭍�̃��A���X�g�A���o�[�g�E�Q�[�c���𐘂����B�Q�[�c���̓I�o�}�����ɑ����Ă����h�����ɗ��C�����B
�@�u�b�V�����ƃI�o�}���͂��ꂼ��A�ČR�̑��h�����Q�[�c���ɑ������B22���̓��_�������l�́A�A�t�K�j�X�^���ł̐푈�\�\���ł͕č��j��_���g�c�̒�����ƂȂ��Ă���\�\�����Ȃ��Ƃ�����2�N�������Ƃ��v���o�����ƂɂȂ�B���̐��͍��ł��A�N������ł�����1000���h���ɏ���Ă���B
�@������9.11���˂�����ő�̃R�X�g�́A�u����܂ŋN����Ȃ��������Ɓv�ɂ���̂�������Ȃ��B�I�o�}����2008�N�A�u�b�V������ƌ��ʂ��A���E�ɂ�����č��̈АM������ƌ��ăz���C�g�n�E�X���肵���B�����Đ��X�̌v�����x�ɑł��o�����B
�ʂ�����Ȃ�������
�@�O�A���^�i���p�̎��e����1�N�ȓ��ɕ�����Ɩ�������A�e�����X�g��č����̈�ʂ̍ٔ����ōٔ��ɂ����悤�Ƃ�����A�������ǁiCIA�j�̉��o���I��点���草����֎~�����肵�悤�Ƃ����B���ӂ߂̋֎~�������āA�I�o�}���̐錾�͂������9.11��̐����̗����̒��ɏ����Ă������B
�@�哝�̏A�C��̍ŏ��̏T�ɂԂ��グ���A�A���u�ƃC�X���G���̘a���v���Z�X���J�n���鎎�݂����l�������B���̂��Ƃ���`���āA�C�X���G���̃x�����~���E�l�^�j���t�̓����j�[�����哝�̂ɂȂ邱�Ƃ�������x�����Ă���B
�@�挎�̑哝�̌��w����������ł͂ق�̏����������y�������̂́A�I�o�}���͋C��ϓ��̖��ɂ��Ă���������Ă��܂����B2009�N�Ƀv���n�Ŗ��炩�ɂ������Â��ɖY�ꋎ���Ă���A�j����̂Ȃ����E��ڎw���v������l���B�������Ƃ́A�I�o�}�������҂��Ă����Ē��i������G2�j���͂̐V����Ȃǂɂ����Ă͂܂�B
�@�����������]�̑����́A���炭�������Ȃ������̂��낤�B�A�C����ɑ啗�C�~���L���Ă��܂������Ƃ̑唼�́A�̌o���������͂܂��Ȃ��������ƂɋN������B�������A�č��̐�����2008�N�ȍ~�A�����قǕω����Ă��Ȃ��B
�@2012�N�ɓ����Ă���̃I�o�}���̊O�𐭍�̐�`����́A�E�T�}�E�r�����f�B���e�^�҂̎E�Q�ɏI�n����B�đI�Ɍ������I����ŃI�o�}���́A���s�ł��Ă���u�b�V�����Ƃ̍��ʉ����ł����Ǝv����{��̂قƂ�ǂɂ��āA�g�[���_�E��������S�����y���Ȃ������肵�Ă���B�O�����Ƃ̓O�ꂵ�����ʂ́A�����I����Ă��܂����̂��B
�@�e���Ɋւ��ẮA�C�O�̃e���e�^�҂ɑ��閳�l�@�U�����}�������ɂ�������炸�A�I�o�}���͈�ʂɎv���Ă������ア�B3�T�ԑO�܂ŁA�I�o�}���͍��ƈ��S�ۏ�Ń����j�[���ɑ卷�����Ă����B
�@�����A�r�����f�B���e�^�҂̎E�Q�͂����`������ς�����J�[�h�ł͂Ȃ���������Ȃ��B�����j�[����2�P�^�̍������Ă����I�o�}���̃��[�h�́A10�����߈ȍ~�A4�|�C���g�O��܂ŋl�߂��Ă���B
�@�I�o�}�����O�𐭍�Ń����j�[���̌�o��q���Ă��邱�Ƃ��������_����������B���钲���ł́A�ǂ���̕������r�A���ɂ��܂��Ώ��������Ƃ����ݖ�Ń����j�[����2�|�C���g���[�h���Ă����B
�o�ς��ő�̑��_�̂͂��Ȃ̂ɁE�E�E
�@11��6���̌��ʂ����E����ő�̗v���Ƃ��āA�o�ςɎ���đ�����̂͂Ȃ��B�����A�����ł����_�̃e�[�}�́A���O���ꂽ���Ƃ����_�ő�������Ă���B���ےʉ݊���iIMF�j�ɂ��ƁA���E�o�ςɐ�߂�č��̃V�F�A��2001�N�ȍ~8�|�C���g�ቺ���A23���ɂȂ��Ă���B
�@�ɂ�������炸�č��̋����͓͂��_�̃g�s�b�N�ɂȂ�Ȃ������B�ǂ����A���E�����郌���Y�Ƃ���9.11�ƒ��荇������̂͑��݂��Ȃ��悤���B�����j�[�����č��́u��Ԃ̒n���w�I�G�v�ƌĂɂ�������炸�A���V�A�͓��_�Ŏ��グ���邱�Ƃ͂Ȃ������B���������c�_���ꂸ�A���B�A�A�t���J�A�����ȊO�̃A�W�A�������b��ɂȂ�Ȃ������B
�@�c�_���邱�Ƃ͂�������̂ɁA���Ԃ��Ȃ��B�����ُk�A���邢�͂���ȏ�Ɍ��I�Ȏ��Ԃ������Ă��Ă��鎞�ɁA�I�o�}���͕č��̑��z�̍��h����ێ�������Ȃ��ƍl���Ă���A�����j�[���͍��h���啝�ɑ��₻���Ƃ��Ă���B�����j�[���͔N��15�ǂ̐V�����t���Q�[�g�͂ƕ��m��10���l����������B
�@���҂Ƃ��A�j���������C�����̕������߂ɊÂ邭�炢�Ȃ�A�푈���n�߂����������Ǝv���Ă��邱�Ƃ����������B�����Ƃ��A�I�o�}���̌��t���z�ʒʂ�Ɏ~�߂鎯�҂͂قƂ�ǂ��Ȃ����B
�@�ǂ���̌����A�u�b�V�����ɂ��ăv���X�̕]�������锭�����J�����ɑ������邱�Ƃ͂Ȃ����낤�B�������A�ǂ�����u�b�V��������Ɏc�������E����E�p����ӎv��͂��Ȃ��悤���B
By Edward Luce
http://jbpress.ismedia.jp/articles/print/36370
�������čl���ׂ��u�č���IT�K�o�i���X�v
���{��Ƃ͂Ȃ���������Ȃ������̂�
2012�N10��23���iTue�j ���R ����
�@���Ђ̃T�[�r�X�́u�O���[�o���ACRM�A�N���E�h�v���L�[���[�h�Ƃ��Ă��邽�߁A��Ƃ���u�O���[�o��������ɓ��ꂽCRM�v�Ɋւ��鑊�k����P�[�X�������B
�@�����ʔ����̂��A�����͌����A�u�܂��͓��{�A���̌�͖���v�Ƃ����b�����܂��ɑ唼���߂�Ƃ����_���B�悭�b���ƁA�O���[�o���v���W�F�N�g�̂���ł�肽�����A�g���n�Ƃ̒����h���K�v�Ȃ̂ŁA�܂��͓��{�Ő��ʂ��o���Ă���A���̐�ǂ��Ȃ邩�͖���A���Ƃ����B
�@���͂��̎��_�ŁA�O���[�o���v���W�F�N�g�Ƃ��Ă̐����͂��łɂ����Ԃ��������ƌ����Ă悢�B�u�����v�̒�`�ɂ����̂ŗ��\�Ȃ��Ƃ͌����Ȃ����A���m�ɂ́u�v���ɐ��ʂ��グ�邱�Ƃ͓���Ȃ����v�Ƃ������Ƃ��B
�O���[�o���v���W�F�N�g�͂Ȃ���������̂�
�@���̊�Ƃ̋��݂������߂ɂ́A���R�̂��ƂȂ���D�ꂽ�Ɩ��v���Z�X���e���e���_�Ŏ������ׂ������A������x����V�X�e���͓������̂ł��邱�Ƃ��]�܂����B����ɂ���āA�O���[�o���ł̋Ɩ����x���̒�グ��A�v���Ȉӎv����Ȃǂ��\�ƂȂ�B
�@�܂��A������������邽�߂�IT�Ɋւ��邨���̎g������A�v���W�F�N�g�̐i�ߕ��A�������S�Ȃǂ��A�O���[�o���ň��̃��[�������Ȃ���Ă���`���]�܂����B
�@������������A�̖������߂Ď�点��͖̂{�Ђ�IT����̎d���ł���B���ꂪ������uIT�K�o�i���X�v���B�@
�@�Ƃ��낪�A�����������u�����̉�Ђ�IT�K�o�i���X�͂����������̂��v�Ƃ������̂����݂��Ȃ��܂܃O���[�o���ł̃v���W�F�N�g��i�߂�ƁA�����邱�Ƃ��e������ɐU���A�ʑΉ��ɂȂ��Ă��܂��B�o�c�̓O���[�o�������Ă�����̂́AIT�ɂ�����}�l�W�����g������ɂ��Ă����Ă��炸�A�{�ЂƂ��Ă̈ӎv��ʂ����Ƃ�����Ƃ������B
�@���ꂪ�A���I��邩����Ȃ��O���[�o���v���W�F�N�g�ݏo���Ă��܂��傫�Ȍ����ƌ����悤�B
�@�č���IT�K�o�i���X�����s�����͖̂�10�N�O�B�����A���{��Ƃ͈ꐶ�����C�O�̐�i��Ƃ̃x�X�g�v���N�e�B�X���w�K���Ă���ł������B�������قƂ�ǂ��u�w�K�v�ɗ��܂��Ă����B
�@���ɂȂ��āu���̍��ɗ͂����Ă���Ă����E�E�E�v�Ƃ����Q�����������Ă������ł���B���������́A�����܂ŃO���[�o���ł̐v���Ȉӎv�����IT�̑S�̍œK���K�v�ɂȂ�ƃC���[�W�ł�����Ƃ͂قƂ�ǂȂ������B�{���̈Ӗ��ł�IT�K�o�i���X�̕K�v���͍��ɂȂ��ċC�Â����Ƃ�����Ђ������̂ł͂Ȃ��낤���B
IT�K�o�i���X�̎�����W����u�l�̖��v
�@�M�҂͕K�������č����́u�e���ʎ���͖������ċ��͂ɉ��ł���������IT�K�o�i���X�v�ɑ�^���Ƃ����킯�ł͂Ȃ��B���ۂɁA�Ċ�Ƃ̃��[�J���X�^�b�t�Ƃ��āgUS Centric�h�i�A�����J�̈�ɑ̐��j�̗ǂ��ʂ������ʂ��o�����Ă����B
�@�������A����̂悤�ɐ��E���̎s��ŁA�ǂ��ʼn����N�����Ă��邩����Ɏ��悤�ɕ�����悤�ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��o�c�����ł́A�����C�ɓ���Ȃ��X�^�C�����Ƃ��Ă��A���͂ȃK�o�i���X������ƂȂ��Ƃł͑傫�ȈႢ���o�Ă���B
�@�Ƃ͂����A�����͕������Ă��Ă��Ȃ��Ȃ��ł��Ȃ��̂����{��Ƃ̌���ł���B
�@���{�̃O���[�o����ƂƐڂ��Ă��āA�č���IT�K�o�i���X�ɋ߂����̂���������̂͑�������̂ł͂Ȃ����Ɗ�����Ƃ�������B
�@���������R������̂����A�����I�Șb�Ƃ��Č����Ɓu�l�̖��v�͂�͂�傫���B�l�ƌ����Ă��\�̘͂b�ł͂Ȃ��A���N�|��ꂽ�g�D�E��������㉺�W�ł���B
�@���Ƃقǂ��܂��Ƀv���p�[�u���͋����A�C�O�̂��������̋��_�ɓ��{�ŏ\���Ɍo����ς�y�Ј��������肷��B���������l������ɁA�u�{�Ђ͂����������Ƃ��������v�ƌ����Ă��A�Ȃ��Ȃ�����Ȃ肢���Ȃ����̂��B
�@���X�ɂ��āu����͖{�Ђ̓s�����낤�B���n�ɂ͂��܂胁���b�g���Ȃ��v�ƌ��n�������N�̗͊W�������o���Č����Ԃ��P�[�X�������B
�@��Ђ̃��[����K�o�i���X�Ƃ͈Ⴄ�Ƃ���ł������������ɗ��B����Ɩ{�Б�����߂��K�o�i���X��A��_�Ȕ��z�̃v���W�F�N�g��悪�������Ƃ��Ă��A�܂��͌��n�̐�y��������Ȃ��ƁA�Ƃ����b�ɂȂ��Ă��܂��̂ł���B
�@�������A�č���ƂƂ͌���I�ɈႤ�Ƃ��낾�B������̏ꍇ�́A�d���Ől���ق��Ă���̂ŁA����Ӗ��A������݂��Ȃ��V���v���ł���B�t�Ɏd�����X���[�Y�ɂ������邽�߂̂��̂Ƃ��āA������ӔC�̖��m�������߂��AIT�ɂ����Ă̓K�o�i���X���m�����Ă��Ȃ��Ƃނ���@�\���Ȃ��B
�@���{�ł��A������݂̂Ȃ��V���̉�Ђł́A�����悤�ȃO���[�o����ēW�J�̃v���W�F�N�g�𗧂��グ�A���R�Ƃ���Ă̂����肵�Ă��܂��B
�u�Ǘ��v���ړI�ɂȂ��Ă��܂�����
�@�܂��A�`���ł���G�ꂽ���A�u�K�o�i���X�v�u�}�l�W�����g�v�Ƃ����ƁA�{�����ʂ��グ�邽�߂̂��̂��A���{��Ƃɂ����Ă͂Ȃ����u�Ǘ��v�̘b�ɂȂ��Ă��܂��Ƃ�����l�b�N���B
�@��ʓI�ɕč���Ƃł́AIT�̊��p�͂����܂ł��e���_��e���傪�~�b�V�������ʂ����Đ��ʂ��グ�邽�߂̂��̂ł���B�����āA����IT�����p���邽�߂̍œK������I�Ȏ��_�Œ���̂��uIT�K�o�i���X�v���ƌ����Ă��悢�B�܂�u�U�߁v�̂��߂̂��̂Ȃ̂��B
�@���������{��IT�K�o�i���X�́A�Z�L�����e�B�A���������ATCO�팸�Ȃǁu���v�̘b�ɑ����Ă��܂��������B�����炭IT���傪�r�W�l�X����ɉ������Ă��邱�Ƃ��N�����Ă���̂��Ǝv���邪�A���̍��{�I�Ȋ��Ⴂ�͖{���ɖ��ł���B
�@����Ɍ����ƁA���̎�̘b������̂͑�̂�����x�ȏ�̑��ƂƂȂ邪�A����������ƂقǑg�D���c����ɂȂ��Ă��āA�{���̖ړI��Y��ĊǗ��ɖڂ������Ă��܂��X��������B
�A�[���[�A�_�v�^�[�قǕ����Ă���u�g���E�}�v
�@����1�_�B������悭����Ŏ��ɂ���b�����A�ߋ��ɃR���T���e�B���O�t�@�[�����g�����Ƃ��낤�܂��������A�g���E�}�ɂȂ��Ă���Ƃ����P�[�X������B
�@���ɁA���v�ɑO�����ŐV�������ƂɎ��g�����Ƃ��Ă�����ƂقǁA�i���b�W������R���T���e�B���O�t�@�[���Ɉ˗����A�O���[�o���W�����x����ڎw���ėl�X�ȃg���C�����Ă����B�������A���z�̔�p�������������̂̐��ʂ�����ꂸ�A�Ō�͗��������ɂȂ��Ă��܂��B�����Ďc�����̂́u�O���̎���肽��ɂ��ڂɑ������v�Ƃ����g���E�}�ł���B
�@�����A����͌����ăR���T���e�B���O�t�@�[�������������킯�ł͂Ȃ��B���݂��Ɏ�T�肾�����̂ł��܂������Ȃ������Ƃ������Ƃ��Ǝv���B�������A�N�������Ƃ͌���Ȃ��B
�@���̃g���E�}�ɍ��ł��x�z����Ă���ƁA�Ȃ��Ȃ��������O�̃e�[�}�ʼn����n�߂�͓̂���̂ł���B���ɓ�����m��l���g�D�̏�w���ɂ���Ƌ��┽���͂����܂������̂�����B
�ߋ��̎��s�₵����݂��C�ɂ��Ă���]�T�͂Ȃ�
�@�ȏ�̂悤�ɂ������̎�������āA���{��Ƃɂ�����O���[�o���ł�IT�K�o�i���X�̊m���͋ɂ߂ē���e�[�}�ƂȂ��Ă��܂��Ă���B�ނ���Y����Ă���ƌ����Ă��悢�B
�@�����͕č����̌o�c��ے肷���Ƃ���������Ă���B�ł͓��{�����m�����ꂽ�̂��Ƃ����ƁA�K�����������Ƃ͌����Ȃ��B�傫�������Ɖ����ς���Ă��Ȃ��̂ł���B
�@���ꂾ���r�W�l�X�̊����O���[�o�������Ă������A�ߋ��̎��s�₵����݂��C�ɂ��Ē���Ă���]�T�͂Ȃ��B�{�Ђ̋��͂ȃ��[�_�[�V�b�v�����āA���E�K�͂Ńv���W�F�N�g�������ł���y�����邱�Ƃ͋}���ł��낤�B
�@���{��Ƃ̊e�����_�A�㗝�X�Ȃǂł����{�̖{�Ђ̃��[�_�[�V�b�v�����҂��Ă���̂ł͂Ȃ����낤���B����̊�@�����o�l�ɁA������IT�K�o�i���X�̊m�����}���łق����Ɗ肤�B
http://jbpress.ismedia.jp/articles/print/36340
�ǂ�Ȃɋ����Ȃ��Ă��������č��ɑ���Ȃ����R
�O���[�o���K�o�i���X�̂��̔j��҂́A�n���҂ł͂Ȃ�
2012�N10��23���iTue�j ��� ����
�@�O���[�o���K�o�i���X�Ƃ́A�u�n�������v�Ɖ��߂���ƌ�����邪�A���E�e���̈قȂ��������ӌ����܂��͓������A�n�����邢�͐��E�S�̂���肭�Ǘ��^�c���Ă������Ƃł���B
�O���[�o���K�o�i���X�ƍ��ی�����
�@�n���ɂ́u���E���Ɓv�����݂����A�匠��L���鍑�Ƃ������ȗ���ŕ���I�ɑ��݂��Ă���B���Ƃɂ͎匠���邢�͎匠�҂����݂��邪�A���ێЉ�ɂ͊e���Ƃz���ē�������匠���邢�͎匠�҂����݂��Ȃ��B
�@���݂̍��ێЉ�́A�e���̍��ӂ̉��A���a�ł���͈͂ŋ��́E�������邱�Ƃ���{�Ƃ��ĊǗ��^�c����Ă���A����ȏ�̃O���[�o���K�o�i���X�̃V�X�e���͑��݂��Ȃ��B���ʂ����鏫���ɂ����Ă��A�匠���Ƃ����鐢�E���Ƃ̒a����\�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��ł��낤�B
�@�O���[�o���K�o�i���X�̍ő�̒S����ł���u���ۘA���v�́A���̌����F����O��Ƃ��Đݗ����ꂽ�B
�@�u���A���́v�̑�1�́u�ړI�y�ь����v�̑�1���u���ۘA���̖ړI�v�ł́A��1�������3����3�̖ړI�������A�����i��4���j�� �u�i���ۘA���́A�j�����̋��ʂ̖ړI�̒B���ɓ����ď����̍s���a���邽�߂̒��S�ƂȂ邱�Ɓv��搂��Ă���B
�@7���ڂ���Ȃ��2���u�ړI��B������ɓ������Ă̍s�������v�̑�1���ŁA�u���̋@�\�́A���̂��ׂẲ������̎匠�����̌����Ɋ�b�������Ă���v�Ƃ��A����ɁA��7���ł́A�u���̌����́A��7�͂Ɋ�����[�u�̓K�p��W������̂ł͂Ȃ��v�Ƃ̏�����t���Ă�����̂́A�u���̌��͂̂����Ȃ�K����A�{���ア���ꂩ�̍��̍����NJ������ɂ��鎖���Ɋ����錠�������ۘA���ɗ^������̂ł͂Ȃ��A�܂��A���̎��������̌��͂Ɋ�����ɕt�����邱�Ƃ��������ɗv��������̂ł��Ȃ��v�Ƃ��Ă���B�i�ȏ�̑�������ъ��ʏ����́A�M�Ғ��L�j
�@�܂�A���A���͂�����p����A�����̃O���[�o���K�o�i���X�Ƃ́A�u���E�e���̎匠�����̌����Ɋ�b�������āA�e���̍s���a���邱�Ɓv�ɂق��Ȃ炸�A�܂��Ă�A�e���卑������I�ȓ������s�����̂ł͂Ȃ��B
�@�܂��A�e���́u�����NJ������ɂ��鎖���Ɋ����錠���͂Ȃ��A���̉������������ɗv��������̂ł��Ȃ��v�Ƃ̊�{���O�̍��ӂ̉��ɐ������Ă���B
�@����A�u�����̍s���a�v���邽�߂ɂ́A���̊�ƂȂ�K�́A���ӌ`���̂��߂̋@�\�A�Ǘ��^�c���邽�߂̐��x�E�V�X�e���Ȃǂ��K�v�ł���A�ߔN�A�������u���ی������i�O���[�o���R�����Y�j�v�ƌĂԂ悤�ɂȂ����B�O�q�̍��A����э��A���͂́A���̏ے��I���݂ł���B
�@�����A�u���ی������v�ƌĂ�Ă�����̂ɂ́A���ۘA���AIMF�i���ےʉ݊���j�AWTO�i���E�f�Ջ@�\�j�A���E��s�A�����āANATO�i�k�����m���@�\�j�AEU�i���B�A���j�AADB�i�A�W�A�J����s�j�AASEAN�i����A�W�A�����A���j���̒n�拦�́i�����j�@�\�Ȃǂ�����B
�@�����̋@�\�A������x����K�͂�x�́A��2�����E����A���E�I�Ȕe�����������č������S�ƂȂ�A���̃C�j�V�A�e�B�u�ɂ���č��ꂽ���̂������B
�@���̂悤�ɁA�u���ی������v�ƃO���[�o���K�o�i���X�̌`���ɂ́A���̎���̔e���卑�������A���A�[���W����Ă���̂ł���B
�e���卑�ƃO���[�o���K�o�i���X�̂��߂́u���ی������v
�@���ۖ@���A�d�v�ȁu���ی������v��1�ł���B�ߑ㍑�ۖ@�́A�@���푈�i1618�`48�N�j���I���������E�G�X�g�t�@���A���i1648�N�j�ɋN�������邱�Ƃ��A�����̌����҂��F�߂Ă���B
�@�c��ɂ��ꐧ�x�z�̒������u���v����u����v�ֈڍs���Ă������̋ߐ��O���̃��[���b�p�ɂ́A���łɗ̈�匠���Ƃƃ��[���b�p�u���ێЉ�v���������A�l�ԁA���i�A���{�̈ړ��ɔ������S��M���̊m�ۂƍ��Ƃ̍��ۓI�����̑��ݒ����̕K�v�������Ă����B
�@�܂�A�����̃��[���b�p�́A���ێЉ�����������E�̐�i�n��ł���A�܂��A�������ׂ����@���푈��p���𒆐S�ɊC�㌠�͂̑��D�킪�J��L�����Ă������Ƃ��A���̔w�i�ɂ���B
�@�@���푈�̌��ʁA�_�����[�}�鍑�����A�E�G�X�g�t�@���A���ɂ���āA�]���̃J�g���b�N����̌��Ђƍ��Ƃ̌��͂����������̒��ŕ������Ă����I�ȑ̐�����|����A�u�D�ʂ��邢���Ȃ錠�Ђ��F�߂Ȃ������̓Ɨ����Ƃ���b�Ƃ��鍑�ې��x�v�i�C�^���A�̍��ۖ@�w�҃A���g�j�I�E�J�b�Z�[�[�j���a�������B
�@���ې����ɂ����鍑�ƊԂ́u���͋ύt�i�o�����X�E�I�u�E�p���[�j�v�̊T�O�����̍��ɐ��܂�Ă���B
�@���̌�A���ێЉ�́A�����̔e�������郈�[���b�p�𒆐S�Ƃ��āA��1�����E���܂łɁA�����̊�{�I���ۖ@�K�y�ь����i�̈�匠�����A���C���R�̌����A���Ɓi�匠�j�Ə��Ɋւ���@�A�O���y�ї̎��W�@�A���@�A�O��I�ی�Ɋւ���K���A�����Ɋւ���K���Ȃǁj���m�������B
�@���ۖ@���x�́A��ʓI�ɁA1648�N����1918�N�܂ł̓`���I���ۖ@���x�ƁA��1�����ȍ~�i1919�N�`�j�̌���I���ۖ@���x�ɕ�������悤�ł���B
�@���̌�҂̑Ώۊ��ԂɊY�������2�����I��������I���܂ł̊ԂɁA���ێЉ�́A�ă\2�卑�𒆐S�Ƃ��ē����A���ۘA�����ݗ�����A���͍s�g�̈�ʓI�֎~�ƏW�c�i�I�j���S�ۏ�𐧓x�������B
�@�܂��A��㏈���̒��ŁA�l�̌����y�і������������F�߂��A�����̍����Ɨ������B��A���n���̃v���Z�X�́A1960�N�̍��A����Łu�A���n�����A���l���ɑ���Ɨ��t�^�Ɋւ���錾�v���̑�����A1960�N��Ɋ��������B
�@���I����́A��ʔj��̊g�U��n�整���A���ۃe���Ȃǂ̐V�����`�̕������������钆�A�ă\�̋����j�팸���i�W���A�l���ɑ���߂�푈�ƍ߂ɑ���Y������ł̍��ۖ@�̔��W�������A����J���ւ̊S�����܂����B
�@����A�����ɂ����鐼�����R�Љ�́A�č��̃w�Q���j�[�̉��A�č��𒆐S�Ƃ��đO�q�̂悤�Ȑ����A�o�ρA���S�ۏᓙ�ɌW��鍑�ۋ@�\�y�т�����x����K�͂�x�����A�O���[�o���K�o�i���X�𐄐i�����ŁA�ɂ߂ďd�v�Ȗ������ʂ����Ă����B
�@�ȏ�A�~�X�q�ׂĂ����̂́A���݂̐��E�������A�����Ȏ匠���Ƃ���b�Ƃ��āu���ێЉ�v�������������B���������Ă𒆐S�ɁA�����ƌ����J��Ԃ��A3���I���]�̒������j��ςݏd�˂č��ꂽ�������Ċm�F���邽�߂ł���B
�@�����āA����܂łɍ��ꂽ�@�\��K�́A���x�́A�ȒP�ɔj�āA�����ɐV���Ȓ����ɒu���������肷�邱�Ƃ��ł�����̂ł͂Ȃ��A�����Ċ��ɂ��̌n�I�ɂł��Ă���B�܂��A���{�A���B���̐�i�����͂��Ƃ��A���W�r�㍑�ɂƂ��Ă�����\�ŁA�����I���L�v�Ȃ��̂ƂȂ��Ă���A���ێЉ�ɐ[�����t���Ă���B
�@���́A�č��̈���I�ȏ����ŏI������B���̔s�҂ƂȂ����\�A�i���V�A�j����ђ����́A�����A�č���Ɏx�z�ɔ����A�������đ��ɉ��̐��i��ڎw���Ă���B
�@���ɁA�����́A���N�A���ے����̌`���ɎQ��ł��Ȃ��������A1970�N�㖖�ȍ~�A���ٓI�Ȍo�ϔ��W�q�Ƃ��ċ}���ɑ䓪���A���ێЉ�ł̔����͂債�Ă���B�����āA���������u���ۋ�������ł��j��A�w�����������I�ȍ��ې����o�ϐV�����x���\�z����v�Ƃ̍\�z��ł��o���Ĉȗ��A�����Ȃ�u���ؓI�V�����v�̊m���������咣����悤�ɂȂ��Ă���B
�O���[�o���K�o�i���X�̔j��҂ɂ͂Ȃ�Ă��n���҂ł͂Ȃ�
�@�����́A1978�N�A�������̎w���̉��A�u���v�J���v�����肵�A�ȍ~�A30�N�]�ɂ�������āu��Ղ̌o�ϔ��W�v�𐋂����B
�@�����̐��E�o�ϋy�ѓ��A�W�A�n��o�ςւ̗Z�����邢�͓����͋}���ɐi�݁A2008�N�ɂ́A�O�ݏ������ɂ����āA���{���Đ��E�ő�̊O�ݏ������ƂȂ����B�܂��A2009�N�A�����́A�h�C�c���Đ��E��1�ʂ̗A�o�卑�����đ�2�ʂ̗A���卑�ƂȂ����B
�@��2010�N�A�����́A�S�̂̋K�͂ɂ����ē��{�𗽉킵�A���E��2�ʂ̌o�ϑ卑�ƂȂ�A2030�N�O��ɂ́A�č��������ǂ����������ł���B
�@�����̍��h��́A�o�ϔ��W�ƂƂ��ɁA�ߋ���\���N�ɂ킽���ċ��ٓI�ȃy�[�X�ő����𑱂��Ă���B
�@���\���ꂽ���h��̖��ڏ�̋K�͂́A2010�N�x�̖�9.8�����O�Ƃ��āA2012�N�x�܂�23�N�A���ŁA�o�ϐ�������D�ɒ�����2���i�\�����j�̐L�ї����L�^���A�ߋ�5�N�Ԃ�2�{�ȏ�A�ߋ�24�N�ԂŖ�30�{�̋K�͂ɖc���ł���B�������A�����̍��h�֘A�x�o�́A���\���l��2�`3�{�ɏ���Ă���ƌ����Ă���B
�@���̌��ʁA�u�ڋߑj�~�^�̈拑�ہv�헪�Ɋ�Â��A�C��R�̑����ߑ㉻�A�F���E�T�C�o�[��Ԃɂ�����R���\�͂̋����A���A�X�e���X���\�������������퓬�@�A�Ί͒e���~�T�C���iASBM�j�Ȃǂ̊J���E���������}���ɐi�s���Ă���B
�@�����̍��͂́A���炩�ɋ���ƂȂ��Ă���B���E�卑�E�č��Ƃ̗͂̃o�����X�͑��ΓI�ɕω����A���A�W�A�͂��Ƃ��A���E�S�̂ɑ傫�ȉe�����y�ڂ����Ƃ͂��͂�ے�ł��Ȃ��B
�@���̒����̑䓪�ɂ���āA�u�Ē��̔e�����͂��蓾�邩�v�̖₢�ɑ��āA���Η��A�n�E�E�J�����C�����w�����͓��A�W�A���ǂ��ς��邩�\21���I�̐V�n��V�X�e���\�x�i�����V���j�́A�u��A�ΏƓI�ȓ��������肤��v�Əq�ׂĂ���B
�@����1�́A�W�����E�A�C�P���x���[���̎咣�ŁA�v��Ɓu�č������S�ƂȂ��č����IMF�A���E��s�AWTO�Ȃǂ͍��ی������ł���A���{�A���B�Ȃǂ̐�i�������͂��߁A���W�r�㍑�ɂƂ��Ă��L�v�ȁA�Ӗ�����@�ւł���B����������ɑウ�āA�����ɂ����Ɠs���̗ǂ����̂���낤�Ƃ��Ă��A�e�Ղɕς��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B���݂̐��E�����́A����Ȃ�Ɋ��ŁA�ȒP�ɉ�����̂ł͂Ȃ��v�Ƃ�����������֕s�\�_�ł���B
�@����ɑ��āA�D���m�ꎁ�̂���1�̌����́A�u���������W�r�㍑�ł��邱�Ƃɂ͕ς��Ȃ��A�卑�̐ӔC���ʂ����Ƃ������A�������v��D�悷��B�C���h�A�u���W���Ȃǂ����l�ŁA���̌��ʁA���E�͂܂��܂����ɉ����A���݂̃O���[�o���K�o�i���X�̃V�X�e���́AWTO�̃h�[�n�E���E���h�̂悤�ɋ@�\�s�S�Ɋׂ�A�s���l�܂��Ă����v�i�ȏ�A�v��j�Ƃ̌����������̔ߊϘ_�ł���B
�@�����́A���O���[�o���K�o�i���X�̔j��҂Ƃ��Ĉ����Ă��邪�A�V�O���[�o���K�o�i���X�̑n���҂Ƃ͌��Ȃ���Ă��Ȃ��B
�@���E�̗��j��U��Ԃ�ƁA���ێЉ�ł́A�D�z�����߂鐨�͂ƑΓ������߂鐨�́A����ێ���}�鐨�͂ƌ���Ŕj��}�鐨�́A���͂̒n�ʂɂ��鐨�͂Ǝ�҂̗���ɒu����t�P�╜����}�鐨�́A���邢�͐�i���͂ƐV�����͂Ȃǂ̑Η��E�R�����J��Ԃ���Ă����B
�@���ɁA���݂́A�Ē��̔e�������Ƃ̎w�E������悤�ɁA���ۏ���_�C�i�~�b�N�ɓ����\�����߂Ȃ��琄�ڂ��Ă���B
�@����A���݂̐��E�ɂ́A�ߐ��ȍ~�A���[���b�p�𒆐S�ɐ������ꂽ���ۖ@���x�ƁA��2������A�č��̔e���̉��ɍ��ꂽ�����̍��ۋ@�\�₻����x����K�́A���x������B
�@�u�����钆���A�C���h�A���V�A�A�u���W���Ȃǂ̍��͑���ɔ����āA���E�I�A�n���I�ȕx�Ɨ͂̕��z�͕ω�����ł��낤�B���łɓ��A�W�A�i�A�W�A�����m�n��j�́A�����̑䓪�ƂƂ��ɁA���܂��܂ȕϗe�𔗂��Ă���B
�@�������A�č��𒆐S�Ƃ��铌�A�W�A�̒n��I�Ȉ��S�ۏ�V�X�e�����Ɏx����ꂽ���������S�ʓI�ɕω�����Ƃ́A�����ɍl���ɂ����B�܂��A���A�W�A�����Đ��E�ɒ������S�̒������`�������Ƃ͌���Ȃ��B
�@�����́A�o�ϗ͂ƌR���͂ɂ��Č����A������Ȃ����E�����ł���B�����āA����2�̓ˏo�����n�[�h�E�p���[�ɂ��e���́E�x�z�͂��g��I�ɍs�g���A�܂��͓��A�W�A�ɂ����钆�ؓI�n�擝���𐬂������A����ɔ��W�����āA���E�I�ɉe���͂��g�傷��헪�𐄐i���Ă���悤�Ɍ�����B
�@�������Ȃ���A�����_���猩�ʂ��������A�����������̍��ی������ɑウ�āA���L�p�����͓I�ŁA�����̍����^������\�t�g�p���[��̑�ֈĂ���A�����𒆐S�Ƃ����O���[�o���K�o�i���X���m���ł���e���卑�ɂȂ�邩�Ƃ̖₢�ɂ́A�傢�Ȃ�^�╄��t������Ȃ��B
�@���ێЉ�́A�i1�j���R�����A�i2�j�����`�A�i3�j�l���A�i4�j�@�̎x�z�����ׂ����ʂ̉��l�A���Ȃ킿���ی������Ƃ��čL������Ă���B
�@����ɔ����āA�����́A���܂��ɒ��؎v�z�|�s�����ȏ㉺�W�̉؈Β����|�Ɏ����Ă���B���܂��A���Y�}��}�ƍق��������A�S�̎�`�y�ы����x�z�̐����̐���ς��Ă��Ȃ��B
�@���̒����𒆐S�Ƃ����O���[�o���K�o�i���X���A���A�W�A���ӂ̂قƂ�ǂ̍������Đ��E�e���́A�͂����ŋ�������邱�Ƃ��������Ƃ��Ă��A����]�ނ��Ƃ͌����ĂȂ��ł��낤�B
�@�����ČJ��Ԃ��A���E�Ɍ������č��ی������Ƃ����\�t�g�p���[��ł��Ȃ������ɂ́A�O���[�o���K�o�i���X�̒��S�Ƃ��Ă̔e���卑�̒n�ʂ��߂鎑�i��������Ă��Ȃ��Ƃ������ƂɋA������̂ł͂Ȃ����B
�@����A���ې����̏œ_�ƂȂ铌�A�W�A�́A���ؕ����A���{�����A�q���h�D�[�E���������A�C�X���������A���������Ȃǂ����݂��Ă��邱�Ƃ�������炩�Ȃ悤�ɁA�n�搭���̔��W���x��Ă���B
�@�������A���{���͂��߂Ƃ��钆�����ӂ̓��A�W�A�����́A�����̑卑���ƂƂ��ɁA�u�@�̎x�z�v�ɑ�\����錻�s�̐��E������ے肷��u�͂����ł̋����v�����́A���Ƃ��Ă��j�~�������ƌ��ӂ��Ă���̂͊ԈႢ�Ȃ��낤�B
�@���̂��߁A�e���́A�h�q�́i�R���́j���������A�܂��A�������邢�͒n��Ƃ̘A�g�E���͊W���\�z���A�u�֗^�v�u�w�b�W�v�u�o�����V���O�v�Ȃǂ̐헪�I�I��������g���āA���̑Ή��ɍאS�̒��ӂ��u�����������킢�v�A�������u�����Ă͒ʂ�Ȃ��킢�v�������Ă������ƂɂȂ낤�B
http://jbpress.ismedia.jp/articles/print/36345
�@
|
|
|
|
���̋L����ǂl�͂���ȋL�����ǂ�ł��܂��i�\���܂�20�b���x���Ԃ�������܂��B�j
�@
�����̃y�[�W�̂s�n�o���@�@�@�@�@ �����C���� > �푈b10�f����
|
|
 �X�p�����[���̒����猩���o�����߂Ƀ��[���̃^�C�g���ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B
�X�p�����[���̒����猩���o�����߂Ƀ��[���̃^�C�g���ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B���ׂẴy�[�W�����p�A�]�ځA�����N���������܂��B�m�F���[���͕s�v�ł��B���p�������N��\�����Ă��������B