http://www.asyura2.com/12/senkyo131/msg/163.html
| Tweet |
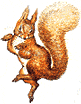
刑事裁判を考える:高野隆@ブログ 2007年05月14日 「二重の危険」
東京高裁第10刑事部(須田賢裁判長)は、5月10日、村岡兼造元官房長官に対する政治資金規正法違反事件(不記載)について、1審東京地裁の無罪判決(東京地裁平成18年3月30日判決[未公刊])を破棄して、禁固10ヶ月執行猶予3年の逆転有罪判決を言渡した。新聞報道によると、日本歯科医師連盟から平成研究会(橋本派)への1億円の献金を村岡氏の指示で収支報告書に記載しなかったという滝川俊行氏(元平成研究会事務局長)の証言について、東京地裁が「思い込みや想像が多く、信用できない」「[他の有力政治家に]塁が及ぶのを避けるため虚偽供述した可能性が大きい」としてその信用性を否定したのに対して、東京高裁は「根幹部分は一貫しており、信用性が高い」「誰かをかばうため虚偽供述する理由はない」としてその信用性を肯定した(日経新聞2007年5月11日朝刊13版39頁)。
これは、刑事裁判における「二重の危険」を禁止している憲法がありながら、無罪判決に対する検察官上訴を認めているわが国の刑事司法が日常的に作り出している多数の悲劇の一つである。
どんなに有力な政治家や資産家でも国家権力には及ばない。東京地検特捜部は日歯連や平成研究会から段ボール箱数十個分の証拠を押収し、関係者数十名を呼び出して事情聴取し、さらには滝川氏や日歯連幹部の身柄を拘束して連日長時間の取調べを行って、滝川氏らの自白を獲得して、この事件を起訴したのである。無実を主張する村岡氏にも彼を弁護する弁護人にもこのような権限は全く与えられていない。そして検察は自分たちが収集した膨大な資料の中から被告人の有罪を証明する証拠だけを裁判所に提出する。それ以外の証拠は検察庁の倉庫に眠ったままだ。無実を主張する被告人は限られた資源で自分の無実を証明する証拠を探索するが、結局めぼしい証拠は既になく、乏しい資料を土台に法廷戦術を駆使して検察の圧倒的な有罪証拠に対して絶望的な闘いを挑むのである。それは経済的にも精神的にも、また、肉体的にもストレスに満ちた戦いなのである。
このような苦労もほとんど報われることはない。刑事第1審否認事件の無罪率は1%ほどである。この現実と身柄拘束からの早期解放(否認すれば保釈は認められない)とを秤にかけて、闘わずして諦める被告人が非常に多い。要するに、無罪判決を獲得するというのは、被告人自身の強靭な精神力や弁護人の能力と、そして、幸運がなければ、なしえない事柄である。村岡氏は1審の無罪判決言い渡しの際に歓喜の涙を流したそうだが、無罪を獲得した被告人は誰もみなそうである。
しかし、これで終わったわけではない。まだ続きがある。検事控訴である。
そして、高裁の判事たちは、地裁の裁判官たちよりもさらに一層検察官びいきである。
わが国の控訴審は「事後審」と呼ばれ、1審の手続や事実認定に誤りがあるかどうかを判断するために、1審の記録だけを審査するのが原則である。裁判をもう一度やり直すわけではない。新聞の見出しによく「高裁も実刑」などと書いてあるのをときどき見かけるが、あれは間違いである。正しくは「高裁、一審の実刑判決を是認」ということになる。高裁では新しい証拠を取調べないのが原則であり、「やむを得ない事由によって第1審の弁論終結前に取調を請求することができなかった」場合でない限り、新しい証拠を取調べないことになっている(刑訴法382条の2、393条第1項)。
高裁の裁判官は被告人側の証拠調べ請求に対してはこの規定を非常に厳格に適用する。だから、被告人が控訴した事件の第一回公判期日に被告側の証拠申請を全部却下して直ちに終結という事件も決してめずらしくない。ところが、検察官が控訴した事件では高裁は非常に緩やかに検察官の証拠申請を認める。1審で検事が請求するのを忘れた証拠やただの蒸し返しに過ぎないような証人申請ですら、高裁判事は検察官申請のときには認めることが多い。弁護人の申請の証拠調べはたいてい「やむを得ない事由の疎明がない」と言って却下する。検事の申請のときにはなにもいわずに「採用します」と言って採用する、あるいは、「裁判所の職権で採用します」などと言って採用する。この職権による証拠採用というのは、要するに、「やむを得ない事由」があったかどうかを問わず、検察官が取調べてもらいたいと思う証拠を、裁判所も積極的に調べてみたいので調べるというわけであり、これほど不公平なことはない。しかし、最高裁判所の判例は高裁判事がこのような姿勢をとることを許している(最1小決昭59・9・20刑集38-9-2810)。
この事件でも、東京高裁第10刑事部は、滝川証人の尋問を認めている。滝川氏は1審での証言を繰り返したうえ、「橋本龍太郎元首相ら当時の幹部に累が及ぶのを阻止するため、虚偽供述した可能性もある」という1審判決に対して、「(虚偽は)全くありません」と反論したと言う(日本経済新聞2007年2月20日朝刊39頁)。この証言が1審証言の蒸し返しに過ぎないものであることは明らかである。高裁が検察側の証人だけ繰返し証言することを許し、しかも当の証人に1審判決への批判をさせるというのは、あまりにも一方的ではないだろうか。しかし、これは日本の高裁判事の平均的な訴訟進行からそれほど大きく離れていないのである。ありがちな訴訟進行の一つである。
結果として、検察官控訴による原判決破棄率は非常に高い。平成17年度の司法統計年報によると、検察官の控訴申立て266件のうち実に202件(75.9%)で原判決が破棄されている(平成17年度司法統計年報第45表、53表)。ちなみに、被告人控訴事件の破棄率は12%(9080件のうち1091件)である。
精神的・肉体的・経済的に多大の犠牲を払ってようやく獲得した無罪判決も、こうして検察官控訴によって反故にされることが多いのである。裁判で無罪を獲得するためには非常に困難な闘いを2回勝たなければならない。いや、上告審があるから、3回勝ってはじめて冤罪の恐怖から解放されるという場合もありえる。わが国の刑事裁判は有罪も無罪も多数決で決定される。したがって、1審無罪・2審有罪という場合、事件を担当した6人の裁判官のうち最大で4人の裁判官が無罪の意見だった可能性がある。4人の裁判官が「滝川証言は信用できない。有罪には合理的な疑いがある」と考えていたとしても、その意見は結果に反映しないということである。
日本国憲法39条はこう定めている――「何人も、実行の時に適法であった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われない」。この条文は非常に分りづらい。その原因は、原案を作成したGHQの法律家の意図を日本政府の担当者が十分に理解していなかったことにある。GHQ草案では刑事事後法の禁止(実行のときに適法であった行為の処罰の禁止)と二重の危険の禁止(同一の犯罪について二度裁判を受けない)は全く別の条文であった。けれどもGHQとの折衝を担当した内閣法制局の入江俊郎や佐藤達夫らは「二重の危険」(double jeopardy)の意味を知らなかったので、日本語の草案では一旦これを削った。しかし、後でGHQが二重の危険禁止条項の削除には同意していないことを知って、残った条文の末尾にこれを付け足すことにしたのである(入江俊郎『憲法成立の経緯と憲法上の諸問題』(入江俊郎論集刊行会1976)、222〜225頁;佐藤達夫(佐藤功補訂)『日本国憲法成立史(第3巻)』(有斐閣1994)、127頁、295頁)。「又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われない」という部分の公定英訳文はこうなっている:“nor shall he, in any way, be placed in double jeopardy.”この表現は合衆国憲法第5修正から来ている:“nor shall any person be subject for the same offence to be twice put in jeopardy of life or limb.”(「何人も同一の犯罪のためにその命や手足を2度にわたって危険に曝されてはならない」)。
無罪判決に対して検察官が控訴することは憲法39条に違反するか。最高裁判所大法廷昭和25年9月25日判決は、違反しないと述べた:「一審の手続も控訴審の手続もまた、上告審のそれも同じ事件においては、継続せる一つの危険の各部分たるにすぎないのである。……それ故に、下級審における無罪又は有罪判決に対し、検察官が上訴をなし有罪又はより重き刑の判決を求めることは、被告人を二重の危険に曝すものでもなく、従ってまた憲法39条に違反して重ねて刑事上の責任を問うものでもない」と(最大判昭25・9・27刑集4-9-1805)。しかし、何ゆえに1審から上告審までが「継続せる一つの危険」に過ぎないのか最高裁は説明していない。
これに対し英米の判例は古くから事実審の公判審理を一つの危険と考えており、したがって、無罪の評決は事件に対する最終判断であり、それに対して上訴はできないとされてきた。1957年の合衆国最高裁判所の判例はその理由をこう説明している:「政府は、その有する全ての資源と権力とを用いて個人を断罪する試みを繰り返すことによって、彼をして困惑させ、出費をさせ、試練にさらし、持続する憂慮と不安のうちに生きることをやむなくさせ、そして、無罪であっても有罪とされる危険を高めるようなことをしてはならないということである」(Green v. United States, 355 U.S. 184 (1957))。ここには、刑事訴追というものが巨大な権限を持った国家と何等の権限も権威もない一個人との間の紛争であることについての深い認識がある。
そして、この認識はわが国の刑事裁判の現状に対してこそそのまま当てはまるのではないだろうか。わが国において、1審無罪判決に対する検察官控訴の実態は、政府が「全ての資源と権力とを用いて個人を断罪する試みを繰り返すこと」に他ならず、被告人をして「困惑させ、出費をさせ、試練にさらし、持続する憂慮と不安のうちに生きることをやむなくさせ、そして、無罪であっても有罪とされる危険を高める」という評価がもっとも相応しい。
裁判員法の制定の際に上訴審をどうするかについて多少の議論はあったようだが、立法的な手当ては結局何もなされなかった。しかし、裁判員と裁判官が評議した結果出された無罪判決に対して検察官が上訴するということ、そして、高等裁判所が今回と同じように一審の判断と反対に「検察側証人は信用できる」と言って逆転有罪判決を言渡すことは、今まで以上に事態の不条理さを際立たせるであろう。仮に1審が全員一致で無罪を言い渡し、高裁判決が多数決で有罪の判断をしたのだとすると、裁判に関与した12人のうち10人が無罪の意見であっても被告人は有罪になるということである。そのような有罪判決を人々は信頼するだろうか。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
(以下、投稿者:大阪都民N コメント)
以上が、刑事裁判を考える:高野隆@ブログ 2007年05月14日 「二重の危険」
からの全文引用です。引用中の「強調太字」は、投稿者:大阪都民Nによるものです。
私は、他の方が書かれたブログ等の記事を引用投稿するのは初めてですが、その意図は、いうまでもなく、今回の陸山会事件の指定弁護士による控訴に対する強い抗議の意志を表したものです。
小沢氏を支持するとかしないとか、事件をどう評価するとかの問題ではなく、私たちの国・日本の司法制度のあり方について、今一度、国民が真剣に考えなくてはならない、という思いを表現するために、このような引用投稿をさせて戴きました。
著者の高野 隆 さんという方を、私はこの記事を見つけるまで存じ上げませんでした。第二東京弁護士会に所属する弁護士さんだそうです。奇しくも、今回の指定弁護士(大室俊三氏、村本道夫氏、山本健一氏)らと同じ弁護士会に所属されています。
この記事は、今回の陸山会事件の控訴より以前に、あくまで「検察官の控訴」について書かれたものですが、文中の「検察官」を、【有罪の確信がる起訴ではなく法廷で白黒をつけて欲しい、という議決を受けた指定弁護士】と読み替えると、その不条理さは増すばかりです。
最後に、これは小沢氏を支持する方の不安や危機感を煽るための投稿ではなく、指定弁護士への反省を求め、高裁で控訴審を担当される裁判官に、このような司法のあり方について、真剣に考えて戴きたいという気持ちを込めての投稿であることを申し添えて投稿させて戴きます。
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます(表示まで20秒程度時間がかかります。)
▲このページのTOPへ ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK131掲示板
★阿修羅♪ http://www.asyura2.com/
since 1995
 スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。
▲このページのTOPへ
★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK131掲示板
 スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。