http://www.asyura2.com/12/jisin18/msg/145.html
| Tweet | �@ |
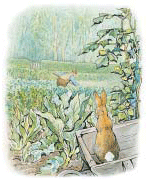
�������Ôg���P������c���ꂪ���Ƃ��x�������Q�G���A���I
http://www.zakzak.co.jp/society/domestic/news/20120312/dms1203121138002-n1.htm
2012.03.12�@�[���t�W
�s���̊�Ȃ��G���A
http://www.zakzak.co.jp/society/domestic/photos/20120312/dms1203121138002-p2.htm
�@��N�R���ɓ����{��k�Ђ��N�����Ĉȗ��A�Ôg�̊댯�������߂ăN���[�Y�A�b�v����Ă���B��s�����^�n�k�̔��������O����铌���ł��A�S�͍��܂���肾�B����Ȓ��A�u�n���v�����̐��Ƃ��A�����ɒÔg���P�������ꍇ�ɐr��Ȕ�Q���o��ӊO�Ȓn����w�E�A�댯���ɖ����o�ȓs���Ɍx�����Ă���B�n�����Î�����s�C���ȃT�C���Ƃ́|�B
�@�u��n�ɊX���݂��L�����Ă��铌���ɁA�����{��k�Ђ̂悤�ɂP�O���[�g�����̑�Ôg��������A�s���̂قƂ�ǂ̒n�悪���v����B�s���́A�������Z�ޓy�n�̍��፷�̊��o�������Ă��āA���̊댯����F���ł��Ă��Ȃ��v
�@�������̂́A�w�n���ɉB���ꂽ�u�����Ôg�v�x�i�u�k�Ёj���㈲�����}�g�匳���w���Ŗ��_�����i����w�j�̒J�쏲�p���B�m���t�B�N�V������Ƃ̌��������B
�@���N�A�S���̒n���̗R�����������Ă����J�쎁�́A�R�E�P�P�̑�k�Ђ��@�ɁA�s���ɓ_�݂���u���v�Ɋւ���u�n���v�ɒ��ځB���፷���������ꂽ�u�����s����}�v�i�P�X�Q�T�N���s�j���Q�l�ɁA�Ôg���P�������ꍇ�ɔ�Q���z�肳���u��n�v�����Ԃ�o�����B
�@�u�n�c�E�]���E�]�ː�E������̍L�͈͂ɍL����w�C���[�����[�g���n�сx�ɂ͐��ɊW����n�����������U������܂��B�z����������Ȃǁw���x�����n���͕����ʂ肻�������������\���������B�ق��ɂ��A������́w�Ė��x�́A���Ƃ��Ɓw�����x�ƌ����Ă����Ƃ����̂�����B����͐������������悤�ɗ��ꂽ�n�`���Î�����n���ł��B�����̒n��́A�i�P�O���[�g�����́j�Ôg�ɒ��������ЂƂ��܂���Ȃ��v�i�J�쎁�j
�@�������������G���A�́A�C���̒Ⴓ����A���˂Ă��댯�����w�E����Ă����B�����A�J�쎁�ɂ��ƁA��ʓI�ɒm��ꂽ�댯�n�шȊO�ł��g�v���ӃG���A�h������Ƃ����B
�@�u�Ⴆ�A���c��̓���J�B���́w����x�͓��Ď��ŁA���Ƃ̓m���E�J�L�Ȃǂ̗{�B�Ŏg��ꂽ�w�q�r�x�Ƃ����}���̒|�̂��Ƃ�\���Ă��܂��B���̗R���ʂ�A���̒n�͍`�̓���]�������ꏊ�ŁA�Ôg�������p����k�サ�Ă�����^����ɂ���Ă��܂��ł��傤�v�i���j
�@����J�́A�c����ۂ̓��̃I�t�B�X�X�Ȃǂɗאڂ��铌���̒��S�X�B
�@�}�O�j�`���[�h�i�l�j�V���̎�s�����^�n�k�u�����p�k���n�k�v�Ȃǂ̑�n�k��z�肵�A�����s���쐬�����h�Ќv��ł́A����J���������҂̂��߂̋������ɁA����J�ɋߐڂ��钆�������̑ז����w�Z�����ɂ��ꂼ��ݒ肳��Ă���B�u�s���ł���r�I���S�ȏꏊ�v�Ɩڂ����ꏊ�����ɁA����ȁg�B�ꃊ�X�N�h���������Ƃ͋������B
�@�����̒����@�\���W�܂�i�c���E�G�ɂ����ӂ��K�v�ȃX�|�b�g���_�݂���B
�@�u�ԍ〈���w����Ճm����ʂ������O�x�ʂ�̈�т́A���āw���r���x�ƌĂꂽ�n��B�����͂��̖��̒ʂ�A���r�������n��ŁA�C�������͂Ɣ�ׂĒ�߂Ő��Q�ɂ͐Ǝ�ł��v�i���j
�@���̂ق��A���ŐZ�H���ꂽ�J���Ӗ�����u�J�v�A���ڒn���Î�����u�E�v�u�v�ہv�A�����ł́u�]�v�u��v���t���n�����v���ӂƂ��A�u���v�u�l�v�t���G���A�͉t���S�z�����Ƃ����B
�@��s���ő�n�k���N���Ă��A�����p���ł̒Ôg�E�Z����Q�́u���ݒn��������Ă���قǑ�K�͂ɂ͂Ȃ�Ȃ��v�Ƃ����̂��n�k�w�҂̌����B�����A�J�쎁�͂����x������B
�@�u��̑�k�Ђł���t���̖؍X�ÂŁi�z�肵�Ă���ȏ�́j�Q�E�Q�W���[�g���̒Ôg���ϑ������B�ň��̎��Ԃ�z�肵���K�v�ł��v
�@�n���ɂ���ĕ����яオ���Ă����g���h���s�s�h�����̎��ԁB�����̏Z�ފX�̐��藧����m�邱�Ƃ��A�h�Јӎ��̌���ɂȂ��肻�����B
�@
���̋L����ǂl�͂���ȋL�����ǂ�ł��܂��i�\���܂�20�b���x���Ԃ�������܂��B�j
�@
�����̃y�[�W�̂s�n�o���@�@�@�@�@ �����C���� > ���R�ЊQ18�f����
 �X�p�����[���̒����猩���o�����߂Ƀ��[���̃^�C�g���ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B
�X�p�����[���̒����猩���o�����߂Ƀ��[���̃^�C�g���ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B���ׂẴy�[�W�����p�A�]�ځA�����N���������܂��B�m�F���[���͕s�v�ł��B���p�������N��\�����Ă��������B