http://www.asyura2.com/12/hasan77/msg/856.html
| Tweet | �@ |
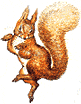

�s�K�ȓW�J���}����BRICs�̕���
2012�N10��10���iWed�j Financial Times
�i2012�N10��9���t �p�t�B�i���V�����E�^�C���Y���j
�@����3�N�ԁA��ʓI�ȊT�O�͐��E�̎�v�o�ύ���2�̊�{�I�ȃO���[�v�ɑ�ʂ��Ă����B�uBRICs�v�Ɓu�a�l�isicks�j�v�ł���B
�@�č��Ɖ��B�A���iEU�j�͕a��ł���A�����Ɨ��ƒᐬ���A���낵���قǂ̍��ɋꂵ��ł����B����ŁABRICs�i�u���W���A���V�A�A�C���h�A������4�J���A�����Ĉꕔ�̌����ł͓�A�t���J�������j�͉��Ă��͂邩�Ɋ��͂ɖ����Ă����B�����Ƃ���ƉƁA���Ă̐����Ƃ́A�������������茩�߂邽�߂ɒ���I��BRICs���������炵���B
��N�J�Â��ꂽBRICs��]��c�kAFPBB News�l
�@�Ƃ��낪���A�������Ȃ��Ƃ��N���Ă���BBRICs���ꋫ�Ɋׂ��Ă���̂��B
�@�X�̍��̖��̐����͈قȂ邪�ABRICs���������т���傫�Ȗ�������������B�܂��A�y�ϓI�ȁu�f�J�b�v�����O�v�_������Ɍ��ꂽ�ɂ�������炸�ABRICs�����͊F�A�ア���Čo�ς̉e�����Ă���B
�@���ɁA5�J�����ׂĂ����A�������鉘�E�����̐����̐��ɑ���M���Ȃ��A�o�ςɏd�����S���ۂ��Ă��邱�ƂɋC�Â�����B
�����s�����o���钆��
�@�����͍����V���卑�̑�\�i���B�����͐��E��2�ʂ̌o�ϑ卑�ł���A�����D��BRICs�ň�Ԃ̋}���������B����ɂ�������炸�A�����͒��N�Ȃ������قǁA�����̌o�ϓI�A�����I�Ȗ����ɑ������s���������Ă���B
�@���钆���̗F�l���ŋߘb���Ă��ꂽ�悤�ɁA�u�����̌o�ς͋}�������Ă���A���̎w���҂͎p�������A���{�Ɍ����đD�𑗂荞��ł���v�̂��B
�@�K�ߕ����͂��̌�A�Ăюp�����������A�ŏ��Ɏp�����������Ɠ������炢�o�܂͓�ɕ�܂�Ă���B�����A��ꤗ����̍ٔ��J�n���ԋ߂ɍT���A�ɂ߂ďd�v�ȋ��Y�}�����藈�钆�ŁA�����I�ȋْ��͍��܂����܂܂��B
�@�ߋ�30�N�قǁA�����I�ȕs�m�����ɑ��Ē������o�������͂��������������B�}���Ȍo�ϐ����ł���B
�@�������A�����̐�������2012�N�ɁA�����I�ɓ����Ă��珉�߂ĔN��8���Ƃ����ے��I�Ȑ���������錩���݂��B����Ӗ��ł́A����͎��R�ł���A�]�܂������Ƃł�������B���������́A�����̘J���͂����͂�ȑO�قNj}�����Ă��Ȃ��Ƃ��������f���Ă��邩�炾�B
�@�����A�݂�o�ϐ����́A���B�ɂ�������v�̌��ނ����f���Ă���B�����̍H��̒������}�㏸���Ă���B����͘J���҂ɂƂ��Ă͘N���A�����̋����͂ɂƂ��Ă͋��B
�u���W����C���h�ɂ��g�y���钆���̐�������
�@�����̌����́A���̑���BRICs�����ɔg�y���ʂ������炷�B�����͍���A�u���W���A�C���h�A��A�ɂƂ��čő�̖f�Ց��荑�ɂȂ��Ă��邩�炾�B�u���W���̌o�ϐ����͂Ƃ�킯�}���ɗ������B���I�f�W���l�C����2016�N�ċG�ܗւ̊J�Òn�Ɍ��܂������N��2010�N�ɁA�u���W���̐�������7.5���ɒB�����B���N�̐������͋��炭2���ɓ͂��Ȃ����낤�B
�@�C���h�͂ǂ����ƌ����A�M�҂����T�ԑO�ɖK�ꂽ���ɂ���x�e�������ƉƂ��b���Ă��ꂽ�悤�ɁA�C���h��Ƃ́u�Տ��I�T�a�v�ɋꂵ��ł���B���Z��@�̑O��9�������o�ϐ����́A���ł�5����h�����ď�����x���B�C���h�͍��āA��6���l�ɉe�����o�����E�ő�̒�d�ɂ���Ď����̐Ƃ����v���o������ꂽ�B
�@�����̐��͋@�\�s�S�Ɋׂ����͗l�ŁA�o�ω��v�̃v���Z�X�͍s���l�܂����B�ŋ߂̂������̔��\�́A���v���ĊJ����Ƃ������҂�����������A2�`3�N�O�̂��ӂ�����̎��M�͊T�ˎ���ꂽ�B
�@���V�A���ꋫ�Ɋׂ��Ă���B�E���W�[�~���E�v�[�`�����̑哝�̕��A�̓��X�N���ő�K�͂ȍR�c�s���������N�������B�����ĕč��̃V�F�[���K�X�v���́A���V�A�ɔߎS�Ȍ��ʂ������炷�\��������B�V�F�[���K�X�v���̂������Ő��E�̃K�X���i���ቺ���Ă��邩�炾�B���V�A�̒�����s�́A������2015�N�Ɍo��Ԏ��Ɋׂ�Ɨ\�z���Ă���B
�@�v�[�`���̐����x����2�{���\�\�]���Ȓ����K���ƐΖ��E�K�X���瓾�������\�\�́A�ǂ����������Ă���悤�Ɍ�����B
BRICs�̈�p�𐬂���A�t���J
�@BRICs�Ƃ������t��҂ݏo�����S�[���h�}���E�T�b�N�X�̃G�R�m�~�X�g�A�W���E�I�j�[�����͂��˂āA��A�o�ς͑���BRICs�����Ǝ��R�ƌ�����ׂ�قNjK�͂��傫���Ȃ��Ǝ咣���Ă����B����ł���A�͒���2���BRICs��]��c�ɎQ���������A���̎�]��c����Â���\�肾�B�����BRICs�������ȊO�̑卑�O���[�v�ɕϖe�𐋂��Ă���\�ꂾ�B
�@������ɂ���ABRICs�̒n�ʂ̐V���ȓ�������̉�����o�ςƋ@�\�s�S�̐������Ƃ���A��A�͂��̃O���[�v�̈���ƂȂ鎑�i������B�����̍z�Ƃ͎R�L�X�g�ɔY�܂���Ă���A���N�͉���l���̐l�����팸����\�����\������B
�@�o�ϐ����͗������݁A3���������\���������B�����āA�W�F�C�R�u�E�Y�}�哝�̂̎w���́i���邢�́A���̌��@�j�͐[���ȕs���������Ă���B
�@��A�̃v���`�i�z�R�ł̑������璆���̓d�q�@��H��ł̃g���u���A����ɂ̓C���h�ł̒�d���烂�X�N���ł̍R�c�����A�u���W���ł̉��E�{���܂ł����ׂČ��Ԓ����͑��݂��Ȃ��B�����ABRICs�����̖������т���傫�ȃe�[�}�͂���B
BRICs�̖������т���e�[�}
�@�܂��A�����Ƃ́u�f�J�b�v�����O�v�錾�́A���v�������BEU�͍������E�ő�̌o�ό����B���B�̌i�C��ނƕč��̒ᐬ���́A�K�R�I��BRICs�ɉe����^����B
�@���ɁA���N�ɂ킽��}������BRICs�����ɐ����I�Ȓ��a�������炳�Ȃ������B�����`���A�ƍَ�`�����킸�A�M�҂�BRICs������K��ĉ��x���o���킵�Ă����e�[�}�́A���E�ɑ��鍑���̓{�肪�����ɂƂ��ċɂ߂ďd�v���Ƃ������Ƃ��B���̂��߁A�����Ƃ������Ƃ����ݓI�Ȑ���s���ɐ_�o���ɂȂ�B
�@�ł́A�����̂��Ƃ�BRICs�̕��ꂪ���Ƃ��b���������Ƃ��Ӗ����Ă���̂��H�@�K�����������ł͂Ȃ��B���̕���̋ɒ[�ȃo�[�W�����\�\BRICs�������ی��Ȃ��`�����X�Ɗy�ώ�`�̍��X�Ƃ��ĕ`�����́\�\���n�����Ă������Ƃ͎������B�����A���ꂾ�������̖�������Ă��Ȃ���ABRICs�����̑唼�͍��㉽�N���a�l��荂�������𑱂��邾�낤�B
�@���̂��Ƃ́A�ˑR�Ƃ��āA��������V�����ւƌo�ϗ́A�����͂��V�t�g���铮������X�̎���̑傫�ȕ���ł��邱�Ƃ��Ӗ����Ă���B
By Gideon Rachman
http://jbpress.ismedia.jp/articles/print/36273
�����̍H��̖\���ɉ�t����l������
2012�N10��09���iTue�j Financial Times
�i2012�N10��4���t �p�t�B�i���V�����E�^�C���Y���j
�]�ƈ��̑��������E�ŁA���f�B�A�Ȃǂ̒��ڂ𗁂тĂ����t�H�b�N�X�R���kAFPBB News�l
�@�����k���ɂ���t�H�b�N�X�R���i���C���z���n�C�������H�Ɓj�̑����H��Ő���N�����\���́A�]�ƈ�2�l�̎��̏�ł̌��܂ɂ���Ďn�܂����ƌ����Ă���B
�@�x�����������Ɋ����ē��������Ɏ��Ԃ��G�X�J���[�g���A���𗧂Ă�2000�l�̏]�ƈ���������邽�߂�5000�l�̌x�@�����h������Ă���͊��S�Ɏ�ɕ����Ȃ���ԂɂȂ����B
�@��p�̎�������T�[�r�X�iEMS�j���ŁA������100���l�̘J���҂��ٗp����t�H�b�N�X�R���́A���N�O�ɐ[�Z���H��ŏ]�ƈ��̎��E���������ł���A�H��̘J�������������Ĉ��͂��Ă����B
�t�H�b�N�X�R���]�ƈ����s�����点�闝�R
�@���Ђ͂���ȗ��A��Ђ̃C���[�W�����P���A���Ƃ��ė��������������]�ƈ��Ƃ̊W���~���ɂ��邽�߂ɁA�����������グ��Ȃǂ̑���u���Ă����B
�@�č��́u�����J������iFLA�j�v�����N���\�������́A�t�H�b�N�X�R�����J�����̑����ɑΏ����Ă����Ƃ̌����������Ă������A�����̖@����x����c�Ǝ��ԂȂǁA�u�d�傩�[���Ȉᔽ�v�̏؋����܂�����Ƃ��Ă����B
�@���̕��́A�����H����ΏۂƂ��Ă��Ȃ��������̂́A���H��͍ŋ߁A���炭�A�b�v���́uiPhone�i�A�C�t�H�[���j5�v�̔����Ɍ����������ɉ����邽�߂��߂ɁA���Y�����Ă����B
�@�t�H�b�N�X�R�������ɑ傫�Ȓ��ڂ𗁂тĂ����̂́A���̋���ȋK�͂ƁA�f���A�\�j�[�A�q���[���b�g�E�p�b�J�[�h�iHP�j�A�����Ă������A�b�v���Ƃ������L���u�����h�����ɍs���Ă���d���̂��߂��B
�@����ł��t�H�b�N�X�R���́A���炭�������Ђ̑��������ǂ��ٗp�傾�낤�B�����̍�ƌ���ŋْ������܂��Ă���̂́A������J�������𑽏��������邾���ł͉����ł��Ȃ��悤�ȑS�ʓI�����{�I�ȃg�����h�������Ă��钛�B
�@�ł����{�I�ȕω��͐l�����Ԃ��B�����͂��͂�A�����ĒP���Ȏd�������ň�����]���ȏo�҂��J���҂��s���Ȃ��ɂ͗���Ȃ��B
�@�A�W�A�J����s�iADB�j�ɂ��A1975�N����2005�N�ɂ����Ē����̐��Y�N��l����4��700���l����7��8600���l�ւƂقڔ{�������B
�@���Y�I�ȘJ���҂̎����I�ȐL�т́A�����肳��ɑ傫�������B�Ƃ����̂́A���Y�N��l���̋}���́A�_�����ɏZ�މ��疜�l���̐l��������A�s�s���̍H��œ�����悤�ɂ����������̌o�ω��v�Ƃقړ������ɋN�������߂��B���̌��ʁA������Ȕ_��̗]��J���͂������l�X�����E�̘J���l���̈�p���Ȃ����Y�I�ȘJ���҂ɂȂ����B
�l���{�[�i�X�Ə��q���
���{��؍��Ɣ�ׂ�ƁA�����̍���͌o�ϔ��W�̑����i�K�ŋN���Ă���kAFPBB News�l
�@�ǂ��m�点�́A���̂悤�ȘJ�������ʂ̑啝�ȑ������A�����̉ߋ�30�N�Ԃ̖ڊo�܂��������L�^�̑啔����������邱�Ƃ��B�����āA�����m�点�́A���ꂪ�I����Ă��܂������Ƃ��B
�@���A�̒�`�ɂ��ƁA�����̐l����2000�N���獂����Ă���B���Y�N��l�����k�����n�߂�2015�N�ȍ~�́A����������܂Œ������Ă����l���{�[�i�X���}���ȋt�]��ԂɊׂ�B
�@�����̍���́A�����悤�Ȍo�ϔ��W�̓������ǂ鑼�����͂邩�ɑ����y�[�X�ŋN���Ă���B�������_�E�t�F���i���f�X�E����������ADB��2010�N�̒������̒��ŁA�����ł�1�l���������������4000�h�����������ɍ�����n�܂����Ǝ��Z���Ă���B����ɑ��āA���{�ł�1��4900�h���A�؍��ł�1��6200�h���ɒB�����Ƃ���ō�����n�܂����B
�@�H��̌��ꃌ�x���Ō���ƁA����́A�o�ϔ��W�̂͂邩�ɑ����i�K�ŁA�J���҂ɗL���ȕ����Ƀo�����X���X�������Ƃ��Ӗ����Ă���B�d����������̂͗e�ՂɂȂ�A�J���҂͌ٗp��ɂ��܂艶�`�������Ȃ��Ȃ��Ă���B�����̌o�ϐ��������}�������Ă���ɂ�������炸�A���Ɨ����قƂ�Ǖς��Ȃ��̂͒��ڂɒl���邾�낤�B
�@���݂̘J���҂͈ȑO�قǁA�P���ł܂�Ȃ������ԘJ���ɊÂ�C���Ȃ��Ȃ��Ă���B�������������T���Ȓ����l�̃��C�t�X�^�C����m��悤�ɂȂ������ƂŁA�s���͈�w�傫���Ȃ��Ă���B
�@�m���ɍH��̒����͌��݁A�N��20�����x���㏸���Ă���B�����A�����̘J���҂ɂƂ��āA����͏������̂Ȃ��d���ō�悳��Ă���Ƃ������o�ߍ��킹����̂ł͂Ȃ��Ȃ��Ă��Ă���B
�Љ�̌��ςɔ��Ԃ��������l���q����
�@����1�A�����Ɣ����Ȑl�����ԏ�̉e������p���Ă���B�����̍�����˔@�N�����̂́A1979�N�ɓ������ꂽ��l���q����̂����Ȃ̂��B
�@��l���q����́A�������s�����Ă��闝�R�ł�����B�j�q��~������Ƃ����̂���̌X�����Ӗ�����̂́A���S���l�̏��q�َ̑������₳��Ă���Ƃ������Ƃ��B���̌��ʁA�����̐��ʂ̐l���\���́A���q100�l�ɑ��Ēj�q�̐���119�l�ɂȂ��Ă���i���R�ɔC����A���̔䗦�͏��q100�l�ɑ��j�q104�l�O��ƂȂ�j�B
�@�j�̎q��~�����邱�̂悤�ȌX���͎�܂��Ă��邪�A���̉e���͍��㐔�\�N�ɂ킽���Ďc�邾�낤�B
�@�H��ł́A���ꂪ�����炷1�̌��ʂ́A�j���J���҂����X�ɑ����Ă��邹���ŁA���čH��̃��C���œ����Ă������|�I�Ȑ��̏����J���҂قNJȒP�ɂ͈����Ȃ��Ȃ�A�Ƃ������Ƃ��B
�@�wThe China Price�i�M��F�����n����]�H��j�x�̒��҃A���N�T���h���E�n�[�j�[���͂���10�N�ԁA�����̍H���K�₵�����Ă����B�����͐��N�O�A����������ɂ�葽���̒j���ɃC���^�r���[���Ă��邱�ƂɋC�t�����B�ŋ߁A����Ⴂ�������ޏ��Ɂu�������̐���͍H��ł͓����܂���v�ƌ������Ƃ����B
�t�����l�����߁A�L�����A��z����
�@�n�[�j�[���͎��ɋ����[���u���[���o�[�O�̃R�����ŁA�����̍H��́A�J���҂��P��������A�ނ�Ɋm���ȏ��i�̓�������肷��̂����ɉ��肾�Ə����Ă���B����ɒ����̍H��́A�X�̐V�K�T�C�N���̎��v�ɂ҂����蓖�Ă͂܂�悤�Ɍق����ꂽ����ق�����ł���u�W���X�g�E�C���E�^�C���E���[�J�[�v�ƌĂԂ��̂�]��ł���Ƃ����B
�@�u���̋^��́A�������ǂ̂悤�ɂ��ĊK�i���オ���Ă������ł��v�B�����Ƃ̕t�����l�����コ����K�v���Ɍ��y���āA�n�[�j�[���͂����b���B
�@����͒����ɂƂ��Ĕ��ɑ傫�Ȗ�肾�B�H�ꏊ�L�҂ɂƂ��Ă������Ȗ��ł͂Ȃ��B�t�H�b�N�X�R���̑n�ƎҁA�s������́A3�N��Ɏ��Ђ̍H���100����̃��{�b�g��ݒu����v������ɔ��\���Ă���B���Ђ͑��p�����i�߂Ă���A�u���W���A���L�V�R�A�����ōH��ɓ������Ă���B�C���h�l�V�A�́A�����ɍH������݂���悤�s����������悤�Ƃ��Ă����B
�@���{�b�g��ݒu������A�H��𑼍��ֈړ]�����肷�邱�Ƃ́A�����̐l�����Ԃɑ���1�̑Ή����B������͂邩�ɓ���̂́A�J���҂���荂�x�Ȑ��i������悤�ɂȂ�̂Ɠ����ɁA�L�����A���z����H����ǂ̂悤�ɐv���邩�𖾂��邱�Ƃ��B
By David Pilling
http://jbpress.ismedia.jp/articles/print/36265
�@
�@
�y��2��z 2012�N10��10���@���c���� [�c��`�m��w�r�W�l�X�E�X�N�[���y����]
�o�ϐ��ƎЉ�F
��I�r�W�l�X�̔w��ɂ���v�z
�@�O��́A��I�i�a�n�o�j�r�W�l�X�̐������T�ς���ƂƂ��ɁA�������芪����\�I��4�̔ᔻ���������B����͂��̔ᔻ�̈�ɔ������邱�Ƃ�ʂ��āA��I�r�W�l�X�̔w�i�ɂ���o�ϐ��ƎЉ�̊ւ��ɂ��Ę_����B
�t���[�h�}�����̍l��
�@���ɍ���̘_�_�̊j�S�ɐG��Ă���̂͑�4�̔ᔻ�ŁA�u�Љ�������ɉc����Ƃ��^����Ƃ����Ă��A���ǖ{���͗��v�ł���A�r�㍑�̌��n�o�ς���悳��邾���ł́H�����ł͂Ȃ��Ǝ咣����Ȃ�A����͋U�P�ɕ�������v�Ƃ������̂��B����͊J���Z�N�^�[�i���ۋ@�ւ�r�㍑�J�������Ɍg���m�o�n��m�f�n�̂��Ɓj����̓`���I�ᔻ�Ƃ��ĕ�����₷���B�����A���͊�ƌo�c�҂̐Ӗ������厑�{���l�̍ő剻�ƂƂ炦��V���R��`���A�u��ƂƂ͂����܂Ōo�ϓI���l���ɑ剻�����邽�߂̃}�V���ł���v�Ƃ��������ɂ����āA�ߋ��̊J���Z�N�^�[�ɑ��݂�����ƊςƂ҂������v����B
�@�V���R��`�̒��S�I���݂ł���~���g���E�t���[�h�}��(1970)�m��1�n�ɂ��A��ƌo�c�҂̐Ӗ��Ƃ́A��Ƃ̏��L�҂ł��銔��̑㗝�l�Ƃ��āA�ނ�̗��v�i���邱�Ƃł���B�t���[�h�}���́A��������Ƃ��u��Ƃ̎Љ�ӔC�v�̖��̉��ɉ��炩�̎Љ��тт������Ɍo�c�����𓊓�����Ȃ�A�u�����ɂ����āA�o�c�҂͒N�ɉ��̖ړI�ł�����ېł��邩�����猈�肵�A�V���ɂ̂ݏ]���āA���R�������P����Ƃ��A�n����o�ł��邽�߂ɂ��̎������₷�v�B�����A�u��ƌo�c�҂�����ɂ���ĔC������Ă��鐳�����́A�o�c�҂��˗��l���銔��̑㗝�l�Ƃ��āA���嗘�v�Ɏ�����Ƃ�����_�ɑ�����B�o�c�҂��w�Љ�I�ړI�x�̂��߂Ɂw�ېŁx��������x�o�����Ƃ��A���̐������͏��ł���v�Əq�ׂĂ���B
�m��1�nMilton Friedman (1970) �gThe Social Responsibility of Business is to Increase its Profits�h The New York Times Magazine, September 13, 1970.
�@�����Ő}1�i�M�ҍ쐬�j��p���Ċ�ƂɊ��҂����Љ�I���ʂ������ɁA��ƂɊ��҂����o�ϓI���ʂ��c���ɁA�r�W�l�X�̑��������Ă݂�B����̏ی��͖@�I�ɗv�������Œ���x�̎Љ�i�Ⴆ�Ύ����J����p���Ȃ��Ƃ��A���K�������炷��Ȃǁj��S�ۂ������I���ʂ̋ɑ剻���u������A����ΐV���R��`���z�肷��ʏ�̃r�W�l�X�ł���B
�@������̑ɂɂ���̂��E���̏ی��A���Ȃ킿�����Ȏ��P���Ƃ��B��t����⏕�����x�[�X�Ƃ������P�c�̂ɂ��Љ�����i�̂��߂̗l�X�Ȋ����A�Ⴆ�Ί��ی��z�[�����X�x���Ȃǂł���B���̏ꍇ�A��t�҂͓��R�Ȃ�������I���^�[������؊��҂��Ȃ����i�����I�������^�[���̓}�C�i�X100���j�A���̊�t�ɂ���Ď�������Љ�I�E���I���ʂւ̊��Ґ����͂���߂č����B
�@�t���[�h�}���̍l�����́A����痼�ɂ̈قȂ鎖�ƊԂɂ����āA�o�ϓI���ʂƎЉ�E���I���ʂ̓g���[�h�I�t�̊W�i�}1�̒��ō��ォ��E���L�т��45�x���j�ɂ���Ƃ������̂��B���Ȃ킿�A��Ƃɂ��Љ�̒Nj��́A�o�ϐ��̋]���̏�ɐ��藧���̂ł��邩��A��Ƃɂ��Љ�Nj��͊���ւ̔w�C�I�s�ׂƂ݂Ȃ����B���̍l���͎��{�s����ƌo�c�҂̊Ԃō��ł��������������������Ă���B
�V���R��`�̎咣��
����ًc
�@���������V���R��`�̎咣�Ɉًc��������̂�Porter and Kramer (2006, 2011)�m��2�n�ł���B�ނ�͎Љ�͌o�ϐ��̋]���̉��ɐ��藧�Ƃ����V���R��`�̑O���ے肵�A���҂̖��ڂȊւ�荇���A������ʂ��咣����B�����Ƃ��A��Ƃ̎Љ�ƌo�ϐ�������l�����́A����Porter & Kramer (2006, 2011)���͂邩�ɂ����̂ڂ�A���䑼�i1994�j�����i1995�j�����łɁu�헪�I�Љ�v�Ƃ����T�O�ɂ���ē����I�t���[�����[�N����Ă��邱�Ƃ������ɋL���Ă��������m��3�n�B
�@���āAPorter & Kramer�́A����܂ł̊�Ƃ͎Љ�I�ӔC�i�b�r�q�j������{�ƂƂ͊W�̂Ȃ������Ɉʒu�Â��A�ꓖ����I�Ɏ����𓊂��Ă���Ɣᔻ����B�����ėl�X�ȗ��Q�W�҂Ɉ͂܂�Čo�c���i�s���錻��ɂ����ẮA��Ƃ��Љ�ɑ��ĐӔC���u��Ƃ̎Љ�ӔC(corporate social responsibility)�v�ł͂Ȃ��A�u��ƂƎЉ�̓����icorporate social integration�j�v���d�v�ł���A�܂���Ƃɂ��Љ�Nj��́A���Ђ̖{�Ɓi���i�������͎��ƃv���Z�X�A�܂��͂��̗����j��ʂ����u������̕���(�����competitive context�A�قځu���ЂɂƂ��Ă̋��������v�Ɠ��`)�v�̉��P�̂��߂ɂȂ����ׂ��A�Ƃ���B
�m��2�nPorter and Kramer (2006), Strategy & Society: The link between competitive advantage and corporate responsibility, Harvard Business Review, December 2006: 1-17.Porter and Kramer 2011), Creating Shared Value, Harvard Business Review, January-February 2011:1-17.
�m��3�n�u�o�c�헪�̖{���́A��Ɗ������Љ�S�̂̌��S�Ȕ��W�ɍv������ƂƂ��ɁA��Ǝ��̂̔��W�ɂ��𗧂Ƃ�����{�I�W��z�����Ƃɂ���B���̂悤�Ȋ�ƂƎЉ�̖]�܂����W��z�����߂ɂ́A�Љ�ɑ��݂��邳�܂��܂Ȗ�����Ƃ��������ׂ��Љ�I�j�[�Y�Ƃ��ĂƂ炦�A�{���̎��Ɗ�����ʂ��Ă��̉����ɍv�����Ă����K�v������B�i�����͕M�ҁj�v�u���̂悤�ɂ��āA��Ƃ̓��Z�i��t�B�����\���s�[���āA�V���Ƃ̑n����ʂ��ĎЉ�̑��l�Ȗ����������A�V���ȎЉ�l�̑n���ɍv������Ƃ����w�헪�I�Љ�x�������ł���悤�ɂȂ�v�i���E����E�R �c�E��c1997:p.317-318�j�BPorter & Kramer�i2006�A2011�j�̃A�C�f�A�́A�قڂ������{�̌����҂̎咣�ɉ��������̂ł���Ƃ����Ă悢�B
����E���ˁE�c���E�����E���E���{�E���c�i1994�j�w21���I�̑g�D�ƃ~�h���F�\�V�I�_�C�i�~�N�X�^��ƂƎЍۊ�ƉƁx�Y�\��w�����������D
�������(1995)�u�n��̎Y�Ɛ���ƒn���Ƃ̐헪�v�w�g�D�Ȋw�x��29.��2�D
���E����E�R�c�E��c(1997)�w�o�c�헪�\�n�����ƎЉ�̒Nj��x�L��t.
�@���������P�̗�Ƃ��Ĕނ炪������̂́A�q���[���b�g�p�b�J�[�h�Ђ��A���Ђ̑��Ƃ���n��̕n���w��N�����ΏۂɁA�v���O���~���O�\�͂̊J���P�����Œ������A���̒�����D�G�l�ނ��m�ۂ��Ă����Ƃ����������ł���B����������Ƃ̖{�Ƃ�ʂ����Љ�̒Nj��i�{����̏ꍇ�͋���@��̒Ǝ����@��̑n���j�́A�o�ϐ��ɑ��Đ��̃V�i�W�[���������邵�A���̂悤�Ȏ�ނ̎Љ�̒Nj���������Ƃ͖ڎw���ׂ����B���������Љ�Nj��͊�Ɛ헪�Ƃ��Ė����̂Ȃ����̂��A�Ǝ咣����B�����Ċ�ƂƋ��ɃR�~���j�e�B����v����u���L���l�ishared value�j�v�Ƃ����T�O���N���Ă���B
��Ƃ��Љ��Nj����邱�Ƃ�
�헪��̈Ӌ`
�@���āA����ɂđ�~�c�A�ꌏ�����A�ƌ��������Ƃ��낾���A�b�͂���ŏI���Ȃ��B����Porter & Kramer�i2011�j�̒��ɂ͊ʼn߂ł��Ȃ��u�h�炬�v�A�������́u�����܂����v���c��B����͊�ƂɂƂ��āu���Ђ��Љ��Nj����邱�Ƃ̈Ӗ��v�ł���B�܂�A��Ƃɂ��Љ�Nj����P�Ɍo�ϓI���l�����̎�i�̈�ɂ����Ȃ��̂��A����Ƃ���ƖړI�̈�ł���̂��A�Ƃ�����肾�B
�@����w��ŃR�[�l����̃n�[�g�����ɓ����₢�����Ƃ���A�u����͓����肾��B�Ȃ��Ȃ痼���ł��蓾�邩��v�Ƃ�������������������A���̘_�_�͊�Ƃ̎Љ�ƌo�ϐ�������c�_�𗝘_������i���ʊW�̂������Ő�������j��ŁA�܂��A��Ƃ����Ђ̎Љ�Nj����ǂ̂悤�Ș_���œ��O�ɑ����������邩�ɂ����āA�����Ēʂ�Ȃ����ł���B
�@��L�_�����̎咣�ő�\�I�Ȃ��̂��Љ��B
1�D�gShared value is not social responsibility, philanthropy, or even sustainability, but a new way to achieve economic success.�h �i���L���l�Ƃ͎Љ�I�ӔC�ł��A�t�B�����\���s�[�ł��A�܂��Ă⎝���\���ł���Ȃ��B����͌o�ϓI�����������炷�V���ȕ��@�ł���j�B���m�ɁA�Љ�̎����͌o�ω��l�����̎�i�A�Ƃ������ƂɂȂ�B
2�D�gCompanies must take the lead in bringing business and society back together.�h �gYet we still lack an overall framework for guiding these efforts.�h �gThe solution lies in the principle of shared value, which involves creating economic value in a way that also creates value for society by addressing its needs and challenges.�h �i��ӁF��Ƃ̓r�W�l�X�ƎЉ�������������S���ׂ����B�i�����j�����A���̓w�͂���I�t���[�����[�N�����܂����݂��Ȃ��B�i�����j����ɑ��������͋��L���l�̌����ɂ���B����͎Љ�̃j�[�Y�Ɖۑ�Ɏ��g�ނ��Ƃɂ��A�Љ�I���l�������ݏo�����@�ɂ���Čo�ϓI���l��n�o���邱�Ƃł���j�B���̕��ʂł́A�Љ�̎������o�ω��l�����̏����ł���A�Ɖ��߂ł���B
3�D�gShared value focuses companies on the right kind of profits ? profits that create societal benefits rather than diminish them.�h�i���L���l�̌����́A��Ƃ𐳂�����ނ̗��v�Ɍ����킹��B����͎Љ�I�։v�傳����悤�ȗ��v�ł���j�B�����ł́A�Љ�̎����͊�Ɨ��v���������ׂ������ł���Ǝw�E���Ă���B
4�D�gIt (shared value) is about expanding the total pool of economic and social value.�h�i���L���l�Ƃ́A�o�ϓI���l�ƎЉ�I���l�̑��a���g�傷�邱�Ƃł���B�j�����ł͖��炩�ɁA���L���l�̍��{���Љ�ƌo�ϐ��̗����ɂ��邱�Ƃ����������B
5�D�gThe purpose of the corporation must be redefined as creating shared value, not just profit per se.�h �i��Ƃ̖ړI�Ƃ͋��L���l�̑n���ł���A�P�ɗ��v���̂��̂ł͂Ȃ��A�ƍĒ�`�����ׂ����B�j��������́A�Љ�̎����͊�ƃp�t�H�[�}���X�̈ꕔ�ł��邱�Ƃ��������������B
�@�����̌����߂Ă݂�ƁA3�̎咣�����݂��Ă���B�܂���1�́i��L���p��1�j�A�o�ω��l�ő剻�̎�i�Ƃ��Ă̎Љ�Nj��ł���B�����܂Łu������̕����i���ЂɂƂ��Ă̋��������j�̉��P�v�̂��߂ɎЉ��Nj����邱�Ƃ̏d�v�����B���͂��̍l�����́A�����I�����D�ʂ̎����i�o�ϓI���l���ő剻�����ō��̏j��헪�̃S�[���Ƃ���]���̐헪���_�̔��e�ɂ����܂���ʊW�ł���B�܂�Љ�̒Nj����o�ϐ��Ƀv���X�̉��l�������炳�Ȃ��ꍇ�A�Љ�͖@�I�Œ���x���Ă͒Nj�����Ȃ��B
�@��2�Ɂi��L���p��2�E3�j�A�Љ�̎������A�o�ϓI���l�i���v�j�n�o�̏����ł���A�Ƃ����咣���B�����ɂ����āA�o�ϐ��Nj��ɂ�����Љ�����ւ̗v���́A��1�̎咣���������Ȃ�B�Љ�̒Nj����o�ω��l�����������̕��@�ɂ����Ȃ��Ƃ����i�K���āA�Љ�̎�����Ȃ����v�͒Nj������ׂ��ł͂Ȃ��A�Ƃ���������ݍ��咣�ł���B
�@Tocqueville (1838) �m��4�n�̌����u�[�����ꂽ���ȗ��v�v�Ȃ����u�������鎩�ȗ��v�v�ƌĂ��l�����ienlightened self-interest�j�́A���l�ȗ��Q�W�҂̕։v�����߂Ă������Ƃ��A���ʓI�Ɏ��Ȃ̍����I�p�t�H�[�}���X�ɕԂ��Ă��邱�Ƃ��Ӗ�����B�u�����I���Ȏ�`�v�Ƃ������邪�A��1�Ƒ�2�̍l�������܂������̂ƌl�I�ɂ͉��߂��Ă���B
�@��3�Ɂi��L���p��4�E5�j�A���Y�_���̒��ɂ͎Љ�̎������o�ϐ��̒Nj��ɕ���Ŋ�ƖړI�̈ꕔ�ł��邱�Ƃ��������錾��������B����ΎЉ�ƌo�ϐ��̓�����������ƖړI�Ƃ���l�����ł���B���ʊW��}������Ɖ��}�̂悤�ɂȂ�B
�m��4�nTocqueville (1838) Democracy in America, Saunders and Otley: London.
�m��5�n���c(2012a)�u�w��I�r�W�l�X�EBOP�r�W�l�X�x�����̒����Ƃ��̌o�c�헪�����ɂ�����Ǝ����ɂ��āv�w�o�c�헪�����x,��12��2012�N6��.
���c(2012b)�u�헪���_�̑̌n�Ɓw���L���l�x�T�O�������炷���_�I�e���ɂ��āv�w�c��o�c�_�W�x29(1):121-139.
�@�����Ŗ��ƂȂ�̂́A�����܂ł��Ȃ���Ƃ̎Љ�o�ϓI�p�t�H�[�}���X���ǂ̂悤�ɒ�`���A�ǂ̂悤�Ɍv������̂��A�Ƃ����_�ł��邪�A����͌��݂����������s���ł���A�ŏI��6��ɏ��邱�Ƃɂ���B
�Љ�ƌo�ϓI���l�̗�����
�����I�����D�ʂ�
�@����̌��_�Ƃ��āA�����3�̈��ʊW���f���̂����A��2�Ƒ�3�̍l�����́A��Ƃ̌o�ϓI���l�ő剻�����ɐ헪�̏]���ϐ��Ɛݒ肷������̊�Ɗςɑ��A���炩�ɏC���𔗂���̂��B�Ⴆ�Ύ���q�ׂ�悤�ɁA����܂ł͊�Ƃ̍����I���^�[����B�ꖳ��̕]���ړx�Ƃ��Ă������{�s�ꂪ�d�r�f�i���E�Љ�E�K�o�i���X�j�Ɋւ�铊��������p���n�߂���A�`���I�헪���_�̕��c�Ə̂����|�[�^�[���g���A�����悤�Ɋ����헪���_�̌��E��f���ɔF�߁A�Љ�ւ̌X�����߂��肵�Ă���̂́A����̎���Ɗς��ω����Ă��Ă��閾�m�Ȓ����Ƒ�������B
�@����������Ɗς̕ω��́A�헪�̋��ɂ̃S�[���ł���u�����I�����D�ʁv�̒�`�ɂ���C���𔗂邱�ƂɂȂ�B�����A�|�[�^�[�E�N���[�}�[�_���ɂ���_���̗h�炬�������Ă���悤�ɁA����͖��m�ɂ��̕����i�ނׂ����A�Ƃ������ʔF���͂��܂���ƃR�~���j�e�B�ɂ����Ă��w��ɂ����Ă��������Ă��Ȃ��B
�@���̂悤�ȏ��ŁA��Ƃ̎��_�ɗ����ď��Ȃ��Ƃ������邱�Ƃ́A����������Ɗρi��Ƃ̌������A��Ƃɖ]�܂�鉿�l�j�̕ω�����肵�A���Ђ̖{�Ɨ̈�ł̎Љ�Nj��Ǝ��Ћ����͂̋����A���ГƎ��̕��@�ɂ��Љ�Nj��ƐV���Ȍo�ϓI���l�n���Ƃ𗼗��ł����Ƃɂ����A�����I�����D�ʂ͏h��\���������Ƃ������Ƃ��B
�@�{�Ƃ�ʂ����Љ�ƌo�ϐ��̌����Ȉ��ʊW�͎��،����ɏ���Ƃ��āA���҂�����������Ƃ����헪�I�Ӑ}�E�\�z�������āA���̃^�t�ȖړI�̎����ɕK�v�Ȏ�����\�͂����������~�ς��n�߂�w�͂����߂��Ă���B�����Ŋ�ƊԂɍ��������낤�B���̓_���{��Ƃ̑唼�́A�����̗�O�������A���Ē��؈̐�i��Ƃɔ�ׂĂ������邵����������Ă���Ƃ����̂��M�҂̔畆���o�ł���B
�@����́A��Ƃ���I�r�W�l�X�Ɏ��g�ލۂɎЉ�ƌo�ϐ����Nj����铮�@�t���������闝�R�Ƃ��āA��Ƃ���芪���O�I���E���Q�W�҂̈ӌ����ǂ��ω����Ă�������_����B
http://diamond.jp/articles/print/26033
�@
|
|
|
|
���̋L����ǂl�͂���ȋL�����ǂ�ł��܂��i�\���܂�20�b���x���Ԃ�������܂��B�j
�@
�����̃y�[�W�̂s�n�o���@�@�@�@�@ �����C���� > �o���ϖ�77�f����
|
|
 �X�p�����[���̒����猩���o�����߂Ƀ��[���̃^�C�g���ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B
�X�p�����[���̒����猩���o�����߂Ƀ��[���̃^�C�g���ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B���ׂẴy�[�W�����p�A�]�ځA�����N���������܂��B�m�F���[���͕s�v�ł��B���p�������N��\�����Ă��������B