http://www.asyura2.com/12/hasan76/msg/545.html
| Tweet |
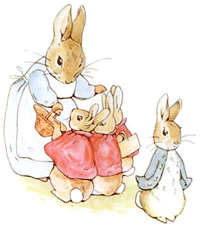
http://diamond.jp/articles/-/20085
姫田小夏 [ジャーナリスト]
中国−労働集約型産業=「?」製造業の空洞化はむしろ中国の問題だ
中国はどうなるのか――2020年の未来像をめぐって、中国国内でも大激論が展開している。中でも、一部の専門家やメディアが懸念し始めているのが、中国における労働集約型企業の行方だ。
空洞化が始まる中国製造業
米企業は「自国回帰」も
中国内陸部で自動車向けの部品を製造する、ある日本人経営者がいる。2000年に工場を稼働させて以来、艱難辛苦に揉まれながらも手塩にかけて人と現場を育て上げた。
だが、彼がいま手を打っているのは、ミャンマーへの拠点シフトであり、その理由をこう話す。
「人手が集まらない」
中国の魅力は、何と言っても「コスト競争力」だった。しかし、ここで生産活動をする外資企業は、競争力がなくなり魅力を失った中国に背を向け、工場の流出を加速させている。日系企業はチャイナネクストを求めて、アジアの途上国を漂流している。
中国からの脱出は日本企業だけではない。
アメリカは自国への回帰を始めている。特に機械、電子機器、コンピューター関連など、家電を中心とした製造業がアメリカに戻る傾向が強い。
ボストンコンサルティングが106社を対象に行った調査によれば、37%が「中国から引き揚げる、もしくはそれを前向きに検討」と回答し、その要因について57%の企業が「労働コスト」と回答している。
だが、結果はアメリカ経済にとって追い風ともなる。アメリカの製造業においては200万〜300万人の雇用が創出され、年間1000億ドルの生産高がもたらされるという予測があるのだ。
次のページ>> 中国がアメリカに生産コストで負ける?
台湾出身の経済学者である郎咸平氏は、著書『中国経済到了最危険的辺縁』で、「アメリカと中国の生産コストの差はますます縮まり、2015年前後、北米市場で販売される商品のアメリカでの生産コストと中国での生産コストには優劣がなくなる」と指摘する。
また同時に、「ローエンドの仕事が別のアジアの途上国に流れ、ハイエンドの仕事がアメリカに流れる。一体、中国に何が残るのか」と警鐘を鳴らす。
賃金上がれど薄まる仕事魂
昨年の離職率は平均18.9%にも
連続自殺事件を出したことでも知られる台湾系EMS工場の富士康(フォックスコン)は、今年5月末、またもや中国国内で働く労働者の月例賃金を引き上げた。2010年以降4度目の引き上げで、基本給は4400元(5万5000円)となった。業界平均のほぼ2倍にも相当し、これはもはや大学新卒並みの給料である。
これだけ出さなければ、もはや優秀な従業員は引き留められない。筆者も取材先各所で実感しているが、採用しても1年もつかどうか、である。中国では、この「従業員の慢性的な流出」が、永遠に解決困難な問題なのだ。
ちなみに、中国の人材サービス企業が発表した離職と昇給についての調査「2012離職与調薪調研報告」によれば、2012年上半期、中国企業の平均給料は9.8%増加した。また、2011年の各業界における離職率の平均は、金融危機以来最高水準の18.9%にも達した。報告からは「賃金を30%引き上げても十分な採用ができない」という厳しい現状も読み取れる。
前出の日本人経営者も「現在の80后、90后(80年代、90年代生まれの若者)の発想は、『楽して金を儲けたい』というもの。彼らとともにものづくりはできない」と語る。
コスト競争力に加えて、“労働者の質の劣化”も問題となっているのだ。
次のページ>> 一説には日本以上に急激な中国の少子高齢化
人口構造の変化とともに製造業が衰退
一方で、中国では少子高齢化が進行している。
過去10年で労働力はおよそ1億人増加した。とはいえ、今後、この労働人口(16〜59歳)は下降線を描くことが懸念されている。
中国で行われた第6次人口普査(日本の国勢調査に相当)の調査結果は、次のようなものとなった。
中国は92年以来、低出生率が続いており、第6次人口普査からの試算によれば、1.5%程度という「超低出生率」にまで落ち込んだ。その一方で1953年には4500万人だった高齢者人口(14歳以下の児童人口に比べ5分の1程度に過ぎなかった)は、2010年には1億7800万人となり、児童人口の5分の4にまで増加した。
高齢化とともに問題となるのは、その中間に位置する「労働人口」の縮小だ。中国国家統計局長の馬建堂氏は「労働力の供給は2013年にターニングポイントを迎え、減少に転じる。そのスピードは2020年以降加速する」と指摘する。
中国が世界の工場と称賛されたのは、労働人口の厚さ故に他ならない。中国では50年代、60年代、80年代において3回にわたるベビーブームがあり、30年間にわたり人口ボーナス(中国語で「人口紅利」)を提供し続け、労働集約型産業を支え続けてきた。
次のページ>> 中国製造業の技術レベルは先進国に追いついたか
中国の経済発展の基礎は、この労働集約型産業の上に始まった。だが、労働人口の縮小が示唆するのは、「道半ばにして発展を断念する中国製造業」である。
先進国に肩を並べ、追いつけ追い越せの途にあるかのような中国製造業だが、実は工業化の初期段階、かつ技術的にも世界の先進レベルには追いついていないと言われている。
同時にいつか訪れるであろうコスト競争力の喪失に、労働集約型から技術集約型への転換を急いできた。つまり、外資企業の下請けとしての安価な加工業から脱却し、ハイテク産業を主軸とする国家への変貌である。
そのために国はさまざま政策を打ち出してきた。しかしもちろん、「資金さえ投じれば技術革新が生まれる」というわけでもなく、あるいは「外国から生産ラインを輸入すればハイテク国家に生まれ変わる」という甘いものでもない。案の定、現実は国家が描いた戦略通りに進展してはいない。
そんな現状において、早くも労働人口の欠乏が大きな足かせとなって浮上してきているのだ。
すでに2002年の時点で20〜39歳の青壮年労働人口は4億5000万人のピークに達し、その後減少に転じている。その中国では今後、2000年代に見た飛躍的な発展が描けるのか――。残念ながら答えはノーだろう。
「第2次産業、すなわち工業こそが中国の競争力。これが衰えれば国力も衰える」と、悲観論者は危機感を隠さない。
ローエンドを軽視する政府
「騰籠換鳥」は絵に描いた餅
また、外資企業の撤退が続けば、中国では失業者が急増する。
例えば、電子産業においては300万人が就業しているが、10%の企業がアメリカに撤退すると中国は30万人分の職場を失う。このまま行けば、中国では就業の機会が減り、経済成長もさらにスローダウンしてしまう。
次のページ>> 何かを入れ替えるだけで産業は育つ?
ローエンド型のものづくりなしで、雇用を維持するのは困難だ。しかし、ローエンド型のものづくりは、中国政府がほとんど顧みることもせず、むしろそれを邪険に扱ってきたきらいすらある。日本の中小企業でも、ローエンド型企業は都市部に留まることを許されず、地方に移転するか、もしくは自社がハイテク企業に脱皮するしかなかった。
ましてや、“ローエンドの地場の中小企業”ともなれば、中国では地方政府からも一顧だにされなかった。にもかかわらず、産業のグレードアップだの、技術革新だのと、頭ごなしの要求だけは突きつけられる。
産業構造の高度化推進政策(低付加価値の労働集約型から高付加価値の知識集約型への転換)の代名詞として、「騰籠換鳥」という言葉がある。直訳すれば、「鳥かごを開けて鳥を入れ替える」の意味だが、まさしく何かを入れ替えさえすればそれで事はうまく運ぶと思っているのだ。
製造業育成は一日にしてならず
人材の重要さに気づいていない中国
日本のものづくりは、十数年もコツコツと同じ事を繰り返してきた、その継続にある。削って何年、磨いて何年という歳月の果てに技術の基礎を築き、人材を育てた。しかし、中国にはそれができない。国もそこに価値を置かなければ、その担い手となる若者も、地味な仕事には振り向きもしない。目には見えない人材への教育や技術の蓄積が、製造業の底力となることに気づいていないのだ。
経済発展を支えてきた労働力である民工が「減り」、そして「働かなくなる」。しかし、労働集約型産業を捨てられるほど、中国のものづくりは底上げされているわけではない。
ここ十数年、「世界の工場」と呼ばれてきた中国は、今まさに足元が揺らいでいる。にもかかわらず、「製造業がダメでも消費市場で発展できる」という確信を持っており、また、国有資産の規模の大きさ、基礎インフラの需要増、国内市場の拡大、豊富な人材などの諸要因を理由に、「2020年、中国は超級大国になる」といった自信も覗かせる。
次のページ>> 「中国から低コスト生産を除いたら、そこに何が残るのか?」
しかし、「仮に中国から低コスト生産を除いたら、そこに何が残るのか?」という議論は、ほとんど見かけない。
中国に進出して二十余年になる日系の縫製加工大手は、最近、バングラデシュに新工場を開設した。同社幹部はこう語っている。
「『ローエンドの中小企業よ、いらっしゃい』ができない限り、中国の製造業に明日はない。中国は今こそ、労働集約型企業を確保すべきです」――。
質問1 10年後、中国の製造業は高成長を続けていると思う?
先進国と同等の工業国になっている 6
成長は続き先進国の一歩手前まで追いつく 10
成長は続くが先進国の背中はまだ遠い 35
成長はかなり鈍化し工業立国化は難しい 48
わからない、その他 1
http://business.nikkeibp.co.jp/article/world/20120612/233291/?ST=print
アジア・国際>世界鑑測 北村豊の「中国・キタムラリポート」
注目を集め始めた中国の土壌汚染問題
汚染された工場跡地に続々と建設される住宅群
2012年6月15日 金曜日 北村 豊
土壌や地下水が汚染された“毒地”
「環境汚染などの理由で利用されなくなった産業跡地」を英語で“brownfield site”と呼ぶ。日本語でこれを直訳すると「褐色地の場所」となるが、中国語はそのまま直訳して“棕地(褐色の土地)”と言う。中国語ではこの“棕地”を“毒地”とも言う。“毒地”とは非常に直截(ちょくせつ)な表現だが、有毒有害な物質を使用したり生産していた工場が移転した後に残された、土壌や地下水が汚染されて、人体や生態への悪影響が懸念される土地を示す端的な言葉のように思われる。
日本では2002年5月29日に「土壌汚染対策法」が成立し、翌2003年の2月15日に施行された。その後、同法は2009年4月に改正法が公布され、2010年4月1日に施行となって現在に至っている。ところが、中国では1993年制定の「地下水品質基準」と95年制定の「土壌環境品質基準」が土壌関連の環境基準として存在するのみで、いまだに土壌汚染防止に関する法律は存在せず、基本的に整備されている環境保護関連法規に空白をつくっている。中国で土壌汚染防止に関する法律が起草されつつあるとのニュースは数年前から度々報じられているが、一向に進展がない。どうして当該法の起草が進まないのか、その理由は定かではないが、中国の土壌汚染の現実は一刻の猶予もならない状況にある。
週刊紙「南方週末」のニュースサイト“南方週末(infzm.com)”は2012年3月19日付で“毒地”関連の特集記事を掲載したし、雑誌「財経」の第322号(6月4日発行)も“毒地”を特集した。筆者の見るところでは後者の記事は前者の記事に触発されたものと思えるが、それはともかく、「財経」の記事は中国社会に大きな反響を呼び、中国国内のメディアは一斉に“毒地”関連の記事を掲載して、“毒地”の危険性に警鐘を鳴らすとともに土壌汚染防止の法規制の必要性を提起した。
「財経」の特集記事は次のような文章で始まっている。「ゴミ捨て場のそばで生活したいと思う人は誰もいない。でも、貴方が今住んでいるところはゴミよりももっと危険な“毒地”の上であるかもしれない。なぜなら、貴方は自分が住んでいる地域の歴史的な経緯を何も知らないのだから」
中国ではマンションやアパートといった集合住宅に住むのが一般的であり、デベロッパーが集合住宅の建設に着手した時点で販売公告を出して購入者を募るのが通例である。住宅購入希望者はその販売公告を見てデベロッパーや不動産仲介業者に出向いて詳細を検討することになるが、当該集合住宅の建設予定地がかつて何に使われていたかを気にする人はほとんどいないのが実情である。
近年、中国では大量の“毒地”が住宅用地として開発されている。北京市広渠路15号の土地はある化学工場があった跡地であり、2004年には一度競売にかけられて“首都城市房地産開発有限公司”によって18.2億元(当時のレートで243億円)で落札されたが、代金の支払いが滞(とどこお)ったために没収となった。その後も競売にかけられたが応札者なしで流札となり、住居と公共サービス施設の建設を条件として2009年6月30日に改めて競売にかけられ、“中央企業(国家直轄の国有企業)”の“中国中化集団”傘下の不動産会社“中化方興投資管理公司”<注1>が40.6億元(当時のレートで約573億円)で落札した。当該土地の面積は約15万6000平方メートル、延べ床面積は28万平方メートルであった。
<注1>中化方興投資管理公司は2010年4月に“中化方興置業(北京)有限公司”に社名を変更した。同社は不動産の開発、建設ならびに商品住宅の販売、賃貸、管理を本業としている。
汚染された土地が地価最高に
延べ床面積28万平方メートルに対して落札価格は40.6億元ということは1平方メートル当たり1万4500元(当時のレートで約20万5000円)となるが、これは当時の北京市では地価最高値の土地となり、北京市広渠路15号の土地は地価の王様という意味で“地王”と呼ばれた。ただし、この土地はたとえ“地王”であろうとも、上述したように化学工場の跡地で、明白な“毒地”であったから、汚染除去の措置が施された上で豪華マンションが建設された。果たしてどの程度まで汚染が除去されたのかは、具体的なデータが見当たらないので分からない。筆者は汚染除去がおざなりなものではなかったかと疑念を抱いており、マンション住民の健康へ影響を懸念するものである。
“毒地”が開発される背景には、2001年に始まってから現在に至るまで継続して推進されている「都市の“退二進三”計画」があるのだという。それは、工業構造の調整と都市用地構造の調整が進められる中で、かつて都市の中心部(環状二号道路の内側)にあった工業企業を移転や立ち退きにより次々と郊外(環状三号道路以遠)に退出させる、あるいは、第二次産業を退かせて、第三次産業を勃興させるという計画である。この計画は50年以上前の“大躍進”<注2>の時期に建設された深刻な汚染を排出する多数の工業企業を閉鎖あるいは移転させたために、大量の“毒地”が都市の中心部に存在することを白日の下に曝け出した。しかし、それらの“毒地”は地理的な利便性が高いため、ほとんどすべてが不動産用地として開発されており、何らの汚染除去措置も取られないまま、正常な土地として使用されているものも少なくない。
<注2>“大躍進”とは、1958年に毛沢東によって発動された、工業や農業の飛躍的な発展を目指した社会主義建設運動で、非科学的かつ非効率的な手段で強引な経済躍進を図ったことにより中国全土に甚大な損失をもたらした。
ある専門家は、「全国には各種各様の“毒地”が無数に存在する。そのうち農薬工場の跡地が相当に高い比率を占めるが、汚染を除去したもの、あるいは除去中であるものは数えるほどしかない」と指摘している。それを証明するかの如く、2004年以降に“毒地”の開発作業中に急性中毒が発生した事件が各地で発生している。その例を挙げると以下の通りである。
【1】2004年4月、北京市の南環状三号道路の外側にある“宋家庄”の地下鉄工事現場で、3人の作業員が中毒症状に陥り、重症の1人は高圧酸素室治療を受けた。その現場はかつての農薬工場の“毒地”であった。
【2】2006年7月、江蘇省蘇州市の南環状道路付近の“郭巷”にある化学工場が移転して1万3300平方メートルの“毒地”が残され、この中を通る道路を修築していた6人の作業員が突然に意識不明となった。
【3】2007年の“春節(旧正月)”の直前に、湖北省武漢市の“赫山地区”で工事を行っていた作業員が中毒症状を呈し、病院へ緊急搬送された。その場所は旧農薬工場の“毒地”であった。
都心部に残る毒地
“毒地”として知られているものは極めて少数で、大部分の“毒地”は地元政府も住民もその存在を知らず、静かに潜伏して人々の健康を脅かす。“毒地”の人体に対する危害は短期間には表面化せず、往々にして十年、あるいは数十年を経て現れるのが通例である。その症状は中毒を引き起こすだけではなく、ガンを誘発し、遺伝性疾病を発症させ、奇形児を出現させる。中国では“毒地”は新しい環境汚染の問題であり、現状は工場の移転前に強制的な汚染評価を実施することが制度化されていないため、問題発生後に「誰が汚染の責任を負うのか」という処理体制が整っていないのが実情である。
上述した「都市の“退二進三”計画」によって、2008年までに江蘇省、遼寧省、広東省広州市、重慶市などの地域では数千社もの工業企業が移転したが、その結果として2万ヘクタール以上の“毒地”が残されたという。重慶市では2004年から2012年までに市内の繁華な地域にあった工業企業137社が移転した。また、江蘇省では、具体的な時期は不明ながら、3年間で汚染が極めて深刻な化学企業4000社以上が次々と移転し、汚染状況が不明な大量の“毒地”を残したという。問題なのはこれらの“毒地”が各都市の中心部に近い交通至便な場所に所在していることであり、空地として放置することは貴重な資源の浪費につながる。
一般に“毒地”の汚染物は、重金属、電子廃棄物、石油化学系の有機汚染物質、残留性有機汚染物質の4種類に大別される。また、汚染された土壌が人体に危害をもたらすのは、直接摂取と間接摂取の2つに分かれる。間接摂取は汚染された地下水を通じて人体の健康に影響を与えるし、直接摂取は浮遊する塵埃(じんあい)、あるいは子供たちが遊んでいる時に不注意で汚染土を口にいれてしまうことなどが考えられる。したがい、これらの汚染物を除去して“毒地”を無害化することが必要となるが、中国では土壌汚染の除去技術はまだ十分に普及しておらず、汚染除去を行う資金も乏しいのが実情である。
中国でも土壌汚染の除去を行う「土壌回復企業」の一部では、有害汚染物を撹拌することで強制的に揮発させて揮発性有機化合物(VOC)を集めたり、活性炭に付着させたり、燃焼させるなどの土壌回復の新技術を採用している。ところが、中国の土壌回復技術の主流は依然として原始的な方法である。すなわち、汚染された土壌を掘り出し、別の場所に運んで埋め立てるか焼却するのである。
“中国科学院”の地理科学・資源研究所の副所長によれば、「土壌汚染除去プロジェクトが先にあって、後から土壌回復企業が出来る。つまり、プロジェクトの関係者が土壌汚染の除去処理を行う企業を組織するから、設備もなければ技術もない」のだという。同副所長は「ただし、土壌回復は適当にやればよいという物ではなく、必ず将来責任を追及される。今や誰もが土壌回復市場を美味しい脂身として見ている一方で、未来のリスクや責任を見ていない」と警告を発している。
「安い」が原則の土壌回復事業
2011年11月に蘇州市で初めて市政府が出資する土壌回復事業の入札が行われた。入札の評価基準は価格60%:技術40%で、どんなに技術レベルが低くても価格が安ければ受注できる仕組みが採用され、最終的には最低価格で応札した企業が受注した。中国では土壌回復事業の費用は地方政府が直接負担したり、土地を転売する際に当該費用分を差し引くのがほとんどだが、誰もが土壌回復費用を少しでも抑えようとするから、廉価で短期間で終了する上述の原始的方法を選択することになる。従って、徹底的な土壌汚染の除去を目指す新技術は費用もかさむし、工期も長いことで敬遠される。
本来ならば、土壌回復は移転したり、破産して“毒地”を残した企業が責任を負うべきだが、それらの大多数は国有企業や“集体企業”<注3>であり、その責任を追及していくと国家になる。また、ある土地は転売が繰り返されたことで責任の追及が困難、あるいは企業が破産していて支払い能力がないというのが実情である。このため、本来なら費用を負担すべき企業の肩代わりで土壌回復をするのだから、少しも安いに越したことはないというのが地方政府の本音なのである。
<注3> “集体企業”は企業の資産が労働大衆からなる集団の所有として登記された経済組織。
2011年に広州市の旧“南方鋼鉄廠”跡地に建設される“保障性住房(保障性住宅)”<注4>プロジェクトの環境評価調査が行われた際には、重金属汚染と有機物汚染の調査を同時に行うべきだと提案した評価委員に対して、プロジェクトを受注した建設会社から重金属汚染の調査だけを行うよう圧力がかかったという。一般に製鉄所の場合は有機物汚染が深刻なので、有機物汚染調査を重点的に行うのが筋であるが、建設会社は最終的に重金属汚染調査だけを行って、有機物汚染調査を無視した。この理由は有機物汚染の除去は処理費用が高額で大幅に予算を喰うというものだった。
<注4> “保障性住房(略称:“保障房”)は中低所得者向けの廉価な分譲住宅および賃貸住宅。
こうして完成した環境評価報告書は広州市環境保護局によって承認され、重金属が基準を微量に超過した土壌はわずか300立方メートルしかないという虚偽の結果が認められた。この結果、保障性住宅の建設は進められているが、この敷地が依然として“毒地”であることは明白な事実である。保障性住宅が完成した暁に入居する住民の健康が気がかりだが、これが中国の“毒地”活用の実態である。これは広州市だけに限定されたものではない。
中国の土壌回復の専門家は、「国外では土壌回復と地下水回復は不可分の関係にあるが、中国ではこの5年間は土壌回復のみに傾注して、地下水回復はほとんど行われていない。たとえ土壌回復を行ったとしても、未処理の汚染された地下水が土壌を汚染させ続けるという事実が認識されていない」のだという。そうだとすれば、土壌回復だけやっても意味がないわけで、地下水回復を含めた総合的な“毒地”への対応が不可欠である。
日本企業に「転ばぬ先の杖」が必要
しかし、“毒地”が全国にどれだけあるかさえも不明だし、たとえそれが分かったとしても、財政上の理由でおざなりな汚染除去で事足りるとして住宅用地として活用するのが通例というもので、こうした状況が早期に改善される見込みは全くない。この点について、6月4日付の「中国経済ネット」が掲載した“毒地”関連記事は、「地方政府は土地財政の角度から、大量の“毒地”を汚染除去の処理をしないまま住宅として開発しているが、これは一種の愚民行為であり、“失徳之挙(徳を失った行動)”である」と指摘している。
目先の利益に釣られることを諺で「鹿を追う者は山を見ず」と言うが、この出所は中国の古典「淮南子」の「遂獣者目不見太山。嗜慾在外、則明所蔽矣。(獣を追う者は目に太山を見ず。欲望が現れると、聡明さが隠れてしまう)」である。目先の利益を追求するあまり、国民の幸福という百年の計を見失うとすれば、まさに“失徳之挙”と言わざるを得ない。
中国はいち早く「土壌汚染防止法」を成立させて、“失徳”を“有徳”に方向転換しなければならない。
ところで、中国で「土壌汚染防止法」が制定された後に、その初期段階で取り締まりの標的となるのは外資系企業、特に日系企業となることが予想される。筆者は従前から講演をするたびに、中国に進出している日本企業に対してこの警鐘を鳴らし、速やかに土壌汚染の除去に取り組むよう力説してきている。何事も「転ばぬ先の杖」の対応が肝要です。
(北村豊=住友商事総合研究所 中国専任シニアアナリスト)
(註)本コラムの内容は筆者個人の見解に基づいており、住友商事株式会社及び株式会社住友商事総合研究所の見解を示すものではありません。
世界鑑測 北村豊の「中国・キタムラリポート」
日中両国が本当の意味で交流するには、両国民が相互理解を深めることが先決である。ところが、日本のメディアの中国に関する報道は、「陰陽」の「陽」ばかりが強調され、「陰」がほとんど報道されない。真の中国を理解するために、「褒めるべきは褒め、批判すべきは批判す」という視点に立って、中国国内の実態をリポートする。
⇒ 記事一覧
北村 豊(きたむら ゆたか)
住友商事総合研究所 中国専任シニアアナリスト
1949年長野県生まれ。慶應義塾大学法学部政治学科卒業。住友商事入社後、アブダビ、ドバイ、北京、広州の駐在を経て、2004年より現職。中央大学政策文化総合研究所客員研究員。中国環境保護産業協会員、中国消防協会員
|
|
|
|
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます(表示まで20秒程度時間がかかります。)
|
|
 スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。