http://www.asyura2.com/12/hasan76/msg/200.html
| Tweet |

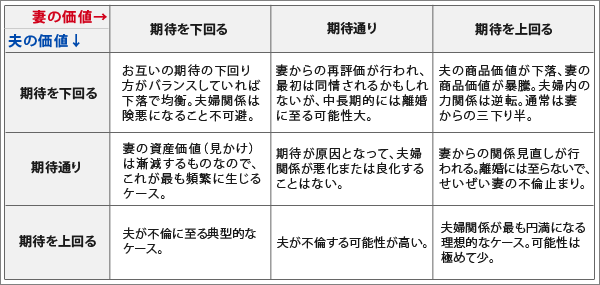
http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/35217
恋愛と結婚の経済学
女も男も格差社会、死語になる「夫婦の絆」
社会の変化が「恋愛と結婚の均衡」を打ち砕く
2012.05.17(木)
森川 友義
今回のテーマは、長い結婚生活における「男女の資産価値の変化」です。「恋愛均衡説」はすでに学びましたが、結婚後に訪れる不可避の不均衡問題が重要です。人生長いですから、いろいろなことが起こります。その各々が離婚の原因になってしまうのです。
まずは恋愛均衡説から
携帯電話の通話記録による調査で年齢を重ねると女は夫や恋人への関心が薄れることが分かった〔AFPBB News〕
この連載では何度も、恋愛は等価交換であると説明してきました。お互いの資産価値を前提にして物々交換をしているのだと。
また、結婚というものは、「女は男の可能性を買い、男は女の旬を買う」というふうに考えることも申し上げました。
女は男の将来性を青田買いします。30歳前後の男なら将来社長になることも可能です。
あるいは、激動する世の中、仕事を失って路頭に迷う可能性がないわけではありません。結婚の時点で、可能性に懸けるというのが女の行う行為です。
他方、男は女の人生の中で最も輝いている時期を手に入れるということになります。特に女の見かけに重きをおいて結婚する場合には、生花と同じように時間とともに視覚的魅力は劣化していきますので、結婚した時点が女の最高の瞬間と言えなくもありません。
このように男女間では交換するものは異なるものの、同性内でのステータス(年収の多寡や見かけの優劣)によって等価交換を行うことになります。
しかし、結婚当初はお互いの商品価値は均衡していたとしても、その後の人生は長い。平均すると50年くらいあります。
バランスがずっと保たれる場合もあるでしょうが、実際には均衡は崩れて、両者の価値に開きが生じてしまう可能性の方が高いのです。
むしろ、必ずバランスは崩れると言ってもよい。それほど、人生は長いのです。バランスが崩れたとき、離婚の危機が迫ります。
均衡が崩れる場合の問題は何か?
現代では、長期的には、自分が将来どのようになっていくか自分自身でも分からないほど不透明になっています。しかし、そう遠くない昔には、勤め始めてから定年までほぼ予想できる制度がありました。
日本では、太平洋戦争が終わった1945年から、バブル経済が崩壊した1990年前半までの長い間、年功序列と終身雇用制度という、社会主義みたいな制度をずっと採っていたのです。
このような状況だと、「自分」の資産価値の計算はたいへん容易だったはずです。何歳でいくらくらい稼げて、どのくらいのポジションに昇進し、定年は60歳で、その後退職金と年金はいくらで、という計算が、好むと好まざるとにかかわらず、分かっていたのです。
当時は敗戦によって将来が不透明という社会的背景があったので、将来が見えることが長所だったのです。極端に言えば、18歳で大学受験をして、どの大学に行くかで、だいたい人生が見えたのです。
バブルが弾けて、欧米型の雇用形態になった昨今、先行きの不透明感は増して、転職も頻繁になったので、「自分」の将来の価値も、結婚関係に入る時には、予想しづらいといったことが生じています。
従って、結婚した当時は、うだつがあがらないサラリーマンだったけれど、その後、一念発起して、法科大学院に通い、司法試験に受かって弁護士になったとか、IT企業を立ち上げたら大当たりして金持ちになったとか、倒産はあり得ないと思っていた大企業が潰れて失職したとか、様々な可能性が出てくるようになりました。
下の図は「市場価格が変動した場合の夫婦関係の結末」をマトリックスにしたものです。自分および相手に対する評価の誤差によって生じる心理メカニズムを図表にまとめてみました。
自分と相手の市場価値が変動した場合の夫婦関係の結末(結婚したときには両者の市場価値は均衡していたと仮定。また自分の下す期待値と相手が下す期待値は同じと仮定)
この図では、自分の価値と相手の価値が、予想以上あるいは予想以下にもなって、それが結婚関係に大いに影響を与えるのが分かります。
(1)自分または相手の資産価値が上がった場合
自分の価値が期待以上に上がった場合には、結婚生活に良い影響を与えると思いがちですが、そんなことはありません。悪影響を与える可能性が高いのです。
自分の資産価値が上昇することですから、価値の上がる前の相手との価値が釣り合わなくなるという事態になります。
「自分が成功したのは、相手のおかげ」と思えるようであれば問題はありませんが、通常、人は「成功は自分の功労、失敗は他人のせい」と考えるようですので、成功を恋人あるいは配偶者に帰することはできないようです。
もし「奥さんのおかげ」、あるいは「旦那さんのおかげ」と思えるような人だと、夫婦関係は長持ちします。
理論的には、お互いの商品価値の均衡が崩れた分、上がった方はよりレベルの高い異性を追い求めようとします。
別れや離婚ができない場合には、不倫によって資産価値の差を埋めようとするようです。経験的に不倫が急激に増えるのは、男が出世したり、年収が増えたりする時です。
(2)自分または相手の資産価値が下がった場合
資産価値が下がる場合にも当然、問題が生じます。
結婚当初に均衡が崩れる原因は、結婚前に秘匿していたものが顕在化した場合です。例えば、男女ともに、DV、極端な性癖、犯罪歴、性病、マザコン、借金といったものが挙げられます。
とは言ってもハネムーン時代はまだ恋愛バブルも生じていることでしょうから、それほど大きな問題とはならないかと思います。
夫の価値が将来下降する場合は、事業に失敗した、勤めていた企業が倒産した、痴漢して逮捕された、セックスが全くなくなった、など相手が持っている期待値を下回ることは、しょっちゅう生じることですが、必ずと言っていいほど、別れや離婚が待っているようです。
繰り返し述べているように、妻は夫の将来性に期待して結婚するので、期待通りに上昇してくれない場合には、落胆が大きいのです。
この図表から分かる通り、夫婦が円満であるケースは、男女ともに資産価値が変わらないか、両者ともに期待を上回るときに限られます。
一方が突出して資産価値が増えたり、減ったりするとどうしてもアンバランスが生じて、夫婦関係円満とはいかなくなるようです。
不透明な時代であることは、夫婦関係も不透明であるということなのです。1つの結婚生活を全うすることがどれだけ難しいことかお分かり頂けたかと思います。
http://business.nikkeibp.co.jp/article/manage/20120514/232008/?ST=print
企業・経営>「気鋭の論点」
失業したら、パラサイトシングルも悪くない
米国で急増する「ブーメラン世代」の消費行動とリスク
2012年5月17日 木曜日 山田 知明
一億総中流と呼ばれた時代が終わり、日本の経済格差が注目されるようになって久しい。書店には、様々な角度から格差問題を論じた本が並んでいる。一番多いのは、派遣労働や生活保護などに代表される、いわゆる低所得者層あるいは社会的弱者をテーマにした本だろう。社会的弱者への配慮は大切であるが、そればかりに注目すると、格差問題が持つ様々な影響を過小評価してしまう。
ラグラム・ラジャン米シカゴ大学教授は、著書『フォールト・ラインズ』(新潮社)の中で、米国発の金融危機の背景に、「所得格差の拡大があった」と論じている。低所得階層向け融資の拡大と証券化の組み合わせが、金融危機の一因であったことはよく知られている。しかもその債務不履行の可能性が高い低所得階層への貸し出しには、政府主導の側面があった。
米国政府は、所得格差に対して教育や税制や再分配政策で対応する代わりに、政府支援機関を通じた安易な貸し付けの拡大に走った、というのがラジャン教授の主張だ。低所得者であっても、「夢の」マイホームを持つことができる。それは彼らが抱える現状への不満を、一時的に和らげる効果があったのである。
このように経済格差は、それ自体が問題になるだけではなく、マクロ経済や政治的意思決定を通じて経済政策にも多大な影響を与える。ここでは、所得格差だけではなく消費格差も分析することで見えてくる事実ついて、マクロ経済的観点から考えていきたい。
臨時収入増と定期収入増を分けて分析
経済格差がマクロ経済に与える影響を理解する上で鍵となるのが、ミルトン・フリードマンの「恒常所得仮説」である。学部レベルのマクロ経済学では、「消費は国民所得の関数であり、所得が増えると限界消費性向に応じて一定割合だけ消費も増える」と教えている。しかし、実際の消費者の行動はもっと複雑だ。
例えば、宝くじで1万円当選した場合と、昇進をして月給が1万円増えた場合を考えてみよう。前者は一度きりの収入増であるのに対して、後者は恒常的に収入が増えている。前者で毎月の生活を変える人はいないと思うが、後者であれば、外食を増やしたり少し高めの家賃のマンションに引っ越したりする人も出てくるかもしれない。
両者を区別するために、前者のような所得変動を一時的ショック、後者を恒常的ショックと呼ぶ事にしよう。もちろん、両ショックは所得を低下させることもある。フリードマンによると、消費者は一時的ショックと恒常的ショックを区別して、消費活動をする。これが「恒常所得仮説」である。
統計上、所得のばらつきが大きくなると経済格差の指標は拡大して見える。しかし、そこからは一時的ショックと恒常的ショックの違いが見えてこない。どちらもショックが大きくなれば、所得格差を拡大させるからだ。だが、一時的ショックの拡大と恒常的ショックの拡大では政策的対応が異なるため、両者を識別する必要がある。そこで注目するのが、「消費支出の格差」だ。恒常所得仮説に基づけば、所得変動にどのように家計が反応したかは、消費に表れるはずである。
所得格差ほどは消費格差が拡大していない米国
恒常的ショックと一時的ショックを区別すると、経済格差の統計から興味深い事実が分かった。いくつかの実証研究によると、米国の所得格差は過去40年間を通じてほぼ単調に増加しているのに対して、消費支出の格差拡大は1980年代以降、緩やかなものであったのだ。
もし現在の所得に比例して消費するのであれば、所得格差と消費格差は1対1で対応するはずである。しかし、実際の家計は所得変動だけでなく、統計に表れない様々な情報に基づいて消費支出を決定している。所得格差が拡大しているのに、消費格差が拡大していない時期は、一時的ショック、すなわち貯蓄の切り崩しなどで簡単に対応ができる一時的な所得の落ち込みを経験した家計が多かったと考えられる。
2008年の米「アメリカン・エコノミック・レビュー」誌に掲載された論文の中で、リチャード・ブランデル英ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン教授、ルイジ・ピスタフェッリ米スタンフォード大学教授、イアン・プレストン英ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン教授の3人は、米国において、一時的ショックと恒常的ショックがどの程度、消費に反映されているかをミクロデータから確認した。
彼らの研究によると、一時的ショックに対して消費はわずか5%しか反応しない一方で、恒常的ショックに対しては65%も反応していた。つまり、米国の消費者は一時的な所得変動というリスクに直面していても、それに敏感に反応して消費支出を増やしたり減らしたりはしなかったのである。
対策が難しい「恒常的ショック」
では、日本経済は一時的ショックと恒常的ショックのどちらがより支配的なのであろうか。日本では、ミクロデータの利用可能性などの問題から、まだ決定的な事実は分かっていない。しかし、筆者たちの現在進行中の研究によると、過去30年間、所得格差も消費格差も拡大傾向にあるが、時期によって所得格差の伸びと消費格差の伸びが異なる時期が存在している事は確認できた。例えば、バブル崩壊と90年代後半の金融危機はどちらも不況であるが、経済格差の観点からはどうやら同じ「不況」で一括りには出来ないのである。税制の変更や日本的雇用慣行の崩壊など様々な原因が考えられるが、この点については更なる研究が必要である。
では、どうすれば所得変動のリスクとうまく付き合っていくことができるのだろうか。一時的ショックを和らげることは難しくない。実際、米国の家計は、一時的ショックからほとんど影響を受けなかったことが分かっている。一時的な所得低下は、十分な蓄えがあれば、貯蓄の切り崩しでしのぐ事ができる。貯蓄という自己保険は、所得リスクから身を守る手段の一つであるといえる。
一方、恒常的ショックに対するリスクシェアリング(リスクの緩和)は容易ではない。いつまで経っても低下した所得が以前の水準に戻らないのであれば、貯蓄を切り崩して高めの生活水準を維持しようとしても、いずれ底をつくだけだ。だが、前述のブランデル教授たちの研究では、若年層もそれなりに一時的ショックや恒常的ショックに対応できていた。中高年層と比較して貯蓄をほとんど持っていない若年層が、どうやってショックに対応しているのか。その理由ついては、それまで消費格差を研究する人たちにとっては一種のパズル(謎)であった。
「恒常的ショック」を「一時的ショック」に変えよ
実は、米国では「ブーメラン世代」と呼ばれる、一度は独立した若者が失業するなどして、親元に戻ってくる現象が起きていたのである。グレッグ・カプラン米ペンシルバニア大学助教授によると、このブーメラン現象が近年の米国の若者にとって大切なリスクシェアリング手段となっているという。
人々は、貯蓄以外にも様々なリスクシェアリング手段を持っているということである。日本でも数年前、パラサイトシングルという言葉が有名になった。「いつまでたっても独立できない子供」というネガティブな側面ばかりが強調されていたが、親元で暮らすというのは立派なリスクシェアリングの手段であると言えるのである。
ただし親元に戻るという選択肢がない場合、すぐに収入を得ないと生活ができないため、留保賃金を下げてでも早急に職を見つけないといけない。そういう人にとっては失職はすなわち恒常的ショックを意味し、生活水準も大幅に低下せざるをえない。一方、親元に戻る事ができれば、多少時間がかかっても、より良い職場を探す事ができる。生活に必要なものは一式揃っているし、生活上の不便はない。そのため、親との同居は、貯蓄に乏しい若者のリスクシェアリングの手段として、そして労働のミスマッチを防ぐ手段としても大切なのである。むやみに子供を独立させることが良いとは限らないのだ。
こうして所得格差と消費格差を組み合わせて分析することで、家計が直面するリスクの違いが見えてきた。一時的ショックと恒常的ショックの区別をしないで、まとめて再分配政策で所得格差を縮小しようとする発想は危険である。
過度な再分配政策は、教育投資へのインセンティブ(動機付け)や働く意欲を阻害する。そのため、経済成長率を低下させる可能性がある。また、一時的ショックも恒常的ショックも貯蓄や様々な助け合いである程度、緩和できている。手厚すぎる公的介入が、「個人間のつながり」という保険機能を希薄にする可能性も無視できない。
一方で、一度きりの就活の失敗が人生を決めかねない現在の日本的雇用システムは、大きな恒常的ショックを放置している状態である。若者が再チャレンジできる社会にすることは、恒常的ショックを一時的ショックに変える事を意味する。消費格差を分析することで、恒常的ショックに対して様々な形で対策を取る事も可能だろう。
政治家による有権者へのご機嫌取りのような再分配政策が長期的な経済運営に影響しないように、格差問題を考える時は、ミクロ的視点からマクロ経済を見なければいけないのである。
「気鋭の論点」
経済学の最新知識を分かりやすく解説するコラムです。執筆者は、研究の一線で活躍する気鋭の若手経済学者たち。それぞれのテーマの中には一見難しい理論に見えるものもありますが、私たちの仕事や暮らしを考える上で役立つ身近なテーマもたくさんあります。意外なところに経済学が生かされていることも分かるはずです。
⇒ 記事一覧
山田 知明(やまだ・ともあき)
明治大学商学部准教授。2000年立教大学経済学部卒業。2005年3月一橋大学大学院経済学研究科単位取得退学。2005年7月同大学博士(経済学)。立正大学講師を経て2009年4月から現職。専門は定量的マクロ経済学、経済格差、社会保険。「Journal of Economic Dynamics and Control」、「Macroeconomic Dynamics」などに論文掲載。
(写真:都築雅人)
|
|
|
|
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます(表示まで20秒程度時間がかかります。)
|
|
 スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。