http://www.asyura2.com/12/hasan75/msg/317.html
| Tweet |
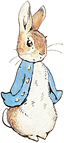
日経新聞が、今週、消費税増税キャンペーンの一環として連載した「消費税増税信認への課題」というシリーズから、私が投稿を続けている消費税の内実に関係するものを紹介したい。
京都大学教授諸富徹氏の論文で、「国民理解へ「公平」重視を」というタイトルになっている。
キャッチには、「中小の「益税」解消急げ 金融取引への課税も課題」と書かれている。
冒頭部分に、「いずれ負担増が避けられないのであれば、できる限り公平に国民の間で分かち合い、なおかつ日本経済の持続的な成長と整合的な税制を構築すべきであろう。グローバル時代に最も重要な課税原則は、「課税ベースを広く取って公平課税を実現しつつ、効果的に税収を調達して税率の上げ幅を必要最小限に抑え、結果として経済活動への悪影響を最小化すること」である。消費税はその条件にかなうであろうか」と、展開を期待させる内容が書かれている。
さらに、「日本が採用している消費税は一般に「付加価値税」と呼ばれる。原則としてすべての財・サービスに対し、生産・流通・消費の各段階で生じる付加価値に一律税率(現行5%)で課税する。この税は、広い課税ベースを設定して多額の税収を効果的に調達し、なおかつ税率を低く抑えられる点で優れている。しかし、現実には理念から乖離(かいり)しているところもあり、改革が必要となっている」と続くので、主流派財政学者も、いよいよまともな論議をするようになったのかとワクワクし始めた。
ところが、“現実には理念から乖離(かいり)しているところもあり、改革が必要”として取り上げられているのは、小規模事業者が該当する「事業者免税点制度」や「簡易課税制度」だけで、3兆円に上るとも言われている肝心要の輸出免税問題は出てこない。
「原則としてすべての財・サービスに対し、生産・流通・消費の各段階で生じる付加価値に一律税率(現行5%)で課税する。この税は、広い課税ベースを設定して多額の税収を効果的に調達し、なおかつ税率を低く抑えられる点で優れている」というのなら、「輸出戻し税」制度により、生み出した付加価値に対して1円の消費税も負担しないばかりか、奇妙なロジックで数千億円の還付金まで受け取っている輸出有力企業を取り上げないで済ませるわけにはいかないはずだ。
諸富氏が輸出免税制度やその後の取り扱い内容を知らないはずもないのに、“美辞麗句”で消費税を持ち上げるや、消費税の本旨に背いているという理由でただでさえぎりぎりで事業を続けているところが多い小規模事業者を“益税”で叩くという恥知らずぶりについ笑ってしまった。
(“益税”と表現されているものは、実質的には軽減税率の適用であり、付加価値税に“益税”という概念は存在しない)
ただ、終わりの部分で、金融・保険分野の主たる収入が“非課税”になっていることを問題にし、“キャッシュフロー付加価値税”やIMF提唱の“金融活動税”を提示していることは諸富氏を評価できる。
金融事業者の消費税非課税問題は、現在投稿をしているシリーズの最後に考え方を示したいと思っている。
理由も書かないままで恐縮だが、付加価値税の公平性という観点で言えば、IMFの“金融活動税”のほうが好ましいと思っている。
===============================================================================================
消費税増税信認への課題:(2)国民理解へ「公平」重視を
諸富徹 京都大学教授
中小の「益税」解消急げ 金融取引への課税も課題
<ポイント>
○課税ベースの拡大で税率上げ幅の抑制可能
○事業者免税点制度や簡易課税制度は弊害大
○欧米諸国は金融セクター課税の議論進める
野田佳彦政権は2月17日、「社会保障・税一体改革大綱」を閣議決定した。現行の消費税率5%を段階的に8%、10%へと引き上げる方針である。国民の消費税増税への反発はかなり強いが、国民は同時に、少子高齢化による歳出増加が不可避であることや、低成長時代にはもはや成長による税収の自然増に頼れないことも知っている。
いずれ負担増が避けられないのであれば、できる限り公平に国民の間で分かち合い、なおかつ日本経済の持続的な成長と整合的な税制を構築すべきであろう。グローバル時代に最も重要な課税原則は、「課税ベースを広く取って公平課税を実現しつつ、効果的に税収を調達して税率の上げ幅を必要最小限に抑え、結果として経済活動への悪影響を最小化すること」である。消費税はその条件にかなうであろうか。本稿では、この観点から消費税の設計上の課題を論じたい。
日本が採用している消費税は一般に「付加価値税」と呼ばれる。原則としてすべての財・サービスに対し、生産・流通・消費の各段階で生じる付加価値に一律税率(現行5%)で課税する。この税は、広い課税ベースを設定して多額の税収を効果的に調達し、なおかつ税率を低く抑えられる点で優れている。しかし、現実には理念から乖離(かいり)しているところもあり、改革が必要となっている。
1点目は、納税実務を行う中小事業者の便宜を図ったり、徴税コストを最小化したりするために導入された「事業者免税点制度」や「簡易課税制度」である。これらは付加価値税導入国に普遍的にみられる制度的工夫だ。しかし、仮に徴税コスト最小化の観点から正当化できるとしても、税収ロス、消費税が適切に納税されず事業者の手元に残る「益税」の発生やそれに伴う消費者の不信、そして免税点以下の事業規模への分割によるゆがみがもたらすマイナス面を比較衡量し、制度維持の可否を判断すべきであろう。
事業者免税点制度は、基準期間における課税売上高が1千万円以下の事業者の場合に課税が免除される仕組みだ。消費者からみれば、購入先の事業者が免税業者かどうか分からず、その事業者が販売する財・サービスに対して消費税を負担することになる。しかし、実際には事業者は免税されているため、消費者が支払った消費税相当分が「益税」として事業者の手元に残る可能性が指摘されてきた。
一方、簡易課税制度は、中小事業者の納税事務の負担を軽減する仕組みだ。売り上げに対する消費税から仕入れでかかった消費税を差し引ける「仕入れ税額控除」では本来、仕入れ実額に基づくべきだ。しかし、事業者が正確に実額を記録・計算するのは大変であるうえ、帳簿や領収書などの証拠書類の保存が負担になるとの配慮から導入された。
現在、5種類に分類された事業ごとに「みなし仕入れ率」が適用されている。しかし、みなし仕入れ率が現実の仕入れ率よりも高ければ、それだけ仕入れ税額控除は計算上大きくなる。結果的に、適用事業者の消費税負担額は実額控除の場合に比べて小さくなり、その分だけ「益税」が発生する。財務省の資料によれば、現実の仕入れ率がみなし仕入れ率よりも低い事業者が多数を占める業種が複数存在しており、「益税」の存在をうかがわせる(図参照)。
政府はこれまで両制度の適用対象を絞り込むとともに、制度の実態を現実に合わせるべく改革することで「益税」の縮小に努め、一定の成果を上げてきた。しかし今後、消費税率をさらに引き上げるのであれば、この問題はさらに増幅される。「益税」解消に向けた一段の取り組みは、消費税増税の必要条件である。
2点目は、課税ベース拡大の必要性である。日本では土地の譲渡・賃貸、住宅の賃貸、金融・保険、医療、教育、福祉などに関わる取引が非課税となっている。諸外国でもほぼ同様である。この措置は、技術的に課税が難しい場合、あるいは非課税とすることで政策的にそのセクターにおける財・サービス供給を促す場合に設けられる。
しかし、付加価値税の趣旨からいって、非課税取引の適用は極めて限定的であるべきだ。技術的に課税困難でも、その克服のための方策を見つけて付加価値税の課税ベースを拡大すべきだとの指摘もある。特にこの点で注目されるのは、経済活動の規模からみても重要性が高く、課税されれば多額の税収を上げられる金融・保険分野である。
銀行を通じた金融取引のキャッシュフローに対して付加価値税(税率10%)を課税するケースを考えよう。まず1年目に、預金者が1千万円を銀行に預け入れ、銀行はこの預金を元手にして企業に1千万円を融資したとする。1年目のすべての金融取引の結果は、資金預け入れ1千万円に対して貸し出しも1千万円なので、銀行の純キャッシュフローはゼロとなる。従って課税ベースはゼロ、結果として付加価値税額もゼロになる。
そして2年目には、貸し出された資金が10%の利子を伴って銀行に返済され1100万円となり、預金者は5%の利子がついて預金1050万円を引き出したとする。この場合、銀行の純キャッシュフローは差し引き50万円、それに対する付加価値税は5万円となる。逆ざやにならない限り、原理的にこうした課税は可能であり、保険やその他の金融商品にも適用できる。
ただし、キャッシュフロー付加価値税は、課税の計算方法が既存の付加価値税とかなり異なるので、課税実務上の問題が生じかねない。そこで代替案として提案されているのが、国際通貨基金(IMF)が提唱する金融活動税(Financial Activities Tax=FAT)だ。キャッシュフロー付加価値税が「消費型」付加価値概念に基づくのに対して、金融活動税は「所得型」付加価値の概念に基づき、金融機関の「利潤+賃金」に対して課税ベースを設定する。
課税方法からいって、現行の付加価値税と別建てで金融セクターに課税することになるが、課税ベースを広げてより公平な課税を実現する一つの有力な手法であろう。欧米諸国で熱心に議論される背景には、世界金融危機以来、多額の公的資金が金融機関救済に投入されたことに対してバランスの取れた負担を求めるべきだという考え方や、将来起こりうる金融危機に対して予防的基金を積むための原資にすべきだという考え方がある。日本でも、金融セクターへの付加価値課税という方策を真剣に検討すべき時期に来ているのではないだろうか。
最後に、垂直的な意味でより公平な消費課税をするためには、制度インフラの整備が不可欠である。消費税率を段階的に引き上げていくのであれば、いずれ本格的な逆進性対策を求められる。
欧州諸国では逆進性対策やその他の政策目的のため、食料品などに対するゼロ税率や軽減税率が設定されている。日本も将来、逆進性対策として生活必需品にゼロ税率や軽減税率を適用するならば、仕入れでかかった消費税を正確に把握できるインボイス(送り状)制度の導入が必要になる。一方、給付付き税額控除を軸にするなら、税・社会保障の共通番号導入が必要になる。いずれにせよ合意形成も含めて相当時間がかかる難題であるだけに、将来を見据えた制度インフラの構築が急務だ。
もろとみ・とおる 68年生まれ。京都大博士(経済学)。専門は財政学、環境経済学
[日経新聞2月28日朝刊P.29]
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます(表示まで20秒程度時間がかかります。)
 スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。