http://www.asyura2.com/12/hasan75/msg/163.html
| Tweet | �@ |
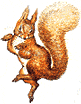
���̂Ƃ��A�o�c�͔��f������� ��Ђ��_���ɂȂ����u�� �\�j�[ NEC�ق�
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/31779
2012�N02��14���i�j �T������@�F����r�W�l�X
�@���{���\�����Ƃł���\�j�[��p�i�\�j�b�N���ꋫ�ɂ������ł���B�ǂ����Ă���Ȃ��ƂɂȂ����̂��B�ǂ��ł��������ԈႦ���̂��B�����ĒN���ԈႦ���̂��B�O�����̂����ɂ��Ă������������Ȃ��B
�������������ŐH���Ă����̂�
�uNEC��d�d����(��NTT)�Ɉˑ����釀�����Ƈ�����A���E���ŃR���s���[�^�A�����́A�ʐM�@�Ȃǂ����鑍���d�@���[�J�[�ɐ����������̂́A1980�N����15�N�߂����В��𑱂����֖{���O���ł��B�����}���o�c�ɂ͔ᔻ�����������A�J���X�}�I�Ƀ��[�_�[�V�b�v�����ĎГ����������������т͑傫���B
�@�����A1998�N�ɖh�q���ւ̐������������������o���A�֖{�������ނ��ƁA�V�В��ƂȂ������_�_�i�����n�[�h����\�t�g�ւ̘H���]�����s���A�ʐM�@�A�d�q���i�ȂNJ֖{������ĂĂ������Ƃ����X�ɐ�̂ĂĂ������B����ɓ{�����֖{���Ɛ��_���̊ԂŁw�֖{vs.���_�푈�x���u���A�ĉ�����悤�ɎГ��ł̓R���s���[�^�h�ƒʐM�h�̔h���Η����\�ʉ������B�U��Ԃ�Ί�@�̌����́A���̎��ɕ����o���Ă����Ƃ�����̂ł��傤�ˁv(NEC�̌�����)
�@2012�N1��26���A�����s�`��łɗ��u�X�[�p�[�^���[�v�n��1�K�̑��ړI�z�[�����ŁANEC�̉����M���В����₢�l�߂��Ă����B
�u����̐l���팸�͏����ł͂Ȃ��{�C�̂��̂��v
�u�g�ѓd�b�̊C�O���Ƃ̐L�т����B���ł��邱�Ƃ����Ăق����v
�@���̓����\���ꂽNEC�̌��Z���e���u�����C���̔�����v�Ɲ��������قǁA�S�邽����̂��������炾�B���ׂĂ݂�A�u�ʊ��̔��㍂�\�z��1500���~�����C���v�u�N�Ԃ̌g�ѓd�b�o�ב䐔�v���150���䉺���C���v�Ƃ��������ŁA�u�\�����v�Ƃ���1���l�̐l���팸�v�u�]��150���~�̍����Ƃ��Ă����ʊ��̓��������v�\�z��1000���~�̐Ԏ��ɉ����C���v�Ɩڂ�����̎S��ł���B
�u����NEC�͒��Ԍ��Z���ɒʊ����㍂�\�z�ƌg�ѓd�b�̔N�ԏo�ב䐔�������C����������B���ꂪ��N10���̂��ƂŁA���̎��͒ʔN������搂��Ă����̂��A������3�����ō����1000���~�̐^���ԂȌ��Z�ɓ]������ƌ����Ă̂����B�������̘T���N�Ԃ��Ⴢ��炵����Q���҂��A���^�����ɓ���Ɖ����В��Ɛ쓇�E��������s�����̗������l�₵���v(�S�����o�ϕ��L��)
�@���Ђ�2010�N2���ɒ����o�c�v��uV2012�v�\���A2012�N�x�ɏ����v1000���~�̖ڕW���f���Ă����B�������A����̉�ł́u���N�x�ł̒B���͂قڕs�\�ɂȂ����v�Ƃ̔s�k�錾����яo�����Ƃ����B
�@���Ĕ����̂Ő��E��̎��ƋK�͂��ւ�A�����@�ƌĂꂽ�p�\�R���uPC-9800�V���[�Y�v��ɔ���܂������ʉe�͏����������B�����̎��Ƃł͊؍��A��p���ɑ啉�����A�p�\�R�����Ƃ͒�����Ƃɇ��������p���B���݂̒ʐM��l�b�g���[�N���Ƃ͊C�O�i�o�ɏ��x��ć����ٌc������E�����ꂸ�A�V�K���Ƃ�����Ă��Ȃ��B�v����Ɂu5���A�������̌����ׂ͖��鎖�Ƃ��قƂ�ǂȂ��Ȃ��Ă��܂������Ƃɐs����v(�O�o�E�o�ϕ��L��)�B
�@�ǂ����Ă����܂Ń_���ɂȂ��Ă��܂����̂��B�O�o�E�������������Č����B
�u���_���A���̌�C�̋������M���ƃR���s���[�^�h����������A���Ƀg�b�v�o�����̂��ʐM���̖��O���B�O�C�҂��������А��i�邱�Ƃɂ͂������Ȃ��Ƃ����H���ł����̂��A��쎁�́w�U�ꂷ�����x�Ƃ��Ď��А��i���Ă������j�ɕύX�����B�В������邽�тɁA���j����v�����̐l�����R���R���Ɠ���ւ��B�����NEC���w���ŐH���Ă����̂��x�m�ɂł��Ȃ��Ȃ�A�Г����o���o���ɂȂ����B
�@��v���Ƃƈʒu�Â��Ă����w�O�{���x�̂����̓�A�g�ю��ƁA�����̎��Ƃ͕s�̎Z�����Ă���̂ɂ�������炸���v���x�ꂽ�B����ƍ\�����v�ɓ��ݍ��߂��̂�2010�N�̂��ƂŁA�������ɍ��x�́w���ꂩ��̓N���E�h�T�[�r�X��`�E���C�I���d�r��ׂ����ɂ���x�ƂԂ��グ�n�߂��B�����̐V�K���Ƃ��܂����ʂ��o�Ă��Ȃ����Ƃ͍���̌��Z���\������Ζ��炩�B�ꎖ���������̒��q�ŗ�������A�C�t���ΎГ��ɖׂ��鎖�Ƃ��قƂ�ǂȂ��Ȃ��Ă��܂����v
�������̌��̎���
�@��Ђ͓����畅��---�B�ςݏd�Ȃ����o�c���f�̌�肪�A���邢�͂�������̌o�c���f�̃~�X���v�����ƂȂ�B
�@�����ň����x���̐Ԏ����Z�ƂȂ錩���݂̃p�i�\�j�b�N�ɂ��A�ے��I�ȁu��Ђ��_���ɂȂ����u�ԁv������B���N���Ђ̎�ނ𑱂���W���[�i���X�g�̈��v�j���������B
�u�p�i�\�j�b�N�͂��܂���2�N�O�ɁA���z4500���~�𓊎����ĉt���H��(���Ɍ��P�H�s)�ƃv���Y�}�̓���5�H����ғ����������A���ꂪ������o�c���f�������B���łɐ��n�����������e���r���Ƃւ̉ߏ蓊������������ł��B�����A���������ғ����ɔY�܂���A�킸��1�N�Ō��������ɒǂ����܂ꂽ���ʁA�o�����������邱�ƂɂȂ����v
�@�헪�̌����O���C���ł��Ȃ��̂́A���̂悤�ȎГ�������邩�炾�Ƃ����B��㎁��������B
�u�����M�v������������Œz���グ���ƍٓI�Ȍo�c�̐��������ł��傤�B�Г��ł͒�����ɉ��������C�������āA���S�ȋc�_���ł��Ȃ��Ȃ��Ă���B������͂��ăe���r���Ƃ𐬌�����������J�҂�����A�Ȃ��̂��ƃe���r���Ƃ̎��s��ے�ł��Ȃ�������B�В��ł���Ȃ��璆����̐헪�~�X���O���C���ł��Ȃ���ؕ��Y���A�o�c���S���̐X�F�����В��̍߂��d���v
�@NEC�ɂ���A�p�i�\�j�b�N�ɂ���A�o�c�����͌o�c�s�U�̗��R���u�~��������v�u�^�C�̍^��������������v�ƌ��A�O�����ɐӔC�]�ł��邪�A���͉�Ђ̓����ɂ���̂��B
�@�����d�@�ƊE�ɂ�����3���A���Ԏ��̋ꋫ�ɂ������\�j�[�́u�o�c�����f��������u�ԁv�͂���������---�B�\�j�[����ȏ햱�̓V�O�f�N���͂������B
�u�\�j�[�����������Ȃ��Ă���ƋC�t�����̂́A'01�N�ɉ�Ђ̐S���J�E���Z���[�����̂Ƃ���ɂ���Ă��āA�w�T�a�̎Ј������̂����������ő����Ă���B���̂܂܂ł͉�Ђ����������Ȃ��Ă��܂��x�ƌ����Ă����Ƃ��ł��B���̌�A�Г��Őe�����F�l�����ɕ����Ă݂�ƁA������'90�N��㔼����R���T���^���g�𑽗p���Đ��ʎ�`������ȂǁA�č����̍�����`�o�c�ɂ̂߂肱��ł��������Ƃɂ���Ƃ킩�����̂ł��v
�@�����̃g�b�v�͏o��L�V���B'95�N�ɎВ��ɏA�C�����A�u�f�W�^���E�h���[���E�L�b�Y�v�u���E�W�F�l���[�V�����v�Ƃ���������f���A�A�i���O����f�W�^���ւƑ傫���ǂ�����B
�@����ɕč��^�Ǘ���@�����œ����B���ł�EVA(�o�ϓI�t�����l)�Ƃ����o�c�w�W���g���Ċe���Ƃ�]������悤�ɂȂ������ƂŁA�J���҂��Z���I�ȗ��v����ɖڂ�D���A�E�H�[�N�}���Ȃǂ̃\�j�[�炵������I�ȏ��i�����܂�Ȃ��Ȃ����Ƃ�����B
���l����Ă��Ȃ�����
�@�ĂѓV�O���������B
�u���Ẵ\�j�[�ɂ͎��R舒B�ɋc�_���A��l��l�������ɔM�����Ď��g�ށw�t���[�o�c�x���������̂ɁA���ꂪ������`�o�c�Ŕj�ꂽ�B����ł͂܂����Ǝv���āA���͂��̎|�̃��|�[�g�������āA���В��ȏ�̌o�c�w�ɒ�o�����B���T�Y����͓d�b�������Ă��������āA�w����͑f���炵�����|�[�g�������x�ƌ����Ă��ꂽ���A�ق��̌o�c�w����͊��S�ɖ������ꂽ�B
�@���̌���\�j�[�͌o�c���j��ς��邱�ƂȂ��A�Ƒn�͂�D��S�Ƃ������w������́x�������������͈��ނ�����A��Ђ̌o�c�ɂ̓^�b�`�ł��Ȃ�����ɒǂ����ꂽ�肵���B����ɁA���̏����O����\�j�[�ɂ͈ꗬ��w���̐��т������Ј����肪���Ђ���悤�ɂȂ��Ă������A�w������́x�ɖR�����҂������A������`�o�c�ɔ��Ԃ����������B��������\�j�[�͈ނ݂�������A�c�ꂠ����p����x�������Ă��Ȃ��v
�@�o�䎁�����p�w�������n���[�h�E�X�g�����K�[���͂������̂��ƁA���̂��ю����В��ɓ��肵�������v�����G���^���A���۔��o�g�ō�����`�o�c���u������^�C�v�B8���A���Ԏ��̃e���r���Ƃ̍Đ��A�؍��⒆�����[�J�[�Ƃ̃O���[�o�������A�������S�����j���Ƃ̊m���Ȃljۑ�͎R�ς݂ŁA�\�j�[�́u���ꂩ��v�͗\�f�������Ȃ��B
�@�o�c�̔��f�~�X�́A��Ђ�ׂ����낵��������B����͉ߋ��̔j�]��������Ζ��炩���B
�@���Ƃ��_�C�G�[�B�n�ƎҁE���������̂��Ɓu���ʊv���v��搂��č��x�������̍����̏�����x���Ȃ���A�g��H������̓]���Ɏ��s����2004�N���ɎY�ƍĐ��@�\�̎x�����ɓ������B���Ђ̌������Ɂu�_���ɂȂ����u�Ԃ́v�ƕ����ƁA�����U��Ԃ����B
�u�_�C�G�[���_���ɂȂ��Ă����ȂƊ������̂́A�����В����W���j�A(��������)��{�C�Ō�p�҂ɐ����悤�Ƃ����Ƃ��ł��ˁB33�ɂ��ĕ��В��ɏA�C�����A1989�N�Ƀ_�C�G�[�̎�����헪�X�Ƃ���Ă����w�n�C�p�[�}�[�g�x�̌o�c��S�ʓI�ɔC�����B�o�c�o���ɖR�����ɑ�����ς˂��̂́A�����̌�p�҂Ƃ��Ăӂ��킵�����т���点������������ł��傤�B
�@�����ēɌ������W�߂�̂��}���A�Ⴂ�Ј��F���ďd�v�ȃ|�X�g�ɂ��Ă������B�ɋꌾ��悵�����Ȏ��т̂�������͉��������A���������x�e���������͎��X�Ǝ��߂Ă������B����Ŋ�ƂƂ��Ă̗͂͗�����Ǝv���܂����v
�@����o�p���ĎГ��Ɋ��C���o��������A�o�p���ꂽ�l�Ԃ̓W���j�A�̇���芪�����ł����Ȃ������B�c�_�������ɂȂ�ǂ��납�m�[�Ƃ����Ȃ����͋C�����܂��Ă��������߁A�u����̓_�����ȁv�ƌ������͎v�����Ƃ����B���ǁA���������i�����n�C�p�[�}�[�g���Ԏ��𐂂ꗬ���_�C�G�[�̎��s�̏ے��ƂȂ�A�唼�͓X����邱�ƂɂȂ����B
�@�o�c�]�_�Ƃ̕ЎR�C�����������B
�u�����ɐ��P�����邩���ӔN�̒������̃e�[�}���������A���܂������Ȃ������B�v����Ɍ�p�҂̈琬�Ɏ��s�����킯�ł��B����́A�Ɛѕs�U�̖��p�i�\�j�b�N�ɋz�����ꂽ�O�m�d�@�̃P�[�X�������B�n�ƈꑰ�ŎВ��A����20�N��������A�q�����A���q�̈�A�q�뎁���В��ɏA�����Ƃ��A�����Ɍ��L���X�^�[�ł܂��������Ⴂ�̖쒆�Ƃ��掁����ɂ����B�O�m�d�@�����������u�Ԃł����v
�@�q�뎁���В��ɏA�C�����̂�'05�N6���A�V�����z�n�k�ŐV���̍H�ꂪ�����1700���~�̐Ԏ����o������@�I���ł̂��ƁB�q�����i�߂����Z�A�s���Y�ƂȂǂ̑��p���o�c�̎��s�����炩�ɂȂ��������ł�����B�ЎR����������B
�u�܂肱�̎��ɂ����A�Г����v�Ƃ����厡�Â̂��߂̃g�b�v�l�������ׂ��������̂ɁA���P�ɂ���������ɉ��v���x�ꂽ�B����ɖ쒆�����N�p���A�Г��O�Łw���P�̐F�����������ł����߂悤�Ƃ������̂ł́x�ȂǂƋ^���A�g�D�̕s�M�������߂錋�ʂɂ��Ȃ����B�����q���Ɂw�O�m���Ȃ��Ȃ��Ĕ��Ȃ��邱�Ƃ͉����x�Ɛq�˂�ƁA�w�l����ĂȂ��������Ƃ��x�ƌ����Ă����̂���ۓI�ł��v
���V���ЂɃ��[�N�����������
�@��Ђ���@�̂Ƃ������A��_�ȉ��v�ɓ��ݐ�`�����X�Ƃ�������B�t�ɂ����Ŏ��i���A�R�̉��ɐ^���t���܁A��Ђ́u���v�Ɍ������ē]�������Ă����B
�@���{�q��(JAL)�����̍D�Ⴞ�낤�B���ЂɂƂ��Ắu��Ԃ̊�@�v�́A�q��j��ň��Ƃ�����䑃��R�̎��̂������B������JAL���悭�m��o�ϋL�҂������B
�u�䑃��R���̂̑O�܂ŁAJAL�͐�ɒׂ�Ȃ��Ƃ����A���e�����̊یo�c���̂��ƂŐl���R���ɖ������Ă����B�Г��͘H�������Ă���l�͘H���̂��Ƃ����l�����A�@�ނ����Ă���l�͂��ꂵ���l���Ȃ��Ƃ����T�^�I�ȃZ�N�V���i���Y���B����������肪�䑃��R�̎��̂Ō��݉����A���Ē����̂��߂ɃJ�l�{�E�(����)�̈ɓ��~������Ƃ��đ��荞�܂ꂽ�B
�@���̂����ɔᔻ�͂�����̂́A�ɓ�����JAL�̕��̈�Y����|���悤�Ɩz���������A���o�c�w�炪���ɓ��U���Œǂ��l�߁A���ǂ͉��v����͂���������Ƒ̎������̂܂܉������ꂽ�B���܍l������̉��v�̎��s���AJAL�j�]�Ɍ������w���̎��x�������Ǝv���v
�@���̈ɓ������u�����̑c�v�Ƃ��ė������J�l�{�E���A2008�N�A��Ђ����ł��Ă���B
�@�J�l�{�E���M���M���̊R�����ɒǂ����܂ꂽ�̂��A2004�N�̂��ƁB�c��ݏオ����������|����ɂ́A�Ղ̎q�̉��ϕi���Ƃ�����������I�����͂Ȃ��A�Г��͗h��Ă����B�u�ŏI���f�v������ꂽ�̂�'04�N1�����̗Վ��������B������͕��������B���p���`�[���̐ӔC�҂߂��햱(����)�̓��c���O�Y���������B
�u�O��Z�F��s����w���ϕi���Ƃp���Ȃ�������A�m���ɒׂ�邼�x�ƌ�����قǁA�҂����Ȃ��̏ł����B����Ȃ̂ɁA�����ɂ́w����ł��ԉ��ɂ͔��肽���Ȃ��x�w�ԉ��ɔ��邭�炢�Ȃ�ׂ��Ă������x�Ƃ�������ӎ��ɋÂ�ł܂������͂��͂т����Ă����B���͂�������őŊJ��}�邵���p�͂Ȃ��Ȃ�A4��3�͍̋��ʼnԉ��֔��p�̌����������B�������̌�ɁA�O�㖢���̎��Ԃ������܂����B
�@�������I����A���c�ɔ����������̓�l���A�V���ЂɈꕔ�n�I�����[�N�����̂ł��B����ɑS�����Ɂw�J�l�{�E�̉��ϕi���Ɓ@�����t�@���h������āx�Ȃ�L������ʂɌf�ڂ��ꂽ�肵�āA�܂��܂��Г����卬���B���ǁA�ԉ��ւ̎��Ə��n�͔j�k�ƂȂ��Ă��܂����v
�@���p�����J�l�{�E���������P�����ʁA����Č��̓��͒f����A�J�l�{�E�͎Y�ƍĐ��@�\���ɓ������B���c���͌����B
�u���đ@�ۋƊE�̗Y�Ƃ��č��Ƃ��x������Ђ��A������s����ɒׂ��Ȃ��Ǝv�����l�����������̂ł��傤�B���ϕi����ɌX�����āA��Y�Ƃ����łɕ������Ă����J�l�{�E���~����͂����Ȃ��̂ɁA�ł��B���邢�͉ԉ��ɔ��p������̐l��������Ă����̂�������Ȃ��B�ߏ�Ȗ���ӎ��ƁA����̐����������Ȃ���������F�߂邱�Ƃ��ł��Ȃ��������A�����ĕېg�B�j�]���ڑO�ɔ��������ł��A����ȗނ����o���Ă��܂��B���������̎��������A�{���̈Ӗ��ł́w�����Ǐ�x�������̂�������܂���v
�@���ܓ��{���\���鎩���ԁA�d�@���[�J�[�́A��@�̕��ɂ���Ȃ����_�ȍ\�����v�ɓO���邱�Ƃ��ł����ɂ���B�����Ŕ��f�����A��ɂ���̂͌��Ă����悤�ȁu���S�ȍŌ�v�ł����Ȃ��B�\�����v�̂��߂ɁA�u���{������Ёv�Ɏc���ꂽ���Ԃ͋͂����B
�u�T������v2012�N2��18�������
�@
���̋L����ǂl�͂���ȋL�����ǂ�ł��܂��i�\���܂�20�b���x���Ԃ�������܂��B�j
�@
�����̃y�[�W�̂s�n�o���@�@�@�@�@ �����C���� > �o���ϖ�75�f����
 �X�p�����[���̒����猩���o�����߂Ƀ��[���̃^�C�g���ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B
�X�p�����[���̒����猩���o�����߂Ƀ��[���̃^�C�g���ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B���ׂẴy�[�W�����p�A�]�ځA�����N���������܂��B�m�F���[���͕s�v�ł��B���p�������N��\�����Ă��������B