01. 2012年12月13日 16:52:21
: IOzibbQO0w
日本原電の格付け、3段階引き下げ R&I
2012/12/12 20:20
小サイズに変更
中サイズに変更
大サイズに変更
保存印刷リプリント共有
格付投資情報センター(R&I)は12日、日本原子力発電の発行体格付けをシングルAからトリプルBに3段階引き下げたと発表した。原子力規制委員会が同社の敦賀発電所2号機の再稼働を認めない可能性が強まり、財務上大きな影響が出る懸念があるため。 見通しは格下げ方向とした。廃炉などの措置が行われた場合は大株主の各電力会社が支援する可能性が高いが、十分な支援が得られず信用力がさらに低下することも考えられるという。
日本原電「根拠が不十分」、規制委に公開質問状
敦賀原発直下に活断層
2012/12/12付
日本原子力発電は11日、原子力規制委員会の評価会合が敦賀原子力発電所(福井県)の2号機直下に活断層が通っている可能性が高いとの統一見解を示したことに対し、判断の根拠を問う公開質問状を規制委に提出した。事業者が規制当局に再考を求める異例の事態となった。ただ規制委の判断が覆る可能性は低く、同原発の廃炉を迫られる公算が大きい。日本原電の経営環境は厳しさを増す。
公開質問状は浜田康男社長名で、規制委の田中俊一委員長に宛てて提出した。書面では10日に開いた評価会合の判断を「科学的根拠を含めた十分な説明がなされておらず、誠に理解に苦しむ」と強調。10項目の疑問点を示し、早急に文書で回答するように求めた。 最大の焦点は2号機直下を通る「D―1破砕帯(断層)」。規制委はD―1破砕帯と敷地内を走る活断層「浦底断層」の枝分かれ部分で見つかった地層変形についてD―1の一部とみなし、浦底断層と連動する活断層の可能性が高いとした。 日本原電はD―1破砕帯を「活断層ではない」と主張してきた。質問状では地層の変形を活断層と認定した理由や、地層の変形がD―1破砕帯の一部だと判断した根拠などをただした。調査が地形変動の観察に偏っており、地質調査や物理探査を組み合わせるべきだともしている。11日に記者会見した増田博副社長は「規制委には真摯に答えてもらえると思う。自社調査の結果も提出し、議論したい」と語った。 規制委は敦賀原発の断層調査を指揮した島崎邦彦委員長代理が現在、報告書をまとめており、質問への答えも盛り込む方向で検討する。同報告書を基に規制委が議論し、「現状では再稼働を認めない」との方針が正式に決まる見通しだ。 公開質問状を提出し記者会見する日本原電の増田副社長(11日、東京・大手町)
再稼働できなければ廃炉が現実味を帯びるが、現状は日本原電に判断が委ねられている。規制委が電気事業者に原子炉の運転停止や廃炉を命令する権限はない。廃炉の可能性や判断基準に関して、増田副社長は「仮定の話にはコメントできない」と明言を避けた。 日本原電には簡単に廃炉を容認できない事情がある。まず経営へのインパクトだ。将来の廃炉費用として1550億円を引き当てているが、引き当てがほぼ終わっているのは運転開始から40年以上が経過している敦賀1号機にとどまる。 活断層の基準が変わったことへの不満もある。敦賀1号機の設置許可が出た1966年には浦底断層が学術的に活断層と認知されていなかった。78年につくられた旧耐震指針は5万年前以降に動いた断層を活断層としていたが、2006年に12万〜13万年前以降に変更。さらに規制委は40万年前以降に広げる意向だ。 国の基準変更で運転停止や廃炉になれば「廃炉費用の一定程度を国も負担すべきだ」との意見もある。規制委の判断を不服として行政訴訟を起こす可能性もある。 規制委の事務局幹部は「これからが勝負になる」と話す。規制委は来年7月から原発に最新の安全対策を課し、規制委が活断層の影響を認めれば運転停止を命じられるようにする。それまでは行政指導で運転停止を求める。日本原電とのつばぜり合いは続きそうだ。
http://www.nikkei.com/article/DGXDASDC1100R_R11C12A2EA2000 |
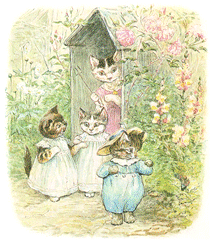
 スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。 スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。