02. 2012年11月17日 18:15:34
: kRbnAhA4bs
脱原発論者はセンチメンタルだと言われる。事故があったから、ただ怖がっているだけの無知な者たちだという見方である。しかし、脱原発はセンチメンタルな訳でも無知な訳でもない。そのことを訴えてほしい。既にご存知の内容も多いことと思われるが勝手におさらいさせていただく。<脱原発は合理的> まず核燃料サイクルが原発の存在理由の原点だと言うことを強調しておきたい。ウランの埋蔵量は限られており、原発とは、使用済み核燃料を再利用しない限り短命に終わる技術である。経済性・費用対効果の観点からしても、原発は核燃料サイクルを実現しない限り成立しない方法論だ。核燃料サイクルは高速炉によって行われる予定であったが、高速炉の実用化が困難と判断した勢力はMOX燃料=プルサーマルに活路を求めた。しかし、イギリスなどでは事業として失敗に終わり工場は閉鎖。原発村はふたたび高速炉に希望を託している。しかし、高速炉の実用化は不可能である。 使用済み核燃料の再利用の実証(=高速炉の駆動)に成功したのは1965年。その後半世紀に渡って、世界中が時に競い合い、時に協力し合いながら挑戦してきたにもかかわらず実用化に至っていない。これに加えて、最新の第4世代高速炉と言われる設計概念にはフクキマ級の災害にも耐えられるという高いハードルが加わっている。つまり、事実上不可能なのだ。しかし、原発村は一縷の望みを抱いており、その結果が判明しそうなのが2030年代と想定しているのだろう。だから、「2030年代までにゼロ」というのは、辞める気はまったく無いと言っているのに等しい。彼らの一縷の望みとは、現在GE日立がイギリスに売り込み中の「プリズム高速炉」の実現だ。GEは旧式実験用高速炉を30年に渡って稼動させてきた経験を持っており、唯一核燃料サイクルの可能性を秘めた開発グループと言える。他の勢力は絵に描いた餅のようなものばかりで、実用化どころか実証実験にも至っていない。このイギリスでの計画については程なく英原子力規制委員会の最初の審査結果が出される予定で、最終的には議会で採択される。もし計画の段階で破棄されれば核燃料サイクルへの「一縷の望み」は完全に断たれる。イギリスが袖にした技術を他の国が使用するだろうか?GEは稼動経験を持っているとは言え、約20年前までの話であり、第4世代高速炉については実験用の用地を確保した程度でしかない。英インディペンデントの見出しには「テストもしていない高速炉で使用済み核燃料を燃やすことになるかもしれない」とも書かれている。この計画が実現される可能性は、ほぼゼロ。さらに、最近注目を集めているトリウム原発という原発村にとってのライバルが登場した。インドが実験炉の駆動に成功し、中国が大々的に参戦を表明したのだ。トリウム原発の特徴は核のゴミを出さない=核燃料サイクルが不要なこと。アメリカがこの原発に支援的な立場なのは、トリウム原発からは核兵器が作れない、つまり、安全保障上好ましいからだ。こうした動向も核燃料サイクルにこだわる原発村を追い詰めている。最新の第4世代のコンセプトより遥かに古くてポンコツな「もんじゅ」を再稼動すると言う話もあるようだが、これは彼らが、ほとんど発狂状態にあると見ていい。 事実上終わった技術にこだわっている原発村こそセンチメンタルなのである!そして、そのようなものに資財を投じるなら再生可能エネルギーに投じるべきだ。 温泉大国日本が注力すべきは地熱発電である。地熱は自然エネルギーの中で唯一安定供給が可能なエネルギー源だ。たとえば、アメリカのカリフォルニア州にある地熱発電所「Navy 1」では、270メガワットを発電する。これは日本の世帯平均の消費量で計算すると、約68万世帯分の供給量になる。もし、今ある原発施設の数だけ「Navy 1」クラスの地熱発電所があったとすると全国の約23パーセントの世帯が地熱発電だけで賄える。地熱発電所は大規模なものから零細なものまで、至るところに設置すればよい。国立公園への設置について景観を損ねるなどの批判があるが、ダム建設の場合は、景観はもとより生態系まで破壊しているではないか。景観破壊論論は詭弁だ。日本の自然の回復力は驚異的であり、空き地などはすぐ雑草が生え、しまいには木まで生えてくる。もし地熱発電所が目障りなのであれば、新たな発電技術が生まれたときに撤去すれば良い。(そもそも山なんて杉だらけではないか。)温泉がぬるくなると言うのであれば、少々沸かしてもよい、命あっての温泉だ。発電会社は資源料=地熱は只な訳であり、何らかの形で温泉宿を支援できるだろう。地熱発電に注力しつつ、個別の企業・世帯への省エネ技術の普及、メガ・ソーラや風力等の再生可能エネルギー使用で原発の穴は埋められる。 脱原発派をセンチメンタルと信じている人々を啓蒙していかなければならない。 <参考文献> なるべく日本語を選んだものの英文もあるでご容赦のほど。信憑性のないサイトは除外している。簡単な解説を加えるのでリンクは興味がある方向けのもの。 * Navy 1 地熱発電所の写真 * これで68万世帯が賄える。
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Coso_geothermal_plant.jpg 写真元 英語版ウィキ
http://en.wikipedia.org/wiki/Coso_Volcanic_Field * Navy 1 だけで68万世帯の積算根拠 * 以下の米エネルギー省及び米海軍のサイトでは、1メガワット=1400世帯で算出し、270メガワットは378000世帯分と算出している。しかし、広い家に住んでいるアメリカ人の電力消費量は日本人より遥かに高い。米当局の情報と電気事業連合会による情報を比較し、カリフォルニア州の住民の電力使用量は日本の平均世帯の1.8倍として算出した。カリフォルニア大の添付は参考程度のもの、こちらの統計ではもっと高い。米エネルギー省の情報で印象的なのは、米海軍がメガ・ソーラの使用を開始したこと。 米エネルギー省サイトより(英語)
http://www1.eere.energy.gov/solar/sunshot/news_detail.html?news_id=18736 一世帯あたりの電力消費量(月単位) 電気事業連合会サイトより
http://www.fepc.or.jp/enterprise/jigyou/japan/sw_index_04/index.html 一世帯あたりの電力消費量 カリフォルニア大サイトより(英語)
http://www.physics.uci.edu/~silverma/actions/HouseholdEnergy.html
* 欧米で進む再生可能エネルギーへの取り組み *
再生可能エネルギーの普及に欠かせないスマートグリッドの整備についてアメリカとEUが協定を結んでいる。効率化を図るため開発分野が重複しないように注意するとのこと。EUのスマートグリッドへの取り組み状況も添付した。進んでいるようだ。 「米国とEUがスマートグリット標準化へ」独立行政法人 NEDOサイトより
http://www.nedo.go.jp/content/100186218.pdf 「EUのスマートグリッド政策」国際協力銀行サイトより(やや専門的)
http://www.jbic.go.jp/ja/report/reference/2011-041/jbic_RRJ_2011041.pdf
* 中国科学院、トリウム原発へ参戦表明 *
毒をもって毒を制すで、トリウム・ブームは脱原発に効果をもたらす可能性もある。 日経ビジネス電子版より(最初にCM入ります)
http://business.nikkeibp.co.jp/article/manage/20110225/218599/?rt=nocnt
* テストもしていない高速炉で使用済み核燃料を燃やすことになるかもしれない *
本記事の中で印象的なのは、英原子力規制委員会が破綻したはずのMOX燃料事業の再開にこだわっていること。高速炉でシビアな事故が発生したら、かつての大英帝国は世界地図から消える。さすがに怖いのではないだろうか。最終的な結果が出るまでには長い道のりが待っていると伝えている。(審査を通過したとしても議会が否決する場合もある。アメリカの場合は94年に高速炉開発から撤退しているが、この時のプロセスは印象的である。米原子力規制委員会がお墨付きを与えた高速炉開発計画を議会が破棄したのだ。「専門家の意見も交えながら」決めて行く、どこか国とはスタンスが異なっている。アメリカは、深入りしたあげくに撤退する国。ベトナム戦争から撤退し、スペースシャトルから撤退し、世界の迷惑かえりみず新型の信用取引から撤退した=リーマンショック。) インディペンデント紙より(英語)
http://www.independent.co.uk/news/science/untested-nuclear-reactors-may-be-used-to-burn-up-plutonium-waste-8061660.html |
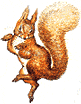
 スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。