http://www.asyura2.com/12/genpatu23/msg/401.html
| Tweet |
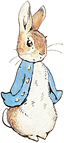
チェルノブイリ被曝の母娘が語る「放射能との26年の闘い」
(日経ビジネス)
放射能の被害が覆い隠され、被害者が切り捨てられてしまう危険性
藍原 寛子
平成24年5月2日
4月26日、旧ソ連のチェルノブイリ原発事故発生から26年を迎えた。
4月以降、福島県内各地で、チェルノブイリ事故の教訓を学ぶ講演会や勉強会が相次いで開催されている。23日には白河市立図書館で「チェルノブイリ被曝者を迎えて〜放射能被害を最小限に抑えるためのベラルーシからの提言」と題し、チェルノブイリ原発事故で被曝した母娘を現地から招いた講演会が開催された。NPO法人アウシュヴィッツ平和博物館(白河市)の主催、白河市と同市教委後援、チェルノブイリ子ども基金の協力。チェルノブイリ子ども基金事務局長の佐々木真理さんが通訳を務め、約80人の市民がチェルノブイリ被曝者の事故後26年の生活に耳を傾けた。
講演のため来日したワレンチーナさん(左)と娘のオリガさん
講師はベラルーシのゴメリ市在住のポポモア・ワレンチーナさんと、その娘のゼレンケヴィッチ・オリガさん。オリガさんはチェルノブイリ原発事故の影響で、7歳の時に甲状腺がんの摘出手術を受けた。ワレンチーナさんは1992年、「私と同じような思いをしている母親たちを支援したい」と、チェルノブイリ事故による病気や障害と闘う親子を支援する団体「困難の中の子どもたちへ希望を」を設立。代表として活動を続けている。
福島第一原発事故後の福島県で2人が語った、「未だ終わらない事故後26年」それは、今後も永遠に続く放射能との闘いの物語と、同じ「被曝者」へ向けた励ましのメッセージだった。
知らされなかった汚染、そして被曝
ワレンチーナさんは原発事故当時の様子と、被曝した経緯など当時の様子を具体的に話した。
ワレンチーナさんと夫は、息子と、オリガさんを含む双子の娘に恵まれた。チェルノブイリ時事故当時、双子の娘は2歳半で、一家はゴメリ市に住んでいた。
原発事故後の1986年5月1日、原発から約80キロのところにある両親の家に家族で遊びに行き、みんなでジャガイモ植えなどの畑作業を手伝った。強い風が吹く日で、作業を始めてから約3時間後、突然、夫が鼻血を出し、ワレンチーナさんも気分が悪くなった。その日、病院で働いていたワレンチーナさんの母親が勤め先から呼び出され、顔色を変えて帰ってきた。その夜にワレンチーナさん一家はゴメリ市の自宅に帰ったが、翌日、マスコミがチェルノブイリ原発事故について報じたことから、初めて原発事故を知った。
「情報は全く不十分で、事故の大きさ、人への影響が発表されることはなかった。住民の安全基準や方針も示されず、ただ言われたことは、外にいる時間を短くすること、帽子をかぶること、外から戻ったらシャワーを浴びて衛生面に気を付けるようにということだった。学校や幼稚園では屋外活動を最小限にし、やがて測定器も売られるようになった」という。
福島第一原発事故直後に福島県内で行われたことと同じことが、チェルノブイリ事故後のソ連でも行われたことが分かる。
http://business.nikkeibp.co.jp/article/life/20120427/231507/?mlp&rt=nocnt
健康への影響が懸念されたことから、ワレンチーナさんの職場は、5月半ばから子どもたちと3カ月間の一時保養の機会を設けた。ゴメリ市にある多くの企業が、同様に母子を保養に行かせたという。
ところが、戻ってきてから、一家の生活が大きく変わることはなかったという。健康対策として唯一できる方法がその土地から避難することだったが、「多くの他の家族と同じように、私たちの家族もどこにも逃げるところはなかった」(ワレンチーナさん)と当時を振り返る。
子どもや自分たち、両親の健康に影響が出るのではないかと不安になったワレンチーナさんらは、被曝予防対策を一から学んだと言う。
「森のイチゴや絞りたての牛乳を飲まないことなど、できることはすぐに実践した。それでも汚染の少ない野菜や食品を買うための補助金などはなかった」。収入や雇用条件が良かったり、避難できる場所があるなど、経済的、社会的に恵まれた人がより良い健康を得られるというような現状について、ワレンチーナさんは「それはまるで、強いものが残るというような恐ろしいサバイバルショーのような状況だった」
その後、1年に1回、当時働いていた職場が「保養券」を発行してくれて、ラトビアやリトアニア、グルジアに保養することができた。チェルノブイリ周辺地域の住民の多くが、ゴメリやミンスクなどに避難し、バルト海北部に行った人もいたという。汚染された村や町は人々が避難していったため、次々と地図から消えて行った。
娘に異変―突然の入院と手術
そんな時、娘オリガさんに異変が現れる。毎年学校で行われていた健康診断で、「甲状腺にしこりがある」と診断されたのだ。1990年、事故から4年後のことだった。ワレンチーナさんら両親にとっては寝耳に水だったが、考えてみると、オリガさんは病気がちになっていて、その頃は体重も落ち、学校から帰ると疲れてしまって横になりがちだったことが浮かんだ。
「それ以来、オリガの健康に対して深刻に考えるようになった」とワレンチーナさん。
定期的に血液検査を受けていたが、翌年の1991年、保養所(サナトリウム)の医師がオリガさんの異変に気付く。「早く甲状腺の検査を受けるように」との医師のアドバイスで、翌日、救急車でミンスクの病院に入院。医師の診断は「リンパ節転移を伴う甲状腺がん」という衝撃的な内容だった。その翌日、オリガさんの甲状腺の摘出手術が行われた。7歳だった。その2年後にもイタリアで手術を受けて完全に甲状腺を摘出している。
http://business.nikkeibp.co.jp/article/life/20120427/231507/?P=2
ワレンチーナさんはその時のことを振り返る。「医師の診断を聞いて意識を失ってしまった。手術後も娘の健康と命を心配する日々が続いた。ミンスクの病院で娘と一緒に過ごす間も、ほかの人に対して病名は秘密だった」
この時のことをオリガさんは鮮明に覚えている。「私の診断が下されたとき、医師の部屋から出てきた母は、帰るまでずっと泣いていた。今、私自身が母親になる年齢となって、あの時の母の衝撃が理解できる。当時は経験のある医師も少なく、検査や治療機器も少なかった」
その後、肺への転移、視力低下、心臓の問題や頭痛もあり、ホルモン剤を服用しながら、現在も定期的な治療が続いている。
病気に苦しむ同じ家族を支え合いたい
娘が退院した直後、ワレンチーナさんはある大きな決断をする。それは、自分と同じようにチェルノブイリ事故の影響で病気に苦しむ子供を抱える母親と共に闘い、支援していく活動を続けるということだった。
「オリガのやつれた顔、注射でやせ細った腕、つながれたチューブを見て、『娘がこのまま生き延びることができて回復したら、自分のような母親が一人で心細くならないように援助したい。子どものためにあらゆる努力をしよう。誰も頼る人がなくて世界で独りぼっちのように感じている、私のような親たちを応援したい』と」
そう思い始めたある日、地元のテレビ番組に出演する機会に恵まれた。自分の体験、娘の闘病の様子などを話し、「健康に十分注意してほしい。特に子どもを持つ親は子供の健康に気を付けて。早い段階で超音波検査を受けることも必要」などと具体的にアドバイスした。視聴者からはすぐに反響があった。電話や直接話を聞きたいと言う要望もあった。
そうして病気の子どもと親を支える団体「困難の中の子どもたちへ希望を」が1992年4月に設立された。会員の多くが甲状腺がんの子どもとその親だった。現在は行政などからの支援はなく、多くがゴメリの企業や海外の支援団体などからの寄付金で成り立っている。
http://business.nikkeibp.co.jp/article/life/20120427/231507/?P=3
現在の会員は病気、障害児の子どもたちなど373人。212人が17歳までの子どもで、そのうち50人は、親が子どもだったときからの会員だ。親だけでなく、子どもの世代にも影響が及んでいることが懸念されている。残る161人は18歳以上。設立以降、154人の子どもたちが神経芽細胞腫、肝臓がん、甲状腺がんなどと闘い、亡くなっていった。
被曝しない努力と保養が有効
旧ソ連では、医療体制が十分ではなかったことが指摘されている。現在、ベラルーシでは1年に1回、国の計画により学校で甲状腺検査が行われており、そのための専門医もいる。しかしそれらの国の制度やプログラムがあるにもかかわらず、甲状腺がんの問題が起きることについてワレンチーナさんは、支援団体の子どもたちの生活の様子などから「汚染された土地に問題があるのではないか。汚染された土地に住み、汚染された土地で作った作物を食べることと明確に関連がある。自分で作った食べ物の多くは検査されていない。汚染度は低いかもしれないが、汚染されたものを食べ続けることで影響があり、四半世紀以上過ぎてもチェルノブイリ事故の影響はある」と話す。
しかし、将来に向けて希望が全くないというわけではないと、娘のオリガさんは話す。彼女が希望を抱いた出来事は、「希望」という名称の保養所で、病気と闘う同年代の子どもたちや医師らと過ごした体験だった。髪の毛が抜けていることや、手術の縫合跡などを気にせずに過ごすことができた。保養所での生活が、物事に前向きに取り組むきっかけを作ってくれたという。
病気のために就職が難しかったオリガさんだが、会計の仕事に就き、現在は主任国税監査官の仕事をしている。さらに、病気の事もすべて知っている大学時代の同級生、アレクサンドルさんと結婚。「近いうちに、夫に元気な子どもを見せてあげたい」。病気と闘いながらも、子どもを持つという将来の希望を抱いて、毎日を過ごしている。
汚染環境が続く一方、削減された社会保障
ワレンチーナさん、オリガさんが講演のなかで、ともに指摘した課題が2つある。1つは、現在もチェルノブイリ原発周辺で続く汚染だ。30キロ圏内は立ち入りが禁止されており、首都ミンスクや他の3カ所の官庁などで特別な許可証をもらわなければその地域に入ることができない。ワレンチーナさんは昨年、事故から25年を迎えて、外国の訪問団とともに30キロ圏内に入った。「区域内に入って線量を測定したが、線量が高い状態が続いている。乗っていた車が汚染されて高い放射線の数値を示したため、車を洗わなければならなかった。大統領は『汚染地域に戻ってもいい』と言っているが、私はそれは正しくないと思う」と話し、汚染地域に人が立ち入ることで、さらなる被曝をする問題を指摘した。
http://business.nikkeibp.co.jp/article/life/20120427/231507/?P=4
もう1つは被曝した人に対する社会保障が次々に削減されている問題だ。ワレンチーナさんは言う。「2009年当時は、薬や交通費、住宅取得、その他にも特典があった。ところが、経済危機などのため、障害児年金や障害者特典が年々削減されているが、その一方で子どもたちへの手厚い保障の必要性は年々高まっている」。目には見えない放射能の被害が覆い隠され、被害者が切り捨てられてしまう危険性を指摘した。
白河市に市民の手で「情報センター」を
講演会やシンポジウムなどで、チェルノブイリの原発事故の影響は、何世代にもわたり、放射能の被害から住民の健康を守る根気強い長期的な取り組みであることが語られてきた。
今回の講演会を主催したNPO法人アウシュヴィッツ平和博物館では、同博物館敷地内に原発や放射能汚染、被曝予防について理解を深めたり、学んだりする「情報センター」の建設を検討、理事や会員らで意見交換を始めた。
完成は早ければ1年後を予定。今後、県内の市町村など自治体で「記念館」のようなものが建設される可能性があるが、同博物館の「情報センター」は、あくまでも市民活動を中心に市民の目線で、命の大切さや戦争と核の問題、原発事故で命や健康が脅かされている現状や、被曝予防に向けた具体的な取り組みを理解する拠点となるような施設が考えられている。
小渕真理館長は「福島第一原発事故が何だったのか、検証する時期がいずれ来る。その時に、市民が体験したこと、市民が考えたことを市民レベルで記録したり、後世に残す場が必要になる。また、長期的な取り組みとなる被曝対策に関する情報提供の拠点や、市民が交流する場が必要」と話す。今後、より具体的な構想を話し合い、まとめていくことにしている。
今後も福島県内ではさまざまな講演会や勉強会、シンポジウムなどの開催が予定されている。拠点となる施設が増えれば、市民への情報提供の幅も広がる。ワレンチーナさんやオリガさんのように、直接原発事故を体験した被曝者による講演会の機会もより増えることだろう。終わることのない原発事故後の対策は、福島ではまだ始まったばかり。福島県民の体験や学びも、まだ始まったばかりだ。
http://business.nikkeibp.co.jp/article/life/20120427/231507/?P=5
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます(表示まで20秒程度時間がかかります。)
▲このページのTOPへ ★阿修羅♪ > 原発・フッ素23掲示板
 スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。