15. あっしら 2011年10月27日 14:47:28: Mo7ApAlflbQ6s
: DvLZNEv2EI
NRvAM7Ti0k さん、こんにちは。野口悠紀雄氏と浜矩子さんがTPPに反対するのは、TPPが限定国家間の「関税同盟」や「ブロック経済化」で、「自由貿易」に反するものというのが基本のようです。 私は「自由貿易」主義者ではありませんが、私の「TPPをめぐる誤解1:日本は「自由貿易」で経済成長を達成したわけでなく、TPP自体が「自由貿易」に反するもの」(
http://www.asyura2.com/11/senkyo121/msg/130.html)に近いTPP観を持っていて、自身が是とする「自由貿易」の観点からTPPに反対しているようです。
野口氏の「中国抜きのTPPは輸出産業にも問題」という指摘は、ちょっと違うなと思っています。中国政府は自国が発展途上国であり保護主義が必要な工業レベルだと考えていますから、内政を縛られると言う話をおいても、TPPそのものに意味を感じていないはずです。
TPP参加を対中国牽制外交の一つとして喧伝している人もいますが、中国政府は、日本がTPPに入るのも入らないのもご自由にというスタンスのはずです。 中国が日本に対しFTA的な交渉を求めるのは、あと5年くらい先になってからだと思っています。 (ASEAN+3のようなFTAについても、それくらい先を見越した話として進んでいくと思っています)
============================================================================================
2010/12/18 土曜日
中国抜きのTPPは輸出産業にも問題 Filed under: 「超」整理日記 — admin @ 8:00:47 TPP(環太平洋経済連携協定)についての議論が行なわれている。問題は農業保護と貿易自由化の兼ね合いであると、一般には考えられている。すなわち、「輸出産業の立場からはTPPに参加して貿易自由化を促進するのが望ましいのだが、引き換えに農産物に対する関税撤廃を求められる。そこで、農業関係者を説得し、農業を以下に保護するかを考えなければならない」という理解である。 確かに、農業問題は重要だ。しかし、その前に検討すべきは、「TPPによる関税引き下げが輸出産業にとって本当に望ましいか」という問題なのである。TPPが貿易を拡大するのは自明のことと考える人が多いが、必ずしもそうではないのだ。 これは、「関税同盟の理論」として、1950年代にヴァイナーなどの経済学者によって議論されてきた問題である。そこで得られた結論は、「関税同盟によってかえって貿易が阻害されることもある」ということだ。だから、貿易自由化の観点から見て、関税同盟は必ずしも正当化できるものではない。本来は、輸出産業の立場から見ても慎重に考えるべき問題なのだ。ただし、この議論は簡単に理解できるものではないので、説明が必要だろう。
TPPはFTA(自由貿易協定)の拡大版なので、まずFTAの貿易阻害可能性について説明しよう。 FTAが締結されれば、協定国との貿易は、FTAがない場合に比べて増大する。これは明らかだ。しかし、二国間協定であるために、協定国以外の国との貿易が阻害される可能性があるのだ。 日本のFTAは海外進出した日本企業の現地工場が日本から部品を輸入する際の関税引き下げを目的としている場合が多いので、それを例にとって説明すれば、次のとおりだ。仮に、日本がたいとはFTAを結ぶが、中国とは結ばないとする。すると、タイに進出した日本の現地企業は、日本から部品を関税なしで輸入することができるので、生産コストを引き下げられる。したがって、日本とタイの貿易は増えるだろう。しかし、中国の現地工場はそうした利益は享受できない。したがって、本来は中国への部品の輸出を増やすべきなのだが、それが実現しないことになる。「中国との貿易を増やすのが望ましい」と言っているのではない。「タイとのFTAがない場合に比べて、中国との貿易が減少することが問題」と言っているのだ。関税を抜きにして考えれば、中国の現地生産のほうがタイの現地生産より効率的に行なえる可能性があるにもかかわらず、中国とタイの関税の相対関係が歪んでしまうために、最適な生産配分が達成できない可能性があるのだ。この攪乱効果は、「貿易転換効果」(trade diversion effect)と呼ばれている。 セカンド・ベストは状況を悪化させることも TPPは多国間協定なので、一見するとFTAのような問題は生じないような気がする。しかし、そうではない。
今提案されているTPPでは、中国が入っていないため、上の例と同じ問題が生じる。つまり、中国との貿易は阻害されるだろう。 中国はいまや日本にとって最大の貿易国であり、中国抜きでの経済活動は考えられない。そうした条件下において中国を排除した協定が日本にとっていかなる意味を持つかは、慎重に考えるべき問題だ。 この問題を避けるには、中国も協定に入れる必要がある。しかし、仮にそれが実現しても、協定に入っていない国はまだ残っているので、やはり問題が生じる。たとえば、本来は東欧に建設した現地工場に部品を輸出するのが望ましいにもかかわらず、TPP圏内の貿易だけが不当に増える、ということが起こりうる。 結局のところ、全世界がWTO(世界貿易機関)を通じて関税引き下げを行なわなければ、問題は解決されないのだ。 WTOを通じて関税を一律に引き下げるのは「ファースト・ベスト」だ。しかし、WTOでの交渉はなかなか進まない。そこで、FTA推進論者は、次のように主張する。「FTAはファースト・ベストではないが、セカンド・ベストだ。だから、状況は現状よりは改善されるだろう」。 しかし、関税同盟の議論は、「セカンド・ベストは必ずしも改善にはならない。かえって事態を悪化させることもある」と指摘しているのである。こうした指摘は、日本ではFTA推進論者の主張にかき消されて顧みられないが、忘れてはならないものだ。 TPPは中国を排除する仲よしクラブ 以上で述べたのは、協定参加国の立場から見ての、経済的な側面の議論である。
協定非参加国の立場から見れば、関税同盟が迷惑であることは明らかだ。
たとえば、韓国がアメリカとFTAを結ぶとしよう。すると、アメリカとの貿易において、日本は韓国に比べて不利な立場に置かれる。韓国とアメリカのFTAは、日本にとっては迷惑なものなのである。 今回のTPPに関しても、「もし日本が参加しないと、日本は仲間はずれにされてバスに乗り遅れる」という議論が行なわれている。確かに、そのとおりだ。特定国間の関税同盟は、非参加国から見れば、迷惑以外の何物でもないのである。
仮に日本が入ったとしても、中国が排除されていることは、中国の立場から見れば大きな問題だ。「これは中国を排斥するための仲よしクラブの結成だ」と中国が受け取ったとしても、少しも不思議はない。それは、中国との政治的な関係に悪影響をもたらすだろう。世界第二位の経済大国になった国を排斥する同盟関係をつくることは、政治的に見て決して得策とは言えない。 交渉の経緯も、いささか奇妙だ。元々は、シンガポール、ブルネイ、チリ、ニュージーランド間の協定として2006年に発足したものだ。そこにアメリカが突然入ってきたのは、直接的には農産物輸出の拡大が目的だったのだろう。 しかし、結果的には、中国を排除する経済圏が太平洋圏につくられることになる。今提案されているTPPに参加する可能性がある国は、日米以外は、経済規模がそれほど大きな国ではない。参加可能国の中では、日本とアメリカが圧倒的なシェアを持っている。つまり、これは事実上は日米間のFTAなのである。 最後に誤解のないように述べておきたい。ここでの議論はTPPに対して懐疑的なものであるが、それは国内農業保護の立場からのものではない。 私は農産物の関税撤廃には大賛成だ。現在の農産物輸入にかかる高い関税のために、日本の食料品価格は国際的に見て、非常に高くなっている。この結果、日本の家計は、多額の食料費の支出を強いられているのだ。日本のエンゲル係数は、先進国の中では異常な高さになっている。家計の犠牲において、日本の農業が成立しているのである。
しかも、そうした手厚い保護を行なうことによって日本の農業の生産性が上昇したかと言えば、決してそんなことはない。むしろ、保護があるために生産性向上のインセンティブが失われ、農業生産性は低下した。 農業の自由化は本来はTPPとは独立に進めるべき課題だが、仮にTPPがそれを進めるためのショックになるのであれば、それは意味があることと考えられる。TPPに関して積極的な意義を認めうるのは、この点だけだ。 http://essays.noguchi.co.jp/archives/492
============================================================================================
TPPを慎重に考える会 ゲスト浜矩子氏 2011年2月4日
2011年02月05日(土) 2011年2月4日、同志社大学大学院教授の浜矩子氏をゲストに迎えて、TPPを慎重に考える会の会合が行われました。冒頭の山田正彦前農水相の挨拶の後、浜氏がTPPの大枠の考え方を示しています。 浜氏は、「TPPは幅広く自由貿易を迫るものだから慎重に考えるべき」と思う人がいたら、それは自分の考えてとは逆である。TPPは「不自由化」を迫るものだから慎重に考えるべきと思っていると、冒頭からマスコミで流布されている「通説」を覆します。
また、FTAやTPPは地域限定の自由貿易協定であるので、現実的には「地域限定排他貿易協定」と言うべきものであるので、そもそもWTOが持っている「自由・無差別・互恵」の理念に反するとも述べています。WTOの理念は、戦前のブロック経済化が第二次世界大戦を導いた反省の元に成り立っているので、ブロック化を促進するような排他性が入り込む協定は日本がとるべき道ではないとも。
「互恵」と「相互」の概念が現在混同されがちであると指摘しています。WTOの理念にある「互恵」とは「お返し」の論理であり、TPPなどにある「相互主義」とは報復的な論理で正反対のものと。 質疑応答では、TPPの為替への影響。アメリカの戦略。(斎藤やすの議員の質問) 日本はどのような外交をするべきか。(田中真紀子議員) スイッチが入ったように一斉に同じ論調になるマスコミをどう思うか(小林興起議員)等、多くの質問が出ました。 為替への影響では、「貿易が自由でなければ通貨も自由ではありえない」という原則のもと、通貨戦争を引き起こす可能性を指摘。また、アメリカの戦略では、オバマ大統領を「不本意男」と。就任演説では一国主義を止めると高らかに宣言したのに、今年の一般教書演説では、再び一国主義に戻りつつあることにショックを受けたと。 日本の外交は、スーパーマンではなくドン・キホーテを目指すべきと指摘。スーパーマンは腕力が強くて一人で何でもできる。ドン・キホーテは、人の痛みを知り、他人に依存することを知っている。21世紀を生き抜くには、このような姿勢が必要ではないか。またねマスコミは本来「王様は裸だ」というのが仕事であるのに、現状はだらしなさが露呈されていると指摘しています。 http://iwakamiyasumi.com/archives/6299 |
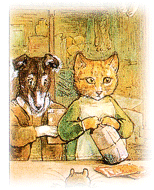
 スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。