http://www.asyura2.com/11/lunchbreak50/msg/450.html
| Tweet |
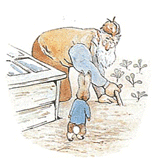
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1315474604/
【住宅】新築造り過ぎニッポンが迎える「空き家40パーセント時代」 [09/08]
1 :ライトスタッフ◎φ ★:2011/09/08(木) 18:36:44.68 ID:???
我が国の住宅はすでに大幅に余剰。このまま行けば30年後には空き家率が
43パーセントになるとの予測もある。人口・世帯数が大幅に減少する
「住宅大幅余剰時代」を迎えることが確実な我が国で、どういった基準で
マイホームを選べばいいのか。
■30年後は「となりは空き家」があたりまえに
日本の住宅市場はすでに「飽和状態」をはるかに通り越して「大幅に余剰」。
5年ごとに行われる総務省の調査によれば、平成20年10月1日時点での
総住宅数5759万戸に対して、総世帯数は4999万世帯と、約760万戸の空き家を
抱える。日本全体を賃貸住宅経営に例えると、空き家率は13.1%だ。現時点では
すでに空き家数は800万戸を超えているだろう。
さらに今後どうなるかを予測したレポートがある。「人口減少時代の住宅・土地
利用・社会資本管理の問題とその解決に向けて(下):(野村総合研究所)」に
よれば、もし2003年のペースで新築(約120万戸)を造り続けた場合、30年後の
2040年には空き家率が43%に達するとしている。いわば「お隣は空き家状態」
である。これではまったくお話にならないから、仮に新築を造るペースを半分
(約60万戸)にした場合でも30年後には空き家率が36%なってしまうとのことだ。
これでは全く持続不可能。今後長期にわたって起こる人口や世帯数の減少、
給与所得の低下などを踏まえれば、新設住宅着工戸数はあと5年〜10年のうちに、
50〜60万台にまで低下するものと私は見ている。かんたんにいえば、我が国は
新築住宅を造りすぎなのだ。
都市の空き家率が30%を超えると、防犯をはじめとする居住環境の著しい低下が
起きることが研究者の間で知られている。また上下水道などのインフラ整備や
ゴミ収集などの行政サービスの効率も悪化して自治体の財政事情を逼迫させる。
■住宅に「資産価値」などなかった
日本はこれまで毎年、おおよそ19兆円程度の住宅投資を続けてきた。ところが、
住宅資産額は常に250兆円程度と一向に積み上がっていない。こんな事態に
なっているのは先進国で日本だけである。
日本の住宅は新築を買った時に最も高く、中古住宅になったとたんにその価値が
15〜20パーセントも低下。およそ10年で半値となり、25年程度でその価値が
ほぼゼロになるというのがこれまでの定説。多額の住宅ローンを組んで新築の
マイホームを買っても、住んだ瞬間から資産価値とローン残高の目減り競争が
始まる。住宅は資産ではなく、あたかも耐久消費財のような扱いをされ、いくら
投資をしてもそれが価値に反映されることはなかった。
日本経済不況期には必ずと言っていいほど、経済波及効果が高いとされる住宅
建設促進策が打ち出され、価値ゼロ住宅を量産してきた。住宅投資の回復による
経済の復興と環境とが、まったく両立してこなかったのが住宅業界の姿だ。(※続く)
●グラフ
http://diamond.jp/mwimgs/d/b/400/img_dbd4c0cfc552ca14e953c7686623b515404710.jpg
http://diamond.jp/mwimgs/6/1/400/img_61f450f4ae2521416996ba4c8a0513bf151272.jpg
http://diamond.jp/mwimgs/b/2/400/img_b2286220625f6b2d74a69b98a5f122af248202.jpg
◎http://diamond.jp/articles/-/13939
2 :ライトスタッフ◎φ ★:2011/09/08(木) 18:36:57.19 ID:???
>>1の続き
日本経済不況期には必ずと言っていいほど、経済波及効果が高いとされる住宅
建設促進策が打ち出され、価値ゼロ住宅を量産してきた。住宅投資の回復による
経済の復興と環境とが、まったく両立してこなかったのが住宅業界の姿だ。
今後は「ストック住宅重視」の政策がうまく機能したとしても「価値を維持できる
住宅」と相変わらず「価値が落ち続ける住宅」とに二極分化していくのが今後
しばらくの、住宅市場である。さてこのような状況のなか、私たちはどうやって
マイホームを選べばよいのだろうか?
■「省エネ性能」はランニングコストのみならず、資産価値にも影響する
例えば「省エネ性能」。建物の省エネルギーに関する行政は今後ますます厳格化
される方向で、2020年には「次世代省エネ基準」を義務化する方向だ。もっとも
このような動きは世界的な動きでもあり、日本の住宅の省エネ性能行政はまだ
かなり立ち遅れている。
「次世代省エネ基準」ときくと、何か先進的な、時代を先取りしたかのような
言葉の響きがあるが、実は12年前に制定された規準である。この規準を制定した
1999年当時は、他先進国と同じレベルの省エネ基準だったが、その後他国は
基準をどんどん厳しくし、今となっては時代遅れ。しかもほとんどの先進国が
省エネ基準を義務化しているにもかかわらず、前述したとおり我が国ではいまだ
省エネ基準に義務はない。販売員が「ウチの建物は省エネ基準を達成しています」
というとき、それは「高い基準を満たしている」という意味ではなく「義務でも
ない基準を守っていますよ」と言っているに過ぎない。
これからは、「次世代省エネ基準」から一歩進み、住宅エコポイントの条件で
あった「トップランナー基準」を目安にしたいところ。「トップランナー基準」
すら、比較的近い未来に「標準的な基準」となるだろう。
このような政策が打ち出される際には、省エネ性の高い住宅について税制優遇や
融資期間や金利で優遇することによって誘導されることになるのが常だ。省エネ
性能のある住宅とそうでない住宅とでは、毎月の光熱費というランニングコスト
のみならず、住宅そのものの資産価値(市場価値)にまで影響が及ぶことは
「すでに起こった未来」である。
●グラフ
http://diamond.jp/mwimgs/4/0/400/img_40ee603f922aa4bc7593ad3579203f82265695.jpg
|
|
|
|
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます(表示まで20秒程度時間がかかります。)
|
|
 スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。